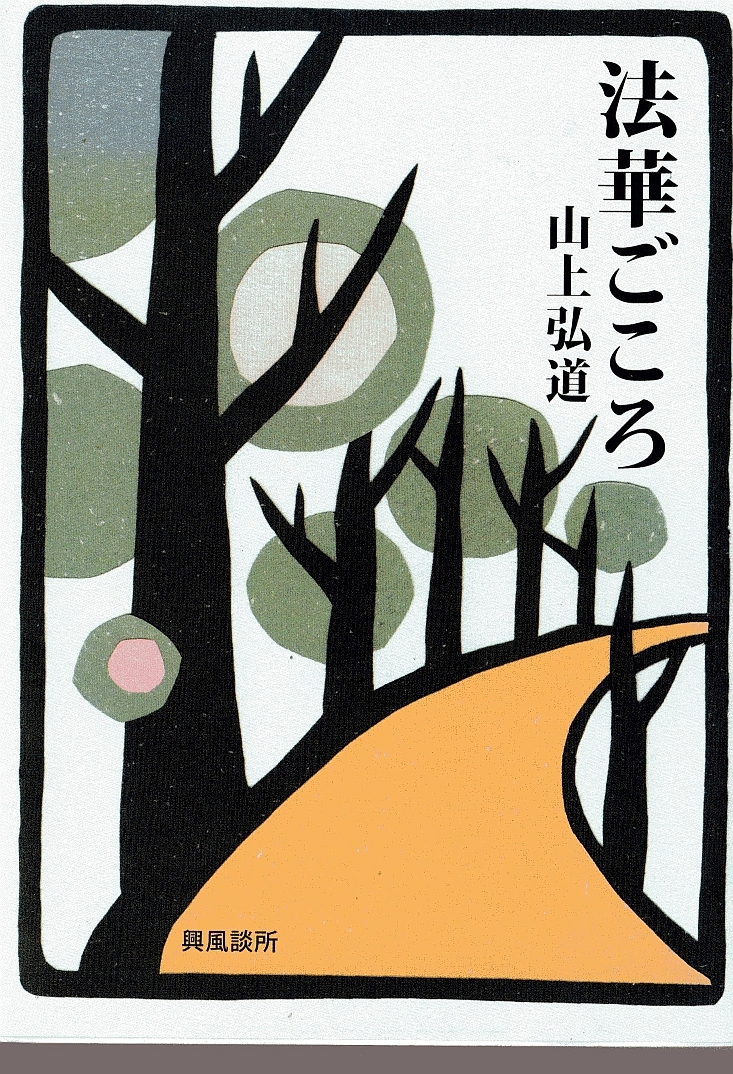
まえがき
「法華経的」という言葉が好きである。何かを読んでいいなと思ったわけではなく、かといって自分で造語をしたという意識もなく、何とかくその言葉を文章に使ったり、会話で使用したりするようになった。
本書は平成2年8月から平成22年11月まで、実に20年の長さにわたって継介新聞に書いた、コラム「法華ごころ」を一書としてまとめたものである。そのコンセプトは、まさに「法華経的」ということであり、「法華経的」に生きるとは具体的にどういうことかを、常に自らに問いかけながら、その答えを法華経や日蓮大聖人のお言葉、さらには多くの先達の言動や振る舞いに求めつつ書いた。またそれがたとえ信仰の世界とは無関係であっても、「ああ法華経的だな――」と感動したことや、逆に全く非「法華経的」なことがらも、時に感激の涙を浮かべながら、時に瞋りに燃えながら書き連ねた。
このコラムを書き始めてから、山に登っても、星空を眺めても、テレビを見ても本を読んでも、人と話していても、「法華経的」という言葉が常に頭にあったような気がする。
本に仕立てるために改めて読み返してみたが、大江光さんの曲を聴いたことや(15)、近所の子供との話(70)、プロジェリア患者ヘイリーチャンのこと(84)など、瞬時に当時のことが蘇って鼻がツンとした。平成11年11月に書いた「20世紀への宿題」(51)では原子力発電の危うさを取り上げた。平成15年に再び瞋りをもって取り上げているから(69)、当時の国の、学者やマスコミを抱き込んでの安全神話作りに、相当頭に来ていたようだ。
「あくまで非暴力」(74)では、当時(平成16年)盛んに行われていた憲法九条の是非を巡っての議論を取り上げ、護憲の立場を明確にして書いたところ、お叱りの電話をいただいた。もちろん私の信念は今も変わらないが、リアクションがあったこと自体はうれしいことであった。「慈悲の眼」(62)の文章の一部を、青森在住の書道の先生が大幅に仕立てられ、自らの個展に出陳してくださった。その後地元の幼稚園に展示されたとのことで、大変ありがたいことであった。(『継命新聞』平成23年5月1日号記事)。
平成16年に上梓した、拙著『白蓮のごとく』をお読みいただいている方ならすぐお気づきになるであろうが、「法華ごころ」はその土台となっている。こもごも含め私にとって連載の20年は、いろいろな意味で大いに勉強になった。
一冊の本として出版するにあたっては、系統立てて編集し直そうかとも思ったが、前後関連しているものもけっこうあり、その時々の話題を取り上げていることも多いので、あえて発表順そのままとした。そんなこともあって、時代性のあるものには、たとえば「今年は」と記している場合、()で何年と表示した。また表記や文章について、従来の意味を損ねぬ程度に手を加えている。
このようなものでも、読んでいただいた方々の心のひだに、一言半句なりとも響くものがあればと切に願う。
最後に本書作成に当たっては、渡邉信朝師にはレイアウトからその他全般にわたって協力をいただいた。また渡邉泰雄師にはカットを、池田菜津美さんには表紙を画いていただき、立派な本に仕立てていただいた。仲間と楽しく仕事ができたことを本当にありかたく思う。記して感謝の意を表したい。
平成24年7月22日 朝霞精舎にて 興風学徒 山上弘道
目 次
42 ひとつの涙
43 瞋恚は善悪に通ず
45 平凡であること
46 大聖人の後ろ姿
47 善意のバリア
48 大地より出ず
49 破戒
50 砂の仏塔
52 一念三千成道
53 柔和質直
54 女人成仏
55 一水四見
56 塔を起つ
57 滅後のためなり
58 実践の教え
59 法華経の色読
60 六難九易の意味
61 旅の分だけ
62 慈悲の眼
63 常に法を説く
64 智恵を捨てよ
65 真の平等
66 己れを折伏する
67 如是相
68 怨みの連鎖を断つ
69 工夫とがまん
70 心性の白蓮華
7! 大乗精神
72 妙とは蘇生の義なり
73 順逆ともに来たれ
74 あくまで非暴力
75 末断惑の導師
76 大聖人気取り
77 本当の果報
78 現代の不軽菩薩
79 心の連鎖
80 下機を本とす
81 衆生を信ずる教え
82 仕付けるということ
83 ムリキの話
84 死を見つめるとき
85 諸仏能生の法
86 あきらめない思想
87 一人しては取り難し
88 源遠ければ流れ長し
89 木を植えた人
90 恋慕渇仰の心
91 あるべき姿に
92 ぶれない生き方
93 再生敗種の力
94 不軽利益という視点から
95 正しきことの意義
96 増上慢が大敵だ
97 我が心の中の仏
98 ポプラの木の話
99 諸法実相が合い言葉
100 「おわりに」にかえて