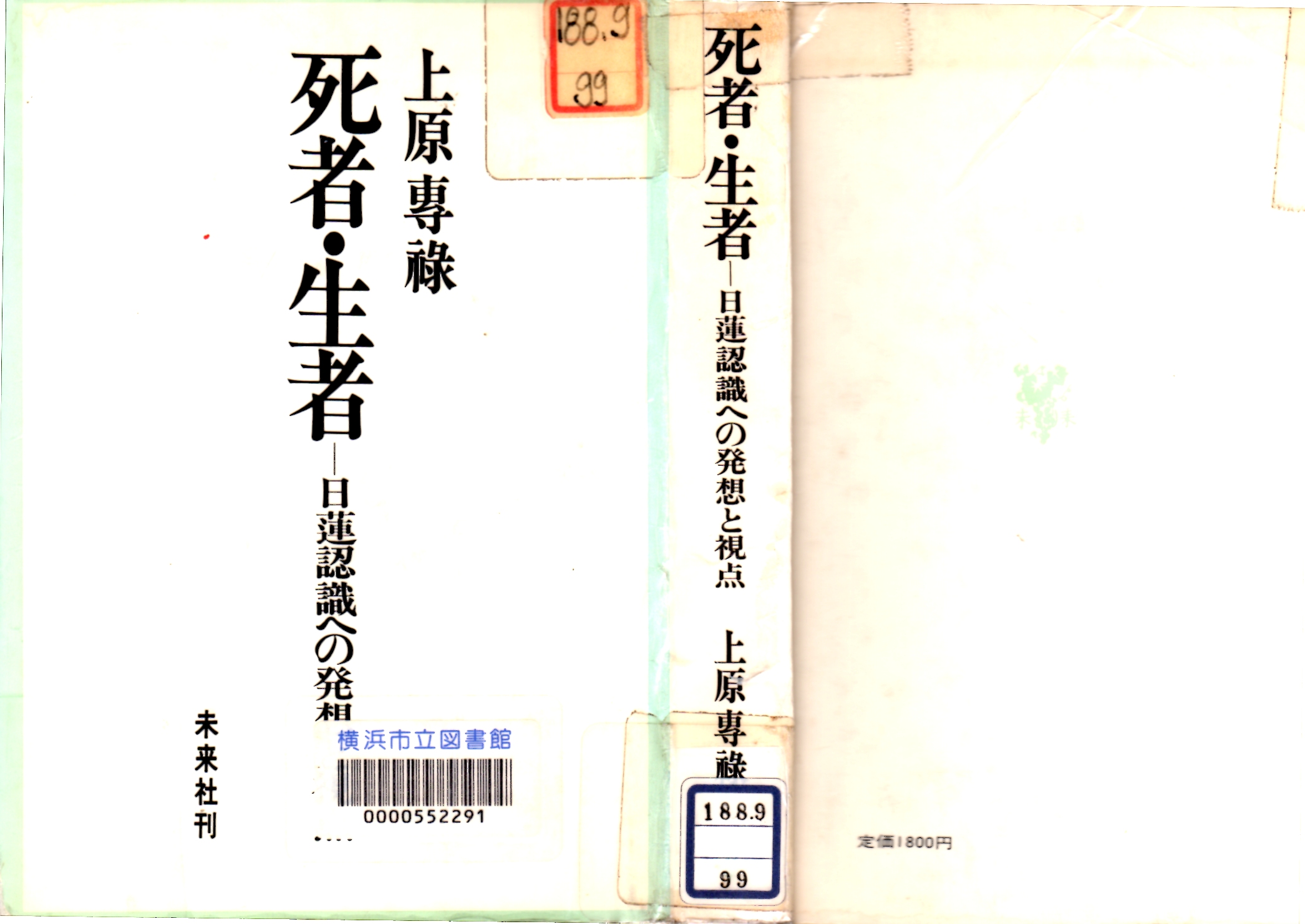
今日、歴史と社会において生きる人間や人間集団は、時には意識的に、時には無意識的に、あまりにも無慈悲に、また、あまりにも無造作に、時々刻々に「死者」を造り出しつつ、己れ自身は「死者」と隔絶した「生者」として、また、「生者」たちだけの集団として、存在し営為しつつあるようにみえる。このような人間や人間集団にとっては、「死者」とは過ぎ去ったものであり、存在を喪失したものであり、権利と意味を放棄したものであり、要するに空無に他ならないものであるだろう。したがって、このような人間や人間集団にとっては、「死者」と共に存在する「生者」、「死者」と共に生きる「生者」、「死者」と共に闘う「生者」のごとき理念は、自己矛盾の観念に過ぎず、「死者」と共存し、共生し、共闘する「生者」のごときイメージは、現実の歴史と社会においては実在したことも、実在していることも、実在するだろうこともない虚像にすぎないものであるだろう。つまり、このような人間や人間集団にとっては、歴史と社会は、「生者」によって独占せられ、それのみによって形成せられ、そのためにのみ営為せられている時間的・空間的構造に他ならないだろう。
しかし、成心を去り、思いを柔軟にして、歴史と社会との現実を凝視すると、歴史と社会は、いずれの時代においても、また、いずれの地域においても、つねに「死者」と「生者」との共存・共生・共闘の時間的・空間的構造として存在したし、存在しているし、そしておそらくは今後も存在するだろうことを、あるいは発見し、あるいは洞察しうるのではあるまいか。それにもかかわらず、今日、多くの人間と多くの人間集団にとって、歴史と社会が、「生者」のみが独占し、それのみが形成し、それのためにのみ営為せられる構造を意味しているのは、たまたま今日の、まさに多くの人間と人間集団の転落している「生者エゴイズム」とかれらを呪縛している「生者コンプレックス」に由るのではあるまいか。今日形成せられつつある歴史、今日営為せられつつある社会は、この狭量で排他的な「生者エゴイズム」と、怯儒で自閉的な「生者コンプレックス」のために、自己の連続性と一体性を喪失してゆき、自己同一性を自ら否定してゆくことにおいて、自己分裂と自己破壊の道を歩みつつあるようにさえみえる。そうだとすれば、「死者」と「生者」との共存・共生・共闘の理念は、現実をたんに認識するための方法概念でありうるだけではなく、現実を救済するための実践原理としても妥当するのではあるまいか。
もとより、「死者」と「生者」との共存・共生・共闘の理念に私が行き着いたのは、歴史と社会との凝視を通してではない。その理念に私が近づき始めたのは、身辺の生活的現実としての妻の死という私的体験を介してであった。妻の死は私から生きるための構造と基盤を奪い去り、私に生きることの自信と原理を喪失させた。そのような絶望の生存情況の中で、おそらくはそのような絶望の生存情況の故に、私に徐々に感ぜられてゆき、やがて信ぜられていったものが、亡妻と私との共存・共生・共闘の事態に他ならなかった。だから、私が最初に達しえたのは、「死者」たる妻と「生者」たる私との、個別的特殊的な事実関係についての実感に過ぎなかったのであり、「死者」一般と「生者」一般との普遍的な関係についての認識でもなければ、いわんやその理念でもなかったのである。いずれにしても、偶然的情念に過ぎぬかも知れないような、亡妻と私との共存・共生・共闘の生活感党が、やがて歴史的・社会的な必然的理念にまで定着させられ、深化させられてゆくためには、思索と観察と行動による検証の積み重ねが必要とされた。
私はその検証の最初の手がかりを、問題の新しさに応じた新しい発想と視点における日蓮認識の諸作業のうちに見出そうとした。なぜなら、日蓮とは、私にとっては、私が私自身を知覚する以前において、すでに私に与えられていた擁護者的聖者であり、私の生涯のあらゆる時期において私の質凝に解答を与えようとしてくれた教師的人格であり、苦境と難局に私が遭遇する毎にそれらを克服する視点と方策を私に示唆してくれた導師的存在であるからである。しかし、日蓮が現実に擁護者的聖者・教師的入港・導師的存在としていきいきと私の面前に立ち現われてくれるためには、いつも私の側で、自分の問うべき問題をつねに事新しく厳選し、自分の負うべき責任をその度毎にあらためて明確にしつつ、日蓮に対して問いかけねばならなかった。私がそうしなかったなら、日蓮は黙して語らなかっただろう。その故に、今度もまた、まず私の側で姿勢を正さねばならない、と考えた。そこで、妻の死によって完全に圧倒され、妻の死を過去化することの不可能な問題意識の中で、「死者」と「生者」とをつなぐ唯一の道として「回向」というものが残されていることに想到した私は、「ただ回向においてのみ生きよぅ」と決意した(本書一『過ぎ行かぬ時間』参照)。その上で私ほ日蓮に回向の方法と内容について示教を乞うた。日蓮の示教は慈愛にみちたものではあったが、同時に峻厳をきわめたものででもあった(本書三警『誓願論』参照)。その教えを受けた私は、「ただ回向においてのみ生きよう」としたその決意を実践に移すにほ、そのための客観的条件を造出しなければならないことに思いいたった。諸縁のあまりにも重畳し、それがあまりにも繋縛と化している東京の地が、「回向のみに生きる」ことを私に不可能にさせていることはいうまでもない。そのうえ、まさに妻の死に縁じて、回向どころか、私の東京在住そのことをも不可能にさせようとする諸方面の動きというものもびしびし感ぜられるようになっていた。そこで回向三昧の可能性を求めて私は旅に出でたち、辛うじて古い西日本の一隅に身を寄せるにいたった。ここが今後の永住の地でありうる保証などはもとより存在しないのだが、回向の実修を暫くはさしゆるしてくれる地辺ではあるようだ。ここまで辿りついた私は、日蓮が鎌倉を去って身延に入った理由と意味について考えた(本書四『日蓮身延入山考』)。その点について考察したのは、私自身の東京退出の体験を媒介とすることによって、従来私の疑問視してきた日蓮の身延入山の理由や意味がいくらかは理解され易いものになっていることだろう、と私考したからではない。そうではなくて、やがて「死者」と「生者」とのかかわり方について私の質凝しょうとする当の日蓮が、すでに鎌倉を去って身延の住者になっている、そのような意識と在り方の日蓮であるからに他ならない。いずれにしても、『日蓮身延入山考』を書き終えて私は、漸く「死者」と「生者」との共存・共生・共闘についての日蓮の所見を質しうる地点に達したような気持ちになった。そこで行なわれた探求が、本書五『死者と日蓮』として一括されている三篇の論考である。その三篇において、「死者」と「生者」とのかかわり方という同一の問題についての、日蓮の全く多様な対応というものが検出された。それと同時に、その検討む通じて、つねに弾力的で、いつも救済性に充ち溢れた日蓮自身の信仰と教義との内奥に、わずかながらも触れることができたように私は感じた。このように「死者」と「生者」とのかかわり方について日蓮の所信を質し、また、まさにその問題にかかわって信仰実践の動的在り方について示唆をえた私は、「死者」たる妻と「生者」たる私との共に生き、共に闘おうとする、その相貌と課題についていささかの報告を試みる立場と方法を手に入れることができた、と私考するにいたった。「あとがき」に代えて記された本書六『死者と共に生きる』の一筋がその報告に他ならない。まことに稚拙な生活記録に過ぎないことを恥じるものではあるが、そこに記録された生括経験が、それに続く私の諸作業とともに、やがては「死者」たちと「生者」たちとの共存・共生・共闘の正義に輝く香潔な歴史と社会が創り出されてゆくための一機縁をなしうるようなら、そのとき亡妻への私の 「回向」 の志も始めて生かされることになるだろう。
前著『歴史的省察の新対象』の場合と同じく、『死者・生者』と広く題し、『日蓮認識への発想と視点』とあえて副題した本書の出版にあたり、未来社の諸氏、とりわけ社長西谷能雄氏、編集長聴本昌次氏に数かずのおせわになった。ここに記して深謝の意を表する。また、印刷の面倒をおかけした精興社の諸氏にもお礼を申し上げたい。
1973年10月27日
著 者