�@
����
�@
�@
�单�@�쓹
�@
�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i1�j
�@
�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i2�j
�@
�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i3�j
�@
�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i4�j
�@
�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i5�j
�@
�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i�U�j
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@�@�ځ@�@�@�@��
2�A�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̕����I�ʒu
3�A�u�{�������v�Ɓu�S�Z�ӏ��v�̊W
4�A�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̖{�����v�z
�@
�@
�@
�@
�@�{�_�́A�����嗬���w�̎和�ł���{�����v�z���ǂ̂悤�Ɍ`������Ă������Ƃ��������������̂ł��邪�A��X�̐���A���͓����̍l�@�ɕK�v�ȏ��ޗ�����āA���̊o���ɂ��悤�Ƃ�����̂ł���B
�@�{�����v�z�̓����ɂ��Ă͎����ȍ~�ɏڏq���邪�A��ʂɓ����嗬���w�̊���ƌ��Ȃ���Ă���u���@�{���_�v�Ƃ������ɂ̎�v�ȍ\���v�f�̓��ł�����ł���̂��A�{�����v�z�ł����E�{瑘_�ł���Ƃ�����B�����āA�����̋`�ɂ��āA�����嗬���ł͌×��@�c�E���@���l���h�c�E�����t�ɗB����l�Ƃ��ē`������A�ȗ������嗬�̓`���Ƃ��đ���̂�������m��Ȃ��`�ƌ֎�����Ă����B����ɑ��Ė嗬�O����́A�@�c�͖ܘ_�̂��ƁA�h�c�̓����t������֗^���Ȃ����ɂĂ˂����ꂽ�`�ł���A���������̓��e�����A�����̓`���ł���ߑ��M�̂炿�O�ɍ\�z���ꂽ�O���̂��Ƃ������ł���ƑΏ�����Ă������j������B
�@���̂悤�ɑS�����قȂ���O���҂̎咣����ѕ]���́A�����ɂ��ꂼ��̖�h�ӎ����O�ʂɉ����o���ꂽ���̂ł���A����䂦�ɖ{���Ȃ�Ȃ����ׂ��ڍׂȌ���������ȉ��l���f�ȂǂƂ�����Ƃ̘J�́A����܂łقƂ�ǎ���Ă��Ȃ������̂ł���B���̌����̈�[�ɂ́A�W�����̎�舵���̓����A�������̂��̂̏��Ȃ����Ƃ�����ւ��������邩�A������ւ��ǂ��ɂ��N���A�[���Ė������̒[���ɕt���Ȃ�����A�E�̂悤�Ȗ嗬���O�̕��s��Ԃ͂��ꂩ������������Ă������̂Ɨ\�z����A����͂��݂��ɂƂ��ĕs�K�ȏł���A�������@�c���͂��߂Ƃ��鏔��t�̐M�I�w�͂ɑ���Y���ł���ƍl������B
�@�{�o���́u�{�����v�z�̌`���v�Ƃ���悤�ɁA�{�����v�z�Ƃ����l�����͓����嗬�ɂ����đ����������Ԃ����������Ō`����čs�������́A�Ƃ����F���̏�ɐ����Ă���B���̌��ʂ����猾���A����͏@�c�Ō�200�N���̊Ԃɂ�����`���Ƃ����ӂł��邩�A���Ƃ����āA�@�c�̐M�̌n�̒��ɑS�����̍��Ղ���Ȃ��������̂��A����ɂ˂�����čs�����Ƃ����F���ł͂Ȃ��B�@�c�̔ӔN�ɂ��������d�v�f�������嗬�Ɍp������A���̌�ɓƓ��̖{�����v�z�ƂȂ��čs���ߒ����l�@����ޗ������Ƃ���̂��A�{�o���̎�|�ł���B
�@�ŏ��ɁA�{�����Ƃ͓V��q�{�́u�@�،��`�v�����ɐ������{��\���̑��ŁA�v���̖{���̈��s���s�v�c�E���ł��邱�Ƃ������B�u�@�،o�v�@�����ʕi��\�Z�́u��{�s��F���E���������E���P���s�v�̈ꕶ�Ɋ�Â��`�ŁA�q�{�ɂ��A�����́u�����v�͌b���̈ӂ��܂ނƂ��납��{���̒q����\�킵�A�u��{�s�v�͖{���̍s���A�u��F���v�͖{���̈ʖ��ɂ��ꂼ��z������A���o���ɒq���E�s���E�ʖ��̎O����������Ă���Ƃ��납��A���̎O�����v���{���̖{���ɂ����鎩�s�̈��Ɖ����Ė{�����Ə̂���̂ł���B
�@����A���̖{�����Ǝ�ɑΒu�����{�ʖ��Ƃ͖{��\���̑�j�ɂ�����A�E�̈���������~�����ďؓ����ꂽ�v���{���̉ʓ������ł���Ƃ����`�ŁA���ʕi�̊J瑌��{�ɂ���ĊJ�����ꂽ�v���{���̐������w���B�@�����ʕi�́u�䐬���ߗ��E�r��v���v�̕��ɋ�����̂ŁA�����́u��v�͐^�@�����̗��Ő^���O�A�u���v�͒q�b�̋`�ŊϏƋO�A�m�ߗ��n�͒q�b�̂͂��炫�������閜�s�Ŏ����O�Ƃ��ꂼ��K�肳��A�^���O�E�ϏƋO�E�����O�̎O�@�����ܕS�o�_���̋v���ɉ~���ɐ��A���ꂽ�䂦�ɖ{�ʖ��Ə̂���Ƃ����B
�@������ɁA�{���ɂ����{�����v�z��v�Ď����A���̖{�ʖ��ł���ܕS�o�_���̋v�������̎ߑ���E�v�̋���ƒ�߁A����ɑ��Ė{����������v�̎��A���̋������s��F�ƋK�肵����ŁA��s��F�̍Ēa�ł�����@���l������̋���A���@�̕��Ƃ��ĐM�����悤�Ƃ�����̂ł���A���̖{������̖��@�Ɩ{�ʒE�v�́u�@�،o�v�Ƃ̊Ԃɖ@�̂̏�������čs�����Ƃ���v�z�ł���B
�@�O�q�̂��Ƃ��A���̖{�����v�z�ƕ\����̂̊W�ɂ���̂���E�{瑘_�ł���B���̗��҂́A����Ӗ��ł͓������̂���E�E�̖{瑂𒆐S�Ɍ��邩�A���邢�͖{�����Ɩ{�ʖ��̏���𒆐S�Ƃ��Č��邩�̈Ⴂ�ł���Ƃ�����B����āA���̃j�҂����S�ɕ������ďq�ׂ邱�Ƃ͖{���s�\�ł���A���ꂩ��̋L�q�̒��ł����҂ɂ͌��������`�ŐG��Ă������ƂɂȂ邪�A�����ł͂Ȃ���E�{瑘_�ł͂Ȃ��āA�{�����v�z�𒆐S�ɗ}���ď��_��W�J����̂��A���̗��R���ȒP�ɏq�ׂĂ��������B
�@���̗��҂̊W�ɂ��ẮA���s�C�G������E�{瑘_�������_�A�{�����v�z��{���_�ƕ��ނ��ďڂ��������������Ă���悤�ɁA�܂���E�̖{瑏���ɂ�艺��v�̑�ڌ����I�ю���A���̑I���̏�ɖ{�����v�z���\�z����āA������u���@�{���_�v����������Ƃ����`�ƂȂ�B������ɁA��q����悤�ɁA��E�{瑘_�̂��镔���ɂ��ẮA���łɏ@�c�̔ӔN�ɂ����ď��Ȃ��炸�咣����Ă���A���ꂩ�c�Ō�ɖ{�����v�z���`������čs�����ŁA�����قȓ��e��t������čs�������̂Ǝ��͍l���Ă���B����āA������u���@�{���_�v���ł�������L�[�|�C���g�̒S����͖{�����v�z�̕��ɂ���A���̌`���̉ߒ���_����A��E�{瑘_�̌`�������̂��Ɩ��炩�ɂȂ�ƍl������̂ł���B
�@���āA�E�ɖ{�����v�z�̍��i��f�`�������A���͂��̋�̓I�Ȏ��ۂ����邽�߂ɁA����܂œ��v�z��������S�I�����Ƃ���Ă����u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗����ƁA���̋����̒��ɖ{�����v�z���F�Z�������n�߂��Ύ����L�t�E���������t�E���{�����v�t�̎O�t�̌������A���X���Ɍ����Ă݂悤�Ǝv���B
�@���́u�{�������v�Ɓu�S�Z�ӏ��v�̗����́A���ꂼ��O��5�N�i1282�j10��11������ѓ�3�N�i1280�j����11���ɓ��@���l��荂��E�����t�ɗB����l�Ƃ��Ď��^���ꂽ�ŗv�[��̑��`���Ƃ��āA�����嗬�ł͌×����u���������v�u�����������v�u�������v���ƌĂ�Ă����B�������A���̐�����Ă�����e�����̏@�c�╶�Ɨ]��ɂ���������Ă��邱�Ƃ�A���{�͖ܘ_�̂��ƁA�M���ł���Îʖ{���������Ȃ����ƂȂǂ���A�������U������o����Ă����B
�@�u�{�������v�̍ŌÎʖ{�Ƃ��āA����܂ŕx�m��Ύ���5��E�����t�i1348�`406�j�̎ʖ{����Ύ��ɏ�������Ƃ���Ă������A���ʖ{�ɓ����t�̏����E�ԉ��⏑�ʔN�L���͂Ȃ��A�܂����̕M�Ղ���͓����t�̂��̂Ƃ��邱�Ƃ͓���B����܂œ����t�̎ʖ{�Ƃ���Ă�����Ύ����u�{�������v�̎��ƁA�����t�̎��M�����ɋ����Ă݂�̂ŁA�ꉝ�̖ڈ��Ƃ��āu�����v�̃j��������ׂĂ������������B�M�Փ��̎��鎗�Ȃ��̔��f�Ȃǂ͏��F���ꂼ��̎�ςɊ�Â����̂ł��낤���A���̗��҂̏ꍇ�͕����̍��i���̂��̂����Ȃ葊�Ⴕ�Ă���悤�Ɍ�����B
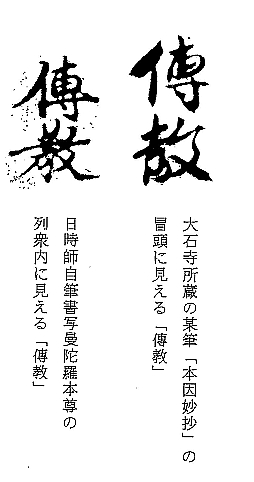 �@����ł͉��̂ɂ��̎ʖ{������܂œ����t�̂��̂Ƃ���Ă����̂��B���̖��ɂ��Ă͒r�c�ߓ��t�́@�u��Ύ����^�M�w�䏑�ژ^���L�x�̉���v�ɏڏq����Ă���̂ʼn������ꂽ�����A���̓����t�̕M�Ƃ���Ă����u�{�������v�̕M�ՂƓ����Ɣ��f�����M�ŋL����Ă��镶�����A��Ύ��ɂ͂��̊O�Ɂu�䏑�ژ^���L���v�i�u���a���v�u�i���ӏ��v�u�O���@���v�M�ʂ⏔�䏑����сu�l���`�W���v�̗v�����^�A���ڎt���`��Z�V�m���ɂ��Ă̓E�L�Ȃǂ��܂ށj�Ɓu�ܐl���j���v�u�{��S�ꏴ�v�̗��ʖ{�ƁA���ʓI�ɂ͂��Ȃ�̂��̂��������Ă���B�������A���̒��ɂ͓��M�Ղ̎�����ɂȂ�����͍��̂Ƃ���قƂ�ǂȂ��A����͑�Ύ�����ѓ����嗬�Ƃ������͂ɖڂ�]���Ă݂Ă��A�ɕω��͂Ȃ��̂ł���B����Ȓ��ŁA��Ύ��ł͓����Ɉ₳��Ă���]�ˊ��̋L�^�Ɍ���������t���M�́u�ܐl���j���v�i���݂͎U�킵�ē`���Ȃ��j���E�̖^�M�u�ܐl���j���v�ƒf�肵�A���̌��ʂƂ��Ď����I�ɂ��̑��́u�䏑�ژ^���L���v�u�{��S�ꏴ�v�A�����āu�{�������v�̎ʖ{�����ׂē����t�M�Ɣ��f�����悤�ł���B�������A����͑S����F�Ƃ��킴������Ȃ����̂ł���A����䂦��Ύ�������܂ōŌÎʖ{�Ǝ咣���Ă����u�{�������v�u�O���@���v�u�䏑�ژ^���L�v�̓����t���ʖ{�͂��ׂĖ������̂ƒ�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@����ł͉��̂ɂ��̎ʖ{������܂œ����t�̂��̂Ƃ���Ă����̂��B���̖��ɂ��Ă͒r�c�ߓ��t�́@�u��Ύ����^�M�w�䏑�ژ^���L�x�̉���v�ɏڏq����Ă���̂ʼn������ꂽ�����A���̓����t�̕M�Ƃ���Ă����u�{�������v�̕M�ՂƓ����Ɣ��f�����M�ŋL����Ă��镶�����A��Ύ��ɂ͂��̊O�Ɂu�䏑�ژ^���L���v�i�u���a���v�u�i���ӏ��v�u�O���@���v�M�ʂ⏔�䏑����сu�l���`�W���v�̗v�����^�A���ڎt���`��Z�V�m���ɂ��Ă̓E�L�Ȃǂ��܂ށj�Ɓu�ܐl���j���v�u�{��S�ꏴ�v�̗��ʖ{�ƁA���ʓI�ɂ͂��Ȃ�̂��̂��������Ă���B�������A���̒��ɂ͓��M�Ղ̎�����ɂȂ�����͍��̂Ƃ���قƂ�ǂȂ��A����͑�Ύ�����ѓ����嗬�Ƃ������͂ɖڂ�]���Ă݂Ă��A�ɕω��͂Ȃ��̂ł���B����Ȓ��ŁA��Ύ��ł͓����Ɉ₳��Ă���]�ˊ��̋L�^�Ɍ���������t���M�́u�ܐl���j���v�i���݂͎U�킵�ē`���Ȃ��j���E�̖^�M�u�ܐl���j���v�ƒf�肵�A���̌��ʂƂ��Ď����I�ɂ��̑��́u�䏑�ژ^���L���v�u�{��S�ꏴ�v�A�����āu�{�������v�̎ʖ{�����ׂē����t�M�Ɣ��f�����悤�ł���B�������A����͑S����F�Ƃ��킴������Ȃ����̂ł���A����䂦��Ύ�������܂ōŌÎʖ{�Ǝ咣���Ă����u�{�������v�u�O���@���v�u�䏑�ژ^���L�v�̓����t���ʖ{�͂��ׂĖ������̂ƒ�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@���āA���̂悤�ɓ����t�ʖ{�����ł���ƁA��������ʖ{�ł͗v�@�����C�t�̉i�\3�N�i1560�j�̎ʖ{�i���R�{�厛���j���ŌÂƂȂ�A�������T�O�N�i1572�j���̖��{������t�̎ʖ{�i�ۓc���{�����j�Ƃ������ƂȂ�B����A�u�S�Z�ӏ��v�̕����A���݂̂Ƃ���A�i�\7�N�i1564�j�̖��{�����R�t�̎ʖ{�i��c�C�f���j���ł��Â��A����ɑ����Ă�͂�v�@�����C�t�ʖ{�i�Έ�q�����j�Ɩ��{������t�ʖ{�i�ۓc���{�����j������Ƃ����B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v���Ɍ����ʖ{�Ɋւ�������16���I�㔼�������̂ڂ邱�Ƃ��ł����A�c��300�N��Ƃ������ƂŁA�ʖ{�̎c���`�Ԃ��炻�̐��{�^�ւ̑��݂��ؖ����邱�Ƃ͔��ɍ���ȏɂ���Ƃ�����B�����ŕ����яオ���Ă���̂��A���̗��������p���镶���ł��邪�A��ȌÕ����͎���2�_�ł���B1�_�͎O�ʓ����t�́u�{���������v�A����1�_�͖��@������t�́u�ܐl���j�������v�ł���B
�@���̓��A�����t�i1294�`354�j�́u�{���������v�͈��p�����Ƃ������́u�{�������v���̂��̂̒��ߏ��ł���A�{�����m���Ȃ��̂ł���u�{�������v�̏@�c��������t�ւ̑��`�Ƃ����`�������ɐ^������тт邱�ƂƂȂ�B�������A�{���ɂ��M���ł���Îʖ{�����݂����A���̂Ƃ���͑�Ύ��ɏ��������M�ʕs���ŕ\���Ɂu�ߓ����V�v�ƋL����Ă���ʖ{���ŌÂƌ����邪�A�����t�i���v�N���ځj�̎��Փ��͑S���s���ł���B���̂悤�ȕs�m��v�f�ɉ����āA���̓����t�̒�����e�Ƃ̑����u���@�@�v�Ȃǂ̎g�p���̖�蓙����A�]�����U�����������o����Ă���B
�@���ɁA����t(�`1384�j�́u�ܐl���j�������v�͓����t�̈ӂ��ē����t���邢�͐��R����t����q�����Ƃ����u�ܐl���j���v�𒍎߂������̂ł��邪�A���̒��ɖ{���E�S�Z�ӂ̗�������̈��p��������B�{���Ɋւ��Ă��A�܂��ߔN�^�U�_�������Ă��邩���A�{��12���Œr�c�ߓ��t���u�w�ܐl���j�������x�̍l�@�v�Ƒ肵�āA�V���Ȏ��_����{���ɏڍׂȍČ����������A���ɂ��̋L�q���e���獶�������i�{���@�����j�t�̏����Ƃ̋����֘A�����w�E���A�����t�i1428�`�j�̒�����Đ����������̂Ɛ�������Ă���B���́u�ܐl���j�������v���܂����{����ьÎʖ{���Ȃ��A�]�ˊ��̖����Z�N�i1658�j�ɖ��@����19��E�����t�����ʂ������̂��ÂŁA���������̎ʖ{���̂���舵�������Ȃ������A�Ƃ�����{���𖭘@������t�̒���Ƃ���ɂ͗]��ɂ���肩�����Ƃ��킴������Ȃ��B
�@���̂悤�ɉE��2���̗̍p������ƂȂ�ƁA�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗����Ɋւ��Ă��̑��݂���̓I�ɏؖ��ł�����̂̎���́A����������퍑���ւ̉ߓn���ł��镶���N�ԁi1469�`87�j�ɂ܂ʼn��邱�ƂƂȂ�B���̕����N�Ԃɂ͎���3�_�̎������w�E�ł���B1�ɂ͍��������i�{���@�����j�t�̐�q�ƍl������u�S�\�ӏ��v�̑��݂ł���B�{���ɂ͒��Җ�������N����L����Ă��Ȃ����A�����̋L�q����x�����t�͕���12�N�i1480�j�̓����t��Ɛ��肵�A���s�C�G�������t�̕���19�N�i1487�j�̐�q�Ɛ������Ă���B���́u�S�\�ӏ��v�ɂ�
���@�����Ɍ�t�������ʎ��d�̌����S�Z�ӏ��̖{瑌����L��B
�Ƃ��āu���ʎ��d�̌����v���u�{�������v�A�u�S�Z�ӏ��̖{瑌����v���u�S�Z�ӏ��v�Ɨ����Ɍ��y���A���ɂ����ꂼ��̈��p���������������ڂ����Ă���B
�@��2�́A�������������t�́u�����v���̉�����������ʖ{�����{�E�������ɏ�������Ă��邱�Ƃ��x�����t�ɂ�����Ă���B���̎ʖ{�́u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�u�{�����ӑ��`�v�u�Y�������v�̍��{�̂悤�ŁA�M�ʂ̐l������єN��͕s���B�����炭���s�E�v�@���ɂ��������̂��A�]�ˊ��ɗ��o�������̂ƍl�����邪�A���̉�����
�@�{�j�]�N�A�{���@�����V
�ȑO�����鑠���n������t���s嫃��L���g���`�A�A�C�e�����j�_�B�n���{���@�V�j��V�L�k�B�R���Ԗ{�������F�X�����X�]�]�Bৃj���L��l�����{���\�V���P���ʃV���k�B�ߔN����g�\�X�s�v�c���l�L���e���M�L���V�B���ט��탊�P�ȃe�s�R���V�V�B�ȃe���{���L�L���Z����B�A���{���V�S�Z�P���n�҈ȃe���q����L�v�V�Y�M��B���j�]�N�A�s�R�L���̃j�s���n�V���A�㌩�L�L����ӓ���B
�@�����\��N�����������@�����ݔ��B
�@�y�����\���N�\���\����̓��扜���L��z
�@�@�{�j�]�N�A���䎛�����l�j���^�V�V���B�����\�ܖ��K�ތ��\�ܓ��@�����ݔ��B
�ƋL����Ă���B�����ɂ͖{���E�S�Z�ӂ̗������܂ނƍl������u�鑠���v������t���t���̓��s�t��葊�`�������ƁA����ы��s�E�v�@���̑O�g�ł���Z�{����\��E���L�t�i�`1487�j�����́u�鑠���v������t�����ʂ������ƂȂǂ��L�^����Ă���B����āA���s��o�_�̓����嗬�ł͓����t�ȑO���u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�����u�鑠���v�̖��̉��ɑ��`����Ă���A���̗����̐����������炭15���I�����ɂ܂ł͂����̂ڂ���̂Ƒz�肳���B�Ȃ��A�����E���s�E���L�̎O�t�W�̈�[�������A�������N�i1469�j���ɓ����t�������̖��Ŏt�E���s�t�Ƌ��ɓ��L�t�̑㊯�Ƃ��āA�������{�Ɂu�Џ�v����悵�Ă��鎖�����m�F�����B
�@��3�̎����́A�g���R�v������11��̍s�w�@�����t�́u���ƒ����`�v�ɏ����͎�����Ă��Ȃ����A�u���]�v���Ƃ��āu�{�������v���l�ӏ��ɂ킽���Ĉ�����Ă���B�{���ɂ́u�����\�O�N�h�N�������@�����䔻�v�ƋL����Ă��邪�A�E�́u�{�������v�̕��Ɋւ��Ă͈��p�����œ����t�̃R�����g���Ȃ��A���̈��p�̈Ӑ}���s���Ƃ��킴������Ȃ��B�������A���̎����ɐg����v�嗬�̓����t�����`���̒��ɋ�����ڂ��Ă��鎖���́A���̐�����������x�����̂ڂ点����̂ƔF�����邱�Ƃ��ł��悤�B
�@�Ȃ��A�u�S�Z�ӏ��v�̉����ɂ�
�E�A�����������v�������n�A���l�o�����{���A�O�����������H��B��l����Ŗ��N�������s���e�����Z���B�L������v���s�ҁA�L�����t�q�g��������B�c�c�ݓ�嫃��׃��g�t�햳�L�V�O�ʏ��������`�҃n�t�����N�փV���t�Җ�B�R���ԋʖ��v�n���阦�J�R�A���ڃn�O�ʘ�������B�ԗ����j�����j�L����s�@�����]�]�B���e���^�V�����B
�@�@�@�@���a���N�p�q�\���\�O���@�@�������X�����j�V���B�E�A�������v�{瑏���n�җB����l�V������A�R���j���R�V�{�o�@�����E���X�ؖL�O��苗������n�ғ��ʎ唺�����l��A�n���E���c�E�����E���R���݁X���X�j��s�@���߃��X�����Z��A���e�s翓��j�������y���w���L���V�A嫃��R���g�˃e�ʌ��̓j�t���X�V���A����Z�p��s�@�ю����A�w���y�T�����A���o�����q�̕��j�������������ю�����g��ڕL���B
�@�@�@�@�N�i���N�p�ߏ\���\�O���@�@�������X����E�����j�V���]�]�B
�Ƃ���A����ɓ����́u�S�Z�ӏ������v���ɂ�
�E������`�n�Ғ��X���ŗv��A�R���j�������E���c�����V�O�ʏ��j��s�@�����X�V���A����E�n�����n���X�ؕ������t�����A���R�E���J����������i�@��A���c�E�����E���v�����X�؉͓����t���_�j�R�������c���]�]�A���e�������V���_�j�V�L�k�]�]�B
�E�����錈�n�ғ�����X���ŗv��A�R���Ԗ@�������V�̃j�ȃe�e�ʘ��[�`���n����㈢苗����T�j���^�V�V�L�k�B�������T�و�苗����s�j���^�X�V���B
�ƋL����Ă���A�u�S�Z�ӏ��v�̑��`�o�߂���̓I�Ɏ�����Ă���B���R�A����炷�ׂĂ��j���Ƃ��Ď�����ɂ͂����Ȃ����A�E�q�̂悤�ɁA���Ȃ��Ƃ����s�\�\�����Ƃ�������͊m�F�����̂ŁA��͂��̌n�����ǂ��܂ők��ł��邩�Ƃ������Ƃł���B
�@����A�u�{�������v�̓��C�ʖ{�̉����ɂ�
�E�A�{�������ꊪ�A�ȃe���z��s�@������l���M�V�{���ʃV�V���L�k�B�A���e�ޘ��{�e���V�������ʔV���`�B�R���j���Z�{�����Z��l�]�N�A�����{�������n���������V�M�Ֆ�B�����؋��n�ғ��R�����Γ��V�����g�^�����������������哯���̖�B
�@�@�i�\�O�M�\�N�\�j���\�������ʃV�V���L�k�B�@�@���C�ݔ��B
�Ƃ������C�t�̏������݂�����A������S�ʓI�ɐM�������ɂ������Ȃ����A��͂�����嗬���ł̗��`���F�Z����������B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�����������q�ϓI�ɔ��f�������ʁA�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v��2���Ɋւ��Ă͂����悻15���I�������炢�ł̑��݂��F�߂���B�܂��A�����嗬�ɂ��̑��Ղ̑������c����Ă���Ƃ��납��A���邢�͓����嗬���Ő��������\�������낤���A�ƍl������B
�@�܂��u�{�������v�ꊪ�́A�`����t�Ő��̐�q�Ɠ`����u�O��͑`���ʑ��������v�ɑ��ē��@�̋`���R�����g��������Ƃ����`�Ԃ���{�I�ɍ̂��Ă���B�܂�A�����Ɏ������u�@�،��`�v�u�@�ؕ���v�u�����~�ρv�̓V��O�啔�ɂ��Ă̎��ʁi���d�j�̌��������p���Ȃ���A�����ɐ������V��@�`��ނ��ē��@�̐��`�������A����ɑ䓖���Ƃ̃j�\�l�Ԃ̏����u���ʕi����厖�v�̒i�Ȃǂ��������đS�̂��������Ă���B
�@���āA���́u�O��͑`���ʑ��������v�͓��������Ő����匳24�N�i808�j5���ɕ������̓�畘a�����O��͑`�ɂ��Ă̎��d�̑��ӂ�`������A������L�^����̍قƂȂ��Ă��邪�A���̓��e������×���蒆�Ó��{�V��ɂ�����U��Ƃ��Ď�肠�����Ă���B���������A�E�̒匳24�N�Ƃ����L�q���炵�āA�Ő��͒匳21�N�i805�j5���ɋA���̓r�ɂ��Ă���̂Ŏj���Ɩ������A���邢�͉���24�N���匳21�N�̌�L���Ƃ���������Ă���B����́A��͂蒆�ÓV�䕶���ōŐ��ɉ�������Ă���u�C�T�����`���L�v�������悤�ɒ匳24�N3���ɐl�����̍Ő������`�����v�`���������߂����̂Ƃ��Ă���A�����N���̋L�ڂƂ����d�v�����ɂ��Ă̂����܂��ȑԓx�������Ă���B�u�O��͑`���ʑ��������v�ɂ��āA�c���F�N���͓����Ɏ~�ϕʗ��������ł��o����Ď~�ς̐�ΐ�����������A����ɂ̎O���ɋ��̎O�����z�������Ȃǂ̋`��������Ƃ��납��A���q�����i1250�j���疖���i1300�j���̐����Ɛ��肵�Ă���B
�@����A�u�S�Z�ӏ��v�́u�{�������v���V�䋳�w�������߂���`�ł������̂ɑ��āA�u�E���㘦�{瑏���v51�ӏ��Ɓu��{瑏���v55�ӏ��̍��v106�ӏ��̍��ڂ�݂��āA�Z���Ȃ�������ꂼ��������������Ă���B���̓��̑����̍��ڂɂ��Ă͒E�̏d�Ǝ�̏d���Ή�����`�ŋL����Ă��邪�A���̐������Ȍ��Ƃ������A���Ƀ����I�Ȃ��̂ł���A����䂦�����̂Ȃ��肩�Ȃ����Ƃ�A�p�����Ă�����̊T�O����肵�Ă��Ȃ����������邱�ƂȂǂ��������āA�������鏔�{�ł͑S�̂𐮍��I�ɗ������邱�Ƃ͂��Ȃ�ނÂ������ƍl������B
�@����ȁu�S�Z�ӏ��v�ł͂��邪�A���Ƃ��Ίe���ڂ̃^�C�g���𒍈Ӑ[�����Ă݂�ƁA�u�{�������v�Ƃ̋قȊW�����Ď�邱�Ƃ��ł���B�u�E���㘦�{瑏���v�̍ŏ��̕��ɂ���^�C�g�����E���Ă݂�ƁA
�@��j�n������O�O���S�O�ϖ{瑁B�E�E�E
�@�O�j�n������㘦�{瑁B�E�E�E
�@�l�j�n瑖�ח��~���v���{瑁B�E�E�E
�@��j�n�n�]�s�j�@�،o���{瑁B�E�E�E
���ƂȂ邪�A������u�{�������v��
��]�A���ʕi����厖�g�]�t��@�@���B���e�]�N�A�B�������@���B��㉞�����C�L���q�J�G�^�����n�����㘦�@���i���n�A�@�ꕔ���j������O�O��A瑘��㘦�{����ʃ]�g���ӃZ�V���������A�E�v����m�\��B������g�n�ҋv�����������������@���]�s�j���^�T�Y�A���B�����ώ��s����O�O�瘦�얳���@�@�،o����B
�Ƃ�����i�ƑΏƂ����Ă݂�ƁA�u��㉞���v��u�]�s�j���^�T�Y�v�Ƃ������t�����͑��Ɍ����Ȃ������I�Ȃ��̂ł���A���邢�́u�S�Z�ӏ��v�̈ꕔ�́u�{�������v�̌����������ړI�Ő������Ă���悤�Ȋ�������B�܂��A�u�S�Z�ӏ��v�́u�E���㘦�{瑏���v�Ɍ�����
�j�\��j�n�E��瑉����ʘ��{瑁B���@�j�n���σ��{�g�p�t�B�̃j�V��n瑃��ׂ��{�g�A�{��瑖m�s�X����B
�ƁA����ɑΉ�����u��{瑏���v��
�j�\�O�j�n�{�����ʔV�{瑁B���@�j�����s���{�g�V�A�ݐ��m���@�g�j�n���σ��{�g�X����B�V�䘦�{���n�����㘦���i���n���瑖嘦�����A��Ƙ��{���n�����㘦�{��B
�̗����Ȃǂ́A�u�O��͑`���ʑ��������v�Ƃ�����x�[�X�ɂ����u�{�������v�̊W���̂��̂�����������̂ł���A�u�V�䘦�{���v�Ɓu��Ƙ��{���v�͂��̂܂ܗ����ɊY�����錾�t�ł͂Ȃ����ƍl������B
�@����ɁA��͂�u�E���㘦�{瑏���v�ɋL�����
�O�\�j�n�E���ܖ����]���{瑁B�V��`�����ܖ��n���G�g���j���]��B�ܖ��n�{�A�C�s���l�n瑖�B�ݐ��Ȕ@�����]�X�@
�ƁA�u��{瑏���v��
�O�\�O�j�n�ܖ��咆�V�{瑁B���@�K�ܖ��n���G���j�ܖ��嘦�C�s��B�ܖ��n���{��A�C�s�n��瑖��B
�Ƃ��������̐��������ꂾ���ł͈Ӗ�����邱�Ƃ͓�����A�u�{�������v��
��s���`���v�t�����s�V�n���ϔ���F�������ܖ��V�嘦�C�s�i���B�̃j����������V�˃��v�p�j
�Ƃ������͂�ǂނƁA���̒��́u�ܖ��V�嘦�C�s�i���v�Ƃ����ꕶ�ɂ��Ẳ���ł��邱�Ƃ��m����B���Ƃ��A���́u�ܖ���v�Ƃ����\���͏@�c�╶�u�]�J�a��Ԏ��v��
�@����ȂČܖ��ɂ��ƂւA�c�c���܌o�͓����̔@���A�όo���̈�̕������̌o�͗����̔@���B��̔ʎ�o�͐��h���A�،��o�͏n�h���A���ʋ`�o�Ɩ@�،o�Ɵ��όo�Ƃ͑��̂��Ƃ��B�����όo�͑��̂��Ƃ��A�@�،o�͌ܖ��̎�̔@���B���y��t�]�N��_�X���n���|���A�@�n�B�ȃe�J���������׃X��������g�B�ƃ��������������Ӎ݃������j�]�]�B���]�N�̃j�m���k�A�@�n�׃���혦���哙�]�]�B���߂͐����@�،o�͌ܖ��̒��ɂ͂��炸�B���߂̐S�͌ܖ��͎������₵�ȂӁA�����͌ܖ��̎��B�V��@�ɂ̓j�̈ӂ���B��ɂ͉؊ށE�����E�ʎ�E���ρE�@�ؓ��N��햡��B���߂̐S�͎��O�Ɩ@�Ƃ�����ɂɂ���B���Ԃ̊w�ғ����݂̂�m���āA�@�،o�͌ܖ��̎�Ɛ\�X�@��ɖ��f�����ւɁA���@�ɂ��ڂ炩���郋��B�J���J�A�قȂ�Ƃ������~�Ȃ�Ɖ]�]�B����瑖�̐S�Ȃ�B���o�͌ܖ��A�@�،o�͌ܖ��̎�Ɛ\�X�@��͖{��̖@���B
�Ƃ�����i�Ɋ�Â������̂ł���A���O�o�̉~���������ɗ����āu�@�،o�v���ܖ��̐���ƒ�߁A���ꂪ�{��̖@��ƋK�肳��Ă���B�������A�����Ɂu�ܖ��̎�v�Ƃ͂����Ă��u�ܖ��V�嘦�C�s�i���v�Ƃ����\���͂Ȃ��A��͂�u�S�Z�ӏ��v�̐����͒��ځu�{�������v�̕��ɂ��ĂȂ���Ă���Ɣ��f�����B
�@�Ȃ��A���́u�]�J�a��Ԏ��v�Ɍ�����u�ܖ���v�̋`���d�v�Ȉ�̈˂�ǂ���Ƃ��Ė{瑏���`���咣����̂��c�і[�����t�ł���B�����t�̖{�����v�z�ɂ��Ă͂��ꂩ�炵���ΐG��邱�ƂɂȂ邪�A�{�����E�S�Z�ӂ̗����Ɠ����t�̊Ԃɂ͋����֘A������������B���Ƃ��A�E�́u�S�Z�ӏ��v�́u�V��`�����ܖ��n���G�g���j���]��v�u���@�K�ܖ��n���G���j�ܖ��嘦�C�s��v�Ƃ��������̒��Ɍ�����u���G�v�Ƃ�����́A���ꂾ���ł͉����Ӗ����Ă���̂�������Ȃ����A�����t�́u�ܒ����v�ɂ�
�q�]�A�Ȗߌ��X���@�@�،o�E���Ӕ@���B���A�߃g�]�n���ߘ���j�N����B�̃j�n���j�A�n�\�j��B���̃n�����n�Ȍ����l�������̉��ߖ�B�n�Ȏl�����ی��j�A�O�l�����e���ז��g��ヒ������̒G�ߖ�B
�Ɩ߁����߁E�߁��G�߂Ƃ�������������A�����炭���̂悤�ȋ`���āu�S�Z�ӏ��v�Ɂu���G�v�Ƃ����ꂩ�t�����ꂽ���̂Ɛ��������̂ł���B
�@�Ƃ�����A�ߏ�̐�������u�{�������v��O��Ƃ��Đ��藧���Ă��镔�����u�S�Z�ӏ��v�ɑ��݂���\�����������Ƃ��m���A�{�����E�S�Z�ӂ̗����̊Ԃɂ́u�{�������v���u�S�Z�ӏ��v�Ƃ����O��W���ꉝ�z��ł�����̂ƍl������B
�@
�@�u�{�������v�͖`���Ɂu�@�ؖ{��@�����������v�Ƒ肳��Ă��邪�A����Ɗ����̓�ӏ��Ɂu�{�����V�s�ғ��@�L�V�v�ƋL����Ă���Ƃ��납��A�×��u�{�������v�ƒʏ̂���Ă����ƍl������B�Ȃ��A��q����悤�ɁA�{�����Ƃ����p��͖{���ł͉E�̓�Ⴉ���邾���ŁA�{�����ɂ͗p�����Ă��炸�A����Ӗ��ł͔��ɓ����I�ł���B
�@���́u�{�������v�̎咣���ł�������₷���`�ŏo�Ă���Ǝv����̂��A���`���ʌ��̑�O�E�l�d��[�̈�ʂɂ�����L�q�ł���B�u�O��͑`���ʑ��������v�ł͖��E�́E�@�E�p�E���̌d���̂��ꂼ��Ɏl�d�̐�[�̎߂�݂��āA���Ƃ��ŏ��́u�����l�d�v�ɂ��Ă͎��̂悤�ɐ�����Ă���B
�����l�d�g�n�ҁA��j�n���̋䖳�혦���B���N�@�؛ߑO�����j�n���X���̖��혦�`���B�݃q嫖��X�g�@�̏�Z���`���˃����d�����j��X���`�j�B��j�n�̎������B���N�@�ؘ��n�o��j�n���X�s�ϐ^�@���B�̃n���j�V�e�����n������i���B�O�j�n���̋���B���N�{�o�嘦�O��n�O�瘦�����A�{�L��Z�j�V�e����s�]�σZ�B�l�j�n���̕s�v�c�B���N�˃��n���Ә��ӎҗ����e�v�ʌ��ꃒ�X�V���̘��s���B�̗p���@�R�g�V�e���O���^�i���B
�@����͖���̂Ƃ̊W�Ŏl��ɕ��ނ��A���ꂼ��u�@�؛ߑO�����v�����O�E�u�@�ؘ��n�o��v��瑖�E�u�{�o��v���{��E�u���Ә��Ӂv���ϐS�ɔz������Đ�[�E��������Ă���A�u�l�d���p�v�Ƃ������ڂ��������Ȃ����A���̒��O�Ƃ�����ۂ�^����L�q�ł���B���́u���m�l�d�v�̈�i�ɂ��āu�{�������v�ɂ�
��j�n���̖��혦�`�A���O�����o���@��B��j�n�̎������A瑖�n�o����i���B�O�j�n���̋���A�{��{�o��Z�i���B
�l�j�n���̕s�v�c�A�����ϐS���B���얳���@�@�،o��B�X�R���]�N�A嫒E����{��]�X�B
�ƋL�q����Ă���B�����ł͓V��̋`�ɂ������l�E�ϐS�d�ɂ��āu�ϐS���B���얳���@�@�،o�v�Ǝ�����A����Ɂu�X�R���]�N�A嫒E����{��]�X�v�̈ꕶ���炻�ꂪ����v�̖��@�ł���Ƃ������Ɓi���@�j�̋`���q�ׂ��Ă���B���̑�l�d�ɂ��ẮA�����ɂ�
��K���ؘ����ʕi���s�m��O�O���B
���@���~���v�t�������@��B
���ʕi�������꘦�@��A����p��g�@�����^�����{��v����O�V�얳���@�@�،o�A嫒E����{�혦����B
�Ƃ���A����̖��@�ɂ��Ă������̖ʂ���������������Ă���B���̂����A�u���ؘ����ʕi�v�ɂ��ẮA������
��㉞�������ʕi���׃V瑖m�A���ؘ����ʕi���׃V�{�A�ߑ��v������������V�e�g�g�ʃg�j���얳���@�@�،o�g�B
�Ƃ���A�ߑ��v���������̐g��瑂Ɋ�Â��{�����̏d�ł��邱�Ƃ��m����B�܂��A�u���s�m��O�O��v�ɂ��ẮA
瑖僒�]�t����m��O�O���g�A�E�v���@�n�{瑋��j瑃i���A�{�僒�]�t���s�m��O�O��g�A���혦�@�n�ƈ�{��i���B
�ƌ����ĉ���ƒE�v�̖{瑂���������A�����
�����n�E���{瑓�僒�׃V瑁A�v���������{�僒�׃X�{�g�B
�Ƃ���A��E�̖{瑂������́u�@�،o�v�{瑓��Ƌv���������i�{�����j�̖{��ɓ��Ă��A���̂����v���������Ɋւ��Ă�
�ߑ��v�����������ʘ���g���C�s���A���@�������@���������g��ڃZ���B
���n�n�E������A�^�n���혦�@��i���B
�Əq�ׂ��āA�ߑ��ɑ�����@�Ƃ������ꂼ��̎�̂ƁA�v���Ɩ��@�Ƃ̂Ȃ��肪�L�q����Ă���B�ȏ�̐��������Đ}������ƁA�����悻���̂悤�ɂȂ�B
�@�@�y�@�،o�E�{瑓��z�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�얳���@�@�،o�z
�@
�@�@�@����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@��㉞���̎��ʕi�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̎��ʕi
�@�@�@����̈�O�O��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s�̈�O�O��
�@�@�@瑁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{
�@�@�@�E�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�����n�E�̖{瑓��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�������̖{��
�@�@�@�ߑ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@
�@���̂悤�ȈӋ`���e�����v�������̖��@�@�،o���R���Ŏߑ���蒼�����ꂽ���@���A���̖��@�@�̏O���ɉ��킵�ċ~�ς��Ă����Ƃ����̂��u�{�������v�ꊪ�ɐ������{�����v�z�̎�|�ł���B
�@������ɁA�E�ɏ����G�ꂽ�悤�ɁA�{���̖{�����ɖ{������і{�����Ƃ�������g���ł̐����͂قƂ�nj����Ȃ��B������ӏ��A���`���ʌ��̑��E�˖����`�̈�ʂŏ@�p�̗����`���߂��āu�O��͑`���ʑ��������v�ł�
�@�g�n�ҏ��싆���B�R���e��������j�ʘ����탒�B�p�g�n�ҏؑ̏㘦���\��B
�Ƃ���̂��A�u�{�������v�ł́@�@
�@�g�n�ҏ��옦����i���B�R���e�{��������j�������{�ʘ����탒�B�p�g�n�ҏ̖ؑ{���{�ʘ��㘦���\���s�i���B
�Ƃ���A�{���E�{�ʂ̌��}�����Ė{��E�{�n�̈ӂ��������Ă��邪�A����͒��ږ{�����v�z�ɂȂ�����̂ł͂Ȃ��B
�@���q�����悤�ɁA�v�������̖{�ʖ��E�ߑ��ɑ�����`�Ŗ{�����̏�s��F��ݒ肵�āA�����ɒE�v�Ɖ���v�̏�������Ă����̂��{�����v�z�̍��q�ł��邪�A�u�{�������v�ɂ͂��̍��q���\�S�ɂ͐�����Ă��炸�A�{���Ɍ������s��F�͂����܂ł��ߑ��������v�t���̈ӂɂ�薖�@�ɓ��@�Əo�����Ė��@�𗬕z�����ڂɎ~�܂��Ă���悤�ł���B����A�{�����̕��͂��̗p�ꂱ���{�����Ɍ����Ȃ����A�u�ߑ��v���������v���̌ꂪ���̋`���ꉝ�����Ă���B���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA�u�{�������v�Ƃ����ʏ̂͗]����e�f�������̂Ƃ͌����������B
�@����͖{���̒�����
�\�J�����n���؊O�p����{瑏����B��V�{瑈�v�g�C�s�Z�n���S�{��t�������C��B�E�E�E��͒�q�������j���s�o�V��`�����𗹘����σ��A�A�e�{瑃j���V�e�ꉝ����ĉ���v���T�`���߃������f�������V�����߃��h�K���R���b�B�E�E�E����J�����j�הj�V�\�͕��@���A��؏O�������i����Α�Z�V�������A���e�t�q�g���������g�A���e���������@�j�{瑈�v�g�]�t�`���\�o�V�e�A�����O�������j���N�����j�B��V�L�����S�҃n�̃e�e�ޓ����t���X�N���\�K���`�j�B���`�m�Җ{瑏��[��A��{�혦������B
���Ƃ���悤�ɁA��E�{瑂����Ė{瑈�v�`��j�����Ƃɖ{���̎�Ⴊ���邽�߂ƍl������B�܂��A���邢�͖{�����Ő��̐�Ƃ����u�O��͑`���ʑ��������v���߂��`����{�I�ɍ̂邽�߁A�S�̂Ƃ��ēV��Ɠ��@�A����ю~�ςƖ��@�Ƃ����䓖�̈�ڂ��������ŁA���̉����Ƃ��Ďߑ��Ɠ��@�̒E�v�E����v�̈ق��咣����Ƃ����`�ԂɂȂ��Ă��邱�Ƃ��������Ă��邩�A�Ƃ��l������B
�@����A�u�S�Z�ӏ��v�̕��͂ǂ��ł��낤���B�{������{�I�ɂ͖{瑈�v�`�ɑ��Ď�E�̗��ĕ����Ɋ�Â�����`���������ɂ��邪�A�����u�{�������v�Ƒ��Ⴕ�āA�{�����̉���v�Ƃ����K�肪�O�ʂɉ����o����đS�̂̏��_���W�J����Ă���B���Ƃ��A�E�̖{瑏���̑�����
��j�n�n�]�s�j�@�،o���{瑁B��㔪�������@�n�{�����m���탒�E�P�e�������N�����i���J�̓�A�ꕔ�����T������������n�A���������@������g�V�e�n�E�Z�V�{瑖�B
�Ɛ�������Ă���悤�ɁA�v���ȗ����Ԉ��܂ł̋��@�̂��ׂĂ��v���{�����̉���n�E��E�����߂邽�߂̋��@�ł���|����������Ă���B�����āA��q����悤�ɁA����͖{�����v�z�̌`���ߒ��̒��ň�̃|�C���g�ƂȂ�`�ł��邪�A�ߑ��̖{��������s��F�Ǝ����A���ꂪ�{�ʖ��̎ߑ��Ƒ��������A�{���̕�F�s���{�ʂ̕����̍����Ƃ��ėD�z���邱�Ƃ��q�ׂ��Ă���B���Ȃ킿�A��̖{瑏���̑�����
��j�n�v���������s���{瑁B�����{�����n�{���i���n�{���B�{�ʖ��n�]�s��n���̓�{���㘦瑖�B�v���ߑ��m�����������@���j������B
�Ƃ���A�攪���ɂ�
���j�n�F�@���@�@�،o���{瑁B�E�E�E�{�ʖ��n�R��������ߗ��P瑖��B瑘��{�n��{�j��B�{�����n��{�s��F���^�����{���B�{��瑃n��瑓�]�X�B
�ƁA�����đ����ɂ�
��j�n�v���]�ʌ������{瑁B�{�ʖ��n�߉ޕ��A�{�����n��s��F�B
�ƁA���ꂼ�������Ă���B�܂��A�v������̖@�ɂ��Ă��A��O����
�O�j�n�v���������̘��{瑁B�v�����������@�n�{��q�i���B�������`���ʁA�߉ރn瑖�B��{�s��F������B���@�K�C�s�n�v�����ڃZ���B
�Ɛ�������Ă���A�����ɖ{�����E��s��F�����킷��v�������̖��@�͐����ӂ̖@����䂦�ɖ{�ʖ��E�ߑ��̐����E�E�v�̋��@�ɏ���A���@�͂��̏�s��F�̍Ēa�Ƃ��Ė{��������v�̖��@�������Ė��@�̏O�����~�ς���䂦�ɁA�ߑ��̋����ɏ����Ƃ����{�����v�z�̑��������Ă���B
�@�ȏ�A�����Ō������u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗����Ɏ�����Ă���{�����v�z�̍\���T�v��}������ƁA�����悻���̂悤�ɂȂ�Ǝv����B
�@
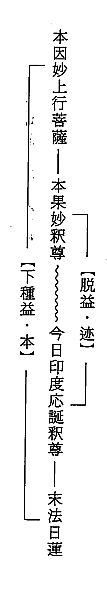
�@
�@
�@�Ō�ɁA�{�����E�S�Z�ӂ̗����Ɉ�����Ă���V��E���y�̎�Ȏߕ��������Ă������B���̒��ɂ͏@�c�Ō�ɓW�J���ꂽ�{瑓��̈�v�E����̘_�c�̒��Ŏ��グ������̂������܂܂�邪�A�{�����v�z�̐������l�@����ۂ̈ꉝ�̖ڈ��ɂȂ���̂ƍl������B
���m���`��n�]���{����瑃��B瑃n�˃����{�j
�@�@�@�@
���m���܈�n瑔n�i������j
���m���܈�n�{�������̓��n�^瑖m�s����i���B�@�̃j�A�^���e���j�ȃe���c�{瑃��B�]���̏@�p�n���j�߃X�������B
���m���܈�n�{瑃��׃X��o�g�B
���m���`���n瑘��{�n��{�j�B�{��瑃n��瑃j�B�{�嫃���i���g�s�v�c���B
���m���`���n�{瑃n��V�g�j��X�ʃj�B�����n��V�q�j��X���j�]�X�B
���m���`���n��_���n���������v�������s��i���B
���m�����n��V���N���n瑒��������T���������e�\�N���n�T���������V�{���B
���m�����n��X���͌o�j嫃������{��i���g���j����������瑘����j�w�{�����P�e�׃X�{��g�B�̃j�m�k�������V�N����瑒������v�j�B
�@�@�@�@�@�@�T���{���ߌヒ��j���N���ԃg�A���Ԙ����{�j�������v���ҏ��z���X瑘��v���A�������^���������B
���m�����n�����V��[�j�B�̃j�H�t�s��g�B
���m���\�n�̃j���N�n�@���B���V�e��j���s���g�Z�j�ڃ��B
���m���\�n�̃j�m�k����������n���N�̘����n���V�@�j�B
���m�����v�O���v���j�֕����P�I���ߎ�j�������������B
���m�L��n嫃��E�n�݃��g���j��j���N�{��j�̃j���N�{�t���g�B
���m�L��n�{�������s�n�B�^�~���X�B�����n�s�薒�L�������B
���m�L���n�X�J����l�j�B嫃�����瑗v�g��V���{�V�߃��͑������{�v�g�B
���m�O����n���n��T������j�̃j�H�q�V�^�g�A�ؒq�~�����̃j�]�t�ƘN�g�B
���m�~�ώO�n�ƈ�@�E�B�̃j���N��Ҏ~�σg��B
�@
�@�O���ł͖{�����v�z���������u�{�������v�Ɓu�S�Z�ӏ��v�����グ�āA���v�z�̓��e�̂���܂��ɐG��Ă݂����A�{���ȉ��ł͂��̎咣�̒��ɖ{�����v�z�����m�Ɍ����n�߂��Ύ����L�t�ƍ��������t�A�����Ė��{�����v�t�̎O�t�̌����������������Ă݂����B�������A���̎O�t�̖{�����v�z������ɂ͂��ꂼ��̋��w��n�̑S�̑��������A���̏�ł̓��v�z�̈ʒu����������q�ׂ�K�v������A�ƂĂ����_�Ȃǂɔ[�܂����̂ł͂Ȃ����A����͂��̐�_�̂��߂̊o���Ƃ������ƂŁA�e�t�̓����I�Ȍ������X���グ�āA�O���̖{�����v�z�̉�������Ă��������Ǝv���B
�@��Ύ���9��E���L�t�i1402�`82�j�ɂ͎��M�̒���͌������Ȃ����A�u���V���v���͂��߂Ƃ���剺�L�^�̕����ނ�8���قLj₳��Ă���B���L�t�̎��ՂƂ��Ē��ӂ��ׂ����Ƃ́A�u���숢苗������v�ɂ��ƁA16�̎��ɏ헤�����c�Ŋ֓��V��̋��w���u���v�𑊓`���Ă���A�܂���g�̔��O�@�t�Ƃ̌�������A���Ȃ葁������֓��V��̋��w��ێ悵�Ă��鎖���ł���B����͓��L�t�����ɓ��ʂȂ��Ƃł͂Ȃ��A������x�����̓��@�@�̊w�m�ɋ��ʂ������ۂł��邪�A��͂�{�����v�z�̐�����ʼn߂ł��Ȃ������ł���B�܂��A���L�t�ɂ͉i��4�N�i1432�j�@�`�V�t�̂��ߋ��s�ɕ������ۂɌc�і[�����t�Ƒ���A�u�l�����v�^���ꂽ�Ƃ����`��������B���������ɂ���ڏؖ�������̂͂Ȃ����A��q����悤�ɁA�����ނ̒��ɓ����t�̌����ɑ��錾�y��ᔻ�����邱�Ƃ��ł���̂ŁA�����t����т��̖{�����v�z�Ƃ̐ڐG�͂����炭�����Ƃ��Ă��������̂Ƒz�肳���B
�@���āA�咘�u���V���v��116���ɂ͖{���E�{�ʂƎ�E�ɂ��āA���̂悤�ɐ�������Ă���B
�P�A�ߑ����m�����j���e�����{瑃m�j�A���A�����m�Җ@�ԛߑO�n���m���q�A�@�Ԍo�n���m���q��B���F�ߑ����m���@�j�@�ԛߑO�j���m���q�������T�����n�@�����q����N����B�T�e�@�Ԍo�j�e���m���q�����T�����n���@�����m���q�m������B�T���n���y�m�߉]�A������q�m�߃V�e�����m�Җ�q�j�A�q�m�Ҍ��q���q��B�m�ґ��ʕʃm�O���n������B�~���n������B�@�ԛߑO�j�n���ʕʃm��������B�{瑖m�Җ�g��ʖ�B�����g�j���ʃm�g�݃X�̂փj�{�����m�g�n�{�A�{�ʃm�g����瑃m���֎��B�v�m�ҏC��~������~�ʃm���g���s�m�����i���g�����e�j�����m�]�t�̂փj�f�f�ؗ��m瑃m���֎惋��B�v�����ߗ��@���ڃj�J�P�e���X�ԁX�m���������֍݃X�n�F�i��瑃m������B�Ԍ��m�����m�]�t��瑃m������B�̂փj�����Ԍ��E���܁E�����E�ʎ�E�@�ԃm���m�@�ցA�@�Ԍo�m�{瑃��F�i瑕��m�����i���̂փj�{瑃g���j瑖�B�����m���ʕi�m�]��瑒��m���ʖ�B�T���n��X���n�o�j嫐����{��i���g���B�T�e�{��n�@���m�]�t�j�v���m���{�{�����m������B�v�m�҉���m�{��B����m�҈ꕶ�s�ʃm�M�v��i�������͎m��s�m�{��B�v�m�ҐM�m���n���B�S�c�j�����e�M�m�탒���X���͖{���B�����q�d�𗹃��ȃe�\�^�c�����n瑖�B�T���n��n�E�m�ʃ��~���m�Z���j�e�S�������A�����m���S�n��m�ʁA�ύs�����n�n�m�ʁA���^����n�E�m�ʃi���B�E�V�I���n�������S�m�ꕶ�s�ʃm�}�ʃm�M�j�J�w����B�߉]�A嫒E�݃g���j��j���{�탒�m�߃V�e�E�n�n�Z�ߏ�j�L���g����j�{��j�A�O���g�߃X����B���m���L�ߑ����m�����͖������S�m�M�m�{�v�j�V�e���N瑃j�n���v��B�F�{��m�v��B���c�e瑖喳�����m�@��n�o���X���i���B�������@�،o�m�{�ӖŌ㖖�@�m���m���L��B
�@���̎n�߂̕��Ɍ�����u������q�v�u�{瑁i�ҁj��g��ʁv�Ƃ����߂́A�u�@�،��`�v�掵�ɖ{��\���𖾂������̑�Z�E�O�����Ȃ̖����ⓚ�ɁB�u�{瑖�g��ʁB������q�v�i�O�����������j�ƌ�������̂ŁA�{瑓��͊O���̗p�ɏ���K����䂦�ɐg�ɖA���̑̂ɐ�[������Ƃ��납��ʂɖƂ��A����A�����j���͋@��������䂦�ɒq�ɖA�����N�����Ƃ��납�狳�ɖ�Ɛ��������B���L�t�͂��́u�{瑖�g��ʁv�́u��g�v�Ɋ�Â��ċv���{�n�̕��g�Ɉ��ʂ����A���ʐ��A�̂��߂̎��s�ł�����s�ł���{������^���̖{���Ƃ��A����ɑ��ĕ��ʂ𐬏A�����{�ʂ̕����O���̋@���ɉ����ĉ����ɕ������������́A�u�@�،o�v�̖{瑃j����܂߂�瑕��ł���Ƃ���B�܂��A�^���̖{��Ƃ͋v���̖{�������w���A���̖{�����ɂ����ċv���̖{�킪������邪�A�Z���̊K�ʂɔz����Ɩ������̏��S�ƂȂ�B���̖{�킪�ܕS�o�_���ȗ��̑������o�钆�ŏn�v�Ċύs�E�����̃j���ɓo��A�����́u�@�،o�v�{��Ɏ����ĕ��^�E����̓�ʂɓo���ē��E����B�������A���E������ɂ͖������S�̐M�Ɋ҂邱�Ƃ́u嫒E����{��v�i�O�����������j�̎߂̒ʂ�ł����āA�{�哾�E���͂��߂Ƃ���ߑ����̗��v�͂��ׂĎ��͋v���{��̗��v�Ȃ̂ł��邩��A������瑖�i�{�ʁE�E�v�j�������̖@�傪��������A�Ɛ�������Ă���B
�@�����ɂ͖{�ʂ������Ė{���Ɋ�Â��{�����v�z�ƁA�O�v�̎���������v�ɒ�߂��E�{瑘_�Ƃ��A���̗��҂̂Ȃ�������܂߂āA���ɗv�̂悭�q�ׂ��Ă���B�����āA�����ɂ����Ă͉ߋ�����������Ȃ��{���L�P�̖��@�̏O���ɂ͉���v�����Ȃ��A�v���{�������ɏ�s��F�K������������̂Ɠ����悤�ɁA����̗v�@�ł��閭�@�@�،o�̌������@���l�ɂ���ĉ�����A�������[�����O�����������̏��S�ɂ����ĉ��푦���E���đ��g��������Ƃ��������_���W�J����Ă���B
�@�܂����L�t�́A���@�̏O���̍s�ʂ͖������̏��S�ł��邩��ߑ��̈��s��{���Ƃ��A���ꂪ���@���l�ł��邱�ƁA�����ď\�E�֑ɗ��{���̒������̓��͖̂{�����̏�s��F�ł���Ǝ����āA�@�c��e�Ə\�E��䶗��{���Ƃ��������嗬�̓`���Ƃ�������{���`�Ԃ�{�����v�z�Ő������Ă��邪�A���̕ӂ肪���L�t�̑傫�ȓ����ł���ƍl������B����ɁA�u���E�����v�ɂ�
�P�A��]�N�A��s��F�m���g���@��m�n��E�m����^���{�ʃm���E�m�����A���Ӎs��F�m�Ēa�����n�{�����m��E�m�����L�k�B�R���n�{�ʖ����@�n�o�������`�ʂփn�{�����m�����n�胒���Z�q�V�ʃt���A�t�푊�V�e�z�o�m���V�M�S�m�����\�V�ʃt��B�\�E���L�V�g�]�w�g�����@�����m�t�탒�ȃc�e�����X����B
�Ƃ���֑ɗ��{���̓��������@�E�����̏\�E��Ő�������Ă��邪�A�������͂�����嗬�̓`���ł�����@�E�����̎t��`��{�����v�z�̒��Ɉʒu�t�������̂ł���A���L�t�ɓƎ��̂��̂Ƃ�����B
�@�]���A���L�t�̕����ނɂ́u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗�������̒��ڈ��p���Ȃ����Ƃ��w�E����A���ꂪ�{�����E�S�Z�ӂ̗����̏o���ȂǂɊւ��Ă���X�̉����ތ��ʂƂȂ��Ă����B�������A�E�ɐG�ꂽ�u�{瑖�g��ʁB������q�v��u嫒E����{��v�̗��߂Ȃǂ͖{�����E�S�Z�ӂ̗����ł����ɒ��S�I�Ȗ����Ƃ��ėp�����Ă��邵�A�u�G�G�����v��
�P�A������]�N�A�@�E�n�L�P���g���ܑ�j�n�s�߁B�T���z�g�j�E�E�E�B���l��@�E�m�ܑ僒��X�����i�J���{����s���@��l����t�P�e��m���X��B������ʖ퉺�m�{�Ӗ�B�T�e���c�J�R�B��^��v���g�]�X�B�{�ʃm����t�N���n���팠�i���n�ʖ퍂�X����B
�ƌ�����u���c�J�R�B��^��v�v�Ƃ����\���Ȃǂ́A�����炭�u�{�������v��
�������i�V�Ƌ������A���O瑖嘦掖@���Ζ�V�A�탌�n���{�嘦���`���A�s����L�i�����g�\�Z�V�J�n�A���N�l����ヒ�U�q�����ǃN�A���������l���N��l���B��g�q���@�r�^��q�����r�v��B
�ƋL�����u�B��g�q���@�r�^��q�����r�v�v�Ɋ�Â������̂��ƍl������B����e�A���܂������Ⓖ�ڂ̈��p�͎c����Ă��Ȃ����A���҂͉��炩�̌`�Ō����������ƍl���ėǂ��Ǝv����B
�@�Ō�ɁA�c�і[�����t�̋`�ɑ�����L�t�̔ᔻ�ɐG��Ă����������A���̗��t�̊W�ɂ��Ď��s�C�G���͎��̂悤�ɊT�ς��Ă���B
���������A���@�{���_���́A�ΎR�ɉ����āE�E�E���ꂪ���炩�Ɏv�z�I�`�ԂƂ��ĕ\�������Ɏ������̂́A���L�Ɉ��ׂ��ł���B�Ƃ��낪�A���L��������v�z��\������Ɏ������̂́A���̓����̒��Ê֓��V��̎v�z�A�܂���v�h���w�̎v�z���A���{�o�v�z�ɌX���A�ϔO�I�Ɏ��ȑ��{�����������āA���̎�̂��Ɏ��Ȃɋ��߁A�M�S�̌b����r������Ƃ���X�����������̂ł���B�����ł�����v�z�ɍR���A���̔����Ƃ��ē��@�{���������A�M�s�ɂ�鑦�g�����������Ƃ������̂ł��낤�B����͋���̓��L�����łȂ��A���L�̓�����̐�y�A�����̃n�i���w�����ɂ����ł������̂ł���B���L�������̖{������_�̋��w�ɋ��������������Ƃ��A���Ȃ�����������ʂ��̂��������̂ł���B
�@��q����悤�ɁA�����t�̖{������̋`�����L�t���͂��߂Ƃ�������嗬�̖{�����v�z�ɑ���ȉe����^�������Ƃ͎����ł��邪�A���������̒��ÓV��@����@�@��v�h�̗��{�o�E�}�v�����̎v�z�ɑR���邽�߂����œ����t�̋`��ێ悵����ł͂Ȃ��Ǝv����B�����炭�����嗬�̓`���`�ł�����@��e�{�����i���u�i�ꕔ�s���u�j���̉��V�ɑ��闝�_�I�ȗ��t���Ƃ��āA���L�t�͓����t���̉e�����œƎ��̖{�����v�z���\�z���čs�������̂ƍl������̂ł���B������Ɂu�G�G�����v�ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���B
�P�A��]�N�A��藬�j�n�������X���߃N�����j�P���g�]�t�̃��ȃc�e������ʖ퉺�m�����{�o�����L�ʃt��]�X�B�����n�x�m�嗬�m�`�j�n�q�Ҙ����s�m���S��A���m�̃n���m�̃m�Ӄn�A�����}�q�R�m�����q�k�����]���j�[�N�q�l�e�{�m����o�e�^���A�̃n�����n���l�m��m���G�^���A���m���n�ݐ��m�E�@�͎��O瑖�m�Ń`�o��f�f�ؗ��V�e��{��V�e�������o�m�僒�J�N�m���m���G�^���A�̓�q�҃m���s��B�T�e�����嗬�m�Ӄn�R�g���A���g���A���g���A�n�V�g���s�فA�A�s�m�s�o�m���҃m���ʖ�]�X�B���m���n�V�n���m�����]�X�B
�@�����Ɍ�����u���X�ɖ������߂��Ȃ�ɂ���A�]��ɎR�̉���q�˂āv�Ƃ����̂́A���ÓV�䕶���ȂǂŎ����a����̓��̂ȂǂƐ����������̂ŁA�����t�̒���̒��ł͂����Ȍ`�ŗp�����Ă���̂��U�������B���͓����t�i��藬�j���A�ݐ��E�v�̋@�����O�E瑖�E�{��ƒ�ʂ��獂�ʂւƒf�f�ؗ����čs���i�]��ɎR�̉���q�˂āj�A�Ō�ɋv���{�����̖{��ɋA���Ė������̐����𐋂���i���X�ɖ������߂��Ȃ�ɂ���j�Ɛ������A�E�v�Ɖ���v��A��������̂Ƃ��Ĉ�o�Ɛ����̂ɑ��āA���L�t���x�m��ł͒E�v���o�Ȃ��Œ��ڋv�������̉���ɎQ������Ǝ��������̂ł���A��q������v�t�̔ᔻ�Ɠ��`�̓��e�ł���B
�@�Ȃ��A�{�����v�z�Ɋ֘A���ē��L�t�̕����ނɈ�������ȓV��E���y�̎ߕ��ŁA�O�f�̏����Əd�����Ȃ����̂��E�ł����ƁA���̒ʂ�ł���B
���m�����n�C�V�e�꘦�~�������X�꘦�~�ʖm�B
���m���`��n�Z�{���{�g�n�����A�N�����{�Ӄj�B
���m�����n���鐔�w�e�����A�������V���K�����B
���m�����n�閧�g�ҁA��g���`�O�g�����ה�g�A�O�g���`��g���e�ז��g�B
���m�O���Z�n����C�����i���n�ʖ�C�����N�B����C�����i���n�ʖ�C�����V�B
���m�O�����v��V�_�Z�n�����|���A�@�n�B�N�ȃe�J���������׃X��������m�B�ƃ������R�g���������Ӎ݃������j
�@���������t�i1428�`�j�́A���s�E�Z�{���i�v�@���̑O�g�j���̏o�_�E�n�ؑ�V�i���{���j�̏Z���Ŗ{���@�����ƍ��������A�����̓����嗬�̋��w�ɖO�����炸�A����13�N�i1481�j���ɑ�Ύ����L�t�̖�ɐl�Č��������Ɖ��߁A������苗��Ə̂����ƍl�����Ă���B���N�ɓ��L�t�̖łɋ����A���̌�͖k�R�{�厛�֕������Ƃ��`���A�܂���B�̓������s��@�ł͓��n�̓�����k�Ƃ��ڐG���A����ɒ���2�N�i1488�j�ɂ͏�썑�̏�@���Łu���ڊˏW���v���q����ȂǁA�e�n�ɓ]�Z���Ē��슈���𑱂��Ă���B
�@�����t�̖{�����v�z�����������ꍇ�ɍł����ӂ��ׂ��́A���q�̂��Ƃ��t�̓��s�t���u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v���܂ށu�鑠���v�𑊓`���Ă��鎖���ł���B���ۂɂ��̒���́u�s�쏴�v��u���ڊˏW���v�Ȃǂ�����ƁA�{�����v�z����ю�E�{瑘_������ӏ��ɂ͂قƂ�Ǘ����A���Ɂu�S�Z�ӏ��v��������Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B����āA�����t�͓��s�t��藼����`������Ĉȗ��A�����ɐ�����Ă���{�����v�z����e���M�Ă������A���ꂪ�T�O�]�˂ɂ��ē��L�t�̖�ɓ]�����͉̂��̂ł��낤���B���̎��ۂ͕s���ł��邪�A�₳�ꂽ�L�q���画�f�����ꍇ�A�����炭�����̋��s����яo�_�̓����嗬�ɖ������Ă����ߑ������Ɓu�@�،o�v�̈ꕔ���u�̋`���̂ĂāA���L�t���������s�����E�s���u�̋`��I�ю�������ʂł��邤�ƍl������B�����āA����͉����̂��Ƃ����A�O�ɏ����G�ꂽ�悤�ɁA�u�{�������v����сu�S�Z�ӏ��v�ɐ�����Ă���{�����v�z���E�{瑘_�͎�ɖ{瑈�v���ɑ���{瑏�����咣���邽�߂̂��̂ł����ŁA���̂܂܂ł͂�����u���@�{���_�v�ɂȂ�����e��K�����������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B����ɑ��āA���L�t�̖{�����v�z�͓����嗬�`���̉��V�ł���s�����i�ߑ���{���Ƃ������@���l��{���Ƃ���j��s���u�i�u�@�،o�v�ꕔ����u������ڂ̌�����Ƃ���j�̎v�z�I�ȗ��t�����ʂ����Ă���A�����t�͂��̗��҂̐����������ꂽ���ʁA���L�t�̖�ɋA�˂������̂ƍl������B
�@���̂悤�Ȏ���ł��邩��A�����t�̖{�����v�z�͖{�����E�S�Z�ӂ̗����Ɠ��L�t�̖{�����v�z�̌p���Ƃ��琬�藧���Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B����Ȓ��œ����t�Ɠ��̗p��Ƃł�������̂��u�݈唺�v�ł���B���Ƃ��A�u�s�쏴�v�ɂ�
�P�A�݈唺�̎��B�ݐ��Ō�̕��@�O�ʁA�{���{�����̕�F�̌�����{�ʂ̐����𐋂���ꂽ�܂ӎߑ��A��R����̊Ԃɂ͋����̎��O�o���āA��s��F���̎l��F�ƌ���āA�@�̑�Ȃ���ȂĒr�̐[����m�邪�@���A��q�̔��������Ė�ᰂ߂���Ȃ��Ďt�̎ߑ��̋v�������������Ęe�m�ƂȂ肽�܂ӁB����Ɏ߉ވȑ剹�������l�O�����܂ӎ��A���@�̖@����������B���@���^�L��Ζ��@�̓��t���@���l�ɂČ�����̂ɁA���̎��͗�R�̎��̎߉ޑ���͘e�m�Ɛ��肽�܂ӁB�݈唺�̖@��Ȃ�B����s��F�̎�X�̐g���������܂ӎ��A�������ɎO���s�ނɖ@�ԏC�s�̌�g�B
�Ɛ�����Ă���B����ɂ��ƁA��s��F�Ǝߑ��̎t�킪�݂��Ɏ唺�ƂȂ�Ƃ����`�ŁA�{���͖{�����̏�s��F�̓����ߑ��{�ʂ̐�����������ꂽ�̂ŁA��s����Ŏߑ������ƂȂ�B���ꂩ�����̉���̂悤�Ɏߑ��O�������̉����s�̎��́A��s��F�͎t�̎ߑ��̕����������J�����邽�߂ɑ�n���O�o���A�t�̔��Ƃ��Ă��̋����������邪�A���@����̎��Ɏ���Ǝߑ��̌��v�t��������s�����@�ƍĒa���Ė��@�̏O�����������A�ߑ��͉ߋ��̒E���Ƃ��Ĕ��ƂȂ�A�Ƃ����@��ł���B�����āA�u�S�\�ӏ��v�Ɍ�����
���Ă����̒��̎߉ޑ��O�̏�����s���̎l��F�e�m�Ɛ���ׂ��]�X�B�������݈唺�Ȃ�B����̖�k�ɂ������̕��͌䗗����A��s���̎l��F�̘e�m�ƂȂ�ׂ��ƗL��B������l��F��e�m�ƂȂ�ׂ��Ƃ�߂�B�u���v�u�́v�̈�ڂȂ�B�䏑�̑O��A�O���@�̎��A��v�ėL�Ĕq���ׂ��B�A�䏑�ɉ��Ă��W�]���ʂ̌�V��L��B
�Ƃ̋L�q����A���ꂪ�u���v��
��͓��{�T����腕���ꓯ�ɖ{��̋���ߑ���{���Ƃ��ׂ��B�����̓��̎߉ޑ���A�O�̏����A���тɏ�s���̎l��F�e�m�ƂȂ�ׂ��B
�Ƃ����ꕶ�̓ǂݕ��Ɋ�Â��@��ł��邱�Ƃ��m����B����́A�����炭��q�����Ύ������̓������w�ʖ{���[���֗^���Ă���Ɛ�������邪�A���@�̖{���̏ꍇ�͎߉ށE���̏�������s���̎l��F�̘e�m�ƂȂ�Ƃ������ӂł���A����Ɂu�{��̋���ߑ��Ƃ͓��@���l�̌䎖�v�ƒf�����āu���v�̓��Y�������߂���Ă���̂ł���B
�@�������A���́u���v�̓ǂ݂ɂ��ẮA���L�t�́u�A�z�[�G�G�����v��
�P�A���@���k�m���g�����n�\�E��m��{���m���̖�B���m�̃n��s���m�l��F�m�e�m��߉ޑ���ʃt���m���̑�i���䎖��B����k�m���Ӄj�n�߉ޑ���m�e�m���s���m�l��F����ʃt�g���Ӄe���g�����m���`�����n�c�V�ʃt��B�E�E�E��s���m�l��F�m�̃n���ԃm���i���B
�Əq�ׂ��Ă���̂ŁA�����炭�����t�͂������L�t���p���Łu�݈唺�̖@��v�Ɩ��t�������̂ƍl������B
�@�����Ă�����A�����t�Ɍ����Ɍ�����̂�����̖@���{���E�{���ɒ�߂�Ƃ����`�ł���B�u�s�쏴�v�ɂ�
���@�͓��@���l�A��s��F�̐�瑂Ƃ��ĉ���̓��t�ɂďo����������B�J�ڏ��ɂ͓��@�͈�؏O���̎�Ȃ�e�Ȃ�t���Ȃ�Ƃ������O���L���̑哱�t�A����{��̎��̌�C�s���Ȃ�B�E�E�E���F�͓���̋���@����O�͖{��̖{���͖����ƍ��̐M���A���鎞�A�߉ޔ@���̈��s�ʓ��̖��s���P�A���g�����̌����@�傪�@��̌���Ɏ��܂鎞�A�M�S���A����ƐM�����Ȃ�B
�Ƃ���A�u���ڊˏW���v�ɂ�
�R��ɓ��@���l����ŗL��Ƃ��⏈���ށB���̎������̎����ɕ��@�������ē���̖@��̏��ɖ{���̗̑L��ׂ��Ȃ�B���̖@��ɒl�Е��͐��l�̐�����ŏo�������܂ӌ̂ɁA���g�̐��l�ɒl���������Ďt�푊�̑�ڂ��ɏ��֕��A�M�S�ّ��Ȃ��q�֗��A���g���V���B�v��m��ʁA���o�҂͖�����̖@��ɒl�Е�鎞�A�{���ɒl�ӂȂ�B������炸�A���m���ɒl�č��o�����������l�̔@���{���ɒl�ӂȂ�B
�Ɛ�����Ă���B����ɂ��ƁA���@�̖{���͏�s��F�ł���A���̍Ēa�̓��@���l�Ƃ��邪�A���l�Ō�͂��̕��@�𑊑���������̖@��̏��ɖ{���̑̂�����A���̖@��Ǝt�푊���đ�ڂ������邱�Ƃ��̗v�ł���Ƃ����_�@�ł���B
�@�������A����Ɋւ��Ă����L�t�́u�����E��v��
�P�A���]�N�A���c���@���l�m�䏴�j�n�A���@�n���{���m��؏O���m�e�i���g�V�V�e���n�l�m��j�e��B�A���m�t���݉ƃj�e���A���A�o�ƃj�e���A���A��E�����j�e���A���A�M�S���j�j�V�e�����@�@�ԃ��\�N�i�����l�T�`��t�e��A�\�N�\�N�S���w�V�B
�Ƃ���A�@��{���Ƃ����悤�Ȗ��m�ȕ\���͂���Ă��Ȃ����A�@�c�͉ߋ��̎�t�e�ł���A��X�͌��݂̎�t�e�����ނׂ��ł���Ƃ����ӂ������A�����炭���̕����������t�ɑ������Ďp����A���ꂪ�E�̂悤�Ȏ咣�ƂȂ������̂Ɛ��������B
�@�ۓc���{����11��E���v�t�i1436�`1514�j�̖{�����v�z��������ꍇ�ɍł����ӂ��ׂ��́A��Ύ����L�t�Ƃ͈قȂ�A�c�і[�����t�̉e���������Ƃ��ĔF�߂��邱�Ƃł���B���v�t�͋�B�������ד��̏o�g�ŁA�����̓������ɍL���ɉh���Ă��������嗬�����@�̊��̒��Ő����������A���̌㖭�{�����i�t�̌㉇�ċ��s�ɗV�w���A��ɓ����t�̉��ŏ@�`�����r�����Ɠ`������B���̓��v�t�������t�ɒ��ڎt�����ďA�w�������Ƃ��ؖ����鎑���͍��̂Ƃ��댩���Ȃ����A����4�N�i1463�j28�˂̎��ɓ����t�̒���u�@�ؓV�䗼�@���i�l�����j�v��x�m����̋v�����ŏ��ʂ��Ă���A�܂���N�A���{����P�P����P������̖����X�N�i�P�S�X�X�j�ɓ����ɋA�������ۂɂ́A���n�ɂē����t�́u���`���������i�꒟���j�v���O�ɒk�`�Ƃ��Ă���A�����t�̋��w�����Ȃ�̒����ɂ킽���Đێ悵���p���Ă���B����́A��̓I�ɂ͌㍀�ɂĐG�������t�̖{������_�ɑ���ϋɓI�Ȋw�K�Ƃ����邪�A��������͓��v�t�l�̔��f�Ƃ������́A����ȑO����̓����嗬�̏@�`���r���@�̗���������̂ł��邱�Ƃ́A��q�̒ʂ�ł���B
�@���Ɏw�E������̂́A��Ύ����L�t�̉e���ł���B���̓��L�E���v�̗��t����̂ǂ̂悤�ȊW�ɂ������̂��A����f���邱�Ƃ͌��\�ނ��������A���L�����́u���E�����v����сu�G�G�����v�̓ɂ킽���ē��L�E���v���t�̋`�����L����Ă��邱�Ƃ�A���v�t�́u�x�m�嗬���Č����v�ɓ��L�t�́u���V���v��������{�����v�z����Ɏ������l�ӏ������̂܂܈��p����Ă��邱�ƁA����ɂ͈�ӏ��Ȃ���A���v��k�u���������L�v�ɂ�
���v�]�A�T�e�̘�����������V�e�n�����̗p������B�T�e�p�����n�p�X�������b�g�q�l�ʃt���A���L�]�A�����t�g�i�����n�̃g���]�X�B
�Ƃ������ږⓚ�̊|���������L����Ă��邱�ƂȂǂ���A���̌��̔Z�������Ŏ悷�邱�Ƃ��ł���B
�@����ɁA�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗����Ɋւ��ẮA�����t�ɔ�r����Ƃ��̕p�x�͂��Ȃ艺������̂́A�u���`���v�u�䑊���v�u��厖�̕��v���̖��ڂň�������Ă���B�܂��A�ۓc���{���ɏ��������u���ܓ`����v�ɂ�
�`���V��
�E�A�ϐS�{�����E�{�������A���O��厖�A�����]���v��l���ܑ����V���A��苗������ɒv�`������B
�V����Nᡛߎ��������@�@�@�@���{���w���V���܁i�ԉ��j
��苗������`���@���B�����V���B
�Ƃ���A�u�{�������v���u�ϐS�{�����v�ƕ���Ō�厖�̕M���Ƃ��ē��v�t�����q�̓��t�ɓ`������Ă���B
���̂悤�ɓ��v�t�̖{�����v�z�ɂ́A����܂ōl�@���Ă����{�����E�S�Z�ӂ̗������Ύ����L�t�̋`�A����Ɍ�ɏ��l��������t�̋��w����������Ă��邽�߂ɁA�v�z�I���i���\�z����i�K�͂͂�߂��āA���̍��i�̏�ɂ����ȓ��Â����{�����i�K�ɂ���Ƃ�����������B���v�t�̒���̑S�e�͂��܂����炩�ł͂Ȃ����A���̒��q�X���͖{�����v�z���E�{瑘_���_����Ƃ��������A�u�J�ڏ��v��u�{���ⓚ���v�Ȃǂ̎�v�䏑�ɑ��Ė{�����v�z����̉��߂��{���A���̒��ŕs�����E�s���u���̓����嗬�`���k����`����{�ɂȂ��Ă���Ƃ�����B
�@����āA���Ƃ��u����ӏ������v�ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���B
�P�A�@�`�ɉ]���A����������։��җǗL�v���q�������̂��ƂȂ�r���ƕ���̎ᕷ�����s������Ǝ߂��āA������������S�\���������O���Z�ʂ̈������ƂȂ�_�ʂ������邱�Ƃ��A�ߋ��{�����̎��v�@���M�����͗p�Ɉ˂�Ȃ�B����Η��������g�������������͂ɂ��炸�A�v�������̗͂Ȃ�Ɖ]�ӂ��ƂȂ�B�F���̈ӂ��ȂČo�|������Γ܂�Ȃ����̂Ȃ�B
�@�����ɋ������Ă���ߕ��͖��y�́u�~�ύO���v���O�Ɍ�������̂ŁA�u������������X�R�g�n�։����ҁA�ǃj�R���v�������ƃj���N�j�탒�B��V�̃V�s���n���J�����z�s�X��Z�B�������^�僒����v�Ɠǂ݁A�����̐���������������邱�Ƃ́u�v���̏��Ɓv�ɂ����đ��̋����������̗͂Ɉ˂���́A�Ƃ����ӂł���B�����āA���́u�v���̏��Ɓv�Ƃ́u�@�،o�v瑖�ɐ������O��o�_�̑�ʕ����ɂ����鉺��v���w���Ƃ����̂��ʓr�̉��߂ł��邪�A���v�t�́u�������̂��ƂȂ�v�ƒ��L���āA������ܕS�o�_�v���́A�������{���������ɂ����鉺��v�̈ӂƂ��A���������������̔��S���̂��̂Ɛ������Ă���B�܂�������������E�����ϐS�߂Ɋ�Â���Ƃƌ����悤���A��������Ƃ��Ό�ɏЉ��A�����t���V��߂̋������d�Ȃ���v���{�����̉���`�𐳓������Ă�����ƂȂǂƔ�r�����ꍇ�A������x�̊u���肩��������B�����āA���v�t�̏ꍇ�͂��̂悤�ȍ�Ƃ����Ȃ�͈̔͂ōs�Ȃ�ꂽ���̂Ɛ�������A�{�����v�z�ɂ�������v�t�̓Ǝ����ł���Ƃ�������B
�@����ɑ��āA���̗p��Ȃǂɂ͓����t����L�t�̉e�����ꌩ���Ċ�������B���͂��̈��Ƃ��āu���h�v�Ƃ���������グ�Ă݂悤�B���Ƃ��u���̋`�������v�ɂ�
�L�e���i�j��o�n�O�n�M�S�����Ȗ�B���]���h�g�]�t����B���ɗ����E�ژA�J�O�o�i�����A��s���̓��j�����V�e���ʕi�j������{��V�e�������n�A�ߋ��n�M�S���{�n�A���i���h�g�]��B���n�ߋ��͉Ƙ����݃m�n�i�i���B�T�e����s�n�ݐ��n���؋���j�X�����n���h�j�����A�˃e���팠�ʖ퍂����s��B�E�E�E�T�e���f�f���ߋ����M�S�����o���V�ʃw�n�����q��u���m�`��B�����n��P�m��s�s���j�V�e�A�@�ރ��n�E�����n��g���`�ʂփ��B
�Ƃ���A�u�@�،o�v�{��̗O�o�i���瑮�ݕi�܂ł̔��i�̉���͏�s��F�ɂƂė��h�A�܂艼��̏h�ł���Ƃ����ӂł���B�܂�A��s��F�͉ߋ��{��������̖{��ɂ��āA�����ɖ��@�ɓ��@�ƍĒa���ċv���������̖��@�����킷�関�f�f���q�̑m�`���{���̎p�ł��邪�A���ꂪ�u�@�،o�v�̔��i�ɒf�f�̏�s�Ƃ��ėO�������̂́A�ߋ��{������薢���̖��@�֕����r���ɉߋ�����̎҂ɑΖʂ��邽�߂ɔ��i������̒��h�Ƃ��Č���ꂽ�܂łŁA��s��F�{���̂������ł͂Ȃ��A�Ƃ̋`�ł���B
�@����́A���Ƃ��Γ����t�́u���`���������i�꒟���j�v�ɂ�
2�A�A�e�O�틳���j�_���{瑘��ك����B�E�E�E���e�ȃe�O�틳�����{瑃����@�@�،o�V���{���ݏ��n����瑒������O���������j�n���V�V�B��������혦���o�n瑖嘦���j�݃��V�B���P���h��B�̃j�ߋ���ʉ��혦���j���Z�V���t�B���P�]���n��O�����j���h�i���n�����e�V�A��O�t�퉓�{�{���y���A���{�ݏ������{�j���t���t�����߃X�����A�@�O�틳����������V�Ӄg�n�]��B
�Ƃ���A�u�����̗Z�s�Z�v�u�����̎n�I�s�n�I�v�u�t��̉��ߕs���߁v�̎O�틳���ɖĖ��@�̍ݏ������������A��O�́u�t��̉��ߕs���߁v�̑��Ŗ��������v���ܕS�o�_�̖{�{�ɑ����ꍇ�́A���̒����E�v�̖��o����̑�ʉ���̖��@�́u���h�v�ƂȂ�Ɛ�������Ă���B
�@���v�t�̏ꍇ�͂��̗��h���u�@�،o�v�{��̔��i�ɓ]�p�������̂Ɛ�������邪�A��ɐG���悤�ɁA�����t�͎�E�̈�v�E��o�̗�����̂邽�߂ɖ{�唪�i�𗷏h�Ƃ��邱�Ƃ͂Ȃ��ƍl������B����āA���̗��h�͓��v�t����E����̗��ꂩ�琏�`�]�p�������̂ł��邩�A����͂����炭���L�����u�G�G�����v��
1�A���L���]�N�A栃q�n�O�m��F��m�]�t���A�n�Z�ߏ�m�����i���n���@�䓙�͔�˗p�E�]�X�B
�ƌ�����f�f�̒n�O��s�i�E�j�Ɩ��f�f�̒n�O��s�i��j�Ƃ����������āA���v�t���f�f�̏�s��F�𗷏h�ƕ\���������̂ƍl������B�����E���L�̗��t�̋��w��ێ悵�A�݂�����̖{�����v�z��g�ݗ��ĂĂ������v�t�̂������̈�[�������ɂ͌����Ă���B
�@����A���̂Ƃ��덶�������t�Ƃ̌��̐Ղ͓��v�t�̒���̒��ɂ͌����Ȃ����A�����t�̓����̈�Ƃ��ċ������u�݈唺�v�ƂقƂ�Ǔ��`�́A�{���Ɩ{�ʂ��݂��ɖʂƂȂ藠�ƂȂ�Ƃ����������U�������B�܂��A���v��k�u���������L�����v�ɂ�
�P�A��Ύ��j�n�{���n�\���A���n�����A�q���n�\���A���n�����A�q���n�\���A�{���n�����g�����i���B���吹�n���v�A���Z�n���v���s�����@�g�]�w���B���ܑ̟b�B
�Ƃ���A�����t��������������@��{���_�ɑ��āA����͍s���߂����`�Ƃ̔ᔻ���\������Ă���B�������A�s���߂����`�Ƃ������Ƃ��猾���A�u����ӏ������v��
����ΔV��ɕt���ēV�ڏ�l�A�x�R�̖�l���֓��u�̋`����Ȃ��Ƃ���������l�]���A���������ޓ������߂ɋ��P����ɂ��炸�A���ςɔC���ē�`�𗧂B��ɏ��j�̂��߁A��ɕ�����Ȃ�B�E�E�E���ɔp瑌��{�̎��ʂȂ�����̋ߏ�𖾂����B�V����ȂĔV����v�ӂɁA���֕i���u�̌��ӂ��������j�̈�i�Ȃ�]�X�B���̌�S���ȂĎv�ӂɂ͎��ʕi�����ǂނׂ��炴�邩
�Ƃ���A����E�v�̎��ʕi�ɓ��v���Ȃ��Ƃ��납����ʕi�̕s���u�ɂ܂Ř_���y��ł���B
�@�Ō�ɓ����t�́u��藬�v�̋`�ɑ���ᔻ�������Ă����ƁA�u�@�ؖ{��J�ڏ������v�ɂ�
���ɉ]���A�䏴���ɁA�@�،o�ɓ�o����A���͂��{���瑖�ƂȂ�]�X�B�@�،o�͈�o�Ȃ�Ɖ]�ӂƂ���o�Ȃ�B�v��Ƃ͎�̖@�،o�A�E�̖@�،o�Ȃ�B�ނ�͒E�A����͎�ƗV����䕶�̂Ȃ�B������藬�ɂ́A�ނ�̒E�͍���̎�ƃe�j�n����݂��ւ�Ɉ˂�Ė{���Ɏ����ӂȂ�B
�Ƃ���A�u���������L�����v�ɂ�
�P�A�䏑�]�A�ݐ����{��g���@�����g�n�ꓯ�����~��B�A�V�ރn�E�A����A�ރ��n��i�A���n�B��ژ�����]�X�B�R���j��藬�j�n�ꓯ�j���~�g�������j���e�A���@����i���א��A������������B
���ƋL�q����Ă���B�����t�̌����ɂ��Ă͌�ɏ����G��邱�ƂɂȂ邪�A�����ł͎�Ɏ�E�𗧂ĂȂ��炻�̖@�̂�Ƃ��邽�߂ɁA���ǂ͎�E�ɍ������ĉ���̓��@�{���`�𗧂Ă邱�Ƃ��ł����A�ߑ����邱�Ƃ���c����Ă���B
�@�Ȃ��A�O��ɂȂ���āA���v�t�̒���Ɉ�������ȓV��E���y�̎ߕ��ŁA�O�f�̏����Əd�����Ȃ����̂��E���Ă����ƁA���̒ʂ�ł���B
���m���`��n�������@�@�،o�n�Җ{�n�r�[�V������B
���m���`���n�{�����m�ҁA�{���j���V�e���S���s�V��F���������C�X������B
���m���܈�n瑒��j嫃����N�g�����j�����L���݃��B�̃j�]�t�{�n�g�B
���m�����n��V���q瑃��w�X�n�{���A������V�e���j�_�X�J���B
���m���\�n�{��n�ȃe�{�����׃V���n�m�A�����n�ȃe�������׃X���n�g�B
���m�����n���V�e�ݔ@���������C���j.
���m�����n���e���������j��V�e�V���s�`�B
���m�L�l�n�{瑎���n�����j�s���J�B
���m�L��n�̃j�{�嘦���ʉi�N�كi�������j�B
���m�L�\�n��O�M��m�ҁA���`�����{�嗧�s�V��B
�@���͈ȑO�A�{����10���ɓ��e�����u���s�̖@��ɂ��āi�܁j�@�O�����N�@�c�ԉ��̕ω����߂����āv�ŁA�O�����N�i1278�j4������6���ɂ����Č�����@�c�ԉ��̕ω��̈Ӗ���������A�������ȍ~�̏��䏑�ɂ���܂łȂ������u�@�،o�̌��O�v�Ƃ����\�����p�o���錻�ۓ����������āA�u�ϐS�{�����v�Ȍ�ɑ��݂����ߑ��{���ƙ�䶗��{���̗��{���`�̂����A���@�̖{���Ƃ��ę�䶗��{����I�肵�悤�Ƃ����@�c�̈ӎu�̌����ł͂Ȃ����Ɛ��������B�����āA���̙�䶗��{���I��̈Ӌ`�ɂ��ẮA���i8�N�i1271�j9���̗����@��Ȍ�̋��w�I�c�ׂ̒��ŁA�@�c�̖��@���v�ւ̋����������Ɋ�Â��āA�ߑ��̏����E�ێ�E�E�v�̍ݐ����E�Ƒ����������Ƃ���Ɍ`�����ꂽ��s��F�̋t���E�ܕ��E����v�Ƃ����Ō㖖�@���E�̈��艻�E�Ɨ������ړI�ł͂Ȃ����Ɛ��l�����B���̏�ŁA�u�܂Ƃ߁v�Ƃ��Ď��̂悤�Ɍ��_�����B
�@�c�̐M�̌n�ɂ�����ߑ��̈ʒu�Ƃ������͎̂��ɔ����Ȃ��̂�����B�O���ɂď@�c�̙�䶗��{���I��̈Ӌ`���Ō㖖�@���E�̓Ɨ����ɂ��邱�Ƃ��w�E�������A�����܂ł�����͓Ɨ����ł����ēƗ����̂��̂ł͂Ȃ��B�ƌ����̂́A�O�f�����u�ϐS�{�����v�́u�ߑ����s�ʓ��̓�@�͖��@�@�،o�̌��ɋ���v�Ƃ̕��ӂɏ]������A���̖Ō㖖�@�ɂ����Ď��B�O�����M�s���A���͍O�ʂ��ׂ����@�@�،o�̎������e�͑S���ߑ��̈��ʌ����Ɉˑ����Ă��邩��ł���B����āA��������ߑ����̂ĂēƗ��ƕ����v�낤�Ƃ����Ȃ�A���̓r�[���̐ꂽ����낵���A�Ō㖖�@���E���̂��̂̋����������炷���ʂƂȂ�B���̖Ō㖖�@���E�̓Ɨ��Ƃ����̂͑S���̃W�����}�ł���B����ǂ��A���ꂪ�@�c�̐M�̌n�̎��ۂł���A���̐���t�̂����߂��E�̙�䶗��{���I��Ƃ�����Ƃ������̂ł���B
�@�@�c�����̔ӔN�ɓ��B���ꂽ�́A����Ӗ��ł͂��̂悤�ɔ��ɕs����Ȃ��̂ł������B�����āA���̏��甲���o�����߂ɁA�@�c�Ō�Ɏߑ��̑�ւ�ݒ肷�邱�Ƃɂ���Ďߑ���ے肵�A���̌��ʖŌ㖖�@���E��^�ɓƗ������悤�Ƃ����ړI�Ō`�����ꂽ�̂���E�{瑘_�ł���A�{�����v�z�ł������ƍl������B��āA�{�����v�z���c�Ō�Ɍ`������Ă���������x�̕K�R���������ɂ͂������̂Ɣ��f�����̂ł���B
�@�����ɁA�{�����v�z�Ǝ�E�{瑘_�̊ԊW�ɏ����G�ꂽ���A��E�{瑘_��v���
�ߑ������̖@�،o�͉ߋ�����̎҂�E�v�����߂�̂ɑ��āA��s�E���@�̖@�،o�i��ځj�͖{���L�P�̖��@�̏O���ɉ��킷����̂ł���A����͋v���{�����̉�������̂܂܈ڂ������̂䂦�{�ƂȂ�A�ߑ��E�v�̖@�،o��瑂ɏ����B
�Ƃ����v�z�ł���B���̓��A�O���́u�ߑ������̖@�،o�͉ߋ�����̎҂�E�v�����߂�̂ɑ��āA��s�E���@�̖@�،o�i��ځj�͖{���L�P�̖��@�̏O���ɉ��킷����́v�Ƃ����ߑ��ݐ����E�ɑ������s�E���@�̖Ō㖖�@���E�̊m�����@�c�̔ӔN�ɒB������Ă������Ƃ́A�E�ɏq�ׂ��Ƃ���ł���B�������A�@�c���̈⌾�Ƃł������ׂ��O��3�N�i1280�j12���́u�ЋŔ������v�̞����Ɍ�����
�V�������Ό������Ɛ\���A���̏o�������ӂׂ�����B�}�K�����Γ��{���Ɛ\���A���ɐ��l�o�ŋ��͂���ށB���͐���蓌�Ɍ��ւ�A�����̕��@���֗���ׂ�����B���͓����o�ÁA���{�̕��@�����ւ��ւ�ׂ������Ȃ�B���͌������炩�Ȃ炸�A�ݐ��͒A���N�Ȃ�B���͌������ɏ����A�܌ܕS�̒��ł��Ƃ��ׂ�������B���͖@�،o掖@�̎҂�肵���͂��A�ݐ��ɂ͖�����ւɁB���@�ɂ͈��̋��G�[�����ׂ��A�s�y��F�̗��v���Ȃ�B�e�X�䂪��q���͂��܂����ցA�͂��܂����ցB
�Ƃ̋��ł́A�ߑ��̍ݐ����E�ɑ���Ō㖖�@���E�̗D�G������������A�����s�y��F�̋t���Ōۋ`�ɏW���āA���̎��H�@�̏O���Ɋ�������Ă���B��āA���̏@�c�ӔN�̂��l���Ɂu�v���{�����̉���v�v�Ƃ����d�v�f�i�E�́u�ߑ��̑�ցv�ɂ�����j��������A��E�{瑘_����і{�����v�z�̍��i�͂قڊ���������̂ƍl������̂ł���B
�@���̂悤�Ȋϓ_���炢���A�@�c�Ō�ɖ{�����v�z���`������Ă������߂ɂ́A�����2�̓�₪����Ƃ�����B��́A�v���ܕS�o�_�ɂ����鉺�킪�{���̉���ł��邱�ƁB�����āA������̓��͖{�ʖ��E�ߑ��̖{��������s��F�ł��邱�ƁB���̓�̓�₪�N���A�[����Ė{�����v�z�̌`���͎�������邪�A�ȉ��A���̓������̉ߒ��������ǐՂ��Ă݂悤�Ǝv���B
�@
�@�{���ł́A�@�c�̈╶�Ƒc�Ō���ɂ����镶�����̒�����{�����v�z�`���ɒ��ڂ���ъԐڂɂȂ���v�f���������E���グ�Ă݂悤�B�܂��A�@�c�╶����͎���3�_���w�E�ł���B
�@�@�͕��i10�N8���́u�g�؈�O�Y �a��Ԏ��v�Ɏ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B
�A�V�L���n�@�،o���s�҉V�탋�����l�����o�����]�]�B�ȃe�����o�����z���X���j���ԃj�l�����V�B�ȃe�J�N���׃��@�،o���s�Җm�B嫃��L�g�G�l�n���V�@�،o�����҃n�B�Q�w�n�@�V�L�e�����N���A�L�e�V�����J�n�B���ꐬ�����ϐ��m�@���B�\嫃����^���g���]�j���֏o�V�e�V���}���X���ꃒ�B�������@�@�t������B������A���A�s�y�i�j���e���g���ߋ��������]�N�����j�L���ꃊ����F�ꖼ�N��s�y�m���]�]�B���]�N�����l�i�l���Z�����B�@���]�N���n�ȃe��؊������ŝ��X�V�����]�]�B�ߑ������ڃe����ʘ����s������V�^�}�t���@���n���B�s�y��F���j�׃j�@�،o���փ��e������j�o���Z�^�}�q�k���o���Ɉʃj�B���@�A���o�V�̃j���g�j�혦����x���������j�B���������ʉ����^�t�V�����B
�@����́A�u�@�،o�v�����i��13��20�s�̘�ɂ͕��Ō�ɖ@�،o�̍s�҂�����A�K���O�ނ̋��G�����o�����Ĉ����E�l���E����E���o�Ȃǂ̔��Q��������|��������Ă��邪�A���������Ȃ�������ɑ��������鎩�g�E���@�����̖@�،o�̍s�҂ɂ�����Ƃ���������������A����Ɏߑ����݂�����̈��ʂƂ��Đ��������s�y��F�̎��������E���@�͐g�ǂ��F�ǂ����̂ł��邩��A�K���ⓖ���̖��ʂ������炳���ł��낤�A�Ɗ��҂���Ă���B�����ɂ͎ߑ����s�̕�F�ł���s�y��F�Ǝ������C�R�[���ł���Ƃ����@�c�̎��o��������Ă���A�{�����ւ̑����̐ڋ߂�ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł���B
�@�A�́u�ϐS�{�����v�̎��̈ꕶ�ɂ��Ăł���B
�o�j�]�N�A��{�s��F�������������P��ᶁA���{�㐔���]�X�B�䓙�J�ȐS����F����B�n�O��E����F�n�ȐS���ߑ����ő���B�E�E�E��s�E���Ӎs�E��s�E�����s���n�䓙�J�ȐS����F��B
�@����͊ԏ��O���̊ϐS�i�̖��ɂ��镶�ŁA�ߑ��̈��s�ʓ��̓�@����������@�������邱�Ƃɂ��A���@�}�v�̏\�E��̊ϐS�����A���A������Ė}�v�S����̕�F�E�������ꂽ�����ł���B������ɁA���Y�̕��ɂ��āA���~������
�ȐS�̕�F�E��_���钆�ɁA�u��{�s��F���v�]�]�̌o���ɂ��āA���߂ɂ͂�����u�䓙���ȐS�̕�F���v�Ƃ����A�Ō�ɂ́u��s�E���Ӎs�E��s�E�����s���͉䓙���ȐS�̕�F�v�Ƃ�������A�u��{�s��F���v�܂�ߑ��̖{���s�̎��̖�����s��F�Ə̂��邩�̂悤�Ȉ�ۂ���B�㐢�̕x�m�h�E���i�h�Ȃǂ̏���h���A�ߑ��̖{�����̖�����s��F�Ə̂���Ɩ��Ă����āA�������狳�w��W�J���Ă䂭�̂́A���l�̂����̕����ɂ����̂Ǝv����B�������E�����̒��Ԃɂ́u�n�O��E�̕�F�͌ȐS�̎ߑ��̓����Ȃ�v�Ƃ���A�v���̎ߑ����ȐS����ł��邱�Ƃ͂��łɑO���Ō��肸�݂ł��邩��A�v���ߑ��̖{��q����n�O��E���܂��ȐS����ł���Ƃ����Ƃ�O��Ƃ��āA�u�n�O��E�v�̏��u��s�c�c���͉䓙���ȐS�̕�F�Ȃ�v�ƂȂ�̂ł���B�������ȐS�̕�F�E�̑�\�Ƃ��āA�����Ŏߑ��̈��s���Ə�s���Ƃ̓�ނ������ꂽ���Ƃ́A�L���Ɏ~�߂Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�Ɖ���������Ă���B�����ɂ�����u�ߑ��̖{���s�̎��̖�����s��F�Ə̂���v���Ƃ��{�����v�z�̌`���ɂ����Č���I�ȃ|�C���g�ł��邱�Ƃ͑O�q�̒ʂ�ł���A���������t����s��F��{�����ƋK�肷�镶���Ƃ��āu�ϐS�{�����v�̖��������Ă��邱�Ƃ͌�q�̒ʂ�ł���B
�@�B�Ƃ��Ďw�E�ł���̂́u���@�،o�v�̈����Ɍ�����{��������і{��������ɑ���S�ł���B���A3��قNj����Ă݂�ƁA��1�́u����L�v����̎��̕��ł���B
���o���{瑓�嘦�{���n���j�كi�����o�j�B���������l�ߗǃj�L���Ȃ֖�B�̃j�l�ߘ����A�B�^����߃����N�{�ő��m�B�������߃n嫃��E�n�݃��g���j��j���N�{��j�B�E�E�E���V��߃n�{���ʃj��V�B�A�ʌ�j���j�n�V�A����j�T�`�E�X�B���j���������A�{���ʃj��V�A�ʌ�߃N�n�V�A�K�j�ߐ��j�E�X�B�w�X�n�O���҃��B
�@����͓V��q�{���u�@�،o�v�̕��X���߂���ۂɗp���������E�E�{瑁E�ϐS�̎l��߂̂����A�ŏ��̈����߂�������钆�ŁA�@���̎��ݐ_�͂ɂ��O���㐢�ɂ킽���Ď�n�E�̎O�v���߁X�ɌJ��Ԃ���邪�A���̂����̑�\�I�Ȏl�߂��������i�i�l�ߎO�v�ƒʏ̂����j�ɖ��y�X�R�������������������̕��ł���B���̒��Ɍ�����u嫒E����{��v������v���E�v�ɏ��邱�Ƃ��������Ƃ��āA�{�����v�z����ю�E�{瑘_�Œ��S�I�Ȗ������ʂ����Ă��邳�܂͊��Ɍ����Ƃ���ł��邪�A���̌�ɓ�ӏ��u�{���ʃj��V�v�ƋL����Ă���B����͎l�߂̂����A�{�ő��ł����1�Ƒ�2�̋v�������\��������ł��邪�A����ɂ��Ɩ{���Ɩ{�ʂ̗����Ŗ{�킪�����ꂽ�Ƃ����ӂ̂悤�ɓǂ߂�B�����āA������ؖ�����̂��u���@�،o�v�ʼnE���ɑ����Ĉ�����铹���́u����㐳�L�v�̕��ł���A�u�{���ʃj�탋�v�ɂ���
�{���ʎ�g�n�ҁA�������`�@���s�X����F�������׃j��������V�A�؉ʔV�����^�׃j����X�B�̃j���c�N�{���ʎ�m�B
�Ɖ��߂���Ă���A�{�������킪���m�Ɏ�����Ă���B�Ō�ɋ�������̂́u���`���܁v���\��
�����e���Z�n�n�����ҁA瑖�n�ȃe��ʃ��׃V���n�m�A�{��n�ȃe�{�����׃V���n�m�A�����n�ȃe�������׃X���n�X�B
�̕��ŁA������{�����v�z�̐����̒��ɑ����p��������̂ł���B�������A���̕��ɖ₵�Ắu�f�ȎO�l���v�ɂ�������������Ă���A������̕��ł͉��̂��u�{��n�ȃe�v�����׃V���n�m�v�Ƃ���A�{�����v���Ɖ��߂��Ă���B
�@�ȏ�A��r�I��ʂɎc����Ă���@�c�╶�̒��ŁA�{�����v�z�`���ɂȂ���v�f�Ƃ��Ďw�E�ł���̂́A���̂Ƃ��낱�̎O�_���ł���B���ɑc�Ō�Ɋ��]���������A��������ł�����̂͂��Ȃ�����Ă���B�����A�����Œ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�c�Œ���Ɍ`�����ꂽ�ł��낤���嗬�ɂ����鉻�V�̖��ł���B
�@���m�̂Ƃ���A�@�c�݂͂�����̓��łɍۂ��Ė{��q�Z�l�̍�����߁A�����炭���ꂼ��̒n��ɂ�����z�������̒��S�ƂȂ�悤�Ɏw�����ꂽ���̂ƍl������B�����āA���̈ӂ��������E���N�E�����E�����E�����E�����̘Z�t�͊����̋��_�ƂȂ鎛�@�����A�݂�����̒�q�⏊���̒h�z�Ƃ����l�I�l�b�g���[�N���\�z����}���ɒ��ʂ����ł��낤�B�����ɁA���w�I�ȑ�n��M�I�ȐS�\���ȂǂɊւ��Ă͏@�c���₳�ꂽ�������̌䏑�����̔C�߂����A��Ԃ̖��͖{���`�Ԃ�C�s�`�ԂȂǂ̉��V���ǂ̂悤�ɒ�߂邩�Ƃ������Ƃɂ������Ƒz�������B���̓��̂������̂��̂Ɋւ��ẮA�@�c�ݐ����̏�������̂܂܈����p���ŏ����ł�����̂��������ł��낤���A���@�̖{���ɂǂ̂悤�Ȗ{�������u���邩�A�����Ă��̖{���Ɍ������ē��X�����Ȃ��s�ł͉�����u���邩�Ƃ����A���ɂނ����������}���ɏ�������Ƃ����ɏ��t�͂������̂ƍl������B�����āA���V�Ƃ������͈̂�U��܂�ƁA��������߂邱�Ƃ͔��ɍ���Ȃ��̂ł���A����Ӗ��ł͂��̌�̖嗬�̗��j����ɋ����S�����Ă������ƂƂȂ�B
�@�����嗬�̏ꍇ�͔h�c�E�����t�̈ӌ��ɂ��A�@�c�����̏\�E��䶗��{���Ə@�c��e�����{���Ƃ��Ĉ��u����A���X�̋s�̏���Ƃ��Ă͕��ցE���ʂ̓�i���u����u���ꂽ�B���̎ߑ����ł͂Ȃ��ď@�c��e����{���Ƃ��邱�Ƃ́A�����炭�{���͂���قǂ̋����I�ȓ��e�������̂ł͂Ȃ��A�f�p�ȑc�t�M��������x�̕������߂Ă����ł��낤���A�@�c����s��F�̍Ēa�Ƌ����ӎ����邱�Ƃ͂�͂肻�̌�̌܈ꑊ��i�����t�Ƒ��̌ܘV�m�Ƃ̑���j��{瑂̈�v�E����ȂǂɂȂ����Ă������ł��낤���Ƃ́A�z������ɂ��₷���B
�@�܂��A�@�c�����̙�䶗��{���ɂ��Ă��A�{���͏@�c���u�ϐS�{�����v�̖{��v�z�̏�ɖ��@�����̖{���Ƃ��Đ}�����ꂽ���̂Ƃ����F���ɂ����ẮA���嗬�ł�����̊i���͂Ȃ����ł��낤���A�������@����q�Ƃ�������ŏ��ʂ���i�ɂȂ�Ə͈�ς���B�����܂ł��Ȃ��A�����嗬�ł͕K���u���@�䔻�v�ƋL���āA��䶗��{���̎�̂��u�얳���@�@�،o�@���@�v�ł��邱�Ƃ��m�F����B��������@���l���O�̈�l�Ƃ��ċL�����A�얳���@�@�،o�̎��̉��ɂ݂͂�����̖����L������̉��V�Ɣ�r�����ꍇ�A��䶗��{���S�̂���@���l���̂��̂Ɣq������@�{���`�ւƓW�Ԃ�����̂ƁA�e�Ղɐ������邱�Ƃ��ł���B
�@���̂悤�ɍl���Ă݂�ƁA�@�c�̓��Œ���ɒ�ߒu���ꂽ�@�c��e�{���`���i���u�`�Ȃǂ̂���������嗬�`���̉��V�ƁA����ɂ�������h�������܈ꑊ�����@�E�����̎t��`�Ȃǂ̍l�����A���̘_���I�ȗ��t���Ƃ���������S�����̂Ƃ��Ă̖{�����v�z�́A���̌�̌`���ɂƂĔ��ɑ傫�Ȑ��i�v�f�ƂȂ����ƍl������̂ł���B�����āA���̂悤�Ȋ�őc�Ō�̏������������ꍇ�A���̂Ƃ��뎟�̎O�_�قǂ��w�E�����B
�@�@�́A�@��[�����t���������N�i1334�j����7���ɑ�Ύ��ōs�Ȃ�ꂽ����t�Ɠ���t�̕��֕i�Ǖs�̖ⓚ���L�^�����u���֕i�Ǖs�V�ⓚ�L�^�v�̒��ɂ́A���̂悤�ɋL����Ă���B
����ăq��t�e�]�N�A�@�N���n�����`���҉��e瑖嘦���֕i�j�L��������B����ăq���փe�]�N�A�A�C�e��瑖嘦���֕i�j�d�X���j���v�V�L�����L���^�D�j���O�`�A�^�g�n�ҎO���������e瑖吳�@���i�����j�փ����L���A���e�ܕi���ʘ����j�_�X�����B���������E����A�V��]�N�A�����C�e瑖�V�������V�N�����������j���`���������v���]�]�A���y�]�N�A����J�P��V�e�]�����n���ʖ�j���`���ꋕ�]�]�A�J�ڏ���]�N�A瑖���֕i�ɂ͈�O�O��E���앧����L�ě��O��혦����E������Ɣ폑�J�A����^���ӂƉ]�t��A嫃��R���g���j��瑌��{�Z���m��O�O�烂�s���n���A���앧���s��}���A�@�P�@�N�����������A���V�������g�̏�ɕ��J�t��Ɏ�����Ɖ]�]�A���y�]�N�A�{�匰�n���탌�n���`����j���i���A�̃j�m�V�k�A瑘����n���e�{�j�P���i����A�@�L�����䏑�{�����߁A�����D���Ӄg�]�t��A�J�ڏ��j�]�N�A���O瑖�̏\�E�̈��ʂ�Ŕj���Ė{��\�E�̈��ʂ���L���n���]�]�A�@�V�����탋���J�A�����j���ӂƉ]�t��A�^���ӂ̕��A�ꉝ���e����j嫃����X�g���v���A�D�j�o�ӂ̕��A�ĉ����e����j���V���v�A�^�������v�n�Ҍ������ʕi������m�����j��B�]����t�����@��s�V�e�����Z�������j���X�����^�f����B
�@�����ł́u�@�،o�v瑖�̕��֕i�̓��v�̗L���ɂ��Ă̓���t�̎���ɑ��A����t���^�E�D�E�j�̎O�`�������A�^�̈ӂł͕��֕i�̕���Ɉꉝ�̓��v�𖾂������A�D����єj�̗��ӂł͍ĉ��E����ɓ��v�͂Ȃ��Ɠ�������ɁA�u�^�������v�n�Ҍ������ʕi�����꘦�����j��v�ƋL����Ă���B���̈ꕶ��f���ɓǂތ���́A�{�����ɐ^���̓��v������|����������Ă��邪�A����ȊO�̐������Ȃ��A�܂����֕i�̓��v���炢���Ȃ���ʕi�̕���ɂ܂Řb�����ł��邽�߂ɁA���̎��͂��܂߂��ڂ����͕s���ł���B�܂��A�{�����ɂ͌Îʖ{�����������A�����I�ɂ������̖�肪�w�E����Ă���̂ŁA���̈ӌ������t�̂��̂Ɗm�肷�邱�Ƃ͍��̂Ƃ������悤�ł���B
�@���ɇA�Ƃ��Ē��ӂ��ׂ��́A�5�N�i1342�j3��14���ɎO�ʓ����t���쐬�����u�����v�Ɍ����镶���ł���B�{���͓����t�̎t���E�����t�̎O�\�O����̖@��ɍۂ��A�m���剺���ꖡ���S�̋F��̘A���������ɂ������ē����t�����������̂ł��邪�A�����Ɍ�����_���i�_���̊�������ю�b�����j�ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���B
���n�˃e�e�a�L���V��j�ȃe���V���j�A���n�����e�x�����M�V�Ѓ��j���@�������烒�A��n�N�V�e�Ϗ�R�V�����m�e���g�s�����A��n���L���������V�P���m�e�s�����Z�҃n�A�փ����Ō����S�O�\�]�N�V�Ԉ�腕���V�����\�L�����䶗����ݘ��߉ށE����E�\���O�������E��s�E���Ӎs�E�����E���ꓙ�����F?���A�g�q�E�ژA���������A���E��E���E���E�l�V�E�������A�����E�Ԑ_���A�V�ƁE�������A�����V�l�ˁA�����E�V�e�E�V��E�`�����A�ʃV�e���{�����̔V���@���l���䔱���A�����j�n���q��g�����g���s���������l���}���A�����j�n�`���ԃj���j��P���m���Y��
�@�����ɂ́A�ŏ��ə�䶗��{���̗�O�����X�ɋ������A���̌�Ɂu�ʃV�e���{�����̔V���@���l�v�Ƃ����āA��䶗��{�������̂܂܂œ��@���l�Ɣq����ӂ�������Ă���B
�@�Ō�̇B�́A�O�ɂ������G�ꂽ��Ύ��ɏ��������u���v�̓��w�ʖ{�ł���B�u���v�̖����ɂ͖��@�O�ʂ̗v�@�Ƃ��Ė{��̎O���@��������Ă��邪�A���̑��ł���{��̖{���ɂ��Č��s�䏑�ł�
��͓��{�T����腕���ꓯ�ɖ{��̋���ߑ���{���Ƃ��ׂ��B�����̓��̎߉ޑ���A�O�̏����A���ɏ�s���̎l��F�e�m�ƂȂ�ׂ��B
�ƕ\�L���ꂢ��B����ɑ��āA���w�ʖ{�ɂ�
��͓��{�T����腕���ꓯ�ɖ{��̋���ߑ���{���Ƃ��ׂ��B�����̒��̎߉ޑ���A�O�̏����A���ɏ�s���̘e�m�ƂȂ�ׂ��B
�Ƃ���悤�ŁA�u��s���̎l��F�e�m�ƂȂ�ׂ��v�́u�l��F�v�������āu��s���̘e�m�ƂȂ�ׂ��v�ƕ\�L����A���̌��ʕ��ӂ����]���āA�ߑ��⑽���̏�������s��F���̘e�m�ƂȂ�Ƃ����Ӗ��̕��͂ƂȂ��Ă���B�m���ɂ��ꂾ��������Ώ�s�{���E��s�{���̈ӂ�ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł��邩�A�E�������ĕ�����悤�ɁA���̒��O�ɂ́u��͓��{�T����腕���ꓯ�ɖ{��̋���ߑ���{���Ƃ��ׂ��v�Ɩ�������Ă���̂ŁA�S�̂Ƃ��Ă͔��ɖ����������͂ƂȂ��e���܂��Ă���B�����A���̎ʖ{�̑��݂Ɋ�Â��č��������t�́u�݈唺�̖@��v�Ȃǂ��ł��������Ă���\�������ɍ����A���̑��݂����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B
�@�@�@10�A�c�і[�����t�Ƃ̌���
�@�ŏ��ɓ����t�̗��`���Љ�Ă����ƁA�t�͖@�؏@�i�{�嗬�j�{�啧���@�E�{��@�؏@���̔��i�嗬�n�̑c�ŁA����2�N�i1385�j�ɉz���x�R�ː��S��䋽�ɁA����E�n�����V�̎q�Ƃ��Ēa�������B���i9�N2�i1402�j���{���i�������j�̒ʌ����ǂɎt�����A�f���Ɠ`����������E�����̊w���ɓ���A�c�і[�i�j�і[�j�����i�i��5�N�ɓ����Ɖ��́j�Ə̂����B���i12�N�ɓ��������₵�ċ�o���������Ƃ��p�������A���V�E���@�̗��ꂪ�r�������A�����E�������t�Ƌ��ɍĎO�Ђ߂���e���ꂸ�ɖ��{����ޏo�����B���̌�A�b�R��O�䓙�̏��n�ɗV�w���A�܂��z��E�{�������w���̏���̐w��K�˂ċ��w���r���邱��10���N�ɂ���сA����ɗL�͂ȊO��҂����ċ��s�E�{�����i��̖{�\���j����E�{�������̏����@���J�n�����B�i�����N�i1429�j�ɂ͖{瑏���E�{�唪�i��s���`�̗v�`��葖������u�@�ؓV�䗼�@�����i�l�����j�v�𗌒����R�ɉ��B���A�Ɨ���錾�����Ɠ`������B���̌�͋��s�Ɠ������҂��Ȃ��狳�c�̊�b���ł߁A���˓������ɓ`�����đ傫�Ȑ��ʂ����߂č�E���{���Ȃǂ̏�����n�������B���̊ԁA�z���̍��ԂɁu�䏑���i�W�v�u�\�O�ⓚ���v�u���`�����������v�v�u���V���v�����āA�w�k�̋���Ɏ������B63������͕z�����Ƃǂ߂ďq��ɐ�O���A73���ɂ����āu�{��O�����v�u�J瑌��{�@�v�W�v�u�O�啔����Ӂv���̑啔�̋��w���������������B����3�N�i1454�j70�̎��ɖ{�������Ɋ��w�@��n�݂��Ė剺����ɐ��ʂ��グ�A���̊w���́u���嗬�v�ƒʏ̂��ꂽ�B����4�N�i1463�j5��13���A�t�͖{�\���@�x7�ӏ����߂Ė{�\�E�{���̗����ꎛ��ʒB���A��5�N�i1464�j2��25����80�ŋA�₵���B
�@�����t�̋��w�͔��i���w�ƒʏ̂����悤�ɁA�u�@�،o�v��\���i�̂����A�{��̏]�n�O�o�i���瑮�ݕi�Ɏ��锪�i���d�����A���ɐ_�͕i�ɐ�������s���̎l��F�ւ̌��v�t���`�𒆐S�ɒu���āA�ݐ��E�v�̈�i��薖�@����̑�ڂ�I�ю���Ă���B�܂��A�{�����̏�s��F���敧�E�ߑ��̖{�ʂ̖@�����킷��Ƃ����{���������W�Ԃ��A�{�������{�傪�s����瑖�ɏ����Ƃ����{瑏�����咣���Ă���B���̊w���͍L�w������r���Č䏑���S��`���Ƃ�A�܂��������s�̒��Ó��{�V��̊ϐS�Ώd��`�������Č����ȋ�����`�ɗ����̂ƕ]����Ă���B�܂��A�����̕������t�̂����A���q�̋K�͂�̌n�̐���������@�w�̖��ɒl����͓̂����t�݂̂Ƃ��������]�����Ȃ���Ă���B
�@���āA���̂悤�ȓ����t�Ɣ��ɐ[�����������Ă���̂��A�ۓc���{����{���Ƃ�������嗬�ł���B
���̖��{�����\����w���ł������t�́u寎ֈٌ����v�̊���ɂ�
������寎ֈٌ������䘦��Ӄi���B�������������B�����n���Ƙ��w�Җ�B�R���ԏ����V���B嫎����g�ޘ��\�������@���ƉӖ�B����n�������@�叕�������A�W��寘����܃��֘��ٌ��V�^���J�@�V�B�̃j�]�������B�E�E�E�����s�������`�钆���[���B���X�����L�ғ������V�B�������n��́A�������q��B����䏑���V�B���`�����n�����A���n�����B
�ƋL����Ă���B�����Ɍ���������t�i�`1472�j�͓����̋�B���������c���ɑ��݂������{���̖����E���~���̏Z�m�ŁA��͂Ƃ����������ʼnb�R��֓��V��ɗV�w���A�K��������������������Ő������̒�q�ɓ`�������Ɠ`������B�E���ł͂��̓����t�́u�������q��v�ƋL����A�c�і[�����t�̒�q�ł��������Ƃ��m����B�����̊����Ɍ�����
�{�]�A�N�������s���߁X�����v�X����B��������厖�q�L����A�������V����V�e�H�A���X�����B����l��N������嫈׃j�u�V�l�s���`�E�]�����m��`��
�Ƃ������͂��̓����t���g�̌��t�ƍl�����邪�A����ɂ��Ǝt�͕N���i1449�`52�j�ɋ��s�œ�藬�̌������q�L���A����ɓ����t��������āu���X�����c�c�v���̕�����Y�����Ƃ����B�����A�������N�i1444�j12��12���ɓ����t����u�����u�{�\�����X�@�x�{�������N���N�����V���v�ɂ�27���̒�q�������E�������Ă��邪�A���̒��Ɍ�����u��͉ԉ��v�͂����炭�����t�̂��̂ƍl������̂ŁA���̕���������ɂ����ē����t�͓����t�ɐ������āA���̋��w�̐ێ�ɓw�߂����̂Ƒz�肳���B�������̓����t��60��̔N����}���Ȃ���A�L���̑��ł���u�{��O�����v�̎��M���ɂ���A����Ӗ��ł͍ł��v�z�I�ɉ~�n���Ă����������Ɛ��������B��N�A�v�@�����C�t�́u���d�L�v�̒���
�R���j�������m������k�n�����m�냊���s�V�e�m���@���m�S�l�\�n�ʃm�䏴���m���j�����e�꒟�������܊�Z�����n����m�ʖځA����m�p�J��B
�Ɠ����嗬��ᔻ���Ă��邪�A���̓����t�����肪�w�E�����u�������m������k�v���̐l�ɊY�����邩�Ǝv����B
�@�������A���̂悤�Ȓ��ړ����t�̖�ɓ����Ă��̋��w���w�ю��Ƃ��������t�̐ϋɓI�Ȋ����́A�����t�l�̔��f�łȂ��ꂽ�c�ׂƂ������́A�����炭�{���ł���ۓc���{���̈ӌ������Ȃ�Ă̂��̂ł��������Ƒz�肳���B����́A���{����X��E�����t�����\�O�N�i1459�j4���ɓ��ɂ����ē����t�́@�u���`�����������v�v���݂����珑�ʂ��Ă��邱�Ƃ�A�O�q�����悤�ɁA��������v�t�������X�N�i1500�j�ɓ������ɉ��������ۂɒk�`���A����ȑO�̊���4�N�i1463�j9���ɂ͏���E�v�����œ����t�́u�@�ؓV�䗼�@���i�l�����j�v�����ʂ��Ă��鎖���Ȃǂ��炵�āA���̉\���͏\���ɍ����ƍl������B
�@�Ō�ɁA���̓����t�̖{�����v�z�����X�����Ă݂悤�Ǝv�����A���͎�X�̐���A�O�ɖ{�����v�z���`������Ă����ۂ̓�̓��Ƃ��Ď������{��������Ɩ{��������s��F�̋`�A�����ē��L�t����v�t�̔ᔻ�̒��Ɍ�������E��v�̈ӂɂ��ď������Ēu�������B
�@�܂��A�{��������ɂ��Ắu�\�O�ⓚ���v���ݐ����펖�̒��ɁA���̂悤�ɐ�����Ă���B
���j���e��s������j�j���{���{�ʖ�ۃ����A�o�����ߑ����Ӕ��r�j�B�o���j�n�䉗������遛�ߏ������S�]�X�A��s���{�ʉ���V���A�o��������]�X�B嫑R���g������{�����߃n�n�O����j���g�{���{�ʃj���W�ʃw���B�`�]�A�v������ߋ����n�g�ߐ����גE�A�n�O������B�L��e�V�B�{���ʃj��V�ʌ�j�߃N�n�V�K�ߐ��j�E�X�A�w�X�g�n�O���Җm���W�ʃw���B�����V�䖭�y�����߁A�n�O������j���g�{���{�ʃj���W�ʃw���B�����o�ߑ���j���^���g�]�w�h���A�o���n���N嫐��g�ʃm��Ӄ��߃n��e�Ӄ��߃e���j���ʃj���X���b�B���F���y���ߖ��N�^�q���ʃj����m���X���Җ�B�E�E�E�R���j���t�������V��w�ғ��n��������n�����{�ʃj������X����B������r�����n����V�^����B����m�҈��ʘ���F�E�j�V�e�����V�A�����팋�����O�����n�E�������j���ɉʃm�n�����߃����������Z���ʃ���B������A����g�Ґl�V���@����j�_�X���V�Җ�B�ɉʐ����m�����n�O���B�߃j�O�捪�������o���]�s�g�\�����j�]�w���B�{�ʐ��������n��e�n�O�̋�O��L�e�V���X�ɉʃ��B���J�L���l�V���혦�@���B�̃j�m�k�A����n�������ʃj�b�]�X�B���y���{���ʎ혦�߃n�痿�ȃX�]�X�B���j���@���Ӄn�Ȗ{��n�i��s�v�t���ߖ{���m�@�|�m�A���m�n�i���Ӄn�Ȗ{�ʃ��ۃj�{���j�{�����ݘ����ʕs�@�@�،o���ȃe�t�V��s�j�A�ȏ�s�{���O�k���E�m��؏O�����j���@���l�j���j�ŏ����탒�������N��B�E�E�E�@�����O�k�L�����ߑ��n��؏O���ŏ����혦���n���e�{�ʃ��ڃ��{���j����s��F�m�A�O�k�m��؏O���j�n�e�����탒�B�����E�����n���e�{�����A�Z���{�ʃj���e�v�����ߑ��m�O���j���X�E�v���B�̃j�m�k�A���ʎߑ���s�n�����̓��̈�g�j�V�e�A����F�E��C��ؖ��n���I�A�@���햞�팰���n���I���m�]�w���`��B
�@�t�́A�u�@�،o�v�̌o���ɂ͏�s���̖{����F�ɑ���ߑ��̖{�ʉ��킵��������Ă��Ȃ����A�O�Ɏ����@�c�╶�̒��ɂ�����{�����v�z�`���̗v�f�̇B�Ƃ��āu���@�،o�v�̒�����E���グ���u����L�v����́u�{���ʃj��V�v�̕��Ɉ˂�A�V��E���y�͉��킪�{���E�{�ʂɘj��Ǝ߂��Ă��邪�A�����̓V��w�ғ��͉���͖{�ʂɌ���ƌ�����咣�����Ă���Ƃ����B�������A����̖{�`�͈��ʂ̕�F�E�ɂĂȂ����̂ł���A�܂�����͐l�V�ɑ��Ę_������̂ł���̂ɁA�{�ʂ̏O���͎O�悾���Ől�V�̋@�����Ȃ��̂ʼn���̋`�����������A����䂦�v������͖{�����Ɍ���ƌ��_����Ă���B�����āA�Ō�ɓ��@�̈ӂƂ��Ă͖{�ʂ�{���ɐۂ��A�{�����̏�s��F���{������і��@�̏O���ɍŏ�������Ȃ����A���E�̎��͏�s���{������{�ʂɈڂ��ċv���̎ߑ��ƂȂ�E�v���Ȃ��A�Ɛ�������Ă���B���̖����Ɍ�����u���ʎߑ���s�n�����̓��̈�g�v�Ƃ����\���́A��q�����E��v�̋`������E���g�ɖ����̂ł���B
�@���ɖ{��������s��F�̋`�ɂ��Ắu�ܒ����v���́w��@�{��\�����x�̒��ɁA���̂悤�ɖⓚ����Ă���B
�q�]�A�䏴�����j�ȏ�s��F���ז{�����m���L���V�A�������@���B���A�ϐS�{�����j��V�V��B�{�嘦�Ӄn���ʖ{�L�j�V�e�ߑ��n�O�n���̘��t��j�V�e��g���ʖ�B�߃j����F�E��C��ؖ��n���I�A�@���햞�팰���n���I�ȏ�B����F�E�g�Җ{�L�n�O��B�g�Җ{�ʎߑ���B���t�퓯�̏�P�j�V�e���n���I��g�]�t���n�{������F�E���n�O��m���^���B
�@�����ɂ͖{��������s��F��������Ă���̂́u�ϐS�{�����v�ł���Ɩ�������Ă���B����ȏ�̋�͎w�肳��Ă��Ȃ����A�����炭��͂�O�Ɏ����@�c�╶�̒��ɂ�����{�����v�z�`���̗v�f�̇A�Ƃ��Ď��グ��
�o�j�]�N�A��{�s��F�������������P��ᶁA���{�㐔���]�X�B�䓙�J�ȐS����F����B�n�O��E����F�n�ȐS���ߑ����ő���B�E�E�E��s�E���Ӎs�E��s�E�����s���n�䓙�J�ȐS����F��B
�̒i���w�������̂Ǝv����B���̖{��������s��F�̋`�ɂ��ẮA�����炭�V��E���y���̎ߋ`����͏��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA���Ȃ�̓�₩�Ǝv���邪�A�����t�̒���̈ꕔ�����������ł͂���قǏؖ��̘J������Ă��炸�A�����ӊO�̊�������B
�@�Ō�Ɏ�E��v�̋`���Љ�Ă����ƁA��̓��v�t�̔ᔻ�̒��Ɂu�ϐS�{�����v�̈ꕶ�ɑ���ǂݕ��̖�肪�w�E����Ă������A����Ɋւ��Ắu���`�����������j�v��
���N��藬���䏴�{�����`���n��㖢����L�����`��]�X�B���e�ϐS�{�����j��i�g�^�����i�Ӄ��߃X�����A�ݐ��{��^���@�V���ꓯ���~��]�X�B�����Ӄn�ݐ����{���i�n��C�j�كj�V�e���O瑖嘦�~���������������j�A�����������g�^�v���ߑ������������ʃC�e������������q�����p�e�A�E�v�����X���v������q�����E�g�^��E�{���{�ʌ�V�O�疭�@�@�،o�����e���i���t�V��s�j�A�����胁�e���@�m�̃j�ݐ����@����E���كn�L���g���A�@�����@�̃n���L�V�̃j�ꓯ�j���~��g�n�߃V�^�}�t��B�����`�i�����n�A�ޘ��E�n������g���_���L���X��B�y�V�e�V�j�������A�ރm��i�n�����A��ژ�����g�L�ǖ�]�X�B�@�N�������X�����_���A���ރn���n�g�ǃ��������ӓ��V�V�B�����_�n�퍷�ʘ��`�����V�A�ރn�����V�_�n�퓯���`�����X��B���F��i�g�^�n�i�ꖭ�V�㘦��E�A�ݐ��Ō��B�̃j��@����`�m�L���Ӗ�B
�ƋL�q����Ă���B����́u�ϐS�{�����v��
�ݐ����{��m���@�V���n�ꓯ�j���~��B�A�V�ރn�E�A���n���B�ރn��i�A���n�A�[��ژ�����B
�Ƃ��������A�����t�́u�ޘ��E�n������v�u�ރm��i�n�����A�^��ژ����v�Ɠǂނׂ��Ǝ咣���A���̌��ʂƂ��Ď�E�͈�@�̓�`�ł���A�ݐ��E�Ō�Ƃ��������ɖ����̂Ɛ�����Ă���B����͓����t�̗��Ă��E�͂����܂ł��u�@�،o�v�{��̋������ŗ��ĕ�����ꂽ��ƒE�ł����āA�E�q�̂悤�ɁA�v���Ɩ��@�ɂ͏�s�E���@�Ƃ��ĉ�����{���A�ݐ��̖{��ɂ͎ߑ��ƌ����ē����@�������ĒE�v��^����Ɛ��������B����ɑ��āA�����嗬�ł͎�E�̖@�̂̈Ⴂ���咣���A�폟�E��Ƃ��ĉ���v�̏�s�E���@��I�ю���Ă������Ƃ͑O�q�̂Ƃ���ł���B
�@����܂ŁA�����嗬�ɂ����Ė{�����v�z����ю�E�{瑘_���ǂ̂悤�Ɍ`������Ă��������A�Ƃ��������l�@���邽�߂̑O��̍ޗ��̈ӂƂ��āA�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗�������ѓ��L�E�����E���v�̎O�t�̖{�����v�z�̂���܂��ƁA�@�c�ӔN�̋��w�̌n�̎��ۂƂ̊W��@�c����іŌ���ł̎v�z�`���̗v�f�A����Ɍc�і[�����t����т��̖{�����v�z�Ƃ̌��̈�[���Љ�Ă����B
�@���̒��Ŏ���������ەt����ꂽ�̂́A���w�ɑ��ĉ��V�������Ă���K���͂̋����ł���B�܂�A�ɒ[�ɂ����Ɓu�ŏ��ɉ��V���肫�v�ŁA���w�͂��̌ォ��t���Ă���Ƃ�����ۂł���B�Ⴆ�A�������N�i1334�j����7���ɑ�Ύ��œ���E���㗼�t�����S�ƂȂ��ĕ��֕i�Ǖs�ǂ̘_����������ꂽ���A����Ȃǂ������炭�h�c�E�����t�ɂ����ցE���ʂ̓�i���u�Ƃ������V�̑�O����A���̋��w�I�Ȑ�������̂ǂ̂悤�ɂ��邩�Ƃ�����肪���Ȃ�̃E�G�[�g���߂Ă����ƍl������B���_���ɂ͓����҂ł������E����̗��t�̊O�ɑ�Ύ������t�E�d�{�����t�E��s�@�����t�Ȃǂ����ڂ���ъԐړI�Ɋ֗^���Ă��邪�A����قǂɋ��w�I�Ȓ茩�̈�v�����Ă��Ȃ������؋��ł���Ƃ�������B�����ɓ��_���̒��ŕ\�����ꂽ�A�^���̓��v�͎��ʕi����̖{�����ɂ���Ƃ�������t�̈ӌ��Ɍ��y�������A�ꕔ�ɂ�瑖哾�v�𗧂Ă����Ƃ���u�{瑈�v�̖����v�ƕ]���ꂽ����t�������{���ɖ{�������v���咣���Ă����ƂȂ�A���V�Ƌ��w�̘�������ɓ����I�Ɏ������ۂƌ����邩���m��Ȃ��B����ǂ��A����͕��ցE���ʂ̓�i���u�Ƃ������V�̏h���̂�Ȃ��̂ł���A�㐢�ɂ����Ă����v�t�����̖{�����v�z�Ɋ�Â��Ď��ʕi�s���u�Ɍ����y��ł��邱�Ƃ́A���Ɍ����Ƃ���ł���B
�@���āA�{��̖{�����v�z�`���ߒ��̖��ł��邪�A������̕��͂�͂�c�і[�����t�Ƃ̊֘A����ԑ傫�ȃE�G�[�g���߂Ă���悤�Ɏv���B�u�{�������v�Ɓu�S�Z�ӏ��v�̊W���q�ׂ����ŐG�ꂽ�悤�ɁA���̗������̂������t�̋`���Đ������Ă���\��������̂ŁA�����̏����ɑS�ʓI�Ɉˋ����Ă��鍶�������t���܂߂āA���ׂē����t�̑��݂�O���ɒu���čl�������K�v������Ǝv����B
�@�����t�̗��`�������ɏЉ�����A�����t�̉��@�E���V�̗��ʂɂ킽�鋳�`���m�������͉̂��i30�N�i1423�j���ł������Ɛ�������Ă���B�Ƃ���A���̍��ɋ��s����т��̎��ӂŐ������Ęb��ɂȂ�����������t�̖{�����v�z�̉e����15���I�����Ɂu�{�������v�����āu�S�Z�ӏ��v���o���ォ��A�����Ύ����L�t�������t�̋��w�Ɏ�������ĕs�����E�s���u�̉��V���������{�����v�z���\�z�����B���������t�͑����{���E�S�Z�ӂ̗������d�Ȃ�����A���L�t�̉��V�Ƌ��w�̐�����������ĕx�m�ɕ����A�����t�̋��w�̐ێ�ɔM�S�ł����������嗬�̓��v�t�́A����ɖ{�����E�S�Z�ӂ̗����Ɠ��L�t�̖{�����v�z�������킹�āA���̎v�z�I���n���ɓ���������B���̂Ƃ���A�ȏ�̂悤�ȓW�]�����͎����ł���B
�@�{�e�́A�@�c�Ƃ��̖Ō�200�N�قǂ̒����ɂ����āA�����嗬�̖{�����v�z���ǂ̂悤�ȗ���Ō`������Ă��������A���̂����悻�̊T�ς�������Ƃ���ɋ}�ŁA���L�t�ȑO�̋��w�A���Ƃ��ΎO�ʓ����t�̏����Ȃǂɑ���ׂ�������A�������̒��ÓV�䋳�w�ɑ��錾�y���ł��Ȃ������B�܂��A�c�і[�����t�̋`�ɂ��Ă��A�����{�����v�z�̈ꕔ�ɐG���Ɏ~�܂��āA���̋��w�̌n�S�̂̒��ł̈ʒu�t�����͂Ȃ�����ɂȂ��e���܂��B�����ׂ̍�����Ɠ��Ɋւ��Ă͑��e�ɏ��肽���B
�@
�@
�@
�@
�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i2�j
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�ڎ�
��1�́@�嗬���ɂ����鋳�w�I�t���ɂ���
�P�A�����u�{��O�ʎ��v�u�O���O�o����v�u���a��Ԏ��v�u�\��v
�Q�A�u�ܐl���j���v�u�x�m��Ֆ�k���m���v
�R�A���ځE����E�����E�����E�����E�����E�����E���s�u�\��v�A�����u��`�y��v
�T�A�����u�����l�X��v�E����u�ɑ���苗���Ԏ��v
�U�A�����u�\���v�u�p�S���v�u�������ŗ������v�u�����i�\�����j�v�u�S�ꏴ�v�u���ח������v�u�����G�W�v
�V�A�����u�������v�E����u���t���^�v�u���咼���䓖�ԓ��L�v
�@�{�ʖ��ߑ��̖{��������s��F�ł��邱��
�A��s��F����؏O���ɉ��킷�邱��
�B�v�����킪�{�����̉���ł��邱��
�@
�@
�@
�@
�@���͓����O���Ɂu�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i1�j�v�Ƒ肵�āA�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗�������������ѓ��L�E�����E���v�̎O�t�̖{�����v�z�̊T���ƁA�@�c�ӔN�ɂ����������w�̌n�̎��ۂƂ̊W�A�܂��@�c�Ƒc�Ō���ł̎v�z�`���̗v�f��c�і[�����t�̖{�����v�z�Ƃ̌��̈�[�ȂǂɐG��āA�����嗬�ɂ����Ė{�����v�z����ю�E�{瑘_���ǂ̂悤�Ɍ`������Ă������A�Ƃ������l�@�̂��߂̍ޗ������݂��B
�@���̌��ʂƂ��āA���i30�N�i1423�j���ɐ����������������t�̖{�����v�z�̉e�����āA15���I�����ɋ��s���ӂŁu�{�������v�u�S�Z�ӏ��v���쐻����A�����Ύ����L�t�������t�̋��w�ɂ��Ȃ������`�ŕs�����E�s���u�̓`�����V����t������{�����v�z���\�z�������ƁA���������t���{���E�S�Z�ӂ̗������w�т��m���L�t�̉��V�Ƌ��w�̐������ɋA�����ĕx�m�ւƕ����A�����t�̖{�����v�z��ϋɓI�ɐێ悵�������嗬�̓��v�t�͗����������Ɠ��L�t�̋��w�����킹�w��ŁA�����嗬�̖{�����v�z���g�Ō`���������Ɠ��̓W�]��掦�����B
�@�{�e�ł́A�E�̓W�]��������ӂ��܂߂��ޗ��Ƃ��āA�@�c�Ōォ��I��1400�N���ɂ����Ă̓����嗬���ɂ����āA�@�c�̋��w�̌n�ɂǂ̂悤�ȕt����Ƃ��s��ꂽ���������Ė{�����v�z�`���ւ̓�����T��Ƌ��ɁA�O�e�Ŕ��ɒ��r���[�Ȍ`�ł����G����Ȃ����������t�̖{�����v�z�ɂ��āA���̋��w�S�̂ɂ�����ʒu�Â����Ƃ��킹�čĘ_���Ă݂����Ǝv���B
�@���͂ł͏@�c���ňȌ�A���m�Ȍ`�Ŗ{�����v�z�������͂��߂���L�E�����E���v���̏��t�Ɏ���܂ł̏��ɂ������Ȓ���i�����̏�����܂ށj����肠���A�����ɂ���������{瑊ς�{���ρA�@�c�̈ʒu�Â���t��q�̋`�A�����ĕ��֕i�Ǖs�̖���{�厛����ѕx�m�R�̋����Ȃǂ̋`��E�o���Ă݂����Ǝv���B���̌��ʁA�����嗬���ł͏@�c�̋��`�̌n�ɂǂ̂悤�ȋ��`�I�ȕt����Ƃ��s���A�����̕t�����ꂽ���`���ʂ����Ă��̌�̖{�����v�z�Ƃ����Ȃ�W�ɂ���̂��A�������l���Ă݂����B
�@�@�@�P�A�����u�{��O�ʎ��v�u�O���O�o����v�u���a��Ԏ��v�u�\��v
�@�ŏ��ɓ����嗬�̔h�c�E�����t�̏��т���肠���Ă݂�ƁA�����ōł����m�Ȍ`�Ŏ咣����Ă���̂́A�V��E�`���̑��@���O�̖@��瑖�ɑ��āA��s��F�̍Ēa�E���@�����@�ɏo�����Ė@�ؖ{����O�ʂ���Ƃ����V��Ɠ��@�̖{瑈�ڂ̗��ĕ����ł���B����͏@�c���u�J�ڏ��v��u�ϐS�{�����v���Ŗ��������u�@�،o�v�{��ɑ�����߂�Ƃ����`��A�Ō㖖�@�ɒn�O�̕�F���o�����Ė��@�@�،o�̌����O�邷��Ƃ����f�ĂɁA��s��F�����@�Ƃ�����`�m�����č\���������̂ł��邪�A�u�{��O�ʎ��v��u�O���O�o����v�ł͂���ɔ�b�R��瑖厛�ɑ���x�m�R�̖{�厛�Ƃ������ĕ�����������A�u�\��v���{�ɂ͎��O瑖�̏��@��Ύ����Ė@�ؖ{��̐��@�𗧂Ă邱�Ƃɂ��A���y�̈�������������Ƃ����F�����q�ׂ��Ă���B�������A��n�E�̎O�v�ɏ������V��̑��@�n�v�ɑ�����@�̖��@����v�Ƃ����Δ�͌������A�܂��ߑ�����т��̒E�v�`�ɂ��Ă̌��y�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���ɁA�ڋ��t������2�N�i1287�j�t�̐g�����R�Ɏ���o�܂��L�����u���a��Ԏ��v�ɂ́A���R�̎������g�؈���~�t��掖@�O�ӏ���������Ă��邪�A���̓��̎ߑ���̕��̑����ɂ��āA���ꂪ��s���̘e�m���Ȃ����߂Ɏn�����o�̎ߑ��ƂȂ�A�v�������̎ߑ������ꂽ�@�c�̖{�ӂɔ����邱�ƁA�����ď������������ċv���ߑ��̖ؑ�������܂ł́A�@�c�}���̏\�E��䶗���{���ƈ��u���ׂ����Ƃ��L����Ă���B����́u�@�،o�v�{��̐����ɏ����āA�v���̎ߑ��i�`�ԂƂ��Ă͈ꑸ�l�m���j�@�̖{���ƒ�߁A����Ə\�E��䶗��{���Ƃ̊W�W���q�ׂ����̂ł��邪�A������ɂ͂܂�
���S�̌��������͂��Č�e�̌��O�ɐi�点�������ւƐ\��B
������e�̍����̌�Ɨ��@���B
�Ƃ�����悤�ɁA�����t����ǂ��Ă����g���v�����̓����ɂ͏@�c��e�������u����Ă���A����͂��̌��Ύ����o�ďd�{�{�厛�ɈڏZ���������t�̏�����Ɍ�����u���l��e�̌��O�v���Ƃ����\���ւƎp����Ă���B
�@�܂��A���́u���a��Ԏ��v�ł͖��������t���͂��߂Ƃ���ܘV�m�����́u���q���N�t�G������ʁv�ƒf�����A���̌��ʁu������l�{�t�̐��`�𑶂��Ė{�����ւ��m�ɑ����Ċo��v�Ƃ����A�@�c���@�̐��`�������l���p������Ƃ����������ӎ����L����Ă���B����͖{���A���`�Ƃ������͊�@�I�ŏ������ꂽ�`�����ƂĂ������ׂ����̂ł��������A���̌㎟��ɑ傫���N���[�Y�A�b�v����āA���@�E�����̎t��q�̋`�Ƃ����`�ŋ�������A�����嗬�̌`���ƓW�J�̉A�̌����͂ƂȂ��Ă������B
�@�@�Q�A�u�ܐl���j���v�u�x�m��Ֆ�k���m���v
�@�u�ܐl���j���v�́A�����嗬�̓������猻�݂Ɏ���܂ŁA������Ӗ��ōł��嗬�̍������������`���Ƃ��ďd�v������Ă������̂ł��邪�A���͓����t�̈ӌ����ĎO�ʓ����t����q�������Ƃ����F���̉��Ɏ�肠���A���킹�Đ����o�܂͕s���Ȃ�����e�I�ȗގ��������u�x�m��Ֆ�k���m���v���������Ă݂����B
�@�u�ܐl���j���v�́u�Z�l���`���āv�Ƃ��Ă�A���̖��̂���@������悤�ɁA�@�c��u�̘Z�V�m�̓��A�����E���N�E�����E�����E�����̌t�̗��`������t�̐��`����j�܂���Ƃ����`���Ƃ��Ă���B�܂��A�t�����ꂼ��́u�\��v�Łu�V�䍹��v�Ǝ��ȋK�肵�A�@�c�ɑ��Ă��u�V��̗]�����ނށv�Ƃ����F�������������Ƃɂ��āA����͑O���`���ɋ������u�V��E�`���̑��@���O�̖@��瑖�ɑ��āA��s��F�̍Ēa�E���@�����@�ɏo�����Ė@�ؖ{����O�ʂ���Ƃ����V��Ɠ��@�̖{瑈�ڂ̗��ĕ����v�ɖ������̂ƒf�肵�A���@�K���̖@�ؖ{��̗��ꂩ�璆���E�V��R�ɑ��ē��{���E�x�m�R�A���������ɑ��ĉ����̏����̗̍p���咣���Ă���B�܂��A���@�̖{���ɂ��Ă͏\�E��䶗��{�������A�@�c���g�̈�̕��Ɏ�������҂ɂ͈ꎞ�̕��ւƂ��ď�s���̎l��F�������|���w�����Ă���B�܂��A�C�s�@�Ƃ��Ă͐����̐ێ�s�Ɋ�Â��u�@�،o�v�̈ꕔ���u�ɑ��Ė��@�̐ܕ��s�̒P����ڂ�I�����A��s�̕��ցE���ʂ̓�i���u�̓��A瑖���֕i�̓��u�ɂ��Ă̓V�ڎt�̋^��ɑ��Ă͏��j�E�ؕ��̓�`�������ĉ�ʂ��Ă���B���̏��j�̋`�ɂ��āu�Ⴕ���j�̂��߂Ƃ����Ȃ�A�O�������\���ׂ��ł͂Ȃ����v�ƓV�ڎt���������Ƃɑ��āA
���j���l�d�V���p�j�A���N���m�O���V�O�o���B�d���V����A�j�ĔV���ɖ�B
�Ɓu�l�d�V���p�v�̌ꂪ�p�����Ă���B���̎l�d���p�Ƃ͓��{���Â̓V�䋳�w���\���鋳���ŁA���Ƃ͓V��q��́u�@�،��`�v�����̐�Җ����߂��镶�Ɋ�Â��`�ł��邪�A�ߑ��̋��������O�E瑖�E�{��E�ϐS�̎l�ɕ����A�O��㏟�ɑ����ď�������ɋ��p��_���A�ŏI�I�ɂ͊ϐS���ŏ��Ƃ��鋳���ł���B
�@�u�ܐl���j���v�̉E���͓������u�l�d�����p�v���L����q�́u�������v�̕����Ɨގ����Ă��邪�A�u�������v���{瑖����̊ϐS�d�ɂ܂Ō����y�Ԃ̂ɑ��āA���́u�ܐl���j���v�ł͂����܂ł�瑖�Ɩ{��̗��d�̑Δ�̂��߂ɗp�����Ă���A����ȏ�̋��w�I�Ȕ��W�ɂ͐G����Ă��Ȃ��B�{���ł͂��̑��A�F���̋֎~�A�_�V��@��A�{����̈˗p�A������l�̐��`�Ȃǂ��q�ׂ��Ă���B
�@����A�u�x�m��Ֆ�k���m���v���@�ؖ{��̗��ꂩ��u�ܐl���j���v�Ƃڂړ����悤�ȓ��e�ƂȂ��Ă�����̂́A�G���E�ؑ��̕���F�ł͂Ȃ����@�@�،o�̌����鐹�l���M�̖{����I�ю��Ƃ�����ґ���̑ԓx���N���Ɏ�����Ă���B�������A�����lj����ӏ��ŏ��t�����ݎ�����u���������̋`�v�̋�̓I���e�Ƃ��āA�_�V��@��Ƌ��Ɏl��F�̑��蕛�����������Ă���A�@�ؖ{��̗��ꂩ��ꑸ�l�m�������e����Ă���B�܂��A�@�c��e�̊G���E�ؑ���}���E��������ړI���A�@�c�̖ʉe�����ɒm�点�邽�߂Ɛ�������Ă���B
�@�ȏ�A�O���Ɠ����̍l�@����A�嗬�̑c�E�����t�̋��w�I�咣�̂���܂���m�邱�Ƃ��ł��邪�A���̖{瑊ςɖ₵�ĕ⑫����A�{瑂��̂��̗̂��ĕ����́u�@�،o�v�O���\�l�i��瑖�A�㔼�\�l�i���{��Ƃ����ʏ�̌o�ɖ��{瑓��ɏ������A���̏�Ő������̎O���O�o����̃��[���ɂ̂��Ƃ��đ��@�̓V��E�`����瑖�ז{�ɑ��閖�@�̏�s�E���@�̖{��ז{�Ƃ����}����������Ă���B�������A�@�c���w�̔��ɑ傫�ȓ����ł��鉻���̎n�I�A�܂��n�E�̎O�v�ɑ��錾�y�͂قƂ�nj���ꂸ�A����䂦�@�c���u�ϐS�{�����v�ɐ����ꂽ�u�ނ�͒E�A����͎�v�Ƃ����Δ����肠���āA�ߑ��𑊑Ή�����Ƃ�����Ƃ����R�s���Ă��Ȃ��B��s�E���@�̑I�ю��͂����܂ł������̑��Ɋ�Â��V��E�`���Ƃ̔�r�̌��ʂɂƂǂ܂�A���Ƃ��Ώ@�c���ߑ��Ƃ̑Δ�̒��Ŏ������ێ�E�ܕ��̗��ĕ����Ȃǂ��A�u�ܐl���j���v�ł͌ܘV�m����ѓV��Ƃ̈ꕔ���u������ڂ��Ƃ����C�s�̓��ۂ�_���钆�ŗp�����Ă���݂̂ł���B
�@�����āA���̂悤�ɓ����t���ߑ��̑��Ή��ɘ_�y���Ă��Ȃ��Ƃ��������́A���̖{���ςɂ��@���ɔ��f���Ă���Ɣ��f�����B�܂�A�����̗h�炬�������Ȃ�����A�@�c�}���̏\�E��䶗��{���Ƌ��Ɏߑ�����я�s���̈ꑸ�l�m�������@�K���̖{���Ƃ��ċ��e����Ă��闝�R�́A�܂��������̎ߑ��̔Ή��ɂ���ƌ�����B�܂��A�@�c��e���m�Ȍ`�ł͖{���ƒ�`�����A���̑����ړI���@�c�̑��e����l�ɓ`���邽�߂Ƃ���̂��A�S���������R�ɂ����̂ƍl������B�����A���̌�e���Ɋւ��ẮA�f�p�ȑc�t�M�Ƃ����͓Y���āA���̌㎟��ɖ{���i�ւƏ����Ă��������̂Ƒz�肳���B
�@�@�R�A���ځE����E�����E�����E�����E�����E�����E���s�u�\��v�A�����u��`�y��v
�@���ڎt������s�t�܂ł�8�t�́u�\��v�������ɂ܂Ƃ߂����A����͂W�t�Ƃ��ɔh�c�E�����t�́u�\��v�̎咣�Ƃ��̓��e���قƂ�Ǔ��������Ă��邱�Ƃɂ��B�E�q�����悤�ɁA���Ō�O���̍O�o����ɏ����Đ������O�̎��O瑖��掖@��ޖ肵�A���@�K���̖@�ؖ{��̐��@���閭�@�@�،o�𗧂ĂāA���ƓV���������Ȃ炵�߂Ƃ�t�シ���|�ƂȂ��Ă��邩�A����Ȓ��œ��ڎt�Ɠ��s�t�́u�\��v�ɖ{��̐��@�̓��e�Ƃ��Ė{���E���d�E��ڂ̎O���@��������A����t�́u�\��v�ɕ��@���@��̗̂��Ɋ�Â��ē��{���̗��x�m�R�ɐ��@���O�ʂ���Ƃ����t�i����Ă���A���������ӂ����B
�@���ɁA���@�E�����E���ڂ̎O�t�̓`�L�����߂������t�́u��`�y��v�̓����`�̒��ɂ́A�u������l��⍐�v�Ƃ��āA
�P�A�吹�l�䏑�a���^���x�L���@�P�A���q�ܐl�V�䍹�喳�����@�P�A�ꕔ��s�߃^��������
�P�A��̕����@�P�A�V�ڗ͕��֕i�s�Ǘ���掖@��
�ƁA�܉ӏ��̎�����������Ă��邪�A���̌�Ɍ����邻�ꂼ��̓��e�́A�O���́u�ܐl���j���v�ɏq�ׂ��Ă�����̂Ƃۂړ������̂Ɣ��f�����B�������A�u�P�A�V�䍹��퍆�\���掖@���v�Ƃ̎����̉��ɖ@�ؖ{��̎O����q�ׂ钆�A����ɂ���
�{�勳��n�v����������O�g�������ʈ��m�鍅��Z�s�ʼn�{�s��F�������������P���s���{�㐔�m�{����
�ƋL����Ă���B�����Ɍ����閳��O�g�Ƃ�������́A���{�V��̑c�E�Ő��́u��썑�E�́v������
�L�ט��n���������ʁA���옦�O�g�n�o�O�������i���B
�Ƃ���A�l�ׂ��������{�����̂�����̎O�g����������@�؉~���̕��̈ӂŁA�����܂ł��v�������̎ߑ��̂Ƃ��ď��߂Đ����ꂽ���̂ł���B�������A���̌�̒��Â̓V��Ə��t�ɂ�Ď��C���̕��ɑ����C���̖}�v��������O�g�̖{���ł���Ƃ��������{�o�`����������Ƃ��������̉��ɒ��ڂ���A����ɖ@�E�̐X�����@������O�g�̌����ɑ��Ȃ炸�A���̂܂܂̎p�ɂď�Z�s�ςł���Ƃ���������Z�`�ւƓW�J���āA���̖{�o�@����������i����d�v�f�ƂȂ��Ă����B
�@���m�̂Ƃ���A�@�c�̐^��������т���ɏ�����╶�ɂ͖���O�g�̐���͗p����ꂸ�A�\�Z�ђ��̎ʖ{�œ`������╶�̒��ɎU����邪�A���̓��̑��������ÓV�䋳�w�̗����{�o�̈Ӗ������̉��Ɏg�p����Ă���Ƃ��납��A���ꂼ��̈╶���̂̐^�U��肪����܂łɘ_�����Ă���B������ɁA�E�́u��`�y��v�Ɍ����閳��O�g�̗p��́A�ꌩ���ĕ�����悤�ɋv�������̎ߑ��ɑ�������Ƃ��ėp�����Ă���A�����܂ł��Ő��̈Ӑ}�ɏ������p�����ł���Ƃ�����B
�@�h�c�E�����t�A��̖�1�N��̌������N�i1334�j����7���A�x�m��Ύ��̓���V�i��@�V�j�ɂ����ē���t�Ɠ���t�̊ԂŁu�@�،o�v���֕i����u���邩�ۂ��Ƃ����_�����s��ꂽ�B�_���̑��_�́A���O瑖��j���Ė@�ؖ{��𗧂ĂȂ���A�ǂ�����瑖�̕��֕i��ǂނ̂��Ƃ�����_�ɂ��������A�E�q�̂悤�Ɏ��O瑖��j���Ė{��𗧂Ă�Ƃ����`�͓����t���@�c�̖{��ז{�ɂ���čł������咣�������`�ł��������A�܂����ցE���ʂ̓�i���u���@�c����ѓ����t�̒�u�������X�̋s����ł������B��ɐG�ꂽ�悤�ɁA�u�ܐl���j���v�����ɂ͓V�ڎt�������t�ɑ��Ă��̗��`�����ꑊ��Ɣ�`���A����ɉ����ē����t�����j�E�ؕ��̓�`�������ĉ�ʂ��������|���L�^����Ă��邪�A���ǂ͂��̖�肪�Ō�Ɏ����z����ē��_���Ɏ��������̂Ƒz�肳���B
�@���̓���E����̗��t�̖ⓚ�Ƃ���Ɋ֘A���鏔�t�̎咣�ɂ��Ă͑����̎j���ɋL�^����Ă���B���͂��̎�Ȃ��̂��璍�ړ_�������Ă݂邪�A�ⓚ���̂��̂̋L�^�Ƃ��Ă͓����t�Ɠ��e�t�̂��̂��₳��Ă���B
�@�܂��A�����t�́u���֕i�Ǖs�V�ⓚ�L�^�v�ɂ́A����t�����O瑖�ɓ��v�Ȃ��{����ʕi�ɂďo����������Ƃ����u�i���ӏ��v�̈ӂɂ���ĕ��֕i�̕s�ǂ��咣���A����������֕i���v�̗L�����������̂ɑ��A���֕i���u���������t�͗^�D�j�̎O�`�𗧂ĂāA�u�^���ӂ̕��A�ꉝ���e����j嫖��X�g���v���A�D�j�o�ӂ̕��A�ĉ����e����j���V���v�v�ƕ��㓾�v�E���ꖳ�v���q�ׁA�u�^�������v�n�Ҍ������ʕi�����꘦�����j��v�Ɠ����Ă���B���̍Ō�̋v���{�����ɐ^���̓��v������Ƃ�������t�̔����ɂ��ẮA�����O���ٍ̐e�ɂĖŌ���ɂ�����{�����v�z�`���̗v�f�̈�Ƃ��Ď�肠�������A���L�^�̒��ł��̈ꕶ�������ˏo���A���̎��ӂ��܂߂��ڂ������s���ł��邽�߂ɁA���̎�舵�������ɍ���ł��邱�Ƃ͑O�L�̂Ƃ���ł���B�{�����v�z���\�z����邽�߂ɂ́A���̑O��Ƃ��Ď�E�{瑘_���K�v�ł��邱�Ƃ͑O�e�ɂ��G�ꂽ���A�����̏ꍇ�͂��̎�E�̉�݂Ȃ��ɖ{�����v�z��������Ă����ۂ�����A��͂肻�̂܂܂̈ӂŎ�邱�Ƃ͓���Ɣ��f�����B����A���e�t�́u�������ⓚ�v�ɂ͓���t���u�\��v�̈ӂɂ��瑖�s���u���q�ׂ����A����͓V�ځE���ٗ��t�̗��`�Ɠ����ł��邱�ƁA����ɑ��ē���t�͊��q���Ɠ��l��瑖哾�v�𗧂Ă��|���L����Ă���B
�@���̗����̑��ɁA�����Ƃ��Ă͎�舵���ɏ��������ӂ�v������̂Ȃ���A�u��L�v�ɂ͓���t��瑖喳�����̂䂦�ɕs�v�E�s�ǂƂ����`���������Ă����߂ɁA��������P���悤�Ƃ�������t��瑖�������A���̓����ɐG��Ă����Ȃǂ��Ă�����ɁA����������������瑖哾���̖@��̎咣�ɂȂ����Ƃ�����̓I�ȕ`�ʂ��Ȃ���Ă���B�܂��A����t���ז{�{瑁E�J瑌��{�E�p瑗��{�̎O�`�̓��A�{瑂̕��ɂ�瑖���̂ĂȂ��|���q�ׂ��̂ɑ��āA��Ύ������t���{�J�p�̎O�`�Ƃ���瑖�͎̂Ă�R�������A��������t���x���������܂��L�^����Ă���B
�@���Ɏ��ӎj���ɖڂ����ƁA���e�t�́u��M���v�͓��e�t���t�̓����t�����@�����ڂ������̂ł��邪�A���̒��ɓ���E�����̗��t�����@�����̗��ɂ͖{瑂̋�ʂ͂Ȃ��Ǝ咣�����̂ɑ��āA�����t�������̖{��瑗�𗧂Ă����Ƃ��L����Ă���B�܂��A�c�r�t���ʂ́u�ⓚ�L�^�v�ɂ͓���t�̋`�Ƃ���瑖���J��̌�͖{��ƌ������ē��Ȃ�䂦��瑖哾���ɂ��ĕ��֓��u�ƌ����A����t�́u���t���^�v�ɂ͓���t���͍̉������u�{�ɑ�����瑁v�䂦�ɕ��֓��u�Ɨ��Ă����ƁA����ɏ��j�̂��߂̕��֕i���u��ے肵�ĐS�@������̎O�@������֕i�E���ʕi�E���ɔz���ē��u����Ƃ��������t�̉��߂�������Ă���B
�@�ȏ�A����E���㗼�t�̕��֕i�Ǖs�_���Ƃ���ɂ܂�鏔�t�̋`���T�ς��Ă݂����A�����悻����t�̋`����`�Ɣ��肳�ꂽ���Ƃɂ��A��ɖ{瑓��̎������Ɋ�Â�瑖哾�v�͔ے肳��A�{瑂̎����ɂ͏�����A����䂦瑖�ɂ͓����͂Ȃ��Ƃ����{瑏���`�����̎��_�Ŋm�F���ꂽ�B�܂��A����t�̕��֕s�ǂ̎咣���u�ܐl���j���v�œ����t���u�t�l�v�ƕ]���ꂽ�V�ڎt�ً̈`�Ɠ����ł���Ƃ��납��A�@�c����ѓ����t�ȗ��̕��ցE���ʂ̓�i���u���`���̉��V�Ƃ��āA���̘_����ʂ��čĊm�F���ꂽ�ƌ�����B
�@�@5�A�����u�����l�j���X��v�E����u�ɑ���苗���Ԏ��v
�@�����i��j�t�͋��s�O���̓����t�̒�q�ł��邪�A�N�i3�N�i1344�j7���ɂ��̍��ɏd�{��ޏo���ĉ͍��E���R�ӂɋ��Z���Ă�������t�ɏ����悵�A�ߑ������ɂ��Ă̌��������߂��B���́u�����l�j���X��v�ɂ��A�����t������l����i���ꂽ�߉ޗ����Ə\���q�����s�E��s�@�Ɉ��u�����Ƃ���A�x�m�嗬�̐l���@�c�E�����E���ڂ̎O�t�Ɏߑ������̎������Ȃ������ƁA�����āu�{���ⓚ���v�̈ӂɂ��`���̖{���͕s�ł���Ƃ����^������炳�ꂽ�B����ɑ��āA�����t�́u�ϐS�{�����v�u���v�̋����狕���i�̏������F�̑������{�ӂł��邪�A���������ɂ������ł��Ȃ��̂ŁA���͎l��F�݂̂蕛�����Ɠ����Ă���B�����t�͂��̂悤�Ȏt�`�ɂ��āA�L�闬�z�ߑO��掖@��ӂ̐ܕ��s�ɐ�S���ׂ��ł���A���������̐ێ�s�͍L�闬�z���Ė{�厛���������ꂽ�ȍ~�̂��Ƃł���Ƃ������Ă������A����t�Ɏ��`�̋����𐿂��Ă���B
�@����t�̏���u�ɑ���苗���Ԏ��v�́A����ȓ����t�̈ӌ���ǔF������e�ƂȂ��Ă���A���傪�A�˂��A���قɂ��{�厛�i���d�j���������ꂽ���ɖ{���}�̂Ƃ���ɕ��������邱�Ƃ��w������Ă���B�����āA�@�c�����g�̈�̕���揊�̖T��ɗ��Ēu���ƈ⌾���A�~�⎞�ɗՖœx���̙�䶗��{���������Ɍ�����ꂽ�Ƃ��������������Ă���Ƃ��납��́A���L�z���̙�䶗��{�����u���q�ׂ��Ă���ƍl������B
�@�ȏ�̂悤�ɁA���̉�������̃e�[�}�͎ߑ����͂��߂Ƃ��镧�������ɂ���A����͉b�R�V��@����@�@�؏@���h���_�W���鋞�s�ɂ��ĕz����������嗬�ɂ͓��ɏd�v�Ȗ��ł������B���Ă̂Ƃ���A��莩�̂͑O�L�̓����t�̈ꑸ�l�m���Ƃ�����肳��ɕ��G�ɂȂ��Ă���A�������Ɋ֘A���čL�闬�z��{�厛����щ��d�̂��ƁA��䶗��{���̈ʒu�Â��Ȃǂ��q�ׂ��Ă���B
�@�@6�A�����u�\���v�u�p�S���v�u������苗������v�u�����i�\�����j�v�u�S�ꏴ�v�u���ח������v�u�����G�W�v
�@�E�f�́u�ܐl���j���v�������t�̈ӂ��ē����t����q�������ƍl������悤�ɁA�����嗬���w�̌`���ɓ����t���ʂ����������͔��ɑ傫���A�܂����̉e���͍L������ɂ܂ŋy��ł���B����䂦�ɖ{�����v�z�Ƃ̊֘A�����傫�����Ɨ\�z����邪�A���Ď��ۂ͂ǂ��ł��낤���B
�@�܂��A���̖{瑊ς��������Ă݂�ƁA�����嗬�`���̖{��瑗��������ŁA���̏������̏���ł���|������A�V��߂́u�{�嫎�s�v�c��v���{��ɂĊJ�ߌ������ꂽ瑖�̗��̓��̂��{��̗��Ȃ邳�܂��u�s�v�c��v�Ƃ͌������A����͖{瑂̗�������ł���Ƃ����ӂł͂Ȃ��ƒf���Ă���B���̖{瑓��̎����̑���ɂ��Ă͂���ȏ�̐������Ȃ��A��̓I�ȓ��e�ɂ��Ă͕s���ł��邪�A����Ɍq����`�Ƃ��Ă�瑖偁�s�ϐ^�@�A�{�偁�����^�@�Ƃ����z����������Ă���B����͍Ő����،����w��ێ悵�Ĉȗ��A���{�V��ɂē`���I�ɐ������{瑓��̗��ĕ����ł��邪�A�]���J��E�f�f�ؗ������瑖�ł͖}�����u�₵�A���̌��̗�����������V�������s�ϐ^�@�̗������ł���̂ɑ��āA���ʑ����E�s���{�ʂ𖾂����{��ł͌����I��̐������̂܂ܐ^���̖{�̂ł���Ƃ��������^�@�̎������ł���A�Ƃ����@��ł���B���̐����E�s�ς̗��^�@�́u�����Ϗ��v���͂��߂Ƃ���ʖ{�`���╶�ɂ͌�������̂́A�^��������т���ɏ�����╶�ł͌��y����Ă��炸�A���ɗ��^�@��{瑓��ɔz������Ƃ�����ƂɊւ��ẮA�����t�����{�V�䋳�w���w�K�������ʂ̋��w�I�t����Ƃ̈�ł���ƌ�����B
�@���ɁA���֕i���u�̗��R�ɂ��Ă͏��j�E�ؕ��̓�`�������A�ؕ��̕����Ƃ��Ă͎�Ɂu�������ߒʓ����p�v���������A�����t�̋����Ƃ��āu�A���j�Ɖ]���ׂ��A瑂���Ė{�̏��ɒu���Ƃ͉]���ׂ��炸�Ƌ�����Ȃ�v�Ƃ���A�ؕ��ɂ����֓��u�ɂ͍אS�̒��ӂ�������Ă���B����͂����炭�A�E�̂悤�Ɉꉝ�{瑂̎����̈Ⴂ������Ȃ�����A�u瑂���Ė{�̏��ɒu���v�ƌ�������ƁA����͖{瑂̎������ƌ�����ꂩ�˂Ȃ��Ƃ����S��������̋����ł��낤�ƍl������B�����āA����͖{���A瑖�ז{�̖{瑈�v���������V�䋳�w�ɋ���Ȃ���{瑂̏���𗧂Ă邱�Ƃ̓�����悭�\���Ă���A�O�L�̓��������֓Ǖs�_���̕��G���̐^�������̂�����ɂ�����̂��Ƒz�肳���B
�@�{���ςɊւ��ẮA�܂��u�����G�W�v�ɂ�
���l�͑����ׂ̈̏o���ɂ͖����A�{�������킳�ׂȂ�B
�Ƃ���A�@�c�o���̖{���������ł͂Ȃ���䶗��{���̐}���ɂ���Ƃ����F����������A���̙�䶗��{���̓��������̎O���`�ɂ���������Ă���B�����āA���̖{�����h�炵�đ�ڂ������A����̖{�������ƒ�ߔ\��̂킪�F�S��q�ƂȂ��āA���q�̕s���̂��ό�����Α��g���������A����Ɛ�����Ă���B�܂��A���}�̙�䶗��{�����@�c�̌ȏł���A���ꂪ�u�����i�\�����j�v�ł́u�{�����̔V���@���l�v�ƕ\������Ă���B���̌�҂̈ꕶ�ɂ��ẮA�����O���ٍ̐e�ɂ����ĖŌ�̖嗬���ł̖{�����v�z�`���̗v�f�̈�Ƃ��Ďw�E�����Ƃ���A��䶗��{�������̂܂܂œ��@���l�Ɣq����Ȃ�A����͓��@���l��{���Ƃ��A���@�̋���Ƃ��ĐM�����悤�Ƃ���{�����v�z�ւ̓�����̂ƌ����悤�B
�@����A�u�S�ꏴ�v�ɂ͖{��v���̒�b����{���Ƒ�ڂ��L�闬�z�����Ȃ�A�{��̉��d�͕K�����������ׂ��ł���A���̒��ɂ͖{���̐}�̂��Ƃ����������u����Ƃ����L�z�����̋`��������Ă���A����͑O���̓���t�̎咣�Ɠ����ł��邪�A�u�F�ח������v�ɂ�
������l�ƃ��m�V�e�ގR�������A�Ύ��V�e���O瑖嘦掖@���~�V�����g�@�ؖ{�嘦���d���A��e���u�V�{��V���䶗������j���t�얳���@�@�،o�m�A���ƕ��ƃj���P�t���������j���j�߃����P�Z�A�������`�吹�V�{���䏴������B
�Ɖ��d���u�͙�䶗��{���ł���Ɨ����ł���ꕶ������A���̗��`�̊W���ǂ̂悤�ɂ���̂��͐�������Ă��Ȃ��B
�܂��A�u�����G�W�v�ɂ�
�R���������{���͋v���̏�s��F�̌����ʂӂׂ��Ȃ�A�R���ɓV���̕���瑕��Ȃ�A�����{���Ɍ����ʂӂׂ��߉ނ͖{���Ȃ�B
�Ƃ���A���{���ɏo������v���̏�s��F�Ƃ͏@�c�̂��Ƃł��낤���A�{���Ƃ��Ă�͂���{���Ɍ����v���̎ߑ��Ƃ͖{���Ƃ��Ă̏o���ł��낤���B����ɁA�u������苗������v�ɂ͓�����l�̐��`�p������u���Ӎs�������b�v�Ɛ�������Ă��邪�A����͓��@�E�����̎t��`�̕ʕ\���Ƃ��āu�{�������v�����Ɏ�����鑊���}�Ɉ����p����Ă���B
�@���̑��A�����t�̋��w�Œ��ӂ����̂͒��ÓV�䋳�w�̐ێ�ł���B�s�ρE�����̐^�@�_�̎�e�ɂ��Ă͉E�ɐG�ꂽ�Ƃ���ł��邪�A����O�g�̐�����@�ؖ{��̋v���̋`���܂݂Ȃ�����A�\�E�̗����{��������Ƃ��ėp�����Ă���B�܂��A�u�����G�W�v�Ɍ�����u�@�؈��ʘ����v�͂����炩�ɒ��ÓV��b�S�����Ӗ@��̗��`�O�ӂ̑�O�E�@�؈��ʂ��ؗp�������̂ł��邵�A���̎��Ɍ�����u�{瑕s�������v�����Ӗ@��̒��Ř@�؈��ʂ̉��ɔ�ۖ@��Ƌ��ɒu�����Z��ł���B
�@�����t�́u�������v�́A�܂����ÓV��̖{�o�@�傪�S�ʂɕ\�ꂽ����ł���A���ɂ́u�V���@�̑��`�v�Ƃ��ėG�C�́u�̐S�v�`�W�v�̕������ӏ�������Ă���B�{瑂̓��قƂ��Ă͓��̎����̈�ڂ��u瑖偁�S�����E�s�ϐ^�@�E���̈�O�O��E���~�E�]�����ʁv�u�{�偁�F�����E�����^�@�E���̈�O�O��E���~�E�]�ʌ����v�Ɩ����ɗ��ĕ������Ă��邪�A��������Â̓V�䋳�w�ł̐��������̂܂܂Ɏؗp�������̂ł���B�嗬�ً̈`�ɂ��āA
���e���O�������j�i�j嫑��X�g�ً`���A���n���f�V�O�혦�����j���N�s�ق֎l�d�����p���A�ÃV�e��t���p���j���X���n�䎷�������׃X��g�B
�Ƃ���A�O�틳���Ƌ��Ɏ��O�E瑖�E�{��E�ϐS�̎l�d���p�������Ă���Ƃ��납��A�{瑂𗧂ĂȂ�����ŏI�I�ɂ͖{瑖����̊ϐS�d���{�ӂƐ�����Ă���B�܂��A�O��o�_�E�ܕS�o�_�����̗����{��}�v�{���Ƃ��Ă̖���O�g��������A�@�ؖ{��̖{���E���d�E��ڂ̎O���@���E�ɐG�ꂽ���Ӗ@�咆�̗��`�O�Ӂi�~���O�g�E�����y�E�@�؈��ʁj�𑊓`������ɓ��ӂ��ׂ��Əq�ׂ��Ă���B�{���ɂ͉����S�N�i�P�R�T�X�j�̖��������t�̎ʖ{���������A������Ύ������t�����`���Ă��铙�A�x�m���ӂŊw�K�E���p���ꂽ�l�q�������A�嗬���̌��r�X���̈�[���M�����Ƃ��ł���B
�@����t�́u���t���^�v�́A�����t�̋����q�̓���t���L�^�������̂ł��邪�A�O�q�̂悤�ɁA�����t�͕��֕i�Ǖs�Ɋւ��ď��j�̂��߂̓��u��ނ��A�S�@������̎O�@���Ƃ��ĕ��֕i�E���ʕi�E���̓��u������Ă���B�����āA瑖��j���Ė{��𗧂Ă邱�Ƃ��@�c�o���̌��ӂƂ��Ȃ�����A
�ꉝ�O�\�l�i��\�l�i�����P���t������g�C�w�h���A�ĉ�瑖{�ݓ�ʃY�����L�V�A�����{�L���瑖��{���ϐS����B
�ƊϐS�ɂ�����{瑂̗Z�ʂ������Ă���B�܂��A�{���`�ɂ��Ă������t�̌��t�Ƃ��āu�L�闬�z�m�����}�f���䶗����V���u�V�]�]�v�ƋL�^���Ȃ�����A�݂�����̈ӌ��Ƃ��Ă͖{��v���̈ꑸ�l�m���i���{���j�����čL�闬�z��҂��Ƃ��w�����Ă���B���̑��A�g���Q�w�̋���@�c�{���̌`�̎��^�������ȂǁA�����t�̗��`�̒��ɔh�c�E�����t�̋`�ɔ�����X���̂��邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B
�@�u���咼���䓖�ⓚ�L�v�͒��2�N�i1363�j��ꂩ�痂�N�����ɂ����āA����t���b�R�̑��T��E�����t�Ƙ_�k�������̂̋L�^�ł��邪�A��ɓ���t�����@����ѓ����嗬�̋`����A���̉ۂ��t�Ɏ�����`�ƂȂ��Ă���B���Ȃ킿�A瑖��j���Ė{��𗧂Ă�`���܂̌ܕS�̖{�嗬�ʁA�{����d�̌�����S�@����̎O�@���̎����s�Ȃǂ́A���̂܂ܒ����t�̎^�ӂĂ��邵�A���֕i�Ǖs�ɂ��Ď������t���E�����t�̖{瑕\���Z�ʋ`�Ɋ�Â����֓��u�ɂ��Ă��u�_���_���v�ƕ]������Ă���B���������A�@�{�������̏����Ƃ��ē���t�ɑ�\���������嗬�̋��w���A�����嗬�̖{��ז{�������ēV��`�ɗ^������ʂ����邱�Ƃ͔ے�ł����A����͓�������t�́u���g�������v��u�O��@�؎��v�Ƃ�������Ȃǂɂ��F�Z�����f����Ă���B����ł��A����t����o����
��S�O�ψ�O�O��n�n�E�m�@��m�]�]�]�B��ڍO�ʃn�{�剺��m�]���V�B
�Ƃ����O���E�O�v�ɂ�闧�ĕ����ɂ��ẮA�����t�͂������Ɂu���嘦�s����v�ƈً`��悵�Ă���B�Ȃ��A�{�������ɂāA�����t���V���t�̖@�ؑ����ɂ��ė�R�����Ƒ��������̓��������A����ɑΉ�����`�œ��@�̗�R��s�����Ɠ������������𗧂āA����t�����̋`�����̂܂ܗp���Ă��邱�Ƃɂ��āA���s�C�G�����u�]�Ă��̎v�z�̍���ɂ́A�@�c�̏�s����������]���āA�@�c�{���_�ւƓW�J��������̂�����v�ƃR�����g���Ă��邪�A�ǂ��ł��낤���B�O�e�ɂł��q�ׂ��Ƃ���A�����嗬�̏@�c�{���_�͎�ɏ�s�̖{��������̋`�Ɋ�Â��č\�z����Ă���ƍl������B
�@���͎t�́u�{瑖ⓚ�\�����v�͌����i1334�`8�j�̍��ɁA�����������ɂčO�����Ă����Z��嗬�̓��S�t���߂��̑��c�Ŗ@�`�𗧂ĂĂ��������嗬�̓��ؖ[�ɂP�V���̓����o�����Ƃ���A���ؖ[�����̋`�ɋ������ĘZ��嗬�ɉ��߂��Ă��܂��̂ŁA���̖T�炩����͎t���ԓ��������̂��L�^�������ł���B���e�͐��{瑈�v���咣������S�t��瑖储��ѕ��֕i�̓��v����X�����̂�̂ɑ��āA���͎t��瑖��j���Ė{��𗧂Ă�����嗬�`���j�܂������Ă��邪�A����Ȓ��A�܂��@�J���c�̕��֕i���u�͏��j�̂��߂ł��邱�ƁA�{��J��̌��瑖�̖����Ȃ��B���@���ł��邱�ƁA������瑖哾�v�ƌ�����O�����v���������_�Ƃ���ĉ��͖{��̓��v�ł��邱�Ƃ��q�ׁA�{瑎����Ԃ̈�v�_�ɑ��Ă͎����̏�����������Ă��邱�ƂȂǂ����ӂ����B
�@�������͎t�́u��M���v�́A���͎t���ĎO��B���֓��ɕ����Ďt�̓����t����w�������`�Ɏ��`�������ĕ҂������̂ł���A���ꂵ�����e�������̂ł͂Ȃ����A�{��̎�����{�Ƃ��邱�Ƃ�瑖偁�s�ϐ^�@�E�ÑR��Z�E���~�E����E���ςƖ{�偁�����^�@�E���N��Z�E���~�E����E���ςƂ������ĕ����A瑖哾�v���ĉ��͖{�哾�v�ł��邱�ƁA�����Ē��ÓV�䋳�w�̗����{�o�`�����U�������B
�@�Ō�ɁA���`�t�́u��j�[�鏴�v�͎�ɖ{��̎O��ł���{���E���d�E��ڂɂ��ċL�q�����Z�҂ł��邪�A�{���̖{��Ƃ͏\�E��䶗��{���ł��邱�ƁA���d�@�͎����̑����̌`�ԂɂČ������A�@���ɂ́u�@�،o�v�����u���邱�ƁA�����Ė��@�ɂĖ{��瑗�̐��O���������邱�Ƃ��{����̂̐��ӂł���Ɛ�������Ă���B
�@�ȏ�A�@�c�Ōォ��I��1400�N���܂ł̓����嗬�̏�����������܂������Ă݂��B���A���̌��ʂƂ��ꂪ�{�����v�z�̌`���ɂ����Ȃ�W�����̂��������Ă݂�ƁA�����悻���̂悤�ɂȂ邩�Ǝv����B
�@�܂��A�{瑊ςɂ��Ắu�@�،o�v�O���\�l�i�ƌ㔼�\�l�i�̖�o�̖{瑂��������A�����̈Ⴂ�ɂ��{瑏�������āA�s�ρE�����̗��^�@���̋`�ɂ������̈�ڂ���������Ă���B�������A�r���ɓ����t�̋��w�ɑ��銴�z�̒��ł��G�ꂽ�悤�ɁA�����̎n�I�����n�E�̎O�v�ɂ��Ă̌��y�͂��̌�̏��t���܂߂ĂقƂ�nj��邱�Ƃ��ł����A��������t���V��~�ς̏n�E�@��ɑ����ڍO�ʂ̖{�剺����q�ׁA���͎t���v���������_�Ƃ����{��̓��v���咣�����ɂƂǂ܂��Ă���B����āA�������炳��Ɏ�E�̉v�ق���e�Ƃ���{瑂𗧂Ăĉ���̖{�����ւƂ��ǂ蒅���܂łɂ͏��X���u������Ɣ��f����A����䂦����t�����֕i�Ǖs�_���̒��ŏq�ׂ��Ƃ����{�����ɐ^���̓��v������Ƃ����`���A�S�����̂܂܂Ŏ�邱�Ƃ͍���ł���B�������A�u�ܐl���j���v��u�������v�ł͒��ÓV�䋳�w����l�d���p�`���ێ悳��Ă����悤�ɁA�����嗬�ł����Ȃ葁������{�o�@���������铖���̓V�䋳�w���w�K���Ă����l�q������������̂ŁA���邢�͂��̕ӂ���{�����v�z�ւ̓������̂��Ƃ��z������邪�A����͂����܂ł������ɉ߂��Ȃ��B
�@���ɖ{���ςł��邪�A�ꉝ�̌����_�ł͙�䶗��{�������d����Ȃ�����A�ꑸ�l�m���̋��e��L�z�����_�Ȃǂ��������Ă���B�������͂�A��E�{瑘_�ɂ���Ďߑ��𑊑Ή����A�E�v�̎ߑ�����ނ��ĉ���v�̙�䶗��{����I�ю��Ƃ�����Ƃ��������A����䂦�{���i�Ƃ��Ď�舵���Ă����ł��낤�@�c��e�������̈ʒu�Â������Ăł͂Ȃ��B�����l����Ɠ����t���������u�{���V���̓��@���l�v�Ƃ�������A�����܂ł���䶗��{�����@�c�̌ȏł���|���ے��I�Ɏ�������Ƃ��������̈Ӗ����Ƃ��l������B
�@���̑��A���@�����̎t��q�`��x�m�R�̑��d�A�{�厛�i���d�j�̌����Ȃǂ���Ɋώ悳�ꂽ���A�����͖{�����v�z�Ƃ������͓����嗬���̂��̂̌`���̏d�v�f�ł���ƌ�����B
�@���̂悤�Ɍ����Ƃ���A�c�Ō�̓����嗬���ōs��ꂽ���w�I�t����Ƃ̒��ŁA�{�����v�z�̌`���Ɍq������̂�����Ǝ��o�����Ƃ͂ނÂ������B�����āA���̂悤�Ȏ���ł���������A���ǂ͓����t�̖{�����v�z���O�����瓱�����Ă̓����嗬�ł̓��v�z�̌`���ƂȂ������̂��Ƃ��z������邪�A����Ȓ��Œ��ӂ��ׂ��͂�͂蒆�ÓV�䋳�w�̑��݂ł���B�����w�̊ϐS��`��{�o�@��ɂ͒ʏ�̋����̘g���ȒP�ɏ��z����͂�����A���̗͂��炷��Ζ{�ʂ���{���ւƌ��������ƂȂNJȒP�ł��낤���A�����������ɂ͋��w�I�ȕK�R�������@���Ă���B�����āA���̕K�R���Ƃ͂�͂��E�{瑘_�ɋ��߂���̂ł͂Ȃ����ƍl������̂ł���B
�@
�@�O�e�ł́A�����t�̎��Ղ���ы��w�ɂ����ȒP�ɐG��Ďt�̓����嗬�Ƃ̌��̂��肳�܂Ɍ��y���A����ɂ��̖{�����v�z�ɂ��ď��X�ڂ����q�ׂĂ݂����̂́A�܂��Ƃɒ��r���[�Ȍ`�ɏI�n�����B���m�̂Ƃ���A�����t�̋��w�̌n�͔��ɑ�K�͂��_�C�i�~�b�N�ŁA���̂��ׂĂ��ꗥ���Î~�I�ɑ����邱�Ƃ͔��ɍ���ł���A�ƂĂ����̗͗ʂɊ����Ȃ��̂ŁA���͂��̊T�v���������Ė{�����v�z�̈ʒu���m�F���A�����Ŗ{�����v�z�`���̓��Ƃ��̉����̗l�q���ɂ��Ċώ@���Ă݂����B�Ȃ��A�E�̂悤�Ȏ���䂦�A�O�e�Ƒ����d�����镔�������邱�Ƃ�O���Ă��f�肵�Ēu�������B
�@�ŏ��ɓ����t�̋��w������̊�{�I�Ȏp�����Љ�Ă����ƁA�܂��L���Ƃ����L�w��`��ނ��ċ����[���Ƃ����v�w���|�Ƃ��A���ɓO�ꂵ���@�c�╶���S��`�ɗ��Ă���B����͖�������Ƃ������@�̔F���Ɋ�Â��A�L�����̂ĂĊ̗v��I�������@�c�̖��ӎ������̂܂܂Ɍp���������ʂł����邪�A�����ɓ����̓��{�V��̖{�o�@��ɋ����e������A�V��O�啔��@�c�╶�ɑ��Ă������{�o�̊ϐS��`�I���߂��{���Ď~�܂Ȃ��������̓��@�@�w�ɋ����ے�̑ԓx�����������̂ł������B
�@����āA�V��O�啔�Ə@�c�╶�̊W�ɂ��Ă��A�����܂ł��╶��\�ƁE�\�J�E�\��Ƃ��A�O�啔�{�������ƁE���J�E����ƋK�肵�āA�@�c���@�̗�����V��E���y�̕��`�����邱�Ƃ��������߂Ă���B����͍ŏI�I�ɂ�瑖�̎����𑫏�Ƃ���V��`�Ɉˋ����āA�{瑂̈�v���咣����������̘_�l�ɑ���ᔻ�ł��邪�A�����t�͂�������@�ؖ{��̗��ꂩ��V��O�啔�����߂��邱�Ƃ��咣���Ă���B�܂�A�O�啔�ɕ\�Ɨ����A�\�͓V��E���y�̊O�K���X���鑜�@���ʂ�瑖�̈Ӌ`������A���ɂ͓V��E���y�̓��ӗ�R�̖ʂ��閖�@���ʂ̖{������킷�Ƃ��A�V���t�͖{��̖��ӂɂ��Ă݂͂�������t�����A����@�̏@�c�ɑ������Ƃ����Ɠ��̗����������Ă���B
�@����ɁA�����t�͐������@�c�╶�̒��ł��u�ϐS�{�����v���ŗv�ƒ�߁A�u�{�����v�𒆐S�Ƃ�������I�Ȉ╶���߂���Ă��邪�A����͓������Ō㖖�@����̖{���ɂ��Ė{�唪�i������s�v�t�̓얳���@�@�،o�����������鑍�v��������ł���B�Ȃ��A�����t�����p���铯���ȊO�̎�v�╶����Ă݂�ƁA���̒ʂ�ł���B
�u�J�ڏ��v�u���v�u�l�M�ܕi���v�u���@�ؑ�ڏ��v�u�]�J�a��Ԏ��i�ĕď��j�v�u�����Ϗ��v�u�]�J�����a���䏑�v�u�ϐS�{�����ӏ��v�u���̋`���v�u�]�J�a��Ԏ��v�u�@�@���v�u�n������`�v�u��a���v�u�{�g�o�E���v�u�Z�폴�v�u�\�͏��v�u�@�؎�v���v�u�{���ⓚ���v�u��썑�Ƙ_�v�u�@�ؑ�ڏ��v�u��㐹����Ӂv�u�@���C�s���v�u�@�؏@���ؕ��@�����v�B
�@���̂悤�ɁA�����t�̋��w�̓��F�́A�����͓V��E���y�̒����V��A�߂��͓����̓��{���ÓV��Ƃ̋��`����ʂ��āA�@�c�╶���S�̏@�w��g�D���悤�Ƃ������Ƃɂ���A���`�I�ɂ͓Ǝ��̖{�唪�i�v�z�ɂ���āA�䓖�̈�ڂʂ������Ƃɂ���B�����t�����̋��w�̓Ɨ���錾�����Ɠ`����u�@�ؓV�䗼�@���v�l���i�ʏ́u�l�����v�j�͑䓖�{瑂��_�������̂ł���A���̒��ňꕔ�C�s�{��瑗�A�{�唪�i��s���`�̋��`�𖾂炩�ɂ��Ă���B
�@���̖{瑊ς����Ă݂�ƁA�����t�͓V��̖{瑊ς̗͑p�{瑂ł����āA�{瑂̎����̑̂͑S�������Ƃ����~�̖�����ł���̂ɑ��ē��Ƃ͋v���̐̂Ƌߐ��̍��Ƃ𑊑��āA�v���̐̂̕�������ċߐ��̍��̕������Ƃ����v�ߖ{瑂Ɋ�Â��A�������{瑓��ɏ���𗧂ĂĖ@�̓I������咣���Ă���B�����āA�t�̌n�������i�h�Ƃ���悤�ɁA�u�@�،o�v������̓��A���ɏ]�n�O�o�i��15������ݕi��22�ɂ���Ԗ{�唪�i�ɂ����ĕ��Ō㖖�@�ւ́u�@�،o�v�̍O�ʂ����������Ƃ���B�܂�A�u�ϐS�{�����v�̐����Ɋ�Â��A���ʕi���S�̈�i�͎ߑ��ݐ��̒E�v�̋@�̂��߂ɐ����ꂽ�����ł���̂ɑ��āA�{�唪�i�͂��̒��ɏ�s��F�ւ̗v�@�t���i�ʕt���j��������悤�ɁA���Ō�ɂ����鉺��̖@�傪������Ă���Ƃ��ċ�ʂ���B
�@�����āA�����t�͐�Җ��̏�̑��Җ���{��̐��ӂƂ��A��i�̖@�̂͐�Җ��s��̗��ɂ��Ė{瑂ʂ��������ʂł���A����䂦��瑂ł���̂ɑ��āA���i�����̗v�@�͖{瑑��������Җ��̎��ł���A�����������@��{��̒��@�ƒ�߂����@�����̋��@�ŁA����䂦�ɖ{�ł���Ǝ咣���Ă���B�������A��i������I�ɔے肷��̂ł͂Ȃ��A��i�͋��ł���E�v�ł���̂ɑ��Ĕ��i�͊ςł��艺��v�ł����ŁA�ꉝ�͋��ρE��E�̈قȂ�������Ȃ�����A�ĉ��͋��ρE��E�͈�v�E��o�Ɨ��Ă�̂ł���B
�@���Ɍ��{�_�ł́A�����t�͓����̓��@�@��v�h����ѓV�䋳�w���ϐS��`�ɌX���Ă��邱�Ƃɋ����ᔻ
�������A������`�̗��ꂩ��o�_�����̗����{�`��r���āA�ܕS�o�_���̎������������Ď��C���̕�g���{��I�ю���Ă���B����͔����ʂ̖@�g�△��̉��g��ނ��ďC�����ʂ̕�g���𐳈ӂƒ�߂邽�߂ł���A���̕�g������Ė{������`���m������Ƃ������߂ł���B���̓����t�̌��{�`�ɂ��ẮA�o�_�����ɋ�����������āA�ܕS�o�_�̎����I�Ȏ��Ԃ��̂��̂ɐ��ꂽ�J�Ԃ��̌��{�ƂȂ�A�O���ɂ킽��ߑ��̉����Ƃ�����肪�������ƂȂ��Ă���Ƃ����ᔻ����o����Ă���B
�@�Ō�ɖ{������_����˂���ƁA���̖{�����v�z����т��̉���_�͓����t�̋��w�̐��v�ł���A����܂ł̖{瑘_�┪�i���Ә_�A����_�⌰�{�_�����ׂĂ��̖{������_�̏�ɐ��藧�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�����āA�{���̕�F���{�����ɐ敧�̖{�ʂ̖@�����킷��Ƃ����{���������W�Ԃ��A�v���̏��߂Ɩ��@�̏��߂Ƃ͖{��������̎��ł���A����ɑ��Ė{�ʂ̕��͖{�ʎ��Ɏ����ĒE�v��������Ƃ���B����āA���@�͖{�����̉���̎��ł��邩��n�O�̕�F������@���l���{���L�P�̏O���ɕ���������ė��v���A���̉���̖@�͖̂{�唪�i�̐����ɂ����ď�s���ɕt�����ꂽ���@���ł���Ɛ����Ă���B
�@
�@�t�̖{�����v�z�̐���������O��Ƃ��āA�����ł�͂�t�Ɠ��̋����ł���ܖ���̖@�����肠���Ă݂悤�B���͑O�e�ɂāA�u�{�������v�Ɍ�����u�ܖ��嘦�C�s�v��u�S�Z�ӏ��v�Ɍ�����u�O�\�O�j�n�ܖ��咆�V�{瑁B���@�K�ܖ��n���G���j�ܖ��嘦�C�s��B�ܖ��n���{��A�C�s�n��瑖��v���̕\�����A�@�c�╶�u�]�J�a��Ԏ��i�ĕď��j�v�̈�i�������̂ł���A����ɂ͓����t���d�p����ܖ���̖@��̉e�����ɂ��邱�Ƃ��w�E�������A�����ł͂��̓����t�̉��߂ɂ��ď����ڂ����Љ�Ă݂����Ǝv���B
�@�܂��A���́u�]�J�a��Ԏ��v�̈�i���Ăю�肠���Ă݂�ƁA���̂Ƃ���ł���B
�@����ȂČܖ��ɂ��ƂւA�E�E�E���܌o�͓����̔@���A�όo���̈�̕������̌o�͗����̔@���B��̔ʎ�o�͐��h���A�،��o�͏n�h���A���ʋ`�o�Ɩ@�،o�Ɵ��όo�Ƃ͑��̂��Ƃ��B�����όo�͑��̂��Ƃ��A�@�،o�͌ܖ��̎�̔@���B���y��t�]�N��_�X���n���|�A�@�n�B�ȃe�J���������׃X��������m�B�ƃ��������������Ӎ݃������j�]�]�B���]�N�̃j�m���k�A�@�n�׃���혦���哙�]�]�B���߂͐����@�،o�͌ܖ��̒��ɂ͂��炸�B���߂̐S�͌ܖ��͎������₵�ȂӁA�����͌ܖ��̎��B�V��@�ɂ͓�̈ӂ���B��ɂ͉،��E�����E�ʎ�E���ρE�@�ؓ��N��햡��B���߂̐S�͎��O�Ɩ@�Ƃ�����ɂɂ���B���Ԃ̊w�ғ����݂̂�m���āA�@�،o�͌ܖ��̎�Ɛ\�X�@��ɖ��f�����ւɁA���@�ɂ��ڂ炩������B�J���J�A�قȂ�ǂ������~�Ȃ�Ɖ]�]�B����瑖�̐S�Ȃ�B���o�͌ܖ��A�@�،o�͌ܖ��̎�Ɛ\�X�@��͖{��̖@���B
�@����́u���όo�v���s�i�ɐ����������E�����E���h���E�n�h���E��햡�̌ܖ���V���t���،��E���܁E�����E�ʎ�E�@�؟��ς̌��ɔz�����Ĉ�㐹�������`�ɂ��āA�u���ʋ`�o�Ɩ@�،o�Ɵ��όo�Ƃ͑��̂��Ƃ��v�u�،��E�����E�ʎ�E���ρE�@�ؓ��N��햡��B���߂̐S�͎��O�Ɩ@�Ƃ�����ɂɂ���v�u�J���J�A�قȂ�ǂ������~�Ȃ�Ɖ]�]�B����瑖�̐S�Ȃ�v�Ƃ����߂ƁA�u���όo�͑��̂��Ƃ��A�@�،o�͌ܖ��̎�̔@���v�u���o�͌ܖ��A�@�،o�͌ܖ��̎�Ɛ\�X�@��͖{��̖@���v�Ƃ����߂ƍl��������߂�������Ă���B�������A�Ɩ�瑖{���ɔz������邱�Ƃ͂Ȃ����A�߂͂��Ƃ��������̖@�ؓƏ��𖾂����Ă��A�@�ؖ{��̒��������������̂ł͂Ȃ��̂ŁA���́u�]�J�a��Ԏ��v�̈�i�͂��̂܂܂ł͐��i�����E���������ƂȂ��Ă��܂��̂ł���B
�@������ɁA�����t�́u���l�����ڌ����v��
�ܖ���g�]���A�]�J���j�]�N�A���o�n�ܖ��A�@�،o�n�ܖ���m�\�X�@��n�{�嘦�@���B�����@��n�V�䖭�y�e���Z�ʃe��փg���s�������i���ԁA�w�Ҙ����m�X�N�i�V�]�]�B�����n�O�j�߃��o�V�e���j�ܖ���g�]�������X���̃j���㘦�{瑃g���^���B��Y�o�{��j�҈ȃe�����b�������ܖ���g�Z����B�������`��O���@���B��O�g�ҋv���{���������M�ʔV���{���혦�얳���@�@�،o�A�����ܖ����B�������@�@�،o�j���t�O�܉��혦�����������O�܉���n���`�ט������ܖ����{���B�ȃe�O��n�_�����탒�_���o�V�������ܖ����O���㘦�O���n��ʉ��탒�߃����n�E�Z�̃j���c�e�ߋ���q�j���O�����r��B�E�E�E���j��V�e�ܕS���o�j�_���o�V���p�V�e瑖剺�탒���X�v���{��������q����q�m�Җ��@�@�،o����B�]���������@�@�،o�m�ꕧ��E���ԍ����ܖ����惒���O�j���O�V�e���N�V���B�̃j�v���{�������ܖ����B�E�E�E�������������ܖ������O���㘦��F�������@��g���J��n���N�˃g�v���{������j�߃X���ԁA���փn�ߋ�����j���O瑖喳������B�̃j�v�����{�����ƃ��ܖ����B
�Əq�ׂāA�ܖ���̖{��Ƃ́u��O�̖@��v�ł���A�u�O�܉���v�ł���Ɩ������Ă���B���́u��O�̖@��v�Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��@�c���u�g���o�E���v��
���e��S��ցB�@�،o�g�^���O���L���P�e���X���j�����[���A�����א߂̎��L���O�c���l�B���@���@��͑�O�̖@���B���ԃj�e�@�N���m�����͐\�Z�Ƃ��A��O���n�s�\�T��B��O���@��͓V��E���y�E�`�����e���Z�g���V�����^�����w�B���F�A�����^�փV���@�V���j��B�܁X�S�͐���B
�Əq�ׂ�ꂽ��ŁA���̌�̉��߂ɂ͏���������A�����t�́u�@�،��`�v����Ɍ�����O�틳���i���O���o�Ɓu�@�،o�v�̏���𖾂������߂ɗ��Ă�ꂽ�����̗Z�s�Z�E�����̎n�I�s�n�I�E�t��̉��ߕs���߂̎O��j�̑�O�E�t��̉��ߕs���߂̑��ł���ƒf���Ă���B����́u�@�،o�v�{��̗O�o�i������ʕi�ɂ����ČܕS�o�_��栚g�ŋv���̖{�n��������A�t�i�ߑ��j��i�{���̒�q�j�̉��߂��������ꂽ���Ƃ��������A�����t�̏ꍇ�́u�O�܉���v�ł���Ƃ���������Ă���悤�ɁA�O�틳���̑��E�����̎n�I�����n�E�̎O�v�̈ӂ��܂�ŁA�O��o�_�̑�ʉ���ƌܕS�o�_�̋v������̉ߋ�������w�������Ă���B�������u��O�g�ҋv���{���������M�ʔV���{���혦�얳���@�@�،o�A�����ܖ����v�Ƃ���悤�ɁA�ŏI�I�ɂ͋v���{��������̓얳���@�@�،o���ܖ���ł���{��ł���Ɛ�����Ă���̂ŁA�����t�͉E���́u�]�J�a��Ԏ��v�̖��Ɍ�����u���o�͌ܖ��A�@�،o�͌ܖ��̎�v�̈ꕶ�ɂ��āA�u���o�͌ܖ��v�͒E�v�ɂ���瑖�A�u�@�،o�͌ܖ��̎�v�Ƃ͉���v�ɂ��Ė{��Ɨ��ĕ����Ă��邱�Ƃ��m����B
�@����܂ł̐����ŁA�����t�̌ܖ���̖@��Ƃ͒E�v瑖�������ĉ���v�{���I�ю��Ƃ����A�������E�{瑘_�ɑ��Ȃ�Ȃ����Ƃ��m���A����䂦�{�����v�z�����ɂ͌������Ƃ̂ł��Ȃ��d�v�f�ł��邱�Ƃ�������B����āA�Ⴆ�u���l�����ڌ����v�ɂ�
�q�]�A��藬�g�V�e���䏴�����σ��ꌾ�j���`�X�����L���V���@���B���A���`�j�]�N�A�q���r���o�n�ܖ��A�@�،o�n�ܖ���A�q�ρr����瑖�{��n�ۃX���@��������ʖ퉺�g�]�]����B�����������ψ�v�����`�L���V���A�V��X�V���V��X�V���B
�Ƃ���A�u�{��O�o���v����ɂ�
���̓V��{�喧�ӂ̌����~�͎��@���ɖ���Ȃ�̂ɋ�����ʖ퉺���ċ����͎O�܉���ܖ���Ȃ�B�ϐS�̏d�͖{���������M�ʂȂ�B
�Ƃ���悤�ɁA�@�c�╶�̒��ŋ����̎��ɂ��������̂����́u�]�J�a��Ԏ��v�̌ܖ���̖@��ł���Əq�ׂ��Ă���B�����āA���̋����ɑ�����ϐS������Ă���̂��u�l�M�ܕi���v��
�����l���O���~���n�ۃV�@���B�������O���~���@�،o�n�ۃV�@���B����瑖�{��n�s�X�@����B������ʖ�Ę��Z���j���e�S���V�ăX�B
�Ƃ̈�i�Ă���A������Ƃ��Ė{�����������̐M�ʂ𗧂Ă�Ƃ���A���ꂩ��q�ׂ悤�Ǝv���{�����v�z�̌��_�����肳��Ă���B
�@�Ȃ��A�ʏ�u�@�،o�v���ʌ����i�ɐ�����錻�݂̎l�M�ƖŌ�̌ܕi�͖{�嗬�ʕ��̏C�s�K�ʂĂ���A�@�c�́u�l�M�ܕi���v�ɂ����Ă��̌o�߂ɏڍׂ��Ɠ��Ȍ����������āA���@�̍s�ʂ���O�M���E������̖������ɒ�߂��Ă��邪�A�����t�́u�ܒ����v��
���]�A���{���������Z���ʃg�]�n�ݐ��������O��E�v���@�j���X�����{������B���\�������ȃe���v�����{�����ʈӃ�
���n���V�{�������A�Z�O�������E�ύs�E�����������j�j��B�����O�ʘ����j���Ȗ����ʃ��L�׃X�{���������Ӗm
��B�l�M�ܕi���j���e��O�M���ґ����{�嗧�s�V�����I�j�ȃe�����m�[�����׃X�{�嗧�s�V�{�Ӗm��B
�Ɛ����āA�ʏ�͏��Z�Ƃ����{�����̐��ӂ𖼎����ƒ�߂邽�߂ɁA���̕������u�l�M�ܕi���v�ɋ��߂Ă���B����͂Ď�v����Ă̖��@���{�����Ƃ�����`�ɂ����̂Ă��낤���A��������̖{�����v�z�����̈�v�f�Ă���B
�@�]���������́u���@���w�̌����v��9�́w�{���ʖ��_�̍l�@�x�ɂ����āA�����t�̋`�����̂悤�ɐ�����Ă���B
���ɐ��i�@�����i1384�`1464�j�̏��_������ɁA�E�E�E�ܕS�o�_�J�Ԃ��̕�g�����̏�ɋ��̏d�̖{�������咣���Ă���B����͗v��Ζ{�����Ď�Ƃ͖{�@���̕�F���{�����ɐ敧�̖{�ʂ̖@���Ď킷��B�v���̓����Ɩ��@�̏��Ƃ͖{���Ď�̎��Ă���A�{�ʂ̕��̎��ɒE�v�����߂�B�{����F�͓��@�A�{�ʕ��͎ߑ��Ă��āA���̎O�v���J�Ԃ����̂ł���B�����u���V���v�Ɂu�ߑ��{�����̏C�s�͒n�O�s��B�̂Ɉ�؏O���̂Ď�̎��͒n�O�ƌ���A���E�̎��͎ߑ��ƌ���ʂւ�B�O���E�v�̎��͎ߑ��Ɣq�����A����̎��͒n�O�ƒm�����B�^���̉���̍��{�͖{�����Ȃ�ׂ��B�E�E�E�ߑ��ꕧ�̗��v�Ȃ�v�Ƃ����̂ł���B
�@�O�e�ł��G��A���e�ł��܂��q�ׂ�ς���ł��邪�A�����嗬�̖{�����v�z�Ɠ����t�̂���Ƃł͂��Ȃ�̑��ق�����A����m�ɂ��邱�Ƃ͈�̃e�[�}�Ă��邪�A���͂��̗��҂̖{�����v�z�ɋ��ʂ��镔���������A���ꂪ�����t�̋��w�ɂ����Ăǂ̂悤�ɍ\�z����čs���̂��A�l�@���Ă݂悤�Ǝv���B����͌�����������嗬���w�̕����ɂ͂��̍\�z�̂��܂�������Ă��Ȃ����ƁA�����Ă����炭�����t�̋��w���w�K�����̖{�����v�z�𐬌`�����Ă��낤�����嗬���w�̏ꍇ�A�����t�̋��w�I�w�͂����̂܂p���A���̏�Ė嗬�Ǝ��̗v�f�荞��Đ����Ɏ������̂Ɛ�������邱�Ɠ��̗��R�Ɋ�Â���ƂĂ���B
�@���̖{�����v�z�̋��ʕ�����P�������Ď����ƁA
�E�v���قǂ����{�ʖ��̎ߑ��ɑ��āA�{�����̏�s��F����؏O���ɂĎ킵�A�Ō㖖�@�ɂ͏�s��F�̌�g�Ă�����@���l���o�����ĉ���̋���ƂȂ�A�Ƃ����l���B
�ƂȂ�B���̏ꍇ�A�ŏ��́u�E�v���قǂ����{�ʖ��̎ߑ��v�ƍŌ�́u�Ō㖖�@�ɂ͏�s��F�̌�g�ł�����@���l���o�����ĉ���̋���ƂȂ�v�̓�̒�`�́A�����悻�V��߂�@�c�╶�̒���������o�����邪�A���̊ԂɌ�����u�{�����̏�s��F����؏O���ɂĎ킵�v�Ƃ�����`�ɂ��ẮA������ؖ����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��ɓ���B�����āA���̂悤�ȍl�������藧���߂ɂ́A�@�c�̋��`�̌n�ɖ��m�ɂ͎�����Ă��Ȃ����̎O���̓�����������K�v������ƍl������B�@�͖{�ʖ��ߑ��̖{��������s��F�ł��邱�ƁA�A�͖{������s��F����؏O���ɉ��킷�邱�ƁA�����ćB�͋v�����킪�{�����̉���ł��邱�ƁA�̎O�ł���B
�@
�@�{�ʖ��ߑ��̖{��������s��F�ł��邱��
�@�{�����Ƃ͋v���̖{�ʕ�����ߑ��̖{���ɂ����鎩�s�̈��̂��ƂŁA�u�@�،o�v�@�����ʕi�́u��{�s��F���E���������E���P���s�v�̈ꕶ�Ɋ�Â����A�o���ɂ͂������̂��ƁA�V��E���y�̎ߋ`�ɂ����̕�F���͓��肳��Ă��Ȃ��B����A��s��F�́u�@�،o�v�]�n�O�o�i�ɂĎߑ��̏����ɉ����đ�n���o�������n�O�̕�F�̏��ł���A�n�O�̕�F�͖{�ʂ̎ߑ����ŏ��ɋ���������q�i�ő��j�ł���Ƃ��납��{���̕�F�Ƃ��Ă�āA�{��\���̑掵�E�{�ő����Ƃ����B����āA�o����V��߂̒��ł͏�s��F�͂����܂ł��{�ʖ��ߑ��̑��̒�q�ł����āA�ߑ��̖{�������̖��̂���s��F�ł���Ƃ͂ǂ��ɂ�������Ă��Ȃ��̂ł���B
�@����ǂ��A���̖{��������s��F�̋`�����藧���Ȃ�����{�����v�z���`�����꓾�Ȃ����Ƃ͉������薾�炩�ł��邪�A���̋`�ɑ�������t�̐�����������Ǝ��̂Ƃ���ł���B�܂��A�u���V���v��l�ɂ�
���j��V�e��g�j�_�n�V���A�{�����n�n�O����F��B�{�������o�o�j��{�s��F���m���P���B�v���{�n����F�A�]���������V�V�B�l��F�T���Z���P������F�n�ꓯ�j�n�O����F��B�̃j�ߑ��{�����������n�O����F�m���e���@�@�،o���C�s�V�ʃw���B���V�e�O���������ʘ��s�n�F�i�n�O���C�s��B��؏O���ŏ����혦���n�n�O�m�����A��؏O�����E�����n�{�ʖ����ߑ��m���V�ʃw���B�E�E�E���c�A�{���{�ʘ������߃X�����A�ϐS�{�����j�{���{�ʓ��������e���E�����E�m�߃V�ʃw���B�{������E�m���^���B�����j���{�ʖ{�����������N���A��{�s��F���m�����o�n�O��E�m��F�m�߃V�ʃw���B�ߑ����{�����m�n�O��F�m��̖�B��X�ʕ��j
�Ƃ���A���Ɂu�{��O�o���v����ɂ�
���̖{�ő��͖{���ߑ����������̓����ő��Ȃ�B�����ő��Ƃ́u�\�E��X�������j���~���v�Ɖ]�Ӌ�@�E�̕ӂȂ�B���̋�@�E�̕ӂ𑍍����Ė{�����Ɖ]�ӁB
�ƌ����A�u���`���������i�꒟���j�v�ɂ�
����ΎO���{�L�Ƃ��Ĉ�؏O�����E�̏I�͖{�ʂ̎ߑ��ƌ���A��؏O���ŏ�����̎n�͖{������s���ƌ��͂�A�ߋ��v���ƖŌ㖖�@�Ƃɍŏ�����𐬂���Ȃ�B���Ď��ʕi�ɖ{���{�ʂ�����{�������Ή�{�s��F�����������]�]�B�����̗O�o�i�ɂ��Ēn�O���Ȃċv���̏���F�ƂȂ���ߕL�āA���ʕi�ɂ��ċv���̐̕�F�����s���Ƃ�����F�́A�{���n�O�̕�F�̏C�s���ߑ����{�����̎��s���Ƃ������Ȃ�B
�Əq�ׂ��Ă���B
�@�ŏ��́u���V���v�̒��ɂ́u�ϐS�{�����v�̓�ӏ��̕��߂��ؕ��Ƃ��Ďw������Ă��邪�A��͏\�E��
��̕����u�@�،o�v�̒����璊�o���Ă������
���ʕi�j�]�N�@�N�����䐬���V�e����ߗ��r��j�v���i���B�������ʈ��m�_����Z�j�V�e�s�ŃZ�B�����P�j�q��{�s�V�e��F�������������Z�V�������P���^�s�L�B���{�Z���㘦���j���]�]�B���o���n���E�����E��B
�ł���A������͎ߑ����ʂ̌�������������@�������邱�Ƃɂ��ϐS�����A����|�𖾂�������ɁA�}�v�S����̖{���{�ʂ�������
���ʕi�j�]�N�R��������ߗ����ʖ��ӕS�疜���ߗR�������]�]�B�䓙�J�ȐS���ߑ��n�ܕS�o�_�T���������O�g�j�V�e���n���Õ���B�o�j�]�N�@��{�s��F���@���������@���P���s�@���{�㐔���]�]�B�䓙�J�ȐS����F����B�n�O��E����F�n�ȐS���ߑ���������B��Z�n�@�V�������������҃n�������b���@�����c�t���ő��@��������b�n�_���c�@�������@�m�����q���b���i���J��B��s�E���Ӎs�E��s�E�����s���n�䓙�͌ȐS����F��B
�Ƃ�����i�ł���B�����ɂ͖{��������s��F�Ƃ����X�g���[�g�Ȗ����͌����Ȃ����A�{���{�ʂ̌o���������āu���E�����E�v�Ɓu�䓙�J�ȐS����F����B�n�O��E����F�n�ȐS���ߑ����ő���B�E�E�E��s�E���Ӎs�E��s�E�����s���n�䓙�J�ȐS����F��v�Ǝ������@�c�̉��߂ɁA�u�ő�����E�����{�����v�Ƃ�����E��}��Ƃ����ő����{�����Ƃ����`���������ꂽ���ɁA�͂��߂Ďߑ����ő������s��F���{�����̕�F�ł���Ƃ����{���̒�`�����藧���܂��A�E�́u�{��O�o���v�̈ꕶ����m�邱�Ƃ��ł���B�����āA������āA�ߑ����u��{�s��F���v�̖{�������ɂ͖{����s��F�̏C�s���s����|���u���`���������v�̕��ɂ͖�������Ă���̂ł���B
�A��s��F����؏O���ɉ��킷�邱��
�@�O���̓�ւ́A�o�߂ɂ͎ߑ��̒�q�Ƃ�����s��F���ߑ��{�����̕�F�ł��肤�邩�Ƃ������ł������A����͂��̏�s��F���O���ɉ�����قǂ����͗p���������邩�ۂ��Ƃ������ł���B����ɂ��āA�����t�́u�@�ؓV�䗼�@���i�l�����j�v��
���ɁA�l�ɖĂ����_���A�l�Ƃ͖{�唪�i��s�v�t�����܂���s��F�Ȃ�B���̕�F�́A�O�������ɏn�E�̍��ɗ��炸�B�v������̍��ƍ����{�唪�i���@���폊���̍��Ƃɗ��Ղ��āA�O�k�E�A�ʂ��Ă͖��@���l�̉���̏����Ȃ�B��c���ɉ]���A�u�n�O��E�̑��F�́i�����j�O�k���E�̏O���̍ŏ�����̕�F�Ȃ�v�Ɖ]����B�]��瑒��̕��E��F�͋ߐ��n�o�ɂ��Ė���Ȃ�̂ɁA�����̕��킱��Ȃ��B�v���̎ߑ��E��s�́A���������̕���q���ꂠ��B�̂Ɉ�؏O���̍ŏ�����̎�t�e�Ȃ�B
�Ƃ���A�@�c�́i�]�J�l���a���䏑�i��c���j�v�̈ꕶ�Ɋ�Â��ď�s��F���v������Ɩ��@����������ǂ�A���@����ɂ��Ă͂��̌�g������@���l�������̖}�v�ɉ��킷��|����������Ă���B
�@������ɁA���́u�]�J�����a���䏑�v�̋�������Ǝ��̂Ƃ���ł���B
�����j�n�O���E�����F�A��j�n�Z�X���R�g���O�k���E�j���o���i���B�j�j�n���e���ߑ��j�����v���ߗ������S����q�i���B�O�j�n�O�k���E���O�����ŏ����혦��F��B�@�L���������h���V���֒��߃Z���������F�j�B
�@����́A�ߑ�������E����瑉��E�����̏����F�������u���āA�킴�킴�n�O�̕�F�������o���Č��v�t�����A�Ō㖖�@�̍O�ʂ��䂾�˂����R���@�c���O�_�����グ�����̂ł���A�����t���ؕ��Ƃ��Ĉ������Ă���̂́A���̑�O�_�ڂł���B�����āA�O�_�̓��A���_�͒n�O�̕�F�����̛O�k���E�ɋɂ߂Ē������ԋ��Z���Ă��邱�ƁA���_�͎ߑ����v���̉ߋ����ɏ��߂Ĕ��S����������]�Ă�����q�ł��邱�ƂƁA���ɑf���ɈӖ�������̂ɑ��āA���̑�O�Ԗڂ́u�O�j�n�O�k���E���O�����ŏ����혦��F��v�̈ꕶ�ɂ͎��͓�ʂ�̈Ӗ����l���邱�Ƃ��ł���̂ł���B
�@���Ƃ��A���a9�N�i1934�j����16�N�ɂ����ĕ��y�����X���犧�s���ꂽ�u���@���l�╶�S�W�u�`�i�ʏ́E���u�j�v�̒ʎ߂ɂ́A�u�O�ɂ͂��̛O�k���E�̏O���ɍŏ��ɐ����̎�����낵�ĉ����ꂵ��F�ł���v�Ƃ���A�n�O�̕�F�����߂ďO���Ɏ���������Ɖ��߂���Ă���B����ɑ��āA���̑O�̏��a6�N�ɏ@�c650�����̋L�O���Ƃ̈�Ƃ��ė���Ђ���o���ꂽ�u���@���l��╶�u�`�i�ʏ́E���u�j�v
�̍u�`�ɂ́A�u�O�ɂ͂��̛O�k���E�̏O���̒��ł́A�ŏ��ɐ����̎��A����ꂽ��F�ł���v�ƌ����A�O�k���E�̏O���̒��ň�Ԏn�߂Ɂi�ߑ����j��������ꂽ�̂��n�O�̕�F�ł���Ɛ�������Ă���B
�@���̂悤�ɁA�قƂ�Ǔ������ɏo���ꂽ���ނ̈╶�u�`�Ɂu�O���ɏ��߂ĉ��킵���n�O�̕�F�v�Ɓu�O���̒��ōŏ��ɉ�������n�O�̕�F�v�Ƃ����A�S�����Ⴗ����߂�������Ă���A���{�����̓����ł���Ӗ��̎��Â炳����`���āA����قǂɂ��́u�]�J�l���a���䏑�v�̈ꕶ�̈����͂ނ������̂ł���B�ł��V������\�I�ȉ��߂Ƃ��ĕ���4�N�i1992�j����8�N�ɂ����ďt�H�Ђ�芧�s���ꂽ�u���@���l�S�W�v�̌�����ɂ́A�u�O�ɂ͂��̛O�k���E�̒��ł͍ŏ��ɕ���������ꂽ��F�ł���v�Ƃ���A�E��2�̉��߂̓��A�u���u�v�̉������n�O�̕�F�Ƃ������߂��̗p����Ă���A���邢�͂��ꂪ�����_�ł̈�ʓI�ȉ��߂Ƃ���Ă���̂����m��Ȃ��B���ہA���̈ꕶ��n�O�̕�F���O���ɍŏ����킷��Ƃ����ӂɎ�����ꍇ�A���̏@�c�╶�̒��ɂ��̂悤�ȋL�q�͈�Ȃ��A���̈ꕶ���S���ǐ₵�����̂ƂȂ��Ă��܂����ʂƂȂ�B
�@����������A�������ŏ��ɐ����̎�����킳�ꂽ��F�Ɖ��߂����ꍇ�A���̒��O�ɋL����Ă���v���̐̂Ɏߑ������߂Ĕ��S����������]���Ă����q�̕�F�Ƃ������R�ƁA���܂�Ӗ��̈��Ȃ����R���d�˂邱�ƂƂȂ��Ă��܂��������邪�A�ǂ��ł��낤���B�Ƃ�����A�����t�͂��́u�]�J�l���a���䏑�v�́u�O��n�O�k���E���O�����ŏ����혦��F��v�Ƃ��āA��s��F����؏O���ɉ�����قǂ�����F�ł���Ƃ����`���咣�����̂ł���B
�B�v�����킪�{�����̉���ł��邱��
�@���̎O�ڂ̓��ł���v�����킪�{��������ł��邱�Ƃɂ��ẮA�O�e�ɂē����t�́u�\�O�ⓚ���v���E�ݐ����펖�̈�߂������Ďt�̈ӌ����܂Ƃ߂Ă݂��̂ŁA���͂�����Čf���Ă݂����B
�t�́A�u�@�،o�v�̌o���ɂ͏�s���̖{����F�ɑ���ߑ��̖{�ʉ��킵��������Ă��Ȃ����A�O�Ɏ����@�c�╶�̒��ɂ�����{�����v�z�`���̗v�f�̇B�Ƃ��āu���@�،o�v�̒�����E���グ���u����L�v����́u�{���ʓ��V�v�̕��Ɉ˂�A�V��E���y�͉��킪�{���E�{�ʂɘj��Ǝ߂��Ă��邪�A�����̓V��w�ғ��͉���͖{�ʂɌ���ƌ�����咣�����Ă���Ƃ����B�������A����̖{�`�͈��ʂ̕�F�E�ɂĂȂ����̂ł���A�܂�����͐l�V�ɑ��Ę_������̂ł���̂ɁA�{�ʂ̏O���͎O�悾���Ől�V�̋@�����Ȃ��̂ʼn���̋`�����������A����䂦�v������͖{�����Ɍ���ƌ��_����Ă���B�����āA�Ō�ɓ��@�̈ӂƂ��Ă͖{�ʂ�{���ɐۂ��A�{�����̏�s��F���{������і��@�̏O���ɍŏ�������Ȃ����A���E�̎��͏�s���{������{�ʂɈڂ��ċv���̎ߑ��ƂȂ�E�v���Ȃ��A�Ɛ�������Ă���B
�@�E�ɂ�����悤�ɁA���̖{��������̖��Ɋւ��Ắu�@�ؕ���L�v����́u�{���ʓ��V�v�̈ꕶ������A���̕������߂��钆�ň��ʂ̂����A�{�ʂ����{���Ƀ|�C���g�����邱�Ƃ��������Ƃ��ł���悢�̂ł��邪��A��r�I�������₷�����ł���Ƃ�����B�����āA���́u�{���ʓ��V�v�̌�ɂ��Ắu�{��O�o���v������
�����{���ɉ��킵�{�ʂɒE�v�����Ė{���ς���ɖ��{���̒n�O�Ɛ����Ď�������Ɖ]�ӂׂ����A�������āu�{���ʎ�v�Ɖ]�ӂȂ�B
�Ƃ���A�{�����Ɉ�x���킵�A�{�ʂ̖Ō�ɂ܂��{���̕�F�ƂȂ��ĉ��킷��̂��u�{���ʎ�v�̈ӂł���A�ƉE�Ƃ͏��ق���������قǂ�����Ă���B���̌�҂̐����͂��ꂾ���ł͈Ӗ���������ɂ����̂ŁA�����t���{���{�ʂ̖{���S�̂���ʂ�����s��������i���u�{��O�o���v����Ɍ�����̂ŁA�����t�̖{������_�̑S�̂𗝉����邽�߂ɂ��A���X�������A���͂���������Č������B
�ߋ����X�ܕS���o�̓����ɑO������B���̖{���ϖ��Ō㈫���ɖ{���������M�s�̕�F����B���̎��̎ߑ��͒P�ɖ}�v�ɂĈ�O�̐M�S���Ȃđ��̎t�̕�F����q�̎ߑ��A�@�،o�����ē얳���@�@�،o�ƌ��ɏ��ʂЂāA�u��O�M���n�ґ������{�嗧�s���V��v�Ɖ]�ւ閼���̐M�҂Ɛ��ď��߂ĉ���𐬂���Ȃ�B���̎��ɉ]���A�{�����m�Җ{���j���V�e���S���s�V��F�����������C�X�����i�����B���̖{�����̎��͎ߑ����Ō㈫���̉䓙���@���}�v�̐M�҂Ȃ�B�����A�����ύs�����ɋ��Z���ď��߂āu��{�s��F���v���鎞�A���̏O����������u�����O���v�͏�s���̐o���̕�F�Ȃ�B�̂ɖ{���̎ߑ��͕��A�{���̏�s�͎q�Ȃ�B�ߑ���s�̕��q�V������Ȃ�B���̎��A�ߑ��̐M�s�̌�����얳���@�@�،o�Ə��֏o���ď�s�̌���Ɉڂ��Ď����ށB�������s���̋v������Ɩ����B�`�̋�ɉ]���A������J��q�i���A���O��J�@���ȃg���[�L�i�����]�ւ�B�L�Ɂu���j�]�e�����������X�v�Ɖ]�ЁA�u�q�O�����@�v�Ɖ]�ւ�͍��̎��̂��ƂȂ�B���̎����{�����̎ߑ��A�Z�O�Z�㓙���揸�i���Ė{�ʖ��̈ʂɓo�鎞�A�����̏O����s���̋�@�E�Ȃ�B�L�Ɂu�{���ʎ�v�Ǝ߂��ʂւ�B�����̔@���{���{�ʎ�����v�����̌�A�ߑ��{���ϖ������ӁB������ߋ����œ������ςƉ]�ӁB���{���ϖ��̖Ō㏥�����Ώ�s�ɕt���B��s�����̏O�ɁA����s�A�얳���@�@�،o�ƌ������ď����̏O�ɏ��ւ��߂ď��߂ĉ���𐬂��B�ߗ����ԑO�l瑖�ɒ��n���Ĉ�i�ɒE���L��ʉ]�]�B
�@�����ɂ͖{���{�ʂ̖{���𒆐S�Ƃ��������̑����ʎ��I�ɏq�ׂ��Ă���A�������}�Ŏ����Ύ��̒ʂ�ɂȂ�B
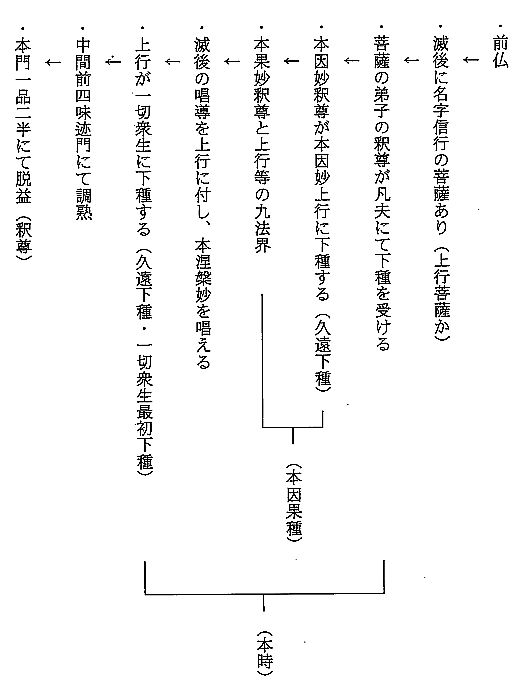
�@�ŏ��ɑO�����o�ꂷ�邪�A���ꂪ��g���̖��n���I�̖�����Z��������߂ɓ����t���Ǝ��ɐݒ肵���ܕS�o�_�̍ی��Ȃ��J��Ԃ��ƕ]�����u�J�Ԃ����{�_�v��������ł���B���̑O���̖Ō�ɖ������̕�F�i��s��F���j���o�����A���̒�q�̎ߑ����}�v�̎��ɉ�����Ė������̐M�҂ƂȂ�B���̎ߑ����{�����ɖ{���̏�s�ɋv�����킵�A���̌�{�ʖ��ߑ��Ə�s���̋�@�E�ƂȂ邪�A���̈�A�̏�����߂����̂��u�{���ʎ�v�̕��ł���Ƃ����B�����āA�{�ʎߑ����Ō㏥������s�ɕt���Đl�ł��A���x�͖{���̏�s����؏O���ɍŏ�����i�v������j���āA���̌�͒��n����E�v�ւƎ���Ƃ��������ł���B���ĕ�����悤�ɁA�����ł͏�s��F���{�����̎ߑ����鉺��ƁA�ߑ��Ō�ɏ�s��F����؏O���ɂقǂ�������ƁA��̋v�����킪�ݒ肳��Ă���B
�@�O�������Ɍ����悤�ɁA�����t�̐����͔��ɏڍׂł���A���ꂪ�Ⴆ�u�{��O�o���v113���ł́u�@�،o�v28�i�S�̂ɁA�܂��u�J瑌��{�@�v�W�v66���ł͓V��@�_�`�̏@�v�Z��65�ӂɂ��āA���ꂼ�ꂻ�̖{�����v�z����щ���_���琸�k�Ȏߋ`���������Ă���A���̋��w�I�ȓw�͂ɂ͂����h���̑��͂Ȃ��B
�@�����āA�����ōl����ׂ����Ƃ́A�����t�ɂ�������嗬�ɂ���A�ǂ����Ă��̂悤�ȑ�ςȎ葱�����o�Ă܂ł��{�����v�z�ȂǂƂ������̂��\�z����čs���˂Ȃ�Ȃ������̂��Ƃ������ł���B����ɂ��Ď��́A��s��F�̎��o�̉��ɕs�y��F�̍s�O���p���Ȃ���A���@�̏O���ɖ��@���̗v�@�����킵�ĉ��Ƃ����������߂悤�Ƃ���čs�����@�c�̐M�s�I�w�͂Ƃ������̂��ǂ̂悤�Ɍp�����邩�A�����Ă��̓w�͂̈Ӌ`���I���E�ς���ї��j�ς̒��ɂ����Ɉʒu�Â��čs�����A�����^���ɍl���͍��������̌��ʂł͂Ȃ��������Ǝv���̂ł���B
�@����āA�Ⴆ�Γ����t�̋��w�ɑ��ẮA���̌��{�_���ŏI�I�Ɏߑ��̋v���������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��u�J�Ԃ����{�_�v�ł���A�܂����̖{瑘_�ɑ��Ă������I�Ɏ����ٖ̈ڂ������ꂸ�ɑ䓖�@�̊Ԃɑ��Ă��铙�Ƃ����ᔻ�������������Ă��邪�A�����͂����܂ł��`���I�Ȉ�̋��w�I�ϓ_����̔ᔻ�ł����āA����ɂ���ē����t�̋��w�̉��l������������Ƃ�����ł͂Ȃ��B�ނ���A���Ƃ��_���I�ɂ͑����̔j�]������Ȃ�����A�@�c���@�̏@���I��M�Ȃ����ƂȂ��A�悭���̐M�̌n���\�z���Ă������Ƃ����_�ł͑������|���Ă���A�����炭�@�w�Ƃ����w��̍ł��傫�ȉۑ�����̕ӂ�ɂ�����̂Ǝv����B
�@�Ō�ɁA�����嗬�̋`�ɑ�����̂Ǝv����ᔻ�����Ȃ��Ȃ�������t�̒���̒��Ɍ�����̂ŁA���e�I�ɏd��������̂��܂߂Ĉ�ʂ�E�o���Ă������B�܂��A�u�{��O�o���v��3��
�A���ߑ��͖{�ʂ��Ƃ̖����A��s�͓��o���Ƃ̖����A���@�͐l�E�̖����Ȃ�B�̂ɖ����Ɩ����Ƃ̕ӂ�����ĈՍs�̖{���Ɛ����A�Սs�̎l�˂�k���B�R��ɖ��@�@�،o�A�ߑ��A��s�́A���@��m�䓙���ׂ߂ɂ͖{���Ȃ�B�{���̎߉ޏ�s���Α����������ē��@��m�̑����v���{���Ɉ��u����鎖�A�x�m�嗬�̖@���Ȃ�B�����͕T���̕T�A���ꑦ���ɑ�掖@�Ȃ�B���䏴�ɔw�����ƂȂ�B
�u���v��5�ɂ�
�����̔@���o�|��قւ��鏔�@�؏@�̒��ɁA�]��ɖ{瑏�����]�Љ߂��āA�߉ޑ���͍ݐ��̖{���Ȃ�̂ɁA�ؑ��ɑ���ׂ��炸�Ɖ]�ЁA��s��F�Ɠ��@��m�Ƃ͖Ō�̖{���Ȃ�̂ɁA�ؑ��ɑ���ׂ��Ɖ]�ӑ�ƌ���掖@�A�����ɂ���B
�u���v��8�ɂ�
�����̔@���̐[�|��m�炸���āA���͓����̖@�؏@�̈�嗬�̒��ɁA�{瑏���Ɖ]�āA�����ߑ���s�Ɠ��@��m�Ƃ��ȕʂ��āA�ߑ���s�̖ؑ����Α��炸�A���@��m�v��̖ؑ���Đ��ʂ̖{���ƈׂ����Ƃ��ꂠ��B�����ƌ��Ȃ�A��掖@�Ȃ�B�V��p�ӂׂ��炸�B���̂��ƈȂĂ̊O�̌y�G�ɂ��āA���䏴�̑�|�Ɉ�ӊԁA�V��j�����̂Ȃ�]�]
�Ƃ��ꂼ��L����Ă���B����́A�����嗬�̖@���Ƃ��Ďߑ��E��s�̖ؑ��ł͂Ȃ����@���l�̖ؑ��Đ��ʂ̖{���Ƃ��Ĉ��u���邱�Ƃւ̔ᔻ�ł��邪�A�����ɂ͓��@�͏�s�̌�g�Ƃ͌����Ȃ���A�����������ł���R���鍷�ʂ����邱�ƁA���@�{���͖{瑏�������������߂��������ʂł���A���䏴�̎|�ɔw����掖@�̖@�`�ł��邱�Ƃ��w�E����Ă���B
�@���ɁA�u�\�O�ⓚ���v��ɂ�
�A���{�嗬�ʘ��s�l�s�g��瑖嘦�]�@�]�����]�j�ҁA�፶�l�j���S��e�n�A�����@�������㏔�䏴����̃e�e�L������v�����V�̃e�e瑖僒��{�僒���g��V��Ӄ����Ӊ߃V�^���嗬�L�V�B�{��g�^瑖听�V�u�����n�s����瑖僒�A���n�s���u�Z�؉�����������l�L�V�B�����s�s�L�B�����s�֘������B�A�������c�V���Ӄj�n�׃��j�V�e�j���i���g�������n�s�w���`�j�����L�V��B�R���j���㖳�q�j�V�e�s���t���Ӄ��A���^�����n����������i�����n���i���U���y�A����k���j���V�A�ߍƉ]�]
�u�{��O�o���v���R�ɂ�
���̎|��قւ���@�؏@�A���䏴�̏@�|�ɔw�ЂĈ����瑖���̂āA���͗��v��p�ЂĈ���ɍL�s���̂�嗬���V�ꂠ��B�����͊F���䏴�Ɉ�Б�|�ɔw���҂�掂ɓ����B�E�E�E����v��j���ׂߔj���̓��A瑖���u������b�B���̎|���鏴�Ɍ��ւ���B���F�j�����҂��Đ��`�ƐS���A����v�ɖ��ӟb�B
�ƌ�����B�������瑖�s�ǂ���ɑΏۂɂȂ��Ă���̂œ����嗬�Ƃ͌���Ȃ����A���̒��ɍL�s����ꕔ�̕s���u�ɑ���ᔻ�������A���ꂪ�u�L�����̂Ăėv�����v�Ƃ����@�c�̈ӂ������S�����������ʂł���Ǝw�E����Ă���B
�@���̂悤�ɁA�����t�̓����嗬�ᔻ����狭�`�̖{瑏���`�Ɋ�Â��s�����E�s���u�̉��V�Ɍ������Ă���A���̓��ۓ��ɂ��Ă͎��e�ŐG�ꂽ���Ǝv�����A���̉��V���嗬�̗��j�ɑ��Ď��S���͂̋����ɂ��Ă͑O�e�Ɍ��y�����ʂ�ł���B
�@���͂���܂œ����嗬�̖{�����v�z����{�I�Ɍc�і[�����t�̋��w�̋����e�����ɐ����������̂Ɨ\�����A���̑O��̏�Ŗ{�e�̑�P�͂ɂ����Ă��嗬���ɂ����鋳�w�I�t�����l�@���Ă݂����A���̑O��������������ʂƂ͂Ȃ�Ȃ������B�܂��A��Q�͂ł����̑O��̏�ɁA�����t���ǂ̂悤�ɓ�ւ��������Ė{�����v�z���`�����čs�������A���̋�̓I�ȗl�q���l�@���Ă݂��B
�@����ǂ������ɁA���̓����t����̉e���ȊO�ɂ������嗬�̖{�����v�z�����̗v�f�͂������̂łȂ����A�Ƃ����͍l���Ă���B���Ƃ��A�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗����������ɂ͊m���ɓ����t�̋��w�̍��Ղ��F�߂�����̂́A�S�̂����̉e�����ɂ���Ƃ��������ł͂Ȃ��B
�@����āA���e�ł͂������̕������������Ă��̓��̉\����������Ƌ��ɁA�����嗬���t�̓����t�̋��w�ւ̔ᔻ����肠���āA���ٖ̈ڂ̗l�q���������Ă݂����Ǝv���B
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i3�j
�ڎ�
��2�́@���������ɂ�����E������h�̌𗬂ɂ���
��3�́@�L���@���C�t�̖{�����v�z�ᔻ�Ǝߑ��{���`�@�@ ���̏œ_
�@�A �����t�̌���
�@�B ���C�t�̌���
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@�@�@���߂�
�@�{�e�́u�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i�P�j����сu���i�Q�j�v���āA�����嗬���w�̎和�̈�ł���{�����z�����j�I�ɂǂ̂悤�Ɍ`������Ă������Ƃ������ӎ��̂��ƂɁA�����̍l�@�ɕK�v�ȏ��ޗ�����āA�����̘_�l�̊o���ɂ��悤�Ƃ������̂ł���B
�@���͂���܂ł̑O2�e�ɂ����āA�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗�������������ɁA���L�E�����E���v��3�t�̖{�����v�z�̊T����A�����ւ̎v�z�I�e�����F�Z���\�z�����c�W�[�����t�̓��v�z�̈�[�����������A����ɏ@�c�ӔN����̓����嗬�̗��j�I�ȗ���̒��Ɍ�����{�����v�z�`���ւ̓����Ɉ�ʂ�G��Ă݂��B
�@�{�e�ł͂��̂悤�ȗ�����Ȃ���A�܂��������_�����炵�āA��1�͂ł͓����嗬�Ǝ��̋��`����щ��V�ł�����@�{���`���ǂ̂悤�ȉߒ��Ő������������l�@���A���`���{�����v�z�̌`���ɂ����Ȃ�_�@��^�������A��l���Ă݂����B���ɁA���͂���܂ł̌��ʂ��̌��ʂƂ��āA1400�N�ォ��1500�N��ɂ����Ă̋��s����ѓ��E�a���Ƃ����E���n���{�����v�z�`���̎�v����Ɛݒ肷��Ɏ��������A�����ł͂��̒����̎j�����瓖���̖{瑏���h���嗬�̌𗬂̂��肳�܂ɐG��āA���ꂪ�{�����v�z�̌`���ɂǂ̂悤�Ȗ����������������2�͂ŏq�ׂĂ݂�B�����āA���̂悤�ȋE���̗��j�I���ēo�ꂵ���̂��L���@���C�t�ł��邪�A���̓��C�t���{�����v�z�ᔻ�̎�v�_�Ɏw�E�����ݐ�����̖��ƁA�t�̎ߑ��{���`�̓��e�ɂ��āA��������3�͂Ř_���Ă݂����B
�@���̓��@�{���`�ɂ��ẮA�O�́u�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���ɖ₷��o���i�P�j�̒��ŁA�@�c�Ō���ɂ����铯�v�z�`���̗v�f�Ƃ��āA�@�c��e�{���`�Ɠ�i���u�`�Ƃ������V�ɒ��ӂ��K�v�ł��邱�Ƃ��w�E���A���̘_���I�ȗ��t���Ƃ��Ă̖{�����v�z�̌`���Ƃ����ȒP�ȋؓ��̗\�z�������������A���͏@�c��e�{���`����@�{���`�ƌĂщ��߁A���̋K����u���@���l�̌�e��������O�Ɉ��u���āA�ߑ�����юߑ����ł͂Ȃ��A���@���l��{���Ƃ��ĐM�̒��S�ɒu���Ă������Ƃ����l���v�Ɩ���������ŁA���̐����Ɩ{�����v�z�Ƃ̊֘A��_���Ă݂�B�Ȃ��A���̌o�߂̒��ŁA�\�E��䶗��{���̗�����@�c�ӔN�̎v�z�I�ȉc�ׂɂ��ẮA�����]�ڂٍ̐e�Əd�����镔���������Ȃ�Ɨ\�z����邪�A���l�@�̕K�R�Ƃ������Ƃł��G�Ƃ������������Ǝv���B
�@�ʏ�A��e�Ƃ͐_����M�l�̉摜��ؑ����������A���͓��@���l�̖ؑ�����ъG���̈ӂɌ��肵�ėp����B���@���l�̌�e���Ƃ����A��ʂɍł��悭�m���Ă���̂́A�r��{�厛�c�t���Ɍ��삳���@�c������̐������N�i1228�j�ɑ������ꂽ��e���ł��낤�B����̖������玘�]������t�Ƙ@�؈�苗������t�����ƂȂ�A�����炭�卑��苗����N�t��r��@�����̎����ɂ���đ������ꂽ���̂ł��邪�A���̓����̈�́A�ꌩ���ĔF�߂��邻�̋�ې��ł���B���ɁA���̖ʎ����͂܂��ƂɃ��A���ŁA���O�̏@�c�͊m���ɂ��̂悤�ł������낤�ƁA�N�l�����[���������ɂ����Ȃ��͂������Ɋ�������B
�@���ʁA���̂悤�Ȓ������̋�ۉ��́A���A���Y����M���Ƃ��镐�m�K���������ɏA�������q����Ƃ����A���セ�̂��̂����ʎ����_�̕\���Ɛ�������邪�A����ɑ��āA�u���@��c�t�Ƌ��w�c�t�M�x�̌n�������ǂ�A���̐M�V��③�`���ɂ���āA�c�t�ɂ悹��M�̐S�ӂ𖾂炩�Ɂv����Ƃ��������Ď��́A���q����̎ʎ��I�ȍ앗�����X�̋�̓I�ȏё�������n�o�������̂ł͂Ȃ��A�쐫�ւ̊��҂��̂��̂��������̑c�t�������������ƁA�����đc�t�̃C���[�W�͐l�X�̑O�Ɏp�����킵�~�ς��������A�܂��Ɂu���g�̕��v�ł��邱�Ƃ��w�E���Ă���B���ۂɂ́A��������v�Ƃ��镡���̈��q������ݍ��������ۂƍl�����邪�A�����������ڂ��Ă���O��3�N�i1280�j�ɐ��厛�b���i1201�`90�j��80�������đ���ꂽ�����̑ٓ��ɔ[�߂�ꂽ��ʂ̕����Q����́A�b�����܂��������g�̕��Ɛ��q���悤�Ƃ���L���̐l�X�̐S�ӂ�����������B����āA��ɐ��������Ė@������A��ɍs�҂���삷��@�c��M�]�����q�E�h�z�����̑c�t�M���A�����̌�e�������̌����͂ł������Ƃ����悤�B
�@���̂悤�ȏ@���I�ȕ��͋C�̒��ŁA�@�c�Ō���Ȃ����Ė剺�S�ʂɂ����đ����̓��@���l��e������������Ă��������A���̂���������́A�c�Œ���ɒ�u���ꂽ��_�֔Ԃ̕�����āA�@�c3����̍O��7�N�i1284�j�����V�m�B�̗����̂��Ƃɐg���R�v��������ǂ��������t���A���̔N��3����O��ɑ��������Ɠ`�������e���ł���B���Ȃ킿�A�u���t���^�v������l�����}��
�O�����N�q�b�\�r�܌��\����A�b�B�g���R�֓o�R�B���\���\�O���A�吹�l�����X������O��䕧�����B
�n�e������l�j�ΖʁA��e���o�d�]�]�B
�Ƃ���A�u�����G�W�v��
�g���R�j�n���@���l��N�A���������l�Z�N����L��A���l�䑶���m�ԃn�䓰���V�A��Ō�j���l��[���䓰�j������l�m��v�g�V�e���ʃt�A��e�������Z�ʃt����������l�m�䗧��B
�ƋL�^����Ă���B�����ɂ��ƁA�����t�͏@�c3��������܂łɏ@�c�̐g���Z�V���䓰�i��e���j�ɉ��߂āA���̒��ɏ@�c��e�������Ĉ��u�������ƂɂȂ�B
�@���̌�A�����t�͊w���E�����t�̋����̉��ɒn���E�g�؈���������Ƃ���掖@�s�ׂ�����Ƃ��āA����3�N�i1289�j�̏t�ɐg���R�𗣂�A�����̒�q�Ƌ��ɕx�m�ւƕ������B���̍ۂɁA�g�؈�������̎q���E�������������t��
�����݂̂ӂ���i�g����j�������i�䂢�j�Č�w�n�ƂĐS���n��������܂�i�d��j��A���납�ɂ������Ђ܂��点��A�����ق��̌��ق�����i�@��j����ӂ�i���j�������ցi�Ⴆ�j�܂��点��n�A�ق�i�{���j�Ȃ�тɌ䂵�₤�l�i���l�j�̌��i��e�j�̂ɂ��܂�𐴒����g�ɂ����ӂ������ӂ�ւ���B
���₤���������˂�i�������N�j�\��
������
�@
�Ƃ����u����v���o�������A�����ɂ͏\�E��䶗��{���Ƌ��ɉE�̏@�c��e���ɂ��Ă̎��f���������L����Ă���A��e�����{���Ɠ��i�̈������Ă��邪�A���邢�͂��̎����łɐg���R�v�����䓰�̌��O�̌`�ԂƂ��āA�\�E��䶗��{���̑O�Ɍ�e�������u����Ƃ������݂ɓ`���`�Ԃ��̗p����Ă������Ƃ��z�������B
�@���̓����t�����̌�e���͓����t�̐g�����R�Ƌ��ɕx�m�ֈڂ���A�V���Ɍ������ꂽ��Ύ��̌��O�Ɉ��u���ꂽ���A���̌�A�����E���ڂ̗��t���ɋN��������Ύ����V�n�W���̍Œ��ɁA����E�v�������o�R���ė5�N�i1342�j�Ɉ��[�E���{���ɑJ������āA���Ɏ���Ɠ`������B�@����A�����t�͓��ڎt�ɑ�Ύ��̌o�c���ς˂āA�i�m6�N�i1298�j�ɏd�{�i�k�R�j�̒n���E�Ή͎��̏����ɉ����āA���n�Ɍ�e����n�����ĈڏZ�����B���̐Ή͔\�����́u��i��v�ɂ�
�k�O���l���n�Z�e�����
�E�j����Ⴄ���i�l�j�݂̂�i��e�j�^�T����ԁA�ЂႭ�����i���@��苗��j�̌�[�A���������T�₤�i�t���j����ԁA�������i��~�j�ӂ����ɂ�����i�i��j��������Ă������Ă܂鏊��A���̃n�����i�V�n�j�̂�������A�Ђ����i���j�n�̂ق�݂����ˁA�����i�k�j��悱�݂����ˁA�ɂ��i���j�n�̂ق�݂����ˁA�݂Ȃ݁i��j�Ȃ݂��̂悱���˖�A���̂����Ⴄ�j�܂����āA���������T����i�q�X���X�j�j������܂āA������炢�Ȃ���n�ނƂ�����n�A���������Ƃ������Ⴄ���ւ��炷��A���Ă����Ⴄ�@�V�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������N�\�ꌎ�\�O���@�@�@�@�@�@�@�����i�ԉ��j
�Ƃ���A�����t���d�{�i�k�R�j�{�厛�ɐV���ɏ@�c��e�����������Ƃ��m����B���̏d�{�{�厛�͓����t�̖Ō�͑����W�ɂ�������q�E����t�Ɉ�����ꂽ���A�s�K�ɂ��ċN����������t�Ƃ̕��֕i�Ǖs�ǘ_���̒��ŁA�{瑖����Ɣ�c���ꂽ���ƂȂǂ������ŏd�{��ޏo���A�N�i2�N�i1343�j���ɐ��R�ɖ{�厛���������Ĉڂ����Ƃ����B�E�̐Ή͔\�����́u��i��v���A���̍ۂɓ���t���g�т������ʁA���͐��R�{�厛�ɓ`��邪�A�������N�i1368�j�ɓ���t�͏d�{�̎��̂̕ԕt��ړI�Ƃ������̂悤�ȁu�ڈ��v���쐬���Ă���B
�ڈ�
������l���t�@����\�X���S�d�{�����V�E��j��e�������B�E�����n�ҁA������l�O�\�]�N�O�ʔV���Ֆ�A嫃����V�g�@��A�ȃe���ヒ�⏈�t�@�g��u�J�胁�L�k�A���M���u�ʑуq�V���L�k�A�����j��k��j�昦�n���Ή͎�����v�����A�e�������������M����i��j��w�V��A���@掖@�V�ԁA�ޘ����n�Җ������j��i�V�n��g�q�׃j�s�y�n�����j�\�V��o�T�L�k�A�����㎮����苗������n���g���S�V�ԁA���N���Z�V�ʃV�e�����V��n�A�ޘ��헹�����_�g�]�]�A���e�n����j�ҁA�������@���l�O�㑊���V�t�@�A�׃�������l���t�@�⏈�A�����ȉ����@�O�ʔV�d���`�X�V���A�R���n�ҔC�Z������l���u���j�Ή͓���������i��V�|�j�A������e�����דn�T���t�A�e�ڈ��@�V�����B�@�@�@�������N�\�ꌎ��
�@�����A�����嗬�ł͔h�c�̓����t����u�����\�E��䶗��{���Ə@�c��e���Ƃ����{���`�Ԃ���v�ȓ`�����V�Ƃ��Ē蒅���Ă����ƍl�����邪�A�E�̐Ή͎��́u��i��v�����t�́u�ڈ��v�ɂ͏\�E��䶗��{���Ɋւ���L�q������ꂸ�A�d�{�{�厛����т��̎��̂̏ے��Ƃ��ď@�c��e�����w������Ă��銴������B����ɏ]���w�E����Ă���A�����t�₻�̒�q�B�̏����Ɍ����鋟�������u�@�ؐ��l�v�u���l��e�v�u�قƂ����悤�l�v�u���O�v�u�@�吹�l�v�u��o�v���ƕ\�������@�c��e���ɔ�I����Ƃ�������Ȃǂ����������ꍇ�A�{���`�Ԃ̒��S���\�E��䶗��{�������A�ނ���@�c��e���ɂ���Ɣ��f���邱�Ƃ��\�ł���B�����āA���̂悤�Ȗ{���ӎ��̗��ꂪ��Ύ�����E���L�t�Ɏ����āA
1�A���@�̖{���̎��A���@���l�Ɍ�����ׂ��A���e���̍O�@�͗��ʂȂ�A�Ō�̏@�|�Ȃ�̂ɖ��f�f�̓��t��{���Ƃ���Ȃ�B
���@�̌䓰�͔@���l�ɑ��肽��Ƃ��F��e���Ȃ�A�\�E���}�̌�{�����|����ւǂ��A���c���@���l�̌䔻������Α���e���Ȃ�B
�ƂȂ�A�����Ɂu���@���l�̌�e��������O�Ɉ��u���āA�ߑ�����юߑ����ł͂Ȃ��A���@���l��{���Ƃ��ĐM�̒��S�ɒu���Ă������Ƃ����l���v�̓��@�{���`�̐������������̂ƍl������B
�@�E�q�̂悤�ɁA�@�c�Ō���Ȃ����Ė剺�S�ʂɂ킽���ď@�c��e������������Ă��������A���������嗬�ȊO�A���Ƃ��Β��R�@�،o���Ɋ��]���Ă݂�ƁA�i�m7�N�i1299�j�ɓ������c�E����t���L�^�����u��C�@�{���������v�̖`���ɂ́A
1�A���@�@�،o�֑ɗ��@��݁@�@�@�@1�A�߉ޗ������j�l��F�q����~�q�r
1�A�\�����@��݁@�@�@�@�@�@�@�@�@1�A�V���t��e�@���
1�A���l��e�@��́@�@�@�@�@�@�@�@1�A���l��U���@�꒟
�Ƃ���A���������O��E���S�t�́u�{�������^�v�̖`���ɂ�
�����q�@�E�{���r�{�������^�@�@�N�i�q�b�\�r��X���X�L�V�B
�䎩�M���䶗����
�߉ޕ�������l��F�@�~�q�j����
�̓�����M�֑ɗ���݁@�@�@�@�\���������
�O�\�Ԑ_��݁q�����r�@�@�@�@�V���e���
�吹�l��e��́@�@�@�@�@�@�@�����e���
���ܗֈ�@�q���吹�l��M�E�����ߕ�䍜�r
�@�@�@�@�@�@�@�@�ߏ�@�؎��q�@�E����䎩�M�O���{���E����a�j�����c�r�@
�䎩�M���䶗���݁@�斾�q��c�����r���g��
�@�@�@�@�i���@���j�߉ޕ�������l��F�q�吹�l�䋟�{�@�~�q�j����r
�ŕ���ڎ߉ޑ����l��F���e���
�߉ޑ���́q���_�{���r�@�@�@�@�\��������݁q��݃n�J�i���J�J�M��r
�O�\�Ԑ_��݁@�@�@�@�@�@�@�@�V���e��݁q��݃n�ٌ����r�@
�吹�l��e��́@�@�@�@�@�@�@�吹�l��e���
�@�@�@�@�@�i���@���j
�@�ߏ�{����
�ƋL�^����Ă���B�����ɂ��ƁA�����͕s���Ȃ���A�x�؏�E���ِ̊Ղ̖@�؎��Ƒ�c�斾���ِ̊Ղ̖{�����ɂ́A��e�ؑ������ꂼ���̂���������Ă���A�{�����ɂ͂��̑��Ɍ�e�G������ݏ�������Ă���B
�@������ɁA���̗����̋L�^�̏������������Ă݂�ƁA�ŏ��ɏ@�c�䎩�M�̑��䶗��{��������A���Ɏߑ������тɎl��F���A�����ď\�������E�O�\�Ԑ_��V���t��e�������āA���̌�ɑ吹�l��e��̂��L����Ă���B������ǂ̂悤�ɓǂނ��A�����̕������Ƃ�������낤���A�O���œ����嗬�̉��V�ł͙֑ɗ��{���Ə@�c��e�������i�̖{���Ƃ��Ĉ����Ă����|���w�E�������A�@�،o���̏ꍇ�A��䶗��{���Ɠ��i�Ȃ͎̂ߑ�������юl��F���ł����āA�@�c��e���͂��Ƃ��ΓV���t��e�ȂǂƋ��Ɉ�����^���������Ƃ���ł̈����̂悤�Ɍ�����B����ɖ{���Ƃ����Ă��A�傫�������ď�Z�I�Ȗ{���ƈꎞ�I�Ȗ{��������ƍl������B�܂�A�O���̐����ڎ�舵���{���Ǝ����F������̑ΏۂɂȂ�{���ł���A���R�@�،o���̏ꍇ�A�֑ɗ��{���Ǝߑ�����юl��F���������Ɋւ���{���ł���̂ɑ��āA�V���t��e��@�c��e���Ȃǂ͂����܂ł��ꎞ�I�Ȗ{���Ƃ��������ł���悤�Ɏv����B�����āA������E�̓����嗬�̓��@�{���`�̒�`�ɑΔ䂵�Ă����A�u�ߑ�����юl��F�������O�Ɉ��u���āA���@���l����т��̌�e���ł͂Ȃ��A�ߑ���{���Ƃ��ĐM�̒��S�ɒu���Ă������Ƃ����l���v�Ƃ����ߑ��{���`�ƋK�肳��悤�B
�@�@�c�Ō�ɓ����t�Ƒ��̌ܘV�m�Ƃ̊Ԃɔ��������܈�̑���́A��ɓ����嗬��������u�ܐl���j���v����сu�x�m��Ֆ�k���m���v�̗����ɋL�^����Ă��邪�A�{���Ɋւ��ẮA�����Ɏ��グ��悤�ɁA�����t�̋`�Ƃ��Ďߑ����ł͂Ȃ��@�c�}���̙�䶗��{����{���ƒ�߂�ׂ����Ƃ�������Ă���O�́A�ߑ���̕��̎�舵���Ə@�c��䶗��{���̎�舵�������ƂȂ��Ă��邪�A�E�̓��@�{���`�Ǝߑ��{���`�̑���ɂ͌��y����Ă��Ȃ��B�������A�@�c����Ԃ̍ł��傫�ȋ��`�I�ȑ���Ƃ������Ƃł́A���̎ߑ��������O�Ɉ��u���邩�A����Ƃ��@�c��e�������u���邩�Ƃ�����ڂł͂Ȃ��������ƍl������B
�@����ł́A�ǂ����Ă��̂悤�ȑ傫�Ȉ�ڂ��������̂ł��낤���B����ڐ�������j���͍��̎������ɂ͗^�����Ă��Ȃ����A�O���ł������G�ꂽ�u�x�m��Ֆ�k���m���v�̋L���Ȃǂ���A����͙�䶗��{���ɑ���F���̈Ⴂ�����̌����ɂ��������ƍl������B���Ȃ킿�A�����ɂ�
�ܐl�ꓯ�j���N�A���e�n�{���j�҉V�g�e�������ێ߉ޔ@�������j���e�A���q�e��q�h�ߓ������j���������{�䏑�݃��V�]�]�B�����Ԑ����j���Ƀ������e�A���n��̃����u�V�A���n�������ꃒ�e�m�g�X�B���e���e�n���l��M���{���j�ҁA�ޘ���������ʃj���P�A�����ɘ��L�j�̃e�u�N�V���^�����]�N�A���e�n���l�䗧���@��j�ҁA�S�N�ȃe�G���ؑ�������F���s�׃j�{���m�B�B�C�Z�e�䏑���Ӄj�ȃe���@�@�،o�������V�׃X�{���m�A���`���M���{��������^��A�@�N��m�ꓯ�j�����{���������j�V�V�ԁA���n��䶗���g�]�q�e�����l�����q�e���X���y���L���B���n���l�p�X�������L���B�@�N�����y�G�X���ԃ^�����n�ȃe���q�L�k�B�^�����]�N�A������M����{���n������腕���j���^���z�Z�A�������j���^�O�ʃZ�{����B�R���n���`���e�n��������k�������V�y�j�ҁA���N���E�q�����j�����A��q���j�s�J���t���X�B���V�N�ꏊ�j���u�V�A�Z�l�ꓯ�j�V���V�B�����w�j�L�闬�z�����L�A�{��������q�l�L�������}�e�[�N�h�d�V�w�V
�Ƃ���A�����ɂ͌ܘV�m�����{���Ƃ��Ďߑ���̑���e�m�����u���A��䶗��{���ɂ͌y�̂̎v���������Ă������ƁA���̂��߂ɏĂ����蔄�蕥�����肵�đ��������Ă��܂������Ƃ��w�E����Ă���B����A�����剺�͏@�c���M�̙�䶗��{���𐳑����O�̖{���Ƃ��Ĉ��u���A�L�闬�z�̎��܂ő��h���Ă������Ƃ��m�F����Ă���B�܂�A�ܘV�m���͖{���̒��S�`�ł���ߑ����Ɣ�r�����ꍇ�A��䶗��{���𑊑ΓI�ɒႭ�����X���ɂ��������ƂɂȂ�A���̂悤�ȋL�q���ǂ��܂Ŏj���f���Ă��邩�A�ɂ킩�ɂ͔������������A������䶗��{���ɑ��闼�҂̔F���ɂ͂��Ȃ�̊u���肪���������Ƃ͗����ł���悤�Ɏv����B
�@�����āA���̔F���̊u��������ɓ`������̂̈���A���҂̙�䶗��{�����ʂ̌`�Ԃ̈Ⴂ�ł͂Ȃ����ƍl������B���Ȃ킿�A�����嗬�ł͔h�c�̓����t�ȗ��A��䶗��{���̒����c�Ɂu�얳���@�@�،o�@���@�䔻�v�Ƒ发���A���ʂ����{�l�̖��O�Ɖԉ��͑����֑ɗ��̍������ɔ�r�I���������M�����B����ɑ��āA�����嗬�ȊO�ł́u�얳���@�@�،o�v�̎��̉��ɂ͏��ʎ�̏����E�ԉ��������ɐ������A�@�c�̖��͂����܂ł���O�̈�l�Ƃ��ď����������Ă���B���̈Ⴂ�̈Ӗ��ږ�������j�����܂��������͒m��Ȃ����A������u�ϐS�{�����v�O���̊ϐS�i�̌����ł���
�ߑ������s�ʓ����j�@�n���@�@�،o�����j��X�B�䓙�X���n���������R�j�����^�w�^�}�t�ވ��ʘ�������
�Əƍ����邱�Ƃɂ���āA���̈Ӗ��̊������̗����������邩�Ǝv���B
�@�܂�A�����嗬�ȊO�Łu�얳���@�@�،o�v�̎��̉��Ɏ��Ȃ̖��O�������ꍇ�A����͎ߑ��̈��s�ʓ��̃j�@����������@�@�،o�̌������A�ߑ��̈��ʂ̌��������^����Đ������鎩�Ȃ̎p�������Ă�����̂Ɖ��߂ł���̂ŁA���邢�͎��Ȗ{���`�Ƃ��̂�����`�ԂȂ̂����m��Ȃ��B����A�����嗬�́u�얳���@�@�،o�@���@�䔻�v�̏ꍇ�́A���@�@�،o�̌������āA�����ɋ�����ߑ��̈��s�ʓ������R�ɏ��^�����̂͏@�c���̐l�ł���B�����āA����ɕ��i11�N12�������̐�t�E���{�������̒ʏ́u���N�~��{���v�̎]������
��o��������Ř���A�o���X����S��\�]�N���B嫃������g�������O�P���V�ԁA���^�L�T������{�����B���n�m�e�s�O���V���A���n�s�m���V���B��K�����ȃe���q���B�V�����e�V���׃j���㘦�c�V�V���B�A��ܕS�ΔV����s��F�o���V�e�����j�n���e�O��X�V���B
��A��12�N2���u�V���O��Ԏ��v��
�����̌�{���͋���ߑ��ܕS�o�_�����S���ɂ����߂������ЂāA���ɏo�����������ЂĂ��l�\�]�N�A���㖔�@�،o�̒��ɂ�瑖�͂������āA�i��莖������Ď��ʕi�ɐ������͂��A�_�͕i���ݕi�Ɏ��ɂ܂�Č�Ђ����A�E�E�E��s��F����O�o�i�ɏ����o�������ЂāA�@�،o�̖{��̊̐S���閭�@�@�،o�̌�����Â点���ЂāA�E�E�E
���̂����ӂ��l�����킹��ƁA����Ɍ��v�t��������s��F�̎��o�āA�Ō㖖�@�ɂĖ��@�@�،o�̙�䶗��{����}�����A�O�邵�Ă������Ƃ���@�c�̎p�������ɂ͂���B��䶗��{���ɂ��Ă̓����嗬�̗��������̂悤�ɑz�肵�đ�߂��Ȃ���A�����Ȃ闝���͊ԈႢ�Ȃ��h�c�̓����t�Ɏn�܂������̂ƍl������B
�@���͓����]�ڂٍ̐e�ŁA�O�����N�i1278�j��5��6�������Ƃ����@�c�ԉ��̕ω��̈Ӗ����A����܂ł̎ߑ��{���ƙ֑ɗ��{���̕����̏�Ԃ���A��䶗��{��������Ō㖖�@�O���~�ς̖{���ƒ�߂�Ƃ���@�c�̈ӎu�̕\���Ɛ������A���̌��ʂ��u�{���ⓚ���v�́u�߉ނ��ȂĖ{���Ƃ������āA�@�،o�̑�ڂ�{���Ƃ���v�̕����ƂȂ��ĕ\��ꂽ�Ƙ_���Ă݂��B���́A���̂悤�ȏ@�c�̈ӌ����āA�\�E��䶗��{���̎�̂��u�얳���@�@�،o�@���@�v�ƌ���߁A���̒��ɖ��@�����Ďߑ��̌���������^�����@�c�ƁA��s�̎��o�̉��ə�䶗��{�����O�邷��@�c�̓�̎p��F�߂������t�́A�c�Œ���ɏ@�c��e�������ę�䶗��{���̑O�Ɉ��u���邱�Ƃɂ��A���̖{���̎�̂Ƃ��Ă̏@�c�̎p������Ɍ�����`�Ƃ��ĕ\�킻���Ƃ����̂łȂ����A�����Ă��ꂪ���@�{���`�̕����ƂȂ�A�����嗬�Ɠ��̉��V�Ƃ��č��ɓ`������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝ��͐�������̂ł���B
�@�����嗬�ƌܘV�m���Ƃ̊Ԃɂ́A�ȏ�̂悤�ș�䶗��{���ɑ���F���̈Ⴂ���������B�������A�ܘV�m���ɂ�����ߑ��{���`�Ə\�E��䶗��{���Ƃ̊W�͂�����s���Ăŕ�����ɂ������A�ߔN�A���̊W���Ɏ����ꂽ�̂����s�C�G���ł���B�ȉ��A�������p�ƂȂ邪�A���́u���@���l�̙֑ɗ��ɂ��ā\�\���ɖ{���Ƃ̊W�ɂ��Ăh�v�Ƃ����_���̒��ŁA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@���������āA�{�����ɐ�����Ă����O�O��́A�ߑ��̌��̐��E�A���Ȃ킿���_�E�������ꂽ���̂ŁA���ꂪ������{���̑�ڂ̖@�̂ł���Ƃ������Ƃ��ł���B�����Ă܂����ꂪ�A�{���̕�F�ɕt������ꂽ�v�@�ł���B�����ɉ����Ė{�����ɂ́A���̖{��̊̐S�A�얳���@�@�،o�̌��ɉ��ẮA���P������ɂ��V��t�������܂킸�B�����₻�̛߉�����A�A�n�O��E�������āA���i����ĔV��t�������܂��A�Ƃ���B�����Ă��̉��ɁA�u���̖{���̑̂��炭�B�{�t�̛O�k�̏�ɕ�ɋ����A�i�ȉ��ȗ��j�c�c�v�Ƃ����̂́A�������A��䶗��̋V�������������̂ƌ��邱�Ƃ��ł��邪�A���̙�䶗��̎�̂��Ȃ����̂́A�����܂ł��Ȃ��A�ߑ��̐��_�E��\�킵����O�O��̖@�ł���A�{��̑�ڂł���B�����Ŏn���̙�䶗����A�{�����̂��̕���}���������̂ł���Ƃ���A����͔��i�̋V���ɂ����̂ł����āA�ߑ������@�@�،o������ꂽ���A�\�E�̂��ׂĂ��A���̖��@��M�āA���������p�����킳�ꂽ���̂Ƃ݂�ׂ��ł��낤�B����Ɠ����ɂ܂��A��ʂ��猩��A���̖{��̑�ڂ�������̂����������A���V����삵�A��O�����Ă���p�ł���Ƃ���������B�X�ɂ܂��{�����ɐ����A��O�O��Ɩ��@���̊W���炷��A���̌��̐��E�Ɍ���ꂽ�A�\�E��̑��������ꂽ���̂Ƃ��������Ƃ��o���悤�B
�@�Ƃ���ŁA�{�����̕��ʂɂ́A���Ɉꌾ�����@���֑ɗ��̗p�ꂪ�������肩�A����ɑ��閾�ĂȂ������������Ă��Ȃ��B�����ł���͂����A�{�����Ɍ���ꂽ�v�z������āA��䶗���������A�ȏ�̂悤�ȉ�����\�ł���Ƃ����ɉ߂��Ȃ��B����������ɂ��Ă��A�{�����̎v�z����Ƃ������A�֑ɗ����̂��̂��ɁA�����̖{���Ƃ���̂ł͂���܂��B����A���̙�䶗����ϐS�̖{���Ƃ��āA�{��̋���ߑ���{���Ƃ���A����{����菟�ꂽ���̂ƌ��邪�@���́A�{�����̎v�z�ɔ�������̂Ƃ��킴��Ȃ��B
�@���ɏq�ׂ��@���A�{�����ɉ��ẮA���@�@�،o�ɂ������Ă��A�܂��\�E��A��O�O��ɂ��Ă��A����͕��̌��̐��E�ł��蕧�̐��_�E�Ȃ̂ł���B�����ł���O���́A������A���Ȃ̊ϐS�Ƃ��āA�M��Ƃ���ɐ���������������B���Ȃ킿�u��O�O��̕���v���A���킷�邱�Ƃɂ���Ă̂݁A�������\�ł���B������̕��̖@��}��Ƃ��āA���Ɉ�@����̂ł���B�̂ɂ���̍s�̐����́A�����̂��̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�@�͎���āA���Ȃ̍s�@�Ƃ��ׂ����̂Ȃ̂ł���B�{��̑�ڂ͕����̂��̂ł͂Ȃ��A���̑����ł���Ƃ������Ƃ��ł��悤�B�i���@���j�@���悤�ə�䶗��́A���ʕi�����̑�ڂ𒆐S�Ƃ��A�\�Ƃ��Č��킳�ꂽ�̂ł��邩��A���̖{��̑�ڂ����킳�ꂽ�A�{��̋���ߑ���{���Ƃ���ʂ����ɂ܂�Ă���Ƃ������Ƃ��ł��悤�B�̂ɂ����{��̖{��������ꍇ�́A�{��̑�ڂ́A�ߑ��̐��_�Ƃ��A���ʂ̌����Ƃ��ē��ʂɂ܂�āA���̂悤�Ȗ{��̑�ڂ�����ꂽ�{��̋��傱���A�{���Ƃ��ׂ��ł���Ƃ����Ă���B�����ɉ��āA��̕��ɂ́A��䶗��ɉ����钆���̖��@�@�،o�́A�{��̋���ߑ��Ƃ��ĕ\�������Ă���̂ł���B
�@���s���͂����ŁA�u�ϐS�{�����v�ɐ����ꂽ�����I���t���ɂ��\�E��䶗������킳�ꂽ�Ƃ����×����x�����ꂽ���Ɋ�Â��āA��䶗��̎�̂��u�{�����v�ɘ_����ꂽ��O�O��ł���A����͂܂��{��̑�ڂ̖@�̂ɂ��ď�s�t���̗v�@�ł��邱�ƁA���������̈�O�O�炨��ё�ڂ͂����܂ł����̑����ł���A�ߑ��̐��_�E�i���ƍl���Ă悩�낤���j�����������̂ł��邩��A���ʂ̌����Ƃ��Ďߑ��̓��ʂɕ�܂��̂ŁA���̑�ڂ����������ߑ��������{���Ƃ��ׂ��ł��邱�Ƃ�����Ă���B�����āA
��䶗��͋v���̕��̐��_�ł����O�O�炷�Ȃ킿�{���̖{����}�������̂ł����āA����͒����ɖ{���̎��̂����킵�����̂ł͂Ȃ��Ǝv���B
�ƌ��ꂳ��āA�ŏI�I�ɂ͏\�E��䶗��͖{��������i��������Ă���B�����Ȃ鎷�s���̍l�����ǂ��܂ŌܘV�m�����̐l�X�̍l�����ق��Ă��邩�͑S���s���ł��邪�A��ʂə�䶗��{���̋����I���t������������ƍl�����Ă���u�ϐS�{�����v�̕����ɏ������Ȃ���ߑ��{���`��������Ă���A���̂悤�ȗ����Ɋ�Â��A��䶗��{����������@�c��M�ł����Ă��A���F�{���ł͂Ȃ��ƍl�����Ă����Ƃ���A�e���Ɉ������Ƃ����������낤���Ƃ��v����B
�@����ǂ��A���s���̉��߂ɂ͒v���I�Ȍ��ׂ�����A����͌��v�t���𒇉�ĖŌ㖖�@�ɗ��z�����ׂ��u���@�@�،o�̌��v�́A�u�{��̑�ڂ́A�ߑ��̐��_�Ƃ��A���ʂ̌����Ƃ��ē��ʂɂ܂�āv�Ƃ������R�̉��ɁA�v���̎ߑ��̒��ւƓ����Ԃ���Ă��邱�Ƃł���B�������A����͉E�f�����u�{�����v�́u�ߑ������s�ʓ�����@�n���@�@�،o�������X�B�䓙�X���n���������R������^�w�^�}�t�ވ��ʘ������m�v�Ƃ̋����炷��Ƌt���܂ł����āA�ߑ��̈��s�ʓ��̂��ׂĂ������얳���@�@�،o�̌��ɕ�ݍ��܂�ċ����A���@�́u�䓙�v�ւƑ�����Ƃ����̂��@�c�̖{�ӂƍl������B���ǁA��䶗��{���������ɖ{��������i�������Ă܂Ŏߑ��{���`���������悤�Ƃ������s���̎��݂͐��������Ƃ͂����Ȃ����A����͗���Ԃ��A����قǂɎߑ��{���`�ɂ����ę�䶗��{���̈ʒu���߂邱�Ƃ������ɓ������\�킵�Ă��悤���B
�@�������A�E�q�̂悤�ɁA�h�c�̓����t�̏��u�ɂ��ꉞ�����ւ̓�����݂͂��߂����@�{���`�̕����A���ȓ�ւƂ������A�s���肳���������ł����B�O���ł��G�ꂽ�O�����N�������Ƃ����䶗��{���I��Ƃ����@�c�̉p�f�́A�ߑ��̏����E�ێ�E�E�v�̍ݐ����E�Ƒ������Ƃ���ɁA���@�i��s�E�s�y�j�̋t���E�ܕ�����v�Ƃ����Ō㖖�@���E���`�������߂����A���̏@�c���ӔN�ɒB�����ꂽ�ߑ��̑��Ή��ɂ͏d��Ȗ�肪�������B
�@����͉E�ɂ����Ύ��グ���u�{�����v�́u�ߑ������s�ʓ�����@�n�c�c�v�Ƃ̈ꕶ���番����悤�ɁA���̖��@�@�،o�̌�����љ�䶗��{���̌����̌���́A�S���u�ߑ��̈��s�ʓ��̓�@�v�ɂ���B������A�����ߑ����E�̑��Ή������������i�߂āA�ߑ����E���̂��̂��̂ĂāA�Ō㖖�@���E�����ł���čs�����Ƃ��̓Ɨ������͂������Ȃ�A���̓r�[�ɐ��̏�ɕ����ѕY�����Ȃ����ƂȂ�ʂĂ�B�܂�A�����疖�@���E�ł̐���������咣���Ă��A�����̎��̂ł���ߑ��̈��ʂ��Ȃ��Ȃ�A����͑S���̋�_�Ƃ��킴������Ȃ��B���ꂪ�@�c�ӔN����Ō�ɂ����Đ�������������䶗��{���I��Ɋ�Â����@�{���`�̎��Ԃł���A����Ӗ��ł͔��ɂǂ��������̕s���肳�ł������B
�@�����ŁA���̂悤�ȓ��@�{���`�͂��̌�ɂ����悻��̕����ւƌ������B��́A���ׂĂ̌����̌��ߑ��ɂ���̂�����A��͂肻�̌���ɋA��ׂ��ł���Ƃ����ߑ��ւ̉�A���ۂł���B�����ł͓��R�A���@�{���`���̂ĂĎߑ��{���`���̗p�����B�@�c�Ō㓖���ł́A���Ƃ��Γ����t���i�m6�N�i1298�j�́u��q���{���ژ^�v�Łu�w������ʁv�ƋL�^���ꂽ�z��[���َt���O�[���`�t�E�����[���ʎt�Ȃǂ��Y�����邩�Ɛ�������A�퍑���ł͌�͂ŏЉ��L���@���C�t�̏ꍇ�Ȃǂ́A���������̎ߑ��ւ̉�A���ۂł��邤�Ǝv����B
�@�����āA������̕����́A�ߑ����Ȃ��̂Ȃ�A���̑���̂��̂������̌���ƒ�߂āA�ߑ����E�͂��Ƃ��ے肵�Ă��܂����Ƃ��������ł���A���ꂪ�{�����v�z���`�����悤�Ƃ����ٓ��ł���B�܂�A�{�����v�z�̕K�v���ł��邪�A���̓�������̓I�ɐ}�����Ă݂�ƁA���̂悤�ɂȂ�B
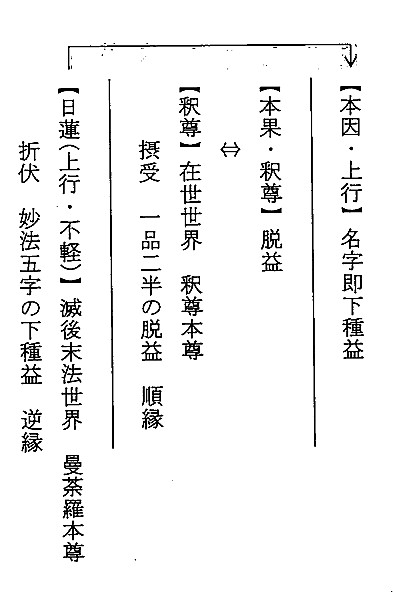
�@
�@���}�̍������ɂ͏@�c���ӔN�ɒB�����ꂽ�ߑ��̑��Ή������������A������p������`�ŁA�ߑ��̖{�ʖ��z�����Ƃ��Ă̖{���������߁A���������ꂪ�ߑ��̖{�����łȂ����Ƃ��������߂ɖ������̖{�����ƋK�肵�A�����ɏ�s��F�E����p��g�@����ݒ肵�Ė��@�@�،o�̌����̌�������߂Ă������Ƃ���A���̂悤�ȋ��w�I�ȗv���Ƃ������A�����̒��ŁA�{�����v�z�͌`������Ă������ƍl������B
�@�����嗬�̖{�����v�z���`������Ă��������͌����ĒP��ł͂Ȃ������낤���A�����j���̂�����A���̓��@�{���`�̋��w�I���t���̕K�v�����A���̍ł���v�Ȍ����ł��������낤�Ǝ��͍l���Ă���B
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@���͂���܂ŁA�����嗬�̖{�����v�z�̌`���Ɋւ��āA��Ɍc�і[�����t�̖{�����v�z�Ƃ̌����𒆐S�ɒu���đ�g�̗�����l�@���Ă������A���͂ł͎������̋E���ɂ����鏟��h���嗬�̌����̈�f�ʂ��Љ�A���ꂪ��̏�Ƃ��Ė{�����v�z�̌`���ɂǂ̂悤�ȈӖ������������A�����Ă��̂悤�ȗ�����Ȃ���{�����v�z�ɋ���Ȕ�����|�����L���@���C�t���ǂ̂悤�ɓo�ꂵ�����A���X�q�ׂĂ݂����B
�@��t�E���{����11��̓��v�t�n1436�`1514�j�́A�������N�i1489�j�Ɏt���̓����t���������̊w���V�E�𑊑������|���I���邽�߂ɁA����������[�B�̖��{���ɓo�������A���̏Z�R���ɑO�Z�E���M�t�̋A��ɂ����A���̂܂ܐ�����Ė��{���̖@�����p�������B���ɓ��v�t��54�B���̒��x10�N��̖���8�N�i1499�j3���Ɏt�͏㗌���ĔO��̑t���𐋂��A���Ō̋��̓����ɕ����āA���T2�N�i1502�j�܂œ��n�ɑ؍݂��đm�����������Ă���B
�@����������v�t�́u�\��v�́u���@���l�����x�m�R���B�����v�v�̖��ō쐬����Ă��邪�A���́u�\��v���o���Đ�����ꂽ�t���Ɋւ���u���v�t��L�^�v�Ƃ����ꏑ�����݂̖��{���Ɉ₳��Ă���A����ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���B
�x�m�{�厛���v�\��q���h�����E���������[�r�����a��G���P�惊�\�V�����A
���֔����a�A���`�t���C���a�A�������ٗ߃��[�Z�ē����A������ǔ탌�B�Z�㕷���q���k�B
�������N�O���\������Q
�����l�����L�o�V�V��
���V�n���䎛����V�\�V������A�ӌ���Z�@�����E�@�M�V����A��ʐ\�M�A��іV�����B
�@�܂��A���̋L�^�ɂ��Ė��{���̓���t�́u�\���v�ɂ�
�����㖾���Z�N���ߎO�����{������o�e���V�N�܌���j���V�A���V�N���N�Ȗ��O���\����L���Q���A�\���ʋ��P�ʃt�A���V�N���l�����䏑�L�o�V���j�����{����L���V�A�\��n����@�ؑm�i�{�\���m��j��іV�����V�M��B��m�\��O�ʏ��L�V����ʃn�嗠�ֈ�ʃn������ʃn�w���V������B���X����������V����V�A�t�����t�҃n�������a��B����V�i���䎛�O�j�n��A�V����j���V�e���X�Ⓙ�m�A�����单������Y�J�S����B���j����Z�@�����n����k����w�����S�Җ�B
�Ɛ�������Ă���B�����ɂ��A����6�N5���ɘa���ɓ����������v�t�́A2�N��̓�8�N3��19���ɓ����ɎQ�サ�A���l�̓��Œ��ق̒�����G�i1469�`1531�j���t�҂ƂȂ�A�`�t�̊��C�������Ɗ֔��̈��~�ǁi1464�`1514�j�̊NJ����A������ǂ���莟���Ō�y���V�c�Ɂu��t���ڏ�l�\��v�Ǝ���́u�\��v��2�ʂ�t�サ�A24���ɉE�́u���v�t��L�^�v���u�䏑�o�v�Ƃ��č쐬����Ă���B
�@�E�L�^�Ɂu���h�����E���������[�v�Ƃ�����A�u�����v�Ƃ͓��v�t�̒헹�ŁA��̉i��5�N�i1508�j3��13���ɓ��v�t���ʂ̙�䶗��{�������^����Ă���B���h�Ƃ���̂́A���邢�͕ۓc���{���o���ȗ��A�t�̓��v�t�ɐ������Ă���Ƃ����ӂł��낤���B������l�́u�����[�v�́A���̑t����5�N�O�̖���3�N�ɘa���̉Ɖ��~����v�t�Ɋ�瑂��Ă���l�ŁA�����~�͂��̌�w��O�ʏ����{�`���x�Ɣ��W���A�����嗬�̖{�R�E���{���ƒ�P����w���V�����݂���������Ƃ̏d�v�Ȓ��p�n�ƂȂ��Ă���B���̗����[�ɂ��āA�x�����t�́u���i�k�v�������嗬�Ƃ��邪�A���̍����͎�����Ă��炸�A���̉\���͍������̂̎��ۂ͕s���ł���B���l�ɂ��ẮA�ނ�����䒘�u��M�G�L�v�ɓ��v�t���u���ƃm��M�Җ�v�Ə̗g���ċ��������֓��̓�����Y�q�哹�S�Ƙa���̐����P���q����Ăƒ}���̒��F�吆�v���i����t�̕��j��3�l�̓��̐����P���q����Ă̂��Ƃł���\�����������ƍl������B
�@���Ɂu���V�n���䎛����V�v�ƋL����钲�䎛�́A���݂̑��{��s�h�@���ɓ��^�嗬�{�R�E�{�����̖����Ƃ��ď��݂��邪�A�{���͓����嗬�̗v�@���̖����ł���A�u���@�N�\�v�ɂ͉��i19�N�i1421�j�̑n瑂����邱�Ƃ��ł���B����V�͓������̑m�V�Ɛ�������A���̖V��̎������͕s���ł��邪�A�E�̓���t�̋L瑂Ɂu���X���������V����V�A�t�����t�҃n�������a��v�Ƃ���悤�ɁA���̓��v�t�̑t���ł͌��Ƒ��̒�����G�Ƌ��Ɏ����I�Ȉ������߂Ă���B�Ȃ��A��G�̕��E����́u������L�v�ɂ��A�i��3�N�i1506�j����4�N�ɂ����Đ���͗v�@���̑O�g�E�Z�{���ł����Ό���瑉̉���s�����肵�Ă���̂ŁA���̂悤�ȓ���I�Ȍ𗬂Ɋ�Â��āA���炭����V���t�Җ����G�Ɉ˗��������̂Ɛ��������B�܂��E�́u�\���v�ɂ́A���̏���V�͌�ɓ����嗬�ɉ��߂��ĎⒿ�Ə̂�����瑂ׂ��Ă���B
�@�����āA�Ō�Ɂu�ӌ���Z�@�����E瑐M�V����A��ʐ\�M�A��іV�����v�ƌ����邪�A���̓��́u��Z�@�����v�Ƃ͓����嗬�̖��@����11����k���������t�i1438�`1503�j�̂��ƂŁA����t���u����k����w�����S�Җ�v�Ƃ��̊w���Ԃ���^���Ă���悤�ɁA�h�c�̓����t�S����̋��w�I�Ȏ��͎҂ł���B������l�̈ӌ��Ƃ��ċL������Ă���u�@�M�@����v�̓`�͖��ڂł��邪�A���v�t�́u�\��v�̕M�L�҂Ƃ��Ė����ɋL����Ă���u��іV�����v�Ƃ́A����2�N�i1488�j�ɖ{瑏���`���咣���ċ��s�E���{���i�������j���Ɨ�������s�y�@���^�t�i1444�`1528�j�̓����ҁi����ɂ͓��^�t�Ƃ͓����̌Z��Ɠ`������j�ŁA�����t���{�������������ē��^�t���}�����ꂽ�Ƃ����B����t�͉E�Ɂu����@�ؑm�i�{�\���m��j�v�ƋL���Ă��邪�A����͓��^�t������t�������{���i�������j��ޏo����ۂɁA�O�ɓ����悤�ɖ{瑏���`�𗧂Ăĕʔh���������嗬�̖{�\���Ɉڂ�A���̎x���̂��ƂɌ�ɖ{�����ɓ������Ƃ����o�߂�����A����Ɋ�Â��āu�{�\���m�v�Ɠ���t�͒��L�������̂ƍl������B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�ۓc���{���̓��v�t������8�N3���ɐ��s�����V�t�Ɋւ��ẮA�����嗬�̑��ɁA���s����јa���̓����嗬�E���^�嗬�E�����嗬�Ƃ����A������{瑏���h�O���[�v�̋��͂āA���ꂪ��������Ă��邱�Ƃ��m����B���̂悤�ȏ���h�O���[�v�̌𗬂͓��R�ꎞ�̂��̂ł͂��肦���A������x�������ꂽ�W�ł������Ƒz�肳��邪�A�E�́u���v�t��L�^�v�Ƃ�����̎j���̏�ɕ\�ꂽ���̈�f�ʂł������Ƃ�����B
�@���i���w�̑c�E�����t�i1385�`1464�j�̎��Ղ⋳�w�ɂ��ẮA����܂ł̊o�����ŕs�\���Ȃ�����x�X���y���Ă����B�����āA���ɂ��̋��w�̒��Ɏ������{�����v�z�ɑ��ẮA�����嗬���ǂꂾ���A�܂��ǂ̂悤�ɂ��Ă��̐ێ�ɗ͂�s�����Ă������ɐG��Ă����B���Ȃ킿�A�����E���~���̓����t���N���i1449�`52�j�Ɂu�������q�v�Ƃ��āA�������w�I�ȉ~�n�����}���Ă��������t����@�告�`���Ă��邱�ƁA�܂����{�����̂ł���8��E���i�t�i�`1460�j�����K���S������ŁA��9��E�����t�i1415�`87�j��E�̓��v�t�����s����ɕ����ē������w���w�K���Ă��邱�Ƃ�A���̉ߒ��̒��œ����t�̎咘�u�{��O�o���v113����u�꒟���v�u�l�����v�f���̒�������ʂ���ȂǁA�����t�̔ӔN����Ō�ɂ����āA�����嗬�̑��͂������ĂƂ����ėǂ��قǂ̏W���I�ȍ�Ƃ��s���Ă���B
�@�O���ŐG�ꂽ�悤�ɁA����3�N�i1494�j�ɖ��{���͘a���ɕz�����Ă���A�����͂���ȍ~�̋E���ł̊����̋��_�ƂȂ����ł��낤���A�E�̂悤�Ȃ���ȑO�̋E���ł̓����嗬�̊�������Ɏx�������̂́A�u���v�t��L�^�v�Ɍ���ꂽ�����E���^�E�����̏��嗬�Ƃ�������h�O���[�v�ł͂Ȃ��������Ƒz�������B�����āA����͏���h�Ƃ�����悤�ɁA�u�@�،o�v�̖{瑓��ɏ���͂Ȃ���{�I�Ɉ�v�ł���Ǝ咣�����v�h�ɑR����O���[�v�ł͂��邪�A�E�̓����嗬���������������̓����E���^�E�����̏��嗬���Ȃ��ł����̂́A���̖{瑏���`�Ƌ��ɓ����t�̋��w�ł͂Ȃ��������Ǝv����B
�@���@�������t�͓����t�Ƌ��ɖ��{���i�������j��ޏo���������@���c�t�i1397�`1478�j��薭�@������p�������A���w�I�ɂ͓����t�̏Џq�ȊO�ɓ��F�Ȃ��ƕ]�����قǂł��邩��A���̔��i���w��{�����v�z�̏K���ɂ������ɈႢ�Ȃ��B����A��іV�����t���E�q�̂悤�ɒ���2�N�ɏ�s�y�@���^�t�Ƌ��ɓƗ������ۂɓ����嗬�̉����Ă���A���w�I�ɂ������t�̋`�Ɏ��i�����Ƃ����B���^�t�͂��̔ӔN�A�������w�̔��i���ӂ�ے肵�Ď��ʕi���ӂ𗧂āA�{������_�ɑ��Ė{�ʉ���_���咣���ċ��d�ɑΗ�����Ɏ��������A���̍ۂɓ����t�͗��҂̒���ɐs�͂����Ɠ`������B
�@����ɑ��āA�����嗬�Ɠ����t�̋��w�Ƃ̌����������Ղ������邱�Ƃ́A���̂Ƃ���ł��Ȃ��B���������A�����̓����嗬�̎��Ԃ͂قƂ�Ǖs���ɋ߂��A�l���ł����Ε���13�N�i1481�j���ɓ����嗬�̋��w�ɂ������炸�ɑ�Ύ����L�t�̖�ɋA�˂����Ƃ������������t�i1428�`�j�����邪�A���̒�����������A�����t�̋`�̉e���͗]��Ŏ�ł��Ȃ��B�������A�����ň���ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��A���̉��������獶�������t���܂߂������嗬���ł̗��`���`������u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗����������̑��݂ł���B���͐�ɂ��̗����������Ɠ����t�̖{�����v�z�Ƃ̊ԂɌ�����֘A�����w�E�������A�������ꂪ�F�߂���Ȃ�A�E�̓����t�̋��w����ĘA�g���Ă��������嗬���̏���h�O���[�v�Ƃ����e�[�u���̏�ŁA15���I�����ɂ��̗������쐬���ꂽ�\���͂�͂肠�邩�Ǝv����B
�@���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA���̎���������1400�N�ォ��1500�N��ɂ����āA�����t�̋��w����ȕR�тƂ��Č`������Ă����ł��낤�E������h�O���[�v�Ƃ�����g�́A�����嗬�̖{�����v�z�A���ɓ����嗬�ɂ����Ė{�����v�z���`������Ă�����ɂ͌������Ƃ̂ł��Ȃ���ȏ����Ă����ƕ]���Ă悩�낤�B�����āA���̏�̒�����o�ꂵ�āA�����t�̋��w���̂��̂�A���̉e�����Ɍ`�����ꂽ�����嗬�̖{�����v�z����ѓ��@�{���`�ɋ����ᔻ�������A�ߑ��{���`���咣�����̂��L���@���C�t�ł���B
�@���s�E�v�@���̑�13��E���C�t�i1508�`76�j�́A�E�́u���v�t��L�^�v���쐬���ꂽ����8�N�i1499�j���9�N��̉i��5�N�ɋ��s�Œa�������B7�ɂ��ėv�@���̑O�g�E�Z�{���ɂē��x���A��i5�N�i1525�j18������{�������^�t�ɏA���āA�V��w�𒆐S�ɁA���^�t���A�₷��܂ł�3�N�]��C�w���Ă���B���̍ŔӔN�̓��^�t�Ɏ�N�̓��C�t���A�w�������R�͕s���ł��邪�A�E�ɂ��G�ꂽ�悤�ɁA���̎����̓��^�t�������t�̋��w�������ᔻ���đΗ�������ɂ��Ă������Ƃ��l����A���ʂƂ��ē��C�t����ɓW�J����{�����v�z����@�{���`�ւ̔ᔻ�̋����I��Ղ��A���̏A�w�̒��ŏ������ꂽ�Ƃ������悤�B���^�t�̋��w�́A�E�L�̑�іV�����t��c�������t�i1471�`1558�j�E�ؐ����Y�t�Ȃǂɂ���Čp�����ꂽ���A���C�t�͓��^�t�ӔN�̓������w�ᔻ�����������p���������t��A�u��o�Ǖs���v�@�u�������s�V�_�v�����ē����嗬���w�ᔻ�ɗ͂��X�������Y�t�Ɛ[�������A���̉ߒ��̒��Ŏ���̋��w���\�z���Ă��������Ƃ���������A���̎�N�ł̓��^�t�Ƃ��琂͌���I�ȉe������C�t�ɂ����炵���ƍl������B
�@����ȓ��C�t�ł͂��邪�A�u���v�����C�V�����m�{���V�֕ԏ�v��
1�A���C�̋��\�M�Д�����������R�{�厛�j���e�Q�w�V���N�l�������������V�A���R���o�A�܌������j�����V�A�V���Z���є��������R�m�@�僒����j���V�e���s��j�e�������u���m�@�僒�O���L�B�����j���m�@��_�`�X���o���N���C�����j�c�B���C�v�n�N�A���m�@����N���m�]�嗬�ⓚ�m���n�ꌾ���s�o�X�B����腖����O�m�ⓚ�����g���V�e�A���R���S��l�m���`�������u���m�@�僒��~�V�ߏ�[�d�i���g�v�e�A����e���O�j���e�����Z�V���B
�Ƃ���悤�ɁA���\3�N�i1530�j23�̎��ɕx�m�̐��R�{�厛�ɕ����ē�����11��̓��S�t�Ɏt�����A�ߑ���������сu�@�،o�v�̈ꕔ���u���֎~����u�������u���̖@��v���w��ŁA���̌�ɋ��s��a���ɂē��@���ɍO�ʂ������A�V��6�N�i1537�j8���ɑ���̏��t�ɔj�܂���Ĕ�����A�����E���u�̍m��ւƓ]���Ă���B
�@����͓��������嗬�ł��h�c�̓����t�ȗ��A�ߑ��̑�����@�؈ꕔ�̓��u��e�F����X���ɂ���A����䂦��x�͎���ے肵�������嗬�̋��w���A�E�̓��^�t����т��̖�킽�����K���������w�Ɋ�Â��čč\�z���悤�Ƃ������C�t�̕ϑJ�ł͂��邪�A�����Ƃ��Ă͂��Ȃ范�������̂Ȃ̂ŁA���̎��͂ɂ������Ȕg��𓊂����������̂Ƒz�肳���B��s�y�@���^�t�̑���q�ɂ�����ؐ��@���C�t�i1532�`94�j���V��7�N�i1579�j�ɒ��������u�^�����`���v���܁E��s�y�i�߂ɂ́A�u�s����u�o�T�A�s��q�v�̈ꕶ�ɂ��āA
�ߔN�����j�����p�S�V�ޏ@�����j�A�������n�]�q�������u�n���i���g�A�����n���������j�����n�������u�ҁA�h�ߕs�A�˘��̃j���V�������u���`���A�@�N��������N��N�V�ԃj�σX���̃j��k��X�j�j�V�A�҃e�x�m�g�^�����������`��g�A����l�������A���b�j�@�N�]�J�e���ρA�������ϖm��A�̃j���������j�ޘ��Z�����]���t�ϖV��m��A�Ή]�]�B
�Əq�ׂ��Ă���B�����Ɏw�E����Ă���u��l�v����C�t�ƒf�肷���㔎�����̌��������������̂ł���A���C�t�̑����E���u�̔ے肩��m��ւ̓]���͒h�߂̋A�˂��ړI�ł��������ƁA���͂̐l�́u�����v�ƌ������ƁA�����Ă��̌�ɓW�J���ꂽ���C�t�̕x�m���R����Ƃ����s�������܂߂āA���ꂪ�x�m�Ƌ��s�Ƃ̋`��������炵���Ƃ����F���������ɂ͎�����Ă���B
�@���C�t�́u���d�L�v�ɂ�
��k����m���������n�{�R�m�Z���w���F�����呼�R�j�������E�X�j�w��X�A���n���j�̃e������k���������嘦�m�m�A�҃e掓�����k�A�ɓ��m�ɓ��m�Z�P���n�̃e������k�����A�V��Ύ��j�A���n�t�L���R�j�A���n���X�d�{�j�A���������k���n�t��j�A���s�m�m�h��l��l�ܐl�O�l���N�A�X�{�\�j�B
�Ƃ���A������k����ѓ�����k�̍����E���ނԂ�ƁA���̌��������w�̕s�U�ɂ��邱�Ƃ��w�E����Ă���B���ɁA�ɓ��≺��̓�����k���x�m���R�ɋA�����A���s�̑m���������嗬�ɉ��߂������Ƃ��Q����Ă���A���̂悤�Ȍ����I���ɑΏ����邽�߁R�ɁA���C�t�̋��w�I�ȗ��Ē������A�c�і[�����t�̋��w������嗬�̕s�����E�s���u�̋`�ւ̔ᔻ��ʂ��čs��ꂽ�ł��낤���Ƃ́A�e�Ղɑz�������B
�@�O�������ɂāA1400�N����1500�N��ɂ����Ă̎��������ɁA�������w�����ʊ�ՂƂ��Č`������Ă����ł��낤�����E���^�E�����E�����Ƃ������嗬�̋E������h�O���[�v�Ƃ�����̒�����A�܂��������C�t�͓o�ꂵ���Əq�ׂ����A����䂦�����嗬���̖{�����v�z���c�і[�����t�̖{�����v�z�̋����e�����ɐ��������Ƃ����o�܂ɂ��āA���C�t�͕����ʂ�n�m���Ă���A���ꂪ�u���d�L�v�Ɍ�����
���s���A�Z�{�\�j���m���v�E���ᓙ�m�]�N�A���i�n�M�m���A�_�J�m��i�ʃV�e�̐S�A�m��i�n���Ӄm��i�m�K��A������k�m�@��n���ރm�@����X�B�R��������m������k�n�����m�냒�s�V�e�m�@���m�S�l�\���ʃm�䏴���m������e�[���������܊�Z�����n����m�ʖځA����m�p�J��B
�Ƃ����������̌��t�ƂȂ��ĕ\���Ă���B�����āA���C�t�͂��̏���h�O���[�v�Ƃ�����̒��̓��^�嗬�̋��w�Ɏ���̑�����ߒu���āA���̑R�W�ɂ������������w�ɔj�܂������A����ɂ��̓������w�Ɋ�Â����{�����v�z�ɂ���ĕs�����E�s���u�𗧂ĂĂ��������嗬�̎咣��A�����嗬�̑����E���u���`�Ƃ��đ�Ύ��ɉ��߂������������t�̓��@�{���`��r���A�ߑ��{���`�𐳖ʂ��牟�����Ăē����嗬�̍Č���ڎw���Ƃ����`�ƂȂ��Ă���B���A���̊W���ȒP�ɐ}�����Ă݂�ƁA���̂Ƃ���ł���B
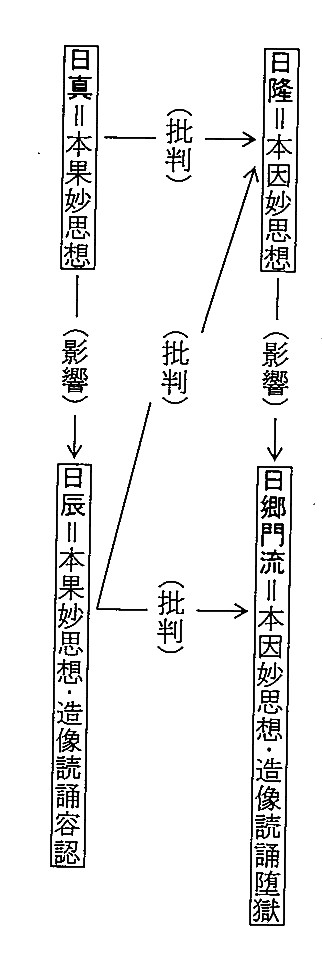 �@���͂ɂĂ��̔ᔻ�̎��Ԃ̈�[�ɐG��Ă݂邪�A���̂悤�ȓ��C�t�̍�Ƃ���A�������͑O�X���̖���8�N�́u���v�t��L�^�v�ȍ~�ɁA����܂ʼn��₩�ȋ��͊W�ɂ������E�����h�O���[�v�Ƃ�����ɁA���̂悤��2�̕ω��̂��������Ƃ�m�邱�Ƃ��ł���B1�́A�O�ɂ������q�ׂ��悤�ɁA��s�y�@���^�t���������w�ɋ����ᔻ�������đΗ��W�ɓ��������Ƃł���A���ꂪ��ɋ��łȋ��w�I�ȑ������C�t�ɂ����炵�����Ƃ��O�L�̒ʂ�ł���B������́A�قƂ�ǎ����������Ȃ���A��ɓ������w�ɋ���Ǝ��̖{�����v�z���`�����������嗬�i�����嗬�������j���A���̖{�����v�z�������I�ȗ��t���Ƃ������@�{��
�@���͂ɂĂ��̔ᔻ�̎��Ԃ̈�[�ɐG��Ă݂邪�A���̂悤�ȓ��C�t�̍�Ƃ���A�������͑O�X���̖���8�N�́u���v�t��L�^�v�ȍ~�ɁA����܂ʼn��₩�ȋ��͊W�ɂ������E�����h�O���[�v�Ƃ�����ɁA���̂悤��2�̕ω��̂��������Ƃ�m�邱�Ƃ��ł���B1�́A�O�ɂ������q�ׂ��悤�ɁA��s�y�@���^�t���������w�ɋ����ᔻ�������đΗ��W�ɓ��������Ƃł���A���ꂪ��ɋ��łȋ��w�I�ȑ������C�t�ɂ����炵�����Ƃ��O�L�̒ʂ�ł���B������́A�قƂ�ǎ����������Ȃ���A��ɓ������w�ɋ���Ǝ��̖{�����v�z���`�����������嗬�i�����嗬�������j���A���̖{�����v�z�������I�ȗ��t���Ƃ������@�{��
�`�̌����I�咣�Ƃ��āu�������u���v�̃X���[�K�����f���āA�ߑ��{���`�ɋ����R�������Ƃł���B
���̂悤�ȗ�����āA���C�t�͓��������嗬�ɂ���Ȃ���A�ߑ��{���`���̗p��������嗬�̍Č��҂Ƃ��āA���̕s�����E�s���u��ے肷�邱�ƂƂȂ����̂ł���B
�@�Ȃ��A�{�͂Łu���v�t��L�^�v�𒆐S�ɑf�`�����E������h�O���[�v�̓����ɁA�����̎��ӏ��܂߂Ēʎ��I�Ɏ����A�����悻���̂悤�ɂȂ�B
�i�����N�i1429�j�@�@�c�і[�����@�u�l�����v�����s�̏��R�ɉ�B���ēƗ���錾�����Ɠ`���N�ԁi1449�`52�j�@�@�����E���~�����������Ɏt�����Ė@�告�`����
���\3�N�i1459�j�@�@���{���������ɂē����u�꒟���v�����ʂ�
����3�N�i1463�j�@�@���{�����v����v�����ɂē����u�l�����v�����ʂ�
���@5�N�i1464�j�@�@�c�і[�����A��
����13�N�i1481�j���@�@�������������嗬����Ύ����L�ɉ��߂�
����14�N�i1482�j�@�@�d�{�E�ۓc�E����̏O�k��Ύ��ɕ����đ��_������������
���@�@�N�@�@�@�@�@��Ύ����L�A��
����2�N�i1488�j�@�@��s�y�@���^�{������n�����Ĉ�h�Ɨ���
����3�N�i1494�j�@�@�����@�a���̉Ɖ��~�i��̖{�`���j�𖭖{�����v�Ɋ�i��
����8�N�i1499�j�@�@�u���v�t��L�^�v���쐬�����
�i��3�N�i1506�j�@�@������G�̕��E������l�N�ɂ����ĒҖ{���ɂČ����A�̉���s�Ȃ�
�i��5�N�i1508�j�@�@�L���@���C�a��
��i2�N�i1522�j�@�@���^�������w�Ɉً`�������đΗ�����
��i5�N�i1525�j�@�@���C���^�ɏA���đ�w�����w��
���\���N�i1528�j�@�@��s�y�@���^�A��
���\3�N�i1530�j�@�@���C�x�m���R�{�厛�ɕ����ē��S���u�������̖@��v���w��
�V��6�N�i1537�j�@�@���C�@�u�������̖@��v���̂ĂĎߑ��{���`�𗧂Ă�
�@
�@
�@�Ō�ɁA�����嗬�ɑ����Ȃ���A���̖{�����v�z���c�������C�t�̋�̓I�Ȍ������Љ�悤�Ǝv�����A���͖{�����v�z�ɋ����֘A������Ƃ��čݐ�����̗L���̖������グ�A���̍ݐ������F�߂邱�Ƃɂ���Đ��藧�ߑ��{���`�ɂ��ďq�ׂĂ݂����B
�@ ���̏œ_
���C�t�́A�u���v�����C�V�����m�{���V�֕ԏ�v��
�{�\�������m�\�O�ⓚ����ݐ��V�g����탌���^���B�x�m��k�m���w�⃒���e���J�g�v�e�ߑ����E�v�m�]�]�B�{�������m���n�n�E�m����m���m�\�X�����V�^���ҍƁA��{�������m���M�L�i���h�g�v�e�ߑ����̃��g�v�t�������W�A����m�����O�E�T�����@�i���h�g�\�@�僒���~���e�S�A�o�ߌ䏑�{�������S�Z�P�m�[�ӕs�m�s�o�j�V�e�������m�S�j�v�q���j�C�Z�e��\�B�\�O�ⓚ���j�]�N�A�߉ރm���@�n�m��m�كm�@�V�g�폑�^�����A�������l���L�o�e���@���l�m���ʃt���@�n���^���كm�@�V�g��\��B���[���l�߉ރn�@���Ę��@�c�n�@�V�g���m��\��B�����m���`���ȃm���L����B
�u�ϐS�{���������v��
��t�A�ݐ����탒��e�����F�A�����B���t�A���e�ߑ��j���t�e���O���A���B���^��n�E���O���A���B�R���j�ݐ����탒�s�����T���n�{�ʉ��탒�s���T�A�s�����{�ʉ��탒���n�ȃe�厖������m��@�����X���@�j�B���@�j���X�����n���N掃����X�B���X���J���N掃��̃j�������l�t�A�����e�߉ރj���v���v�����V�A�z�X�l�]���Ό����ȃe�ߑ����ăe���e�s���M�h���B���n���B���q�m�i���A�J���m�`�߃������A���n���������`���ȃe�׃e���`�m�𗗃X���]�����̃j�A�����A�g�؈䘦�Z�Y���⃒���ʃt���e���j���V�ƌ����s�����T�؊G������ޏo���X
�u���d�L�v��
���l�A�ݐ��E�v�m�߉ރn�䓙�J����m����������N�A���^�S�o���Z�V�J�̃j�o�ߌ䏑���׃V�{�g�ݐ�����L�V�|�����q�L�B���`�`�����j�X���j�������\�O�ⓚ�����ݐ����혦�_�`��B���`�����j�X���j�s���m��`����B
�ƁA���ꂼ��L���Ă���B�����ɂ��ƁA�c�і[�����t���u�\�O�ⓚ���v�̒��Ŏߑ��̍ݐ��ɉ���͂Ȃ��Ɛ������Ƃ���A�x�m��k����������Ďߑ���E�v�̕��Ɣ��f���A���ꂪ�u�{�������v��u�S�Z�ӏ��v�̕����Ƃ悭���������̂ŁA���@�̉���Ɏߑ��͕s�p������A��������҂͑����Ǝ咣�����Ƃ����B�܂��A�����u�\�O�ⓚ���v�́u�߉ނ̖��@�͖̏�̉ق̔@���v�Ƃ����������āA�ߑ��̖��@�Ɠ��@���l�̖��@�Ƃ̊Ԃɂ́A���������̏�̉قƗ������فA���邢�͔��ĂƖ��Ƃ�����E�̖@�̏�̑��Ⴊ����ƁA�x�m��k���ȉ��������Ƃ��w�E���Ă���B
�u�ϐS�{���������v�ɂ��A�ߑ��̍ݐ������F�߂Ȃ����Ƃ͖{�ʖ��ߑ��̉����F�߂Ȃ����ƂƂȂ�A����̋@���ɂƂ��Ė{�ʖ��ߑ��͖��v�Ƃ��đ��h�����A����䂦�u���B���q�̂Ȃ肠����v���������i�̎���p��g�ƋK�肵�Ă���Ƃ����B�����āA����Ȏ`�Ɋ�Â��āA��������u���a��Ԏ��v�Ɍ�����
���@���l��o���̖{���얳���@�@�،o�̋���ߑ��v�������̔@���̉摜�͈�j�l��ւƂ��A�����ؑ��͒N���s��ɁA�c�c
���̕������߂�����̂�����A�؊G�̑��������e���Ȃ���ނ��o�������ƒQ���Ă���B�Ō�́u���d�L�v�ł́A�ȏ�̂悤�ȔF������A�u�@�ؖ�v�W�v�ł͎ߑ��ݐ��ɉ��킪���邱�Ƃ�_�������A����͓����t�́u�\�O�ⓚ���v�̎咣��j���Ƌ��ɁA�ߑ��s�����̋`�����_�j������̂ł���Ƃ������C�t�̖ژ_�����q�ׂ��Ă���B
�@���̍ݐ����킪���邩�Ȃ����Ƃ������́A�����܂ł��Ȃ��u�ϐS�{�����v��
�ݐ����{��m���@�V���n�ꓯ�j���~��B�A�V�ރ��n�E�A�����n���B�ރn��i�A���n�A�[��ژ�����B
�Ƃ����ꕶ���ǂ����߂��邩�ɋN�����Ă���A�u�ރ��n�E�v�Ǝ����ꂽ�ݐ��{��̈�i�́A�����ʂ�E�v�����Ȃ̂��A����Ƃ�����v�����F�߂�̂��ۂ��Ƃ������ł���B����ɁA���̎�E�̖����v���̖{���ɃX���C�h�����āA�ݐ��{��̈�i�Ɠ����悤�ɖ{�ʖ���E�v�ƋK�肵�A�����{�����ɔz����̂��A����Ƃ��{�ʖ��ɂ�����v�͂���Ƃ���̂��Ƃ����{�ʉ���̗L���������ɘ_������B
�@���̌��ʂƂ��āA�����@�ؖ{��̋v�����{�̎ߑ�����і{�ʖ��ߑ����E�v�Ɍ��肳��Ă��܂��A�Ō㖖�@�ŏ�s��F�̎��o��тт��@�c�E���@���A����v���邱�Ƃ����肵�Ă��鎄�����ɂƂ��āA�ߑ��͖��v�ƂȂ�A���̑������s�v�ƂȂ�B�{�����v�z�ɑ��Ė{�ʖ��v�z�𗧂ĂāA�ߑ��{���`���咣������C�t�Ƃ��ẮA���̘_���I�����ł���ݐ����킨��і{�ʉ���̑��݂��A���Ƃ��Ă��_����K�v���������̂ł���B
�A �����t�̌���
�@�O�̓��C�t�̎w�E�ɏ]���āA�u�\�O�ⓚ���v�̖`���w���E�ݐ����펖�x�ɂ���ē����t�̌��������X�����Ă݂悤�B
�@�悸�A�ݐ�����ɂ��āA���@�@�̈ӂƂ��Ė��@������̎��ł���A����̖@���{��̓얳���@�@�،o�ł���Ƃ�����O�����������ŁA�O��o�_����ьܕS�o�_���\�E�F���̍��{����ł���A�����ݐ��͉����̏I���ł���E�v�Ȃ̂ŁA�����ɉ���� �_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƁA�ݐ����킪�ے肳��Ă���B���̏ؕ��Ƃ��āA�V��E���y�̌o�߂ł́A�u���`���܁v���\�̌d���`�̑�܁E�����̑�ӂ𖾂���
�����{�n���^�����Z�ߘ����^�A���N鍳�������T�������召���O�@���B�̃j�]�t�{�s��F���������������P���s�g�B��j����瑒��������؎��j�V�e���j鍳�������召���@����B���j���]�����n�ʃV�e���X鍳�@���B�Ș������V���������v���V�q���B�E�E�E�̃j�m�k����������n���N�̘����n�V�@�j�B
�̕���A�u�@�ؕ���v����̎l�ߎO�v�̓��A���̋v������̒n�O���Ƒ�O�̑�ʌ���������
�v������g�ߋ����n�m�ߐ����גE�g�A�n�O������B�����j���ԃ���m�l�����n�g���郒�גE�g�A���V�J��������Җ�B
�̕��ɁA�u�@�،��`�v����ɐ������O�틳���i�����̗Z�s�Z�̑��E�����̎n�I�s�n�I�̑��E�t��̉��ߕs���߂̑��j�̑�j�Ȃǂ������A�@�c�̌䏑�ł́A�u�x�ؓ����a��Ԏ��v��
���ʕi��栂֖j�A���O瑖����栃��e�j�V���Ȃ�B�o���ɖ��L���V�B�������E�����א߁E�召���v�n�@���e���B�{��̖@��͔@���g�ؘ��]�]�B�����ʕi�ߑO�V�ݐ��V�v�͈Œ����؉e��B�ߋ��ɕ��V���ʕi���Ҙ����瓙�]�]�B
�̕���A�u�]�J�������䏑�v��
��e�H�N�A�،��V���ʉ~�����F�T���όo���V�����}�v�������n�@���B���e�H�N�A�ޓ����O�n�҈ȃe�����_�X���n�V�𑴌o�����^���g�������j�A�ȃe�������X���V���O�܉���m�y��B
�̕��A�����āu�@�@���v��
����Ώ�����œ���ɏ\�����E���o���̑��F�E�V�l���̉_�̔@���ɏW���ČA��W�E��i�̏������A����o�E�������o���̐��S�]�����A�ߋ��ɖ@�،o�̎��������Ă��肵�l�X�A�M�͂�͂����ĎO�ܘ��o�_���o�����ǂ��A���x�߉ޕ��ɒl���Ė@�،o�̌��������ތ̂ɗ�R���܂������āA���O�̌o�X�����Ƃ��ē����Ȃ�ƌ�������B
�̕��������āA����炪���ׂĉ�����ߋ��ɒu���ĒE�v�������ɒu���A����䂦���O瑖�⟸�ς̏����̉~�͊F�E�v�ƂȂ�̂ŁA�ݐ����킪���藧�]�n�͂Ȃ��Ƃ��āA
�@���@�`���F�n�ݐ�����~�j�E�v�j�惊��m�e�ȃe���E���҃��ߋ���j�A嫒E����{��V�e���ȉߋ��{��t�V��s�j���X���@����g�A���{�嗬�ʘ��{�Ӗ�B���\���V�ݐ����혦�`����B
�ƌ��_���Ă���B
�@���ɖ{�ʉ���ɂ��ẮA�O�X�e�Ŗ{�����v�z���`������Ă����ۂ̓�ւƂ��Ė{��������s��F�̋`�Ƌ��ɖ{��������i�{�ʉ���̔ے�j�����グ�A�u�\�O�ⓚ���v�́w���E�ݐ����펖�x�̈ꕔ�̋L�q�ɂ���Đ����������āA�����O�e�ɂ��Čf�����B���͑����̏d��������Ȃ���A���̑S�̂̊T���������Ύ��̒ʂ�ł���B
�@�O�X�e�ł��G�ꂽ�悤�ɁA���̖��͖{�ő�����n�O�̕�F�̎O�v�̓��A����v�ɑ�����߂��œ_�ƂȂ��Ă���A�悸�u�@�،o�v�]�n�O�o�i�ɂ�
�䃌���e�����������j���V�e���e���X���R�g���Ő��o���A�]�V���㘦�@�փ��A���V�e�T�`�����V�e�V���A�߃������e���T���S���B
�Ƃ���A���o���{�ʖ��̎ߑ����n�O�̕�F�̓��S���N���������Ƃ��āA�{�ʉ��킪������Ă���B����ɑ��āA�E�ɂ��f�����u�@�ؕ���v����̎l�ߓ�v�̑��ɂ�
�����j�v������g�ߋ����n�m�ߐ����גE�m�A�n�O������B
�Ƃ���A�V���t�́u�v������g�v�Ƃ��������Ȃ����A���y��t�́u����L�v����ɂ�
���j���������A�{���ʃj��V�A�ʌ�߃N�n�V�A�K�j�ߐ��j�E�X�B�w�X�n�O���҃�
�ƌ����A�n�O�̕�F�ɑ��鉺�킪�u�{���ʃj��V�v�Ǝ߂���Ă���B�����t�͂��́u�{���ʃj��V�v�̎߂ɂ��āA����͈��ʂɌ��邱�ƁA�܂�����͐l�V�̋@�̏�ɘ_������̂ł���Ƃ��������܂��ė��Ȃ����Ƃ̕K�v������������ŁA
�����@���Ӄn�ȓ�{�唪�i��s�v�t���ߖ{���m�@�|�m�B�����i���Ӄn�Ȗ{�ʃ��ۖ{���j�{�����ݘ����ʕs�@�@�،o���ȃe�t�V��s�j�A�ȏ�s�{���O�k���E�m��؏O����j���@���l�����ŏ����탒�������N��B
�Əq�ׂĂ���B���͎t�̊�{�I�ȗ��������������̂ŁA�u�@�،o�v�{�唪�i�̈ӂ́A�{�ʂ�{���ɐۂ������ʕs��̖��@�@�،o����s��F�ɕt�����A���̖{�����̏�s���{������і��@�̏O���ɍŏ��̉�����قǂ����Ƃ������̂ł���B�����t�͂��̕��Ƃ��āu�]�J�������䏑�v��
�����j�n�O��E�����F�A��j�n�Z�X���R�g���O�k���E�j���o���i���B��j�n���e���ߑ��j�����v���ߗ������S����q�i���B�O�j�n�O�k���E���O�����ŏ����혦��F��B�@�L���������h���V���֒��߃Z���������F�j�B
�̈�i�������āA�v���̖{�ʐ����ɂ��{�唪�i��s�v�t�����邱�Ƃ��w�E���A���̖{���ϖ��̖Ō㖖�@�ł̏�s�ɂ��ŏ�����ɁA�u��q���{���n�v���ߑ���B���혦�{�t�n�v���n�O��v�Ƃ����{�ʎߑ��Ɩ{����s�̊W���܂܂��āA���y�́u�{���ʃj��V�v�Ǝ߂������A���ƂƂ��Ă͉���͖{�����Ɍ���Ƃ��Ė{�ʉ����ނ��Ă���B
�@�Ō�ɁA�t�́u�{���ʃj��V�v�̎߂ɂ��āA�E�`�܂��Ȃ�������߂ē�`��������ĉ�ʂ������Ă���B���`�́A����͖{���Ɍ��邯��ǂ��A�{���̈��ʂ͌ݗZ���ē��̂ł���ӂɖāA����͈��ʂɘj��Ɩ��y�͏q�ׂ��Ƃ����B���`�́A�{�ʂɉ���͂Ȃ�����q�͂���Ƃ������́B�܂�A�{�ʎߑ��ؓ��̖��@�@�،o�̎�q��{����s������āA��؏O���ɉ��킷��ӂ𑍂��āu�{���ʃj��V�v�Ǝ߂����Ƃ����B�����āA��O�`�́A�v���{���ɍ����Ɠ��l�ɖ{�唪�i��s�v�t�̖Ō㖖�@�̉����������A��͂荡���̂悤�Ɂu�ރ��n�E�A�����n��v�ŁA�ݐ��E�v�Ɩ��@���킪���邪�A���@����̗��ɂ���ݐ��E�v�̕ӂ������̉���̖@�ɏ]���Ė{�ʎ�Ə̂��A����ɉ���̖{������{��������킹�āu�{���ʃj��V�v�Ɩ��y�͏q�ׂ����̂Ɖ�ʂ��Ă���B
�B ���C�t�̌���
�@�{���ł́A���C�t�̒��u�@�ؖ�v�W�v�̖����Ɏ��^����Ă���w�ݐ�����L���V���x�ɂ���āA�t�̌����������Ă݂�B�E�q�̒ʂ�A���́w�ݐ�����L���V���x�̈�i�͓����t�́u�\��ⓚ���v�`���́w���E�ݐ����펖�x�̎咣�ɔ������邽�߂ɏ�����Ă���A���ɂ��̑O���͓����t�̋`�̒���̔j�܂ɓ��Ă��Ă���B
�@���C�t�́A�悸�u�ݐ��͒E�v�A�Ō�͎�n�v�Ƃ�����v�̑��z�͂����܂ł��ꉝ�̑Δ��ł����āA�ݐ��ɂ͎�n�E�̎O�v�����݂��邱�Ƃ�͐����Ă���B���̏؋��Ƃ��āA�t�͓�̃O���[�v�̕��������Ă���B���O���[�v�́A�O�������Θb��ƂȂ��Ă���l�ߓ�v�̑��v������̒n�O�̕�F�ɂ��Ắu�@�،o�v�]�n�O�o�i�E�u�@�ؕ���ꊪ�E�u����L�v����̈�A�̌o�߂ɁA��痁u����㐳�L�v��
�{���ʎ�g�n�ҁA�������`�@���s�X����F�������׃j��������V�A�؉ʔV�����^�׃j����X�B�̃j���c�N�{���ʎ�g�B
�̕��������������A�u����L�v����́u�{���ʃj��V�v�Ɠ�痂̎߂ɖ{�ʉ���̑��͖����ł���Ǝw�E���Ă���B���̃O���[�v�́A�E�̎l�ߓ�v�͂����܂ł���\�I�Ȏl�߂������������ŁA������߁X�ԁX�ɂ͓�v�����݂����Ƃ��ؖ����邽�߂̈����ŁA�l�ߓ�v�̌�Ɍ�����u�@�ؕ���v�����
�����Ԑߐ߃j��㐢�Ã���m�n�m�גE�g�A�������W�B�����ȃe�̌̃j�B�@�����ݐ_�ʔV�́A�t�q���v�吨�ЖҔV�́A���݃j���N��B
�Ɓu����L�v�����
�㐢�A��n�E���O�A���B�������`�O�O���O���A�O�O�����A�O�O����i�A�O�O���t���A�O�O���g��A���s�����A�@�������j�B�E�E�E�O�i���j������j���X�퓙���B���`�m�k�����������A�����O�O�j��j�׃j�O������X�ꕧ�昦��m�E����B
�̕��ɁA��틳���̑��E�����̎n�I�s�n�I�̑��Ɍ�����u�@�،��`�v�����
���j�E�V���j�n�V���j�탆���R�m�Ԕԃj�s���}���吨�Жғj�v�X�����B
�Ɓu���`���܁v�����
���E���g�n�Җ�V�e���l�����N�B���e�n������A���e�n���j�����n�A�݃j���N�R�g�V�m���B�����̃j�]�t���y���Ԕԕs���g�B�E�E�E�̃j���������O�O�j�F�L���J�퓙���O���̖�B
�̕���������Ă���B��O�̃O���[�v�́A�@�c�╶�́u�]�J�������䏑�v��
���e�����Ō�j�L���O���B�������]�N�j�n�P�L�����혦�ҁB��Z�n�@�V�ݐ��l�\�]�N���B�s���o�m���@�������N���E�s���^�t���o���B���n���j���e���@�j�ݐ����������҃n�Q�X�j�����V�e�A��������@�F���N�s�L�k�B
�̕��ƁA�u�ϐS�{�����v��
�n�O��E�s���n�o�e�����j�ҁA���@���N�V�ԃn����E������B�@�����j���V�V�B�l�˘���m�ȃe�������׃V�e���g�ݐ�������߃��E�Z�V���B���N�V�e掉L�j���n�v���̃j�s���J�V���B��Z�n�@�V�ݐ����O�l�����@������B
�̕��̓�ŁA�@�c�̈ӌ��Ƃ��čݐ��̉���i�����j����������Ă���Ɠ��C�t�͏q�ׂĂ���B
�@���ɁA����͐l�V�̋@�̏�ɘ_������̂ł���A�ߑ��ݐ��͓�捪���̂��߂̐����ł��邩�牺��͂Ȃ��Ƃ��������t�̎w�E�ɑ��āA���͎l�O�i���N�O�E�e���O�E���@�O�E�����O�j�̓��@�O�ɖ��ꍇ�ł����āA�����O�ɖƉ��킪����|���q�ׁA�t�͏��߂������Ė�����������������̋`���ؖ����Ă���B
�@����ɁA�u�{���ʃj��V�v�̌�ɓ����t����������߂̓�`�𒀎��������Ă���B���`�́u����͖{���Ɍ��邯��ǂ��A�{���̈��ʂ͌ݗZ���ē��̂ł���ӂɖāA����͈��ʂɘj��Ɩ��y�͏q�ׂ��v�Ƃ�����߂ɂ́A����͖{���Ɍ���Ƃ������A����ł͉E�Ɏ������{�ʉ��������o�߂͂ǂ������̂��Ɣ��_���Ă���B
�@���`�́u�{�ʂɉ���͂Ȃ�����q�͂���Ƃ������́B�܂�A�{�ʎߑ��ؓ��̖��@�@�،o�̎�q��{����s������āA��؏O���ɉ��킷��ӂ𑍂��āw�{���ʃj��V�x�Ǝ߂����v�Ƃ����ӌ��ɂ��ẮA���߂Ė{�ʂ̍ݐ��ɉ��킪���邱�Ƃ������A�u�{���ʃj��V�v�̌��{�ʎߑ����ؓ��������@�@�،o�̎�q��{���̏�s���t������A��������킷��Ɖ��߂���̂͌��ŁA�u�{���ʃj��V�v�̎ߕ��͖{����s���g���ւ鉺������������̂ł����āA��s���s�Ȃ��O������Ɋւ��Ă̎ߕ��ł͂Ȃ��ƒf���Ă��邪�A�l���Ă݂�ƁA����͔��Ɋ�{�I�������Ȏw�E�ł���B
�@�����āA��R�`�́u�v���{���ɍ����Ɠ��l�ɖ{�唪�i��s�v�t�̖Ō㖖�@�̉����������A��͂荡���̂悤�Ɂw�ރ��n�E�A�����n��x�ŁA�ݐ��E�v�Ɩ��@���킪���邪�A���@����̗��ɂ���ݐ��E�v�̕ӂ������̉���̖@�ɏ]���Ė{�ʎ�Ə̂��A����ɉ���̖{������{��������킹�āw�{���ʃj��x�Ɩ��y�͏q�ׂ����́v�Ƃ�����ʂɂ��Ă��A��Q�`���l�A�u�{���ʃj��V�v�̎߂���s�̍O�ʂɖ����̂ł͂Ȃ��ƒf������ŁA�u�ϐS�{�����v�́u�ރ��n�E�A�����n��v�̕��͎�E�����̈ꉝ�̈ӂł����āA�ݐ��ɂ�����͂��邪�A���ʂ��R���ŁA�������Ō�̏O���ɖ����߂Ɂu�ރ��n�E�v�Ƃ����\���ƂȂ����Əq�ׂĂ���B
�@�ȏ�́A�w�ݐ�����L���V���x�̑O���œ��C�t�������t�̌����ɉ����������̂���܂��ł��邪�A���C�t�͎���̍ݐ�����E�{�ʉ���̋`�ɂ���ɋᖡ�������Ă���B�悸�A�u�@�ؕ���v���\�̏�s�y��F�i�߂Ɏߑ��ƕs�y��F�̋������̑����������
��e�H�N�A�߉ރn�o���V�e��蹰�V�e�s���J�B���n���������Ӄ\�B�����j�V�e�����N�n���\��B���e�H�N�A�{���j�L���j�n�P�߉ވȃe����������V�V���A�{�����j�n�L���P�s�y�ȃe�僒�����ŃX�V�����]�]�B
�̎ߕ�����A���ʁE�{���L�P�E�t���E�Ō�̕s�y��F�̉���ɑ��āA�ʈʁE�{���L�P�E�����E�ݐ��̎ߑ��̒E�v�ƑΔ����A����䂦�ɍݐ�����͖����Ƃ��錩���ɑ��āA����͓��@�O�ɖ��ߕ��ł���Ɖ�ʂ��Ă���B��������Ă��Ȃ����A�t�̋`�ɏ]���A���̑��Ɍ����O������A���ꂪ�ݐ�����ɊY�����邱�ƂƂȂ낤�B
�@���ɁA�{�ʂ̏�y�͎���̋ł��邪�A����͗����A�ς̖}�l�ɑ�����̂Ȃ̂ŁA�����{�ʂ̐��@�ɉ���̋`�������A����y�ɖ}�v���������ƂƂȂ�̂ŁA�{�ʂ̎���ɉ���v�͂Ȃ��Ƃ����ӌ��ɑ��ẮA�����������̖}�l�͎l�y�����̎���ɋ����Ȃ���A����y�ɓ����y�̎v�����Ȃ��̂ŁA����͋Ɨ͂̏����ł����āA�{�ʂ̔@�������y�̉ߎ��ł͂Ȃ��̂ŁA�{�ʂ̍ݐ��ɉ���͑��݂���Ƙ_���Ă���B
�@�Ō�ɁA����͓����t�̌����Ƃ��Ă���������̂ł��邪�A����͖{���Ɍ���A����ȍ~�̍ŏ��������璆�ԍ����Ɏ���܂ł̉��\���E�G�O���̐߁X�ԁX�̉���́A�����܂ł��n�v�ɉ���Ɏ�̖���^�����u����̎�v�ł����āA�^���̉���ł͂Ȃ��Ƃ����ӌ��ɑ��ẮA����͋v������E�������E�̋@�ɖ��D�`�ł����āA�^�`�ł͍����̍ݐ�����̂悤�ɁA���Ԃ̏����ɂ�����͂��邪�A���̍ۂ̉���̖@�͖̂{���̖��o�ł���Ɖ�ʂ��Ă���B
�@�ȏオ���C�t�̍ݐ������F�߂錩���̊T�v�ł��邪�A�O���ł��w�E�����悤�ɁA�{�����v�z���������邽�߂ɂ́A�����������{��������̋`�i�ݐ�����E�{�ʉ���̔ے�j�Ƌ��ɁA�ߑ��̖{��������s��F�ł��邱�Ƃ��K�{�̏����ƂȂ邪�A������{�ʖ��v�z�ɗ��r���Ė{�����v�z��ނ��悤�Ƃ�����C�t�́A���R�̂悤�ɖ{��������s��F�Ƃ�����`�ɂ��ً`�������Ă���B
�@�t�́A�{���{�ʂ͎ߑ��ꕧ�̏�̕������ʂł���A�ʕ��ʕ�F�̈��ʂł͂Ȃ��A��@�̓ł���Ƃ�����������������ŁA�u��_�c���ӏ��v��
�{������F�n�{���C�s����F�j�V�e��{�����j��B�{�����m�]�n�ߑ������ʖ�B�W�j�n�{�ʃn�����߉ށA�{���n������s��m��B�Ӄn��s���n�����߉ޘ��{��������q�i���J�̃j嫉g�o���ʈʃj�A���N�׃j�����J�v�����t�혦�����A���V��F�����`���������ʃj�Ӄ��{��������s�]��B
�Əq�ׁA�{�����͎ߑ��̈��ʂł���A�{����s�͖{���C�s�̕�F�ł͂��邪�A�ǂ��܂ł��ߑ��̖{�������̒�q�ł���ƋK�肵�āA�u�S�Z�ӏ��v�Ɂu�{�ʖ��߉ޕ��A�{������s��F�v�Ƃ���̂́A�ߑ��Ƃ̎t��W���������߂ɁA��s��F�����ʂ̕�F�n�Ɏ~�܂��Ă���ӂ��q�ׂ���ł���Ɖ��߂��Ă���B
�@�Ȃ��A���̂悤�Ȑ����̎d���͓��C�t�̋��w�I��Ƃ̓����̈�[���悭�����Ă���B�܂�A�ǂ��炩�Ƃ����ΓV��E���y�̘Z�啔�̎ߋ`�������E���Đ������镔�����������t�̖{�����v�z�Ȃǂɂ́A�����̌����_��V��E���y�̌o�߂���Ĕ��_���A���̈���Łu�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗���������������嗬�̑��`���ƔF�߂���C�t�́A�����Ɍ�����{�����v�z�I���ɂ͉�ʂ������邱�Ƃɂ���āA����̋��w�̌n���j���邱�Ƃ�h���ł���B�����ł��G���悤�ɁA���ɗ��������̕����̉�ʂ͎t�ɂƂ��ďd�v�ȍ�Ƃł������B
�@����܂ŁA�c�і[�����t�̎ߑ��̍ݐ���{�ʖ��ɉ���͖����Ƃ�������x�m�̓�����k���u�{�������v���̕��ɕ�������Ɣ��f���ĐM�p���A����Ɏߑ��͖��W�ƍl���Ă��̑������֎~�����ƔF�������L���@���C�t���A����ɑ��Ďߑ��̍ݐ�����і{�ʂɂ����킪���݂��邱�Ƃ��ǂ̂悤�ɏؖ����Ă��邩�A���̂���܂��������A�����Ė{���͂ǂ��܂ł��ߑ��̖{���ł����āA��s��F�ł͂Ȃ��Ǝt���咣���Ă���|�ɐG��Ă����B
�@�O�ɂ��x�X�L�����悤�ɁA�{�����v�z�͏@�c�̌䏑�Ɏ����ꂽ���`��j�ɁA�{��������Ɩ{��������s��F�̋`��������ď��߂Đ�������ƍl������̂ŁA���C�t�����̓�_���E�̂悤�ɔے肵�����_�Ŗ{�����v�z�͂��̐����v�f�������A�����ɓ����t�̋��w�ɋ���Ǝ��ɒz�����{�����v�z�Ɋ�Â��Đ��藧���Ă�������嗬�i�����嗬�������j�̓��@�{���`������A���̐�����Ղ�D���Ă��܂������ƂƂȂ�B����䂦�A�{�ʖ��̎ߑ���{���ƒ�߁A���̑������������Ƃ������C�t�̎ߑ��{���`�̐��������_����邽�߂ɂ́A���̑��ɂ����悻���̓�̍�Ƃ��K�v�ł������B
�@���́A�ߑ��̑�����F�߂āA�������������@�c����єh�c�E�����t�̋L�����������Ƃł���B����ɂ��āA���C�t�͎��̂悤�Ȍ䏑���ʂƓ����t�̏�����ʂ���Ă���B���Ȃ킿�A�u�ϐS�{�����v��
���{�����ב́A�{�t���O�k����j���V��j�A���������@�@�،o�����E�j�߉ޖ��E���A�ߑ����e�m�n��s�����l��F�A����E���ӓ����l��F�n�t���g�V�e���V�����j�A瑉��E�������召������F�n���������V�e��n�j�@�V�����J�_�t�������B�\���������n���V�^�}�t��n����j�B�\�X��瑕�瑓y���̖�B�@�L�����{���n�ݐ��\�]�N�j���V�V�B���N�V�ԒA�^�������i�j�B�������N�V�ԃn���昦�ߑ��n�ޗt�E����׃V�e�m�m�A�������q�j���ρE�@�،o��瑖哙���ߑ��n�ȃe����E���������׃X�e�m�m�B����������������P�g�������j���^�L�T���ʘ����B�����V�e���@�j�f�n�e�������L�߃��o���Z�b�B
�u���v��
��e�]�N�A�V��E�`���̍O�ʂ����n���鐳�@�����B�E�E�E���e�]�N�A��j�͓��{�T����腕���ꓯ�ɖ{��̋���ߑ���{���Ƃ��ׂ��B�����̓��̎߉ށE����E�O�̏����A���ɏ�s���̎l��F�e�m�ƂȂ�ׂ��B��ɂ͖{��̉��d�B�O�ɂ͓��{�T�����y������腕���ɐl���ƂɗL�q���q������͂��A�ꓯ�ɑ��������Ăē얳���@�@�،o�Ə��t�ׂ��B
�u���@�ؑ�ڏ��v��
�{���͖@�،o�����E�ꊪ��i�E���͑�ڂ����Ė{���ƉV�g�胀�@�t�i���ɐ_�͕i�Ɍ�������B�����ւ����l�͎߉ޔ@���E�������Ă����ł��@�،o�̍��E�ɉV�g�V�B�B�����ւ����͏\���̏����E������F���������肩�����Ă܂�ׂ��B
�u�^�Ԏ߉ޕ��䋟�{����v��
�߉ޕ��䑢���̌䎖�B���n�捅��肢�܂�����܂��܂��ʌȐS�̈�O�O��̕��A���茰���܂��܂����B�E�E�E�@�،o�ꕔ�A�䕧�̌�Z���ɂ�ݓ����܂��点�āA���g�̋���ߑ��ɂȂ��܂��点�āA���ւ�Č}�q�����܂��点�������ցB
�u�l������߉ޕ����{���v��
����L�����j�߉ޕ��̖ؑ���̓��]�]�B�E�E�E�����������g�̕��ɂĂ��͂��܂���ցB
�u���Ꮧ�߉ޕ����{���v��
�O�E����A����ߑ���̎O�����ؑ��������h�ߓ��Ꮧ�B�E�E�E�@�،o�j�]�N�A��l�ט������̃j���X�����`�����A�@�L�������l���F�߃j���V�L�������]�]�B���̐S�́A��̏��l�߉ޕ�����A���݂ɂ͓��X���X�̑召�̓�ЁA�㐶�ɂ͕K�X���ɂȂ�ׂ��Ɛ\�X����B
�u�؊G�J��V���v��
���ɗL���O�\�A�E�E�E�O�\�ꑊ�̕��̑O�ɖ@�،o��u�L���Ă܂�ΕK�X���~�̕��i���]�]�B
�u��y�@�d���v��
��腕���̓��j�@�،o�̎��ʕi�̎߉ޕ��̌`������������铰���A���܂���͂��B�����ł������ꂳ�����n����ׂ��B
�̔��ʂ̌䏑�ƁA�O�f���������t�̏����u���a��Ԏ��v��
���@���l��o���̖{���얳���@�@�،o�̋���ߑ��v�������̔@���̉摜�͈��l����ւƂ��A�����ؑ��͒N���s��ɁA�E�E�E�B
�̈ꕶ�ł���B
�@���́A�l�{������{�ʖ��ߑ��Ɩ@�{�����閭�@����������䶗��{���Ƃ̊W�𖾂炩�ɂ��āA�ߑ��{���̐����������łɂ��邱�Ƃł���B�t�́m�{���ⓚ���n��
��e�]�N�A���㈫���̖}�v�͉������ȂĖ{���ƒ胀�x����B���e�]�N�A�@�،o�̑�ڂ��ȂĖ{���Ƃ��ׂ��B
��E�f�́u���@�ؑ�ڏ��v�̕��A�����āu���@��䶗����{���v��
���@�@�،o����{�����{��q�k�B���֑ɗ��͕����͌������ɂČ�ւǂ��A�O�������̌�t�A��̏��l�̐����̈�B
���̏����ɂ��A�@�c�����̖{���Ƃ��Ė��@�̙�䶗��{����F�߁A�u�ϐS�{�����v�Ɍ�����
���s���얳���@�@�Ԍo�������j�{�嘦�{�����^�L�N�s�Z�V���B
�̕�����A�l�@�̗��{������������|���w�E���Ă���B
�@�����āA���̗��{������̂ǂ̂悤�ȊW�ɂ���̂��Ƃ����A���Ƃ��u��_�c���ӏ��v���l�E���ʕi�߂ɂ�
���j�l�@���{���n�ȃe�������ד���`���{���m�똦���A���@�n�@�N��ǖߑ��n�@��Lj㘦�A�L�����s���b�B�ĉ��n�_�X�����������탒���n�ȃe���@���L���`���{���m�b�B���@�����n�׃��߉ށE��s�V�t�̖�B�{���ⓚ�������،o�ߐ���B���j�l�@���{���]���������߁E�o���V�^�}�t�똦���A�l���{���n�{���{�ʘ���A����p��g�@����B�����@���V�{���������������ؓ��V�^�}�t���o����E�����l�@�o�����ŏ���B
�Ƃ���A�@�{�����ǖ�A�l�{�����Lj�ɏQ�����āA���҂͕s���Ȃ��Ƃ���邪�A�ĉ��̋`�Ƃ��Ă͔\���E��������юt��̕ʂɂ��A���@���̖@�{���̎��`����������Ă���B�܂��A�����̎����ɂ́u���@�ؑ�ڏ��v�̕��������A�L���v�̎O��̖{���ɂ���
�����n�L�����{���n�g�C���@�����s���j�]����B�A��O���@�j���n�v���{�����`��B�ꎆ����䶗��n���i���V���A���n���ʘ��V���n���{�����Ӗ�B�g�n�������L�\������������F�����ҍL���{�����`��B�L���v����혦�{���F���j�@�c�����e��B
�Əq�ׂāA�l�{������{�ʖ��ߑ��͗v�̖{���A��䶗��{�������{���ł���̂ɑ��āA�L�̖{���͙�䶗��S�̂̊G�����E�������ł���A�v�̎ߑ�����шꑸ�l�m�͕K�����������{���ł���̂ɑ��āA���L�̗��{���͋@���ɉ������đ������邱�ƁA�����Ă��̎O��͂��ׂď@�c�����e���ꂽ�{���`�Ԃł��邱�Ƃ����Ă���B�������A�u�ϐS�{���������v�ł͖{���ɑ��̂ƕʑ̂��A�E�̍L�̖{���̖̂{���Ƃ��A�v���̐l�@�{����ʑ̖̂{���Ɛ������Ă���B
�@��{�I�ɂ́A�ȏ�̂悤�ȍ�Ƃɂ��A���C�t�̎ߑ��{���`�͈ꉝ����ʂ��������Ă���Ɣ��f����邪�A�t�̏ꍇ�͂�����d�v�ȍ�Ƃ��c����Ă���A���ꂪ�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗��������̏����Ǝߑ��{���`���ǂ̂悤�ɒ��߂��邩�Ƃ������̍�Ƃł���B�������A���̍�Ƃ̗l�q�͓��C�t�̒���ɐ����������A�����ɂ�����ڍׂɐ�������ɂ͗����������̏������e������K�v������A���͂ƂĂ����̗]�T���Ȃ��̂ŁA���C�t�́u�����_�`�v���炢�����̓_�����グ�Č�����Ɏ~�߂Ă��������B
�@�悸�A�t�͖{���{�ʂ͎ߑ��ꕧ�̈��ʂł���A��s��F�͎ߑ��̒�q�ł����Ė{�����ł͂Ȃ��Ƃ����A����̖{�ʖ��v�z�̑匴�����m�F���A���̏�Łu�S�Z�ӏ��v�`���Ɍ�����
�v�����������{���{�ʔV��A�{�n����p��g����瑁A��s��F���Ēa�{��V��t���@
�̈ꕶ����A�{�n����p��g�@������{�ʎߑ����{���{�ʂ̎�ł���A���̐�瑂���s��F�A����ɂ��̍Ēa���u�{��̑�t���@�v�ł���Ƃ����O�҂̊W��ǂݎ���Ă���B�����āA�u�{�������v��
���n�n�E������A�^�n���혦�@���B
�ɏn�E�̋���Ƃ����u���v�Ƃ͉������i�̎���p��g�ł����āA�v�������̎���p��g�ł���{�ʖ��ߑ��̂��ƂłȂ��ƒf���Ă���B���̓�̎���p��g�̈�ڂɂ��ẮA�u�S�Z�ӏ��v��
���A�{�ʘ����@�@�،o���{瑁A�������{�ʃn�]�����ʃi���n�{���{�ʃj�n�v��B���ʘ��E�v�A�ݐ���i�m��i�B�׃����ɗ��������������ϐS��B�䓙�J�׃j�n������B��n瑃n���{�n�����g��B
�Ƃ̐����Ɋ�Â��āA�u�����̖{�ʁv�Ɓu�{�̖{�ʁv�̈�ځE����ł���Əq�ׂĂ���B�܂�A�u�����̖{�ʁv�͎��O�E瑖�E�{��Ə��i���A�@�����ʕi�ɂĊJ�������]�����ʂ̖{�ʂł���A�������i�̏n�E�̕�g�Ȃ̂ŁA�u�{�i�v���j�̖{�ʁv�ł���{�ʖ��̎ߑ��i�v�������̎���p��g�j�ɂ�ꡂ��ɋy�Ȃ��Ɨ��ĕ�����̂ł���B���̖{�ʂɁu�����̖{�ʁv�Ɓu�{�i�v���j�̖{�ʁv�ʂ��āA�����������Ŗ{������s�ɑ��Ċ�{�I�ɔے肳���{�ʖ��ߑ����u�����̖{�ʁv�Ƌ��ق��ĉ�ʂ��A���̌��ʂƂ��Ė{�ʖ��ߑ���i�삷��̂́A���C�t�̗������������߂ɂ�����傫�ȓ����̈�ł���B
�@���ɁA�v�������̎���p��g�ɂ��āA���[���{���E���v�t�́u���c�������v�̉��ߓ��ɂ��A�v�������Ƃ͖{���̖������ł���Ƃ���咣�ɑ��ẮA�v�������̎���p��g�͖{�ʂɌ����Ė{���ɘj��Ȃ��Ɩ������A���̗��R�Ƃ��āA��g�͏C�����ʂ̕��ł��邩����ʂɘj�炸�A������g��{�������ƋK�肷��Ɛg�y�̑��z���������邩��Ƃ����B�܂��A�E�ɓ��C�t���ߑ��{�����w������ؕ��̈�Ƃ��ċ������u���v�̕��ɂ��āA���������t���ߑ��Ə�s���@�́u�݈唺�v�̋`�Ɋ�Â��ē��@�{�����咣���A���{���̓��v�t���ߑ��E��s���ꕧ�ł���Ƃ��������t�̋`�ɂ���āA����v�̋v�������̕�g����s�E���@�Ɖ��߂��邱�Ƃɂ��āA���C�t�́A���@�͏�s��F�̉��g�ł���A��s��F�͎ߑ��̒�q�ł���Ƃ����O�q�̊W���Ē��A�ߑ���������n�E�̎O�v���݂̕��ł���Əq�ׂāA�����̋`��ނ��Ă���B�����āA�u�S�Z�ӏ��v��
�\��A���혦�@�،o���嘦�{瑁A����p�g�n�{�A��s���@�n瑃i���A��J���ؘ����ʕi�g�ҒE�v���ʘ����꘦�{����������B��������n�^��B
�������ĉ���̋��傪�O�l�ł��邱�Ƃ������A
���j��������@�،o�m�A���혦�@�n�{�����V���@�@�،o������B�{�������o���C�s�V�e���`���߉ޘ��o���ύs�E�����j�o�����Z�j�A���Z���������L��{�s��F���m�A�o�{�ʘ��@���ʈʃj��������p��g�g�]��B�����{�����혦�@�،o������j�L���g�{�n�E��瑁E�]�����@�،o������m�n�]��B���n�荆��B��^���t�����{�n�E��瑃����A����p�g�n�{�A��s�E���@�n瑖�g�B���j�荆�j�W�V�e���혦�@�،o�����嘦�{瑖m�A���V����p�g�n�{�m���X��s�E���@�n瑖m�B�����i���������j�J��ށA���v�J��k�A���j�J�e���გ�q���V�e���������܃���掃X��������k���B
�Ƙ_���āA����p�g����{�ʖ��ߑ�������̋���̖{�n���邱�Ƃ��������Ă���B
�@
�@�]���A�����嗬�̖{�����v�z�ɂ��ẮA���������ɐ��������c�і[�����t�̖{�����v�z����������Ď�E�{瑘_���_������悤�ɂȂ�A����Ɋ�Â��Ė{���_�E�{���_���\�z���ꂽ�Ɛ�������Ă����B���͂���܂ň�A�̎O�̘_�l�ŁA�����嗬�̖{�����v�z�̌`���ɊW�����Ȑl���̋��w�⒘����T�ς��A�]���w�E����Ă��������t�̋��w�̉e���Ƃ����`���f���������悻�����Ă݂����A���ʂƂ��Ă͉��߂Ă��̈��ʊW��ǔF����`�ƂȂ����B�������A�{���_�Ɋւ��ẮA���ꂪ�{�����v�z�`���̌��ʂɍ\�z���ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�ނ���{���`�̗��t���̂��߂ɖ{�����v�z���v�����ꂽ���ƁA�����Ă��̖{���`���̂͏@�c�ӔN�̋��w�I�ȓ��B����ёf�ӂ��p������Ƃ������̂ł��邱�Ƃ��q�ׂĂ݂��B
�@����Ȓ��A���܂����̈ʒu�����܂炸�ɕs����Ȃ܂܂Ȃ̂��A�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗����������ł���B���̗����ɓ����t�̋��w�̍��Ղ��F�߂��邱�Ƃ͊��q�������A���̖{�����v�z�̍\�����̂��̂܂ł��������w�̉e�����ɂ���ƍl���邱�Ƃ͓���B���ɁA�u�{�������v�̕��͂��̉��~���ƂȂ��Ă���u�O��͑`���ʑ��������v�Ɍ�����l�d���p�I�Ȏ~�ς̍����Ɋ�Â��āA���̖{�����v�z���\�z����Ă���\���͍����̂ł͂Ȃ����Ɨ\�z�����B���e�ł́A���ӂ̕������E�₵�������邱�Ƃɂ���āA���̕ӂ�̖�����T��Ȃ���F�����Ă݂悤�Ǝv���B
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@