
�@

�@
�@
�@
�@
�����I�v�@�n����
�@
�@
�͂��߂�
�@
�@���ʁA�����k���Ƃ��āA�N�Ɉ�x�w�����I�v�x�s���邱�ƂɂȂ����B
�@���Ƃ̋N����́A��N�Ԃ̌��w�̐��ʂ�p�������Ȃ��甭�\���悤�Ƃ����P���Ȃ��̂ŁA�����͎��ǂ���A���t��̔j�ܘ_�������^���邱�Ƃ����S�ƂȂ����B
�@�������A�{���ړI�Ƃ���Ƃ���́A�x�m��Ύ��@����A�@���O�̎����L�������A��ǁA�T�����邱�Ƃɂ���āA���ؓI�ɘ_���悤�Ƃ������̂ł���B
�@���̈�ߒ��Ƃ��āA���Ɠ`���@��̎v�z��ՂɂȂ��Ă��銙�q�A�������̓V��Ȃ�тɓ��厛�W�����̉�ǂ��A���l�̏����ɂ���Ēn���ɐi�߂Ă���B�������������_���Ƌ��ɁA�@�w���r�Ɏ����鐶�j���̏Љ���s���Ă����\��ł���A�ǎҏ����ɂ͗l�X�Ȍ�ӌ��A�䎶�ӂ�M�]���鎟��ł���B
�@
�@���a56�N10�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����k�������ꓯ
�@
�@
�@
�ځ@�@�@��
�@���@���̖@��ɂ���
�@�@�@�@�@�@�͂��߂Ɂ@
�@�@�@�@�P�A�����̍l����
�@�@�@�@�Q�A�����Ɨ���
�@�@�@�@�R�A�����̖@�傪�����Ă�������
�@�@�@�@�@�@�͂��߂�
�@�@�@�@�P�A�v���Ƌv�������̑���ɂ���
�@�@�@�@�Q�A�@�̂ɂ����鎖���̍���
�@�@�@�@�R�A���̖@�̂ɂ���
�@�@�@�@�S�A���s�̖��@�@�،o�ɂ���
�@�@�@�@�T�A������l�̖��
�@�@�@�@�U�A�����`�ɂ���
�@�@�@�@�V�A掖@�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�I����
�@���@�����E���ј_���̒t����j��![]()
�@�@�@�@�@�@�͂��߂�
�@�@�@�@�P�A�����_���ɂ���
�@�@�@�@�Q�A�@���b�r�E�t��q�̖@��ɂ���
�@�@�@�@�R�A�@�́E�@�告���y�ѓ�ӑ���
�@�@�@�@�S�A���ј_���̔j�܂ɂ�������
�@�@�@�@�T�A����{���ςɂ���
�@�@�@�@�U�A�ȐS�̖@��ɂ���
�@�@�@�@�V�A�a�����o�E���@�����܂��Г��ɂ���
�@�@�@�@�@�@�E��y�т܂Ƃ�
�@�@�@�@�@�P�A�n�����w�̖��_
�@�@�@�@�@�Q�A�v�@�����C�ɂ���
�@�@�@�@�@�R�A�n���w��Ɠ��C�̗ގ��_
�@�@�@�@�@�S�A���Ƃ̐ܕ��A�L�闬�z
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�n���w���掖@�s�ׂ��߂����āA�@���͂��悢�整�����A�X�ɖ��͎Љ�S�̂ɍL���낤�Ƃ��Ă���B�u�J�̖҂������ė��̑�Ȃ��m��v���Ƃ��A�n���w���肪�@��I�ɂ��A�Љ�I�ɂ��A���ɍ��[�����̂ł��邱�Ƃ�m��̂ł���B
�@�Љ�I�s���́A���ꂪ�����ɍ��[���Ƃ��A�܂��A�L�͂ɂ��ĕ��G�Ȃ��̂ł����Ă��A����Љ���Ƃ��đ傫�����W���A���O�̗͂��K���������������ł��낤�B��������X�̓w�͂Ȃ����Ă͂Ȃ����ʂ��Ƃ����B
�@�������A�@��̋����́A��X�@��̎҂��ӔC�������ċ������Ă����Ȃ���͂Ȃ�Ȃ��B�܂��āA�Љ�I�s�����܂߂đn���w����߂��鏔�ԑ�́A�ЂƂ��ɖ@��̋����ɂ��̍��������邱�Ƃ��l����A�Ȃ������X���M��ڎw���҂̐Ӗ��͏d��ł���ƌ���Ȃ���͂Ȃ�Ȃ��B
�@�����@��̋����́A�z���ȏ�ɍ��[���[���ł���B��X�ɂ͑�_�Ȕ��z�̓]���ƁA�傢�Ȃ�@��̌��r�A�����Č��̂ɂ��ނ����Ƃ��M�S����̕����C�s���v������Ă���B����Ȃ����č����̖��͉�������͂����Ȃ����A�܂��@�傪�@�����S�邱�Ƃ͂��肦�Ȃ����Ƃ���L���ׂ��ł���B �@ ���������n���w����߂��鏔���́A�ЂƂ�n���w��Ǝ��̊ԑ�ł���ƍl����͖̂�Ⴂ�ł���B���̒[�͏��Ȃ��Ƃ��S�N�͑k���čl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����ېV�ɂ���ē��{�͊J������A���m�̕������A������͂��߂�ƁA����܂ł̎O�S�N�̍����̔������A���{�l�͂�������ׂāu�ǂ����v�Ƃ��Ē��d���A�ێ悵�Ă������B���X������������Ȃ����A����Ɍ����͐��m�����͕������S�̕����ł���B����ɑ��ē��{�̕����͐��_�����S�ƂȂ�B�Ȃ����`���̒��Ŕ|��ꂽ�S���������镶�����A�ꋓ�ɗA�����ď����������͂����Ȃ��B�����������}���ɁA�������������̂܂܂ǂ�ǂ�����ďo�������������̂́A�`�����}�Q�ɔw�L�p���l�A�S����ȁA���Ȃ����̂��Ƃ��Љ�ł������B
�@�����E�o�ς����ʕ����E�@���Ɏ���܂ŁA������̕��������̉e�����ʂ��̂͂Ȃ��B�����Ă���́A���̗���ƂƂ��ɂ��悢��[���������Z�����āA�����ɂ͓Ǝ��̖{���E�`��������������قǂ̉e���ƂȂ��Ă����̂ł���B
�@�����������Љ�̒��ŁA���@�������Ă��̗�O�ł͂Ȃ��B�@�傪�����Ȃ�e�����A�����Ȃ鋶���������B�܂�����Ȃ�͋����̐�����ȑO�̖@��͂�����A�Ƃ������Ƃ��l����̂��{�_�̈Ӑ}����Ƃ���ł��邩��A�ς����͌�q����Ƃ��āA���ꌾ�������Ă���������́A���،ȐS����Ƃ����@�傪�A���������̉e���ɂ���Ď���ɊO�������Ă������Ƃ������Ƃł���B�������ďo�������������w���ꉞ�������w�ƌẮׂA���̋� �w�͂��̂�����O�����S�̋��w�ł���B�O��y�݂ł���͂��̖{��̉��d���A�P�Ȃ镨�̂Ƃ��ēƂ�������邢���鍑�����d�_����d�{���^�U�_���́A�������w�̒�����o��ׂ����ďo���B
�@�@��̐������A���O���@����吹�l�̌�����A�t�푊����ĉ�炪���Ɍp�����Ƃ��玟��Ɍ`�[�����āA�ю��l�ɖ@���A�Ȃƌp����Ă���Ƃ������Ƃ��A�_�b�I�Ɍ����悤�ɂȂ����B�����ȋ��c�ł����������́A���̕ω������قNjC�ɂȂ�Ȃ��������A�ꕔ�������ĎЉ�炻��قǖ��ɂ�����Ȃ������B
�@�������A���Ƃ��͌����ɂ��Č����A���Ȃ����j�I�����Ƃ��Ă̗B����l�����t�@�������ē��@�̐������咣����́A��ɑm���L�u���甭�s���ꂽ�A�n���w���@��ւ̌��̎����Ɍ����邲�Ƃ��A������|���ҁA���邢�͎n�߂���@����U������ҁA�����Đ^���Ɏ��̐^����Nj�����҂ɂƂ��ẮA���܂�ɂ��c�t�ȁA�s���S�ȁA���j�I�����������A�����͂������ʐ����ł��邱�Ƃ��A�ǂ����Ă��F�߂Ȃ���͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@�Ƃ�����A���̊O�����S�Ɖ������������w�́A���̌�n���w��݁A�n�����w�މ����ƂȂ��Ă����̂ł���B
�@���̑n���w��̋}���Ȕ��W�́A���s�����獂�x�������A�X��GNP���E���ʂ��ւ�Ɏ�����{�̍���ƁA�藣���čl���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���̐[���ȕ��s���́A���O�ւ̎����ɂ��肽�Ă��B�l�X�͕������߂āA���銾�𗬂����B���͂��ׂẲ��l�ɗD�悵���B���ꂪ���̓��{�̎p�ł���B�n���w��͂��̋@�ɏ悶�Đl�X�ɐM��������̂ł���B�u���̐M�S�����́A�T���ɂȂ�܂���v�ƁB�m�������ދC�����ŁA�l�X�͑n���w��ɓ�����B�����āA�m���ɑ����̉�����o�ϓI�ɖL���ɂȂ��Ă������B����͂���������Ə̂��l�Ԋv���Ə̂��čX�ɐܕ��͓W�J����A����݂͂�݂�Ԃɂӂ���Ă������̂ł���B
�@�������A�L���ɂȂ����̂͌����đn���w��������ł͂Ȃ������B���{�S�̂��L���ɂȂ����̂ł���B�����A���Ɋnj��I�ɂ����������邱�Ƃ��ł��Ȃ������̉���́A�Ȃ�B��������{���̌����ŖL���ɂȂ����ƐM�����̂ł���B�ނ��吹�l�̕��@�A���@���@�̐M���A����ȂƂ���ɂ���͂��͂Ȃ��B
�@�����ē��{�̌o�ϐ����ƂƂ��ɑn���w��͔��W���A�n���w��̔��W�ɂƂ��Ȃ��āA�Ɠ��ȑn�����w�͏o���������Ă����̂ł���B�]���̖������w�͂��̖@��I���ׂ̂䂦�ɁA���̐����ɏ悶���n�����w�ɍR�����ꂸ�A���ɏ@��S�̂��n�����w�ɕ����Ă������ʂƂȂ�B�ہA�����Ă����ƌ������́A�ނ���A���Ƃ��ƕ������S�ɐ��藧���Ă����@��̖������w���A�n���w��̏o���ɂ���čX�ɓO�ꂳ��āA�n�����w�Ƃ��ď������ƌ����ق����K��������Ȃ��B�Ƃ�����n�����w�ł́A�{�����A���d���A��ڂ��A�M�S���A�������A�����A���{���A����Ƃ�������̂������I�ɉ��߂��ꂽ�B
�@�����č��A���̓y��̒��ŁA�{���͍����n�߂Ƃ��鐔�X��掖@�s�ׂ��A�n���w��ɂ���ĂȂ��ꂽ�B�������� ��́A�@�傪�O���i����)���S�̋��w�Ɋׂ����Ƃ�����A�o��ׂ����ďo���s�ׂł������ƍl����ׂ��ł��낤�B
�@��X�������̑n���w��������z���āA�^�̓��H���@�̖@����@����S�点�邽�߂ɂ́A���̂Ƃ�����悭�������āA��X���g�̋����ɂ��鍡�܂ł̏펯�Ƃ������̂���������̂ċ����āA�傢�Ȃ锭�z�̓]��������K�v������B�����āA����́A�����ȍ~�S�N���̋��w�ւ̌��ʂ��Ӗ�����̂ł���B
�@���ꂩ��q�ׂ悤�Ƃ���u���̖@��v�́A���@�̗��r�_�E��Ղ��������̂ł����āA�����𐳂����������Ȃ���́A�@��̓��͈������i�܂Ȃ��ƌ����Ă������ł͂Ȃ��B���������̎��̖@�傪�A�u���v�̂��������i��������)�I�Ӗ��ƕ��������Ƃ�������āA�{���̎��̖@��݂̍����S�l�\�x������ꂽ�`�ō�����������Ă���B�����Ă��̂��Ƃ������̖@��̋����̌����ƂȂ��Ă���Ǝv����̂ł���B
�@
�@
�@�܂�������l�̘Z�������钾�������p����B
�@
�u�C�T�����ɖڂ킭�A��x��t��O�O��̖{�����Ȃ��Ēq�ґ�t�ɕt���A�����G���̏\��ʊω��Ȃ�B����̖ʂɏ\�E�̌`����}���A��O�O��̑̐������킷�A�c�c-�c���ɏ\�E�̌`����}�����킷�A���ɐ��ꎖ�̈�O�O��Ȃ�ׂ���B
�����A�V���}�����킷�Ɠ���P�����ꗝ�Ȃ�A�̂ɒm��ʁA�������Ɍ��킷���Ƃ��B���̌̂ɖ@�̗P�����ꗝ�Ȃ�A�̂ɗ��̈�O�O��Ɗe�Â���Ȃ�B�Ⴙ�ّ�t�̌��������s�̑�ڂƖ��Â��邪�@���B�Ⴕ�����̈ӂ͎������Ɍ����A���̌̂ɖ@�̖{���ꎖ�Ȃ�A�̂Ɏ��̈�O�O��̖{���Ɩ��Â���Ȃ�B
�₤�A�Ⴕ����͑��̖@�̂̎��Ƃ͉����B �@�����A�����]���Đl�Ɍ������č����̔@������������]�]�v
�@���̌䕶�ɂ́A�ʏ팾���鎖���Ɨ��O�̎����ƁA�@�̂��̂��̂̎����Ƃ���̓I�ɋ������Ă���B�܂��x��t����O�O��������Ɍ��킵�ēV���t�ɕt���Ă��邪�A����͎��̈�O�O��ł͂Ȃ��̂��Ƃ����₢�ɑ��āA����͖@�̂��̂��̂����ł��邩��A����������玖���Ɍ��킵�Ă����̈�O�O��ł����Ȃ��B���Ƃ��A�V���t�̌�����ڂ����̖@��������Ɍ��킷���䂦�ɗ��s�ƈꌾ�������Ƃ��ł���B�������A���@�͎��̖@��������Ɍ��킷�̂ł���B�@�̂����ł��邩�玖�̈�O�O��Ƃ����̂ł����āA�����Ɍ��킹���ׂĎ��ł���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��Ƌ��Ȃ̂ł���B
�@��X�́A�Ƃ�����́A�n���w�����́u���Ƃ͐v�}�̂悤�ȕ��ŁA���Ƃ͎��ۂ̌����ł���v�|�̌��t�ɑ�\�����悤�ɁA���Ǝ����A���ۂƋ�́A�ϔO�Ǝ��̂Ƃ��Ă݂̂Ƃ炦��X��������B���������@�̌����Ƃ���̎��Ƃ́A���̈ӂ��܂߂āA������i�[���Ӗ��������Ƃ��A���̓�����l�̌䕶�͋������Ă���̂ł���B���̈�ݐ[�������Ƃ́A�@�̂��̂��̂Ɋւ��鎖���ł���B�}������͍��̂��Ƃ��Ȃ�B
�y���Ɓz �@�@
�@�@�@�@�@�@ �����i���V�j�@���y���Ă͓��@�͉��V���@�Ƃ������̂Ƃ���ɏ@�|�𗧂�Ȃ� �i�L�t�k�������j �@
�y�@�́z���@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@ �����i���@�j
�y��Ɓz
�@�@�@�@�@ �����i�����j ���V��`���ƍO�ނ鏊�̎��̈�O�O��͌咆�̎����ɖ� �̂ɗ��ɑ�����Ȃ�ׂ� �i��s���`�O���@���������j
�y�@�́z���@���@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@ �@ �����i���_�j
�@
�@
�@����ł́A�@�̂̎����̑���Ƃ͉��ł���̂��A�܂����̖@��Ƃ͉��ł���̂��B������l���u�l�Ɍ������Đ������v�ƈꉞ�邳�ꂽ���𖾂炩�ɂ��Ă����Ƃ���ɁA�����̖@���̋�������������J�M������̂ł���B
�@
�@���L��l�͗L�t�k�������ɁA
�@
�u�y���Ď��Ɖ]�З��Ɖ]�Ћ��҂Ɖ]�Вq�҂Ɖ]�Вf�f�Ɖ]�Ж��f�f�Ɖ]�Ж{�Ɖ]��瑂Ɖ]�Ѝݐ��Ɖ]�Ќ���Ɖ]�ӁA�����瑖�Ɖ]�͂Η��Ȃ�q�҂Ȃ��Ȃ�P�Ȃ�A�\�����ɍ����̔@�����@�����͖{��̎��Ȃ�A�R��Ԏ����̉��V�̏�ɏ@�|�𗧂�@�Ȃ�A����Ԏ��Ȃ���҂Ȃ�{��Ȃ�A�v
�u���Ė��@�����͈��S�݂̂ɂ��đP�S�Ȃ��A�t��ɎO�ŋ����̖}�v�̎t�푊���āA���]�O�Ȃ����@�@�،o�����鏈�g�����Ƃ���������Ƃ��]�͂�T�Ȃ�A�v
�u�R��͏C��~���̖{�����̏��ɓ��@�͏@�|����������Ȃ�A�͂⊴��~�ʂ̏��͊O�p����Ȃ�q�҂Ȃ藝�Ȃ�S�����@�̏@�|�ɔ��Ȃ�B�v
�Əq�ׂ��Ă���B�����}������ƁA
�y�����z
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y����z
�@�����ҁE���S �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���q�ҁE�P�S
�@�����f�f�E�t�틤�ɎO�ŋ����@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ���f�f
�@���{�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���
�@������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���ݐ�
�����ؖ{�n �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���O�p���
�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���̐}�̎����Ƃ���A�ꌩ���Ď����Ƃ́A���f�f�E���ҁE�t��Ƃ��ɎO�ŋ����ƁA�O���}�v�̏�ŕ������_�����鐢�E�������A����̐��E�́A�f�f�E�q�ҁA�����镧�E�q�҂̐��E��\���Ă��邱�Ƃ�����B�����āA���̖}�v�O���̑����A�{�n���E�����{�ł���A���̑����A�O�p��瑁E�ݐ��E瑂ł���Ƃ��Ă���̂ł���B
�@ ���̂��Ƃ́A�吹�l�̑��@�������́A
�@
�u�}�v�͑̂̎O�g�ɂ��Ė{���������B���͗p�̎O�g�ɂ���瑕��Ȃ�B�R��͎߉ޕ��͉䓙�O���̂��߂ɂ͎�t�e�̎O��������ӂƎv�Ђ��ɁA���ɂĂ͌�͂��A�Ԃ��ĕ��ɎO�������Ԃ点���͖}�v�Ȃ�B�v
�@�@�Ƃ��������t�B�܂��A�O���@���������́A
�@
�u���̈�O�O��͖����̎��Ȃ�A���͖̌̂Ϗ�̏\�E���{�L����̊o�̂Ɖ]�ӂȂ�A����̎��̊O�Ɋo��̎������҂Ȃ�A�V���Ȃ��Ĕނ��v�ӂɁA�V��`�����O�ނ鏊�̎��̈�O�O��͌咆�̎����ɖ̂ɗ��ɑ�����Ȃ�ׂ��B�v
�@�@���̌䕶��q����ƍX�ɂ悭�����ł���̂ł���B�����Ō��������̖}�v�Ƃ́A瑕��E�{�ʖ��ɑ���{���E�{�������w���̂ł����āA���R�ߑ������̒��ł̗����C�s�r��̖}�v�Ƃ͈قȂ�B���@�������̌䕶�́A���̖{�����̖}�v��������̎O�g�ɂ��Ė{���ƈꌾ���A�v���E�v�̕���瑕��Ɛ�����Ă���̂ł���B���̖}�v���{���ŁA����瑕��Ȃ̂��ƈꌾ���A�m���ɖ{�ʑ��Ԑ����̎ߑ��͏O���̂��߂ɎO���������čϓx����Ă������A���̎ߑ��̌��̍��{��q�˂�A����͐X�����@���Ȃ킿��؏O�����̂��̂Ȃ̂ł���B�ߑ��͉�疢�f�f�̈�؏O����@���Ɍ��Č����킯�ł��邩��A�u�Ԃ��ĕ��ɎO�������Ԃ点���͖}�v�Ȃ�v�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B
�@�]���Ė{�ʂ̕����Ɩ{���̕��@�Ƃ̑���͎ߑ��̌��𒆐S�Ƃ��������ƁA�ߑ�����炵�߂��}�v(�@)�𒆐S�Ƃ��������Ƃ̑���ł���A�@�̂̎���(�����Ɨ���)�ɖA�O���̕ӂɗ����Č������ꂽ���@�ƁA���̕ӂɗ����Č������ꂽ�����Ƃ̑������킵�Ă���̂ł���B�����̏��ɖ@����������铖�Ƃ́A����̕������M�������E�F�������̕���(�O�����S)�Ƃ��đނ����A�t��Ƃ��ɖ��f�f�̈�؏O���̐��E�����^�̑̂ɂ��Ė���O�g�ł���Ƃ��āA�����ɐ^���̕��@�̎p���Ƃ炦�Ă����̂ł���B
�@�����������Œ��ӂ��Ȃ���͂Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���ƂŌ����}�v�{���Ƃ����̂́A�����鎺�����ȍ~���������ÓV��̗����{�o�E�}�v�����v�z�Ƃ͑S���قȂ�Ƃ������Ƃł���B
�@
�L�t�k�������ɁA
�@
�u���t�]���i�V��)��q�Ɖ]�ӂ͗����{�@�̏�������q�ɂĔV��L��A�S�������̏��S�ɂĔV�ꖳ���Ɖ]�]�B ���ɉ]��(���L��l�]��)����͒q�҂̎�q�Ȃ�A���̌̂͗����Ƃ͈�O�̐S���@�������ɂė��Ȃ�ԕ��̈ӂ̎�q�Ȃ�A���̗����{�@�̎�q�𖼎��̏��S�ɂ��Ďt�틤�ɎO�ŋ����̖}�v�ɂ��Ė��]�O���������̖����̉���Ȃ�A�����͒A��q�̖{�@�ɂĎw���u������Ȃ�A�����ɂĉ���̋`�͈ӓ�����Ȃ�A����Ɖ]�ӂ͎t�푊�̋`�Ȃ�B�v
�@�@�Ƌ��̂��Ƃ��ł���B
�@�����{�o�Ƃ́A�{�o�v�z�̋ɂ����`�Ƃ���A���̌����Ƃ���͖}�v���̂܂܂̎p���{���ł���Ƃ���v�z�ł���B���L��l�͂�����A�ꌩ���O�̑��ɗ��������k�̂悤�ł��邪�A�������ĕ��̑��̏��k�ł���Ƙ_�j����Ă���B���Ȃ킿�A�����Ƃ͖@��M����C�������A�䂪�g�Ɏ�q�̂��邱�Ƃ�����m��ʎ҂ł���A�����Ɏ�q������ƌ�����͕̂��̏��k�Ƃ��������悤���Ȃ��B�}�v�Ȃ���M���N�����A�䂪�g�Ɏ�q�����邱�Ƃ�F�����邻�̓���������Ƃ���̂��A�^�ɖ��O���ɗ������@��ł���A�{�o�v�z�ł���Ƃ����̂ł���B
�@���ɒ��ӂ��Ȃ���͂Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�M���N�������}�v�́A���@�@�،o�̓��̂Ƃ��āA�I���C�ɂ��炦�o���n�ɖ��ނ����Ƃ��A���@�̈ꕪ�ł͂���ɂ��Ă��A�l�O�������{���Ƃ͌����Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�X�����@���Ȃ킿�{���̈�؏O���́A���ꂪ��ӂ̖{���ɏ�����Ă����{���Ə̂����̂ł���B���@�ɂ����ẮA���f�f�̈�؏O���E�X�����@���A���f�f�̏�s�A���v�������̎���p��g�̈�g�Ɏ��߁A�v�������̖��@�@�،o(���@����)�Ƃ��āA�����{���Ɣq���Ă����̂ł���B �@�ȏ㎖���Ɨ���ɂ��Ċȗ��ɏq�ׂ����A���ǁA���@�̊�ՂƂȂ鎖���̖@��Ƃ́A ��A�Ō㖖�@�̑吹�l�̕��@�́A�t��Ƃ��ɖ��f�f�̏O���̐��E�Ɍ�������Ă��邱��(�t��̖@��) ��A����̖@�傪�A�O�p��瑂̖@��ł���̂ɑ��A�����̖@��͓��ؖ{�n�ɂ����Ă̖@��ł��邱��(�ȐS�̖@��) �������Ă���̂ł���B �����Ɨ���̍����A������l�̂����t�������A���߂̍����������A�����̖@��̋����̍����ł���B��̉���Ƃ�����̗p����Ƃ��Ă݂Ă��A��������̌��t�ł��邩�A���O������̌��t�ł��邩�̑���ŁA���{�I�ɈӖ����ς��Ă���B���݂��̂��Ƃɂ��܂�ɖ��ڒ��ł��邱�Ƃ��A���߂̍������܂˂������ł���ƍl������B���O���@��W�T����@��́A�����̕ӂ���݂����@���T�̍쐬���}���ł���B
�@
�@
�@��Ɏ����̖@��̖{���́A�t��̖@��ƌȐS�̖@��ł��邱�Ƃ��q�ׂ��B�����ł͍����̏��������̓`���@��ɏƂ炵�A���̖��_���w�E�������Ǝv���B
(1)�@�t��̖@��Ɋ֘A�����@
���@�t���ӂ̖{��
�@�Z�����ɁA
�u�䓙������鏊�̖{��̑�ڑ��̑̉�������B���킭�A�{��̑�{������Ȃ�B�{��̑�{�����̑̉�������B���킭�A�@�c�吹�吥��Ȃ�B�̂Ɍ䑊�`�ɉ]�킭�A�����̎��A���E�̏\�E�F�������@�Ȃ�A�̂ɓ��@���Ǝ�t������B���]�킭�A�������r������ɕs�v�c�Ȃ�A���@���e���̑��䶗��Ȃ�B���]�킭�A������ꋋ�����̎����͕��E�Ȃ�R�������䓙�O���͋�E�Ȃ�R���ꑥ���^���̏\�E��Ȃ�]�]�v
�@�Ƃ����䕶������B
�@��珥����{��̑�ڂ̐��̂����{���ł���A���{���̐��̂͑吹��̓��ł���Ƃ����̂͏�̏��k�ł���B�������X�ɂ��̑吹�l�̓��̐��̂��A���̌�́u�䑊�`�ɉ]���v���������Ă��邱�ƂɋC�Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���̌䑊�`�ɉ]���Ƃ́A�u��{�����ӑ����v�̂��Ƃł���B�܂��A�O�����@�̋�Ɩ��������̖{���ɂ���āA�吹�l�̓��i���q�̐l�ԓ��@�Ƌ�ʂ���j������p��g�E�v�������̖��@���{���̑̂ł��邱�Ƃ��q�ׂ��Ă���B
�����āA���̎����́u���]�킭�v�ȍ~�́u��{�����ӑ����v�́A
�u���ւ�ꋋ�ӏ��̎����͕��E�Ȃ�A���֕��䓙�O���͋�E�Ȃ�A���ꑥ���l���̈��ʂ�Ŕj���Đ^�̏\�E�̈��ʂ�������͂��]�]�A���̎��̉䓙�͖���O�g�ɂ��Ď���y�ɏZ��������Ȃ�A�o���̉����͐�瑎{���̌����Ȃ�v
�Ƃ����䕶�����p����āA���E��E�̏\�E��Ɏ��āA���E��E�t���ӂ̖��@����������Ă���B����͉��V���́A
�u�t���L��Ύt�̕��͕��E�̕��A��q�̕��͋�E�Ȃ�̂ɁA�t�푊���ӏ��A�����̖��@�Ȃ�̂ɁA���瑦�g�����Ȃ�̂ɑ��@�̔@���Ȃ炸�A���ꑥ���s�̖��@�A���̑��g�������]�]�v
�Ƃ̌䕶�Ɠ��ӂł���B
�@���������A���d�̑��{�����A���̏@�c��}���̌�{���ƈقȂ�A�吹�l�̌�{���Ƃ����䂦��́A�܂��Ɏt���ӂ̑��{�����邱�Ƃɂ���B�O�t�`�ɁA
�@
�u���ĔM���̖@�؏@��l�������L�ʁA���̎��吹�l�䊴�L���ē�����l�ƌ�{���ɂ������݂̂Ȃ炸�]�]�v
�@�Ƃ��邪�A����͉��d�̑��{���̌䎖�ł���B�厖�ȂƂ���́A���{�������̋N�����A�Œꉺ�̏O������M���@�؏O�̎ɂ��邱�Ɓi�t���Ӂj�A�����āA�吹�l����l�łȂ�������l�Ǝt�푊����Č�������Ă���Ƃ������Ƃł���B���̎t���ӂ����������̖@��吹�l�̕��@�̐^���ł����āA���d�̑��{���E�v�������̖��@�̐��̂ł���B
�@�䂦�ɑ吹�l�̌�{�������d�̑��{�������ɂ��邱�Ƃ͂������ł��邪�A���̑��{��������P�ɁA���̂Ƃ��Ă̖{�������Ɖ��߂��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@���l���ɁA
�u�c�c�c���̌S�̓��������Ɛ\�����̏����V�̎������̓�ʂɂ��āA�߂̎��ɍ��̖@��\���͂��߂č��ɓ�\���N�A�O����N�i���Ζ��K�j�Ȃ�B���͎l�\�]�N�A�V���t�͎O�\�]�N�A�`����t�͓�\�]�N�ɁA�o���̖{���𐋂����ӁB���̒��̑��\���v��Ȃ��B��X�ɐ\�������Ƃ��B�]�͓�\���N�Ȃ�B�v
�@�Ƃ����䕶������B���̌䕶�ɂ���ĔM���@����߂�����d�̑��{�����@�c�̖{���Ƃ���̂����A�������d�̑��{�����I�ɔq����Ȃ�A���̌䕶�͍O���Q�N�P�O���P���ɂ��F�߂̌�����ł��邩��A�P�O���P�Q�������̑��{���͖{�����̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�����ɉ��d�̑��{���̔q�����̏d�v��������̂ł���B��̎O�t�`�̌䕶�̂��Ƃ��A�M���@����߂����āA�@�吹�l�Ƃ͈�ʎ����Ȃ����q���ӂ́u��s�̎҂ǂ��v���A���������đ吹�l�̌�@��������Ƃ���ɁA�吹�l�͐^�̎t���ӁA�Ȃ��{����F�߂�ꂽ�̂ł���B�����āA���@�����t�푊����Ďt���Ӊ��d�̑��{�������ƂȂ����̂ł���B���n�n���̖{���A���N�~��̖{�����Ƃ̑���́A�܂��ɁA�t�̖{���ƁA�t���ӂ̖{���Ƃ̑���ł��낤�B�����Ďt�̖{���������I�{���ł���ɑ��āA���d�̑��{���͓��ؖ{���Ɣq����Ƃ���ɁA���̖{������䂦����B���{�R�ɂ����ĉi���镧�Ƃ��āA��ɔ鑠����Ă����̂́A����𑼂̈�@�ꉏ�̖{���Ƌ�ʂ������I�ɁA�����I�ɔq�����邱�Ƃ������邽�߂ł������낤�Ǝv����B�N�Ћs�̍ۂ̑��{���y�q�̋V���A�X�ɓ��B��l�́u���{���͋q�a�̉��[�����u����Ƃ������`������܂��v�Ƃ��������t���������l����Ƃ��A���ɂ��ĕ��ɂ��炸�A�́E�p����ʐr�[�̈Ӌ`�����������̂ł���B
�@���̎t���ӂ̑��{���ɂ��ẮA����X�ɐ[���A��̓I�Ɍ�������Ă������Ƃ��]�܂��B����ɂ́A��ӑ�����A�{�������E�O�t�`�E���V���E�Z���������A�P�Ȃ鑊�����E�j�`���E���w���Ƃ��ĂłȂ��A�t��̖@��������@�发�Ƃ��ė������邱�Ƃ��K�v�ł���B���ꂪ�A����̎t�̖@��A�F���̖@��ɑ���A�����t��̖�A�ȐS�̖@�傪�@����S��������ł��낤�B
�@
���@�@��ɂ���
�@���ݖ@���l�ƌ����Α����ю���w�����A�{�@�×��̍l�������炷��A����͑傫�Ȍ��ł���B�ю��@��ƌď̂���悤�ɂȂ����̂́A�A���炭�@�傪�����I�ɋ������߂��������납��Ǝv����B
�@���@�ɂ�����@��A�܂�u�@�̎�v�͋v����������p��g���吹�l�̓��؈ȊO�ɂ͂��肦�Ȃ��B
�{�������ɂ́A
�u���͏n�E�̋���A�^�͉���̖@��Ȃ�v
�@�Ƒ��`����A�܂�������l�̌�����̒��ɂ��A
�u���@�吹�l��_�a����i�v
�Ƃ��A�܂��A
�@�u�c�c�c�@�吹�l�̌��O�ɕ���i�v
�@�Ƒ吹�l�̌��O�A�܂�A���؋v����������p��g��@��Ƌ��ɂȂ��Ă���B���݂̂��Ƃ��A����ю傪�@��Ƃ����Ȃ�A������l���@��Ƃ������ƂɂȂ��āA���̂悤�ɑ吹�l��@�吹�l�Ƃ����͂����Ȃ��B
�@�Ȍ�A�������ɂ����āA���s�Z�{���̑m�Ō�ɓ��L��l�Ɏt�������Ƃ����鍶�������t�̖s�쏴�ɁA�@�c���Ƃ͕ʂɁA��X�̊ю��@��ƌď̂������U�����邪�A����ȊO�A���ɓ��@����ɂ����ẮA�L�t�E���t���͂��ߗ���@��ƌ�����͂Ȃ��B���������t�́A���炭�A���s�ɂ����Đ^�@���ɂ���Ēʗቻ����Ă����ю偁�@��Ƃ����Ăѕ������̂܂܁A�K���Ƃ��Ďg�������̂Ǝv����B�������t�ɂ����Ă��A��|�́A�@��Ƃ͏@�c�̓��Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă���B
�@������ɂ��Ă��A���@�×��̓`���ł͖@��Ɗю�Ƃ͖��m�ɋ�ʂ���Ă���̂ł���B����́u�@�̎�v���Ȃ킿�t���ӂ̋v�������̖��@�ȊO�ɁA�u��v�̑��݂�F�߂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�@��̌��O�ɑ��A�s���S���m�̊ю�ƏO�c���݂��ɐ��ߍ������������Č������A�t�푊�̒��ɖ@���𑊑����Ă����Ƃ������Ƃ��A�@��Ɗю�̋�ʂ͕�����Ă���B
�@�@��̋����ƂƂ��ɁA�t��ς������Ȃ�M�����������z���Đ��ԕ��݂̎t��ƂȂ��āA�ю��l�Ɉُ�Ɍ��͂��W�����Ă������B��ɖ@��ɑ��Ē�q�̗�����Ƃ��Ă����`��������āA�ю傪���t�̗���ƂȂ�B����ɑ�������悤�Ɋю傪���̊Ԃɂ��@��ƌĂ��悤�ɂȂ��āA�����ł͊ю�{�����v�킹��قǂ̏�ԂɊׂ��Ă���B����ЂƂ��Ɏt��̍����̂Ȃ���p�ł���B
�@�@��̋����A�t��̍����͈�X�ɒ����Ă����Ȃ���Ȃ�ʁB�܂��͗��ю��@��ƌĂԉ������p�~���邱�Ƃ��}���ł��邱�Ƃ������i����B
�@
���@�B����l�ɂ���
�@�吹�l�̕��@�́A��{�I�ɐ�ΓI�ȕ����ς̏�ɗ��r���Ă���B�t��Ƃ��ɖ��f�f�Ƃ����@��̏o���_��������ؖ����Ă���B
���L��l���V���̖`���ɁA
�u�M�˓����̍��ʂȂ��M�S�̐l�͖��@�@�،o�Ȃ�̂ɉ���������Ȃ�A�R��ǂ��|�ɏ㉺�̐߂̗L�邪���Ƃ��A���̈ʂ��Η������m���̗�V�L��ׂ����A�v
�@�Ƃ����䕶������B�@��ɂ��Љ�I�ʒu�A�X�ɂ͈�W�c�Ƃ��Ă̒����͕K�v�ł���B�����Ƃ́A�����b���A�㉺�̍��ʂm�ɂ���Ƃ������Ƃł���B����������͉���̍��ʂł����āA�@���ł͐�ΓI�ȕ���������B���̉��V���̌䕶���܂��@��Ƃ��Ă̕����������A�������A������ۂӖ��ɂ����āA����̍��ʂ�������Ă���̂ł���B
�@�l���Ă݂�ƁA���@�̉��V�́A���Ƃ��Ƃ����̕����ςɗ��������̖@��ɂ��ƂÂ��ďo���Ă���悤�ł���B���͏��ł��Ă��܂������A�ю傪���N�A�����E�Ԍ��̂Ƃ��ɒt���m�ɋ��d������K�������������A����͏㉺�̍��ʂ͌����Ƃ��Ă��邪�A�@��̐��E�ɂ͊ю�����m���Ȃ��Ƃ������Ƃ��V���������đm���E���ԂɎ����Ă������̂ł��낤�B
�@�܂��A���@�̑m���������U���E�߂́A��ю��艺�����Ɏ���܂ŁA�����̌U���A���n�̈߂ɓ��ꂳ��Ă���B�����Ƃ������ł͂��̓��ꐧ���������N����������āA���l�Ȃ��͔�̈ߊ�܂��̊ς����邪�A�Ƃ����ꂱ�̔����̌U���A���n�̈߂́A�܂������ς����킵�Ă���̂ł���B���̕����ς��F�������̐��ԁE�M�������ɑ��āA�ւ�ׂ����@�̖@��ł���A���V�ł���B
�@�吹�l�̌���̑O�ɁA���ׂĂ������ł��邪�䂦�ɁA��ΓI���͎҂͔F�߂��Ȃ��B������l�̈�u���ɂ́A��Ύ҂�F�߂Ȃ��Ƃ��������ς����X�Ƃ��Ă���B
�@�@��A�����L�闬�z������Ԃ͐g�����̂ĂĐ��͍O�ʂ�v���ׂ����B
�@�@��A�g�y�@�d�̍s�҂ɉ��Ă͉���̖@�t�����嫂����@�h���̓����ɔC���M�h��v���ׂ����B
�@�@��A�O�ʂ̖@�t�ɉ��Ă͉��y�����嫂��V�m�̎v�����ׂ��ׂ����B
�@�@��A����̎҂����嫂�����q���ꂽ��҂����Ŏt���Ƃ��ׂ����B
�@�@��A���̊ю��嫂����@�ɑ��Ⴕ�Čȋ`���\���ΔV��p���ׂ��炴�鎖�B
�@�@��A�O�c�����嫂����@�ɑ���L��Ίю�V��F���ׂ����B
�@�@��A��ⓚ�ɍI�݂̍s�҂ɉ��Ă͐�t�̔@���܊シ�ׂ����B
�����͌P���Ǝ~�߂�O�ɁA���̖@���������@�发�Ƃ��Ď~�߂�ׂ��ł��낤�B
�@���āA�ߗ����̓`�����S�������āA���͂���l�ɏW�����A���̖@��Ƃ͑S���t�]�����l����悵�Ă���B�����̌������ЂƂ��Ɏt��̍����A���߂̍����ɂ��邱�Ƃ͐�Ɏw�E�����Ƃ���ł��邪�A���A�X�ɋ�̓I�ɏq�ׂ�Ȃ�A�B����l�̎��Ⴆ�Ƃ������Ƃł��낤�B
�@������l�̊ϔO���Ɂu�얳�@���b�r�B��^��v�Ƃ���̂�Z���I�ɗ��ɒu���āA��ォ����ւƖ@������H���R�炳���b�r����Ă��邱�Ƃ��_�b�I�Ɍ���Ă��邪�A����͏@�j�ɏƂ炵�Ă݂Ă��A�܂��@��̏ォ��������������Șb�Ȃ̂ł���B���́u�얳�@���b�r�B��^��v�Ƃ́A��Ɏt���߂̖{���ɂ��ďq�ׂ����A�܂��Ɏt�E���@�吹�l�ƒ�q�E������l�ɂ����Ďt���ӂ̖@����������ꂽ���̂Ɣq���ׂ��ŁA��������Ղɓ��@�̌��ЂƂ��Ă̗B����l�ɂ��Ă�ׂ��ł͂Ȃ��B
�@�@��ɂ͌×����A�@�J�O�c�������ď@�c�̓������킷�Ƃ����`��������B�����E��ɁA
�u�ɉ]���A�J�o�ɉ]���A�����̍���ƍ��̕v�l�Ƙa�����ĕ�F�̎q�ނƉ]�ւ�B�����̍����Ƃ͍��c���@���l�Ȃ�A���̌o�̕v�l�Ƃ͓�����l��A��F�̎q�Ƃ͓��ڏ�l����Ȃ�A����Γ���k�̐M�͍��̐S���厖��A�c�c�c�v
�@�Ƃ��邲�Ƃ��A�O�c��̂̂Ƃ���ɖ@�����Ȃ킿�@�c���؋v�������̖��@��q���̂ł���B�`���I�ɎO�c�܂ł�c�v�ƌ����A�l���ȍ~���u���v�ƌ����̂͒P�Ȃ�K���ł͂Ȃ����āA���������@��I�Ӗ����܂܂�Ă�����̂Ǝv����B
�@�Ƃ������A���̎O�c��́A�t��̖@�����p�����Ƃ��B����l�����Ƃ���A�@��I�Ɍ����A�M�S����ɕ����C�s�̎҂͂��ׂėB����l�ł���B
���V���́A
�u�M�Ɖ]�ЁA�����Ɖ]�ЁB�@���Ɖ]�ӎ��͓������Ȃ�A�M����������Α��̋ؖڈ�ӂׂ��炴��Ȗm���A��͂���Ό����@���͈�ӂׂ��炸�A�v�Ƃ͐��Ԃɂ͐e�̐S����ւ��A�o���ɂ͎t���̐S������ւ��邪�����̒������Ȃ�A���c�ߗ��̐M�S����ւ��鎞�͉䓙���F�S���@�@�،o�̐F�S�Ȃ�A���̐M�S����ӎ��͉䓙���F�S�}�v�Ȃ�A�}�v�Ȃ邪�̂ɑ��g�����̌����Ȃ�ׂ��炸�A�v
�@�Ƃ̌䕶���A�悭�悭�q���ׂ��ł���B
�������Ȃ���A����������ė��̗B����l��S���ے肵�Ă���킯�ł͂Ȃ��B
��̓�����l�̈�u���ɂ��A
�@
�u��y�Ȃ��嫂����ʂ̒h�߂�薖���ɋ����ׂ��炴�鎖�v
�@�ƕ����̒��̍��ʁA�܂蒁����搂��Ă��邵�A
�܂����V���ɂ��A
�u�R��ǂ��|�ɏ㉺�̐߂̗L�邪���Ƃ����̈ʂ𗐂����m���̗�V����ׂ����v
�@�Ɛ������Ƃ���A�����Ƃ��Ē����͕K�v�ł���B�䂦�ɗB����l���ΊO�I�A���邢�͂܂��@���̒����̂��߂ɁA���X�̌�@�����鑍�叫�Ƃ��Ċю�Ɉ��Ă���̂ł���B�������A����͖@��I�ȕ����ς܂�������̎p�A�ǂ��炩�Ƃ����ΐ��Ԃɏd����u�����A���ʂ̐��E�ł̗B����l�Ƃ����ׂ��ł��낤�B
�@�����Ƃ����̐��Ԍ����̊O���̗B����l�ɂ����Ă���A�Ȃ��ю��l�ɂ݂̗̂B����l�͗��j�I�ɖ���������B������l�̈�u������L��l���V���������čl����A�ю�ƏO�c�̎t��̒��ɗB����l��F�߂�ׂ��ł��낤�B
�@�܂�A�{���݂̍���͖@��I�ȐM�S�̓��،����E�B����l���ŏd�v�ł����āA�@�|���ɂ�����B���̏�Œ����̂��߂ɊO���i�@�����j�Ƃ��Ă̗B����l���ю�ƏO�c�̑��݊W�̏�ɐ��藧���āA�Ō�ɁA���ʓI�ɏے��Ƃ��Ċю��l�̒��X�t�@�E�B����l�������̂ł���B���ꂪ�t��Ƃ����f�f�̖��O���@�̍Œ���̍��ʂł���B
�@���݂ł͂��ꂪ�S���t�ɂȂ��āA�������ю��l�̗B����l���ŗD�悳���B��x�@�傪�����͂��߁A���������낻���ɂȂ��Ă���ƁA����Ɍ��͎w�����s���A�@��Ƃ͐^���̐�ΓI���Ђ��ُ�ɋ��߂���̂ł��낤���B�͂��߂��猠�Ђ�F�߂鐢�Ԃ�M�������́A����Ȃ�̐��R�Ƃ����������o���Ă��邪�A���@�̂��Ƃ����Ђ�F�߂ʏ@����]���͎w�����Ȃ����ƁA��̃u���[�L���Ȃ��A���ߑ��ȓƍٓI�Ȍ��͂��o���オ���āA�Ƃɂ����A�B����l�A�B����l�ƁA���̌��Ђɂ���đ���ɏ���邱�Ƃ�����A�@��m�����Ј�����̂́A���߂ɂ���đ���ɂ�����ʂقǂɁA�܂��@��̈ꒁ����ۂĂʂقǂɁA�@�傪�y�������Ă��邩��ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�����ȑO�͂��̌��ЂƂ��Ă̗B����l���A����l�̂����t�̒��ŁA���ǂ낭�قNJȒP�ɂ������Ă���̂��A�{���̖@��̏�ł̐M�S�̌����A�B����l���A�������肵�Ă�������ł��낤�B�A���A�����ȑO�ɂ����Ă��A�@��ɋ����̂���Ƃ��i���i�O��j�͐���Ɋю�B����l��搂��Ă���B���܂�ɋ�������Ă��闠�ɁA������ςȎ��Ԃ̐����Ă������ƁA�܂�B����l�ɂ���ĈЈ����Ȃ���Ȃ�ʎ��������������Ƃ�����������B
�@�Ƃ������A���@���@�`���̗B����l�����t�@�Ƃ́A�������K���X�e��̒��̐����A���낻��ƁA���鋰�邨�Ƃ��ʂ悤�A���킳�ʂ悤�A�n�����ɂ���邪���Ƃ��A�����Ɏp����邲�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A��������Ƒ�n�ɍ������낵�A���O�i�t��Ƃ��ɖ��f�f�̖��O�ł���j�̗͋����p���[�̒��ŁA���܂�A���������A�������̂Ȃ̂ł���B
�@
�@
�i�Q�j�@�ȐS�̖@��Ɋ֘A����
�@�����ɂ����āA���݂̖@�傪�A���悻�����I�ɉ��߂����Ƃ���ɁA�����̏����̐����錴�������邱�Ƃ��w�E�����B�����ł́A������Α����I�łȂ��{���̖@��i�ȐS�̖@��j�Ƃ͂��������ǂ��������̂��A�܂������ɂ͌ȐS�̖@��ƕ��s���đ����I���ʂ�����킯�ł��邩��A���̒��a�͂����ɍl����ׂ��ł��邩�A�Ƃ������Ƃ�_�������B
�@
���@�@�|���Ə@����
�@��ɗB����l�ɂ��āA�@�|���Ə@�����Ƃ������ĕ������������A�����ł�����x�@�|���E�@�����Ƃ����l�����ɂ��Ăӂ�Ă݂����Ǝv���B
�@�Ⴆ�A���@�͖@���ɂ����ẮA��ΓI�ȕ���������B�����������̖��Ƃ��Ē����i�㉺���ʁj�͕K�v�ł���B�ꌩ���Ȗ����I�ȑ��������l�����ł��邪�A���������̑o�����A���܂����a���ꗼ������Ă����A���@�{���̓`����������������̂Ǝv���B
�@���āA�����̑o����l�����ɏ@�|���Ə@�����Ƃ�z����Ȃ�A�@���̕����ς��@�|���ƂȂ�A�����Ă���܂�����ł̉���̍��ʂ��@�����ɂ�����B�܂�A�@�傻�̂��̂Ɋւ���Ƃ�����@�|���ƌ����A����܂��ĂȂ��A�������Ƃ��ĕK�v�Œ���̐��Ԃւ̑Ë����@�����ƌ����̂ł���B
�@���ԑ����@�Ƃ����A���ԃC�R�[�����@�Ǝv�������ł��邪�A���͂����ł͂Ȃ��Ăނ���S�������������̂ł���B���ԁi�y�ыM�������j�͐F����{�Ƃ����F�S�s��ł��邵�A���@�͓��،ȐS��{�Ƃ��āA�F�S�s���_����B���̑����������̂��A�݂��ɏ��������Ƃ���𐢊ԑ����@�Ƃ����̂ł���B
�@�䂦�ɕ��@�͂��̖{�����ł�������邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł����āA��������ɐ��Ԃɓ�������A�������Đ��ԑ����@��������ƂɂȂ�̂ł���B�����������Ӗ��܂��āA���@�i�@�|���j�{���̖{�������Ȃ���A�S�����̐��Ԃ֓]���邱�ƁA�܂��Љ�̈���A�Љ�̈�W�c�Ƃ��Ă̈ʒu�E������ۂ��߂ɁA�������͈͂̐��Ԗ@�Ƃ̑Ë��A���ꂪ�@�����ł���A�܂��@�����̕K�v�Ȃ�䂦��ł�����B
�@�������A���@��l���A
�u�����O���̌���؈�w�����l�ɑP�I���֗L���҂��v
�@�ƌ����邲�Ƃ��A�@�|�ɏƂ炵�S����w������́A���邢�͊�ƂȂ�ׂ��@�|���Ɨ��ꂽ�Ƃ���̏@�����́A�Ɏ���ʉ���̂��Ƃ��A�S�����Ӗ��Ȃ��̂ł���B
�@�v�́A�@�|������������Ƒ�n�ɍ����͂�A��{�ƂȂ�A����ƂȂ��āA���̏�ŏ@�����������Ă����A�o���̒��a�͑�����̂ł���B
�@���@�ɂ́A�u�L�闬�z�v�ɂ��Ă��u�O��v�ɂ��Ă��@�|���Ə@�����̗��ӂ������āA�×����@�|���𒆐S�Ƃ��đo���̒��a���Ƃ��Ă����B�����������͏@�|������������Y����āA�@�����������Ƃ���������Ă���悤�ł���B���̐[�����͂����ɂ���B��ɏq�ׂ����Ƃ��A����ł͕Ɏ���ʉ��ρA�܂�A�܂ڂ낵�ł����Ȃ��B
�@�@�|���E�@�����Ƃ������Ƃ́A���R�L�闬�z�E�O��Ɍ��������Ƃł͂Ȃ����A�Ƃ肠�����A�ł��d�v�Ǝv���邱�̓ɂ���āA�@�|���Ə@�����Ƃ͂����ɒ��a����Ă������{���݂̍����T���Ă݂�Ɠ����ɁA�����̖@���̌��ׂ��w�E�������Ǝv���B
�@
���@�L�闬�z
�@�ߗ��̓��@�̍L�闬�z�ρA�܂��X���L�闬�z�Ƃ������t���đ����ɓ��Ɏv�������ׂ�̂́A�L���X�g���ɐ�����郆�[�g�s�A�I�ȁA���ׂĂ̐l�X���吹�l�̕��@��M���鐢�E�ł���B������L�闬�z�ς̈�ʂł���ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A����������������ē��@�`���̍L�闬�z�ς̂��ׂĂ�����Ă���Ǝv���̂͊ԈႢ�ł���B���_���猾���A�L�闬�z�ɂ��@�|���E�@�����������āA����͂��̏@�����ɂ�����̂ł���B
�@�@�����Ƃ͏@�|���Ƃ�����ΓI�Ȋ�Ղ������Ă����Ӌ`�̂�����̂ł����āA�@�����̓Ƃ�����͐�ɋ�����Ȃ��B�Ȃ����Ȃ�A�@�����Ƃ͂��Ƃ��ƐF�����S�̐��Ԃւ̑Ë��_�ł��邪�䂦�ɁA�S���s���S�Ȃ��̂�����ł���B���ꂪ�؋��ɁA�������ꂾ���A�L�闬�z�A�L�闬�z�Ƌ���Ă���ɂ�������炸�A�ł͂��̍L�闬�z�Ƃ͂��������ǂ�������ԂɂȂ����Ƃ��������̂��Ɩ��ꂽ�ꍇ�A���������A�ǂ������ł��ƁA�͂�����Ɠ�������҂͂܂����Ȃ��ł��낤�B���邢�͓V�c���M�������Ƃ��ƌ����A���邢�͓��{�̎O���̈�̐l�X���M�������Ƃ��ƌ����A���邢�͑吹�l�̕��@�����{�̍��@�ƂȂ����Ƃ��ƌ����A���邢�͑S�l�ނ��M�������Ƃ��ƌ����A���܂��ɂ͉F���S�̂��Ƃ����悤�Ȉӌ����o�Ă���ł��낤�B�F�����o�Ă���������ɂ������Șb�ƋC�Â��ł��낤���A�s���S�Ƃ����_�ɂ����ẮA�ǂ��������\���S���ł���B�ꌩ��̓I�Ɍ�����F�̐��E�Ƃ́A���͑S���s���S�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���Ă���ł́A�@�|���̍L�闬�z�Ƃ͂����������ł��낤���B
�吹�l�͋F���o����ɁA
�u����ɕt���Ă��@�،o�̍s�҂͐M�S�ɑޓ]�����g�ɍ��e�����A��ؖ@�،o�ɑ��̐g��C���ċ����̔@���C�s���A�҂Ɍ㐶�͐\���ɋy���A���������Љ����ɂ��ď����̑�ʕ�A�L�闬�z�̑��������A�����Ȃ�B�v
�@�Ƌ��ɂȂ�A
���L��l�͗L�t�k�������ɁA
�u���Бm�V�͕��@�ɔ��q�d�ˊo�����@�ɔ��l�������@�ɔA�c�c�c�����ĐM�S����ɂ��ċؖڂ���ւ����@�C�s������C�s�L�闬�z�Ƃ͉]�ӂȂ�A�v
�@�Ƌ��ɂȂ�A������l�͉̉�ł���l���A
�@�u�J���Ắ@����ւ��l���̏t�A���掟��Ɂ@���掟��Ɂv
�@�Ƃ����̂��r�̂��]����āA�@�u�g�q�̐�������؏O���̐����Ȃ�A�������L�闬�z�Ȃ�A��h������栂̂��Ƃ��A����ǂ��O��ɏ����a���Ȃ邩�v
�Ƌ��ɂȂ��Ă���B
�@�吹�l�͐M�S�ɑޓ]�Ȃ��g�ɍ��e�Ȃ��C�s�̂Ƃ��낪�L�闬�z���Ƌ����A���L��l�͐M�S����ɂ��ĕ����C�s�̂Ƃ�����L�闬�z�Ƌ��ɂȂ��Ă���̂ł���B�����ē�����l�����ꂽ�̂̔�]�́A�~��ւ��J�����̂����Ďl���̏t��m��悤�ɁA�@�،o�ɂ����Ďɗ�������l�A�q�����̂ĂĐM�������Đ��������Ƃ��A���̐M�̒��Ɉ�؏O���̐���������A�����ɏ@�|���̍L�闬�z������B�������A���̎��掟��͎��̌o�߂܂�@����������킵�Ă���䂦�A�O��Ƃ͑a���ł���Ǝw�E����Ă���̂ł���B�܂�A�@�|���̍L�闬�z�Ƃ́A�@�����̍L�闬�z���O�ɊJ���Ă����ɑ��A���ʁE�ȐS�Ɏ��܂�Ƃ���̍L�闬�z�ł���B
�@�ꐶ�������ɁA
�u�O���̐S�������Γy��������A�S�������Γy�������ƂāA��y�Ɖ]�ЋE�y�Ɖ]�ӂ��y�ɓ��搊u�ĂȂ��B���䓙���S�̑P���ɂ��ƌ�������B�v
�@�Ƃ����䕶�́A�܂��ɌȐS�̍L�X���z������ꂽ���̂ł��낤�B
�@���̌ȐS�̍L�闬�z�A���Ȃ킿�@�|���̍L�闬�z�����@�̊�{�I�ȍL�闬�z�ςł����āA��ɂ��ꂪ��ƂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏�ŁA�i���̖ڕW�Ƃ��ď@�����̍L�闬�z�������̂ł���B
�@����������́A�@�|���ł���Ƃ������Ƃ��m������Ă̏�ł����āA�����ĕ\���Ƃ����Γ��̊W�������Ă���̂ł͂Ȃ��B�@�|�����@��I�ɒ��S�ƂȂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���L��l�̂悤�ɁA�@�����̍L�闬�z�͂��܂茾���Ȃ����t��������B��r�I�A�@�����̍L�闬�z�����������ꍇ���A�@�|���͌���Ȃ��Ƃ����R�̂��Ƃǂ��Ĕc������Ă������䂦�ł���B
�@������ɍ����ɂ����ẮA�@�|���Ə@�����̒��a�͂��납�A�@�|���̑��݂��S����������āA�@�����������@�|���̂��Ƃ��Ɉ����Ă���悤�ł���B����͐�ɂ��q�ׂ����Ƃ��A���邪�Ƃ�������Ă���悤�Ȃ��̂ł��邩��A�@��I�Ɍ����ΑS�����Ӗ��Ȃ��̂ł���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���đn���w��A�L�闬�z���A�ɉq�̎O���̗�������Ȃ���A���{�̎O���̈�̐l�X���M�S��������Ԃƒ�`�Â����B�m�ł���@�|����������A����ɑւ�@�����Ɋm�ł����`���K�v�ƂȂ�͓̂��R�ł���B���̌��ʖ�����肱�����č��ꂽ���̂��A���̒�`�ł������B����́A�@������{�ł������Ƃ����Ƃ��A�K�R�Ƃ��ċN����ۑ�ł������B���̎��A�@��Ƃ��āA�@�|�����L�b�ƒ��A�@�����̍L�闬�z�̑��݈Ӌ`���A���Ȃ킿������������`�̕K�v�̂Ȃ��i���̖ڕW�ł��邱�Ƃ��A�������Ă�����Ȃ��������Ƃ��A�����̔ߌ����錴���ƂȂ����̂ł���B
�@��X�͖{���̏@��`���̍L�闬�z�ς������ǂ����߂ɁA�L�闬�z�ɂ͏@�|���̍L�闬�z�Ə@�����̍L�闬�z�̂��邱�Ƃ��A�܂��͒m��Ƃ��납��n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA���̗��҂̒��a���@�|��������Ƃ��A���S�Ƃ���Ƃ���ɂ��邱�Ƃ�m��ׂ��ł��낤�B
�@�}�q�������āA�����v���E�o�ϊv�����������A�������̌������ɍL�X���z�����邩�̂��Ƃ��ɍl���č�ӂ��߂��炷���Ƃ͋����Ȃ��Ƃł���B�܂��Ă�A�����܂łɂƊ������߂ċ����ȕz����W�J���邱�Ƃ́A���@�̖@�`�ɑS�����������̂ł���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@��X�͂����Ƃ����ƌȐS�̍L�X���z�Ƃ������Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ȐS�̍L�闬�z�A�@�|���̍L�闬�z�Ƃ́A�M�S�ɑޓ]�Ȃ��A�g�ɍ��e�Ȃ��A�M�S����ɕ����C�s����Ƃ���ɐ�������̂ł���B�����āA�l�l�����̐M�S�ɗ����Ė��@���s���Ă������Ƃ��A�Ђ��Ă͉i���̖ڕW����@�����̍L�X���z�ɁA�m�炸�A�������߂Â��Ă����̂ł���B
�@
���@�O���@
�@�ߗ��A���ɖ����ȍ~�ɂ����āA�吹�l�͌����T�N�ɖ{��̑�ڂ����킳��A�O���Q�N�ɖ{��̖{�������킳��A�c��̖{��̉��d�ɂ��Ă͌㐢�̒�q�ɑ����ꂽ�Ƃ����O��e�ʂ̐����x�z�I�ł���B
�@�������`����t���w�����ɁA
�u����s�����A����s����A����s���d�A�O�w��ɓ`����𖼂Â��Ė��@�Ɖ]���v
�@�ƌ����A�܂�������l���Z�����ɂ����āA
�u�}������d�͕��Ƃ̋O���Ȃ�A���̌̂ɐ{�k��������ׂ��炸�v
�@�Ƌ����邲�Ƃ��A�O�w���Ȃ킿���ƂɖΎO���@�́A��ɓ`�����A�{�k������ʂƂ���ɂ��̖{�`������B���R�吹�l�̕��@�͎O�鑊���E�~�Z���V�̕��@�ł����āA���������邲�Ƃ��A�@�c�͎O���@������������Ă��Ȃ��Ƃ��āA�O����e�ʂɘ_���邱�Ƃ́A�吹�l�̕��@�͎O���@�i��b�j����������Ă���ʌ��ו��@�ł���Ƃ������Ƃł����āA�S���@�c��`��������̂ł���B
�@�吹�l�̕��@���O�鑊���E�~�Z���V�ł�������A��X�͉��������̓�����A�O�铯���Ɏ������̂ł���B�����A�O�邪�e�ʂł����ĉ��d�������Ƃ���A���̂Ɂu���g��蕧�g�ɂ�����܂ŁA���O瑖���N�@���̂ĂāA�@�ؖ{��̖{���Ɖ��d�Ƒ�ڂ���������ۂ�v�Ɩ₢�A�u�������ׂ��v�Ɛ����̂ł��낤���B�O�鑊���ł��邪�䂦�ɁA������邱�Ƃ��ł���̂ł���B
�@����ł́A����������Ƃ���̖����E�L�闬�z�̋łɉ��d����������Ƃ����l�������S���Ȃ������̂��Ƃ����A�����Ă����ł͂Ȃ��B������l�̘Z��������钾�����q���A�����������l���������������Ƃ͔F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����������ŁA��ɏq�ׂ��@�|���Ə@�����Ƃ������Ƃ�������x�v���o���Ă������������B�L�闬�z�ɏ@�|���E�@����������悤�ɁA�����ł��@�|���E�@�����������āA�O�鑍�݂̑�@���@�|���Ƃ����A�O�邪�e�ʂɘ_�����A�����ɉ��d����������Ƃ���_�͏@�����ɂ�����B���̏@����������d�����́A�@�|������O�鑊���̋`���킫�܂��Ă����A���̏�ɑ��݂����関���i���̖ڕW�ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ă�����L�闬�z�Ɠ��l�A���ՂȒ�`�i�������Ƃ����O���Ƃ����j�͐T�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����܂Ŗ����i���̖ڕW�Ƃ��Ĕq���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�O�ʓ����t���S�ꏴ�ɁA
�u���d�̕��ʂ͒n�`�ɐ����ׂ��A����M���������̎�����Βq�b�哿�X�����Q�c�𐬂��ׂ��A�����̎���͌��������ɍ݂�A���ڍ������L�����Ƃ����킸�v
�@�ƌ���ꂽ�̂��A���ǂ̂Ƃ���͂�����Ƃ�����`�͒��L���ׂ��ł͂Ȃ��A�ۂł��ʂ��̂��Ƃ����̂ł���B�L�闬�z�̍��Ŏ������Ƃ���A�u���v�Əo���Ƃ��́A�ꌩ��̓I�Ȃ悤�ŁA���͐�ΓI�Ȓ�`�����݂��Ȃ��S���s���S�Ȃ��̂Ȃ̂ł���
�@�䂦�Ɍ×��A���̏@�����̎O��e�ʂ̘_���͌����ēƂ���������A��ɎO�鑊���̏@�|���܂�����Ō���Ă����̂ł���B
�@�Z�����ɂ����Ă��A����钾���̂��Ƃ��A�ꌩ�O�邪�e�ʂɘ_������ꍇ�ƁA�ˋ`�������̌㔼�ȍ~�̂��Ƃ��O�鑍�݂�_������ꍇ�Ƃ�����B������l�͓��R���̕ӂ̒��a�i�@�|�������S�ƂȂ�䂦�ɑ啔�������݂̐����ɔ��Ă���j���l�����āA�Z�������ׂĂ������Č䋳�����������Ă���̂ł��邪�A�����ł͂��̓ǂ݂̐���A����钾�������ɗ͂������āA�@�������Ƃ���������Ă���悤�ł���B
�@���āA���̏@�|���i���݁j�Ə@�����i�e�ʁj�Ƃ̒��a��[�I�Ɏ�����Ă���̂��A�ˋ`�������̎O���@�J���̑��ł���B��Ɉˋ`�������̌㔼����@�|�����������Əq�ׂ��̂́A�܂��ɂ��̊J���̑��������ꂽ�ȍ~�Ƃ������Ƃł���B
�@�O���@�J���̑��Ƃ́A�ǂ�Ŏ��̂��Ƃ��A�O���@��������`�ƁA�J���`�������ꂽ���̂ŁA�܂��͉��̂ɂ��̗��`���K�v�ł���̂��Ƃ������Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���_���炢���A�O�������@�ɍ����O�鑊�������킷���Ƃ́A�@�|����������Ă���̂ł���A�O����X�ɘZ�ӂɊJ���̂́A�O��́u���v�Ƃ��Ă̑��ʁi�@�����j���A�@�|������@�c�ȐS�O�鑍�݂̈���@�Ƃ̒��a�̂��߂Ɏ����ꂽ���̂Ɣq����̂ł���B����͓�����傪�A���̎O���@�̊J���̑����������ɂ������āA��Ƃ��Ĉ��p����Ă��鍂�m�`�́A
�u��S�Ɩ��@�̑��̖�A�����ĉ���b�ƂȂ�A�J���ĘZ�x�ƂȂ�U���Ė��s�ƂȂ�v
�@�Ƃ������Ƃ��킹�l����Ηe�Ղɗ����ł���Ǝv���B
�@�܂�A���@�̑��̂���吹�l�̓��E���s�̖��@�@�،o�E�O�鑍�݂̑�{���������@�|���ł���A�ȐS�ҖŖ�ł���B�����Ă���́A�O�邪����@�ɍ�����p�ł���B
�@��������Ɏ��������Ƃ��A�O�邪���ꂼ��ɕ��̂Ƃ��Ă̌�{���A���邢�͌����Ƃ��Ẳ��d���A�����Č����̑�ڂƁA�F�i�����j�̐��E�Ŋe�ʂɘ_�����邱�Ƃ�����B���ꂪ�ȐS�̖@��i�@�|���j�̐��ԁi���ʁj�ւ̍Œ���̑Ë��A���Ȃ킿�@�����ł���B�����Ă��̏@�|���Ə@�����̒��a���Z�ӂɊJ���邱�Ƃɂ���Ď�����Ă���̂ł���B
�@����钾���ɂ����Ă͎O�邪�Z�ӂɊJ����Ċe�ʂɘ_�����A�ˋ`�������̎O���@�J���̑���������Ă��ȍ~�́u�O�w��`�v�u�O�w�͐{�k�����ꂸ�v�ƁA��ɑ����̗�����q�ׂ��Ă��邱�Ƃ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@�ꎞ���ɖ��ƂȂ��Ă����������d�_���A�����ȍ~�̖@��̋������琶�����A�������w�̗����q�ł���B��㌾����Ƃ���̉��d�����Ƃ́A�@�|������O�鑍�݂̑��{���E�v�������̖��@�@�،o�܂�����ł̉��m���ɗ^����ꂽ�i���̖ڕW�Ɖ����ׂ��ł���B��炩�ȏ��̌��t�̌��t�������āA��ꍑ�����A��ꖯ�O�����Ƌ����ɒ�`�Â��悤�Ƃ��邱�Ƃ͑S�������Ȃ��Ƃł���B������@�|���������āA�@�����������ď@�|���Ǝv������ł��܂����ǂ݂̐������炵���ߌ��ł���B
�@�吹��̌�@��̐[����ǂ݂Ƃꂸ�A��������ɏ@������ǂ��܂킹�A�吹�l�̕��@�Ƃ͑S�������ȁA�\�͂�������B���{�����Ƃ����A���{�������邱�Ƃ��l���A���E���Ƃ����ΐ��E���e���l����̂́A�吹�l�̌�@��̉����邩��S�������ł��ʂ���ł���B���ケ�̉��d�������A�i���̖ڕW�ł��邱�ƁA�����ď@�|���܂�����ő��݂�����@�������邱�Ƃ��m�F���邽�߂ɂ��A���r���[�Ȓ�`�͂�߂āA��腕��Ƃł����ׂ��ł���ƍl����B�������{���̉��d�����́A�i���̖ڕW�̍L�闬�z��^���ɖڎw���A�����C�s�ɗ�ނƂ���ɌȐS�̍L�闬�z������悤�ɁA��腕��̉��d������ڎw���A�M�S����ɎO���@���݂̑�@���������Ƃ���ɁA���ȐS�̕����y�ɁA���������̂ł���B
�@
���@�ܕ�
�@�ܕ��Ƃ́u�@�ؐܕ��j���嗝�v�Ƃ����āA����̗��A���Ȃ킿�^���łȂ����̂ɑ��āA�Ë����������Ă����s�ׂł���B���ݐܕ��Ƃ����ΒZ���I�ɁA��z���@�Ƃ��Ă݂̂Ƃ炦��ꂪ���ł��邪�A�����Ă���Ɍ��肳�ꂸ�������܂߂Č���̗��𐳂��Ă����Ƃ����A�L���Ӗ��ł̐M�p�������������̂ł���B
������l�́A
�u��ɐS�ɐܕ���Y��Ďl�ӂ̖������v�͂���ΐS��掖@�ɓ������R���ɐܕ������͂���Ό���掖@�ɓ������R��Ɏ쐔�������Ė{���Ɍ��͂���ΐg��掖@�ɓ������A�̂ɖ@�ؖ{����ʕ��ꉺ�펖�̈�O�O��얳���@�@�،o�Ə��鎞�A�g���ӂ̎O�Ƃɐܕ����s����Җ�B���ꑥ�g���ӎO�Ƃɖ@��M����l��]�]�v
�@�ƌ����A�ܕ��Ƃ͊�{�I�ɂ͂܂��Ȃ�Ɍ�����ׂ����Ƃ������Ă���B�܂�@�c�吹�l�̕��@��S����M���A�{���Ɍ������얳���@�@�،o�Ə����A���S�R���䂪�S�̔ϔY�����߂āA����ɑË������A�j�܂��邱�Ƃ������Ȃ�ɑ���ܕ��ł���B
�@���ɕz�����@�Ƃ��Ă̐ܕ��́A�@�c���A
�u���@�͕s�y�̐Ղ��Ќp���v
�@�ƌ���ꂽ�悤�ɁA�@�،o��s�y��F�i��O�\�ɐ������s�y��F�̍s�������Ă��̎�{�Ƃ���B
�@�s�y�i�ɂ́A�s�y��F����؏O���d���]�Q���āA�l���l���ƂɁu���͐[�����Ȃ������h���܂��B�������Čy���������܂���B�Ȃ����Ȃ���Ȃ����͐��@��M����F�̓����s���ĕK�����ɂȂ�ׂ����X������ł��v�ƌ����Ď�����킹��q���A�O�l���������Ă��Ԃ��������Đ𓊂��A��őł��Ă��Ȃ��A���苎���ĉ�����萺���ɂ��̌��t���J��Ԃ������Ƃ�������Ă���B
�@�J�Ԑܕ��Ƃ�����ɂ́A���ɔr���I�E�\�͓I�C���[�W�������悤�ł��邪�A�{���͑S���t�ŁA�ނ���z���̌��ʌȂ�ɑ���\�͂������Ă��A�����E�ёς��āA�����Ĉ��ނ��ƂȂ��A�Ȃ����@��������߂̍s��ܕ��Ƃ����̂ł���B
�@�@��̗��j��U��Ԃ�A�@�c�吹�l�ȗ��\�͂������Ƃ͂����Ă��A��x�Ƃ��Ė\�͂�U��������Ƃ��Ȃ����Ƃ�m��̂ł���B�����Ȃ�\�͂��Ă��A����Ȍ��͂ɂ����������Ă��A���ꂪ�ԈႢ�ł���ΑË��������`���咣���鋭���������ܕ��̖{�`�ł���B�������O�Ɍ������āA���͍s�g�̕z�����s�Ȃ���Ƃ���R����͐ܕ��ł͂Ȃ��@���Ƃ͖����ȒP�Ȃ�\�͂ɂ����Ȃ��B
�@�ߗ��n���w��ɂ���đS���I�ɓW�J���ꂽ�ܕ������́A���̖\�͐����Љ�̖��ƂȂ��Ă���B�������n���w��̐ܕ��͐�q�̂Ƃ��苳�`�̓ǂ݂̐ƁA�n���卑���ɂ݂���悤�Ȕ@�I�Ȗ�]�A�����ĉ���ُ̈�Ȍ������v�w���i�ܕ��̐���������Α����قǁA�����̊肢�������ƓO��w������Ă���j�Ƃ����ւ��ďo���オ�����A�w��Ɠ��Ȋw��ܕ��Ƃ�����B
�@���݁A���@�`���̖{���̐ܕ��̈ӂ��A���ԓI�ɂ��A�܂����@�M�k�̑啔���ł���w����ɂ����Ă��A�S��������ꂽ�`�ő������Ă��邱�Ƃ́B���Ɏc�O�Ȃ��Ƃł���B�@��Ƃ��Ă̐ӔC�̏d��Ȃ邱�Ƃ�F������ƂƂ��ɁA�{���݂̍���𐢊ԁA�܂��@���葖����邱�Ƃ��}���ł��邱�Ƃ�Ɋ�����B
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�͂��߂�
�@�ߓ��A�v�ې�t�̘_���ɑ��ĎR���L�t�ꓯ�Ə̂���_�����@���ɗX������܂������A���̒��Ŗ{���`�y�ь����`�Ɋւ��@�`��w�̉ӏ��������܂��B
�@�܂��R���L�u�_���́A�v�ې�t�̏��_�ɑ��Ă��܂�ɂ�����I�ɂȂ�A�����p��𗐗p���c�t�Ȍ����ɏI�n���Ă���܂����A�����ɂV���ڂɂ킽���Ă��̌����w�E���A�Ȃē��Ɩ{���̖@����q�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B
�@�R���L�u�]���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�u���d�̑��{�����v���̖{���v
�u���@�吹�l���v���̖{���ƐM�����܂��]�]�v
�@�R���L�u�͉��d�{���y�ѓ��@�吹�l���v���̖{���Ƃ��Ă��܂����A����͈�̔@���Ȃ�_�߂Ɉ˂�̂��A�����]�ĕ��������Ƃ�����܂���B���d�{���E���@�吹�l�Ƃ͋v�������̖{���ł����āA�����ċv���̖{���ł͂���܂���B���炭�R���L�u���v�������Ƃ����Ӗ��ŗp���Ă���̂ł��傤���A����ɂ��Ă������I�ȃ~�X�Ƃ����܂��B������x���@�p��̈ꂩ����Ȃ����ׂ��ł���܂��傤�B
�@���������v���Ƌv�������̑��Ⴊ�����ł��Ă��Ȃ����Ƃ��琶������ł���܂��傤���A�v���Ƌv�������̑���͓��Ɩ@��̑�O��ł����āA������������Ă���R���L�u�_���̒��x�������ƒm��悤�Ƃ������̂ł��B
�@������l�̖��@�������ɂ́A
�u�₤�A�����C���L�ɉ]�킭�A��@�̖{���v�������̎���p�g�Ȃ�A�v���̌��A�{���{�ʂɘj���嫂��A�v�������̎���p�g�̌��͒A�{�ʂɌ����Ė{���ɘj�炸�v
�ƁA����͗v�@���L�����C�̐��ł��B���̈ӂ͋v���Ƃ����ꍇ�A�{���{�ʁA�����ߑ��̈��s�ʓ��̑o���ɒʂ��邱�Ƃł���A�v�������Ƃ������́A�{�ʑ����v�������ܕS�o�_���Ɍ���Ƃ������Ƃł���܂��B
�@����ɑ��ē�����l�́A
�u���Ⴕ�Ă��v���ƌ�������Ώ���ʂɒʂ��A���������{�ʂɒʂ���݂̂Ȃ��B�Ⴕ�v�������Ƃ͒A�{�������Ɍ����ď��{���̏��Z�ɒʂ����A���ɋ����{�ʂɒʂ������v
�Ɠ����Ă��܂��B�����ŋv���Ƃ������ɂ́A�L�����C�̂����悤�ɖ{���{�ʂɒʂ���̂ł͂Ȃ��A�{�ʑ����ܕS�o�_���݂̂Ȃ炸�A�����O��o�_���ɂ��ʂ��Ƃ����A�v�������Ƃ͂����{�������Ɍ���̂ł���Ɖ]���Ă���̂ł���܂��B
�@�R���L�u�́u�v���̖{���������@�吹�l�v�Ȃ�ꂪ�@���Ȃ�Ӗ��������Ă��邩�A���̖��@�������ɏƂ��Ė��炩�ł���܂��B�Ⴕ�v�����{���A�����ܕS�o�_���̓����ɂ��ʂ���Ɖ]���A�v�@�����C�̋v���Ɖ����ς�Ƃ��낪����܂���B�v���Ƃ͎O��o�_�����܂߂ČܕS�o�_���A�v�������Ƃ͌ܕS�o�_���̓����A�����v�������̎����]���̂����Ə����̋`�ł���܂��B�ނ̎R���L�u�ɂ͍L�����C�Ɠ��������߂̍���������悤�ł��B
�@�R���L�u�]���A
�u�B�S�v�z�ɂ��Ԃꂵ����t�ɂ͌�{�������Ǝv���{�Ǝv���A���̈�O�O�炱�����ŋɖ���Ɗς��Ă���l����v
�u���̈�O�O��Ǝ��̈�O�O��̈Ⴂ�͉����ɂ���̂��A�l�@��ӂƂ͉�����v
�@��{��������Ǝv������ł���͉̂����v�ې�t�␛��t�ł͂���܂���B�ނ���R���L�u�̕��ł���܂��B
�v�ې�t�␛��t���j�܂����̂́A�R���L�u���ɑ�\�����@���A��{���⌌����B�������ł����Ƃ炦�邱�Ƃ̂ł��Ȃ����݂̖{���ϋy�ь����ς�j�܂����̂ł����āA�����Ė{���̖{���`�A�����`��ے肵�Ă�����̂ł͂���܂���B�������̂悤�Ɍ���̂ł���Ό�����ɖ�肪����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�����������Ɩ@��ɉ�����@�����Ə@�|���̈Ⴂ�������ł��Ă��Ȃ����ɁA���̌��̍���������悤�Ɏv���܂��B�@�����Ƃ́u���Ƃ͐��l���ɔ�炵�ނ�̌��v�Ƃ����@���A���ɑ��݂����䶗��ɑ���M�y�яC�s�̊����̈Ӗ����܂߂Ė{�ʁA���������O���̈ӂŁA�@�|���Ƃ͉��d�̖{���̂ł�������܂ł̉ߒ��A�{���̓��e�A�����{���A�����㋁���Ɋւ��邱�Ƃł���܂��B�����}�Ɏ����A
�@�@�|���|�{���C�s�A�㋁���A���d�̖{����������܂ł̏C�s
�@�@�����[�{�ʏC�s�A�����O���A��䶗��ɑ���M��
�ƂȂ�܂��B�v�ې�t�␛��t�͂��̏@�|���̘b�����Ă���̂ɑ��A�R���L�u�͏@�������Ȃď@�|����j�܂��Ă��܂����A����͌����Ⴂ���r�����Ƃ���˂Ȃ�܂���B�v�ې�t�͎���p��g�@���̗��t���������A����ɍ����ꂽ����������Ɨ������ĉ��d�̖{���ł���Ƃ����悤�ȗB���I�v�l�ɑ��Ĕj�܂��������̂ł���A�]���Ƃ������͌������̕����ɂ���Č��킳��Ƃ�������p��g���������d�̖{���ł���Ƃ������Ƃł���܂��B
���ꂪ�@�`��w�Ɖ]���Ȃ�A����͑吹�l�A������l�ɔw�����ƂɂȂ�܂��B�吹�l�́A
�@
�u���ɂ��ɂ��Ȃ���ʕi�̎ߑ��Ȃ�v
�Ƌ��ł��B����͑���{��������ʕi�̎ߑ��Ƃ������Ƃł͂���܂���B���ɂ��{�ɂ������镶����ʕi�̎ߑ��Ƃ����Ӗ��ł��B���R������ʕi�̎ߑ��A�����v����������p��g�����{�łȂ���Ȃ�܂���B�v����������p��g�̗��t���̂Ȃ���䶗��͕L��{���ł͂���܂���B
�@�������A�R���L�u�͂��̎���p��g�𗝂̈�O�O��Ɖ����Ă��܂����A����͏��X�\���ł͂Ȃ��̂ł��傤���B
�v����������p��g�Ƃ́A���ꎖ�̈�O�O�炩��F����ꂽ�v�������̎��s�̖��@��l�ɖĎ���p��g�Ƃ����̂ł���A�@�ɖΉ��d�̖{���ł���܂��B���̋v����������p��g��ے肷��Ƃ������Ƃ́A���d�̖{�������ے肷�邱�ƂɂȂ�A���ꂪ�@�`��w�łȂ��ĂȂ�ł���܂��傤�B
�@���̂悤�ȍ����́A��Ƃɉ]�������Ɠ��Ə����̎����A�����@�̂̎����̑��Ⴊ��������Ă��Ȃ����̂ɋN��
���̍����ł���悤�Ɏv���܂��B
������l�͖{�������i�ɁA
�@
�u�����̖��ڂ͂܂��ɖ@�̂ɖׂ��v
�@ �Ƌ��ł��B���̈�O�O��A���̈�O�O���_���鎞�ɂ́A���ꂪ�䓖�̖@�̂̎�����_���Ă���̂ł���A�Ƃ������Ƃ��R���L�u�͂܂��m��K�v������܂��B
�@�̂̎����ɉ�����䓖�̑���Ƃ́A����钾���ɉ]���A
�@
�u�₤�A�C�T�������ɉ]�킭�A��x��t��O�O��̖{�����ȂĒq�ґ�t�ɕt���A�����G���̏\��ʊω���B����̖ʂɏ\�E�̌`����}���A��O�O��̑̐������킷�A�T����ʂ͈�S�̑̐������킷�]�]�B���ɏ\�E�̌`����}�����킷�A���ɐ��ꎖ�̈�O�O��Ȃ�ׂ���B
�����A�V���}������嫂��P���ꗝ�Ȃ�A����ƂȂ�ΎO��̑̐��A��S�̑̐���}������̂Ȃ�B���ɒm��ׂ��A�̐��͑������ꗝ�Ȃ�A�̂ɒm��ʁA�������Ɍ��킷���Ƃ��B���̌̂ɖ@�̗P���ꗝ�Ȃ�A�̂ɗ��̈�O�O��Ɩ��Â���Ȃ�B�Ⴙ�Α�t�̌����ė��s�̑�ڂƖ��Â��邪�@���Ȃ�B�Ⴕ�����̈ӂ͎������Ɍ��킷�A���̌̂ɖ@�̖{���ꎖ�Ȃ�A�̂Ɏ��̈�O�O��̖{���Ɩ��Â���Ȃ�B
�₤�A�Ⴕ�R��Α��̖@�[�̎��Ƃ͉��B
�����A�����]�Đl�Ɍ����č����̔@������������]�]�v
�ƁA���̕��ɉ����鎖���̐����́A�R���L�u�̍l���Ă����ɂ݂��镨�A���������Ɍ���ꂽ���̂����Ɖ]���A��ɉf��ʂ��́A���������𗝂Ɖ]�����Ƃ��A�����ł͂Ȃ��Ɣے肵�Ă���̂ł���܂��B
�@�܂�A��x��t���V���t�ɕt�����G���̏\��ʊω��͈�O�O��������Ɍ��킵�����̂ł��邩��A����͎��̈�O�O��ł͂Ȃ��̂��Ƃ����₢�ɑ��āA����͖@�̂��̂��̂����ł���ȏ�A���Ƃ�����������Ɍ��킻���ƁA�����܂ŗ��̈�O�O��̔��S���o�Ȃ��B���������Ƃ͖@�̂��̂��̂����ł����āA����������Ɍ��킷�̂Ɏ��̈�O�O��Ƃ����̂ł���A�����Ɍ���ꂽ���̂����Ɖ]���A�����Ȃ����̂𗝂Ɖ]����ł͂Ȃ��Ɠ�����l�͋��ɂȂ��Ă���̂ł���܂��B�R���L�u�́A��ɂ݂�����̑������A��ɂ݂��Ȃ����̑������ƒZ���I�ɗ������Ă���悤�ł����A����͖��炩�ɒʓr�̎����̍l�����ƁA�@�̂̎����̍l�������������Ă���Ƃ����]���悤������܂���B
�@����ł͖@�̂̎��Ƃ͂ǂ̂悤�ɔc��������悢�̂��A����ɂ��ē�����l�͕���钾���ɂ́u�l�Ɍ����Đ������v�Ɣ邳��Ă��܂��B�����ŎR���L�u�̌������o���Ă��������ׂɂ��A����ɂ��Ė��炩�ɂ��Ă��������B
�@�܂��J�R������l�͂ǂ̂悤�Ɏ�����Ă����邩�Ɖ]���A�d�~�L�ɁA
�@
�u�����͊ϐS�̏�Ɍ��ӂ𗧂B���͏�s���`�̖��@�{�厩�s�̗v�@����Ȃ�B�߂ɉ]�킭�A���̖��@�@�،o�͖{�n�r�[�̉����Ȃ�B�{�n�Ƃ͌��ӂƓ������ƂȂ�B�O���@���̎t�Ƃ����������A�ꕧ�s�o�����ӂ̑�@�ɔ�B������ȂČ��ӂƂ͖{�����C�̖@�̂Ȃ�B�܂̏\�ɉ]�킭�A�����͏������ȂĈ����ƈׂ��A瑖�͑�ʂ��ȂČ��|�ƈׂ��A�{��͖{�����ȂČ��|�ƈׂ��ƁB���|�ƌ��ӂƓ��ӂȂ�v
�Ƌ��ł��B�����Ŗ@�̂̎��Ƃ́u�O���@���̎t�Ƃ����������A�ꕧ�s�o�����ӂ̑�@�A�{�����C�̖@�́v�Ƃ������ƂɂȂ邪�A����͎O�������͉����C���ĕ��ɂȂ������A�����ߑ��y�юO�������o���̗̌��i�{�n�j�Ƃ͈�̉����Ɖ]���A����͖{�����C�̖@�̂ł���Ǝ�����Ă���̂ł���܂��B�v����ɖ@�̂̎��Ƃ́A�ꌾ���Ȃĉ]���Ζ{�����C�̖@�̂Ƃ������Ƃł���A���̖{�����C�̖@�̂��̗��A�����{�n�Ƃ��邪�̂ɖ{�ʎߑ��y�юO�������͐�瑁E���ƂȂ�̈ӂł���܂��B�����S�Z�ӏ��̈�㉞���̖{瑁A�����A�u�v������E��R���E�E���@�l���̏O���𗘂���ׂɁA����O�g�����y���O��O�q���Ȃċ�E��m������瑂𐂂�A�����{���A��ɖ��o������A�̂ɍ����̖{瑋���瑂Ƃ������̂Ȃ�v�̕��Ő}������ƁA
�{�n�@�����y�̖���O�g�c�{�����C�̖@�́i���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i�@�،o�E�{�ʁj
��瑁@��瑎{��������o�c�����̖{瑋���瑁i���j
�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@���Ď����y�ɋ�������O�g�Ɛ������ꂽ�{�����C�̖@�̂Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�Ɖ]���A
�{�������ɉ]���A
�u�ށi�V��j�͐����̖��@�̖���ւ��Ĉ�S�O�ςƖ��Â��A�L��̘Ԃ̑�@�ɔ�Αь��̖@�Ɏ�����v�@
�@
�ƁA���̕��ɂ��Ǝߑ����������V��̈�O�O�炪���̑ь��̖@�ł��邩�Ƃ����ƁA�L��̘Ԃ̑�@�łȂ�����@�ł���Ɛ�����Ă���̂ł���܂��B�t���]���A�^���̖��@�Ƃ͗L��̘Ԃ̑�@�łȂ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����Ă���Ɖ]���܂��B
�@����O�g�̖���Ƃ͍��Ȃ��A����̂܂܂̈Ӗ��ł����A�ߑ��y�юO�������͂���̂܂܂̑�@����o�łāA����̂܂܂łȂ����삵����������Ă��邪�̂ɁA�����瑂Ɖ]���A����̂܂܂̑�@���Ȃē��Ƃł͖@�̂̎��Ɖ]���A�܂����ꎖ�̈�O�O��A�v�������̖��@�Ɖ]���̂ł���܂��B
�@�Ƃ���ł���̂܂܂łȂ����삵����������Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��w���ĉ]���̂��Ƃ����A���Ƃ͊o�҂Ƃ����Ӗ��̒ʂ�A�S���ϔY������܂���B�܂��肾���̐��E���Ӗ����Ă��܂��B���Ƃ��ƌ��Ƃ͔ϔY��f���邱�Ƃɂ���ē�����̂ł����A������������Ă����ϔY���S���Ȃ��Ȃ��Č�肾���ɂȂ��Ă��܂��A����͂���̂܂܂łȂ����낢�̕��Ɖ]����̂ł���A���̕�����ɉ������i�̎���p�g�Ə̂���̂ł���܂��B
����ł͂���̂܂܂̑�@�Ƃ́A�@���Ȃ邱�Ƃ��]�����Ƃ����A�u��؏O�����L�����v�̟��όo�̌o���̔@���A��؏O���͂��̋�Ă���ϔY�̒��ɕK���܂��������������Ă��܂��B���͂��̔ϔY������C�s�ɂ���Ēf���Ă��܂��̂ł���܂����A����̏ꍇ�͔ϔY������C�s�ɂ���Ēf����̂Ă͂Ȃ��A�ϔY����Ȃ��炻�̔ϔY�̒��ɕ��̐��������o���A���Ƃ��đ����ɑ̒B���Ă����̂ł���܂��B���̂悤�Ȑ�����O�̉������i�ɑ��A���ʑ����s���{�ʂ̐����Ɖ]���A�{�ʂ����߂邱�Ɓi�ϔY��f���s�����Ɓj�Ȃ��A���ʂ̂܂ܑ����ł���Ƃ����Ӗ��ł��B�����đO�̉������i�̒f�f������ߑ��������M�������Ɖ]���A���ʑ����s���{�ʖ��f�f�̐���������@�O���@�Ɖ]���܂��B�M�������Ƃ͉����ߑ����M���o�g�Ă��邪�̂ɋM�������Ɖ]���̂Ă͂Ȃ��A���O�����̂���̂܂܂̑�@����o�āA�K�i��o��@���ϔY��f���A��肾���̐��E�A�������O�i��؏O���j�Ƃ͓V�n�̊u��̂��鑢�삳�ꂽ���ł��邪�̂ɂ�����M�������Ɖ]���̂Ă���܂��B
�܂��M�������𗝁E瑂̖@�́A���O���@�����E�{�̖@�̂Ƃ����̂́A�ߑ��A�����M�������̑�����ς�̂ł͂Ȃ��A���O�̑�����M���������ςāA����𗝁E瑂Ɖ]���A��������E�{�Ə̂���̂ł���A
���@�������ɉ]���A
�u�}�v�͑̂̎O�g�ɂ��Ė{���������A���͗p�̎O�g�ɂ���瑕��Ȃ�v
�@�Ƌ��Ȃ̂��S�����̗��R�ɂ��̂Ă���܂��B
�@����܂Ŗ@�̂̎����̂Ƃ炦���ɂ��ďq�ׂĂ��܂������A�ȏ�̂��Ƃ�v���̂��O���@���������ł��B
�@�]���A
�u���̈�O�O��͖����̎��Ȃ�A���͖̌̂Ϗ�̏\�E���{�L����̊o�̂Ɖ]�ӂȂ�B����̎��̊O�Ɋo��̎������Ȃ�A�V���ȂĔނ��v�ӂɁA�V��`�����O�ނ鏊�̎��̈�O�O��͌咆�̎����ɖ̂ɗ��ɑ�����Ȃ�ׂ��v
�ƁA�v����ɖ@�̂̎�����_���鎞�ɂ́A���Ƃ͎����i����j�A���Ƃ͗���i�L��j�ƕ��ʂ��邱�ǂ������ā@���܂��B���L��l���̋������S�����̕��ʂł���܂��B
�@����ɎR���L�u�́A�v����������p��g�@���𗝂̈�O�O��Ɖ����Ă���̂ł���܂����A����p��g���@�̂̎��̈�O�O������ɍs�������̖@���l�A�l���@�A�l�@��ӂ̎���p��g�ł���ɑ��A�Ђ��ƌ咆�̗��̈�O�O��Ɗ����Ă���B����p��g�����̗��̈�O�O��Ƃ���̂��A�܂��ɓ�����l�̉]��ꂽ���߂̍������̂��̂Ɖ]������̂ł��B
�@�Ƃ���ŋv�ې�t�␛��t������p��g�̗��t�������������d�̖{�����]���Ƃ��āA���̗B�������ɑ����{���ς�ے肵�Ă���̂ɑ��A�{��������{�Ǝv������ł��܂��Ă���B���_�҂���R���L�u�ɂ́A�ǂ����B�S�v�z�Ɖf��炵���B�O�҂����ꎖ�̈�O�O�炪�X�ɏ������v�������̎���p��g��_����ɑ��A�R���L�u�͖@�̂̎����̕��ʂ����Ȃ��܂܁A���̈�O�O��Ɣj���Ă���̂ł��邪�A���������҂̘_���Ă��鎟���ɂ��܂�̍������肷���āA���Ƃ��n���ɂ����Ȃ���������̂ł���܂��B
�@���������R���L�u�͌�{������̂��̂ƌ��߂Ă������Ę_���Ă��܂����A��䶗�����{���ƌ��߂ĐM���邱�Ǝ��́A�M�҂Ƃ��Č����Ĉ�����ł͂���܂���B����ǂ����ꂾ���Ȃ�Ή����M�k�ƕς鏈������܂���B�{���m���Ƃ́A���̖{�����ł������閘�A�����@�|������������Ɣc��������ʼn����O���ɓ���̂��{���ł���܂��傤�B���ꂳ�����ے肷�邱�Ƃ͎���̗��ꂻ�̂��̂�ے肷�邱�ƂȂ̂ł���܂��B�������R���L�u�̘_���ɂ͂����������@�|���������o����܂���B���̂悤�ȏ@�|����c�����Ȃ��m���������Ȃ������̂ɁA�����n�����w�Ɉ����Â��Ȃ���A�����������ӂ��Ă���̂����킩�炸�A�@�傪���U�������悤�Ȏ��ԂɂȂ����̂ł���܂��B�u�V����m�炸�A�r���Ɏ����̑z�����Ȃ����̔@���v�͋v�ې�t�␛��t�ł͂Ȃ��A�R���L�u�̕��ł���Ɖ]��Ȃ���Ȃ�܂���B
�@
�@
�@�R���L�u�]���A
�u���d�̑��{���𗣂�ċv�������̎���p�g�@���݂�Ƃ͓V����m�炸�A�r���Ɏ����̑z�����Ȃ����̔@���āA�S�����@���@�m�����n�ɑ������̂Ă���B���̈�O�O��Ǝ��̈�O�O��̈Ⴂ�͉����ɂ���̂��A�l�@��ӂƂ͉�����v
�@�R���L�u�ɖ@�̂̎����̕��ʂ��S�����Ă��Ȃ����Ƃ͑O���ďq�ׂ��@���Ă���܂��B�R���L�u�́u���d�̖{���𗣂�ċv�������̎���p�g�@���v�͌��Ȃ��Ƃ��Ă��܂����A�v�������̎���p��g�𗣂�ĉ��d�̖{���͌��Ȃ��̂Ă���܂��B���̂悤�ɎR���L�u�̐��͂��ׂĂ��{���^�|�ɂȂ��Ă���A�{�����L�̋^���Ƃ�܂���B�R���L�u�̍����͕���O�炩��F������v����������p��g�A�����Ă��̎���p��g�����d�̖{���Ƃ��ď����Ă������̉ߒ����S����������Ă��Ȃ����̂̍����Ă���܂��B
�@�O���ɉ����ẮA�@�̂̎��ɂ��āA���̍l�����A�Ƃ炦�����q�ׂ����A�����Ă͕���O��̑�@����F������v����������p��g�B�������̖@�̂��̂��̂ɂ��čl���Ă݂����B������l�͘Z�����̒��A����钾���Ă͖@�̂��̂��̂ɂ��Ắu�����]�Đl�Ɍ����č����̔@������������v�Ɖ]���A���ꂪ�������͓̂����s�����̏���тɉ��ĂĂ���܂��B
�]���A
�u�䓙������鏊�̖{��̑�ڑ��̑̉�������B���킭�{��̑�{������Ȃ�B�{��̑�{�����̑̉�������B���킭�A�@�c�吹�l����Ȃ�B�̂Ɍ䑊�`�ɉ]�킭�A�����̎��A���E�̏\�E�������@�Ȃ�A�̂ɓ��@���Ǝ�t�i�ʂ��Â��j������B���]�킭�A�������r������ɕs�v�c�Ȃ���@���e���̑��䶗��Ȃ�B���]�킭�A������ꋋ�����̎����͕��E�Ȃ�A�������䓙�O���͋�E�Ȃ�A���ꑥ���^���̏\�E��Ȃ�]�]�v
�@�u���̋`���ɉ]�킭�A
�@
�{����ʂ̓��̘@�ؕ��Ƃ͓��@����q�h�ߓ��̒��̎��Ȃ�]�]�v
�u�{�������ɉ]�킭�A�V��]�킭�A���ߐ��������]�]�A�`���]�킭�A���E�̒q�͋�E�����ƈׂ��A��E�̒q�͕��E�����ƈׂ��A���q�݂��ɖ��O���}����P�Ȃ�A����ߐ����Ɖ]���A�O�����O���Ɖ�����Ώ��������܂��^�P�Ȃ�A������Ɖ]���v
�@�ƁA���ꓙ�̕����������ƁA
�@�P�@�䓙������鏊�̖{��̑�ڂ̑̂Ƃ͉��Ă��邩�Ɖ]���A����͖{��̑��{���ł���B
�@�Q�@�{��̑��{���̑̂Ƃ͉����Ɖ]���A�\�E��̘@�c�吹�l�Ă���B
�@�R�@�\�E��̘@�c�吹�l�Ƃ́A������ꋋ�����̎����̕��E�i�t�j�Ə������䓙�O���̋�E�i��q�j�����q���������\�E��̎t���ӂ̏����w���āA�@�c�吹�l�Ɖ]���̂Ă���B
�@�S�@�@�c�吹�l�Ƃ́A�܂��{����ʂ̓��̘@�ؕ��̂��ƂĂ���A�{�t�@�c�ƒ�q�h�߂��ׂĂ��w���ĉ]���̂Ă���B
�@�T�@���̂悤�Ȏt���ӂ̘@�c�吹�l�Ƃ������̘@�ؕ��Ƃ́A�ǂ̂悤�ɂ��Đ����邱�Ƃ��Ă��邩�Ɖ]���A�t�͒�q�̑����Ă��閭�@�����Ƃ��i���E�̒q�͋�E�����ƈׂ��j�A��q�͎t�̎����Ă��閭�@�����Ƃ��i��E�̒q�͕��E�����ƈׂ��j�A�݈唺���āA�X�ɑS���t��̍��ʂ̂Ȃ��t���ӂ������ɘ@�c�吹�l�Ƃ������̘@�ؕ��������邱�Ƃ��Ă���B
�@���̓��̘@�ؕ����̂��āA�v����������p��g�@�c�吹�l�A�܂����ɋv�������̖��@�Ƃ��]���A���ꂪ���̖@�̂̐��̂Ă���܂��B���d�̖{���Ƃ́A���̋v�������̖��@�����ɍs���Đ�����̂Ă���A�v�������̖��@��������p��g�̗��t���̂Ȃ��{���͂��肦�Ȃ��̂Ă���܂��B�R���L�u�́u���d�̖{���𗣂�Ď���p��g�v�͌��Ȃ��Ƃ����l�����ɁA���q�ׂ����̎���p��g����������Ă���Ƃ͓���v���Ȃ��̂Ă���܂��B
�@
�@
�@
�@
�@�R���L�u�]���A �u�Ȃ�A�_�C�i�}�C�g��{�ł����ƂԂł��낤���@�吹�l���v���̖{���Ƃ͐M�����܂��A����Ȏ���B�Ȃ���A���Z���̎l���Ƃ��������̎p�ɂ̂ݎ����Ă������m�ɂ́A���O���~�Z�������̖��n���I�͐M�����܂��v
�@ �v�ې�t�A����t�A�����Ď��B�͓��Ɩ{���̖{�����@�吹�l����d�̖{���������ă_�C�i�}�C�g��{�ł����ƂԂƂ͎v���Ă����Ȃ����A�]���Ă����Ȃ��B�����R���L�u�����Ă���B���I�{���E�{���ς�ے肵�Ă���̂ł���܂��B
�@ �R���L�u�́u�Ȃ�_�C�i�}�C�g��{�ł����ƂԂł��낤���@�吹�l�v�ƁA����t��ᔻ���ĕ\�ʂ͔֒����̉i���s�����������Ȃ���A�t�Ɏ���{���E�{�����_�C�i�}�C��{��A�����͐��Z���̗��ɂ���ĕK���ł��邱�Ƃ�F�߂Ă��܂��B�{���������Ƃ��ĂƂ炦�Ă������R���L�u�͂��̗�����Ƃ�邱�Ƃ͂ł��܂���B�������{���Ƃ͋����ł͂���܂���B
�ϐS�{�����ɉ]���A
�@
�u�����łɉߋ��ɂ��ł��������ɂ��������A�����Ȃē��̂Ȃ�A���ꑦ���ȐS�̎O���A�O��̐��ԂȂ�v
�@�Ƌ��̔@���A�{���͌����Đ��ł��邱�Ƃ�����܂���B���̂��݂���̔@���A�ȐS�Ɍ��������{���ł��邪�̂ł���܂��B���̌ȐS�̖{���E�{����Y��A�O����ӓ|�Ɏ����Ă���̂��R���L�u�̐��ł���A�܂��@���@��M���ɑn���w��̎���ł��B
�@�ł͏@�c���̌ȐS�̖{���E�{���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��]���̂ł��낤���B�O�ɖ@�̂̎��ɂ��āA���̍l�����y�ѐ��́A�����{�������́u���E�̒q�͋�E�����ƈׂ��A��E�̒q�͕��E�����ƈׂ��v�̕��̔@���A�݈唺���ċ��킽�t���ӂ̏���@�c�吹�l�Ɖ]���A�v�������̖��@�ł���Əq�ׂ��B
�@���Ă��̋v�������̖��@�Ƃ����@�̂��@���ɂ��ČȐS�̖{���E�{���Ƃ��ď����邩�Ɖ]���A
�{�������ɉ]���A
�@
�u���̒�Ƃ͋v�������̖��@��]�s�ɓn�������B���ς��鎖�s�̈�O�O��̓얳���@�@�،o����Ȃ�v
�@ �Ƃ���@���A�v�������̖��@�����ɍs���鎞�A�����Ɏ������ɍs�������s�̖��@�@�،o��������A���ꂪ�O�鑊���̈���@�ł���A���̈���@��l�ɖ�Γ��@�吹�l�A�v����������p��g�Ɖ]���A�@�ɖĉ��d�̖{���Ɖ]���̂ł���܂��B
�@�@�c�ϐS�{�����ɉ]���A
�@
�u���s�̓얳���@�@�،o�̌����тɖ{��̖{���A�����L��������s�����v
������l�d�~�L�ɉ]���A
�u�{��̌��ӂ̉~�Ƃ͎��s�̖��@�@�،o����Ȃ�v
�����n���@�؍u�O��Ԏ��ɉ]���A
�@
�u�Ȃ��Ȃ����̖@��͎t��q���������ĕ��ɂȂ�@��Ȃ�v
���L��l���V���ɉ]���A
�@
�u�t�푊�Ώ\�E��̎��̈�O�O��̎��s�̖��@�@�،o�Ȃ�̖�v
�u�t�푊�����������̖��@�Ȃ�̂ɁA�i����)�A���ꑥ�����s�̖��@�A���̑��g�������]�]�v
������l����钾���ɉ]���A
�@
�u�������ɍs����̂Ɏ��Ɖ]���v
�@ �ƁA�����ɗ������s�̖��@�����A�u�O���@�����̖{���v�ł���܂��B�������A�������ɍs�������s�̖��@�@�،o�Ƃ́A��̓I�ɂ͕��ɖ��炩�Ȕ@���A�t�ƒ�q�����������A���O���邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B�܂����s�̖��@���ɂ��āA
������l�͓��Ɍd�~�L�ɁA
�@
�u�����Ƃ̉~�@�͎��s�̖��@�@�،o�@��v
�@�ƁA���Ƃ��t���ӂ̎��s�̖��@�@�،o�@�Ƃ܂ŋ��ł���܂��B
�@���̎O�鑊���̎��s�̖��@���A���@���N�̎�{�Ƃ��āA��腕���ɑ��^���ꂽ�̂��O����N�̔{���ł����āA�{�����̂��̂͐��Z���̎l���̗��ɂ���Đ��ł��邱�Ƃ͂����Ă��A����ɂ���Ď����ꂽ���s�̖��@�͉i���ɐ��ł��邱�Ƃ�����܂���B��������O���~�Z�̖{���Ƃ����̂ł����āA���̖{���̓_�C�i�}�C�i���ȂĂ��Ă��A�����ȂĂ��Ă��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�u���Ă����Ɣ\�킸�A�����Y�킷���Ɣ\�킶�v�Ƃ͑S�����̈ӂł���܂��B
�@
�u���@�����ߞD��Ȃ�Γ얳���@�@�،o�͖��N�̊O�A�����܂ł�����ׂ��v
�@�ƕ��ɋ��ɂȂ����u���@�����߁v�Ƃ́A�B���ɑ����{���ł͂Ȃ��A�i���Ɍ����邱�Ƃ̂Ȃ��O�鑊���̖{�������āA��腕��^�̎��߂Ƃ����̂ł���܂��B
�@�Ƃ���ŎR���L�u�́u����M�S�̖��Ȃ�ΐ��������܂��v�Əq�ׁA�{���������͖ł��邱�Ƃ��ÂɔF�߂Ȃ���A����Ŕ{�������ĉi���s���̂��̂Ɓu�������ł��M�����Ă����v�Ƃ����p�����������Ă��܂��B���Ȗ����̋ɂ݂Ǝv���܂����A����ɂ��Ă����̂悤�ȐM�͑m���Ƃ��āA��͂��ł���Ƃ����]���悤������܂���B������l�͖��^���M�ɂ��āA
�@�ؑ�ڏ����i�ɍO���������ĉ]���A
�@
�u�]���A�^���ߗL���嫂��A�R�����ׂ��炭�v�����ׂ��A���g�ɉ����Č����ċ^�ӂׂ��炸�B�t�@�̓�͋^�Ă��ׂ��炭�ł�ނׂ��B�Ⴕ�^�͂���Έ��͓��ɕ����t�ז@���G��Ȃ�ׂ��B�̂ɉ��ɋ^���n���đP�v�V�����Ԃׂ��A�^�����̒Âƈׂ��Ƃ͍��̈���B�t�@�߂ɐ��Ȃ�Έ˖@�C�s����A�����O(�t�A�@�A���g)�^�i���{�����ׂ��v
�@�Ƌ��ł��B���e�́A�^���͕K�������ǂ����Ƃł͂Ȃ�����ǂ��A�������������g�Ɏ��Ȗ����������Ă͂悭�Ȃ�����A�悭�悭�v�҂��ׂ��ł���B�����Ďt�Ɩ@�̓�ɂ��Ă͓O��I�ɋ������āA�^����̓����ׂ��ł���B�^���͉�E�̓�����ł���A�^���ʂ��Č��Nj^�����s���A�S���^���̓���]�n���Ȃ��Ȃ��Ă��܂������A�����ɐM�����܂��B���̋^����������M�Ɖ]���̂ł���A�Ƃ̈Ӗ��ł���܂��B
�@������ɎR���L�u�́A
�@
�u�A���A������_�̋^�f�A�s�M�A�䖝�������̕��@�ɑ��đ�����Ȃ�A�����Ɍ䏑�A�Z�������n�ǂ��悤�Ƃ��A�V�n�^�|�̎��ɑ���]�]�v
�@�Ɖ]���Ă��܂��B������l�̋��Ɛ^���ł���Ɖ]��˂Ȃ�܂���B�R���L�u�̉]���M�S���m���Ƃ�������ɂ���Ȃ���A�@���ɐ�͂��ȐM�ł��邩�A�@�ؑ�ڏ����݂ɛ߂ɖ��炩�ł���܂��B
�@
�@
�@�R���L�u�]���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�u"���X�_"�Ƃ���������҂̏����ɂ���āA���^�U�s���̋L�^�ɂ���āA���̎���̔w�i�A��Ύ������܂����̏����������A����̎҂Ȃ炢���m�炸�A���̌����̗���̒��ɐ������X���킪�A�w������l��掖@�������x�ƁA�y�X�ɉ]�]���ׂ����Ă͂Ȃ��̂Ă���B������l�����̎��ɉ]���A�w���������̎��A�S�����Ƃɉ����Ēm�炴��@��Ȃ�A�吹�l��葊�`�̕��͓�����l�Ȃ�A�V�ɂ���č��ɂ����đ��`�₦���]�]�x�Ɓv
�@�R���L�u�́A�@�c�吹�l�A������l�ȗ��̌����͊ю��l����ю��l�����݂̂ɂ����`���Ȃ��Ƃ������ƂɌŎ����Ă���̂Ă���܂����A�@�����̌����ςƂ��ẮA����Ă��悢�Ă��傤�B����ǂ��@���ɉ����Đ^���@�|���̌����ς�_�`����Ƃ��Ă��鎞�ɁA�@�|���������،�����Y��A�@���������O���̌��������ɂƂ���ē��،������l���悤�Ƃ��Ȃ��R���L�u�̐��͔@���Ƃ������������̂Ɍ����܂��B
�@�R���L�u���ю��l����ю��l�ւ̊O�������������B���̌����Ă���ƌŎ����������A���j�I�����A�����͏@�`��E�̊ю�̎�舵���ɍ���A�������˂��Ȃ��A�\�ʂ����������낢�A�t�ɂ��̕��A�����̊ю��吹�l�̍Ēa�ȏ�ɏグ��悤�Ȍ��ʂɊׂ���̂Ă���܂��B�R���L�u���ׂ����Ă���ю喳�T�_���@���Ɏ��������Ă��邩�A���̋�̗��������ƁA������l���X�_�ɉ]���A
�@
�@�u���Ƃɉ����Č×���葢�����u�𐧎~���邱�ƔN�v���AূɐM�S�̒h�z�L��āA�����ċ��ɖ�ĉ]���A���̖�k�F���������ꕔ����u���B�x�R�̈�Ƃ͉��̈ӎ�L��Ă����̋`�����������A�肭�Α��̈ӂ������B��V�Ɍ��ē����A���l�o���̖{���͎O�ӂ̔�@���O�ʂ��ׂȂ�B�����͑�����ӂ̖{���Ȃ�B�N���V����炴��B�R��ɍ��Ɏ���܂đ��������邱�Ƃ͐��l�̍ݐ��ɕ��������u�����邩�̂Ȃ�B���u�͈�i�ې��ق�Ȃ�B���̌̂��u�o�L����Ȃ��嫂����ɈȂē��u���v
�@
�@�Ɖ]���āA�������u���吹�l�̏o���̖{���̈�Ă��鎖�������A�Ō�Ɏ��̂悤�Ɍ���Ă��܂��B�]���A
�@�u�E�̈ꊪ�͗\�@�َ������̗��N���������B䢂Ɉ����Ė�k�̐^���^���v���́A���Ζ����N���������ׁA�p�Y�������ׂɕM����ނ�҂Ȃ�B
�@�@�@ ���i�\���N�����g���@�����ԉ��v
�@�Ƃ���܂��B������l�������]���Ă��邩�A�����̕K�v�͂Ȃ������m��܂��A�����ē�����l�͖@�َ������̗��N�A�߉ޕ������Ĉ��u�������A�@���̑m������ᔻ���N�������A�����Ă��̋������J���ׂɂ��̈ꊪ���L�����Ɖ]���Ă���̂Ă���܂��B
�@�]���܂Ă��Ȃ��������u�_�͓��Ƃ̗��`�Ă͂���܂���B���̈ٗ��`�𐳓������悤�Ƃ��A���ۂɑ������s�Ȃ���������l�ɉʂ��Č�肪�Ȃ��Ƃ����邩�ǂ����R���L�u�ɂ͂悭�l���Ă��������������̂Ă���܂��B������l�́A
�u���t�䏊���͓��Ǝ��`�Ƒ告���v
�@ �Ɖ]���A��������l���A
�@�u�����Ɏ���Ă͍]�˂ɒn�Ղ����ւāA�����݂��A�������g������ɏ悵�Đ��ɑ������u���n�߁A�S�������̗v�R�����炵�߂���A�A���{�R�ɑ������y�ڂ����肵�͒��S�̐^����͂̐��ق��A������l�\�N�Ȃ炸���ē����o�g�̓��r���[�̍��ɂ͎���ɑ�����P�p���]�]�v
�Ɖ]���Ă��܂��B�R���L�u�͌����Ƃ������̂̊O�������ɂƂ���A�ю��ΐM�ɋ߂����̂�����悤�ł����A���̂悤�ȗB���I�����ς��@���ɐ���ڗđR�Ă���܂��B
�@������l������F�߂Ă�����@���A�䎩�g�����������ꂽ���A��O�ƐM�k�̒��ē�����l�̍s�����ɔᔻ���������l�X�������悤�ł���܂��B�����̐l�X�̑��݂��A��ɓ��r��l�A���[��l�̍��Ɏ����ĕ��������O���牺���錴���͂ɂȂ����̂ł���܂��B���̎��A�吹�l������l�ȗ��̓��،�����������l�ɑ��������A����Ƃ�������l��ᔻ������O�y�ѐM�k�̕��֗��ꂽ���́A���̌�̗��j���@���ɂ�����ؖ����Ă��܂��B������ɓ��i��l�A������l���ɂ���ĕx�m�{���̖@�傪��g����A�t�ɍL�����C�ȗ��A��Ύ����P���ɓ����Ƃ����v�@�����ɑ�Ύ��@�傪�N�����A�v�@���̖����̒��ő�Ύ��ɋA�����閖�������������A���̗v�@���O�\�O���������������u��j��m�͒Ǖ��ɏ����Ƃ����@�߂��ĎO�o�����ɂ�������炸�A���̗�����~�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����肩�A�p���ėv�@����O�̔������A�Ƃ��Ƃ��O�\�l�����S�̎��ɂ́A
�@�u��A���R�̉��V�͓V���@���ߗ��b�����R�ɏ����������ɍ��ߓ����p��v������p���Ė嗬�̖{�ӂ����ӂ̊ԁA���ʌ䓰�Č��̏��ɏO�]�����߁A���̂̒ʂ蕧�d�̑̂��炭�����ߌ�v
�Ɖ]�킵�߂�Ɏ������̂ł���܂��B�܂�v�@���͓V���@���Ȍ�A�������u���@���Ƃ��Ă������A�p���ē����嗬�̖{�ӂ����Ȃ����ׁA���̓x�䓰�Č��ɓ���A�̂̔@���A��{���ƌ�e�����u���A�������u�����߂�Ɖ]���Ă���A����͂܂��ɑ�Ύ��@��Ɋ҂邱�Ƃ�錾���Ă���̂ł���܂��B
�@���̂悤�ɗv�@���̖@�傻�̂��̂���ς����Ă��܂������ڂ̌����́A���i��l�A������l���̑�Ύ��{���̖@��̐�g�ɂ��邱�Ƃ͘_���܂��܂���B���������̌����́A�ނ̓�����l�̍��ɗv�@�����̑������u��ᔻ����Ύ��S�̂����u�̈����ɂ��炷���Ƃ������Ȃ�������Ύ���O�y�ѐM�k�̑��݂ɂ��Ɖ]���Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@������l�̖��@�������Ɍ����鑢�����u�ɑ���j�܂��A�P�ɍL�����C�ɑ���j�܂Ƃ������A�ނ��듖����Ύ��嗬�̒��ɖ������Ă���������l��M���Ƃ���v�@�����`�̔j�܂Ă���ƍl���Ȃ���Ȃ�܂���B���̂悤�ɍl����Ȃ�A������l�̖��@�������̈Ӗ������葖��ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�R���L�u�͂����ю�͐�ł���A�ю�̉]�����Ƃɂ͉������ł��M�����]���Ȃ�������Ȃ��Ƌ������Ă��܂��B�������n���w���掖@��掖@�ł͂Ȃ��Ɖ]���A�t�ɐ��M�o���^�������ю�̈ӂɏ]��Ȃ�����掖@�ł���ƌ��߂��A���܂������ԕ��@�̗��ʂ�������w�E�����Z�t�ɑ��A�\�͂��Ȃē������ю�̂Ƃ��ɐ��`������̂��r���^�킵���Ɖ]�킴��܂���B���͂�\�͂��ȂāA���@��}���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂́A�v�@�����������@�ɑ�Ύ��@�傪�t�A�l����A��Ύ��A���̖��������������A�@�߂��ȂĂ����}���悤�Ƃ��Ă��}���ꂸ�A���Ǘv�@�����̂��̂��������u���̂Ă邱�ƂɂȂ����ߋ��̗��j���@���ɂ������Ă���Ǝv���̂ł���܂��B
�@���݂̊ю�A�y�я@���@�A�������A�����Ă��̌��͂ɏ悶�Đ��M�o���^�����`�Ƃ��Đ������Ă���R���L�u�ɂ͂����̏���������x�n�����āA���Ɩ{���̖@����l���Ă������������Ǝv���̂ł���܂��B
�@
�@
�@
�R���L�u�]���A
�@�u�w�v�ې�_���ɉ]���A�����͌�����`����ׂ̊ǂ��{�݂��āA�펞�͖@��̊ǂɂ���ė���Ă��邪�A�Ⴕ�̏Ⴕ�l�����悤�Ȏ��́A�����I�ɑ�O�̊ǂ��g���ė����悤�ɖ��S�̍H�v������Ă���̂ł���܂��ĉ]�]�x�@�ƁA�v�ې�t��I������l�́A�ʂ����A���ǂȂ��̌�@��̐��@�ɁA���̗l�Ȍ�w�삪����̂��B���������V�����̂��Čȋ`�A�`�Ƃ����̂Ă���B�n�����x�x�݂ɂ��Ă��炢�����B�}�����@���@�Ɩ���邩��ɂ́A���̏@���ɏ]�����܂��v
�@�R���L�u�͖{���������ł��邯��ǂ��A�������܂��O���̌������������l�����Ȃ��悤�ł���܂��B��������A�B���I�v�l���@�����o���Ȃ��߂����K���̏��Y�ł��邪�A�{���Ɠ������A���������A�@�����A�@�|���A�����O���Ɠ��̗��ʂ����邱�Ƃ�m��K�v������悤�Ɏv���܂��B�v�ې�t�̉]���Ƃ���̂������̏��ł���A����������Ȃ�ю��l�����l�ւ̌����ے�Ǝ���������肪����Ɖ]��Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�O���ŏq�ׂ��@���A�ނ̏\����������l���������u�_�Ƃ����v�@�����`���@���ɒ蒅������Ƃ��Ė@�َ��y�ё��̐������ɑ��������s�������ɁA��Ύ��{���̕s���s�ǂ��������̂͑��Ȃ�ʓ�����l�䎩�g���ᔻ���ꂽ�u�^���v���^���v�ł���܂����B���̎��A�吹�l������l�ȗ��̐����@���������̂͊ю�ł��������A����Ƃ�����ɔ�������O�y�ѐM�k�ł��������͐\���܂ł��Ȃ����ƂĂ���܂��B���ꂪ�v�ې�t�̉]��ꂽ�ю�ȊO�̂�����{�̊ǂłȂ����ĉ��ł���܂��傤�B
�@�����R���L�u�̎咣���錌���Ƃ́A�ю�l�̏��L���łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����O����ӓ|�ɕ��������ςł͂ǂ��ɂ������̂��Ȃ����Ƃ��A���Ǝ��S�N�̗��j�̒��ɂ͓�����l�̖����܂߂Ċ������܂��B�����ł͂��̒��̈��Ƃ��āA�\������l�Ə\�O�����@��l�̑����Ɋւ��āA�����𖾂炩�ɂ��Ă݂����Ǝv���܂��B
�@������l�̎��Ղɂ��ł́A�O���ю�Ă��邱�ƁA�����Čo�ϓI��뗧�Ă̂��ƂƂɑ�Ύ�����������ꂽ���Ɠ��͂悭�m���Ă���ʂ�ł����A�S�̓I�ɂ͂킩��Ȃ����Ƃ̕��������Ɖ]���܂��B�킩���Ă��邱�Ƃ́A�����Q�N�i�P�S�W�W�N�j�̖{���ɂQ�O�Γ����Ƃ��邱�ƂƁA�ƒ����y�ё�ߋ������̋L�q��������i�V�N�i�P�T�Q�V�N�j��Ƃ������Ƃ����ł��B���̓�̎������琄����ƁA��N�̑�i�V�N�i�P�T�Q�V�N�j�͂T�X�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��ߋ����͂��̓_�T�X�Ύ�ł��邩��M�p�ł���Ƃ��āA�ƒ����͂V�P�Ύ�ƂȂ��Ă���̂ł���܂����A����͑O�̓�̎������琄���ĐM�p���������B���������ĕx�m�N�\�ɉ����Ă���i�V�N�T�X�Ύ�ƂȂ��Ă���̂ł���܂��B
�@���ē��@��l�͓V���P�V�N�i�P�T�W�X�N�j�V�Q�̎�ł��邩��A���܂ꂽ�͉̂i���P�T�N�i�P�T�P�W�N�j�ł���A������l���₹��ꂽ��i�V�N�i�P�T�Q�V�N�j�ɂ͂킸���P�O�Ă��B���@��l��������l�Ɠ������t���ю�ł���܂����A���̗��R�͑�Ύ��N���ɂ��o�ϓI���R�ɂ��̂ł���܂��傤�B�Ƃ��������@��l�͓�����l���班�Ȃ��Ƃ��P�O�ŕt���������ƂɂȂ�܂��B���݂̖��N�߂ł����X�ł��B
�@�Ƃ���ł��̑O�N�A�܂���@��l�W�̎��A������l�����Ύ��y�O�h�߂ւ̕t��������Ă���܂��B
����ɂ́A
�@�u�Ԉ�M���\��B���lj��a�V���c���V����Ɍ����B嫑R�M�S��u��āA���m�i���l�j��v��ҁA�����̐��ԕ��@����n�A�{���V�m������\��B������V�@���B
�@�@�@�@�@�@�@��i�U�N�X���T���@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ԉ�
�@�@�@�@�@�@�@��Ύ��y�O�h�ߌ䒆�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v
�@�Ǝ�����Ă��܂��B�킩��₷�������A���̗lj��a�i���@��l�j�͗c�Ȃ����ł��邯��Ƃ��A�M�S�̎u���������邩��A���l�������ɂ́A��Ύ��̍s���ʁA�M�ʋ��ɓ��@��l�ɓn����A�@���̑m����v���ē��@��l�𒆐S�ɑ�Ύ�������Ă����ĉ������A�Ɠ�����l�����ɂȂ��Ă�����̂ł���܂��B�܂�lj��a�i���@��l�j�����l����܂ł͑�Ύ��̍s���ʁA�M�ʋ��ɑ�Ύ��y�O�h�߂Ď��悤�ɂƂ������Ƃł���A�����ɏ�l�䎩�瑊�����ꎞ��O�y�ѐM�k�ɂ䂾�˂Ă��܂��B������l�̂��̂悤�ȍs�ׂ́A�R���L�u���]���悤�Ȃ��Ƃ��炷��ƁA�ȋ`�`�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂����A�ʂ��ł����Ă��傤���B�v�ې�t�̏����ƎR���L�u�̏������r����ƁA�ǂ��݂Ă��v�ې�t�̐��̕�����Ύ��{���̍l�����̂悤�Ɏv���Ďd������܂���B
�@�X�ɎR���L�u�́A
�@�u��@���l��l���킳�˂Γ��@���@�͖����v
�@�Ɖ]���Ă��܂����A����ɂ�����肷����Ɠ�����l���₹���A���@��l�����l������܂Ă͓��@���@�͖����������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B���A���ƒ����ɂ��A
�@�u���R���t�Ƒ�h�ߓ��ّ���ƌ����Đ��t�x�m��ދ����]�ˉ��J��ݎ��ɈڏZ���A�V��Ɉ˂��ē��R����@�Ȃ�B���ɏ��R���ւ�������ߗL��A���鏈���R���Z�ɏA���ď��ɔp���ɋy��Ƃ��A�O�h�V���Q����Z�̎�����ّ���i�h��@�j�ɐ����B���̊��I�т������B�@�َ����Z�����]�킭�A�w���ɔ@���҂Ȃ��]�X�B���đ���A�t�����ē��R�ɓ��@�����ߋ����Ȃ�v
�@�u�R�鏈�����{���ċ�����ē������i��E�@�فj���Z������A����h��@�l�̌�ӂɔw���ꗼ���V��ޏo���B��A���̐Ֆ@�َ��ɂ͓����Z������Ύ����Z�ɂĈꗼ�N�����߂���R�A������ߗL�薳�Z�̎�������ԕ~���̗R�ɕt���A��Ύ��O�h�h��@�l�֑��肢�A���w���w�}�Ɉ˂��ē����̐l��ɂē��R�l�@���A�]�˂։��萸�t�ɖʉy�����̌���Ղ��v
�@�ƁA����ɂ��Ɠ�����l�ƌh��@�Ƃ̊ԂɋT�����A������l���ю�E����~�낳���N�ɒU���đ�Ύ������Z�Ă��������Ƃ��L����Ă���B�R���L�u�y�я@���@�����A�ю��l����ю��l�ւ̌䑊�����������ƗB���̌����ł���ƌŎ����������A���j�͂��̖������悭�m���Ă��āA���B�ɂ��̐^������肩���Ă����̂ł���܂��B
�@�ł͓��Ƃɂ͏@�c�吹�l������l�ȗ��A������ƂƂ��Ă̌����͑��݂��Ȃ��̂ł���܂��傤���B�ہA���B�͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͌����ĂȂ��Ǝv���Ă���܂��B�������R���L�u�̔@���A������B�������ɂƂ炦�ĊO��������ǂ��A�f��Ă��Ȃ��e�@�f��Ă��Ȃ��ƐM����e�Ɖ����Ă݂Ă��A�v�ې�t�̎w�E����@���A���̂悤�Ȍ����͊��ɏq�ւė����悤�ɉߋ��ɂƂ��ɂ������̂��Ȃ����Ƃ��������A���̐��������������������A�����̗������Ɋׂ����Ă��܂��̂ł���܂��B
�@�{���̌����Ƃ́u���ؕ��@���������v�Ƃ����@���A���،ȐS�̐��E�̘b���ł����āA�B�������̘b���ł͂���܂���B�O������������Nj�����A�m���ɐ�Ă���Ƃ���Ă��Ȃ��Ƃ��̘_�c�ɂȂ�ł���܂��傤�B�v�ې�t�͊O�������̐_�鉻�ɑ��A���̖����𓊂������A�^�̓��،����Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩���]���Ƃ��Ă���̂ł����āA������ȋ`�A�`�ƌ��߂��A�͂����A���ˏ����ɂ��ď@�傩��Ǖ��������Ƃ́A���̘_�_�̎����̒Ⴓ�ɋ����A���̖\�̘͂_���ɂ͂�����������������ł��B
�@����ł͓��Ɩ{���̌����Ƃ͈�̂ǂ̂悤�ɔc�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A����ɂ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B�R���L�u�͌����Ɖ]���ƁA�����ю��l����ю��l�ւ̏����ޓ����]�����`���������l�����Ȃ��悤�ł����A���@��l���L�����C�ւ̌��ɉ]���A
�@�u�������{�ӂ̏C�s�@���𗐂����t�i���t�E�@�|�j���i�����E�@���j�̗������A�O�ӂ̔�@���ɓ��āA�l���O���̍��𑊑҂҂Ȃ�v
�ƁA�܂��S�Z�ӏ��ɂ��]���A
�@�u�i�@�|�j�m���i�@���j������j��ׂɉ]�]�v
�@�Ƌ��̔@���A�����ɂ��{���Ɠ������@�����A�@�|���̗��ĕ��������邱�Ƃ�m��Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�@�����̌����Ƃ́A�O���̌��������̂��Ƃł���A�ю��l����ю��l�ւ̑��`�̂��Ƃ��]���A�@�|���̌����Ƃ͓��̌����ł���A���L��l�̌䕶�ʼn]���A
�@�u�M�Ɖ]���A�����Ɖ]���A�@���Ɖ]�����͓������Ȃ�B�M����������Α��̋ؖڈႤ�ׂ��炴��Ȃ�A��킸��Ό����@���͈Ⴄ�ׂ��炸�v
�@�Ƃ��������Ă���܂��B�ܘ_�����ɉ]���M�Ƃ͋^��������M�Ƃ����A���^���M�̐M�̂��Ƃ��]���A���]�����̏@�����̌����A�@�|���̌����͂܂����ʂ̓�`�Ɠ����Ӗ��ł��B
�@��Ύ��ɗv�@���o�g�̊ю傪�a������O�́A�Ō�̊ю�Ă���\�l�������l�Ɏ��̂悤�Ȍ䕶������܂��B
�����Տ��X�������ɉ]���A
�@�u�x�\�l�����̒��ɎO�P���͈����Ȃđ����퐬��B���͑y�t�����Ȃ�B��Ύ��͌�{�����ȂĈ��퐬��B�����ʕt���B����l�̈ӂȂ�B�吹���{����d��{���A�]���t�����V��{���@�̌�t���A��ҏ�s�F埵�茋�v�t���哱�t�A�ȓ��Ӕ@���{���̗v�Ȃ�B�]�v��������R�_�͌��v��s���`�V��t���A���@���@�E�����E���ڌ����t���S�̕s�F�֑��͂Ȃ�B���ʎl�ʎґ��t���ğb�B�����ꎆ�O�P��V�t����؎��ʕi�V�Ȃ�A��{���ҋv���ȗ����茜�t����v
�@�ƁA������킩��₷���v��ƁA�x�\�l�ӎ��̒��ő�Ύ��������O�ӎ��͕t����A�莆���`���̈����Ȃđ����Ƃ��Ă���B����͑��t�����i�@�����̌����j�ł���B��Ύ��͌�{�����Ȃđ����Ƃ��A����͕ʕt���i�@�|���̌����j�ł���A�����吹�l���̖{����d�̌�{���A������l���̐����O�N�̏����{���i���֖{���j�A���̎t���ӂ̖{���̖@�̂��ȂČ����Ƃ��A�����B����l�Ɖ]���B���ʁA�����͎l�ʂƂ����t����A�莆���̑��`���͂���Α��t���ɓ���A���Ƃɉ�����ꎆ�O��������Տ��X���Ƃ����t�����͎t���ӂ̖{���̕��āA�@�،o�Ă����Ύ��ʕi�ɑ���������̂ł���A��{���̖@�̕t���������A���ؐ^���̕t���ł���A�Ƃ����Ӗ��ł��B�R���L�u�́u���@�͑��`�̏@�|�v�Ƌ������Ă��邯��ǂ��A�����l�̎����Ɣ�r����ƁA�@�����̔��S�̌����Ɖ]������̂ł���܂��B
�@�R��Γ�������̓�����l���̐����O�N�����{���@�̕t���������@�|���̌����ł���Ƃ����A���̏����{���@�̂Ƃ͉����]���̂ł��낤���B
�@�O�ɖ@�̂̎���_�������ŁA�@�̂̎��Ƃ͓�����l�����s�����ɉ]���A
�@�u������ꋋ�����̎����͕��E�Ȃ�A�������䓙�O���͋�E�Ȃ�R����^���̏\�E��v
�@�u���E�̒q�͋�E�����ƈׂ��A��E�̒q�͕��E�����ƈׂ��A���q�݂��ɖ��O���}����P��v
���Ƌ��̔@���A�t�푊���A��ӂ��Đ����鏈�̋v�������̖��@�Ă���A���̋v�������̖��@�����ɍs�������s�̖��@�@�،o����{���̐��̂ł���Ɛ�����������ǂ��A�����l���̏����{���@�̕t���̈ӂ��A���̎t���ӂ̋v�������̖��@�̖@�̕t�����Ȃď@�|���̌����Ƃ��Ă���̂Ă���܂��B�@�c�吹�l�����ɁA
�u���@���������Ȃ�A�얳���@�@�،o�͖��N�̊O�A�����܂ł��Ȃ���ׂ��v
�@�Ƌ��́u���@���������v�Ƃ́A��腕��^�A������؏O���ɕ����ɗ���Ă���v�������̖��@�A�@�̕t�����w���̂ł���A���̑吹�l�̎��߂����B���o�m���鎞�A�����v�������̖��@�����ɍs���鎞�A�����Ɍ���������A�������،����Ɖ]���A�@�|���̌����Ɖ]���̂ł��B�v�ې�t���]����O�̊ǂƂ́A���̎t���ӂ̓��،����̂��Ƃ��w���Ă���̂ł���A�ܘ_�ю�����̎��͒�q�̈ꕪ�ł����āA���L��l���̔@���A���̑��ӔC�ҁA������p���̎t���ł���܂��B���̓��،����́A�O�������ɋ������낤�ƂȂ��낤�ƊW�Ȃ��A�����Ēf�₷�邱�Ƃ�����܂���B
�@�ߗ��A�������ю��l�����̏��L���̂悤�ɉ��߂���R�ю呦�����@�̂悤�ɋ�������Ă��܂����A����͖��炩�Ɍ��ł���Ɖ]�킴��܂���B�ю�Ƃ́u�l�̎u���l�֎�莟���\����S����Ȃ�v�Ƌ��̔@���A�吹�l�䋋�d�\���グ�A�����]�̑�O�Ƃ̎�莟�����ł��B������l�͈�u���ɁA
�u���̊ю傽���嫂��ȋ`���\���ΔV��p���ׂ��炴�鎖�v
�@�ƈ����Ă��܂��B����͌ȋ`���\���āA��p���̎t���S���ł��Ȃ��ю�Ȃ�A���̊ю���O�͗p���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����J�R��l�̌�w��ł����āA���̏ꍇ�A�ю傪�ȋ`���\���Ă��邩�A���Ȃ����́A���������t���]���悤�Ɋю厩�g�����߂�̂ł͂Ȃ��i�����t�������Ȋю�ł��邩�ۂ��͕ʖ��Ƃ��āj�A��@�呦���吹�l�̌䏑�A������l�̌��A���L��l�A������l�̌�w��ɏƂ炷���Ƃ͉]���܂ł�����܂���B
�@���āA�b�����ɂ��ǂ��āA���̓��،����A�܂�v�������̖��@�����ɍs����Ƃ́A��̓I�ɂ͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ������̂��Ɖ]���A
�u���̖@��͎t��q���������ĕ��ɂȂ�@��Ȃ�v
�@�ƊJ�R������l�����̔@���A�t��q���������Đ����邱�Ƃ��Ă���̂Ă���܂��B�A���A���̎t��q���������Ƃ́A���w�����呺�����t���́u�t�E��q���������v�Ƃ����悤�ȋM�������I���z�̎t��q���������ł͂���܂���B��\�Z�ӏ��́A
�@�@�u���̊ю傽���嫂��ȋ`���\���ΔV��p���ׂ��炴�鎖�v
�@�@�u�O�c�����嫂����@�ɑ���L��Ίю�V��F���ׂ����v
�@���ɑ�\�����A�t�����Β�q�������A��q�����Ύt�������A�݈唺���Č݂��̐S�����O���A�t��̍��ʂ��Ȃ��Ȃ�A��ӂ��Ă����ɐ��܂ꂽ���^���M�̐M�̈ꎚ�̒��ɁA���̓��،���������Ă����̂Ă���܂��B���L��l���V���ɉ]���A
�u�䂪��q�������̔@����ɐM�����ׂ��v
�@���A
�u�M�Ɖ]���A�����Ɖ]���A�@���Ɖ]�����͓������Ȃ�A�M����������Α��̋ؖڈႤ�ׂ��炸�A��킸��Ό����@���͈Ⴄ�ׂ��炸�v
�@���Ƌ��ɂȂ�ꂽ���̐^�ӂ��A�����ɑ�����Ɖ]����̂ł���܂��B
�@������l�������ꂽ�u�t��q���������v�Ƃ́A�v����ɎO�ŋ����̎t�킪�A�݈唺�A�{�����킵�Ė��^���M�̐M�̈ꎚ�����߂�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@
�@
�@�R���L�u�]���A
�@�u�^�Ԏ߉ޕ����{���ɉ]���A
�w�߉ތ䑢���̌䎖�A���n�D����薤���A���������L����ȐS�̈�O�O��̕��茰�킵�݂����A�y���Q��Ĕq�ݐi�点���]�]�x
�@�l������߉ޕ����{���ɉ]���A
�w�O�E�̎�A����ߑ���̎O���̖{���A�V�������A�h�ߓ��Ꮧ�A���݂͓��X���X�召�̓���A�㐶�ɂ͕K�����ƂȂ�ׂ��]�]�x��
�@���M��t��I
�@�w���邵����A�J�j�̑���{�x�Ă���A���Ƃ����ꂪ��@�O�ʂ̏��߂ł���A���{�ꓯ����ɕ���{���Ƃ��钆�Ă���A�����@�Ȃ��掖@�ɈႢ�Ȃ��낤�B����������e�F���^�V���ꂽ�吹�l���^���߁A掖@�Ƃ����̂Ă��낤���v
�@�R���L�u�ɂ́A���Ƃ����Ɏ����đO��s�o�Ɋׂ����Ă��܂����炵���B�R���L�u�̐��́A�吹�l�̐^�Ԏ߉ޕ����{���A�l������߉ޕ����{���ɂ�����߉ޕ������̍ۂ̏̒V�����グ�A���M�o���^���̑m���̎咣����掖@�����ɑ��āA�Ȃ�Α吹�l���������̒V���Ă���̂ł��邩��A掖@�Ă͂Ȃ����Ƃ������Ƃł����A����͂ǂ��݂Ă��J������Ƃ������܂���B�����B��掖@�^����I�グ����ׂɁA�吹�l�̑����̒V�̌䏑�����p���Ă���Ƃ����v���Ȃ��̂ł���܂��B
�@�R���L�u�̈��p���������䏑��p���āA��O�A�l�S�N�̐́A�������Ƃ��咣�����l�X������܂��B���A��l�قǖ���������A��l�͗v�@���L�����C�B�]���A
�@�u�₤�A�i���C�j�]���A�^�ԋ��{����\���ɉ]���A�߉ތ䑢���̌䎖���n�捅���ߗ����������L����ȐS�̈�O�O��̕��茰�킵�݂����A�y���Q��Ĕq�ݐi�点����A�~�ߏO���J���m���T����������ߗ��͐���Ȃ�]�]�A���l������߉ޕ����{����\���ɉ]�킭�A����L�̒��Ɏ߉ޕ��̖{����̂Ɖ]�]�A�T�����̕��͐��g�̕��ɂČ����։]�]�A�����Ꮧ�߉ޕ����{���ɉ]�킭�A�O�E�̎�A����ߑ���̎O���̖{���V��������A�h�ߓ������A���݂ɂ͓��X���X�召�̓���A�㐶�ɂ͕K�����ƂȂ�ւ��]�]�A�����̕��@���v�ƁB
�@���C�̉]�����́A�@�c�̐^�ԋ��{���A�l������߉ޕ����{���̕��������āA�����瑢���͏@�c�̖{�ӂɊ����A�Ⴕ�������{�ӂĂȂ��Ƃ���A�@�c�͎��ꑊ����������Ă���A�Ⴕ������掖@�Ɖ]���̂Ȃ�A�@�c���g掖@�ł͂Ȃ��̂��A�Ɖ]���̂Ă���܂��B������l�́A�\����������l�B���X�_�ɉ]���A
�@
�u���A�吹�l��ݐ����Ă���Ɂi�߉ޕ��́j��J��x�X�Ȃ�B�����^�Ԏ߉ޕ����{���A�l������߉ޕ����{���A���Ꮧ�߉ޕ����{���A�{�G�J�ᓙ�Ȃ�B�i�����j��ĉ]���A�x�R��Ƒ����������ƂȂ���ۂ�A�Ⴕ�V�������Ή����ӂ�������������A�ᖒ��������Ώ�̏����@����p�����v
�@�ƁB������l���L�����C�ƑS���������Ƃ�_�����Ă���܂����A�R���L�u�̐��́A�����̎t�ƁA���̂����������̂��Ƃɏ@�c��`?���Ă��܂��B
�@�R���L�u�́A�O�Ɏw�E�����@���A�v���̂Ƃ炦���A�@�̂̎����̂Ƃ炦���A�����Č�{����B���I�ɍl����������q�A�X�ɂ��̎߉ޕ������̒V�̖��A���ւĂ����̂��v�@�����w�Ɠ��������������Ă��܂��B�v���ɎR���L�u�́A�L�����C�������l�Ɠ��l�ɖ@����O���̖ʂ����ɂ����Ƃ炦�邱�Ƃ��o�����A�ȐS�̐��E�𗝉��o���Ȃ����ɂ��̍��{����������悤�ł��B�R���L�u�̏@�c�^���߂̋^��ɑ��āA���B�̍l���͂����Ђ����A�������̖��@�������̕��œ��������Ǝv���܂��B�]���A
�@
�@�u�����A�×���ĉ]�킭�A����͐��ꊎ����@�ꉏ�ׂ̈Ȃ�A�P���p�q��U�̒����̔@���A�i�����j�A���ނ�ňĂ��ē��킭�A�i�߉ޕ��́j�{���ɔ�嫂������V���̒V���������ɗ����ĎO�ӗL��A��ɂ͗P�������@�O�ʂ̏��߂Ȃ�A���̌̂ɗp�̎��X�ɐ������B��ɂ͓��{�����ꓯ�Ɉ���ɕ����ȂĖ{���ƂȂ��A�R��ɔނ̐l�X�K�ߑ������A毚�V��������B�O�ɂ͌Ⴊ�c�̊ό��̑O�ɂ͈�̕��̓��̑S�������O�O�瑦����p�̖{���̌̂Ȃ�B�w�ҋX�����P���V����v���ׂ��v
�I����
�@�ȏ�A�v�ې�t�̘_���ɑ���R���L�u�̋^��ɑ��āA���̌��ƁA�v�z�I��Ղ��v�@�����̊O�������߂鋳�w�ƍ������Ă��邱�Ƃ��q�ׁA�ȂČ����w�E�������A�S�Ă͓�����l���́u���߂̍����v�ɋA����Ɖ]���܂��B�R���L�u�ɂ́A�u�𑁂��M�̐��S�����߂đ����Ɏ���̈�P�ɋA����A�R��Α����O�E�͊F�����Ȃ�v�̌������q���A�@�c�吹�l�A�J�R������l���̎t��q�̓����������āA�{���̑�Ύ��@��ɋA��A�{���C�s���s���Ă������������ƔO�肷����̂ł���܂��B
�@���A�R���L�u�_���̌�ɁA�@���@���w���̏��F�̂��Ƃɐ����A���ї��t���ɂ��v�ې�t�ɑ��銴��ނ������̘_�����o����Ă���܂����A�����Â��Ă����̘_���ɂ��Ă����̌����w�E���čs�������Ǝv���Ă���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȁ@��
�@
![]()
�@
�@
�@
�@
�͂��߂�
�@���M���U�����тɘ@�؎�����u�����v�P�W���ɁA�v�ې�@�͎t���u���E�@���ւ̒E��v�Ɓu���ɂ̖{���v�Ƃ̘_���\���ꂽ�B�Ƃ��낪�����̏��_�ɑ��āA�@���̐��������t���u�w���E�@���ւ̒E��x�̖ό���j���v���эL���t���u�w�����x�ɂ�����{���ς�j���v�킵�A�@���@���w�����������܂Ƃ߂āu�v�ې�_���̖ϐ���j���v�Ƃ������̂��̂����_���t���ď����q�����s�����B�呺�������w�����́A���̔����ɂ������āA�v�ې�t�̘_���u�t��̓��݂͂����햝�s�����`�v�Ƃ��߂��A�u�ٗ��א��ɘf�킳��Đ����ւ̓���r�����邱�Ƃ̂����悤�v�Ƒi���A�@���m���ɍL�����q��z�z�����B
�@����A�v�ې�t�͏@���@�ɂ����q���s�ȑO�ɂ��łɝ��˂ɏ������A���@���@�̑m�Ђ������Ă���i�n�ʕۑS��i���j�@���ɂƂǂ܂��Ă̔��_�͋�����Ă��Ȃ��B���̊ԁA�v�ې�t�֏@���@���u�P���v�Ȃ镶�����������炵�����A���̓��e���A�u�t�̘_���͉��d�̖{���A�����ے肾����ِ������߁A��������v�Ƃ̈���I���ƑP�I�����̂炵���B�t�͂��̉Ɂu���d�̖{���ƌ�����ے肵�Ă�����̂ł͂Ȃ��B�ǂ��Ĉς����_�������܂��傣�v�Əq�ׁA���̋@���҂��������ɔ����̂͝��˂̒ʍ��ł����B
�@�v���ɁA�t�̎咣�͍r���Ƃ͂����A���ƂƂ��Ă̖{���E�����ς̖{������ׂ��p��_����ꂽ���̂ł���B����͌����s�����Ă���B���I���v�l�@�E�X������ᔻ���Ă���̂ł���A���Ƃ̖{���E������ے肵���Ƃ͑S�������Ȃ��B�ނ���A�_�q�ɑ���Ȃ��������������邮�炢�ł���B
�@�@���@���t�̓���������ꂽ�{���E�����_�̍��{�ۑ��^�ʖڂɍl�����A�_�����邱�ƂȂ����Ղɏ����ɑ��������Ƃ͑傢�Ɉ⊶�ł���B�@���@���s�́@�u�v�ې�_���̖ϐ���j���v�����̓����ł���Ȃ�A�����̑O�ɒ�o���A�t�l��Ȃ�A�j�܂Ȃ肷��̂������ł��낤���A�����ɋv�ې�t�ٖ̕����\�ɂȂ�A�^�ӂ����炩�ɂ����Ǝv���̂ł���B�����Ɠƒf�ň���I�����߂������A�݂����߂̂悤�Ɏt��l���������Ă��A�@����O�͎ߑR�Ƃ��������肩�A�X�ɋ^�f�ƍ����������̂ł͂������Ɗ�䂷����̂ł���B�ʖڂ������y�����ǂ̈�Č��\���ꂽ�����E���ї��t�̘_�����S�̓I�ɐr���ᒲ�ŁA�v�ې�t�̘_���̓ǂݑ������F����ƂȂ��č앶����Ă���悤���B
�@�Ƃɂ����A���ݏ@��̍����́A�@�|�̍������錌���E�{���_�����h���Ă��鎖�ɋN������ƍl���A����x�A���t�̘_�������܂߂āA�����ȍ~�̌����E�{���ɂ��Ă̍��{�ۑ��_���Ă݂����B
�@
�@�����t�͋v�ې�t���w�E���ꂽ���j��̑����̒f���ɂ��ā@�u�슱�̖i���邲�Ƃ��A���ׂ�@�w�f�₵���A�f�₵���x�Ƃ���Ԃ��Ă݂Ă��A�₦�Ă��Ȃ����̂͐₦�Ă������v�Ƌ��ق���A�l�X�������������ꉝ�̏C�������݂Ă���B�������A�v�ې�t�̘_�̎��͗��j��̑����𐡒f���邱�ƂɖړI������킯�ł͂Ȃ��A���Ƒ����̖{������ׂ��p�E�@�傩��݂������ς�_����ɖړI������A�����t�̔��_�̑唼���f��̏C���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��ւ����I���͂����c�O�Ȋ�������B�����̏@��ł́A���j��̑����̒f��߂邱�Ƃ��B��̓��ł���A����������d�������̂ł��낤�������_���ɂ͐����Ɩ����Ȉ��p��A���낪�������ł���B�����ɂ�����_���̎����@��I�����������ς����ɂ���A���ۂ̏�Œf�s�f�̘_��W�J����͈̂Ӑ}����Ƃ���ł͂Ȃ����A�����t�̘_���������ɂ߂Ă���̂ŁA�܂��Q�A�R��c���ė��j�I�l�@�����킦�邱�Ƃɂ���B
�@���t����@�t��
�@�����t�͒��t�̍s�ւƔN����m�Ȃ̂́A��{���̘e���ɂ���u�����Q�N�A�Q�O�Γ����v�����ł���Ƃ��Ă��邪�A������̎j���Ƃ��đ�ߋ����L�ڂ́u��i�V�N�U���Q�S����A�T�X�v����������B���̖T�Ƃ��ĉƒ����Ɂu��i������Z����\�l���v�̎��ꂪ�݂���B�������A�����͍s�N���V�P�Ƃ��Ă���A��ߋ����̂T�X�ƈق���݂��Ă���B��N�͋��ʂ��Ă��邪�N��Ⴄ�̂ł���B�ǂ���̔N��������Ƃ����A�����t���������m���j���A�{���e���́u�����Q�N�Q�O�Γ����v���t�Z����A��i�V�N�T�X�Ɣ�������B�܂��i�V�N�V�P�͎j���Ɣ����Ă���̂ł���B���j�I����������Ă���Ήƒ����̂V�P�͉����̌�L�Ɣ��f���A��ߋ����̋L�ڕ��тɉƒ����̎�N�������Ƃ�A�u��i�V�N�U���Q�S����A�T�X�v���j���Ƃ��ׂ��ł���A���R������x�m�N�\���@��S������ߋ����̋L�ڂɂ��������Ă���B
�@��������l�����t�́A�����ȂV�P�Ύ�����Ƃ肠���A�u������l�̓��Ŏ�����i���N�Ƃ������Ƃ����S�ł͂Ȃ��v�Ƃ����u�ƒ����̍s�N�V�P�ΐ���p����Ύ�Ŏ��͓V�����N�ƂȂ�v�Ƒ����A���ɂ́u���@��l�͂Q�Q�ɂ��đ����������l����ꂽ�Ɣq���y���v�Əq�ׂ�Ɏ����Ă���B�������A���m���Ȃ��̂��������āA�����Ƃ��j���ɉ����v�Z�̍���Ȃ��V�P�������̈ӂɎ��グ�āA���j��z���Ă��A����͂����̍��b�̈���łȂ����̂ł���B
�@���̌�������_����X�ɁA���̎��������߂��ĉv�X�[�݂ɂ͂܂����悤�ł���B�����t�́u��������i�U�N�ɓ�����l����Ύ��̑y�O�y�ђh�ߌ䒆���Ă̕t��������Ă���B����ɂ��Ɓw���lj��a�V���c���V����Ɍ����B嫑R�M�S��u��āA���m�i���l�j��v��ҁA�����V���ԕ��@����n�A�{���V�m������\��x�Ƃ���A�lj��a�i��̓��@��l�j�͗c���ł��邪���l���ꂽ���ɂ͓����̐��ԕ��@�̑S�Ă�n���䂦�ɖ{�������̑m���͂�������ׂ����Ƃ��L����Ă���B�������̏���ǂ�����@��l�͂Q�Q�ɂ��đ����������l����ꂽ�v�Ƃ����A�t������̌��ߎ�Ƃ��Ă���B�������A�j���ɂ��ׂ��͐�̘_�q�̒ʂ�ł���A���t�͕t���̗���i�V�N�ɂ͎��₳��Ă���A���̎��@�t�͂P�O�ɂ��āA�͂邩���l�ɂ͋y�Ȃ��B
�@�����t�̕t�����߂ɂ��A���t�͉@�t�����l�����玩��A������n���Ƃ����B�����������ɂ́A�@�t�P�O�̎��ɒ��t�͎��₳��Ă��܂����B���̕t���͉��̈Ӗ����Ȃ����̂ɂȂ����̂��낤���B�����t�̓ǂ݂͐������̂��낤���B���t���@�t�̐��l���܂��đ���������Ȃ�A�@�t�X�̎��ɁA�{���̑m���ɂ킴�킴�����������K�v���Ȃ��l�ȋC������B�Ȃ�A���̕t���͂ǂ��ǂނׂ��Ȃ̂ł��낤���B�q�ׂɂ݂�B
�@�w�����V���ԕ��@����n�A�{���V�m�����x�̈ꕶ�͕s���R�ł͂Ȃ��낤���B����͒��t���M�̏���ł���A���t���@�t�ɑ�������n������Ǝ���h����g���邱�ƂȂǂ���܂��B���̈ꕶ�͒��t����i�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ł���B����ł͒N���@�t�Ɍ�n������̂��Ƃ����A���_���̕t����Ղ������O�A�܂��Ύ��y�O�y�ђh�ߕ��ł���B��i����Ύ��y�O�y�ђh�ߕ��Ȃ�A��n���̌�������ł��邵�A���t���킴�킴�t����F�߂����R���킩��B�@�t�̂��̓����̔N�����t�̎�N���̗��j�I�������t���ɏƂ��ĉ����ّ��͂Ȃ��B���̏㑊���̂�����܂œ��@�ł��悤�Ƃ������̂ł���B
�@�v�ې�_���̎j���̔c�����͑�ؐ������A�u�N�\�Ɉ˂�A�P�R�����@��l�͉i���P�T�N�i�P�T�P�W�j�y���ɐ����Ƃ���A�P�Q��������l�͑�i�V�N�i�P�T�Q�V�j��ƂȂ��Ă��邩��A���̎��ɉ@�t�͐����P�O�ł���B�ƒ����Ɉ˂�Ɠ��@��l�́w�P�R�ɂ��ĕx�m�ɓo�蓖�Ƃ��K�w���x�]�]�Ƃ��邩��A������l�͋͂��P�O�́A�������݉Ƃ̎q���ɑ����������ƂɂȂ�A�ƂĂ��l�����Ȃ��v���ɂ��̒ʂ�ŁA�ƂĂ��l�����Ȃ����Ƃ͍s��ꂸ�A���t���̑����͈ꎞ��Ύ��y�O���a�����̂ł���B
�@���Ȃ킿�t���́A�lj��a���i��̓��@��l�j�c���ł���A���������ɑ�������킯�ɂ͂����Ȃ��́A��Ύ��y�O�ɗ��ߒu���A�lj��a�����l�����Ȃ�A���o���̑�����y�O�����n���A�Ȍ�͑S���{���̑m���Ƃ��ɏ]���Ă����Ȃ����B����ׂ̈ɋL�������܂��B�ƌ���Ă���B���t�͑�i�U�N�ɂ��̕t��������킵�A���V�N�Ɏ��₳���̂ł���A����Ȍ�P�O���N�߂��y�O������������肵�A���������ĉ@�t�Ɍ�n�������B�����ɂ������̒f���͂Ȃ��A���̕s�s�����Ȃ��B�����̑����̍l�������@���ɋ����ł��邩�����̕t���͎������Ă���B
�@�A�P�V��������l�ɂ���
�@�v�ې�_���́u������l�͎��瑢�����s���ꕔ���u�����������łȂ��A���X�_���Ă��̐��������咣�����v�Ƃ̎w�E�ɂ͉����٘_���͂��ޗ]�n�͂Ȃ��B�����Ă���͂R�P�����t��������悤�Ɂu���t�䏊���͓��Ǝ��`�Ƒ告��v�ł��邱�Ƃ͘_���܂��Ȃ��B���ꂪ���Ƃ���@������ю�̌����ł����Ă�掖@��掖@�ł���Ƃ��킴��Ȃ��B
�@������𐅓��t�́u������l�͐����ɓo������ꂽ���i�P�S�N�Ȍ�A���w��l�ɖ@��������܂ł̂X�N�Ԃ͂ނ��̂��ƁA���ł܂ł̂S�V�N�Ԃɑ�����ϋɓI�ɐ������ꂽ�Ƃ��������͑S���Ȃ��v�Ƃ����A���u�o���ȑO�̖����Z�E�Ƃ��Ă̍����w�������̂ł��낤�v�u��o���ȑO�̎��������Ȃ��v�Ɛ���ɓo���ȑO����������A�o���Ȍ��掖@�͂Ȃ������Ƙ_��W�J���Ă���B���ɂ͉����Ȃ��������̂悤�Ɂu�����Ȃ��l�i�掂ł����Ȃ��v�Ƃ����Ɏ���B�����t�̘_�̓W�J�́A�����߂�ꂽ���_�ɓǎ҂�U�����ׁA����������p���邱�ƂɏI�n���Ă���A�ƂĂ����j�I�����̔F�ɂ͒������B
�@�����t�̐��ɂ��A���t�͊��i�X�N�P���ɏA�t��葊����t�����ꂽ�ƈꉝ�L���Ă�����̂́A�����ɂ͊��i�P�S�N�̓o���ł���Ƃ��Ă���B�������A���̊��i�P�S�N�́A��ɖ@��t�����P�W���m�t����Â̎������֕a�ׁ̈A�މB�����ɋy��ŁA���t���Ăѕ��A������R���ꂽ�N�ł���B�ʒi�u�������Ă���T�N��Ɍ�o������Ă���v�킯�Ă��Ȃ���u�����ɓo������ꂽ�v���̂ł��Ȃ��B�����Đ����̌���g���̂Ȃ�A���i�X�N�@�َ��ɂ�����P�U�����A��l���̑����ɕt���ׂ��ł��낤�B
�@���́A�����Ƃ������p���Ď����̋ȉ����s�Ȃ���̂��낤���B����́A�����t���F�߂��鑢�����u�̏��@�u���X�_�v�����i�P�O�N�ɒ��킳��Ă��邱�Ƃ���A�ǂ����Ă������ɓo�����ꂽ�N�����i�X�N�ł͂Ȃ��A���P�S�N�ɂƂ肽���Ƃ����t�̊�]�̂�����Ȃ̂ł���B�u������ϋɓI�ɐ������ꂽ�Ƃ��������͑S���Ȃ��v�Ƃ����邪�A���t�͐����ɑ��������̂��u���X�_�v�킵�A�x��l�̂����悤�Ɂu�����̔@���͎����𗘗p��������薖���ɕ��������]�]�v�ƁA�ю�̎����������āA�͂̋y�Ԍ���@���ɑ����𐄏����ꂽ�̂ł���B�����������t�́u����疖�������̌�S�O�N�����炸���đ�Q�Q�����r��l�̍��ɂ͑����͑S�ēP�p���ꂽ�̂ł���B�܂��ɑ�Ύ��̐���������Ȃ��������Ƃ����ӂ��ׂ��ł���v�̌��͐��ɂ��̒ʂ�ŁA������l��掖@�����̂܂܋����Ȃ������S���{���̑m���ɑ傢�Ɋ��ӂ���Ƃ���ł���A���̎��_�����ې�_����ǂ߂A�t����m�ł��邱�Ƒ�ł���ƍl����B
�@�܂��u�ނ����e���ɂ͉��d�̌�{�������u�����v�Ƃ����Đ��t��������_����ł͂Ȃ����̂悤�ɏq�x�Ă��邪�A��e���ɉ��d�{�������u����Ȃǂ͓��Ƃ̖@��Ɋ���Ȃ��ً`�Ȃ̂ł���B�{���A�ɔ鑠�����x�����d�{�����A�h��@���ق̌�e��������i�ɂ���Č�e�����u��]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ݂�x���ŁA�h��@�̌��͂̋�������������ł͂Ȃ����B������l�̑������́A����̗v�@�����w�ɂ��ɈႢ�Ȃ����A���̍�������������𖾂���ɂ́A�h��@���ق̐��Ȃ錠�͂̔w�i�̂��Ƃɐ��t���������Ƃ�m��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����͌Í��Ɍ��炸�A�o�ϓI�x�T�Ƃ��������I�Ȕ��W�̑㏞�ɁA����ɑ�Ύ��@��̉e���������Ȃ����Ƃ������j�̏ؖ��ł�����B
�@�����t�͗ʎt�̑��ƒ����́u�������C�����c���A�₦������p���A�p�ꂽ��������M������Ȃ�A���钆���̑c�Ƃ����x�����̂��v���Ђ���A���t���Ύ��̋����Ə@��̐U���ɑ���̌��т��c���ꂽ���ƕ]���Ă���B�������A����͂��̂܂܌h��@���ق̌��͂̑傫�������̂ɉ߂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�����ē������݂�A�u���̏�@�َ��̌䌚����@�����x��p���ށA�R�鏊���������Z������A���̌�h��@�l�̌�ӂɔw���ꗼ���V���ޏo���v�Ƃ���B�@�َ����������A��Ύ��̊ю���߂��Ă������t���A��h�߂̌h��@���ق̌�ӂɔw�����ׁA������ޏo��������j�ڂɂȂ�B��Ύ��̊ю���h��@�̑O�ɂ͕��̑O�̐o�������̂�������Ȃ��B�X�ɑ��ƒ����́u���̐Ֆ@�َ��ɂ͓����Z������Ύ����Z�ɂĈꗼ�N�����߂���R������ߗL��A���Z�̎��w������ԕ~�̗R�ɕt���A��Ύ��O�h�h��@�l�w���Г��w���w�}�Ɉ˂��ē����̐l�ɂē��R�w���@���]�˂։��萸�t�ɖʉy�����̌���Ղ��v�Ɠ����̏�`���Ă���B���t���h��@�ɑދ��������Ă���A��Ύ��͖��Z�ɂȂ��Ă��܂��A���ɏ��R�̌�����߂��L��A�܂��ɔp�n�ɂ����Ƃ��鎞�A��Ύ��̏O�h�͌h��@���قɌ�Z�̎�����肢�����B�h��@�́A���t�̂��Ƃɖ@�َ��̏Z���ɂ����������Ƒ��k���w�t��I�т����u�t�����ē��R�ɓ��@�����߁v���Ƃ����B
�@��Ύ��̊ю���ӂɔw�����Ƃ����Ă͑ދ������A�X�ɂ͎��̊ю��I�яo�����̌��͂����h��@�B���̂��Ƃŗv�@�����w�������ď@��̑��Ă�ϊv���悤�Ƃ������t�B���t�ޏo�O��̖@�َ������̖����A�P�X���Ɍh��@�Ɠ����ɂ���Đ������ꂽ�w�t�̗���B�����̕��G�ɋ��܂������ڂɕ��Ԃ悤�ł�����B���������A���t�̌Z��q�ł���A���t��葊�����������P�W���̉m�t���A�o����A�Ԃ��Ȃ��ɋ{�J�ɍu�`�ɍs���Ă���B�ю傪�{���𗣂�āA���E�̊Ԓ��Y��̒h�уw�u�`�w�s���ȂǂƂ����̂���̕s�v�c�ł͂���܂����B�m�t�̐S���ɂ͕��G�Ȃ��̂���������������Ȃ��B
�@�����������ŁA��h�߂̌��͂�t�̑����ɔᔻ�A�����A�X�ɂ͏w�t�ɕs���̐����Ԃ��錳����̑�Ύ��m�O�����������Ƃ͗e�Ղɑz���ł��邵�A���R�������Ȃ���ΐ^���̗��j�͂�����Ȃ��B���t�̎��Ȃǂ͑m�O���肩�݉Ƃ����ւ��Ċю�ɑ��ĕs�M�A���f���点�A���������ɈႢ�Ȃ��B�����ɐ��t�����X�_�킳�˂Ȃ�Ȃ����R���������̂ł���B
�@�u�E�̈ꊪ�͗\�@�َ������̗��N���������B䢂Ɉ����Ė�k�̐^���^���v���̞N�����U���הp�Y�������ׂɕM����ނ�҂Ȃ�v���������t�̎v�f�͂S�O�N��ɍ��܂��݂�B�ю�ɑ��ċ^����Ȃ�����k�^���̉�����̐���肪�A��ɑ�����P�p���錴���͂ƂȂ����̂ł���B�����t�̂悤�ɖ@�َ������̏���������āA�@��̘_�@���w�E������O�Ȃlj����ɂ����Ȃ��ȂǂƂ����̂͌��͎҂̑�����݂����j�ł���A����^���̗��j�Ƃ͂����Ȃ��B�}�A�����t�����p���ꂽ�@�َ������̏���ɂ́u���w�������N�Ɍ�Ԏ��h��Čy�X�~�v����͂ƏΎ~�ɑ�����A���̌̂͗}���@��@�䏑���̎���ȂĈ�@���O�ߌA�����ꓯ�̋V�Ɍ��A�ʂ��đ�Ύ����́A�����̑����Ɛ\������Đ��̑�������l�͊w�s�w�ɂ�炸���g�̎߉ޓ��@�Ɓi�����j�@��R�F�ю�̉��m�ɐ��Њю�̍���܂��鎖�����M�̈ꎚ�̏C�s�i�����j���̎|�𑊒m����͔@���l�̑m�ю�ƂȂ�Ƃ������`����́A���g�߉ޓ��@����x���v�Ƃ���A��̔w�i���v�������ēǂ߂ΐ����Ɣ[���������̂ł���B
�@���̏��́A�@�������ꂽ�Ƃ������A�@���̍������O�̔ᔻ���ю�̌��Еt�������邱�Ƃɂ���Đ������悤�Ƃ��鈫��������̎Y���Ƃ�������B�����t���v�ې�t�����āu���������l�Ԃɂ͐M�̈ꎚ�̑厖�Ȃǔ���܂����v�Əq�x�A�M�̈ꎚ�̏C�s���@�َ������Ɠ��l�A�ю��M���邩�M���Ȃ����Ɍ��肳��Ă��܂����́A��Ύ��@��r���̎���ɂ��܂��Ă������ٗ��א��Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B���t���܂��u���Ɛr�[�V�����̎��B�S���]�m�Ɉꌾ������\�����������ƔV�Ȃ��B�ю��l�̊O�͒m��\�킴��Ȃ�v�Ǝ��炢����̂��ŋ߂̓����t�̔����ƋO����ɂ��Ă��苻���[���B���܂�ю���ŏo���Ɛ��t�̎���Ɏ���ɑ������Ă��邩��s�v�c�ł���B��q���邪�A�ю呦���g�߉ޓ��@�Ƃ����͖̂ܘ_���Ƃ̋����ł͂Ȃ��B
�@�Ƃɂ����A�{���t�Ɂu���̓����t�̏����ǂ�Œp�����Ȃ��̂��v�Ɣ����Ă��A����p�����Ƃ��v�����A�������ċv�ې�t�̂����u�@��ɔ������҂����������v�Ƃ������ɂ��ȂÂ�����̂�����B�����t���g��������悤�Ɂu�����ꂪ���M�����悭�悭�l���Ă݂�v��������܂��B
�@�M�҂͉����D�����̂�ŏ@��V�O�O�N�̗��j�̑e�{�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B���݂̑�����x�m�{���̐����Ɋ҂��ׂɂ́A��X�͐^���̏@��j�ɖڂ����ނ����������A��������P�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�@��j�ɂƂ��āA�������ɐ��t�̎���͈Â�����ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B�������A���̈Â�������ɖ��邢���ゾ�Ǝ咣����̂͋���Ȏq���̂��邱�Ƃł͂Ȃ����B�Â���������P�Ƃ��āA��Ɍ���ɐ������Ă����͂��߂Ă��̎���𗧔h�ɓ`���̈ꕔ�ɉ����邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����ƍl����̂ł���B
�@�@�@�@�@�@���@�@�@���@�@�@��
�@�]�k�����A�����t�͑����Ɋւ��āu���@���̕��q��`������ɐ��Ԃ̔N���̌����Ƃ͂��̎������قɂ��v�Ƙ_���A��Â̔��Ց��̗�������P�T�C�U�ł��Ⴍ�Ȃ��Ƃ�������A�u�ӂ₯���������a���\�̐l�ԑ����Ȃ��Ċr�ׂ悤�Ƃ��邱�Ƃ͂�߂������悩�낤�v�ƒ�������Ă���B����������ł͓����́u���w�������N�Ɍ�ԁv�����܂��Ď��グ�A�u���w��l���R�T�Ō�o�����ꂽ���Ƃ�z������āv�q�ׂ��Ă��邱�ƂɁA���X���������B��������a���P�T�̎��ɑ吹�l��莒������^�Ղ��S�O�E�T�O�̌���l���ȒP�ɓǂ߂�ł��邤���B�Ƃ������Ă��邪�A����Ȃǂ́A�A�����J�ɂ����ăA�����J�l�̎q�����p���b���̂����ċ����Ă���̂Ƃ����ւ炸�A�������ɂɒB������������B
�@�܂������t�͂T�S�łɁu�v�ې쎁��A�w����x�Ȃ钿���Ȍ�͓��{��ɂ͂Ȃ��v�Ƒ�i�ɐU�肩�����đ匩�h�������Ă��邪�A������t�̓Ǐ��͈͂��������Ƃ���N����ߌ��ɊO�Ȃ�Ȃ��B�����̒m��Ȃ����̂͂��̐��̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ����p���͌��グ�����̂����A��ϋX�~���Ȃ��B�u����Ȃ��v���́A������Ƃ������{��ł���A���Ƃł��×����g���Ă���B�t�����̕����u�ǂȂ��ƐS����v�Ƃ���ꂽ������l�������Ɏg���Ă���́B
�@�u����v�ɂ�����܂ēǏ�����̂��ꋻ�ł��낤�B�܂��A���ˉ����ɁA���̕����ǂȂ��ƐS���鎮�ē�����l�����������ɏo���̂��A���܂�ǂ��S�|���Ƃ͂����Ȃ��B���t���g���삱��܂��B�����邾�������Č��Ђł����Ĝ�������悤�Ș_���́A�m��ʂ܂Ɍ䎩���������邾���������Ă���̂ł���A���ɂ��Ղ̈Ђ����肽�����{�����a���������Ȑ����ł͂Ȃ����B����Ȃ��Ƃɐ����o�����A�܂���@����̂������痧�āA�����ȕ��͂ł���킷�P�������ׂ��ł���B���t���h���ĉ�������A���O�Ƃ̋����͂��悢�打���Ȃ����ŁA�v�����悹�������Ȃ������O�́A�ɒ[�Ȍ��͕����ɂ�����Y���A�������݂̂ł͂Ȃ��낤���B
�@
�@
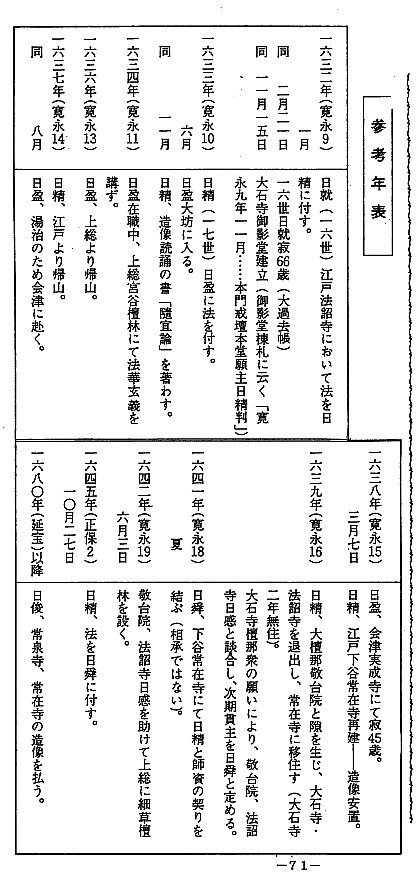
�@
�@
�����E���ј_���̒t����j���i�Q�j
�@�ŋ߂̕����Ƃ��āA�ю��Ζ��T�Ƃ��������@��̂�����Ƃ���ŏ������Ă���B����l�͐��M��t�ɑ��āu��@���l�lj��̕G���ɜ����ō߂���Ƃ�S����F��v�Ƃ����A����l�͓�����l�����āu�^�������ƌ��Ӂv�u�\���E�\�ƁE�\���ʁv�Ǝ]�V����A����l�͗L�t�́@�u���@�̑��g�����̖@��͎t�푊���ď������]�O���������]���Ȃ�v�̕�����Ⴆ�āA�lj��ɐ�Ε��]��������̂ł���B�݂̂��炸�A�lj��䎩�g���u���@�̑�`�E�{�`�̏ォ��ԈႢ�Ȃ��v�Ƃ����āA�ꕪ�̌낿�������F�߂ɂȂ�Ȃ��B
�@�������A���̂悤�T�Ȑ�Ύ҂������ɐ݂���v�z�́A���Ɩ{���̎v�z�ł͂Ȃ��A�@�喢�n���N��Ƃ���̈ٗ��`�Ƃ���˂Ȃ�����B����͎t��q�̖@��A�@�|���Ə@�����A�ҖŖ�Ɠ��]��̗������ɓ�d�E�O�d�̍����𗈂����ׂɐ��������̂ł���A���̎v�z�I�y��͐Ȗ������w�ɋ��߂邱�Ƃ��ł��悤�B
�@�捆�ɂďq�ׂ��ʂ�A�����t���u�M�̈ꎚ�̑厖�v��ю�ɂ��ĂĂ���A�ю�M�������ɋɂ�����������B������ꌾ����A���@�����͗���l���b�r���Č��ю�Ɏ����Ă���吹�l�����ю�ł���A�����ő吹�l�Ɗю�̗���͓^�|���A�{���吹�l�ւ̐M���A�ю��M���邱�Ƃ����吹�l��M���邱�Ƃł���Ɛ�����Ă���̂ł���B
�@�������Ȃ���A�@���b�r�̌�͌����Ɉ��̐������Ɉڂ�������Č��ю傪�@���̏����҂ł���Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B����́A���ʁA�@���b�r�̔@���ɂƎg�p�����悤�ɁA�吹�l�̎��߂�����N�A�����N�����Ă��F���ς炸腕���ɗ����؏O�����������Ƃ������ꂽ�@���̔�g�ł���B�����̏�ŁA�ю��l�̖@�������̊ю�ֈڂ�Ƃ����A����������Ă���Ƃ��A�����̊킪���Ă���Ƃ̎w�E�ɍR������Ȃ����Ƃ͑O�͂ɂďq�ׂ��B�܂��A���_�I�ɂ��A���̍l���ł����A���ۂɓ��E�̊ю傪�����ю�ɖ@�����b�r���ĉB���ɂȂ�A�B���͓��R�@���������Ă��Ȃ����ɂȂ�A�����̐܂ɕt�����邱�ƂȂǏo���锤���Ȃ��B�B���������̕s�f�ɔ�����Ƃ����͖̂����ɂȂ��Ă��܂��̂��B�܂����x�̂悤�ɖ@����J���̂P�N�R�������O���b�r���Ă��܂������B��l����̊�̂܂ܓ��E���߂��Ă������Ƃ����������ł͂Ȃ����B
�@���܁A�������Ƃ������t���g�p����Ă����l�����A��́A�������Ƃ͉����낤�B栚g���Ă����A�����̑����̗��Ȃ̂��A��������ΊO����������̂��A���ؑ����ƊO�p�����i��q�j�Ȃ�Η����ł��邪�A����Ƃ͈Ӗ����Ⴆ�Ă��邵�A�f�p�ȋ^��͂��Ȃ��Ƃ������ł���B�����t�̏�������ł͂Ȃ��A�����̑���@�̘_���������A�@���ƌ��������A��������ҖŖ�Ɨ��]��̗������A���������Ă��炸�A�@��̐��E�ƌ����̐��E�ɖ��f���Ă���悤�ł���B
�@���ʋ`�o��
�u�@��栂��ΐ��̔\���C�q��Ɂi�����j�F�����\�����L�̍C�q����@���A���̖@�����������̔@���B�\���O���̏��̔ϔY�̍C���v
�Ƃ���A�@���͈�؏O���̔ϔY������A�������킷���̂ł���Ƃ����B���Ƃ��܂��o�̈ӂɂ̂��Ƃ�A�@���̎��߂Ɣc���Ă���B�����킿�A����
�@�u���@�����ߍL�������A�얳���@�@�،o�͋��N�̊O�����܂ł��Ȃ���ׂ��B�̌䕶����{�����ӑ�����
�@�u���̗����ւ���͓��@�����ߍL��̋`�Ȃ�v
�Ƒ��`���Ă���̂�����ł���B���Ƃł́u���̗���₦������@�̎��߁v���X�ɑ�Ύ��̉����Ɏ����Ƃ��Č��킵�A�ߔN�܂ŕۂ��Ă����̂ł���B�܂���̕���藬�ꗈ�����͋q�a�̂Ƃ���Ŗ������r�ɂȂ�A�X�ɒC���Ɍ����Ĉ�腕���ɗ��ꋎ��A���̎���y�̐��̗����@���Ə̂���̂ł���B�����Ɏ��ӑ����̖��������̖{���`������B
�u�ނ̒r������ɕs�v�c�Ȃ���@���e���̑喟䶂Ȃ�i�����j�����͘Q�̏�ɂ���Č����Ђ돈�̖{���̌�`�Ȃ肵���Δ\���\���������Ȃ�A���Ė{�����ʂ̎�����ɓ����V�����ʂ��������ƁB�v
�q�a�̉��[���݂��܂��p�`�̂Ȃ����@�����i�v�������̎���p�g�j�͖����r�ɂ����Ă̂ݏ��߂ĕ����Ƃ������B����������l���ʂ��Ƃ��Ĉꕝ�̙�䶗��ƂȂ�̂ł���A���ꂪ�{�����ʂł���B���傩��C�߂ɗ���鐅�̗���ƁA�q�a�[�����r�[�{�����ʎ��̔z�u�͍��ł��������Ȃ���A��Ύ��ɍ��Ղ𗯂߂Ă���B�����ɂ�����{�����ʂ��₦���鐅�̗���ɂ̂��Ĉ�腕���ɗ���A��؏O���������̂ł���A�{�����ʂ͎��߂̈ꕪ�Ƃ�����B
�@�@�����u���@�����߁v�ł���A���̐��͖̂��@�̏O�����~�ς����@�ł���A�O�鑊���̖{���ł��邱�Ƃ͘_��ւ��Ȃ��B�������b�r�Ƃ͏��ʂɒʂ���́A�@���b�r�Ƃ͂��̂܂ܖ{�����ʂ���ɂ�����B���ꂪ������l�ɖ@���b�r�̌ꂪ������鏊�Ȃł���B�{�����ʂ�������l���l�ɋ������Ɠ��l�ɁA���R�@���b�r�̌��������l���l�Ɍ�����B����l�͓�����l�̗���ŁA������l�̔@���ɖ{�����ʂ����̂ł���A�܂肻�ꂪ�@���b�r�@���ł���B�����t�́A���t�̌�f���ɑ��āu�吹�l�̌�S�̂܂܂ɏ��ʂ���B�t��̗������ȂǂȂ��v�Ɨ͐����Ă��邪�A����͊ԈႢ�œ����t�͒�q�̗�����悭�ق��āA������l�̔@���ɏ��ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@���̂悤�ɖ@���b�r�̌�͖{�����ʂɒʂ��A������l�̗���i��q�̕���j�𖾂炩�ɂ��ꂽ�@���̗v��ł���B�k��ɊO���ɏo���Ĉ��̐������Ɉڂ����Ƃ���A���͂��ʂ��̟v�ɂȂ�A���͉̂��������A�{�����L��掂��Ƃ�Ȃ����Ƃ��炢����Ȃ��̂ł��낤���B������肩�A�J�R��l�͂�������l�̌��l�ɐ�������ɂƂǂ܂��Ă��܂��A�@���̈Ӗ��͑S����������B�x�m�嗬�̈Ӌ`���r�������B�J�R��l�̗��ꂪ�����䂭���Ƃ͒�q�������R�Ƃ��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����A�t��q�̖@��S�̂��낤���Ȃ邱�Ƃł���B�悭�悭�l���˂Ȃ�Ȃ��B
�@�]���ɂ���邪�A�t��q�̍��������炩�Ȃ��̂Ɍ�{���̎^��������B���t�́u��{���̎^���̓�\�]�N�ƎO�\�]�N�̍��ق́A�t��q�̖@��̌����ł͂Ȃ����v�Ƃ̖₢�ɑ��āA�����t�͌�C���r���u����ȗ������͂Ȃ��B�t��q�ȂǂƂ��������Ȃ��Ƃ������ȁA����͂��O�̖@�傩�v�Ƃ���ꂽ���A��{�����ӑ������q�ׂɂ݂�A�t��̗�����������͖̂����ł͂Ȃ����B������l�̌��ɂ�����S�O�\�]�N�Ƃ���A���t�̌�`�y��ɂ͏@�c�`�ɓ���S��\�]�N�A�J�R�`�ɂ͓���S�O�\�]�N�̑��䶗��ƋL����Ă���B�X�ɊJ�R�`�̋L�ڂɂ́u�i�O�\�]�N�Ɓj�}��������{���ɔw���ӂ͍߂ԂɊJ���]�]�v�Ƃ���A���J�Ɂu�}���v�Ɠ��t�����r���ӂ��Ă���B���t����\�]�N�ƎO�\�]�N�ɑ��`����Ƃ����Ă���B�����t���ȑO�A������w�{��p�C����_��鎞�A��\�]�N�ƎO�\�]�N�Ɋւ��u�����̋�ʂ����������Ȃ��A�Œ��Œ��ɐ蕶���W�߂āA����̂��A�{�莁�̕a�ł���B��\�]�N���O�\�]�N�����Ȃ���^�̖����Ƃ��A�Ӗ������炸�Ɋ������Ă�������́A����ł��w�Ɏu���l�Ԃ��Ƌ^����v�Ƃ����Ă���B��̍��t�ւ̔����Ƃ��l�����킹��A������������̂��Ȃ��̂��������E�ɂ��Ă�����̂ŁA�[���̂����Ȃ��Ƃ���ł���B�����t�ɉ��炩�̗�����������̂Ȃ�u�Ӗ������炸�������Ă�v�Ɛl�ɂ����O�Ɍ䋳�����肢�������̂ł���B
�@�Ƃ�����A���ݓ����t���@�J���c�̒�q�����邱�Ƃ�Y�����A�u�@��ɔw���Ă������ڂɂ͌������Ȃ��v�ȂǂƂ����đ吹�l�C���ł��邱�Ƃ͎t��q�̖@��𗧂Ă铖�ƂɂƂ��āA���ɒQ���킵�����Ƃł���B������肩���͂܂ŁA�t��q�̖@��ɖ��f���Č��݂̊ю���̎t�Ƃ���Ƃ͈�̂ǂ��������Ƃł��낤�B�����t�Ɏ����Ă͋v�ې�t�́u��X�̐^����̎t�͑吹�l�ȊO�ɂȂ��v�Ƃ̔�������肠���āA�n���̈��ł���Ƃ܂ł����Ă���B�����t�͑吹�l�ȊO�ɐ^����̎t����̉����ɋ��߂Ă���̂��낤���B��X�ɂƂ��Đ^����̎t�͑吹��Ɍ����Ă���ł͂Ȃ����B����Ƃ������t�͓����t�ɐ^����̎t�𗧂Ă�Ƃł������̂ł��낤���B�ڂ������Ȃ�^�|�ɁA���V���n�̎v���ł���B
�@�҂��ɁA�����t�͎t��q�̖@����ю�Ƒ�O�ƂɌ��肵�A���ې��E�ɌŒ艻���Ă��܂����l�����A�����[��̖@�傪�A����ȊȒP�ȍ\���ɂȂ��Ă���Ɛ^���ɍl���Ă���̂��낤���B�t��q�Ƃ����Ă��A���@�E�����̎t��q������A�@�c�E�J�R�ɑ���ڎt�̎t��A�@�J�O�c�̎O�c��̂Ɠ��t�ȉ��̎t�퓙�A�l�X�Ȏt�킪����̂ł���B�������A���̉�������@��̏�ʼn��d�̌�{����F������ׂ̎t��q�ł���A�܂������Ă��@�傩��͂���āA���ې��E�Ŏt���c������̂ł͂Ȃ��B���i�K�ɍ�����������A�������́A����ł͓����t��̊ю�M�Ɋׂ�����A���ł́u�Ֆڑ����̑I�����s���āA�ʂ��ē�����l�����I����Ǝv���Ă���̂��낤���v�ȂǂƂ������Ȃ��Ƃ������j�ڂɂȂ�̂ł���B��́A�Ֆڑ����ȂǂƂ������X�������t�́A���Ƃ��@��Ƃ͉����䂩����Ȃ��B�t��q�̖@�傪����ĊO���ɂł�A����Ȍ��͑����ɂȂ鎖�𐅓��t���g���ؖ����Ă���̂ł���B�Ȃ���A�v�ې�t�̌��t�̈�X���S���炨������̂Ƃ���l���́A����̌��͎u���I�Ȉӎ��̔��f�Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�ܘ_�A���Ƃ͊O���ɂłė��]�̐��E�Ɏt��𗧂Ă���̂ł͂Ȃ��B�̂ɓ��@�E�����E���ڂƂ����Ă��A���g�����������j��̐l�������̂܂w�����̂Ƃ͌��炸�A�@�������킷��̗v��ł���ꍇ������B���R�A���̎��͊ҖŖ�̏��k�ł���B���]�E�Җł��ȒP�ɐ�������A���όo��
�@�@�@�@�@�@
�@�@��
�]�� �@��
�ҖŖ�
�@�u���s����E�����Ŗ@�E���ŁX�߁E��ňy�v�Ƃ̕�������悤�ɁA���̒��̌��ۂ͉����Z�Ȃ��̂͂Ȃ��A�����։鐶�ł̖@�ł���A���Ȃ킿����𗬓]��Ƃ����̂ł���B�������^���̊y�i�����j�́A�������]���鐢�E�ɂ͂Ȃ��A���ł̖@���X�ɖł��߂�����ł̐��E�ɋ��߂���ł���A������ҖŖ�Ƃ����̂ł���B
�@���Ƃ��A���@�E�����̎t��Ƃ����Ă��A���]��E�ҖŖ�̓�l������̂ł���A�ҖŖ�̓��@�E�����͖@��̏�ŁA���Ə@�|�̍��{�ł���v�������̖��@�̑̂𖾂������t��ł���B�̂ɓ��Ƃł́A�×����t���ӂ̖��@�Ƒ��`�����Ă���̂ł���A���@�Ƃ����ΕK���t�푊����āA�͂��߂Đ��A������̂Ȃ̂ł���B�L�t�̋���
�u��s��F�̌��g�E���@��m�͋�E�̒��ソ��{�ʂ̕��E�ƌ����A���Ӎs��F�̍Ēa�E�����͖{�����̋�E�ƌ����L��ʁA�i�����j�t�푊���Ďz�o�̉��V�A�M�S�̏���\�����܂ӂȂ�A�\�E���L���Ɖ]�ւǂ����@�����̎t����Ȃ��Č��A����Ȃ�B�v
�Ƃ���̂��A�ҖŖ�̏��k�ł���A���Ƃɂ����閭�@���@��̏�ŁA���@�����̖��������Ďt���ӂƌ��肳���|�������Ă���̂ł���B�����ĕ��E�E��E�^����
�\�E��������Ė��@�Ƃ��A���̖��@�������Ė{���ƌ�����̂ł���B
�@���R�̂��ƂȂ���A���̎t��A���E��E�́A�t�i���E�j����ʁA��q�i��E�j�����ʂƌŒ艻���ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�����ʂ̒��ɉ���ɍ��ʂ��݂���ꂽ�t��ł��邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ʂ̒��Ō݂��Ɏt�킪����ւ��ďC�s����B�t�̒q�͒�q�����ƂȂ��A��q�̒q�͎t�����ƂȂ��A�݂��ɐ؍��������Ďt���ӂ𐬂��鎞�A������v�������̖��@�Ƃ����̂ł���B�̂Ɋ��t�́A�Z�����ɓ`����
�@
�u���E�̒q�͋�E�����ƂȂ��A��E�̒q�͕��E�����ƈׂ��A���q�݂ɖ��O���}����P�Ȃ�v
�̕��������ꖳ���ʂ̎t��̏�ɋv�������̖��@����������Ă���B���Ƃł́A���̍��{�̎t���c���ē��@�E�����Ə̂����̂ł��蓖�R����̏��k�ł���ΊҖŖ�ɗ����̂ł���A����g�����������]��̓��@�E�����ƍ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�v�������̖��@������킷���@�E��������̎t��Ƃ���A���ɂ��̏@�J���c���t���ɂ��āA�O�c�ڎt����q���ƂȂ��đ��������̎t�킪�������B���Ȃ킿�ڎt�̗���́A�@��̏�ł̏O���̓o�������킵�A���@�i�q���E���j�A�����i����E���j�̊Ԃɐ�����t��s��A���q�����̈�q�ł���A���E���E���C������Ė����ƌ�����̂ł���B�����̂Ƃ����L�t��
�u�j�]�O�J�o��]�N�A�����m�����m���m�o�m�v�l�m�a���V�e��F�m�q�������g�]�w���A�����m�����m�n���c���@���l�i���A���m�o�m�v�l�m�n������l��A��F�m�q�m�n���ڏ�l�����i���A�T���n����k�m�M�n���m�S����厖��v
�Ƃ����āA���@�E�����̂��ƕ�F�̎q�O�c�ڎt���a�����āA�����̖@��̍j�i���Ȃ邱�Ƃ𖾂�����Ă���B
�����Տ��X����
�u�E���ڂ͏\�܍Γ����ɒl���Ė@��M���Ă��ȗ����\�O�̘V�̂Ɏ���B�����ĈᎸ�̋V�Ȃ��A�\���Γ��@���l�̏��Ɍw�ōb�B�g���R�䑶�����N�̊ԏ퐏���d���v
�Ǝ�����Ă���̂��A���@�E���������Ɏt�Ƃ���ڎt�̒�q���𖾂�����Ă���A�ڎt�̓o��ɂ���Ă͂��߂ē��Ƃ̎t��q�̖@�傪�������邱�Ƃ��킩��B�X�ɏ\�l����t�ɁA�����Տ��X������������A����ɂ��A
�u���@���@�E�����E���ڌ����t���S�̕s�F�֑��͂Ȃ�B�[�����|�����ꎆ�O�����i�����Տ��X���j�t�����暎��ʕi�V�Ȃ�v
�ƋL����Ă���A���̐Տ��X���́A�@�،o�ł����Ύ��ʕi�ɑ������āA�t���ӂ̖{�������킷�ׂ̕�暂̂悤�Ȃ��̂��Ƃ����Ă���B�����āA���̎t���ӂ̖{���Ƃ͓��@�E�����E���ڎO�c�̌����t���̑S�̂ł���Ǝ�����Ă���悤�ł���B���Ȃ킿�A�@�J���c���t�Ƃ����q�ڎt��������čĂюt���ӂ𐬂��A�O�c��̂ƂȂ��Ă͂��߂ē��Ƃ̖{���Ƃ�����B�̂Ɏ�t�͏����{���̎������ɂ��A�E�Ɂu�����䔻�q�a��B���v���Ɂu���ڎ��^�V���q�����{���ƋL���Ă���A�������̓얳���@�@�،o���@�䔻�ƍ������ĎO�c��̖̂{���`������킳��Ă���B�����̔@���A�ڎt�̏o���ɂ���ĎO�g�����߂Đ����A���Ƃ̖{���A�t��q�̖@��̍\�����Ȃ���Ă���̂ł���B
�̂ɓ��Ƃł́A�@����\������@�J�O���A�×����O�c�Ə̂��A�l�����t�ȉ��̗���l�𐢁E��ƌď̂��A�@��ƌ����̐��E�m�ɗ��ĕ����Ă���B���E��͖@����������E�Ő��X��X�ɘj���Ď��т��Ă����ӂŁA���]�������킵�Ă���B�܂�O�c�́A�ҖŖ�ɂĈꑦ�O�ƊJ���A�O�ꑦ��ƍ������āA��ɂ����܂�A�@��͈�l�ł��邱�Ƃ�����킵�A����l�͎l����莟�悵�Č܁A�Z�A���Ɛ���ǂ����]��̐��E�ł���A�ю�͘Z�\�Z�l�𐔂��Ă��Ȃ̂ł���B���R�A�@�̎傪�Z�\���l���o������ȂǂƂ����n�������b�͋�����Ȃ��B���̈Ӗ��ł��A����l�͖@��ł͂Ȃ��A�ю�Ə̂���̂������ł��낤�B
�@�����ɎO�c���t���Ƃ��A���ю�ȉ��̑�O���q���Ƃ���O�Ԗڂ̎t�킪������̂ł���B�\�O���@�t���v�@�����C����
�u���ɉ]���A�����̍����Ɛ��̌o�̕v�l�Ƙa�����ċ��ɐ��̕�F�̎q���Ɓ\�\�����\�\���F�A�O���̌��暈�w�����l�ɑP�I���ւ����҂��B�v
�Ƌ��ɂȂ�A��̗L�t�̓��@�q���E��������E�O�c��F�̎q��������ĎO���̓�暂Ƃ����A�@�t����͂��̓�暁i�t���j�Ɉ�w�����s�����q�̗������������Ă��邱�Ƃ́A�t��q�̖@�傩��݂Ď��ɓ��R�̂��ƂƂ���˂Ȃ�Ȃ��B���݂ɁA���̓��C���͓V���@���ŎR��ɂ�藌�O�֒Ǖ����ꂽ�v�@�����C���A���͂̏�̒��Ŗ@�����₂��čĂї����ɋ�����A���̗]��������đ�Ύ������P���ɓ����Ƃ������̉@�t�̕ԓ��ł���B�O���̓�暂ɂ͂���ĊO������ꂽ�ܕ��́A�O���͐ܕ��ɂ݂��Ă��A�������Ă���͐ێ�̍s�ł͂Ȃ����A�@�|�����悭�ق�����ŁA�@������W�J���Ȃ����A�u�O���̌��暁A��w�����l�ɑP�I���ւ����҂��v�ƁA���Ȃ荂���E�及���@�t�����C�̋��s���r�ӂ��Ă���B
�X�ɓ����
�u�c�Ѝ��̔@���A�R�тɓl�����ݐl�ɑ����Ƃ��`���Ɉ�w�V�ꖳ����ΐܕ��̑�ڂƐ���A�������l�ɑ���k�`�Ȃ�ǂ��A�A�̏C�s�͐ێ�̍s���ƂȂ�ׂ����A�������吹�̋��]�X�v
�Ƃ̌䕶�́A�x�m�嗬�̌��i�Ȏp����������Ă���A�����̉䂪�@��̍s���܂ňĂ����Ă���悤�ł�����B�͂����Ċw��̐ܕ����A�吹�̋��Ɋ����Ă������A���݂̊w���i�삷��@���@���A�`���Ɉ�w�̂Ȃ��ܕ��̑�ڂɂȂ��Ă��邩�A�čl�̕K�v�����낤�B��X�͌��݂̍������A�����ڐ�łƂ炦��̂ł͂Ȃ��A�@��I�Ȍ��_�ɑk���Ė��炩�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����瑊�I�ɂ݂āA���̊j�S�������ɂ��Ă��܂��A�^���̈����͉i���ɂ��Ƃ���Ȃ��ł��낤�B
�@�p���A���܈�x�t��q�̖@�������A���@�E�����̎t��͖����ʂ̒��Ō݈唺���ċv�������̖��@�𐬏A���鍪�{�̎t��ł���B���ɁA���̏@�J���c�̎t����܂Ƃ߂Ďt���Ƃ������A�ڎt���@��̏�ł̏O���A��q���Ƃ�����A�����ɏ@�c�i���j�i�J�R�i���j�A�ڎt�i���C�j����̂ƂȂ��Ė�����������A���̎O�c�̓��������A���Ƃ̌����E�{���̓��e�������t��q�̖@��ł���B���̖@��̏�Ɍ������ꂽ�O�c�̓����t���Ƃ��āA���t�ȉ�����l�y�ю��]�̑�O�S�̂���q�ƂȂ��āA�t���ӂ𐬂��鎞�A��Ύ��@��Ƃ��Ẳ��d�{�����͂��߂Ēa������̂ł���B����́A���傤�ljN�Ћs�̎p���̂��̂ł���A���]�Җœ����̂Ƃ���ł�����B������w���Ď������ɍs����Ƃ����̂ł���B���݂͗��]�@�E�Җł������藐��āA�J�R��l���щz���ď@�c�ɂȂ肩�������A�l�c������l�Ƃ�������A�����̐��Ŗ��T�̕��l����������A�t��q�̖@��̍��������ɋɂ��Ƃ������l����悵�Ă���B
�@�����t���t��q�̖@��ɓ���āA���n���@�؍u�O��Ԏ���q�ǂ���A�����t���̎t�ɂ���悤�Ȏ`�Ɋׂ炸�ɂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B��������
�u����̂ł��ǂ����A����͂��₤�l�̂����̌�ł��Ɛ\�₩�炨�ق���B�����̐l�X�͂��ڂ��ɂČ��B�v
�Ƃ���悤�ɁA���Ƃł͒��̌��q�͓�����l�������Ȃ��̂ł���A����l�́A�J�R��l�̒�q�ɂ�����B���̊ю傪�����Ȃ������l�ɂȂ肩����Ē��̌��q�Ƃ������Ƃ𐽂߂��Ă���B�̂ɗ��ю�̐\��ɂ�
�@�u���@���l��q�������������������ތ��v�@�@
�@�u���@���l��q������퓙�ތ���v
�@�u���@���l��q���������L���������ތ��v
�Ƃ����āA���̊ю�͓�����l�̒�q�����邱�Ƃm�Ɏ�����Ă���B�����ɕx�m�嗬�̈Ӌ`���N���ɂȂ�A�t��q�̖@��̈�[�����f�����Ƃ��ł���B���̊ю傪�A������l���щz�����Ƃ́A�@��̗̈��N������
��ł���A�����ɂ͕K�����]��A�ҖŖ�̍�������݂�
�Ă���B���������āA��������@��I�ɉ��߂���A�u��
�ł����������v�u���ł����ɂ���������ւv���̌䕶�́A
�ю�Ƒ�O���@�J���c�̓��Ɋ����悤�t��q��������
�āA�܂�݈唺���Ė��@�𐬏A���Ȃ����Ɠǂ߂��
�ł���B
�@���Ƃɓ`��鑊�`����l�X�Ȑ؎��́A�����Ɏt��q��
�@��������ɓ`���Ă���B���ꂪ�^�ꗝ���ł��Ȃ��̂́A
������X�̊w��C�s������Ȃ��̂ł��邩��A��w���i
���Ȃ���Ȃ�܂��B�킩��Ȃ����Ƃ�I�グ���ď��
�̖@�傪���������Ă������Ƃ́A�r�����t�ɐ\��
�����Ƃł���B�L�t��
�u��V�����m���j�i���n���c�m�䎞�V���A���@���ԃg���j����X���������A�����g�e������l�m�䎞�l�������m�\�X�������L�u�L���t�ԉ�J�\�X�����j�A���X�A���m�����s��\��B����k�m��n��X�m�ӊy�ӊy�j�e�X�j������ԏ��m�����䑶�m�L�N��Ԉ���H���j����s�L��m�]�]�v
�Ɖ]���Ă���悤�ɁA���Ƃ̏@�|�́u��X�̈ӊy�ӊy
�Ɋe�X�Ɍ����v�������̂ł͂Ȃ��B���̊ю傪�A����
�s�x��Ύ҂ɂȂ�Ȃ�A�ӊy�ɖ@��̌������Ȃ����
���Ƃ�Ƃꂦ�Ȃ��ł��낤���A����͂������đ��剺��
�D�ނƂ���Ȃ̂ł���B�܂��Ă�u���ɋt���҂͔�@��
�O���v�Ƃ����Ė@�ɂȂ肩����Ă��܂��A���łɂ���
�͎��̕��ނɓ���B��͂�A���Ƃ̊ю�́u���m���v
���Ⴆ���ɓ`���闧��ɓO���A�O���̓����O�Ƌ���
���т���q���̗���ɂ����Ăق������̂��B
�@
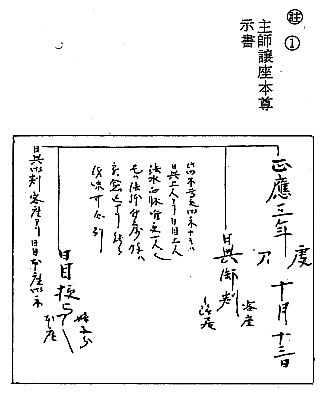
�@
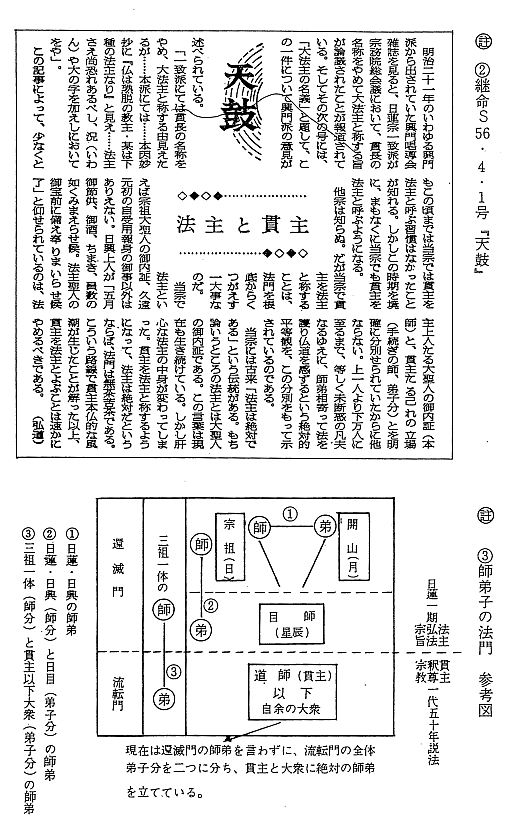
�@
�@
�@
�@
�����E���ј_���̒t����j���i3�j
�@
�@
�@�@�����_���ɂ��ẮA����܂łɗ��j�I�����̒f���A�����Ŗ@���b�r�Ǝt��q�̖@��ƁA����ǂ��ĕM��i�߂Ă������A�����ł͖@�̑����Ɩ@�告�������グ�Ĉꉝ�̏����Ƃ������B
�@�����t�̘_���������ɂ߂Ă��邱�Ƃ́A���܂��~�X�w�E���Ă����ʂ肾���A�����̌�T�̑�͗��]��E�ҖŖ�̍����ɂ���Ƃ�����B�ҖŖ�ɗ��Ă�ׂ��@��𗬓]��ɗ��āA��������̂܂܌��������ɃX���C�h�����Ă��܂��A����͂��̍����ɂ����C�t�����ɂ���悤�ł���B�@�@
�@�@�����A�@��Ɗю�̗��������ł��Ă��Ȃ��̂��A���̗ނł���B�O�͂ɂĐ��������ʂ蓖�ƂŖ@��Ƃ����A�O���i�O�c�j�̓��]�����吹�l�ƐS����̂ł���A����͂��̂܂O�鏊���̐l�Ƃ��ď�s��F�ɒʂ�����̂ł���A��@��y���ɉz����腕���ɖ����̎��߂𗬂��A�܂莞����z�������݂��@��ł���B����ɑ��Ċю�͎���̐���̒��Łi�܂藬�]��j�@��@�̓����҂Ƃ��Ė@�����т�����ł���B
�@���Ȃ킿���݂́A���]��̊ю傪�ҖŖ�̏��k�ł���ׂ��@�����������Ă��܂��A���������ɍ������낵�Ă��܂����̂ł���B�ߐ��܂Ŋю�i�������͊ю�j�̖��̂��g�p����Ă������A�����ɓ����ď@���@�l�@�̐ݗ��̍ۂȂǂɊю�̖��̂͏����A�@�傪�����Ɏg����悤�ɂȂ�A����ɊҖŖ傪�N�����悤�ɂȂ����B�Ȃ��ɂ́A�ю�Ƃ͊ǒ��E�̂��ƂŁA���@�ł͖@��Ɗǒ��͓���l�������s���Ďi����̂Ǝ咣����l������B�������A���m�̒ʂ�ǒ��E�ȂǂƂ������̂́A���͖ܘ_�A�]�ˁE���������ɂ��Ȃ��A�߁X�ɏo�������̂ł���A�M�ȊO�̐��Ԗ@�ɏy���Đ��ꂽ���̂ł��邩��A���R�×����̊ю�Ɨ��������Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����������m�ɂȂ��ꂽ��ŁA���̊ю�Ɗǒ��̖�����l���ׂ����Ƃ́A���Ȃ����]�̂����k�ł���́A�\�Ȃ��ƂȂ̂ł���B������ꑫ��тɁA�ǒ��Ɗю�͓������ƂŁA���ꂪ�@�������ƂȂ�Ȃ�A���@�ɐ��Ԗ@����������A�X�ɗ��]�E�Җłɖ����Ƃ�����d�̍����������ɂ݂͂���B�����݂ɁA�@��E�ю�E�ǒ��̎O�҂̊W��}������A
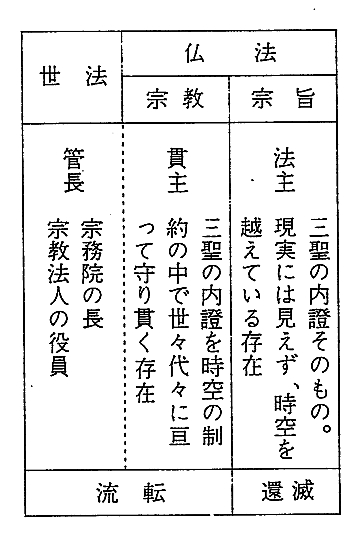
�@�ꌩ���Ă��킩��̂悤�ɁA�ю�Ɗǒ��͕��@�E���@�̑��Ⴊ������̂́A�Ƃ��Ɍ��g�����������]�̏��k�ł��邩��A�ꕽ�ʏ�ɘ_���邱�Ƃ��o����B�������@��Ɗю�́A���]��ƊҖŖ�̎��߂���߂��Ă���A�؊������Ȃ��Ɉꕽ�ʏ�ɖ@��Ɗю��_����悤�ȍ����͋�����Ȃ��B�킩��₷�������A�����ɐ����Ă��鈽�����̐l���w���Ė@��Ƃ������Ƃ́A���łɗ��]�E�Җł̍����ł���A�{�����肤�ׂ��炴�邱�Ƃ����݂Ȃ���Ă���̂ł���B�܂��Ă�@��Ɗǒ��Ƃ������ƂɂȂ�A���������肷���āA���Ƃ��n���ɂ����Ȃ���������B��X�͂܂����@�Ɛ��@�̗������m�ɂ��A�X�ɕ��@�ɓ����ẮA���]�A�Җł̍����Ɋׂ�Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���Ƃ̑������l���鎞���A���i�̎���̂悤�ȁA�����̈�Y�����I�l�����܂��r�����A�X�Ɋю�̖ʂɗ������ƁA�@��̖ʂɗ������A�܂�A���]�E�Җł̑���ɓ���čl���n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ⴆ�A�g���E�r��̓�ӑ����A���t�Ƌ����A�ƒm���A�ʕt�Ƒy�t�A�@�̂Ɩ@�哙�́A��������A���]�E�ҖŁA�ݐ��E�Ō�̗�
���������邱�Ƃ��ł���B
�@�����t�́A�@�́E�@�告�������߂��āA�u���ׂ���������A�B����l�̌��������͕ʕt���@��
�����ł���A�v�ې쎁�̂��������w���{���`�x�͑��t���@�告���̂��Ƃł���A������������邱�Ƃ͉]
�@�]�v�u���������̖@���Ƃ͖@�̑����ł���A�@�`�Ƃ͖@�告���ł���v�Əq�ׂ��A�@�̕ʕt�E�@�呍�t�ƕ����Ă͂�����̂́A���]��Ƃ������ꕽ�ʂ̏�Ř_�����Ă���A��������ю�̏����Ƃ���Ă���悤���B���Ɂu�ʕt���@�̑����͒f�₹�����ďЌp�����v�Ă���Ƃ����A�u�v�ې쎁�̂��������w���{���`�x�͑��t���@�告���̂��Ɓv
�Ƌ�ʂ���Ă��鎖���l��������A�v�ې�t�̎w�E���ꂽ�����̒f��͖@�告���̕���ŁA������͒f������邩������Ȃ����A�@�̑����Ɋւ��Ă͒f�₵�Ă��Ȃ��Ƃ̎咣�Ƃ�������B�������A�@�̕ʕt�E�@�呍�t�̂�����������]��ōl���A���j�̘�ɂ̂��Ă��܂��A�����t�̎咣�͗�ɂ���āA���Ȗ����Ɋׂ��邱�ƂɂȂ�B�@�̕ʕt�E�@�呍�t�̓�͓��ꕽ�ʂōl��������̂ł͂Ȃ��A���]�E�Җł̎��̐؊����A���������K�v�Ȃ̂ł���B
�@�@�̕ʕt���ҖŖ�A�@�呍�t�𗬓]��ƍl�������A�Ȃ���A�ю傩��ю�ւ̗��]��͂Ƃ���Ă��A�M�̏�Ɍ�������ҖŖ�̌����͐�Ă��Ȃ��Ƃ�����B���ʂ̓�`�Ƃ����Ă��A�o���Ƃ��ɗ��]��̊ю�ɏW������Ƃ������Ƃ́A���x�A�n���ɂ���ׂ�����̖@�傪�n��ɂ��炳��āA�厖�̖@�傪���Ȃ��邱�Ƃ��Ӗ�����̂ł͂���܂����B
�@�܂����ʂ��A�ʕt���͊ю��l�ցA���t���͑�O�����܂ޑ����Ƃ���������邪�A����͑��ʂ����ɗ��]��ōl������ɁA�X�ɑ��ʂ��t���܂Ɏ��Ⴆ�Ă���B�{�����t���́A���]��̐��E�����Z�߂Ĉ�l�i�ю�j�ɏW��Ƃ̈Ӗ��ŁA�ю傩��ю�ւ̑����������Ă���B�ʕt���͓��ʂƂ����悤�ȈӖ��ł͂Ȃ��A���߂������ĊҖŖ�ɗ����A��؏O���i�ю���܂܂��j�̓��ɗ���錌�����w���Ă���̂ł���B
�@���Ƃɉ����Ă��A�ю傩��ю�ւ̑����i���t���j���ɂ��邪�A����́A�����ɂȂ�����̖@�̕t���i�ʕt���j���m�F������ŁA�����L�݂����`�ł�������̂ł���A�{�Ԃ͖ܘ_�A�ҖŖ�̖@�̕t���ɂ���B�����@�̕ʕt�̑����Ƃ́A�N����N�ւƏ����ɗ����p�`�̂��鑊���ł͂Ȃ��A��؏O���̓��ɗ����@�̂��̂��̂̑����ł���A�M�̏�Ɋo�m����������̂ł���B�܂�ʕt�Ƃ͓���������킵�A�L�t�͂��̌������A
�u�M�m�]�q�����m�]�ƁA�@���m�]���n���V����B�v�i�x�v�@�|�Z�l�j
�@�Ƃ����Ă���B���A�\�l���̎�t�͓����Տ��X�������ɁA
�u�x�m�l�P���̒���O�P���҈�ȃe�����퐬��B���n�y�t�����i���E��Ύ��Ҍ�{���ȃe���퐬��B�����ʕt���B�N��l�Ӄi���B�吹�����{����d��{���A�]���t����V��{���@铌�t���v�i���@��S���@�|�l�܋�j
�@�Ƃ����Ă��邪�A��������t���ƕʕt���̑���𖾂炩�ɂ���Ă���B
�@���̕x�m�n�̖剺�ł́A�t�����莆���̈����X�̊ю傪���`����Ă��邪�A����͑y�t�����Ƃ�����B��Ύ��ɂ����Ă��A���l�ɗ���ʂ��đ��t�����̑������Ȃ���Ă��邪�A���Ƃ̍��{�ɂȂ錌�������́A���d�{���E�����{���̎t���ӂ̖{���������Ė@�̕ʕt�̌����Ƃ�����̂ł���A���̎t���ӂ̖{�����O���̌ȐS�ɐM�̈ꎚ�������Č������ꂽ����B����l�Ƃ����̂ł���B���̖@�̕ʕt�̑����͊ҖŖ�̏��k�ł����āA���R�ȐS�����ɐ��藧���̂ŁA�{���Ƃ����Ă����łɓ���̔⎆���w���̂ł͂Ȃ��A���d�{���E�����{�����A�����Ɉ��u���ꂽ��䶗��͎O���̓���������Ɏ����Ɍ��킳�ꂽ�Ɣq�����ł���B�F����Ƃ�����d�̖{���Ƃ����A���łɖŌ�ȐS�Ɍ��킳�����̂ł���A�u�q�a�̉��[���܂��܂��v���d�̖{���Ƃ������`�́A�q�a�̓����A���Ȃ킿�{���͓��ɂ����Ďp�`�̂Ȃ����̂�����킳��Ă���̂ł���B�����������ɂ́A�q�a�̒��Ɍ�����Ă�͖̂����Ȃ̂ňꉝ�q�a�̂������Ɍ�������Ă���̂ł���B�̂ɋߑ�܂ŁA�q�a�ł͓njo����Ƃ����Ă����ڔ�䶗���q���邱�ƂȂ��A�m���������͂��璆���̋��Ɍ��������悤�ȍ��z�ɂȂ��Ă����̂ł���B�����l����A�N�Ћs�̍ۂɕK����̉��d�{����y�q����Ӌ`���N���ɂȂ�B
�@�����̔@���A���d�̖{���Ə����{���͑�ϖ��ڂȊW�ɂ��邪�A���̗l�ɗy���ޕ��ɉ��d�{�����O�����Ȃ��Ĉ��u����Ă��܂��A�ȐS�����̖@��Ƃ����Ă������s���Ɨ��Ȃ��̂����ɓ��R�Ȃ̂�������Ȃ��B�×���莖�����݂ē�����T��ׂ����t�����`���ꂽ���̂��A���݂͎��������������ω��肸�炢���肩�A�������w���ē������Ƌ��ق��Ă���B�{�����A�@�c���ϐS�̖{���Ƃ����Ă���ɂ�������炸�A�����ɂ����ꂽ���̂Ɏ������āA���ꂱ���������Ƒ����ł���̂ł���B
�@�ς����͌�q���邱�ƂɂȂ邪�A���d�{���E�����{���E���N�~��{���́A���ꂼ��E�q�a�E�䓰�ɂ����āA���̈��u�̕��@��`���A�܂������̔z�u�ɂ���ē�暂������ł���悤�ɂȂ��Ă����̂ł���A�k��ɋ������q�݂̂̍ޗ��ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂��{����B�������A���ю�̏����i�Ƃ��Ĕc���āA�@�̕ʕt�E�@�呍�t���ɓ����t�ɑ�������Ă���ł͂Ȃ����Ƃ����l�����邪�A����́A���@�ɂ�����@�|�E�@���̂����ꂩ������ꂽ�A�����̈�Y�����̘b�����Ă���̂ł���A����͊ǒ��Ƃ��Ă̌����̔����ł��邩��A�M�Ƃ͉���W���Ȃ��B
�@���āA���܂Ŗ@�呍�t�Ɩ@�̕ʕt�̑����ɂ��ďq�x�Ă������A�v��A�@�呍�t�͊ю傩��ю�֑�������A�@�̂̓��e�𖾂炩�ɂ����|��̂悤�Ȃ��̂ł���A���]��̏��k�ł��邩��A�V�O�O�N�̏@��j�̂Ȃ��ɂ͑ޔp������A�f�₷��悤�Ȏ����������B�������A����͓����ɁA���̓s�x�ю�y�ё�O�������ɑS�͂�s�����V�O�O�N�Ƃ�������B
�@�@�̕ʕt�́A�u���@�����߁v�u�@���v�Ƃ���킳�ꂽ��A��{���������đ����Ƃ���Ƃ���ꂽ�悤�ɁA�@�c��
�u���@�����ߍL��Ȃ�A�얳���@�@�،o���ݔN�̊O�����܂ł��Ȃ���x���v�i�S�W�R�Q�X�j
�@�Ƃ̌�ӂ̂܂܂ɁA��邱�Ƃ̂Ȃ����̌��������ł���B��腕��^�A������؏O���ɋ����Ă���v�������̖��@���w���A���̖��@��M�̏�Ŋo�m�������鎞�A�����������Ƃ����̂ł���B������l���Z�����ɁA
�u��q���o�m������앧�Ɩ�����Ȃ�v�i���T�W�P�T
�Ƃ���ꂽ�̂�����ł���A���R�ҖŖ�̏��k�ł���B
�@�����̂��Ƃ������́A���]�Җł̗����������m�ɂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃɂ����鑊�����ꉝ�������č��ɗ�L����A
�@
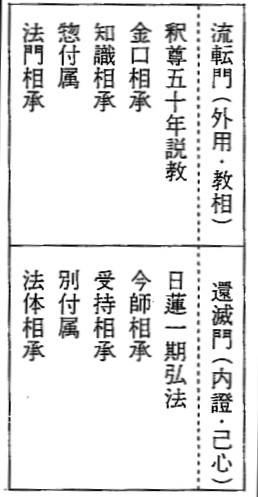
�Ƃ��邱�Ƃ��ł���B�y�ʁA�@��@�̂ɂ��Ă͊��q�̒ʂ�ł���B
�@�E�m�������͕S�Z�ӏ��ɂ݂���Ƃ���ł���B���Ƃɂ�����Ƃ́A���s�A���ϐS�Ƃ�����@���A��暌ȐS�̐M�̈ꎚ�ł���A���ꂪ�O���̌ȐS�̂����Ɍ��������A���ꂼ��B����l�̌����Ƃ�����B�m�������Ƃ́A�����ʂ�̐��̂Ƃ͉����������m���ł���A�{�������E�S�Z�ӏ����̑��̐؎��A���`���͂��x�Ēm�������ɓ���A�×��ю���ю�֓`����ꂽ���̂ł���B
�@�����E���t�̑����́A�\�O���@�t�̓��C����
�u�t�i���t�j���i�����j�̗������A�O�ӂ̔�@���ɂ��āA�l���O���̍��𑊑҂҂Ȃ�v�i���@��S���@
�|�S�T�P�j
�@�ƌ�����B���Ƃ��Ƃ��̑����͑�Ƃł悭�����A���Ƃł͂��܂萔���݂Ȃ����A��͂���e�́A���@����������ɂ݂ė��]��ɑ��������Ă���������ƁA�t���ɂ݂ĊҖŖ�ɂ��Ă鍡�t�����̓�l�ł���B���y�́A���������͑O����Ɍ����A���t�����͌���O�Ɍ����ƍO���ɋL���Ă���A���t�̑���́A���̂܂܍ݐ��������]�呦���O�p�A�Ō�t���ҖŖ呦������������킵�Ă���B
�@�g���E�r��̓�ӑ����ɂ����������]�E�Җł̗�����������A�ߑ��\�N�̐����𗬓]��A���@����O�@���ҖŖ�Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B
�@���̓�ӑ����͌×��^�ւ����Ă���A�ʖ{�������ē`������Ă���B���̎ʖ{�ɍ��������̗��ڊˏW����
���̂��̂ƁA�v�@�����C�̏��ʂɂ�������̂����邪�A��҂̓`���͍��{�I�ȏ��ɍ��ق������Ă���A�r�������[���B���̂Ȃ�A���̍��{�I�ȍ��ق̂ǂ�����Ƃ邩�ɂ���āA�v�@�����w�ɂȂ邩�A���Ɩ@��ɂȂ邩�̊�H�ɂ�������Ă��邩��ł���B�S���͍��T�邪�A�L�q�̌o�߂ɏ]���ė��{�̑���_��������A
�@
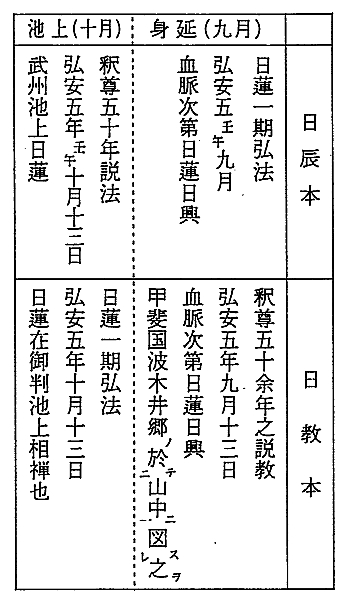
�ƂȂ�B
�@���C�{�́A�㌎�ɓ��@����̍O�@���������A��Ŏ��Ɏߑ��\�N�̐��@�𑊏�����Ă��邪�A�����{�͋㌎�Ɏߑ��\�N�̐����A�\���ɓ��@����̍O�@�ƂȂ��Ă���B�ߑ��̋������ƊȂ�ŁA����ϐS�̖@��𗧂Ă铖�Ƃ��A�͂��߂ɓ��@����̍O�@�������Ă��܂��A��Ŏ��ɋ�������̎ߑ��̋����𑊏����ꂽ�ȂǂƂ͕���ƂƂ��ď����ł��Ȃ��B�㌎�ɓ��@����O�@�A�\���Ɏߑ��\�N���@�Ƃ����̂́A�ߑ��𒿏d������C�̗v�@�����w�̂�����ł���A���������̐����x�m�嗬�×��̂��̂ł��낤�B���C�{�̎ߑ��\�N�̐��@���A�����{�ł͐����Ƃ���Ă���̂��A�����i�ߑ��j�ƕ��@�i���@�j�A���@�̑��Ⴊ���̂܂ܗv�@���Ɠ��Ƃ̈Ⴂ�����킵�Ă���B���e����݂Ă��A�ߑ��\�N�]�]�ɂ͋v�����̕ʓ��E�������Ă���A�ю�Ƃ��Ă̗��]�傪������Ă���B�̂ɓ����{�ɂ́u����������@�����v�ƁA������ɏ���������������Ă���B�u���@����O�@�ɂ͌������悪�Ȃ����@�䔻�Ƃ���A���@�̋������킷���v�������A���C�͂�����t���܂ɂ��Ă���A���@����̍O�@�Ɂu����������@�����v�Ə������]������킵�A�ߑ��\�N���@�Ɂu���@�ԉ��v��p���Ă���B
�@�����̔@����ӑ�����q���鎞�A��������ƊϐS����A�y�сA���]�E�Җł̗����������邱�Ƃ��킩��B���̈Ӗ���N���ɂ���ׂɂ����C�{���̂ĂāA�����{���Ƃ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ߑ��\�N����A���@������]�Ƃ���v�@���̓ǂ݂����̂܂ܓ��Ƃ��g�p����Ζ@�傪�������邱�Ƃ́A������݂Ĉ�ڗđR�ł���B
�@���Ƃ́A�܂��ߑ��̋����i���]��j�������Ă��̌`�[���̂ċ���������ɓ��@����̍O�@�i�ҖŖ�j���Ȃ킿�v�������̖��@���݂�̂ł���A��ӑ����͗��]����Җłւ̐؊����������Ă���̂ł���B������l����x������ꂽ�v�����̕ʓ��E���~��āA��Ύ����J�R����̂��A���Ƃ����]���Ƃ߂āA�Җłɗ����A�O�����̂ĂČȐS��暂ɖ@�����Ă鏊�Ȃł͂���܂����B
�@�Ƃ������A�����t�̂悤�ɖ@�́E�@����A��ӑ������A�����牽�܂œ�����l�A������l�ł́A���t�����܂��Ȃ���A�^�ʖڂȋ��`�_���Ȃǖ]�ނׂ����Ȃ��B
�u���������͐����Ȃ�A���@�͎����̏�̐s������Ƃ���v�i�x�v�@�|�U�P
�Ƃ͗L�t�̋��A�l�X�Ȍ����̞~�����痣��āA�@��͌��r���ׂ��ł���܂��悤�B
�@
�@
�@
�@
�����E���ј_���̒t����j���i4�j
�@
�@�{���A�ڂٕ̐��ɑ��Ă��A�ŋ߁w�@�|�x�w�@���x��@�w���]�x�w�ҖŁx�Ƃ����������͓��Ƃɂ͂Ȃ��Ɨ͐�����l������B�������A����͋����ɉ߂���咣�ł͂Ȃ����낤���B
�@���Ƃ̖@��͂Ƃ����A�@�|�̎O�ӁE�@���̌܉ӂƓ�����悤�ɁA�܂������ď@�|�Ə@���̑�����K��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B������l�͘Z�����Ɂi�Z�����\�\�w�є�P�Q�T�Q�j
�u�@�|�̎O�ӌo���ɕ����Ȃ�A�@���̌܉ӂ�暕��@���B�i�����j�����A�������ėv������ɑ��̑��������ׂ��A���̌܋`���Ȃ��ċX�����O�ӂ��O�ނׂ��]�]�v
�Ƃ����Ă���B�����A�@�|�Ƃ͎O��E�@�̂Ɋւ��鏊�k�ł���A�@���Ƃ͎O����O�ނ�ׂ̏��k�ł���Ƃ���Ă���B
�@���݂ɁA�Z�����͑S�̂�ʂ��ď@�|�𖾂�߂�@�发�ɂȂ��Ă���A���̈�O�O����O�鑊���̖{�����F�������܂ł������Ă���B�̂ɁA�O�d��`���`���̊J�ڏ��̈�O�O�當��钾�̕��́A�Z���S�̂ɒʂ�����̂ł���A���ꂪ���Ƃ̎O�鑊���̖{���Ƃ������̂͑�ܓ����s�����A��Z���ƎO�ߏ��܂ł܂��˂Ȃ�Ȃ��B���@���@�v�`�ł͘Z���������苳���_�E�@�|�_�E�J���_�E�j�ܘ_�E�s�@�_�E����_���Ɗe�X�z�����Ă��邪�A�S���̃i���Z���X�ł���A��Z�́u����_�v�Ȃǂ͐r��������Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B�܂����́u�@�|�_�v�������Ⴂ�ł���B�ނ���A����钾���͘Z����ʂ��Ă݂鎞�A�Z�����̏���A�O�i�Ƃ�������ׂ����̂ł���B�����A�O��͕��ׂĂ�����̂́A�����͑����̎O��ł͂Ȃ��A����d�Ǝ��悷��Ƃ���̊e�ʂ̎O��ł���A���ڂ��f�����ɉ߂��Ȃ��B��O�ˋ`�����������Ƃ��āA��l���A��܂��d�ƂȂ��A����d�Ǝ��悵�āA���悢��O�鑊���̖{�����������̂ł���B
�@����͂Ƃ������A�@�|�E�@���̗������́A��̊��t�̌䕶�̔@���A�@�|�������{�ł���A�@�������}�t�ł��邱�Ƃ͘_���܂��Ȃ��B���̏@�|�Ɋւ��錌���Ƃ͉�����A�{���Ƃ͉�����̘_�|�ɑ��āA�u�n���w��̐ܕ��ł���Ȃɖ{�����O�܂����ł͂Ȃ����v�ƑS���ڒ����ȉ��҂����Ă���̂����݂̏@��ł���A�����ɏ@�|�E�@���̍������[�I�ɂ�����Ă���B���юt���_���Ɂ@�u���@���N�Ɂw�₦���炵�߂�x�ƌ�������ꂽ��{���ł���B�w�₦��͂����Ȃ��x�Ɗm�M���A�Ȃ��w��₵�Ă͂Ȃ�Ȃ��x�Ǝ�삷�鎖����X�̐M�S�łȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����Ă��邪�A���܂��悭���̖{�����̂ݍ��߂Ă��Ȃ��悤�ł���B�܂��_�����ɁA���ϐS�̌���݂��邪�A���̎��u�{���������Ă�����̂Ɋ�{�I�ɘ_�@�͂Ȃ��v�Ƃ�������A�{�����z�Ƃ������t������킷�w��ƂقƂ�Ǔ��ӂł���A���t�̂�������ϐS�Ƃ͑S������������Ă���B���юt���g�͏@�|��̗v��������āu�@�|�̍��{�v��_���Ă������Ȃ̂ł��낤���A���e����������@�����ɓ���ւ��Ă��܂��Ă���̂ł���B
�@�����͐��m�ɂ����A�@�|�@���̍����Ƃ������@�������@�|�����U���ēo�ꂵ�A�������@�|�������ł����̂ł��邩��A���ɕ��@�̚��O�ɂłĂ��܂����Ƃ�����B���̂Ȃ�A�@�|���Ƃ͏@�����̗��t���ł���A�@�|���̂Ȃ��@���Ȃǂ͂��肦�Ȃ�����ł���B�@�|���͗��t���Ƃ������炢������A�{���ʂɂ͏o�ė��Ȃ��B����ɑ��镶��A�E�ɑ��Ă̎�̂悤�Ȃ��̂ŁA���Ɛ[��̖@��ɂ͎����@�|�@���̗�������������B
�@�{���͖ʂɂłȂ����t���i�@�|���j�̘_�`�̍ۂɁA����Ɏʂ�Ȃ����̂�M����͎̂��s�ł͂Ȃ��A���̖@��ŊϔO�_�ł���Ɣ��юt�͔�������Ă���悤�����A�ʂ��Ă��ꂪ�܂Ƃ��Ș_���Ƃ�����ł��낤���B���Ȃ��Ƃ����t�͔��ѐ���ے肳��Ă���B
�@���A�@�|�Ə@�����ȗ��ɐ�������A��{�̖̒n���̍��s�ƒn��̎}�t�ɏQ���邱�Ƃ��o����B
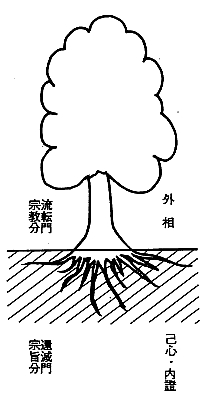 �n���ƒn�㍇�����Ĉ�{�̖ł���A��̖@��ł��邪�A���{�ɂȂ�͕̂����ʂ�A�n���̍��s�̕����ł���B�n��ɂł��}�t�͂������ɉ䂪�}����y���܂��Ă���邪�A��������͒n���[���}��Ɍ����Ȃ����s�����Ă̘b���ł���A�}�t�̂Ȃ����͂܂��l�����Ă��A���̂Ȃ��}�t�Ȃǂ��蓾�Ȃ��B
�n���ƒn�㍇�����Ĉ�{�̖ł���A��̖@��ł��邪�A���{�ɂȂ�͕̂����ʂ�A�n���̍��s�̕����ł���B�n��ɂł��}�t�͂������ɉ䂪�}����y���܂��Ă���邪�A��������͒n���[���}��Ɍ����Ȃ����s�����Ă̘b���ł���A�}�t�̂Ȃ����͂܂��l�����Ă��A���̂Ȃ��}�t�Ȃǂ��蓾�Ȃ��B
�@�����Ƃ��䖝�Ύ��̐l�́A���͓y��x�肨�����Γ���ɐG���A��͂荪�͖}��Ɏʂ�̂�����A���̏Q���͓���Ȃ��Ɣ��_���邩������Ȃ��B�������@�c���䏑��
�@�@�u���I��ʂ�Ύ}����A�������Η���y���v
�@�@�u���[����Ύ}�������A��������Η���Ȃ����v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�]�J���������䏑�E���j
�Ƌ��̂悤�ɁA����I��ɂ��邱�Ƃ́A�}�������Ɍ͂����Ƃł���A����͂��̂܂܁A���@�̏��ł��Ӗ�����B���͒n���ɂ����Ċ�ɐG�꓾�Ȃ����炱�����ł���A�n��ɂłĊ�����Ă��܂��Ί��ɍ��Ƃ͂����Ȃ��B���ɔA�}�t�ɂ��A�܂�@�|�@���̂ǂ���Ƃ��ď̂ł��Ȃ��Ŗ@�̊O�ɂł����̂ł���B
�@����͍X�ɏd�ǂŁA�n���̐��E��M����ꂸ�A��Ɍ�����n��̎}�t�̐��E�������đS�̂ƍ��o���Ă���B����͐����̗]�n�̂Ȃ����A�����ɐ����̗��]�ɂ܂Ŋׂ��������Ƃ�����B�����A���]�Җł��n��̎}�t�ƒn���̍��s�ɂ��Ă͂߂���B
�@�n��̗��]��́A���̓s�x���ʂ�ǂ��ĉʎ������߁A�n���̊ҖŖ�́A��ɂ͌����Ȃ����̂̂��̉ʎ��݂������̖��������Ă���B栂��͈�{�̖Ə����Ⴄ���A���x���t����E�̑����Ăƃ��~�������ču�`�����@���ł���B�]�킭�u�������w���P�R���ϐS�{�������L�v
�@�@
�u�Ĕ@���N�č��N����X����B�@���A�����Ė�]���ċ��B���@�l���~�}�}��X����B�̏W���]�k�J�������Č��]���E�ݐ��Ӗ�B�ݐ����ă}�C�e�ăi���w�L��A�F�N�T����i
�@��ƒE�͖@�̂ɂ����đւ�Ȃ��Ƃ̋^��ɑ��āA���Ă͗��]��̒E�E�ʂƂ��Č����ɐl�̐H�����̂ƂȂ邪�A�������A��E���Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�����Ď��ۂɂ͐l�̌��ɓ���Ȃ��A���m�}�}�̃��~����ƂȂ邩��A��E�E�̖@�̂��̂��̂��قȂ�Ɣj�܂���Ă���B�܂蓯���Ăł����Ă��A���]��̔��ĂƊҖŖ�̃��~�̍�����������Ă��Ȃ��B
�@�����悤�ɒn��i���]��j�ƒn���i�ҖŖ�j�͍����ē�����{�̖ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A�u�n��ƒn���̗������͂Ȃ��v�Ƃ����Ζ@��͐��藧���Ȃ��B�܂��Ă�u�}��ɂ݂��Ȃ��n���̍��s�ȂǂȂ��v�Ƃ����A���ƈꗬ�̏@�|�E�ҖŁE�ȐS��暂Ƃ������E�����ׂĎ�������������ƂɂȂ�A���킹�Ď�E�̖@������낤�����Ă���̂ł���B
�@��̂Ɂu�}��Ɏʂ�Ȃ��v���̂͐M�����Ȃ��Ƃ������z���́A��E��_�����蕧����_�����肷��y���ȑO�̗c�t�Ȃ͂Ȃ��ł���A����͑f�p�Ȑ��Ԏ�`�A���y��`����ɂ����O���̘_�`�Ǝw�E���邱�Ƃ��o����B�悭���y��`�͊w��̐ꔄ�̔@���@����O���ᔻ����Ă��邪�A���̎v�z�I�����͌�����{���ςɂ���̂ł͂Ȃ����ƍl����B�x�m�嗬�{���̐^�̖{���ς�ώ����Ă��܂���
�u�]�g���S�^���Ȃ炴��҂������ɉ�����Ό����P�������v�@�i�O���j
�u���̖{����M���ē얳���@�@�،o�Ə���F��Ƃ��Ċ��킴��Ȃ��v�@�i�{�������i�j
�Ƃ̖��y�⊰�t�̗L��䕶���҂��čЂ��ނ��ƂɂȂ낤�B�_���͏؋��ŁA�n���w��Ƃ�������ȗ~�]�W�c�������߂錋�ʂɂȂ����ł͂Ȃ����B
�@���ݘ_�`���Ă���l�X�Ȗ��̑������A�瑊�I�ɑn���w��̎Љ�I�ӔC��Nj����邾���ł͂Ȃ��A���̍����ɂ́A���݂̖{���ςɖ@��I���ׂ���ق��Ă������Ƃ��m�F����K�v������͂��Ȃ����낤���B���̂Ȃ�A��A�̎Љ�I���́A�����L�z�A���V�̐ܕ��ɑ�\�����悤�ȑn���w��̌�����L�闬�z�ς������炵�����̂ł���A����͖{�����z�����ǂ��Đ��ɍ��{�̖{���ς������͕̂K�R�̋A��������ł���B�����ē��Ƃ̖{���ɁA���ʒB���Ă��锤�̏o�Ƃ̐ӔC�́A���R�M�k���d���Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B
�@���āA���юt�́u�{����d�̌�{���ɋ����L�喳�ӂ̌����ƁB���@�s�v�c�̗͗p�v��`�����Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ����Ă��邪�A�N�ꂪ���d�̌�{����`�����Ă���̂��낤���B�N����`���Ȃǂ��Ă��Ȃ��̂ł���B���Ƃ̖{���̂���ׂ��悤��_���Ă���l�Ɂu�{����q�߂Ό���������v�Ɛ��������̂́A���������ɂ͂���Ă��邾���ł���B��������ꂸ�ɂ����A���^�ʖڂɌ��r�����ׂ��́A���d�̌�{���Ƃ͉�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ����낤���B
�@���юt�̐��́A���d�̖{���͊�Ɍ�����A����p�g�͊�Ɍ����Ȃ��B��Ɍ����Ȃ����̂͗��̏�̖@��������A�����q�ނ��Ƃ͏o���Ȃ��A��������������l�@�P��@�i����͂��܂�ɓ��˂�����̂����j�Ȃ̂������������p�g�Ȃ̂��A�Ƙ_�����Ă���l�ł���B�������A����͑啔��������l�̌�w��Ƃ͈Ⴄ�B
�@���юt�̐����A��̒n���i�ҖŖ�j�ƒn��i���]��j�ɂ��Ă͂߂�A����p�g�͖}��Ɏʂ�Ȃ��́A���̏�̖@���Ō����ɐM���邱�Ƃ͏o���Ȃ��A�܂�ҖŖ�͂Ȃ��ɓ������B���������Ɍ�������d�̖{���i���̈�O�O��Ƃ������Ă���j�������ɂ���̂����炻���q�ނ̂����s�Ƃ����B�����Ċ�Ɍ������������p�g���Ƃ����Ă��ׂĂ𗬓]��A�n��ɏo���Ă��܂����̂ł���B
�@���юt�͉��d�̌�{���𗬓]��Ŕc���Ă���́A����Ɏʂ�ƐM���Ă�܂Ȃ��悤�ł��邪�A���d�̖{���͊ҖŖ�̏��k�ł���A�{���M�̏�̌����ł��邩��A����Ɏʂ�Ƃ��ʂ�Ȃ��Ƃ��̘_�`�̊O�ɂ���B�܂����Ƃ̎���p�g�𗝂̏�̖@���Ɣq����̂͊J�R��l�ȗ��A�����̒����Ŏ��B�͊nj��ɂ��āA���̈ˋ���m��Ȃ��B�X�ɂ͎t�̂������̎���p�g�����́A���̈�O�O��Ɛl�@�P��ɂȂ����̂��悭�킩��Ȃ��B���t�́A����p�g�Ɖ��d�̖{���͊m���ɐl�@��ӂł͂��邪�A�Ƃ��Ɏ��̖@��A�ҖŖ�̂����ɂĈ�ӂł���Ɛ�����Ă���B�n���ɂ����Ė{���I��ɂ����ׂ������̂��̂ł͂Ȃ��́A�}��ɐG���G��Ȃ��ɂ�����炸�A�O���̌ȐS�̏�ɐM�̈ꎚ�������ę��߂Ɍ��������̂ł���B�ܘ_�A���Ƃł͖ڂɌ����Ȃ��n���͗��ŁA��Ɍ�����n��͎����Ƃ����V��ʓr�̎����͂Ƃ�Ȃ��B���]��𗝁A�ҖŖ�����Ɨ�������́A����p�g���������i�̎���p�g�͗��ŋv����������p�g�͎��ł���B
�@�@�w�J�ڏ��x�̊J�ڂ����ї��ł́A�������������J���Ė{��������Ƃ������炢�̉��߂̊i�����ł���A���t�̂����閌�ɕ���ꂽ�O���̌ȐS�̖ڂ��J�����ނ�ӂƂ͊i�i�̑���ł���B���юt�́A�Ӗڂ̐l�̐M�͂��ׂĊϔO�ɑ��Ă���Ƃł��v���Ă���̂��낤���B�{���ɓ�����J���Ζ{����������Ƃł��v���Ă���̂��낤���B���юt���Ђ����
�u�ӊ�̎҂͔V�������A����̎҂͕����ƌ���A���͋���ƌ���A��F�͖��ʂ̖@��ƌ���v
�w�����l���̚g�x�͌ȐS�̖@��������Ă���B����͕����ƌ���̂����E�ł���A�X�ɖӖڂ̐l�͌����ɂ͉������邱�Ƃ��o���Ȃ��i���]��j�B�������A�M�̈ꎚ�������ČȐS�̊���J���A�����Ɍ��R�Ɩ{�������������̂ł���B���Ȃ��Ƃ��@�c�́A���@�̏O���͂��ׂĖ{���L�P�̖Ӗڂƒ�߂��Ă���B
�@��������юt���u���{���̑��e�͔q�����Ă��v�Ƃ����Ă���ʂ�A����ł͑��{���̑��e��������܂łŁA���{�����̂��͔̂q�����Ȃ��B��͂�{���͌ȐS��暂̖ڂ��J�������A�͂��߂Č����������̂ł���B
���d�̖{������ɉi���鑠����Ă����̂��ȐS��暂̓��Ƃ̖@�������킷�ׂł���B�䏑�Ɂi��u�����j
�u���̖��@�@�،o�͖{�n�r�[�̉����Ȃ�v
�Ƃ�����悤�ɁA�O�鑊���̖{���Ƃ́A�B���A���܂��Ă����Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A���Ƃ��{�n��暂ɑ�����Ă���Ƃ̈ӂł���B��X�̓���́A�O�鑊���̖{����邵�Ă���Ƃ���̑��͌����Ă��A�{�����̂��̂͌����Ȃ����Ɛl�Ԃ́u�S�̑��v�����邪�@���ł���B�S������肢�����Γ���������āA���̑������邱�Ƃ͏o����B�������A�S�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�����瑟���J���ĐS�������݂悤�Ƃ��Ă��A���Ɍ��邱�Ɣ\�킸�ł���B���l�ɕ��J���Ă݂Ă��A�S����O���@�̓얳���@�@�،o�i���d�̖{���j�͖{���݂邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���A���̗l�ɁA�����ɉ��d�̖{����������o�����l�Ȍ`�ɂȂ�A����͂��łɎO�鑊���̋���̖{���ł͂Ȃ��A�O��e�ʈ�@�ꉏ�̖{���Ƃ������ƂɂȂ�͂��Ȃ����B��X�͑����݂ĐS�̂��邱�Ƃ�m��悤�ɁA���݂āA���̓�暂ɉ��d�̖{����q����̂ł���A�鑠����邱�Ƃɂ���Ďn�߂ĎO�鑊���Ƃ�����̂ł���B���̈Ӗ��ŁA���{���́h���h�ł�����h���h�ł��邱�Ƃ���������K�v������B
�@�̂ɓ��Ƃł͎��S�N���A�N�Ћs�̍ۂɌ���d�l��y�q���Ă����̂ł���A�y�q�͎p�`�̂Ȃ��ҖŖ�A�ȐS��暂̐M�S������킷�ׂ̕K�R���Ȃ���Ă���B�����āA���̉N�Ћs�����A���Ƃ̐����̒����ł��邱�Ƃ́A�@��l�ł���ΒN������٘_�̂Ȃ��Ƃ���ł���B
�@�������A���݂͂���������������ڒʂ肪���߂�ꂽ�ׁA��ϗy�q�̈Ӌ`�������Ȃ�A������ĉ��d�̌�{���͒��q����̂����R�Ƃ܂Ŏv���Ă���B����ł͑����A�O���͐����̏�����o���邱�ƂɂȂ낤�B�����ƈ�ʂ̊肢���Ƃ͑S���Ⴄ����ǁA�w����������[�t�́h���肢���h����J���̍ۂɋF�O���Ă���̂��킩��悤�ȋC������B
�@�����܂ł��Ȃ���J���́A�M�k�̂����Ă̊肢�ɂ��A�L�闬�z�܂Ŕ鑠���ׂ��{���������ɂ��������Ă�����̂ł���B���Ȃ킿����d���@���K���u�肢�ɂ��E�E�E�v�Ǝn�܂�悤�ɁA�O���̋@��ɐ����ĉ��ɂ��������Ă���킯�ŁA�{���M�s�̏�ł͂Ȃ��B������l�́u����ɐ������A�F���𑑌����v�����͋����ł���Ƃ����Ă��邪�A���d�̖{�����܂��A�n���i�ҖŖ�j�ɂ����Ă����^���ł���A�n��i���]��j�ɏo�Â�A�����ƂȂ�͂��Ȃ����낤���B
�@���݁A���d�̖{���̗y�q�ƒ��q���A�@��̏ォ�牽�̗��������Ȃ����s����Ă��邱�Ƃ́A���]�ƊҖŁA�����ӂƐ����ӁA�e�ʂƑ����A�����Ɛ^�����̗������������B���͌ЂƂ��Ă��邱�Ƃ��Ӗ����A�����ɐM�S���r�ɂ��鋰��������o�����Ƃ��o����B�܂��č���A���o�I�ɂ͒��q�݂̂ɕ���ꂽ�悤�ł�����A���͐[���Ȃ̂ł͂���܂����B
�@����́A���������n���ɂ���ׂ����s���x�肨������āA��O�̊�ɐG��Ă���l�Ȃ��̂ŁA�l�́u���ꂪ���s���v�Ƒ�����������Ȃ����A�n��ɂ��炳��Ă�����͍̂��s�Ƃ͂����Ȃ��Ɛ�ɏq�ׂ��@���ł���B�܂�^�̉��d�̖{���Ƃ͂����Ȃ��̂ł���B���d�̖{���́A�ҖŖ�ɂ̂�������邱�Ƃ���X�͍Ăі��L���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���юt�́A
�@�@�u���ɋ��������ȁB���{�ɘ_�@�w���̈�O�̑�����Ƃ���A�{����d�̑��{���Ƃ����@�|�̍��{�ɂ������M�S�A�@�`����܂�A�����ɐ��M�����̂���ǂ��A�@�q�͛@�q�A���̐l�Ԃ̌������A�������A�ׂ����A���̑S�Ă������Ă��܂��̂ł���B�v
�Ƙ_���̖����ŁA���M���X�u�k���ɏq�ׂ��Ă���B�������A���Ɏt�̘_���̓��e�́A�����Ɏ��⎩������悤�Ȍ˘f����Y�݂ɋ�Ⴗ��p��������B����́@�u�@�|�̍��{�ɂ������M�S�E�@�`�v�Ɍ��𗈂��Ă��邩��ƍl���A���̌����w�E���Ă�������ł���B�܂��A���̏��_�������ł��x�m�@��ɂƂ��ėL�Ӌ`�Ȃ��̂ɂȂ�Ǝv���̂Őٕ��Ɍ�T����낪����A�o������蔽�_��Ղ����������Ċ肤���̂ł���B
�@�܂������t�́w���сx�ɂā@�u������A�@�̓��O���킸�v�ې�_���Ɠ����悤�ȁA���@���`��A�����������Ĉ��ӂ������������ɑ��Ă͎����̗͂̋y�Ԍ���ɂ����Ĕj�܂��A���ӂ������Ǝv���Ă���v
�ƋL����Ă���B���B�́u���@���`��A���������ɂ��Ĉ��ӂ������������v���o���Ă������͑S���Ȃ����A�����t�̏����Ƃ͐^������Η����Ă��邱�Ƃ������Ȃ̂Ŏt�́u�͂̋y�Ԍ���ɂ����Ĕj�܂��A���Ӂv����邱�Ƃ��܂��āA�X�ɔ��_�����������Ǝv���B
�@�@�@���@�O�ʓ����̎G�W�Ɂi�������P-50
�u��A����d���A����d�������@�C�s�V����A����d�����@�V����v�Ƃ���B�܂����d�Ƃ͖{�n���s������킵�A����d�͐��疉���������킷�B�����ӂƐ����ӂ̈Ⴂ�́A���̂܂@�|���Ə@�����̈Ⴂ�ł���B���A�h�т̏���ł��鐼�J���ڂɂ����Ă�����d�E����d�E�d����̎���ɂ��Ę_�q����Ă���B
���A�O���ɂāA�ߑ��̗��]���Ƃ߂ē��Ƃ͊Җłɖ@������Ă�Əq�ׂ��悤�ɁA���̗��]�ҖŁA�@�|�@���͎ߑ������Ɠ��Ƃ̑Δ�ɂ�������B�X�ɕt������A�ߑ������͓]��i�@�����j�̂Ȃ��ɗ��]�ҖŁi�@�|�@���j��_���A���Ƃł͓����悤�ɗ��]�ҖŁi�@�|�@���j�Ƃ����Ă��ҖŖ�ɂ�����݂Ă���B�܂�ʓr�ɁA��Ƃ̎����𑩂˂ē��Ƃ̗��Ƃ��X�Ɏ��𗧂邪�@���A�ߑ������̏@�|�@�����Ƃ��ɓ��Ƃ̏@�����Ƃ݂čX�ɁA�ȐS�����ɏ@�|�𗧂Ă�̂ł���B
�@
�����E���ј_���̒t����j���i5�j
�@
�@
����{���ςɂ���
�@���юt��
�@�u���ł����{�������ŋ���̖@�̂Ȃ���̂��Ƃ̖��m�̖\����f���Ȃ�A���ł���䶔��ɕt�����l�ȕ����A�ǂ����ċv���̖{���Ȃ���̂��ƌ������ƂɂȂ�͂��Ȃ����v
�Əq�ׂ��Ă���B���X�˘f���C���Ȃ�������ɑ����ȋ^��ŁA���̋^���@�`�̏ォ�琰�炵�Ă������Ƃ��A�����̖{���ρE�{���ς̌����������ɂȂ邩�Ǝv����B�c�O�Ȃ���t�́u�吹�l�͖��n���I�����A��{���͏��ł��邩��v�������̎���p�g�ł͂Ȃ��ƌ����Ȃ�A�吹�l�̖{�L��Z�A���̈�O�O��l�@�̈�̌�w��ɔw������v�Ƒ������āA���Ƃ̖@��ł�����吹�l�̐��̂�s���߂邱�ƂȂ��A���ɕt�����Ǝ��炢���Ȃ���A���q���@�����������Ղɖ{�L��Z�̑��݂ɂ��Ă��܂����B�����đS�����˂ɁA�l�@�̈�Ȃ̂������{�����i���ɏ��ł��Ȃ��Ƃ����Ă��邪�A����͌��Ɍ����d�˂��_�@�ł���B
�@�t�͂܂����q�ɐ��ꂽ�l�ԓ��@�ƁA�v����������p�g������@�吹�l�Ƃ̗����������m�ɂ���ĂȂ����肩�A�������č������Ă���A������̑��ł���B�����ŁA���̌������������āA�l�@�͑̈�ł���A�̂ɔ�䶗��̔����ł��Ȃ��Ƃ����A������̑��ł���B�����Đ��Ɂu���ܘ_�҂͌`������͕̂K���ł���Ƃ����A�}�v�̒Z���ʼn��d�̑��{�������Ă��邪�A���ꂪ�}�v�̖����ł���v�Ƃ����Ɏ���B�������A���Z�ٖł��J�Ԃ����]��̓���̕��́i���юt�̂������d�{���j���Ƌ�������̂͊O���̋����ɍ������Ă���̂ł͂���܂����B���d�̌�{���͐₦��͂����Ȃ����A��ɕ����ɂ���Č��킳�ꂽ��䶗��́A���̂��̂͂�����͏��ł�]�V�Ȃ������B�₦��͂��̂��̂��u�₦�锤���Ȃ��v�Ɗm�M�����v������̂́A���M�̂����߂ł͂Ȃ��낤���B���ꂪ�ʂ��ē��Ƃ̖{���ρE�{���ρA�������M�Ƃ�����̂��낤���B
�@������l�Ɠ����悤�ɁA�l�@�̈�A����p�g�A�@�c�吹�l���̖@��v����g���Ă��A���̓��e�����ւ��Ă��܂��A���Ƃ̖@��Ƃ͉��������̂ɂȂ낤�B���̒��ł��A���q�ɐ��ꂽ���@�����̂܂܌�������p�g�ɒu��������Ƃ���������{���ς��A�l�X�Ȗ������N���Ă��鍪�{�ƍl������B����͒P�ɔ��юt�̐��Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�ߔN�Ă��@���ɖ�������v�z�Ƃ�������̂ŁA�@�`���f�����͂��́w���@���@�v�`�x�ɂ����u�剞���N�\�Z�����@�̑哱�t�{���吹�l�̒a���v�Ƃ̋L�q���݂���B
�@�����͖@��̓����ɓ���ׂ����Ȃ����M�̐M�k�ɍu�b�Ƃ��āu���@�̖{�����剞���N�ɒa�����A�O���ܔN�ɖS���Ȃ����v�Ƃ������ɂ̂������ׂ��ł����āA���`������������ׂ��ᔻ�_���ɂ����āA���������L�q��������悤�͂����Ȃ��B
�@�v���ɁA�����̎v�z�͖{�������ꂽ��A����A���g�Ȃ݂̐��ł��J�Ԃ����]��ɗ��Ă�ꂽ���Ƃɂ���Ďn�܂�B�����āA���ꂪ�Ђ��Ă� �u�吹�l�����{�����c����ē��ł��ꂽ��́A�N���n�O�̕�F�Ƃ��čL�闬�z��i�߂čs���̂��B�����Ɍ˓c�O��́A�吹�l�Ō㎵�S�N��̏o�����d��ȈӖ��������Ă���v�@�i�r�c���j�Ƃ�����ςȎא���e�F���A���܂����u�n���w��L�闬�z�����v�Ƃ����S���Ⴂ�����߁A�X�ɂ͂����ϋɓI�ɗi�삷�邱�ƂɂȂ����Ă���B�܂�n���w��̍l���ł́A���@�吹�l�͊��q����ɓ��ł����̂ł����āA��{�����c���ꂽ����ǂ��A���܂�O��Ȃ������A������������ďo�����A��������ςȂ炴�炵�߂��̂�����ł���B�Ƃ����̂ł��낤�B�����āA���̍l���̕��������ǂ�A��ɏq�ׂ����q�ɐ��ꂽ�l�ԓ��@�ƌ�������p�g�̗�������m�炸�ɁA�������ē��ꎋ����@��̌�����{���ςɂ䂫���̂ł���B
�@��̂ɁA���̌�����{���ς͊J�ڏ��́u���@�Ƃ���҂͋��N�㌎�\����q�N�̎�����͂˂��ʁB����͍�鮍��n�̍��ɂ�����āv
�̌������������������̂ŁA�@�c���}�g��瑂��āA�ȐS���ɖ@�����������ꂽ�Ӌ`��ώ����Ă���B�ԑԁA�@�c���u��͂˂��ʁv�Ƃ܂ł����ĊO�����̂Ă��A���ꂩ��́u��鮁v�@�i�ȐS���j�ɂ��Ė@��𖾂��Ƌ�������Ă���ɂ�������炸�A�����ɊO���Ɏ������Ă���̂ł���A���ꂱ���u�}�v�̒Z���v�Ɛӂ߂��悤�B
�@�u�t��q�̖@��v�̍��ɂĂ��G�ꂽ���A�{�����@�吹�l�Ƃ͎��ԂƋ�Ԃz�����M�S��̑��݂ł����āA�������j��̑��݂ƍ�������̂͋����Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B
�@���Ƃ��Ύߑ��ɂ��A��x���a�̎߉ޖ���Ɩ@�،o�Ɍ���ꂽ�v�������̎ߑ��A���̑��ߑ��Ƃ����Ă��A���͓����ł��̑̂͑S���قȂ邮�炢�̂��Ƃ͏��w�̎҂ł����m�̂��Ƃł���B���Ƃɓ��@�@��ł́A�Z��̎ߑ��𗧂Ă�̂ł���B����Ɠ��l�ɁA���@�吹�l�Ƃ����Ă��A���q����̓��@�A��s�Ēa�̓��@�A�{�����@���A���ꂼ��Ӌ`���Ⴄ�̂ł���A������l�̋L�q�ɁA�@�t�A�@�c���l�A�@�c�吹�l�A�얳���@�吹�l���̗��������f���邱�Ƃ���X�͏[���ӎ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�䏑�ɂ��Ă��A����������ΎO���@���� �u���̎O���@�͓��]�N�̓����A�n�O��E�̏��Ƃ��ē��@�҂ɋ����o�������������������Ȃ�v�Ƃ���ꂽ�ꍇ�́m���@�n�Ƃ́A���j��̎��݂̐l���łȂ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B������Ƃ����āA���̌䕶���^���ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃɂ͖ܘ_�Ȃ�Ȃ��B�܂�A���q����̐l�Ԃł�����@���A���]�N�O�ɗ�h�R�ɂ����Ďߑ����璼�ڂɖʎ����������Ƃ������Ƃ͌������E�̘b�ł͂Ȃ����A�Ȋw�I�ɐ^�U��_���鐢�E�̂��Ƃł��Ȃ��B���Ȃ킿�A����́u�ȐS�����s�@��v�Ƃ������ƂŁA���@�吹�l�̌ȐS���̐��E�̂��ƁA��������Γ��@�吹�l�̐M�S�̐��E�̂��ƂȂ̂ł���B
�@�}�A�O���@���́A�S�̌ȐS���������Ĉˋ`�������ׂ��ł���A�ꕔ��������I�ɉ��߂���A�@��S�̂�c�߂邱�ƂɂȂ�̂͗��̓��R�ł���B�������d���߂����Ă̖��M�u�Ƃ̑Η����A�@�傪������тɌ䋳���͌���ł����Ό��z�����ɓ������Ƃ��A����͎匠�ݖ������獑���̑��ӂł���Ɖ��҂���A���M�u�Ɠ����y�U�̗��]��ł̌��������ɂȂ�A�@�c�̖{�ӂ���͗�������ł���B�����ɏ@�c���u�O���@���̑̔@���A���ĉ]���\���ȐS�̑厖�V�ɔ@�����v�Ƃ���ꂽ�@���A�O��͐{�k������邱�ƂȂ��A�ȐS���̊ҖŖ�ɂ����܂�ׂ����̂ł���B�킴�킴�ȐS�̖@��𗬓]��Ɉ�������o���A���y�𗬓]��̓��{���y�Ɍ��肵�č����̉��d�����ĂĂ���Z�̏�y�Ȃ炸���Ă܂����ł��Ă��܂��ł��낤�B���������ł��@�c�̎O��̖@��͓��{���y�ł͂Ȃ������y�ɂ��Ă��Ă���̂ł���B�����ĕ����y�Ƃ͈�̉����Ɍ������邩�Ƃ�����
�@�@�u�Ⴕ�S����Ύ��߁A����S����Α����O�����v
�@�@�u���@�͌ȐS�Ɏ��܂�Ĉ�o���������v
�@�@�u�䓙���q�y�Ɍ�ւǂ��S�͗�R�ɏZ�ׂ���ʂ����Ă͂Ȃɂ�����S������Ɍ�ցv
�@�Ə��䏑�ɋ��̔@���A�O���̌ȐS�̏�ɐM�̈ꎚ���Ȃ��Č��������̂ł���A���݂��܂��ɍl�����Ă��錻���Љ�Ƀ��[�g�s�A�����o����悤�ȋY�_�͏@�c�̋����ɂ͂Ȃ��ϑz�ł���B�悭�ȐS�̖@���]���ĊϔO�_���Ƃ����l�����邪�A����͑吹�l�̖@����ϔO�_���Ƙ_��Ă���ɂ����Ȃ��B�ڂɌ�������̂����M���Ȃ��B���_�҂��猩��A�@�c�̖@����������݂ȊϔO�_�E�B�S�_�Ƃ������ƂɂȂ낤�B�u�S������Ȃ�v�Ƃ̏@�c�̌䖭�����Ȃ�Ɣq����̂ł��낤�B���̂悤�ȕs�M�̂��̂́A�����A���������ϔO�����A�{���̑O�ɊϔO����̂���߂邪�悩�낤�B�܂��A���M�u��w��̉������ݕ��ȍL�闬�z�ςƗL�t�⊰�t��������ȐS�̍L�闬�z�ƁA�ǂ��炪�����ɑ����Ă���A�ǂ��炪�ϑz�̗V�Y�ɑ��Ă��邩�A�čl����܂ł��Ȃ��B�ǂ������������������Ă��A
�@�u�������}���Ȃ炳���A�J����ӂ����i�����j�l�@���ɕs�V�s���̗�����v�Ƃ́A�������E�ɋN�肤�錻�ۂł͂Ȃ��A�M�҂̐M�S�̐��E������킵�Ă���B
�@�����̂��Ƃ��l������ŁA�b��{�ɖ߂��A�u���@�v�Ƃ����Ă��A���q����Ƃ��������̐��E�ɐ��g�̐l�ԂƂ��Ď��ԓI�ɂ���ԓI�ɐ��ꂽ�L���I���݂Ƃ��Ă̓��@�吹�l�ƁA����̐�����Ȃ��{���I���݂Ƃ��Ă̓��@�吹�l�����邱�Ƃ��킩��B������l�̖{���ς����R�{���I���݁A�܂茳������p�g�̕ӂ�c���āA���Ă�ꂽ���̂ł���B
�@�ߔN�̖{���ς̌�T�́A�v�@�����C���Ƃ���������̂ŁA���傤�ǖ��@�������ɂ����������l�̔j�܂ɂ�����B���Ȃ킿���C�̖₢�́A
�@�u�Ⴕ�@�c���Ȃ��Ė{���Ƃ��A���E�Ɏ߉ޑ�������u���A��s���e�m�ƈׂ�ׂ��Ȃ�A�Ⴕ����Ζ����̖}�m���Ȃ��Ē����Ɉ��u�����E�͐g�F���F�̕���F�Ȃ���]�]�v
�Ƃ������̂ŁA�l�ԓ��@���{���ɂȂ�Ȃ�A���̘e�m�����F�̎߉ޑ���ł͂��������ł͂Ȃ����Ƌ^����N���Ă���B����ɑ��Ċ��t��
�u�䑊�`�ɁA�{��̋���ߑ��Ƃ͘@�c���l�̌䎖�Ȃ�Ɖ]���́A���̍��̕��̈ӂ͎���p�g����O�O����߂��邪�̂Ȃ�A�N���@�c�̍��E�Ɏ߉ށE��������u���ƌ�����v
�Ɣ��l����Ă���B���Ȃ킿�A���Ƃ͊��q�̓��@�̌�����錳������p�g�������Ė{���Ƃ���̂ł���A�N�����q���@���̂��̂��������ɖ{���Ƃ���Ƃ����܂������A�Ɠ��C�̋���ނ����Ă���B�X�ɑ�����
�@�@�u���C�@�����A�����}�v�̕ӂ������āA�{�n����p�g�̕ӂ�}�~�����v
�@�@�u���C�A�F���Ɏ����Đ^���̑z���𐬂��v
�@�@�u�@�@���]���A��l�̐��`�ɈႤ���Ɛ̂������قȂ炸�A�R��Α������҂̏K���O���̂M��œ��q���M�܂��v
�Əq�ׂ��āA���Ƃł͓��@�吹�l�̓�����{�n�̕ӂ������Ă̂ݖ{���E�{���Ƃ����Ǝw�삳��Ă���B
�@���юt�́u���ł���䶔��ɕt�����悤�ȕ����ǂ����ċv���̖{���Ȃ���̂��ƌ������ƂɂȂ�͂��Ȃ����v�Ƒi�����Ă��邪�A�{�������ł���䶔��ɂӂ���ď��ł��Ă��܂��̂ł��낤���B�S���A���юt�͕Е��ł͔{�������ł��Ȃ��ƌ�������A�O����Z�̂͂��̖{����䶔��ɂӂ����Ƃ�������A�����̋ɂ݂Ƃ����ق��͂Ȃ��B
�@�{���E�{���Ƃ��ɏ��ł����������݂ł��邱�Ƃ��܂��������ׂ��ł��낤�B���Ƃ��Ɠ��Ƃ�䶔��ɕt����銙�q�̑��g���@�ɂ��Ă͖{���Ƃ���Ȃ��̂ł���B�����Ƃ��A���юt�̏ꍇ�͑��g�̓��@�Ɏ�������肩��������p�g��ے肳��Ă���̂�����A�����Ƃ��������悤���Ȃ��B�v�ې�t�̘_����j���ɂ������āA���Ƃ����낤�ɑ��߂Ɂw�����̕���q�܂Ȃ���Ό����Ȃ��Ƃ̊ϔO�_��j���x�Ƃ̕\����f���Ă���̂�����ł���B�䂪����^���ĉ��x���ǂݕԂ��Ă݂����A�m���ɂ���������Ă���B��������p�g�̔ے�́A���̂܂ܖ{���̔ے�ł���B���S������O�ɁA�{����ے肵���_�����A���w�����̂��n�t���ŏ@���@���甭�s���ꂽ�ƂȂ�A�����ɂ͉����[���Ӗ��ł�����̂��낤���B�@�|�����ς��Ė{���s�݂ł͎��S�����̈Ӌ`������܂����A������l���J�R�Ƌ��K�v���A���͂〈���o���Â炢�̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���ɁA���юt�̘_�ɖ���������̂́A�����̂��Ȃ����Ȗ�����s���̂悳�����Ȗ@��v��������ď�肫�낤�Ƃ���Ƃ���ɂ���̂ł͂Ȃ����ƍl����B�u�l�@�̈�v��u�v�������@�v�͂��̓T�^�ł��낤�B�ڂ����͎��͂ɏ��邪�A�l�@�̈�̌���A���]�ɂł����q���@�ƐF���ɏo�����d�{���i��䶗��j���̈�Ȃ̂ł͂Ȃ��A��������p�g�ƐF���ɂ�����Ȃ��鑠���̉��d�{���̕ӂ������Ă̂ݐl�@�̈�Ƃ�����̂ł���B���]��ɂ͐l�@�̏����邱�Ƃ́A���t�̘Z�����Ɉς����������Ƃ���ł���A�܂���юt�̐����Ƃ���ɐl�@�̈�͐��藧���Ȃ��B
�@�܂��Ă⌻���́A�l�@�̐l�Ɋю�����Ă͂߂�悤�ȁA���]���������͂ݏo�������E�ł͐l�@����͓V�n�̔@���ł���B
�@�@�u��{���������̂Ɋ�{�I掖@�͂Ȃ��v
�@�@�u�������A���̎w��ɋt�����̂�掖@���v
�ܘ_�A���Ƃ̐l�@�ł͂Ȃ����A�������ĂƂ肠����A�l�@�̏��炩�ł͂Ȃ��낤���B
�@�Ƃɂ������ɂ��A���]�Ƃ������̂́A�Ƃ߂ǂ��Ȃ��։���̂ŁA���ɂȂ�Ȃ�قlj���ɂȂ�B���Ƃ��Ɨ��]��̋v�������̎ߑ���{���Ƃ���g���⑼��ƂȂǂ́A����Ȃ�̃u���[�L����������ł��ƂɗՂ�ł���悤�����A���Ƃ̂悤�ɕ��ꂪ�Ƃ͈���ԈႦ�ČȐS���������A���݂̂悤�ɐ������⌠�͏W���̐ꉡ���������ʂ邱�ƂɂȂ�B�n���w��r�c���_�Ƃ��āA����A�{�����ƑQ�X��a���ɂ�����܂ŁA�X�P�[���������������r�c���ɂ���ĉ^�c�i����̎x�z�j����Ă���̂́A���@�傪�e���������Ɋe�������e���̌��Ђ��J�T�ɂ��āA�M�k��ꑮ�����Ă���̂ɂ悭���Ă���B��͂�A������{���ς�����������̂ł��낤���B���c���W�t�́u���t�ɋA�˂���M�S�v���͂��߂Ƃ��āA������������@�����̖e���ւ̗�]�A�A�˂́A���Ĕނ̕��������Y�����u�t�ւ̋A���v��M�����ꂽ���ƂƉ����ς�Ƃ��낪�Ȃ��B�����A���Ƃ̋����͂܂�Ƃ���e���{���ŁA���M�o���^�����e���{�����痣�ꂽ���玄�͉^������߂��Ƃ������l���������A�@�n�̏�w�����͈�̂ŁA�������E�Ɗ����ƐE�Ƒm�����e�ʂɑ��{���Ɩe���{���́h���M�̂����߁h�������Ă���̂�����A���M�ȐM�k�͂��܂������̂ł͂Ȃ��B
�u�v���̖{���v�̌�́A�ȑO���t��́w�R���L�u�̌�p���w�ɓ����x�ɂāA�����Ǝ����̍��ق�s���Ăɂ�����ł���Ƙ_�����B�����ł͏d��������邽�߁A�v�������̖{���Ƃ��Ĉ������B�������Ȃ���A�����Ǝ����̍��ق͈ˑR�Ƃ��č��G����Ă���悤�Ȃ̂ŁA�ǁX�_���y�Ԃ��̂Ǝv���B
�@
�@
�����E���ј_���̒t����j���i�U�j
�@
�@
�@
�@�x�m�w�т̍ہu�ȐS�̖@��ȂǂƁA���������Ȃ��Ƃ�������������v�Ɠ�����l������ꂽ�����ł���B���������t������炵���b�����ꂽ���������A�����ɂ͖ʂƌ����Ĉꌾ���Ȃ��A�~�ނȂ���ʁA���ċy�ы��w�������ɍ��t��́u�咣���тɗv�����v����e�ؖ��ɂ��Ē�o�����B�i������\�O���{�R���j
���̖����̉ӏ���
�@�P�C���t��s�́w���̖@��ɂ��āx�@�w�R���L�u�̌�p���w�ɓ����x�@�w�������ј_���̒t����j���x�ɂ��āA�@�����Njy�ы��w���̉��Ȃ����ׂ��̎��B
�@�P�C����@���ɂ݂���ю�{�����A���Ƃ̏@�`�Ƃ��ĔF�߂�̂��ۂ��̉��Ȃ����ׂ��̎�
�@�P�C�v�ې�t���˂ɂ��āA�@�����ǂ̋��w�̕s���Ȃ�_�A����ɂ���ċN�鏊�̏������R�̞B���Ȃ�_�A�X�ɏ����Ɏ���o�߂�����ȍs���@�ւƂ��Ă̓K���������_�ɂ����ē��t�̏�����P�ׂ����B
�̎O�_�������A�@���@�̉��܂��Ă��邪�A���܂��ɉ��̉��������Ȃ��B�����Ƃ�������H���������i�߂�ɂ́A��������ׂ��̎���ł��Ȃ��A�u���ق͋��v�Ƃ���ɂ��܂��Ă���̂�������Ȃ��B�������A����҂̂��Ȃ��Ƃ���ŁA������肭�����Ă݂Ă��A���̉��i���̂悤�Ȃ��̂ŁA�Ƒ��Ȋ����͂ǂ����Ă��@���Ȃ��B
�@�܂��u�ȐS�̖@��v�������̂�����B����͂Ȃɂ����t��̐V���ł��Ȃ���Ύא��ł��Ȃ��A�吹�l�䌚���̖@��ł���A�ϐS�{�������͂��߂Ƃ��鏔�䏑����Ɍ�������Δ@���ɂ�����Ă���B���t�̕��i���A�Z�������܂��R��ł���B������̖\����f���Ȃ�A�܂����t��_��A�吹�l��j�܂��Ă���A���t��ւ܂���Ă�����Ă��x���͂���܂��B�����u�ȐS�̖@��v������Ȃ��̂ł���A�������������K�v���Ȃ����A���łɎ��̖@������������Ȃ��B���d�{���������đ���ɏG���ł邱�Ƃ����������낤�B�@�c�����̊ϐS�̖{���Ƃ���ꂽ���A���̏\�E��̙�䶗��������Ė{���Ƃ��ꂽ���čl�̕K�v������B�g���h�̂悤�ɋv�������ɏ@�|�����āA�ꑸ�l�m��{���Ƃ���@�h�Ȃ�Ƃ������A���Ƃ͂����ƊȂ�ŁA����ɏ@�|�����Ă�̂ł���B�\�E��̙�䶗��{���́A�܂�ȐS�ɂ��Ă���{����}�����ꂽ�̂ł���A�ȐS�������A���Ƃ̖@��̍j�i���������ƂɂȂ낤�B
�@�ϐS�{�����`���Ɏ~�ϑ�܂̈�O�O��̕���������Ă���̂��A���R�ƌ��߂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�u���O��݈�O�S�B�ᖳ�S���߁B��L�S����O��B�T�����ȏ̈וs�v�c���B�Ӎ݉������]�]�v
�u�̏����]���ȐS�����s�@��B�ǗL�Ȗ�v
�@���̈�O�O��̕����ϐS�̖{���̈˕��ł���A��O�O��@�傪�u�ȐS�̖@��v�ł��邱�Ƃ͘_����܂ł��Ȃ��B
�@���t�͂���i����
�u�ϐS���]���O��݈�O�S���ҁA����O�O��{���S���ݗ]���O�A�A�݉䓙�O���M�S�B���̉]���O��݈�O�S��A�ᖳ�M�S�s���O�O��{���̉]�ᖳ�S���ߖ�A�i�����j�@�c�����A����{�����M�S������v
�Ɛ�����Ă���B�ꌾ�̐����̗]�n���Ȃ��������̖{���ςƂ͑S������Ă���B�@�c�⊰�t�͋��ɓI�ɂ͖{���͗]���ɋ��߂���̂ł͂Ȃ��A�O���̐M�S�̒��ɂ���Ǝ�����Ă���B�܂藬�]��̑��̐��E�ōl�����Ă����{�����A�ҖŖ�ɐ؊������A�䂪�g�ɂЂ����Ă�ꂽ���A�͂��߂ē��Ƃ̖{�����������Ƃ����̂ł���B�{����
�@�@�u���@���g�ɓ��ĂĈ���̑厖�v
�@�@�u�{���Ƃ͖@�،o�̍s�҂̈�g�̓��̂Ȃ�v
�@�@�u�������g�Ɉ��ċ����v
�Ƃ���ꂽ�̂��A���]�i���j����ҖŁi���j�̐؊���������킵�A�O���̌ȐS�̏�ɐM���Ȃ��Đ�������{���𖾂�����Ă���B�܂蓖�Ƃł͌ȐS�ɖ@�̂̎����߂���ŁA�X�ɐM�s�M�������Ď��s������킵�Ă���B���ꂪ�u�������ɍs����v�Ƃ����鏊�Ȃł���A���̖@��Ƃ́u�ȐS�̖@��v�ٖ̈��ł���B
�@���ј_���ł́A���s�������܂Ō����̍s�ׁA���ۂɎ������āA��ڂ���������Ƃ��A�{���������ɏ������킷�Ƃ��̓V��̎����Ɋׂ����L�q���݂�ꂽ���A����Ƃ̎����ƍ�������̂͊ԈႢ�ł���B������������A���t�͖{�����̍u�`�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�ɉ]���Ă���B
�@�u�T�e���s�ғV��@���@���\��ώ��s�\�̑薭�@�����̎��s�]��A�����C�`�s��A�������s�]�v����������p��g�@�c�F�S�S�[���]��A�����{���s�����̉]���s��A���@�̎���A�s����A�̎��s�]��A���S����������쐔�s���{���������̔�]���s�@�[���X�s�̎���O�O��{���]�������A����C�@�]���s�@�[�����s�̎��]�ԓV�䏟�@�c���s��]�V�v
�@�|���Ĕ��юt�́u�v�ې���ɂ��A���ɂ̌�{���͖}��Ɏʂ�ʑ吹�l�̍���q�ނ̂��ƌ����B����ł͖@�E�̗��̏�̖@���ɂƂ����ϔO�_�ł����āA���ꎖ�����ɍs���镶��ƈ�{�厖�̈�O�O��̕��@�Ƃ͌������Ȃ��v�Əq�ׂ��Ă��邩��A�S�����C���Ƃ�������̂����A�c�O�Ȃ��ƂɁA����͈�l���юt�̐��Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�ߔN�Ă��@�����������āA�@��l�̑��������s�̖@���������Ă���B���Ȃ킿�A�V��ʓr�̎�������d�����������Ƃ���ɓ��Ƃł����@�̂̎����������邱�Ƃ̕��ʂ����Ă��Ȃ��̂ł���B���t��ł́A��Ɂw���̖@��ɂ��āx��_�������A����������p���āA���Ƃ̖@�̂̎����ɂ��Đ������Ă݂����B
�i�ȉ��w���̖@��ɂ��āx�j
�@�@�̂̎����̑���Ƃ͉��ł���̂��A�܂����̖@��Ƃ͉��ł���̂��B������l���u�l�Ɍ������Đ������v�ƈꉞ�邳�ꂽ���𖾂炩�ɂ��Ă����Ƃ���ɁA�����̖@���̋�������������J�M������̂ł���B
�@���L��l�͗L�t�k��������
�u�y���Ď��Ɖ]�З��Ɖ]�Ћ��҂Ɖ]�Вq�҂Ɖ]�Вf�f�Ɖ]�Ж��f�f�Ɖ]�Ж{�Ɖ]�Ѝ��Ɖ]�Ѝݐ��Ɖ]�ЖŌ�Ɖ]�ӁA�����瑖�Ɖ]�͂Η��Ȃ�q�҂Ȃ��Ȃ�P�Ȃ�A�\�����ɍ����̔@�����@�����͖{��̎��Ȃ�A�R��Ԏ����̉��V�̏�ɏ@�|�𗧂�@�Ȃ�A����Ԏ��Ȃ���҂Ȃ�{��Ȃ�v
�u���Ė��@�����͈��S�݂̂ɂ��đP�S�Ȃ��t�틤�ɎO�ŋ����̖}�v�̎t�푊���āA���]�O�Ȃ����@�@�،o�����鏈�g�����Ƃ���������Ƃ��]�͂��Ȃ�v
�u�R��ΏC��~���̖{�����̏��ɓ��@�͏@�|����������Ȃ�A�͂⊴��~�ʂ̏��͊O�p��瑂Ȃ�q�҂Ȃ藝�Ȃ�S�����@�̏@�|�ɔ��Ȃ�v
�Əq�ׂ��Ă���B�����}������ƁB
�@�@�@�k�����l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�k����l
�����ҁE���S�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���q�ҁE�P�S
�����f�f�E�t�틤�ɎO�ŋ����@�@�@�@ �@�@�@ ���f�f
���{�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���
���Ō�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���ݐ�
�����ؖ{�n�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@���O�p���
�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���̐}�̎����Ƃ���A�ꌩ���Ď����Ƃ́A���f�f�E���ҁE�t��Ƃ��ɎO�ŋ����ƁA�O���}�v�̏�ŕ������_�����鐢�E�������A����̐��E�́A�f�f�E�q�ҁE�����镧�E�q�҂̐��E��\���Ă��邱�Ƃ�����B�����āA���̖}�v�O���̑����A�{�n���E�Ō��{�ł���A���̑����A�O�p��瑁E�ݐ��E瑂ł���Ƃ��Ă���̂ł���B
�@���̂��Ƃ́A�吹�l�̏��@��������
�@�u�}�v�͑̂̎O�g�ɂ��Ė{���������B���͗p�̎O�g�ɂ���瑕��Ȃ�B�R��Ύ߉ޕ��͉䓙�O���̂��߂ɂ͎�t�e�̎O��������ӂƎv�Ђ��ɁA���ɂĂ͌�͂��A�Ԃ��ĕ��ɎO�������Ԃ点���͖}�v�Ȃ�v
�Ƃ��������t�B�܂��O���@����������
�@�u���̈�O�O��͖����̎��Ȃ�A���͖̌̂Ϗ�̏\�E���{�L����̊o�̂Ɖ]�ӂȂ�A����̎��̊O�Ɋo��̎������҂Ȃ�A�V���Ȃ��Ĕނ��v�ӂɁA�V��`�����O�ނ鏊�̎��̈�O�O��͌咆�̎����ɖ̂ɗ��ɑ�����Ȃ�ׂ��v
���̌䕶��q����ƍX�ɂ悭�����ł���̂ł���B�����Ō��������̖}�v�Ƃ́A瑕��E�{�ʖ��ɑ���{���E�{�������w���̂ł����āA���R�ߑ������̒��ł̗����C�s�r��̖}�v�Ƃ͈قȂ�B���@�������̌䕶�́A���̖{�����̖}�v��������̎O�g�ɂ��Ė{���ƌ����A�v���E�v�̕���瑕��Ɛ�����Ă���̂ł���B���̖}�v���{���ŕ���瑕��Ȃ̂��Ƃ����A�m���ɖ{�ʑ��Ԑ����̎ߑ��͏O���̂��߂ɎO���������čϓx����Ă������A���̎ߑ��̌��̍��{��q�˂�A����͐X�����@���Ȃ킿��؏O�����̂��̂Ȃ̂ł���B�ߑ��͉�疢�f�f�̈�؏O����@���Ɍ��Č����킯�ł��邩��A�u�Ԃ��ĕ��ɎO�������Ԃ点���͖}�v�Ȃ�v�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B
�@�]���Ė{�ʂ̕����Ɩ{���̕��@�Ƃ̑���͎ߑ��̌��𒆐S�Ƃ��������ƁA�ߑ�����炵�߂��}�v�i�@�j�𒆐S�Ƃ��������Ƃ̑���ł���A�@�̂̎����i�����Ɨ���j�ɖΏO���̕ӂɗ����Č������ꂽ���@�ƁA���̕ӂɗ����Č������ꂽ�����Ƃ̑�������킵�Ă���̂ł���B�����̂Ƃ���ɖ@����������铖�Ƃ́A����̕������M�������A�F�������̕����i�O�����S�j�Ƃ��đނ����A�t��Ƃ��ɖ��f�f�̈�؏O���̐��E�����^�̑̂ɂ��Ė���O�g�ł���Ƃ��āA�����ɐ^���̕��@�̎p���Ƃ炦�Ă����̂ł���B�i�ȏ�w���̖@��ɂ��āx���j
�@�_�q�̂Ƃ���A�@�c�͖��O���@��W�Ԃ���ׂɁA�]���̐F������r���ę�䶗��{�������������̂ł���B���ꂪ�ׂɁA�@�c�͏����Ɂu���Ō����S��\�]�N���]�L�̑��䶗��v�Ƌ��ɂȂ�ꂽ�̂ł����āA�u�����]���Ă܂��܂����v�Ƃ́A�M���������疯�O���@�ւ̎��߂̓]���ł���B
�@���ɏ\�E��䶗��́A�����̎����Ɏ����A�F���ԋ������q��Ŕj���A�ȐS����ɏؓ�����{�������킳�ׂ̂��̂����A���ꂪ�������\�N���A�F���̕����ȏ�ɋ����I�ɐ��q����Ă��邱�Ƃ́A���ɕs�v�c�Ȍ��ۂƂ���˂Ȃ�Ȃ��B
�@������A�킩��Ղ����������A���t�͖{�������i�ɁA
�@�@�u�▭�@�@�،o���E������������F���^�F��������������F���L���ٖ�v
�Ɩ₢��݂��A���̓�����
�@�@�u��{�E�v�A�V�n�_�D��A��������������F���{�n���ؖ��@����{�L�̓���A�i�����j�F��������������F��瑒������`����v
�Ƃ���Ă���B���@���̍��E�ɕ����������ĕ���F�����킷�̂ƁA�F���̕���F�������Č��킷�̂ł́A�ǂ��Ӗ����ق邩�̐ݖ�ɑ��āA�����͖���{�L�̑̓�������킵�A�F���̑����͍��������̌`���Ɏ����邱�ƂɂȂ�ƍ��ق�������Ă���B�܂�A����͖{���������̂Ȃ�����̑̓��i�ȐS�̐��E�j�����킷�ׂɂ́A�`�������������K���ł���Ƃ����̂ł���A�����ɂ��\�E��䶗��͌ȐS����E�ϐS�̖{������������ׂ̕K�R���N���Ă���B�̂ɉ�X�̖}��Ɏʂ��䶗��E�����̙�䶗��͉��Ɏ����ɊČ��킳�ꂽ�Ɣq���ׂ��ł����āA���y���O���Ɂ@�u�O�����`��s���A�R����@�فv�Ƃ����Ă���B�F���鏊�A���̎O���͋�Ɍ`�̂Ȃ����̂ł����āA���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�̂ɉ��Ɏ��Ɋĕق���Ƃ����̂ł���B
�@����̕��i�ɁA�u����̈���v��m���Ă͂��߂ĕ���Ƃ�����Ƃ���悤�ɁA�����̙�䶗������t���̌ȐS�����̖{���������āA���߂Ė{���Ƃ�����̂ł���A���t���i����j�������Ă��܂��A���R�ɕ���E�O���ɏo�Ă��܂��A�ϐS�̖{���Ƃ��A����[��Ƃ������Ȃ��Ȃ�B
�@�l����l������A��Ύ��̖@����k���ɂł��Ă���B��{�����A�@�|�̍��{�͂����܂ň�腕��^�̉��d�{���ł���A���̖{���͈�@�ꉏ�ƌĂ����̂ŁA�@�����Ƃ���������̂ł���B���@��ƒ�ɂ����@�ꉏ�̙�䶗�����X�́A�����ɔq���邱�Ƃ��ł���A�܂蒼�q���Ă���B�������A����́A���ׂĉ��d�{���̎ʂ��ł���Ƃ����A������A���d�̖{���͂ƁA������q�ʂ�Εɔ鑠����Ă���A��X�̓���ɐG�ꂦ�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���B�܂�y�q���邩�������Ƃ��Ă���B�@�����͈�@�ꉏ�̙�䶗��ɑ����āA�ۉ��Ȃ��{�ʂ̏C�s�̗�����Ƃ��Ă��邪�A�@�|���͉��d�{�����鑠����Ă��邱�Ƃɂ���āA�{���C�s������킳��Ă���B����͎��R�ɏ@��������@�|���؊������Ȃ���Ă���̂ł���A����ɂ���ď@�����������Ă���̂ł���B���Ȃ킿�A�@�����ł͍s�҂Ƒ����Ă����{�����A�@�|���ł͎��́A�s�҂̊O�ɂ�����̂ł͂Ȃ��A�M���Ȃ��ę��߂ɌȐS�̂����ɏؓ������Ɛ������̂ł���B�����̂��Ƃ́A�@�c�̓����`���A�y�ъ��t�̕��i�A�Z�����ɐ[�`����������Ă��邪�A�u�ȐS�]�X�v�Ƃ��̂�������A�Ŕ������X�ɂ́A���̂܂��ɊϐS�{��������ǂ���邱�Ƃ��]�܂����Ǝv����B
�@�܂��A��s���`�O���@�����ɂ��āA�����̂悤�ȕs���ĂȂ��̂����p����͕̂s�s�����Ɣ������������悤�����A����͓��Ƃ̖@��̉����邩��m��ʈׂɋN�钿���ł���B���̎O���@�����́A�\����������肠����A�������Ƃɂ����`���@��ł͂Ȃ��B���N�剺�A�������͔��i�嗬�ɂ��{���Ɠ�����e�̋L�^��`���Ă���B���e����݂Ă��A�\���͓`���̎R�Ɗw�����̉���d�A�����Ő_�͕i�̋����ɎO���@�̈˕������߂����̂ŁA���̂܂܂ł́A���ƂƂ��đՂ��Â炢�̂ł͂���܂����B�\���𗝁i����j�A���������i����j�Ƃ��āA�͂��߂ĎO���@�����͓��Ƃ̖@��̍j�i�ɂ̂��Ă���̂ł���A�X�ɂ́A�w�����̉���d��{�@�A�_�͕i�̈˕��𗬓]��A�����̉���d���ҖŖ�Ɣz����悤�ł���B���ɗ����͓��Ɠƕ��̖@��ŁA�����̎����A�咆�̎����A�Ɩ@�̂̎���������킵�A��g����������ċ̓��ւ��������Ă���B���t���A���̍j�i�ɂ����Ĉˋ`��������
�@�@�u�O���@�����ɉ]���i�����j�A�����ɉ]���i�����j�B
�@�����ɉ]���i�����j�邷�ׂ��邷�ׂ��v
�ƓW�J����Ă���B
�@�Ƃɂ����A���`���̗ނ́A���������Ă��邩��g���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�悭���e���ᖡ����������S���āA�g��Ȃ���Α��Ƃƍ��G���邱�ƂɂȂ낤�B���юt�������̕\�������p����Ă��邪�A��͂�u�����Ă��邩��g���v�̌��ŁA�w��ǕK�R���̂Ȃ��Ƃ���ŁA�������R�ƂЂ���Ă���B������x�A�����̕\������̑��`���Ƃ��čl�����邱�Ƃ��A���Ȃ������ʂɂ͂Ȃ�܂��Ǝv����B
�@��ӑ����ɂ��ẮA���łɖ@��I���߂����݂����A���Ƃɓ`���Y���L�E�O�t�`�E�{��O�ʎ��E�����Տ��X���E�{���������`�E�L�t�����E���V�����́A�����w�̘�ɂ̂��ĉ]�X����܂��ɁA��̂����̈�X������`����Ƃ����̂��A���e��@��I�ɐ[���T������K�v������B�����ɂ͐g�����̑��Ƃɂ͓`���Ȃ�������ʂ̖@�傪�����Ă���̂�����B
�@
�@
�@
��m��������O�Ӕ�@�o�����R��A�v�m�^�s�m��A�_�D�������A��s�m�Ŗ@���Ŗ@�������@��A�@�����m���ȘŖ@�דn������m�Ŗ@�����@���Ŗ@��A�[�����@�����Ŗ@�����ꌾ�����Ɠ��F�����@����A��s�@�m�@�،o���@�@�ؒA�����O�o�@�i�����j��s�m��������ꓭ���n�E�@�@����k�k�O�Ӕ�@����A��m������@�n�E�����B�����@��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���������\��l�l�j
�@
�@
�����E���ј_���̒t����j���i7�j
�a�����o�E���@�����܂��Г��ɂ���
�@���юt�̘_����j�܂���ɂ������āA����ǂ��āA���X��X�̐����_���邱�Ƃ͍���ł���B����͎t�̘_�����A�����̉ӏ������Ŕޏ�����ł���Ǝw�E�ł��Ȃ����A�S�̓I�Ȏv�z��Ղɑ傫�ȐS���Ⴂ�����Ă��邩��ł���B�ЂƂ��ƂŌ����A�{���̏@�|�Ɖ]���Ȃ���A���͒m��Ȃ������ɖ{�ʓI�Ȃ��̂ɏ@�|�𗧂ĂĂ��܂��Ă���̂ł���B�̂Ɍ䏑�E���`���E�Z�������̑���������̈��p�����A�قƂ�LjӖ����Ȃ��ĂȂ����肩�A�������Ę_���S�̂ɔj�]�������炷�����ɂȂ��Ă���B
�Ⴆ�A
�u��S�͖��@�̑��̂Ȃ葍�̂͑�ڂ̌��Ȃ�v
�u����s�����A����s����A����s���d�A�O�w��ɓ`����𖼂��Ė��@�Ɠ����v
�u���F�\�E�A�O��A�ː��������Ȃւ��Ɖ]�����Ȃ��A�T�������ɉ]�����ɂ��ɂ����镧�Ȃ�]�]�B���̈ӂ͑��ɂ����苋�ւ���ʕi�̎ߑ��Ȃ�A�o�ɉ]���@���閧�_�ʔV�͉]�]�v
�u�����[�`�̈ӂɉ]���{����ʕ���̋���ߑ���{���ƈׂ��ׂ��A���ꑥ�������}�v�̓��̖{�����̋���ߑ��Ȃ�A���d��ږ����Ȃ�B�����{����ʕ���̉��d�{����ʕ���̑�ڂȂ�A�̂ɊJ�ڏ��ɖ{����ʕ���钾�Ɖ]���͐���Ȃ�v
�@���̌䕶�́A�t�̘_�|�ɂ͕s�K���ȁA���p���ׂ��ł͂Ȃ��䕶�ł���A�S���Ⴂ�������Ă��Ȃ���A�ނ���ȐS�̖@��̈ˋ��ƂȂ���̂ł���B�܂����̈��p���̑������A��p��d���ɏI�n���A�����̏���̂悤�Ȃ��̂���蕥���A�t�̘_���͉�����͂���͂܂ŏڐ������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�[�I�Ɍ䗘�v��`�̋������q�Ƃ�����邱�Ƃ͐悸�ԈႢ�Ȃ��Ƃ���ł���B
�@����͍ŏI��Ƃ������Ƃ������āA�����Ȃ��t�̒n�̕�����A�O�ً̈`���ȒP�Ɏw�E���邱�Ƃɂ��āA�܂Ƃ߂Ɉڂ肽���B
�@�悸���߂́A
�@�u�����{���̕����a�����o�̑厜�߂̂��ƂɁA���ԏo���̕��A���@����̕��Ƃ��Č�o���V���ꂽ�ȏ�́v�Əq�ׂ��Ă��邱�Ƃł���B�a�����o�Ƃ́A���Ƃ��Ɖ��g�I�Ȕq�����ŁA�F���̉���������a�炰�Đo�ɓ�����̂ł���B�����{���̕��Ƃ́u����O�g�v�u�v�������̐U���v�ł���A����a�炰�邱�Ƃ��Ȃ��B���ԏo���̕��Ƃ����\�������������B���Ԃ��{�����獡�ԏo������̂��낤���A����ł͓��@�吹�l�������{������̐�瑂ł��邱�Ƃ�ے�ł��Ȃ��ǂ��납�A�ϋɓI�ɐ�瑂��m�肵�Ă���B�����瑕��łȂ����ׂɁu����̈ӂɂ����ċv�������@�𗧂Ă�v����Ƃ����̂ł��낪�A����͏����ǂ��납�啪�����Ȃ̂ł͂���܂����B
�@���̂��̂悤�Ȗ������s�Ȃ��邩�Ƃ����A�v���������v�������Ɠ�����̎��Ԑ���ɂ����āA�����͎������y���̂ƋK�肷�邩��ł���B�g���h�Ƃ̘_���ł��A�����͖��n���I�����A���Ƃ̌����́A��������y���ޕ��̖��n���I�ł���Ƃ����A����͐��|���_�Ƃ������A�ނ��듖�Ƃɕ����Ȃ��悤�ł���B���̎咣�͌����Ǝ����̈Ⴂ�����̈Ⴂ�Ȃ̂��S�������ł��ĂȂ��Ƃ��납��N����̂ŁA�{�ʂ̉�������ɖ{�������Ă邩��{���Ƃ͖��ڂ���Ŏ��̂��Ȃ��A������̌����ɖ{�ʂ̕��i���m�ɂ͖{�ʂł͂Ȃ��A�̂ɐ�ɖ{�ʓI�Ȃ��̂ƋL�����j�𗧂Ă�悤�ȉH�ڂɊׂ��Ă���B�܂茻���̖{���_�͎ߑ������̂܂@�c�ɒu�����悤�ƍ�Ƃ��Ă���ɉ߂��Ȃ��B�������A�����ƌ�������������̎��Ԃ̌o�߂̒��ɍl���Ă��邩����A�ߑ��̋M�������Ə@�c�̖��O���@�Ƃ̗������͉i�v�ɂ��Ȃ����낤�B�����ƌ����Ƃ́A�{�ʂ̕��̑��̏��k���A�{���̏O���̑��̏��k���Ƃ������Ƃ��������t�Ȃ̂ł����āA�S������ė��ꏊ���قȂ邱�Ɩ������Ă���B�@�c���ЋŔ������
�u���όo�]�A��؏O����ًꎻ���@����l�ꓙ�]�]�B���@�]�A��؏O������ꎻ�����@��l��Ɛ\�X�ׂ��v
�@�Ɖ]���鏊�Ȃ������ɂ���A�ق̋�Ɠ���̋�͋M�������Ɩ��O�����̕�����ڂł���B�܂������u�ق̋�v�Ƃ͐F���̉����̘a�����o�̎p������킵�A���юt�̐��̔@���́A�����{���Ƃ����Ȃ�����A�ߑ������̔��S��������o�Ă��Ȃ����ɋC�t�����ɂ���̂ł���B
�@���ɁA
�@�@�u�u���@�����܂��Ёv�Ƃ́A�Ƃ���������A�v�������̎���p��g�@���̍��ł���v
�Ƃ����邱�Ƃɂ��āB
�@�@�u���@�����܂��Ёv�͋v�������̎���p��g�@�����̂��̂ł���A����p��g�@���̍��ł͂Ȃ��B����͉��㉮���˂��悤�Ȍ낿�ŁA��A�Ƃ��v�������A�S�̘̂_�����l����A��͂蕪�ʂ����Ă��Ȃ��̂ł��낤�B���Ƃł́u���@�����܂��Ёv��l�ɖΌ�������p�g�A�@�ɖΎ��̈�O�O��i�v���������@�j�Ƃ��Ă�̂ł���A�����ɐl�@��ӂ�����̂ł���B�����ł����юt�͊��q�̐l�ԓ��@�ƌ�������p�g�ɍ������݂���ׁA�u����p��g�@���̍��v�Ƃ����\���ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@���ɁA
�u�O���@�͂�������A���̖{���͋v�������̎���p����̖@�̂ɂ���̂ł���A�{���������Ȃ�Ζ{���������ł���A��ڂ����d���S�ċv�������ł���B�{���̋��q�s�ʂ͈�̂̂��̂ł���B�����ĕ���̈ӂɂ����āu�v�������@�v�𗧂Ă�̂��A���Ƃ̑��`�̕��@�ł���v
�@�Əq�ׂ��Ă��邱�Ƃɂ��āB
�@�������̃p�^�[���Ȃ̂����A���̈ӂ́A�����ȒP�ɂ����A�u�v�������@�v�Ȃ̂�����v���̘̐̂b�̓C�R�[���Ŗ��@�̍��̂��Ƃ��Ƃ����̂ł����āA���̎���̑����̂��錻�ې��E�ɐ�𗧂ĂĂ���̂ł���B�������A�����ȓǎ҂����łɂ��C�t���̂悤�ɁA���@�ɂ����R�����ɂ��Ă閖�@�Ƌt���ɂ��Ă閖�@�̑��Ⴊ������̂ł���B���Ȃ킿�A�ߑ������̐������Ə���ǂ����j��̖��@�ƖŌ�ȐS�̏�ɂ����@���@�ł������@�Ƃ̑���ł���B���m�̒ʂ�A�@�c�̖@��͊J����̔�瑌��{���������ɏ�������t���֓]������Ă���̂ł���A���@���A�{�����A��v���̖��@�Ȃǂ͖Ō�ȐS�ɂ��Ă��Ă��邱�Ƃ�m��˂Ȃ�Ȃ��B������u�v�������@�v������������߂��ς��Ă���̂ł���A���юt���k��Ɍ����m��ׂ̈ɖ�N�ɂȂ�O�ɁA�@��Ƃ��Ă̒T�����K�v�Ȃ��Ƃ�F�����đՂ������B���ɂ��̒i�̔��юt�́u����̈Ӂv�Ƃ��u���`�̕��@�v�Ƃ������Ă��邪�A���̎g�����ł͖�����ʂ�����A�܂��͉������Ӗ��̒ʂ��Ȃ����ׂ̈Ɂu����v��u���`�v�̌ꂪ����݂����ŁA���ꂱ��ł͑����[�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤���A�����C�p��������ɗ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�E��y�т܂Ƃ�
�@�@��700�N�̗��j�̒��ŁA��ǓI�ɂ݂āA�@��I�Ȋ�@����z���A���Ē������͂���ꂽ������2�x����B9�����L��l�̍��ƍ]�˒����̓��i��l�E������l�̍��ł���B
�@���L��l�͐������̓`���ɂ���Č�����Ă��邪�A���m�Ȏ����͂��܂��ɂ͂����肵�Ȃ��B�N�߂�90�L�]���s�m���Ȃ�A���q���S���Ȃ����Ƃ���̕s�v�c���B�悻���Ă��A�悻���Ă��s���Ȃ��ѓ�̂��Ƃ�A��Ύ��Ƒ吙�R��{�k�Ɉ����Ƃ����`���A��l���̂��ƁA���Ŏ^���̂Ȃ���{�����A���̑��ɂ�����]��`���A�����̉����������Ƃ��Ă���̂��A����`����Ƃ��Ă���̂��悭�͂킩��Ȃ��B�������Ă��鐔�����̕������������̗��������ꂸ�ɕ��u����Ă���Ƃ����̂�����ł���A��������ɓ��L��l�͈̑�Ȑl�ƍ��ɓ`�����Ă���݂̂ł���B
�@�����������ŁA���ڂ낰�Ȃ�����邱�Ƃ́A�L�t�̎����ɁA���łɎ�����ɂ�����炸�A�@��I�ȑ�ςȍ������P���Ă��Ă����Ƃ��������ł��낤�B���ꂪ�A���Ȃ苭��Ȃ��̂ł��������Ƃ͕����ɂ悭������Ă���B
���Ȃ킿�A
�u����Γ��嗬�ɌÂ͐ד���������������l�B�������L�肵���Ή��V�@�̋��Ɏ��瓾�ӋʂЂ��ԁA���l�̖@����ΔV��邷��B���͉��V�@�̋��ɖ����Ȃ�Ԕ邷���Ƃĉ]�͂���Ε��@�F�j�����A����ԍ����̔@�����R�ɐ\����]�]�v
�u����ɖ����ɐ����ւΖ@�E�̋@�ɂЂ���ē��@�������ɐ����B���̌̂͌Â����M�S�キ�����B���̏�掖@�߂̍������̊O�Ɋɂ�����s����B���ꑦ�����@�̖����Ɗo�����V���ɂȂ�Ɖ]�]�v
�@���ƋL����Ă���̂�����ł���B�ƒ������e�`�ɁA�L�t�̐��ɂ�����e�t���A�݉Ƃ̖����@�Ɍ������������]�]�Ƃ���̂��A�`���ׂ��l�ނ����Ȃ������Ƃ��������A�������Ђǂ��A��Ύ��@�傪�m���̏�Ԃɂ��������Ƃ�������Ă���悤�ȋC������B�����S�����L�t���A���̔ߎS�ȏ�Ԃ��A���ɗ����҂�A��Ύ��@��̋Ɉӂ�q�˂邱�Ƃɂ���Ė@��I���Ē������͂������̂ł���A���̎p���́A
�u�Ⴕ�����̖��ɂȂ�͍��c�̌䎞�V���A���@���ԂƂ��ɑ��Ⴗ�鎖���₠���Ƃē�����l�̌䎞�l�������Ɛ\�����������u�����ӊԉ䂩�\�������ɂ��炷�A���̎���s��\��B����k�̎�͑�X�̈ӊy�ӊy�Ɋe�X�Ɍ�����ԏ��̎����䑶�m�Ȃ���Ԉ���H���ɐ���s����Ɖ]�]�v
�@�̌䕶���悭����킵�Ă���Ƃ���ł���B������Α�Ύ��@��̋ɈӂƂ͉��ł��邩�Ƃ����A���V���A��������ɂ݂�A�t��q�̖@��A�����̖@��ł��邱�Ƃ͗e�Ղɗ����ł���B�܂��A���̋t���Ƃ��ē����̍������A�t��q�̖@��A�����̖@��̌���A�ώ��ɂ��N���Ă��邱�Ƃ������ł���B
�@�Ȃ��ɂ́u���V���͌Â��Č���ł͒ʗp���Ȃ����V������v�ƃA�b�T���؎̂Ă�l�����邪�A���́u���V���v�Ƃ�����͋ߔN�t���ꂽ���̂ŁA�{���͈�ʂ�́u���V�v��������ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�t��q�⎖���̖@����������ꂽ�@�发�Ƃ݂�ׂ��ł���B
�@�����Ă܂��A�{���̊e���╷���ɏq�ׂ���t��q�⎖���̖@��́A���݂ł͖��݂̂����Ď��������A�Ӗ����킩�炸�A�������Ќ��͂ɂ���ĉ�c��������Ă���A���ꂪ�܂��L�t�̎���Ɠ����悤�ɁA���݂̍����̍ő�v���ɂȂ��Ă���̂�����A��X�͎��̂Ƃ�����悭�v�҂��A��������ʂ����Ύ��@���������K�v������B���炭�A�L�t�ɂ܂��l�X�ȓ`�����A��Ύ��@��Ɩ����ł͂���܂��Ǝv���邪�A�⊶�Ȃ��猻��ł͖��m�ɋL���Ȃ��B
�@�Ƃ������A��X�ɂƂ��đ�Ȃ��Ƃ́A�L�t�̂����Ă��邱�Ƃ��u�䂩�\�����A���ɂ��炷�v�ŏ��̎����̖@���������A�t��q�̖@��������Ă���̂�����A�u���V���v��u�����v�̕s���������������������A�@�J���c�̎v�z�I��ՁA�����嗬�̏@���̊������ł������ɂ����Ƃ������҂������āA�O�O�Ɋw��C�s���邱�Ƃł��낤�B
�@24�����i��l�A26��������l�̎�����@��̍����A�����ĕ����Ƃ����_����A�L�t�̎���Ɠ����悤�ɐ����ł���B�L�t�̎���莑���������A����������Ă���̂ō����̓��e�����������m�ɂ���Ă���B
�@�c������15�����t���23���̌[�t�܂ŁA��Ύ��͗v�@�����牡����I�Ɋю���}���Ă������A9��100�N���̊Ԃɂ́A�{���̑�Ύ��@��͎���ɗv�@�����w�ɂ���ēh�肩�����Ă������B�ܘ_�A��Ύ��������̒�R���Ȃ��Ɉ��ՂƂ��Ă����킯�ł͂Ȃ��A����̐����Ƃ��āA����ނȂ��Ɏ������Ƃ����ׂ��ł��邪�A��͂�@��j�̂Ȃ��ł́A�Â�����ƌ��킴��Ȃ��B
�@���t�ւ̑������A��Ύ��y�O�ɂƂ��āA���܂�ǂ����ƂłȂ��������Ƃ́A�o���Ɉٗ�̌䑊������Ȃ���̂����݂��邱�Ƃɂ���Ă��m���B���t�̓o����A���ȓ˂��������������炵���A��肪���������N��l�Ȃ�A�ю�E�����肽���Ƃ����l�ȏ��t�̏��������B
�@�����̔@���A�s���Ȗ����܂�ŃX�^�[�g�����v�@������̊ю���A�t�A���t�Ƒ��������ɕx�T�Ȍo�ϗ͂���`���Ă��A����ɁA��Ύ��͗v�@���F�ɓh�肩�����Ă������B���t�̎��Ȃǂ́A��Ύ��@��͖��S�ɂ��v�@�����w�ɂ�������W���ꂽ�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B���ƌ×��̖@������āA�ю傪�����ɐF�����̑����ƈꕔ���u���咣�����̂ł���A���̎��̍����Ԃ�͖{���U�V�łɘ_�q�����Ƃ���ł���B���t�͑�Ύ��m���̔������A�ٗl�Ɍ����������������A���`�I�ɂ����X�_�������̂��邱�Ƃɂ���Ē����ɂƂ߂����A�������ɂ܂������A�ꈬ��̑m���͋������Ȃ������悤�ł���B
�@�������A�{�i�I�ɑ�Ύ��@�啜���̐�ڂ�����ꂽ�̂�24�����i��l�̍��Ǝv����B�i�t�ɂ͒��q���`���Ȃ��̂ŁA�@��I�Ȃ��Ƃ͍���N���ɂȂ�Ȃ����A�v�@��9��̗�オ�i�t�ɂ���ēr�ꂽ���ƁA�i�t���g���x�m���̏o�g�ł��邱�ƁA������l�̎t���ł��邱�ƂȂǂ́A��Ύ��@�啜���̐擱�����Ȃ��ꂽ�ł��낤���Ƃ��A���t����ɏ[���ł���B�����ĉi�t�Ō�A�t�̌O����������������l���Z������������킵�A�v�@�����w����|���A��Ύ��@���̌n�����ꂽ���Ƃ́A���m�̒ʂ�ł���B
�@��ʂɁD�Z������l�̖��@�������́A�L�����C�Δj�̏��Ƃ���Ă��邪�A���C�͊��t����200�N���O�̐l���ł���A����͓��C�l�ւ̔j�܂Ƃ������A�����@���ɖ������Ă��������E���u�_�`����C�̖���t���Ĕj�܂����Ɨ�������������ʂ�B
�@�܂��A�Z�����S�̂��A�������ΊO�I�Ȃ��̂Ƃ��Ĕc����ꂪ���ł��邪�A���͏@���̖@��I�������꒩�̂��Ƃɉ������ׂɏq���ꂽ�̂ł���A���̏���
�u����͐�����ɗߖ@�v�Z�ׂ̈Ȃ�A���퓙�[���Ⴊ�ӂ��@�ɂ���]�]�v
�@�̌䕶��[�����@���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����Ƃ��A�Z�����̈З͂͏@���̗v�@�����w����|����݂̂Ȃ炸�A����ɁA���s�v�@���̖{���ɂ��e�����A���̗v�@���ю���_�������I�Ȗ@�߂��āA��Ύ��֓]������Ƃ��閖���������Ƃ߂˂Ȃ�ʒ��ɂȂ����̂ł���A�����ɑ�Ύ��Ɨv�@���Ƃ̑吨�͑S���t�]����Ɏ������B����́A�܂������A�@��̑�����㐢�̉�X�ɋ������ꂽ���̂Ƃ������悤�B
�@�������A���̘Z�����ɐ��ꂽ��Ύ��@��Ƃ͉����Ƃ����A��X�͂��܂�Ɉ��Ղɍl���Ă���A�ыقǂ̗��������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���܂ł̘Z�����̉��߂́A���܂�ɕ��X��X�ɂƂ���āA��j�̖@����������Ă���l�ȋC������B�������ɗL�t����Ύ��@����������悤�ɁA���t���܂��A�Z�����ɁA�����̖@��A�t��q�̖@�������킻���Ƃ����̂ł͂Ȃ����낤���B�Z�����̐^�ӂ�͂ނ��Ƃ��A�ǂ�������̍������~�����ƂɂȂ邩�A�����ɂ͑���m��Ȃ����̂�����B
�@���A700�������܂��ɂ��āA�@��ɑ�3�̊�@���P���Ă���B����͉ߋ�2��ɂ��܂��đ傫�Ȗ@��I��@�ł͂Ȃ����낤���B������ꌾ�ł����A�����ȗ��̉��Ďv�z�ᔻ�Ɏ����ꂽ���ʁA���،ȐS����Ƃ����@�傪�B���u���̉e���������āA����ɂ�����A�����Ă��܂�A���S�ɊO�������Ă��܂����Ƃ�����̂ł���B�������A���Ďv�z�̉e���Ɋւ��ẮA���Ԉ�ʂɂ������邱�Ƃ����A���_���E�ɏd����u�������E�ł́A�Ȃ��̂��ƑŌ��͑傫���B�A���A�ȐS�����|�Ƃ��铖�Ƃ̂悤�Ȗ��O���@�͐�����f�ꂽ�Ɠ����ł���B���Ƃɑn���w����o���Ă���̏@��ُ̈�Ȍo�ϓI���W�́A����m����s���������A��Ύ��@����Ȃ����̂ɂ����B��X�͈���������A��O�ɂЂ낪�鍻��̘O�t�̂悤�Ȕɉh����ڂ��o���A�^���̑�Ύ��@������߂Č��r���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���A��X�̒u����Ă��闧��́A�����Ċ��t�̎���ł��Ȃ���A�i�t�̎���ł��Ȃ��B����ȑO�̓����̎���Ȃ̂ł���A�\�ʂ̉₩�����悻�Ɉꈬ��̑m�����^�ɑ�Ύ������āA���`�̖@������߁A�i��������Ȃ̂ł���B��X������A���̎��o�ɂ����Ēn���Ȗ@��̌��r������A�K��������̌����������������Ƃ��ł���ł��낤�B
�@�ł��[���Ȃ�Ȃ���A�閾���͋߂��B
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@���A�n���w���т��Ďg���Ă������t�ɁA�u�L�闬�z�v�u�ܕ��v������B���߂́A�w����̂��߂ɗ��p���Ă������A��ɐ����Q���Ɠ����ɁA�L�闬�z���A��ڕW�ƂȂ��Ă����B�����V���A�唒�@�ؓ��ł́A���݂ł��A�w��͍L�闬�z���s�̒c�̂ł���A��搂��Ă��邪�A�w��̑�����L�闬�z�Ƃ͂ǂ��������̂ł���̂��B�X�ɁA���̍L�闬�z�ς��@���Ȃ���̂��Ƃɐ��܂ꂽ�l�����ł��邩�B�����ŁA���ƁA�`���@��̍L�闬�z�Ƃ͉��ł��邩�A�ɏA���Ę_���Ă݂����Ǝv���B
�@�ȉ��A�l�͂ɕ����ďq�ׂ邱�ƂƂ���B
�@�n���w����@���@�M�k�Ƃ��đ��������Ղ́A�L�闬�z��簐i���Ă���Ƃ������o�ɂ���B�������A���̍L�闬�z�Ƃ́A����O�@���A�y�юO���@���Ɏ����ꂽ���d�ɂ��Ă̌䕶��Z�����āA�����Ɍ����̍L�闬�z�Ɍ��т����l�����ł���B�L�闬�z�������̗��z���Ƃ��đ����A�{�厖�̉��d���A���̍L�闬�z�̋łɌ����������̂Ƃ��A�X�ɂ́A�����y���݂Ƃ����ܕ������̍ŏI�S�[���Ƃ��đ������Ă����̂ł���B
�@�����́A��ʐM�k�ɂƂ��āA�������̔@���ł������L�闬�z���A�n���w��̐��͊g���̂��߂̖ڕW�Ƃ��ė��p����A�ܕ����A�����Ɏ��邽�߂̎�i�Ƃ��āA����̑������͂���ꂽ�B���̓r���ɁA�����ւ̎Q�����Ȃ��ꂽ�̂ł���B
�@�u���炪�����ɊS�����䂦��́A�O���@�̓얳���@�@�،o�̍L�闬�z�ɂ���v
�@�u�L�z�̏I�_�́A�������d�����ł���v
���ƁA�L�闬�z�A�������d���������m�ȖړI�Ƃ��āA�S����ɑł��o���ꂽ�̂ł���B�Ɠ����ɁA�����������������̋��w�I���t����Ƃ��s�Ȃ��A�@�֎���p���ĐZ�����͂����Ă������B
�@�}���A�n���w��ł́A
�@�u�吹�l�̏o���̖{���́A�O���@�̌����ɂ���A�����ܔN�ɑ�ڂ������͂��߂��A�O����N�\���\����̖{����d�̑��{���̌䌚���ɂ���̂ł���v
�@�Ƃ������߂ł���B�܂�A�吹�l�͏��䏑���ɎO���@����������ꂽ���A���ۂɂ͖{��̑�ڂƁA�{��̖{���̌����܂łŁA�{����d�����́A�����Ɉ▽����Ă���A�Ƃ������̂ł���B�S���瑊�I�Ȃ����Ƃ���ł��邪�A�w��͂��̈▽�i���ӕ����j�A���܂��M���̎��R�Ƃ�������I�ȗ��āA�L�闬�z��簐i����c�̂ł���A�Ƃ����̂ł���B�Ƃ�����A����@�����Ɍ�������A�L�闬�z�̋łɎc��̉��d�����Ɖ�����o���_�ɁA�w��H�������A�����̍������Ђ��N�����������������Ƃ��]���悤�B
�@���{���́A�����������߂̉�������Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł���B����́A�u���ɓ��@�吹�l�o���̖{���ł�������d�̑��{��������u����"���̉��d��"�[�[���{���������Ɍ��������v�Ɩ������A���{����������A�L�闬�z�̔肪�S�����������ɍ��ꂽ�̂ł���B
�@���������L�闬�z�Ɏ����i�Ƃ��āA�ܕ����p������B�w��ł͐ܕ����u�j�܋����̋`�v�ƈӖ��t���Ă���B
�@���Ȃ킿�ܕ��́A����̎@�`��܂�A���@�ɋA�������߂���H�s�ׂȂ̂ł���B���@�͖{���L�P�̋@���ł��邩��A������掖@��ӂ߁A�M�S�ɕ�������ܕ��A�Ƃ����������ł���B���������]��ɂ��P���ȑ������ł��������߁A���Ԃɂ����Ď��͍s�g�̕z�����s�Ȃ��A�\�͓I�C���[�W��^���Ă��܂����̂ł���B
�@�ȏ�q�ׂĂ����w��̍L�闬�z�ρA�ܕ��ς̋��w�I�����́A��̂ǂ��ɂ���̂��B����͂ǂ��₿�{�������i�̂悤�ł���B
�u���ɉ]�͂��A���ɒm��ׂ����̎l��F�����A��ӁA���Ɏl��F�ܕ��������鎞���m�Ɛ���Ɖ]�ӂׂ��A�����@�c�̔@���A���������Ɖ]�Ӗ�A���ӁA�ܕ��ɓ�`�L��A��ɂ͖@�̂̐ܕ��A���͂��@�ؐܕ��j���嗝�̔@���A�@�c�̏C�s�����A��ɂ͉��V�̐ܕ��A���͂��A���όo�ɉ]�͂��A���@���쎝����҂͌܉������ЋV���C�����A���ɓ����|���g�̂����ׂ����]�]�A��\�����������A�����V�̐ܕ��ɖ]�݁A�@�̂̐ܕ����Ȃ��Ę��ێ�Ɩ��Â���A���͕����˂ď����L�z�̎�����b�]�]�v
�@����́A���t���A�ϐS�{�������u���ɒm��ׂ����̎l��F�]�]�v�̕��ɂ��Ď߂���Ă��镔���ł���B�w��ł́A���̕��͂����̂܂܊��t�̐��ł���Ƃ��Ă��邪�A�����ɖ�肪����B
�@�w��ł́A�吹�l������ʂ��ĂȂ��ꂽ�ܕ��̐��ʂƂ́A���\�l�A�����������S�l�ɉ߂��Ȃ��Ƃ��A���S�����т������w��Ɣ�ׁA�吹�l�͖@�ؐܕ��j���嗝�̖@�̂̐ܕ��ł���ƒf�肷��B����ɑ��w��́A�ܕ����ʂ̑����́A�����L�z�̎���������̏o�����Ƃ��A�����|���g�̂𐭎��������܂ނ����镶�������ɒu�������A���ѐ��𐔗ʓI�ɑ��₵�āA�����L�z���}����A�Ɖ��߂����̂ł���B�吹�l�̖@�̂̐ܕ��́A�@�̂̍L�闬�z�A�t���L�z�ł���A�w��̉��V�̐ܕ��́A���V�̍L�闬�z�A�����L�z�̎����ƂȂ�B�����ł́A�n���w���������ƂȂ�A�����`�̌���ɂ����āA�s�J����J����̂́A���u���ł����ł���A�ƌ��т����Ă���B
�@�������A���i�����q�ׂɂ݂�Ȃ�A�����Ă��̂悤�ȓW�J�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����A���i���́u�l��F���ܕ��������鎞�́A�@�c�̔@�����m�ƂȂ�ׂ��ł���B���̂Ɍ����ƌ����̂��v�Ƃ̖₢�ȉ������́u�ܕ��ɓ�`�L��c�c�E�E��\�����������v�܂ł́A�v�@�����C�̏����̈��p������ł���B�X�Ɂu�����V�̐ܕ��ɖ]�݁A�@�̂̐ܕ����Ȃ��Ę��ێ�Ɩ��Â���v�Ƃ́A���C�̕��ɑ��銰�t�̉���ł���A���t�̍l���́A�u���͕����˂ď����L�z�̎�����b�]�]�v�̋͂������ł���B
�@�w��́A���̓��C�̐������t�̐��Ɗ��Ⴂ���āA�����Ɋw��̐ܕ���Ղ������A�w��������V�̐ܕ����s���Ă���Ƃ��Ă���̂ł��邪�A�����ɂ��w��炵�������I�ȃ~�X�ł���B�S�Ă����t�̕��Ƃ����@�n�����w�ɂ���ĕ~����Ă����ܕ��̓����A����Ȃ���͓̂��R�ł���B
���@�@�������d�́u�����v�̌�́A���̌�A�����}���������A�O�c�@�ɐi�o����ہA�}�̃C���[�W�_�E��������āA�g���Ȃ��Ȃ������A���̂��u�{�厖�̉��d�v�ƁA���ƌ×��̖��̂ɂȂ��������ŁA���e�́A�ˑR���Ԃ̒��ő�����ꂽ�܂܂ł������B
���A�@���{���͏��߂�����d���Ƃ������߂ł͂Ȃ������B�����́A�L�闬�z�̎���҂܂ł̈ꉾ���ɂ��Ȃ��������A���d�̑��{���݂����A�����d�Ȃ�ƌ��т��A�L�闬�z���A�ɉq�̎O���̋����Ȓ�`�t�����Ȃ��āA�ߖ����̎��Ƃ��A���{���������L�闬�z�Ƃ����̂ł���B
�@
�@��ɑn���w��̉߂��̍������A�{�������i�̓ǂ݈Ⴂ�A�������t�̍l���łȂ��A���C�̍l���ł���Əq�ׂ����A���̂��Ƃ��͂����肳���邽�߂ɁA�悸�v�@�����C�̋��w�̓����A�Ƃ�킯�L�z�ς��q�ׂĂ݂悤�Ǝv���B
�@���C�͑��t�����̋���s�@�ƁA���t�̒�q����J�R�̏Z�{���̗������ꎛ�ɂ����v�@���̎�������̊ю�ł���B�㐢�A�x�m�嗬�̋��w�U���̗Y�Ƃ��āA�ۓc���{������Ƌ��Ɂu����ђC�v�ƕ��̂���Ă���B���C�̒��q�ɂ��ẮA�u�������\����������Ȃ��v�ƌ��M�Ԃ��`�����A�×��A���g�̒����������Ɖ]���Ă���B�����������C�̐��U�Œ��ڂ��ׂ��́A���C���g�A���߂͕s�����s���u�_�҂ł������̂��A�r���ő������u�_�҂ɕς�������ƁA���̓]���̗v�����A���s�ɉ�����V���@���ɂ��邱�ƁA�ł���B
�@���C�͂Q�R�̎��A�Z�{���O�k�̋���@�ւ̍u�t���Ƃ߂Ă���B����͏t�H�̓��A���ꂼ��X�O���Ԉʂ�P�ʂƂ��A�ĂƉ]������̂ł���B���̉Ă��I���ďH�A���s�����ƂɁA���R�{�厛�Ɍ������A���C���P�O�ΔN���̓��S�Ɏ��i����B�x�m�嗬�̋��w���]���ړI�ł������B���R���S�́A���R�A�x�m�̓`�����`�ł���s�����s���u�_�҂ł��������A���C�����̂܂܂Ɏ�e���A���s�ɋA���Ă�����A�s�����s���u���O�߂�̂ł���B
�@�M�āA�����̋��̗l���́A�܂��ɓ��@�@�����̊��ł������B�u�@�؏@�̔ɏ��́A���ڂ����������̂Ȃ�v�Ƃ��A�u�V�����N�̂���A���s�ɓ��@�@�ɏ����āA���������O�������A���@�o�����A���������ڂ̍J�Ɂv�Ɠ`������B�����̌֒�������������ɂ��Ă��A���@�@�Q�P���{�R�́A���������ƌĂꂽ�n��Ɉʒu���A���ɂ͖x������������A��������邱�ƂȂ���A���s���O�ւ̉e���͂��傫�������Ǝv����B
�@�V���T�N�i�P�T�R�U�j�ɋN�������V���@���́A�����ɐ��͂������@�@�ƁA�b�R�V��@�Ƃ̐M��̑Η���w�i�Ƃ��Ă���B�悸�A�b�R�̑m�ƁA���@�@�k�̖ⓚ���������ƂȂ�A�����������ꂽ�b�R�����A�����̓��@�@�ɏ��̗l�ɂ��܂肩�ˁA���͂������āA�����̓��@�@���@���U�������B�m������������A���Â����Ƃ������Ƃ́A��s�k��̑m���ɑ�\����邪�A���̌�A��k���̎Љ�s���̂��߁A���@�̊Ԃɂ��A�����т��镗�������A���͂������킦�Ă����B
�@���@�@�ɉ����Ă����l�ł������B�����V�N�i�P�S�U�U�j�Ɍ��ꂽ���@�@�������{�R�a�r�̖���ɂ́A
�@�u��A�ّ̓��S�̈ӂ��Ȃ��Đܕ��O�ʂ���ɂ������v
�@�u��A�@���ɏA���ċ���̗��їL���嫂��A���`���Ȃ��Đ��ƈׂ������v
�@�Ƃ���A�ܕ����_�́A����̕��Ƒ��ւ��āA���X�V�g�������̂ƍl������B�����������`�̕������A���͕ێ���A���͂œG�Ƒ��Λ�����Ɏ��邱�Ƃ́A�e�Ղɑz�������Ƃ���ł���B
�@�V���@���́A���ǁA�����̔����ȏ���Ă��ꂽ���@�@���̑ޏo�ɏI���B�Q�P���{�R�S�ďĎ��̓��@�@�́A���������ɓ��ꂽ�B���̂Q�P����ɁA���{�́A���@�@�k�̗����O�p�j���֎~���A�U�N��ɁA�A���������o���ꂽ�Ƃ͂����A�P�T�����̍ċ��̓r�ɂ����̂́A�V���P�T�N�̂��Ƃł������B
�@�A���Ɏ��閘�̊ԁA��̓��@�@�́A���h�߂��o�āA���{�A�����ɑ��āA�l�X�ȓ�������������B�������A�A���ɂ�����A�ł��T�d�ɑΏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂́A�b�R�ł������B�V���@���́A�b�R�Ɠ��@�@�̕��͂̂Ԃ��荇���ł��邪�A���@�@�̕��͒~���ɂ́A���`�̐ܕ����̋��`��̍��������������߂ł���B�����A���`�̐ܕ��ɂ���āA�M�k���̋}���ȑ����������A�̂ɉb�R�Ƃ̑Η������܂�A���̌��ʁA���߂�͖̂@�͂ɂƂǂ܂炸�A�����̕��͂ɂȂ��Ă��܂�������ł���B�]���āA���@�@������A������ɂ́A���`��́A��Ƃ��Đܕ��`�̉��ς��K�v�ł������B�������A���̉��ς́A�V��@�Ɏe����A���{�ɂ��F�߂��鋳�`�ł���A���@�Ƃ̖@�`��̑Η��������A�Ăѕ��͂����߂邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ȋ��`�ɂ��邱�Ƃł������B�������Ȃ���A���ɉb�R���������A���@�@�̋A���́A��������̂ł���B
�@����A���C�́A���R���S�̋����ɂ��A�s���s�ǘ_�҂ł������̂��A���̓V���@���̗��N�A���ǘ_�҂ւƈ�ς���B���C�̒��ɂ��A���R�{�厛���狞�ɒ����Ĉȗ��A�s���s�ǂ̖@����O�߂Ă������A���͂Ƃ̘_�`�ɂ���āA�x�m�̖@��ł���s���s�ǂ̘_���~���A���O�ɉ��āA���������Ƃ���B���ǘ_�Ɍ����ĉ]���A���̋��`�̕ϊ��́A������l�̂��Ƃ��A�������̊��q���ɑ���A�Ƃ����ׂ����̂ŁA������l���ܘV�m�ɑ��A�V��̖���Ɛӂ߂�ꂽ��ɑ��ʂ�����̂ł���B���C�̋��`���ς́A�����̕N���������A���@�@�S�̂̎������ł��������Ƃ���Ă���B���C�͋��s�Ŋ����邽�߁A���`��S�ʓI�ɕύX�����B����͕x�m��ɗ����u�v�����v���@����A���Ԏ̂���L���̋��`�ւ̓]���ł������B�����_�A���u�_�́A���������w�i���琶�������̂ł���B����ɂƂ��Ȃ��āA�ܕ��ρA�L�z�ς��ω����Ă���̂ł���B
�@���Ƃ̐ܕ��ƁA���C�̐ܕ��Ƃ̑���́A���@��l�́u�v�@�����C���v�ɖ��炩�ł���B
�u�c�Ѝ��̔@���R�тɓl�������l�ɑ����Ƃ��A�`���Ɉ�w�V�ꖳ����ΐܕ��̑�ڂƐ���A�������l�ɑ���k�`�Ȃ�ǂ��L�̏C�s�͐ێ�̍s���ƂȂ�ׂ����A�������吹�̋��]�]�v
�@�܂�A���Ƃ̐ܕ��Ƃ́A���@���`�𐡕���킸�����ł���A���Ƃ����Ƃ̈��͂��������Ƃ��Ă��A����ɏ]��ʗv�����v�̏C�s�ł���B���������C�͍��A�����������Ȃ�����ɂ���B�Ɠ����ɁA�ܕ��̌�͓`���I�Ɏ̂Ă��ɂ������Ȃ��B�����œ��C�́A�ܕ��������A�܂茠�͎҂ɏ������̂ł���B�����̈ӂɏ]�����Ƃ���̐ܕ��A���ꂪ���͂Ɍ��F�����ܕ��ł���B�����đm���鎩���B�́A��؍���ɂ����炤���Ƃ̂Ȃ��ێ�Ƃ��A���C�͌����ɂ��̎�����̂т�̂ł���B����ǂ��납�A�v�@���͈ȑO�ɂ��܂��āA�傢�ɔ��W����̂ł���B�������A����͂��Ƃ�蓖�Ƃ̖@��Ƃ͐^���́A�ނ���ߑ��������̂��̂̋��`�ł����āA���@��l�́A������A
�u腕����]�L�̖��ނ̏��R���ւ����Ɩ����A�����̏��ɐM�V�ꖳ�����͈��ׂ����^����ƁA�R���嫂��b�����ւ̍s�Ȃ�A�I�ɍL���̐����t�ɋA�����҂��v
�ƁA�吹�l�̖@�����ւɂ���ĕ����B�����Ƃɂ��A�k��ɐ��݂͂̂��g�債�Ă��������C�����������j���ꂽ�̂ł���B
�@���C�̊ϐS�{���������́A�@��̉��ό�̏��ł���B���A���t�̕��i���ƁA���C�̊Y�����镶���r���Ă݂�A���̒ʂ�ƂȂ�B
�@
|
�@
�@ |
�@
|
�@����ɂ��ƁA���t�́A���C�����p���A�͂��ɖ�̕��Ɂu�����@�c�̔@���v�ƁA�����Ă���ɉ߂��Ȃ��B�X�Ɋ��t�͈��p�̂��ƂɁA�u���́A���V�̐ܕ��ɑ��āA�l���l�̖@�̂̐ܕ��́A�ێ�Ɩ��t������v�ƁA���C�̈ӂ�������A�Ō�ɁA�u���͕����˂ď����L�z�̎�����b�]�]�v�ƁA�ӌ����q�ׂ���ɂƂǂ܂�̂ł���B
�@�����̐l�Ύ��́A���łɑ����ɂ͂��܂�v�@�����̋��`�ɐN����Ă���A�i�t�A���t�́A�l�Ύ��`���@����Ƃ���ǂ����Ƃ��Ă����B���̍�Ƃ̍Œ��A���t�́A��O�̑���ł���v�@���̕����A���̂܂܈��p����ƍl������ł��낤���B�܂��āA�v�@���ł͊J�R��l�̍ė��Ƒ����������C���A���̑���ł���B���t�̗���́A�����܂ł����Ɠ`���@��̍ċ��ɂ���A����ɂ́A�܂��v�@�����w�A�������C�̋��w��j�����Ƃł������B�ƂȂ�A���t�́A���i���ł͓��C�̕������p���Ă��邾���A�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B
�@���ɁA���C�̖{���������ɂ���āA�����ɏ��t�̍L�z�������A���ł̂悤�ɂȂ�B�������C�́A�l���l�̖@�̂̐ܕ��͖��@�̎n�ߌܕS�N�Ɍ���̂ł���A�t���̍L�z�͏I�����A��X�̎���͏����L�z�̎��ł���A�ܕ���
|
|
�݉Ɓi���͎ҁj���s�Ȃ��A�m���͐ێ���s�Ȃ��B���̍݉Ƃ̐ܕ������V�̐ܕ��Ƃ����A����ɔ䂷��A�@�c�̐ܕ����A�P�ێ�ɂƂǂ܂�Ƃ����̂ł���B�܂���C�́A�@�c���V��𑜖@�ߎ��Ƒނ���ꂽ�悤�ɁA�@�c�@�ܕS�N�̉ߎ��Ɖ������悤�ł���B�ނ��A���肪�l���l�䂦�A�����܂ŋ��ق��o�����A
�u�Ⴕ���i�t���L�z�j���i�����L�z�j�L�z�̎����_���A���̋t���̍L�z�͏���A���̍L�z�͗���A����Ƃ́A�n�O�̋��œx��̐l�����A�����̍L�z����A���̍L�z����A���ƂȂ�A������L�z�@�c�̌�{�ӂȂ邪�̖�A�ĉ��͋����ď�����炴���v
�Ƃ����A���Ƃɂ��A�g���ɂ��Ƃ�����̂킩��Ȃ��Ƃ���ɗ������Ă���B
�@�������A���C��w��]���悤�ɁA�l���l�̎���͏I�����A�T�A�[��X�̏����L�z�̎��オ�����Ƃ������Ƃ��A�ʂ��ċ������̂��낤���B����͓��Ƃ̈ꌾ�ېs�̖��@�A���s���Ȃ�������ɂ���א��ɂȂ�͂��Ȃ����낤���B�Ȃ��Ȃ�A���C�͍X�ɖ@�؎�v���̕��������āA�u���̏����͈ꕔ��ǂނׂ��v�ƁA���@�����̂ĂāA��o���u�����߂Ă��邩��ł���B�����͂��ׂāA��X�̎��オ�����L�z���ƍ��o����Ƃ��납��n�܂��Ă���B���Ċ��t�́A���C�̖@�؎�v�����߂Ɏ��̂悤�ɓ����Ă���B
�u�������S�������̈ӂɓ����B�ނ̕��ɉ]�킭�A�����̐l�͉��Ɩ����Ƃ��@�،o�ɔw�����Ɉ˂��Ēn���ɗ����^�������A�̂ɓe���p���@�،o�������Đ����������ׂ��A�M����l�͕��ɐ���ׂ��A掂���҂��Ōۂ̉��Ɛ����ĕ��ɐ���ׂ��Ȃ�]�]�B��v���̈Ӗ�Ȃ��ĕ����Ȃ�A�X�ɖ��̏����ꕔ��ǂނׂ��̈Ӗ����A���Ȃ��Ď���ɉ���v
�@�����A���t�͎��ɂ���Ċe�X�̐l���A��X�̎��オ�����L�z���Ƃ����̂͊ԈႢ�ŁA��ɖ��@�͋t���̍L�z�̎��ł���ƁA���m�ɔj�܂���Ă���B�܂����C���A�����L�z�ɟ��όo��z���Ă���̂ɑ��A���t�̍u�`�����ꂽ���t�⒉�t���A���όo���t���L�z�ɔz���Ă��邱�Ƃ��A����ɂ����������B�L�t�����V���̐������ɁA�u���όo�̓���v���L����Ă���̂��A���ɁA���@�͋t���L�z�ł��邱�Ƃ�������Ƃ��Ă���̂ł���B
�@����ɂ���Ċ��t���A���C�̐����A
�u���͕����˂ď����L�z�̎�����b�]�]�v
�@�Ƃ���ꂽ�Ӌ`���N���ɂȂ낤�B�����@�͋t���L�z�Ɍ��邪�A���C�������悤�ȏ����L�z�������̏�ɂ���̂Ȃ�A�����������߂��悩�낤�A�Ɗ��t�͂�����Ă���B�ܘ_�A���Ƃ͂��̂悤�ȏ����L�z�͂Ƃ�Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�R�A�n���w��Ɠ��C�̗ގ��_
�@�O�̂Q�͂ł́A�n�����w�ő������Ă����ܕ��ρA�L�闬�z�ς̌����q�ׁA���̌��̍������A�{�������i�̌�ǂɂ��邱�Ƃ��w�E�����B�X�ɁA���i�̊Y�����������C�̕��ł��邱�Ƃ���A���C�̎v�z�w�i�ɂӂ�A�Ō�ɁA�w��A���C���ɁA���Ɠ`���@��ɔ邱�Ƃ�_�����B�����ł́A���҂̋��`��̍l�����̋��ʓ_�������A���̗ގ������q�ׂ邱�ƂƂ���B
�@�n���w��Ɠ��C�̍l�����̑傫�ȋ��ʓ_�́A�@�c�̔q�����Ɍ����ł���B�����A�w��A���C���A�吹�l���@�c�Ƃ��Ă͂��邩�A�����B�̎���ƁA�@�c�����̎���ƕ����čl���Ă��鎖�ł���B����́A�@�c�̎���Ɖ�X�i�w��A���C�j�̎���͈قȂ�A�@�c�̐ܕ��ɂ͌��E������A���ɂ͒ʗp���Ȃ��Ƃ����l�����ł���B�ނ��A������@�c�Ɛ藣���A�@�c�̎��ƁA���̎��Ƃ͑S���Ⴄ�Ƃ��Ȃ���A���̐��ʓI���W�͂Ȃ������ł��낤�B
�@���C�́A�@�c�Ǝ����B�̎���̑����\�����ď@�c�̐���̂āA���s�Ő������сA����w��́A���i�̕������C�̂��̂ƒm���Ă��m�炸���A�w��ɂƂ��Đ��ɓs���̂悢���̂Ɣ�т��A���͊g������w���đ傢�ɗ��p���Ă����B���̌��ʁA���C�͑�@��̈ʂ��āA�����̖��{�A���삩���e�F����A�w��͋���ȑg�D�̗͂𗘗p���āA�O���̐����Ƃ͑S���W�̂Ȃ������ւ̐i�o�A�܂�A�����̌��ЂÂ����}��A���̌��Ђ��Љ�ŗe�F�����悤�ɁA���������A���a�^�����Ȃ��ꂽ�B�r�c��쎁�́A�u�@�c�͈�����A�w��͖���v�Ɖ]���A���C���A�@�c�ݐ����܂ޖ��@�ܕS�N�ƁA���C�Ȍ�̖��@���N�Ƃ����A�@�c�����q����ɕ����߂悤�Ƃ��Ă���B���̓��I�́A�@�c�����q����ɉ������߂āA���͎����B�̑�ł���A�@�c�̑�͗y���̂ɉ߂�����A���݂ɂ͓���Ȃ��Ƌ������邽�߂ł���B���C�͂��ׂ̈ɁA�@�c�̐ܕ����݉ƌ����ɏ����āA���C���g�͍I�݂ɐێ�ƂȂ�A���͂ɛZ���āA���@�̐����I�ɉh���͂���̂ł���B�Ƃ͉]���A���@�剺�ł��邩��A�����炳�܂ɐێ�Ƃ͖���ꂸ�A�ܕ��̒��ɖ@�̂̐ܕ��A���V�̐ܕ��ƕ��ʂ��A�@�c�͖@�̂̐ܕ��Ƃ����ێ�A�݉ƌ����͉��V�̐ܕ��Ƃ��Ă͂߁A���V�̐ܕ����鏇���L�z���A�@�c�̖{�ӂƎ咣����̂ł���B���C�́A���@���N�͍݉ƌ����̉��V�̐ܕ��̎��߂Ƃ��āA�m�̐ܕ����݉ƌ����ɏ��������ƂɂȂ�B
�@�w��́A���C���猫���ɏ���ꂽ�ܕ����A���̂܂�����`�ɂȂ�B�@���c�̂Ƃ��đ��݂���ȏ�A���`�I���t���͕K�v�ł���A���V�̐ܕ��ɂ�鏇���L�z���@�c�̈▽�Ƃ��Ȃ�A�w��̑��݂͏@�c���K�v�Ƃ��Ă������ƁA�Əؖ�������̂ƂȂ�B���ہA�w��̋�������Ƃ���́A�@�c�̌�▽���鉻�V�̍L�闬�z�i�����L�z�j���������邽�߂̒c�̂ł���A�Ƃ������Ƃł����āA�l�X�ȎЉ�Ƃ��a�����A���̑���W�̑O�ɂ͍��ׂȏo�������A�����͖@��ƌ����������āA�����G������B�w��̓G�́A�����ɑ吹�l�̓G�ł���Ƃ��āA���@�j��҂Ƃ���A���V�̍L�z���͂ގ҂Ƃ��āA�G�Ύ����邾���̂��Ƃł���B�w����ŁA���⏇���L�z�̎��Ɛ���ɐ������Ă��A����́A���Ƃ̓`���@��Ƃ́A�S�����Ĕ�Ȃ���̂ł���B
�@���������@�c��藣���čl����w��A���C�̓��e��}�ɂ��Ă݂�ƁA�}�����̂悤�ɂȂ�B
| �w��̍l���� |
�@�c |
������ |
�@�̂̐ܕ��i�ێ�j |
�t���L�z�i�@�̂̍L�闬�z�j |
|
�w�� |
���� |
���V�̐ܕ��i�ܕ��j |
�����L�z�i���V�̍L�闬�z�j |
|
| ���C�̍l���� |
�@�c |
���@�ܕS�N |
�@�̂̐ܕ��i�ێ�j |
�t���L�z |
|
�w�� |
���@���N |
���V�̐ܕ��i�ܕ��j |
�����L�z |
�@���̐}�ň�ڗđR�̂悤�ɁA�w��A���C�̎v�z���e�́A�S�������Ƃ�����B�قȂ�_�́A���C�͑m�A�w��͑��Ƃ������ꂼ��̗��ꂾ���ł���A�@�c��@�̂̐ܕ��A�t���L�z�Ɣz���A����Ȍ�́A����A���͖��N�Ɋ����ĉ��V�̐ܕ��A�����L�z�̎��ł���Ƃ����̂́A�O����ɂ��Ă���B�������C�́A���V�̐ܕ��A�����L�z���݉ƌ����ɏ����āA���C���g�͏@�c�Ƌ��ɐێ�ɂ����܂邪�A�w��͂���ɑ��āA�����B�������V�̐ܕ��𐄐i����c�̂ł���Ƃ��āA�@�c�����S�ɉz���Ă���̂ł���B���̓_�A�w��́A���C�����X�Ɉ�d��������������Ƃ��Ă���Ɖ]���悤�B
�@
�@�O�͂ɂāA�w��Ɠ��C�̎v�z��̗ގ��_�����炩�ƂȂ������A����ɑ��āA���Ƃʼn]���Ƃ���̐ܕ��A�L�闬�z�ɏA���ďq�ׂ邱�ƂƂ���B�܂��A����ɂ́A���Ɠ`���@��̍l�����̊�Ղm�ɂ��Ă����K�v������B
�@���ɁA���t��ŏo�����u���̖@��ɂ��āv�ɂĐ�������Ă���悤�ɁA���Ƃ́A�t�틤�ɖ��f�f�̏O���̐��E�A���������̏��ɖ@����������Ă���B�ߑ������𗝌�Ƒނ��A���ƕ��@�������Ɍ����A�ƒ�߂邻�̊Ԃɂ́A���̐��E���O���̐��E�ւ̎��̐芷�����Ȃ���Ă���̂ł���B����̐��E�͊O�p����̐��E�Ƃ��Ďߑ��̗��v��ւނ�ɑ��A�����̐��E�͓��ؖ{�n�̐��E�Ƃ��āA���f�f�̎t�킪��ӂ��āA�����𐬂��Ă����]���āA���Ƃʼn]���Ƃ���̐ܕ��A�L�闬�z�́A�ߑ����������ς�������O���@�ɂ��Ă���ܕ��A�L�z�ł����āA�L�t�A���t���͂��ߌ���́A�ߑ������̍ݐ��A���]��Ƃ͈�����悵�āA�Ō�A�ҖŖ�̘b�Ƃ��ĂȂ���Ă���B
�@��Ύ��Ɍ�^�ւ𑠂���ЋŔ������ɁA
�u���όo�ɉ]�͂��A��؏O���ق̋����́A��������@����l�̋�Ȃ蓙�]�]�A���@�]�͂��A��؏O���̓����́A����������@��l�̋�Ɛ\���ׂ��v
�Ƃ���悤�ɁA�߉ޔ@������؏O���̋���ق̋�Ƃ���L���ʂ̐��E�ɋ����̂ɑ��A�@�c�͈�؏O���̋��̋�Ƃ��閳���ʂ̐��E�A�����A���ɖ��f�f�̈�؏O���̐��E�ɋ����Ă���B���̓�̐��E�́A���̂܂�掖@�҂̂��Ȃ����E�A�܂菇���̐��E�ƁA�S�Ă�掖@�҂̐��E�A�܂�ߑ��ɑ���t���̐��E�̈Ⴂ�ƂȂ�B
���̂��Ƃ́A
�u���͖@�،o掖@�̎҂��������͂��A�ݐ��ɂ͖�����ւɁB���@�ɂ͈��̋��G�[�����ׂ��A�s�y��F�̗��v�@����Ȃ�v
�̕��Ɏ���A���@�͎ߑ��̗��v�ł͋~���ʐ��ł����āA�ɕs�y��F�̐ܕ��C�s�̗��v�̐��ƂȂ�A�ߑ������̐������ς��Ă���B
�@�@�c���u���@�͕s�y�̐Ղ��Ќp���v�Ƌ����A������l���u���@�̏C�s�v�Ǝ~�߂�ꂽ�̂́A�@�c�̏C�s�A���̂܂ܖ��@�O�ʂ̎p�A�ܕ��C�s�̎p�ł���Ƃ��ꂽ�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�Љ������̖��@�̕s�y�̎p�����A�@�c�����K��ꂽ�ܕ��̎p�ł���A�@�c�͏�̑ŝ����Ȃ�����A���U�ʂ��Ċт��ꂽ�p�ł���B
�@�Ȃ�قLjꌩ����A�@�c�̎p�ƕs�y��F�̎p�Ƃł͈Ⴄ�ł��낤�B�@�c�̈ꐶ�́A���l���x�A����m�ꂸ�Ƃ������Q�̈ꐶ�ł���B�s�y��F�́u��[�h�v�̓�\�l����������A�s��q�ł���B�O���݂̂�����Ȃ�A�@�c�͐l�X���q���ĉ�����Ƃ����̂͂Ȃ��B�@�c���Ќp�����̂͗�q�s�ł͂Ȃ��A�������@�i�Љ������Ǝߑ��j�ɂ����āA�@�����p���Ќp���ꂽ�̂ł���B�l��F�������́A
�u�����ē��@����q�Ɖ]���Ė@�،o���C�s����l�X�́A���@���@���ɂ���ցv
�̕������̂܂܂Ɏ��A�����Ɠ�������������҂͂Ȃ��A�����ɂ͖@�ؐܕ��j���嗝�̎p���w�ԁB���l�ɁA�s�y��F�ɂ��A�@�c�Ɠ������ܕ��̐M�p�����w�Ԃ̂ł���B
�@�@�c�ɂ́A���C�̂悤�ɋ��s�ҏZ�̂��߂̖@�`���ςȂǖܘ_�Ȃ��A���A�w��̂悤�ɐ��I�g�����w���āA�s���̂悢���`�c�ȂȂǂ��낤�����Ȃ��A���ǖ@�ؐܕ��j���嗝��ʂ��ꂽ�B�@�ؐܕ��j���嗝�Ƃ́A�B����̗��A�����^���łȂ����̂ɑ��āA�Ë����������Ă����s�ׂł���B�@�t���A
�u�c�Ѝ��̔@���R�тɓl�������l�ɑ����Ƃ��`���Ɉ�w�V�ꖳ����ΐܕ��̑�ڂƐ���@�E�E�E�E�E�E�@�v
�Ɠ��C�ɕԓ�����Ă��邱�Ƃ�A���t���A
�u���ɋ�����@������C�s����v
�Ǝ��s�̕ӂ������Ă���̂́A���s�Ƃ��Ă̐ܕ��A�@���ڎO�c�̓��̋`���Ɉ�w�Ȃ��悤�A�Ȃ�Ɍ�����ܕ��̎p���w���ĉ]���Ă���̂ł���B
�@��Q�͂ɂāA���C�����V�̐ܕ��A�����L�z�ɟ��όo�́u�������c�c�c�v��z���Ă���̂ɑ��A���t�̖{�����u�`�̒��u�҂ł��铌�t�A���t�����A�t���L�z�ɟ��όo��z���Ă���Ⴂ�ɂ��Ăӂꂽ�B�܂��L�t���A���V���Ɂu���όo�̓���v���L����Ă��邱�Ƃ��l�����킹�Ă݂Ă��A���Ƃ̓���Ƃ́A���Ɍ����铁��ł͂Ȃ��A�Ȃ�Ɍ����铁��ƍl����ׂ��ł���B�Ƃ���A
�u�P�A�o�d�̎����͑品������ԂɎ��������A�ܕ��C�s�̉��V�Ȃ邪�֖̂�v
�Ƃ����品���A��q�A�x�ł̂��߂Ƃ��������A���ؕ��@�̑����̂��߁A�`���Ɉ�w���ʂ悤�Ȃ�ւ̐ܕ����A
�����ɕ\�����p�ƍl������̂ł͂Ȃ��낤���B
���Ƃ��ƁA���Ƃ͊�Ɍ����Ȃ����ؕ��@���咣����B���A��Ɍ����Ȃ��Ƃ́A�����ȐS�̏��k������ł����āA�ܕ������R��ł���B�������Ŕ��ʂł���O���Ɏ��o���āA���ꂪ�ܕ��̖{�`�ł���Ɖ]���Ȃ�A����͗��]�̐��E�ł̓W�J�ŁA�k��ɐ��ʎ�`�ɓ˂��i��ł����͖̂��炩�ł���B
�@���ɁA���Ƃɉ�����L�闬�z���A�ܕ��Ɠ��l�A�ȐS�̏��k�ł���B���t���A
�u��ӁA�����͛߂ɔ@���̖Ō���Z�S�]�N��A��ܕS�̎��߂ɉ߂�����A�R��Ɏ��O�̏��o�����B�v�����A�������ɐ���Ȃ�A�@�̎O�Ӗ������z�����A�A�Ⴊ���̂ݖ�A�@���̌��Ӌ��̔@���A�����ς̐��k��Ȃ�Ɏ�����@���A���ӁA�����̗L�����Ȃ��ĉB�v���z��m�����A�����K�����������ɍS����v
�ƁA�����̗L�����Ȃ��ė��z��m��ׂ��ł���Ɖ]����悤�ɁA���ʂʼn]�]�����]�n�̂Ȃ����ɓ��Ƃ̍L�闬�z�����Ă�B�����v���A�o�ϊv�����������A���̂ނ������ɍL�闬�z�����邩�̔@���Ɏv���̂́A�����Ȃ��Ƃł���B
�@���t�A���t�̖{���������̋L�ɁA
�u�t���L�z�̎��͟��όo�̔@�������т����v
�Ɗ��t�̈ӂ��L����A�X�Ɋ��t�䎩�g���A
�u�����Q�X���z���A��t���鎞�F�H��m��A��؊J������V���̏t�Ȃ�A��L�闬�z�ɔ�A�����t���ɖΓ��{�����L�闬�z�Ȃ�A�����@���̋����͑�C���̎������ւ��邪�@���A�t�̌�ɉė��邪�@���A�H�|�����ӂ��Ɩ����A�Ⴕ����ΏI�ɂ͏��l��艺�����Ɏ���܂ňꓯ�ɑ������̂ĂāA�F�얳���@�@�،o�Ə��Ӊ��A�����L�z�����V���^�Ӑ{�����A����҂����]�]�v
�Ɖ]���Ă���B�܂�A���Ƃ͊ҖŖ�ɂ��Ă�t���L�z�i�@�ؐܕ��j���嗝�A������j��{�^�ڂƂ��A�O���̓����Ⴆ����ܕ��̏@�Ȃ̂ł���B���t�̋��̈�Ƃ́A�O���̒��̈�l�ł͂Ȃ��ɁA��؏O����ۂ߂��Ƃ���̈�ł���B���̌ȐS�Ɏ��܂�ҖŖ�̍L�闬�z���A���Ɠ`���@��̍L�闬�z�ŁA����ɑ��āA��l���͓�l�A��l���͎O�l�A�O�l���͎l�l�ƁA����ǂ��ĊO�ɊJ���Ă������]��̒��ŁA���l��艺�����̑S�Ė��@��M�邻�̎����A�����L�z�ł���B���Ƃɉ����ẮA�ꉞ���]��ɉi���̓��W�Ƃ��ď����L�z��u�����̂́A�{�`�ҖŖ�Ƃ��ẮA���݂��A���������t���L�z�ł����āA�O���̎t�̎������q�Ƃ��āA���t�̋��̂悤�ɁA�ȐS�̐ܕ��A�t���L�z�𐬂��Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
|
�@ |
���@�@�t |
�w�@��@�E�@���@�C |
|
���]�� |
�����L�z |
�L�闬�z�@�@���V�̐ܕ��A�݉ƌ��� �@�@�@�@�@�i���όo�A������c�j �@ �@ �t���L�z�@�@�@�̂̐ܕ��A�@�c�̖��@�O�� �@ |
|
�Ŗ� |
�t���L�z �s�y�̍s�@�i���όo�A������c�j �@ |
�@ |
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@