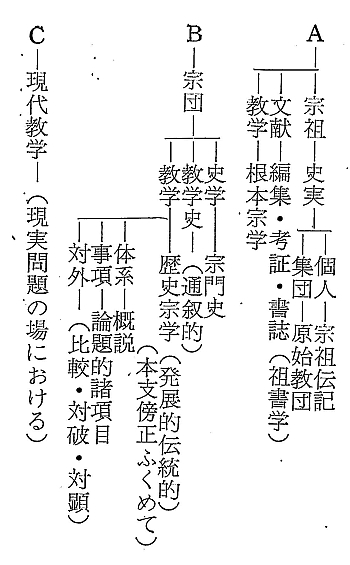
�@
�@�@�w�@�_
�@�@�@�@�@�\�@�@�w�_�̉�ڂƓW�]�@�\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�n�Ӂ@��z
�@�́@�@���@�@���@�@��
�@�@�w�ɂ��ẮA�Ƃ��ɐ��ɂ����āA���܂��܂ɘ_�����Ă����B�������ŁA�@�w�ɂ��čl���Ă݂悤�Ƃ���̂́A���������_�c�����̂܂܌J��Ԃ����Ƃ���̂ł͂Ȃ��B�@�w���߂��鍡���I�̂Ȃ��ŁA�@�w�͂ǂ��F������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv������ł���B
�@�����܂ł́u�@�w�_�v�̓W�J�ɂ��Ă͌�ɂӂ�邪�A����͎�Ƃ��Ċw��̗��ꂩ��A�@�`���H�Ɗւ���ď@�w�����݂̍���ɂ��Ę_�����Ă����B���R�A���̘_�c�̒��ɍ��܂�Ă͂��邩�A�����Ă����Ȃ�A�@�w���x������̂Ƃ��ĎO�{�̒�������̂ł͂Ȃ��낤���B�܂Ñ��ɋ��c�Ƃ̊֘A�ł���B�����A�@�`���H�Ə@�w�Ƃ͐[���ւ��������A�z���҂̍O�����傫���i��ōs���A�K���@�c�Ƃ��Ă̏@�`���H�E��z�̉ۑ�Ɉ�������ł��낤�B���ɋ���Ƃ̊W�ł���B�����ɂ������炪��Ƃ��Ď����S���m������ɂ��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�����āA��O�ɏ@�w�����̈Ӌ`�Ɩ����ł���B�����O�{�̒������a���čs�Ȃ��˂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@�����̂��Â�̖ʂ������Ă��A�@�w�͑傫�Ȍ��ׂ������ƂɂȂ�ł��낤�B���c�Ƃ����g�D�͏@�`�Ƃ������O�ɂ���đ��ݗ��R�����B���̏ꍇ�A��Εs�ς̏@�`�����{�Ƃ����A�����ɓ���I�ȋ�̓I�Ȗ��ɂ������čs�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ�����A���ׂĂ̖��ɑΉ��ł���悤�ȃ��B�W�����Ƒg�D�̌n�Ƃ������̂ł���ׂ��ł���B�@�w�͂˂ɋ��c�̗��O���������čs���˂Ȃ�ʂ��A�܂����c���{���̈Ӗ��ł̋��w���O�Ɋ�Â��L�@�I�ȑg�D�ɂȂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�u�@�`��j�v�͂��̂悤�ȕ��݂̑����Ƃ��čl������B�j
���̋��琧�x�Ƃ̊֘A���A���͋��c�Ƃ̊֘A�̈ꕔ�ɂȂ���̂����m��Ȃ��B��̓I�ɂ����A������w�����w���@�w�Ȃ̋���Ə@�w���O�Ƃ̈�̉������Ȃ̂ł���B�@�w�Ȃɂ����鋳��̖ڕW�������S���N�����t�Ƃ��ė{�����邱�Ƃɂ���A���@�@�@�w���������ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�߂��͓��@�@��h�шȗ��̋���A�k��Δэ��E�����h�шȗ��̋���̗��j�Ɋ��݂Ă��A�@�w����̖����͏[���l�����悤�B�����āA�@��l�͓��R�̂��ƂƂ��ĔV���v������̂ł��邪�A�����ɂ�����̖��_���͂��ł���̂ł���B���݁A�傫�ȎЉ���ƂȂ��Ă����w���Ɍ�����悤�ɁA��w����݂̍�������{�I�Ɋԑ�Ƃ���Ă���B��w���玩�̂����Ƃ���Ă����ɁA�V����w�̒��ɐݒu����Ă���@�w�Ȃ̖��������̏�ɑ��݂��邱�Ƃ������ł���B
�܂ÁA�V����w�ɂ����鋳��̖ڕW�͎s������ɂ���B�����āA�V��Ɍ��������J���L���������s�Ȃ��Ă���̂ł���B�Ƃ��낪�@�w�ȍ݊w�����@�w�̎��H���l����A�K�����c�̖��Ɗւ�肠���ė���̂ł����āA���܂��܂ȋ^��Ɉ�������̂ł���B���̏ꍇ�A���c�̗��O�Ə@�w�݂̍���̊W�����m�łȂ��ƁA�@�w���ǂ��c��������悢�̂��ɍ��f���Ă��܂��A�����ł͏@�w�͕���������݂ɂȂ��Ă��܂��B���ꂪ�@�w�Ȋw���̈�ʓI�ȔY�݂ł��낤���A����A�����̑����炷��A���Ȃ��Ƃ����݂̏@�w�Ȃ͒P�̓��@�@�Ƃ������c�\���҂݂̂�Ύ�ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ��B�Ђ낭���@���c�A���͓��@���w�ɊS�������Ă̐l�ɖ�˂��J�����Ă���킯�ł���B�����āA���ʓI�ɂ���͈����_���肠��킯�ł͂Ȃ��B�@�w�͈�@�̋��`��`���ɏ]���ċ������邱�ƂɌ��肷��̂ł͂Ȃ��A�����̐����ȎƂ���Ƃ��Ă̓��@���l�̋��w�ՓI�Ȃ��̂Ƃ��Č����`�����ׂ��ł���Ƃ������{�I���_�ɗ��Ȃ�A����͌����Ĕߊς��ׂ����Ƃł͂Ȃ��B
�@�������A���̂悤�ȗ��z�́A���c�̗��O���m���Ɂi�{���I�ȈӖ��ł́j���c�Ƃ��Ď��H����Ă���ꍇ�ł����āA���c�̎��H�Ə@�w�̌�������������ݍ����Ă��Ȃ��ꍇ�͔��Ȃ��ׂ��_���ė��悤�B�܂��A���c�Ƃ��Ă̖ڕW�E�j�̂Ƃ����悤�Ȃ��̂��@��̊w���ɓ`���čs�����ʂɐ݂��Ȃ���A���݂̂܂܂ł͋�̓I�ȏ@��̗��O��`���čs�����Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���̏イ�ȁA�@�w�ɂ����鋳��I���ʂ��y������Ȃ�Ώ@�w�͑������Ȃ��Ă��܂��A�����ł��Ȃ��ł��낤���A���c�̗��O�`���ɖ𗧂��Ƃ͍���ƂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���āA���̂悤�ȋ��c�E����Ƃ̊W���ł��ʂƂ����Ӗ��ŁA�@�w�͓���Ȋw��ł���Ƃ����悤���A�@�w���@�w�Ƃ��Ă���̂͏@�w�����Ƃ����W�����������邩��ł���B��Ƃ��Ă��̓_�ɂ��āA��w�����͏@�w�_��W�J���Ă����B�ȉ��A��w�̏@�w�_����ڂ��Ă݂����B
�@�@�@�@�@�@�@�w�_�̓W�J
�@�@�w�_���N�鏊�Ȃ́A�@�w����̓���ȈӋ`�i�܂��̓W�������j��������ɑ��Ȃ�Ȃ��B����́A�@�`�Ƃ������̐�ΓI�ȉ��l�̌n�ɂ��Ƃ������Ƃ����Ă��Ȃ���A�����������ɑ��ΓI�ȁu�w�v�𐄒肷��Ƃ���ɁA�܂Íő�̖��_���͂��ł���̂ł���B
�@�ܘ_�A�@�c�Ō�̐�t�����ɂ���āu�@�`�v�܂��́u��`�v���p�������ʂƓ����ɁA���@���l�̋��w�̌n�𗝉����A�@�`�����r����w�͂��s�Ȃ��Ă������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B���̈ꖭ�����t���w�c���j�v�x�킵���̂́A�O��T��������̏@�`�p�����@�c�̋��`�̌n��^���r���邱�Ƃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��Ƃ������ȔT���ᔻ����o�������̂ł���A�w�j�v�x�͏@�c�̋��`�̌n�𗝉����邽�̌��r�̐��ʂł������B���̂悤�ȏ@�`���r���@�w�̉ۑ�ł��邪�A��������ȍ~�̕����w���̔��W�ƂƂ��ɁA�@�w�ɂ�����w��A�����̕��@�����ƂȂ����B
�@�w�⌤���Ƃ����T�O�����m�ɂȂ����̂́A�ǂ̕���ɂ����Ă���������Ȍ�̐��������̉e���ɂ����̂ł��낤���A�]���̏@�`�p���ɑ��Ċw����֎������͕̂����w�ł���@���w�ł������B����͏]���]��ɂ��_��I���Ђ̂��Ƃɂ������M�E�@�����q�ϓI�ɔ����̂��Ƃɔ��炷���Ƃ��ł���Ƃ������͂������Ă����B�����w�͕����̗��j�E�����̎v�z�̓W�J���q�ϓI�ɂƂ炦�邱�Ƃő傫�Ȍ��т��ʂ������A����͂����܂ŋq�ϓI�Ȍ�����ڕW�Ƃ�����̂ł������B
�@����A��ʓI�Ɍ����āA�`�����c�̏@�w�͓`�����p�����ė������A�ߑ�I�K�������ڊԐڂɗv������Ă������Ƃ͔ۂ̂Ȃ��ł��낤�B����𐄐i�����̗��R�́A���琧�x�ł����āA�����Ă̒h�т���w�тɁA�����Đ��w�Z�߂ɂ���w�ւ̏��i�ւƐi�ނ����ɁA�]���̔��R�Ƃ����̌Ă���@�恨�@�w�ւƒ蒅���čs�������̂Ƒz�������B���̊ԁA�K���������ꂪ���o�I�ɍs�Ȃ�ꂽ���ɂ��Ă͎�̋^������邪�A�����w�̕��@�̒����當���ᔻ�A���j���q�̕��@�Ȃǂ��Ƃ���ꂽ�_������A�������@�Ɋw��I���삪����������Ƃ������ł��낤�B
�@�������āA�w��I���삪������čs�����ŁA�{���I�ȋ����I����̐�ΐ��ƁA�����I���ʂƂ̊W����莋����ė����Ƃ���Ɂu�@�w�_�v�����Ƃ���Ă����Ղ��������̂ł͂���܂����B�e�@�ɂ����ď@�w�_�����Ƃ���Ă��钆�ŁA���a�P�P�N�ɐ^�@�ɂ����ċ��q��h�����w�^�@�w�����x�킵�Ă���B
�@���@�@�ɂ����čŏ��ɏ@�w�_�\�����͎̂R��q�����ł���A�����ň��i�ٓN���ł���B�i�w�������R�搶�ËH�L�O�_���W�x�����u�@�w���ρ��ᓙ�͔@���ɏ@�w���ׂ����v���a�P�T�N�v�u�@�w���ρv�@�i���i�ٓN�t�j�Ɓw�@�w�̍��{�I����x�@�i�ēc�~�Y�t�j���i�t�̘_�_�̒��S�́A�w�@�x�Ɓu�w�v�Ƃ̔��ȓ����Ƃ����_�ɂ���A�g�D�I�@�w�̎����A����Αg�D�@�w����Ă���B���͎R��q���u�@�w�̖{���Ƃ��̓W�J����v�i�M�l�R�S���j�u�@�w�ɉ����錻�݂̏������ƌᓙ�̑ԓx�v�i�@�w�����n�����j�A�^�쐳���u�@�w�g�D�_�v�@�i���w��
�W�U���j�����Q�Ƃ��A�u�@�w�Ƃ͓���@���̋K�͊w�Ȃ�v�Ə@�w���K�肷��B�����A�����̉M��E�d���E�q�����ɂ��A�u�@�v�������ɂ����āu�����i�l�̈Ȃđ��ԓ��j��v�i����j�̖Ԗڂ��ギ��@���A��̖@��`���V�ɏ]�ӈӋ`�j�v�̈Ӗ��������̂ŁA�w�@�Ƃ͑��ɂ̈��x�ł���ƌ��_����B�]���āA�u���Ȃ̑������ɗv�Ƃ���Ƃ���̋�����@��Ə́v����̂ł���B�Ƃ��낪�u�@��v�ɑ��w�@�w�x�Ƃ����ꂪ�p�����Ă����̂́A�u�ߗ��̏����Ȋw�I�����ɑ���Љ�I�S�̍V�g�ɔ����A�Ȋw�̈Ӌ`�ɉ��Ďg�p�����w�̋`���A�@��̌��r�ɍۂ��Ă������ӎ�����ꂽ���f�x�ł����āA�u�@��ɑ���w�k�̑ԓx���]�O���r�I�M�I�̉�I�Ȃ���̂��A���w�I�ᔻ�I���^�I�Ȃ���̂ւƈڍs����X�����ꗬ���Ă���v���̂ł���Ɨ�������B�������A�u�w�Ƃ��Ă̏@�w���L������ꐫ�v�Ɋӂ݂āA�w�@�w�̌��r�ɓ����ẮA�@�̊w�Ƃ��Ắq�@�w�̗���r�ƁA�@�̊w�Ƃ��Ắq�@�w�̌������@�r�Ƃ́A��]�̊W�Ɂv���邱�Ƃ��m�F����B
�@�ȏ�̂悤�Ȏ葱�����o�āA�@�w�Ƃ͓���@���̋K�͂����r����w��Ɨ�������̂ł��낤�B�ȏ�̂悤�ȏ@�w�̋K�肩��@�w�����̎�肪�u�@�̋��`�M���A�@���@�|�̑���I�����v�ɂ��A����͌��ǁu�@�c�̐l�i��S�I�ɓI�m�ɔc�����A���̏@���I�̌��𖡎��̓����āA�Ȃē���@���ɁA�Q��Ƃ���ȊO�ɏ@�w�̋��ɖړI�͂Ȃ��v�Əq�ׂ�B�����āA�@�w�̔C���͈ȏ�̈Ӗ��Łu�@�w���邱�Ƃɂ�����炳�ꂽ�����鐬�ʂ�ʂ��āA�L������𑼐l�ɓ`�ցA�Љ�ɍO�ʁv���邱�Ƃł���ƌ��_����B���̂悤�ɂ��āA�@�w�̖{���̗̓��ɕt�����ĎЉ�I���H���v�������Ƃ��A�@�w�����́u�{���I�{�ԕ���v�Ɓu���H�I���p�I����v�Ƃ̓�ނɑ�ʂ����Ƃ���̂ł���B
�@�����ŁA�{�ԏ@�w�́A�]���A�����_�Ƌ����_�ƂɊ�Ă����@�`����x�w�I�A�����j�w�I�����ɂ���Ė����ė����̂ŁA�u�Ăѕ��c�Ə��@�h�Ƃٖ̋��s���̘A�n���m�ۂ��ׂɉ������̐V�Ȃ錤�����삪��w�I�w�͂��v�������v�̂ł����āA�v�z�j�I�����j�I�𖾂ɂ���Ď��@�̗���ɍ��{�����̘_���I�J�W�Ƃ��Ă̗��j�I�K�R�������o�����Ƃ��ڕW�ƂȂ�ƌ���B���̂������p�@�w�Ƃ́A�@���҂Ƃ��Ă̐M�I����ƁA�����҂Ƃ��Ă̒T���I���ꂪ�ꉞ�͕��s����ɂ��邩�̂悤�Ɍ����Ă��A���҂͒��a�����K�v������Əq�ׂ��A��҂̌����҂Ƃ��Ă̒T���I����Ɩ��ڂɊW���čl�����Ă���悤�ł���B�����A�u�N�w�I�����A���k�l�̑̌��A���c�̗��j�A�ߑ㕶���̏��̈�ɉ�����Љ�i�w�j�I�S�v�̎l�_���w�����߂̂悤�ŁA�����������ď@�w���߂���u��̊w�I�H��v���s�Ȃ���ׂ��ł���Ƃ����Ӗ��̂悤�ł���B
�@���āA���i�t�͐^�쐳�����̗��j�@�w�E�g�D�@�w�E���H�@�w�ɂ��g�D�@�w�̌����ɂ���ӂ�Ă��邪�A�̐��v�ِ搶���c���w�����̕K�v�����钆�ŏ@�w�̑g�D�I�����ɂӂ�Ă���B
�@���搶�́u�c���w�̏@�w��ɉ�����ʒu�v�@�i�w���@���l���w�̌����x�V�V�Łj�ŏ@�w���������{�@�w�E���j�@�w�E����@�w�̎O����ɕ����Ă���B���{�@�w�Ƃ́u��@�����̍��{�@�T�ɂ��Č��r����w�ł���v�ƋK�肵�A��̓I�ɂ́A�u�@�،o�̓N�w�y�я@�����������A���@���l�̋��`�E�v�z�E�l�i�E���_����c������v���Ƃ�ړI�Ƃ���B���̂��߂̕����w�I����̕K�v������̂ł��낤�B���j�@�w�Ƃ͐��l�Ō㌻��Ɏ��鏔�t�S�Ƃ̏@�w���w�����̂ŁA�@�w�j�̕���ɓ���ł��낤�B����Ɍ��`�E�P�e�E���E�g�D�E�މd�E�_���E�̌��E�@�ؐ_���E�j�`�̖��_���f���Ă���B����@�w�Ƃ͎��ԓI�ɂ͌���l�̗v���ɉ�������ԓI�ɂ͐l�ނ̑S�l�i�I�v���ɉ�������̂ł��邱�Ƃ������������̂łȂ���Ȃ��Ȃ��Ƃ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ�B�u����@�w�͎��㐸�_���w������ׂɎ���Ƌ��ɐ����Љ�_��P������ׂɁA������Љ�ɑ����Ĕ��W�𐋂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ɍ��{�ɓ��˂���Љ�̗v���ɉ��ցA�X�ɏ����Ɍ����ĕ��ՑÓ��Ȃ鐳�n�I���W�𐋂��ׂ��ł���B�v
�@���搶�͂����ɁA���{�@�w�̌����̕K�v���A���̕����w�Ƃ��Ắu�c���w�v�̕K�v������������̂ł���B
�@�ēc�~�Y�t�́u�@�w�̍��{�I����v�@�i�w�]�������搶�ËH�L�O�_���W�x�����j���قڈ��i���̘_�_�Ɠ����ʂɗ����Ă���B�_�_�͏@�w����ʂ̊w��I���i�ƈقȂ����I���i�������̂ł���̂ɁA���ꂪ�^�ɗ�������Ă��Ȃ����߂ɁA�g�D�@�w�A�ᔻ�@�w�A�����@�w�A���{�@�w���̗�������u�@�w���������Ȃ���@�w�I�ɍl���Ȃ��ŁA�N�w�I�ɉȊw�I�ɍl���悤�Ƃ���X����������v�Ƃ��A�u�@�w�����@�w�I�v�����Ȃė�������v���Ƃ̕K�v��������̂ł���B���́u�����Ȍ�A��ʂ̎v�z�w��̔��B�ɔ��Ȃ��āA�e�@�h���c�̐^����ُ���K�v����A��ʊw�p�̌������@���̗p���Ċw�I�g�D�̌n���ւ̎��݂��s�Ȃ���Ɏ������v�Əq�ׁA�����́u��Ƃ��ăL���X�g���ߑ�_�w�̐����_�w�i���j�_�w�j�A�g�D�_�w�A���H�_�w�̎O���Ȃ̕��@���̗p���Ă�����́v�ł��邱�Ƃ��w�E����B�����ɁA���j�w�I�A����w�I�A�����w�I�������@�i���j�@�w�A���{�@�w�j�A�N�w�i�@���N�w�j�I�������@�i�g�D�@�w�j���̈�ʂ̊w��̕��@����������Ă��邪�A����͕⏕�I�Ȋw��I����Ƃ͂Ȃ蓾�Ă��A�@�w�Ǝ��̕��@�Ƃ͂Ȃ蓾�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���̂Ȃ�A�u�w��Ƃ͑̌n�����ꂽ�m���������̂ł���A�l�ԗ��������{�Ƃ��鏊�̂��̂Œʏ�Ȋw�i�o���Ȋw�j�ƓN�w�ɓ��ʂ���Ă���v���A�N�w�́u�������W�Ԃ��A���肻�̂��̂������v���悤�Ƃ���_�ď@�w�ƑS���������A�u�o���Ȋw�i�@���w�A��w�A�|�p�w���j�̔@������̑Ώۂ���������v�_�ɂ����Ď��ʂ��_�����邪�A�u�@�w�̌����Ώۂ��A�@���I�̌��̐��E�́h�M�S�h�Łv����A�u���̑Ώۂ̔c���͓����̌����䂪�g�Ɏ����ɂ���Ĉׂ����v�_�œ��ِ���������ł���Ƃ���B
�@�������āA���͏@�w�̑Ώۂ͐M�S�̐��E�ł���A�����w�E�N�w���͂��̐M�S�̐��E���O������⏕�I�Ȗ���������݂̂��Ƃ���̂ł���B
�@���i�t���ēc�t���A�v��Ώ@�c�̏@���I�̌����M�S�ւ̎Q�����@�w�̖������Ƃ��A���̍����I�ȐM�S�̐��E��N�w�E���j�w���̔F���Ǝ~�g���čs�����߂Ɋw��I������s�Ȃ��̂��@�w�ɂ�����w��ł���Ƃ����l���̂悤�ł���B�������A�����ɂ����̌��Ƃ͉��Ȃ̂��낤���B���l�ɂ͂������ɖ@�،o�̐F�ǂƂ�����X�}�v�̓���y�ʑ̌��̐��E�����邱�Ƃ͎����ł���B�������A����͑̌��̂��߂ɑ̌����ꂽ�̂ł͂Ȃ����ł���B���@�ɂ�����l�Ԃ̐������i�����j������Ă������K�R�̌��ʂƂ��ĎЉ�ɑ��鐹�l�̓������������l�̖��Ƃ��ĒNj������A�@�،o�̐F�ǂƂȂ�̂ł���B�]���āA���l����s��F�̉����ł����Ă��A��X�}�v�̐������i�����j�Ƌ~�ςƂ����_�ɂ����āA���Ր�������Ă���̂ł���B�l�Ԃ̎������Љ�ƘA�q���A�M���l�̐����������肵�čs�����̂ł���ȏ�A�M�͐M�̌��Ƃ����_�I����悤�ł͂Ȃ��A���܂��܂ȖʂƂ̐ڐG�������̂ł��낤�B�����A���v�z�i�����̎Љ�����Ă�����̂��A�����łȂ����̂��j�Ƃ̐ڐG�������A�M�҂̎Љ�I�����������肷��M�̍\���I�̌n���K�v�ƂȂ�Ǝv����߂ł���B�����āA�܂����w��⏕�I�w��Ƃ��ĉ��p����Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��B
�����ɖ��_���c����Ă���̂ł͂���܂����B
�@�@�@�@�@�@�]�������搶�̏@�w�_
�@���A���c�͌o�ϓI�ȑŌ��������A���_�I�ɂ����h�𗈂����B���a�Q�R�N�ɑ�P����@�@���w�������\���J���ꂽ�̂��A���̂悤�Ȕw�i���������Ǝv����B�ݖ�̏��t�����\�҂̒��S�ƂȂ��Ă��邪�A���̒��ɏ@�w�_�����t�ɂ���čs�Ȃ��Ă���B���J�쐳���t�͏@�w�̐V���݂ɂ���Ă��̐��_�����c�̒��S�ƂȂ��čs���˂Ȃ�ʂƏq�ׂĂ���i�u����@�w�̉ۑ�v�@�w���@�@���w�������I�v�x��Q�W�����j�B�n�ӓ���t�́A�����鑊��ɂ���ď@�w�g�D���l�̌`�������̂ł͂Ȃ����Ƃ��āA���i�o�Ɓj�p�A��ʕ����p�A�m���K���p�A�h�M�k�i�݉Ɓj�p���l���A�Ⴆ�ΐ��p�͋����E�ϐS�i�@�j�A�����E�����E�@�|�E�M�s�i�l���@�j�A�����E�����E�@���E�M�s�E���S�i�ܕ��@�j�́w�g�������ȂĂ��邱�Ƃ��ł��������ꂽ���̂̂悤�Ɏv����x�Əq�ׂĂ���i���I�v�u�@�w�̑g�D�ɂ��āv�A�j
�@���s�C�G�����́A�u�l�Ԏv�z�̔��B�́A�@���I�M���N�w�I�v���ցA�N�w�I�v�����Ȋw�I�m���ւƓW�J�������̂ł���Ƃ́A�N�w����ɋ��ꂽ�Ƃ���ł���B�R�������錩���́A�l�Ԏv�z�̓��ʓI�`�Ԃ��炢�ւA�O�ʓI�`�ԂƂ͋t�ɁA����͉Ȋw�I�m���̋ɂ܂�Ƃ���N�w�I�v���ւƐi�݁A�N�w�̋ɂ܂�Ƃ���X�ɏ@���I�M�ւƓW�J�������̂ł͂Ȃ��낤���v�Əq�ׁA�u���敧���́A�m�����d�A�}�Ă��Ȋw�I�ɉ𖾂���Ƃ������͂Έ��̉Ȋw�I�@���v�ł���A����ɑ��u������N�w�����A�ϗ�������Ƃ����v�̂���敧���ł���B�܂��u������ϗ��I�A�N�w�I�����ɂ���Ă��A�Ȃ��l�Ԃ̏@���I�v�����[�����Ƃ��o�����v�@�u�����i�@�������v������A����ɉ������̂��A��敧�������W�J���ꂽ�~�ϋ��Ƃ��Ă̏�y���v�ł������B�@�R�̗�������ސe�a���u���ϗ����ɗ��r������ɖ{��̐�ΐM�������v���u�m���̎ܔM�Ɉ˂��Č͟�����Ƃ��������́A��ɖ{��̎��J�Ɉ˂��ď@���Ƃ��Ă̐������Ƃ肩�ւ����v���A����́u�m����ے肵�A�����ے肵���ޕ��ɏ@���̗̈�����̂悤�Ƃ����v���ׂ����B���̂悤�ɂ��āA�u�����ɉ�����m�ƐM�A�����Ǝ����A���݂ƒ��z�Ƃ̖�肱���A���l���w�̊j�S���Ȃ����̂ł����āA�@�w��ɉ�����ۑ�ł���v�Ƃ��A����́u�@���̗̈�ɉ����Ċm������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ�B�܂�A���̂悤�ȏ@�w�̉ۑ���@���̗̈�i�Ȋw��N�w�łȂ��j�ɉ��čl���˂Ȃ�ʂ��Ƃ��咣���Ă���i���I�v�u�@���̗̈�Ə@�w�̉ۑ�v�j
�@���i�ٓN�t�́A�O�Ɍf�����_�̉����Ƃ��āu���@�@�w�̎�̐��v�ɂ��Ę_���Ă���B
�@�Γc�䋳���������u�@�w�����v�\���A�@�w���ΏۓI�Ș_���Ŏv�l��i�߂邱�Ƃ͎��Ȃ̖��Ə@�w�Ƃ�藣�����ʂɂȂ�Ƃ��A�@�w�͎��Ȃ̖�肩��o��������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��Ǝ咣���Ă���̂����ڂ����B
�@��P����@�@���w�������i���Q�R�N�P�P���J�Áj�ł́u�@�w�̏����v�Ƃ������_��s�Ȃ��Ă���̂ł����Ă��̑��S�̂ɏ@�w�_�̖�肪���������C�^���������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���āA���̂悤�ȏ@�w�ւ̗v�]�ɉ����A�@�w�̌��Ж]�������搶����̓I�ȏ@�w�̕��@�ƍ݂�����������邱�Ƃɂ���ď@�w�̐������l�@����Ă���B�i���w��P�Q�R�������A�]�������搶��e�u�@�w�e�_�v�j�����āA���_���u���āv�Ƃ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B�u���ȂɊ����ˏƂ��ꂽ���c�̐^���_�i�S�l�S���j��ΏۂƂ��āA����ɗ��r�������Ȃ̐M�I�̌��̕��@�ɂ���āA�@�����l�̐��E�����o�����@�ƋK�͂Ƃ��w�Ԋw�ł���B�v
�@�]�������搶�̏@�w�_�́A�@�w�e�_�̑��u�Ƃ��ė�����w�ɂ����ď��a�Q�T�N�x�ɍu�q���ꂽ���̂ŁA�i�P�j�@�w�̖����v��������́A�i�Q�j�@�w�̗ތ^�A�i�R�j�@�w�Ƃ͉�����A�̎O���ɕ����ču�����Ă���B
�@�܂��i�P�j�@�w�̖����v��������̂ɂ����āA�u�@��v����u�@�w�v�ւ̌ď̂̓W�J�������Ȍ�s�Ȃ�ꂽ���Ƃ́u�@�w�v�����S�ɐ��������A�{�����e���I�m�ɔF������Ă��Ȃ����Ƃ����{�̌����ł���ƂƂ��ɁA�u�@�w�v�̐����ւ̋��Ɠw�͂����������Ƃ�F�߁A�Q�_����u�@�w�v�̐��i���l�@���Ă���B���ɃL���X�m���u�_�w�v�ɔ�����T�O�Ƃ��āA�u��E���Q���̖{���I�Ȋw�̋�ʂ𖾂��ɂ������Ƃ̗v���v�����������Ƃ��炢���A�_�w�ɑ��u�@�w���A���ꎟ���̐��E�ɁA�~�ςƉ�E�Ƃ��������镧���̖{�����\���ł���悢�v�̂ł����āA�@�w�́A����̏@���̌��̔��Ȕᔻ�ƁA�����ɋq�ϐ��E�_�����̊m�����v�������Ƃ���B���ɕ����̒��ōl����A�@�w���@�h�w�Ƃ��đz�肳��Ă���Ȃ�A�u�T�O�I�ɂ͑��݂��邪�A���̂̂Ȃ����́v�ɂȂ�Ƃ����B�e�h�̐_�w�����̐��E�̐_���w�̑ΏۂƂ���̂ɐ_�̑��݂��������Ĕc���邱�Ƃ��\�ł���̂ɑ��A�@�w�́A�ꎟ���̐��E�Ɋw�̑Ώۂ�u�����߂ɁA�u��q�z���鉿�l�̋��n�����߂鐫�i���琶����Ǝ������A�w�̕��@�ƑΏۂƂ����ʁv�����Ȃ��_�ɓ��ِ�������̂ł͂Ȃ����Ƃ���B�����ł���ȏ�A�@�w�Ɏ��̂���邽�߂ɂ́A�u�@�h�I���i���z���������̍����I����ɁA�}�Ă��A�ꂷ���ے��z�I�̈Ӌ`���A�@�w�ɔ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�B�v�Ɛ����B���̂悤�Ȋϓ_����A�u�@�w�́A�e�@�h�̊w���̕��@�A����̑��ق͂����Ă��A���̖ړI�ƑΏۂƂ͈�v�ł���A�e�@�̏@�w�́u���c�̑̌��������E�Ɉ�@���邱�Ƃ�v������_�ɉ��Ĉ�ł���B�v�Ƃ��A�u�e�@�c�Η��̌����ƈꕧ�@�w�ւ̗��z�v�Ƃ̊Ԃɉ�݂��閵������������r�́A�w���c�ւ̍�������A��Γ���A�̐M�ɂ���Ǝv���B�x�Əq�ׂ�B
�@�������āA�搶�́u���@�͉���̏@�̌��c�ɂ����炸�A�����t�ɂ����炸�v�@�i������l������j�Ə@�c������ꂽ�̂́u�@�h�w�I���i�����錾�v�ł���Ƃ��A�֘A�̈╶�����p���āA���̂悤�Ȍ��_���o���B�u���@���l�̏@�w�͑����{���ւ̓���ł����āA���̏@�w�̐��E�����@�̏@�w�̐��E�ł���A�܂��䓙�̏@�w���������ɓ��ꂷ��Ƃ���Ɋ�Ղ�����B���悤�ɍl���Č���ƁA�e�X�̏@�w�͊e�X���h���I�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�����֓��ꂹ��Ƃ���@���I�w�͂ɂ������ł���B�v
�@�����ŁA����Ȃ�u�@�w�͊e�X�̏@�c���č݂�̂ł��낤���v�Ɣ��₵�āA�u�@�w�͕�ۂ����z�����Ƃ���ɍ݂�Ƃ��������A����͌��������ĉ]���A�\����̏@�w������Ƃ������Ƃł���B�\����̏@�w�͕��c�̐^���_�̔c���Ɠ����ɐ�����̂ŁA���c���đ�����̂ł͂Ȃ��B�v�Əq�ׂ�݂̂ł���B���́u�\���v�Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��A�e�@�𑊑ΓI�ɂƂ炦���Ƃ���Ȃ�A�@�w�̔\���ꐫ�͋t�ɉ_�U�������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�₪�N���悤�B���Z���������_�S�P���́u�@�w�_���c�v�Ŗ]���搶�̏@�w�_���Ƃ肠�����_�_�������ɂ���̂ł��낤���B
�@���āA�搶���@�w���l����Ƃ��A�搶���g�ɓ�̗v�����������̂ł͂���܂����B���̈�͕����e�@���������d�˂ē���ł����A���@���܂��e�h�ɕ������čs���Ƃ��������ł���B�����ɁA�����k�Ƃ��Ă̔\����̗v�����������̂ł͂Ȃ����B��ɂ͏@�w�̓`���I�������@�͉ʂ��đÓ��Ȃ̂��Ƃ����^��ł������낤�Ǝv����B
�@(2)�@�w�̗ތ^�͏]���̏@�w�����@�ɑ��錟���ł����ĘZ��z�肵�Ă���B�@�싳�I�ԓx�A�A�c�q�I�ԓx�A�B���ÓI�ԓx�A�C�g�D�I�ԓx�A�D�ᔻ�I�ԓx�A�E�n���I�ԓx�ł���B�����A�搶�͏]���s�Ȃ��Ă����@�w�����̕��@���@���D�܂ł̕��@�Ɏ��Ă���B�����āA���ꂼ��Ɍ������@�Ƃ��Ă̗����͂����Ă����ׂ�����̂ł͂Ȃ����Ƃ���B
�@�@�싳�I�ԓx�́A�u�@��`���̋��w�������I�Ɋm�ہv���悤�Ƃ��邪�A����͈�ʂł́u��ʕّ`�ɖz���v���邱�ƂɂȂ�A�܂��A�u�����P�e�̊w�v�ƂȂ��Ĕᔻ�Ǝ���Ƃ��������ƂɂȂ邱�ƁB
�@�A�c�q�I�ԓx�́A�u�@�w��̗��r�_�c�̐^���_�Ȃ鉼��ɒu���A���̊ϓ_����A�@�w��̏�����ᔻ�_�c���A�g�D�I�Ɍn���I�ɑc�q�v���悤�Ƃ�����̂ł��邪�A���ۂɂ͂����̘_�c�́u�e���̊����̎���I�ᔻ�c�̖��ɉ��ĉ�����Ƃ������݁v�ƂȂ��Ă��܂��A�u�`�w�I���ʁv�͔��g���Ă��A�{����Y�ꂪ���ł��邱�ƁB�i�����ɕ��c�̖@�����o�I�Ɏ�̂���̐ӔC�ƌ��E�����炩�ɂ���Ȃ���A���c�̖@�͜��ӓI�̎�ɂ�����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�₪�搶�ɂ������̂ł͂���܂����B�����āA����͓��@�@�w�V�O�O�N�̊w���j�����̎���ʂ��Ĉ�w�^���[�߂�ꂽ�̂ł͂���܂����B�j
�@�B���ÓI�ԓx�́A�u���c�̍��{�ɕ��A�����^���Ȃ�Ƃ���l�����ŁA��T�͕����w�I�{����]�I���@�ɂ��A�o�T�c����B��̌����ΏۂƂ���B�v�@�u�����ɂ��Ĕ�c���ׂ��ł͂Ȃ����A���{���^���ł���Ƃ���ԓx�́A�K�����S�ʓI�ɍm�肳���Ƃ͌���Ȃ��B�����Ƃ��A�j�I�ɑk�����ė��j�̐i�W������_�ɁA���{�I�Ȍ��ׂ�����̂ł͂���܂����B�v�Əq�ׂĂ���B���́A���{���K�������^���ł���Ƃ͂����Ȃ��Ƃ����Ӗ��͂ǂ������Ӗ��Ȃ̂ł��낤���B�搶�́u�䓙�����ݓ�����͉̂ߋ��̌��݂łȂ��āA���݂̉ߋ��ł���v�Ƃ��āA�u�ߋ������݂��K�肷��̂ł͂Ȃ��A���݂����݂��K�肷��̂ł��낤����A���ÓI�ԓx���炷�鍪�{�@�w�v�����Ő^���͈��߂Ȃ��ł��邤�Ƃ���B�����āA�u�ĊO�A���{�@�w�����߂āA�ŐV�@�w�̌��ʂ��v��������邩���m�ꂸ�A���ꂪ�]�܂����Ƃ����B�i���炭�����ɐ搶�̏@�w�ɑ��鍪�{�I�ԓx������̂ł͂Ȃ����Ǝv���邪�A���{�@�w�ƌ��ݓI�݂���̖��͑傫�Ȗ����͂��ł���ł��낤�B�j
�@�C�g�D�I�ԓx�́A�u���㐸�_�ɗ��r���āA���̊ϓ_����Љ�w�I�ɁA�Ⴍ�͔�r�@���w�I���@���ȂāA�@�w���q�ϓI�ᔻ�ΏۂƂ��ĐV����I�@�w��g�D����Ƃ���ԓx�v�ł���Ƃ���B�����́u�Ȋw�Ƃ̖����̒����A�Љ�I�v���ւ̑Ó��A�@���w�I�����̎����v�����v������悤���A�����̕��@�ɂ���āA�g�D�I�@�w�����������Ƃ��Ă��A����͗��_�@�w�ɂƂǂ܂�̂ł͂Ȃ����B�Ȃ��Ȃ�u�@���I�����͎��Ȃ̐M�I��M�ɂ��v����Əq�ׂ�B�i����ΉȊw�I�������@�A�g�D�I�@�w�ւ̎u���ƐM�I��M�Ƃ̊֘A�̖��ł���B�j
�@�D�ᔻ�I�ԓx�́A�u���Ȃ̏@���I�M�܂��͏@�w������̉b�m�ɂ���Ĕᔻ���A�܂��͎���̗ǐS�ɂ���Ĕ��Ȃ���Ƃ�����̂ł���B�v����u���ɑg�D�I�ԓx�ƕ\�����ł���������ԓx�ł͂��邪�A���͉��^�I�ƂȂ�A�ϔO�I�ɑ��āA�M�̊m���ɏ�Q��^����v���ꂪ����Ƃ���B
�@�@�A�B�͂�������`���I�ȏ@�w�ɑ���搶�̔ᔻ�ł��낤�Ǝv����B�����A�@�͖ӖڂɂȂ鋰�ꂪ����B�A�͍�����Y��鋰�ꂪ����B�B�͗��j�����鋰�ꂪ����Ƃ���B�C�D�͂���ߑ�I�w�₩��̏@�w�ւ̃A�v���[�`�ł��邪�A�C�͔�r�@���I���@�A�@���Љ�I���@�̓����D�͓N�w�I���@�������Č���@�w���݂̕��@�Ƃ��悤�Ƃ�����̂ł��邪�A�@�w�ɂ�����M�Ƃ̊֘A�����ƂȂ�B
�@���������`���I�@�w�A�ߑ�I�w��ɂ����@���A��������@�w�̍����ɂ����Ė������ł��Ȃ��Ƃ���Ƃ���ɁA�搶�́u�n���@�w�v�_���s�Ȃ���̂ł��낤�B
�@�搶�́u�@�w�����̍��{�����́A�u�@�w��L������́A��������A�M��L����҂̂݉\�ł���v�Ƃ���B
�@�u�M�Ȃ��҂��@���w�҂Ƃ͂Ȃ蓾�A�N�l�Ȃ炸�Ƃ��N�w�̌����҂��蓾�邪�A�@�w�́A�M�҂݂̂��L��������ł���ƍl������v�Əq�ׁA�u�@�w�́A���Ȃ̐M��ΏۂƂ���w�ł���Ƃ���A���Ȃ����Ȃ��@�w���邱�ƂŁA�n���̎��ȊO�ɂ͂����\�����邱�Ƃ͔\���Ȃ��v�ƁA�D�n���I�ԓx���@�w�̍����ł��邱�Ƃ��咣����B�����āA��������{�Ƃ��āA�@���D�Ɏ��鏔���@����g����Ȃ���Ȃ�ʂƂ���B�����āA�u�����̏@�w�́A���M�I�Ȃ�Ɠ����Ɏ���I�ɁA�Ȋw�I�Ȃ�Ƌ��ɔ��ȓI�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�����Ƃ��A���{�I�����ł���M�ɁA����I�q�ϐ��^����v���Ƃ��v�������B�����A�u����ɗ��r�v����ׂɁu�@�w�̕��Ր��v���v������A�u���̑Ó���ێ��v����ׂɁu�w�I���@�v���v�������Ƃ���B
�@�������āA�i�R�j�A�u�@�w�Ƃ͉�����v�ɂ����āA�ȏ�̍l�@����A�u�@�w�̗ތ^�v���R�ɋ敪����B�����A�P�u�@��̊w�v�Q�u�w�I�@�w�v�R�u�n���@�w�v�ł���B�P�@��̊w�́A�����̇@�싳�I�ԓx�i�`���@�w�j�A�c�q�I�ԓx�i���`�@�w�j���Ђ�����߂āA�����͖��ᔻ�ɕ��c�ƈ�@������ςɗ����Ă���u���������Ƃ��Ă̋��`��c�T�o�T���v�̏��^�̑Ώۂ��u�����q�ϐ��Ȃ��l��ρv�ɂ���ĔF����������ɂƂǂ܂�Ƃ���B��w�I�@�w�Ƃ��āA�����̇B���ÓI�ԓx�i���{�@�w�j�C�g�D�I�ԓx�i���_�@�w�j�D�ᔻ���ȓI�ԓx�i�ᔻ�@�w�j�͂��ꂼ��j�I���@�A�Љ�w�I���@�A�N�w�I�ȕ��@��p���āu�A�[�I�Ɋw�I���@�Łv�@�u�Ȋw�I�ɏ������悤�Ƃ���v���A�`�A���̔F����ς��l�Ԃ��畂������Ȋw�q�ł��邱�ƁA�a�A�B�C�ɂ��Ă����A�u�@���I���l�̖����q�ϊE�̎��ۂƂ��ď�������Ƃ���X���ɂ���v�_�ɂ����ď@�w�ƌ����Ȃ����ƁA�b�A�D�ɂ�����ᔻ�┽�Ȃ́u���Ȃ̏@���I���l�̖��ł��邪�A���̔F����ς͑����Ɏ�q�I�v�ł����āA�B�C�Ƃ̌��E�����炩�łȂ����ƁA�̗��R�ŏ@�w�I���@�Ƃ��Č��ׂ������Ƃ��w�E����B
�@�������āA��O�́u�n���@�w�v�����A�@�w�̗v���ɓ�������@�ł���Ƃ���B�u�n���@�w�Ƃ͐l�ԓI�ȑn���ł����āA���Ȃ��ꎩ�̂����̑̌��I�ȕ��@�ŏ@���������J��g���A���o���čs�����Ƃł���B��̓I�ɂ����A�w�̑Ώۂ́A���Ȃ̏@���̌��ɋ���ꂽ���c�̑S�l�i�S���`�ł���B�v�@�u���̐��E��n�����邱�Ƃ́A�P�Ȃ��m�̊w�ł͂Ȃ��A�����Ƒ̌����l�Ԃ̑S�\�𑍍��~�g�������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B����̑̌���̌n�Â���L�q�ƁA����̑̌����X�ɋ����K�͂Ƃ́A��ɋ��߂��A��ɑ����Â����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�w�Ƃ͍s�Ȃ�Ƃ��������������Ȃ��A���̏@�w�͕s�f�̏@���s�ł���Ƃ������悤�B�v
�@�������āA�����Ɍf�����u�@�w�̊T�O�K��v�i���āj�����_�Â�����̂ł���B�]���搶�̂����u�n���@�w�v�Ƃ́A���Ȃɑ̌�����̌n������镧�c�̑S�l�i�S���`�̌����ł��낤�B����͎��Ȃ̎�̂ɂ���đn���I�ɗ̎ꂽ���̂ł��邪�A�����Ɂu����I�Ȋw�I�Ȃ���̂𗠕��Ƃ���l�v�ɂ����đ̌����ꂽ���̂ƍl�����Ă���B�����ɁA�]���̂��܂�Ɏ�ϓI�ȕ��@�ƁA�܂����܂�ɋq�ϓI�ȕ��@�Ƃ�ے肵�āA��̓I�ł���Ɠ����ɁA����ɐ�����l�ԂƂ��Ă̋q�ϓI�F����w�����l�ɂ��@�w�̕��@�����K�v�ł���ƍl����ꂽ���̂ł͂���܂����B�u�@�w�̗ތ^�v�Ɏ����ꂽ�@�`�D�̑ԓx�i���@�j�́A����Ӗ��ŋ�̓I�Ȑ������R�@�w�E�R��@�w�E���i�v�فj�@�w�A�f�Љ�w�E�N�w���̔ᔻ���܂��Ă����̂ł͂���܂����Ǝv���B�����ɁA�]���@�w�̕��@���������Ƃ���ӗ~���������ƂƂ�͍̂l���߂��ł��낤���B
�@����́A�܂��A�]���̏@�w�̐��ʂɂ��Ă̔��Ȃɔ�������̂ł��邩�Ǝv���B�����A�����ȍ~�A�@�w�̒��q�����܂�s�Ȃ��Ă��Ȃ����ƁA�Q�����q���s�Ȃ���悤�ɂȂ�������`���@�w�̕��@���ʂ��ď[���ȏ@�w�̐��ʂƂ����邩�Ƃ����^�₪�������̂ł͂Ȃ��낤���B
���Z�ꖭ�����́u�����@�w�v�Ɓu�̌n�v
�@�]���搶�́w�@�w�ɂ��āx�ɑ��āA�g���R�Z��̎��Z�ꖭ�������ŋ߁u���_�v�S�P���Ɂu�@�w�_���c�\�n���@�w�ւ̗����\�v���ꂽ�B�_�_�́A�]���搶�́u�n���@�w�v�̒�`�ɑ��A���Z���������˂Ď咣���Ă���u�����@�w�v�̗�������̋^����o�������̂ł���B
�@���Z�����͖]���搶�̘_���̕��͂ɂ��Ă��ߍׂ����_���Ă��邪�A�����ł͖��Ƃ��Čf���Ă���U�_�ɂ��Ċȗ��ɏЉ��ɂƂǂ߂����B��P�́A�w�@�w�̌��E�\�e�@�w�͕����@�w���Ō�̌��E�Ƃ���B����܂ł͊g�傳��Ȃ��B�{���̑��Ⴉ��ł���B�x�Ƃ̖]���搶�̘_���̕\���ɑ��A�u�e�@�w�Ƃ́A�@�h�I�Z�N�g�I�Ȃ�����e�@�̏@�w�A�E�E�E�����@�w�Ƃ́E�E�E�����X�c�́u�ߑ��̏@�w�v�̂��Ƃ炵���v�Ƃ��A���̊W���炻���ɂ����u�@�w�v�̊T�O�ɖ���������̂ł͂Ȃ����Ƃ����^����o����B�����A�u�\����̏@�w�v�́u���@�̏@�w�̐��E�v�ł��锤�ł���A���̎��u�����@�w�v�Ƃ͂ǂ�����������悢�̂��A�܂��u�@�h�w���ے��z�����v�@�w�Ɍ��E������̂��Ƃ������Ƃł���B��Q�ɂ́A�u���̍L��ȏ@�w�A��ے��z�̐��E�ɑ��āA�E�E�E���@�@�w�͈�́A�ǂ��Ɉʒu���ĂĂ����̂��A�ǂ�Ȗ�ڂ�����̂��v�A�u���݂��Ă��Ă���e�@�w�͂��ׂĕ��̂������āA�u���c�̐^���_�̔c���v�Ɠ����Ɂu�\����@�w�v�ɓ���̂��B�v�Ƃ����^��ł���B��R�ɁA�w�@�w�́A���Ȃ̐M��ΏۂƂ���w�ł���A���Ȃ����Ȃ��@�w���邱�ƂŁA�n���̎��ȊO�ɂ͂����\�����邱�Ƃ͔\���Ȃ��B�x�Ƃ���̂́A�u���Ȃ̐M�̏�������ɗ����āA����Љ�ɉ������^���Ƃ����̂ł��낤�B����͂��̂܂܁A���̒ʂ�×��̏@�w�҂����̓�������������ł����錾�ł͂���܂����B�v�܂�A�`���@�w��ے�ł��Ȃ��ł͂Ȃ����Ƃ����B��S�ɁA�]���搶���������Ă���w�̌��I���@�x�́u���㐸�_��̂��������i����ɂ�����Ȃ��w�I���@�ԓx�𑍍���g����j�Ƃ������Ƃ��낤���A�u�����@�w�i�Ƃ����j�E�E�E�n���I�ԓx�ő̌��I���@�ŁA�q�ϐ����@�Ƃ����B�����Ɋw�łȂ��Č|�p�ɗނ��邱�ƂƂȂ낤�B�v�Ƌ^����f����B�ȉ��A�Q�_�ɂ��ďq�ׂĂ���B
�@���_�I�ɂ́A�]���搶�߁u�n���@�w�v�ɋ^��𓊂������]���搶���w����ߑ̌���̌n�Â���L�q�Ǝ���̑̌�������ɋ����K�͂Ƃ́A��ɋ��߂���ɑ����Â����˂Ȃ�Ȃ��B�x�Əq�ׂ��߂��A���̎�����@�c�ɂ��������āu�@�c�̖@�،o�̍s�ғI�̌����A�̌n�Â��邱�Ƃ����A�̌��������̂̑̌����Ϗo���ׂ��ł͂Ȃ����v�ƋK�肷��ׂ��ł͂Ȃ����Ǝ咣�����B
�@�ȒP�Ɍ����Ă��܂��A���Z�����́A��X�͏@�c�̖@�،o�̍s�ғI�̌��̓��̂̑̌n�i�s�ғI�̌��̓��̂ɂ��łɑ̌n�͊������Ă���̂ł��邩��j�����̂܂����Ɏ�̂���̂ł����āA��X�}�v�̜��ӂ�p��ł͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�������̂��Ɛ��@����B�����A�M�҂͖]���搶�̎�グ��ꂽ���ƁA���Z�����̎咣���K�������X�g���[�g�ɑΎՂ���̂ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl����̂ł��邪�A���̓_�ɂ��Ă͎��Z�����⏔���ƂƂ��ɍl���čs�������B
�@���āA���Z�����́u�@�w�_���c�v���Ƃ苓�����̂́A���̘_���T�e���Љ�邽�߂����A�ނ���A���a�X�N�ȗ��u�����@�w�v���f���āA�u�@�w�_�v��Nj����Ă������Ƃɑ���h�ӂ̔O����ł���B���Z�����̎咣�́A�u���@�@�w�F�w�j�v�@�i���a�X�N�A���_��Q�O���j�ȗ��A��т��Ă���悤�ɐ��@����B
�@�@�w�Ƃ������̂́A���̏@��ɉ��Ă��̑��Ɗ�������z���A�����̐����ێ��A�����@���������邱�Ƃɂ���B�@����������̓I�ɔ������Ă����ɂ͈�ɑΊO�z���ƑΓ������Ƃ����Ėܘ_�@�̓��O�ɖA��҂͐M�k�̐ۉ����ł��邪���̔C�ɓ�����̂��A�����o�ƁA�m���ł���B
�@���̈�͂��̑m�������炷�鏊�̑Γ����炪����B�V�������@�w�̒��A�ɗv�Ȋj�S�ł���B�{���@�w�Ƃ����ׂ��ł���B�Ȃٖ@�������̕⏕�Ƃ��Č������ʂ�����B��ʂɂ͏@�w�Ƃ��ւΑ����͂��̕⏕���ʂ��闝�_�I�����I�@�w�݂̂��Ӗ����āA�w��ǖ{���@�w���ᒆ�ɂ����Ă͂��Ȃ��B�V�͊w�Ƃ��������ɂƂ�͂ꂽ�傢�Ȃ鎸�ӂł���B
�@���ƂȂ�A�����ɂ���ė��_�ɂ���Đl�������̂ł͂Ȃ��B�@���̑����͑S���{������ɂ݈̂˂�̂ł���B���̑Γ������肵�āA��͑Γ������ɁA��͑ΊO�z���ɁA�O�͕⏕�I�����Ɍ����Ă����̂ł��邩��A�Γ�����̏[�S���ۂ��ɂ���āA�z���A�����A�������̖��ʂ̎��Ԃ������邱�ƂƂȂ�B�l�̖��Ƃ����̂͂����̂��Ƃ��B�{���@�w�͊m���ɖ@�������̒��j���Ȃ�����̂Ȃ̂ł���B�i���_�Q�O���A�P�U�X�Łj
�@�m���Ɏ��Z�����̏@�w�_�̏o���͊w�⌤���̕��@�ł͂Ȃ��A�@�������̉ۑ�ł������B�����A�e�@�̊Ԃɕ��N�����@�w�_���A�����@�w�i�u���̗��_�@�w�ɓ���v�Əq�ׂĂ���j�E���j�@�w�i�u�ߋ��̏����T�����H�@�w�������߂Ă���v�j�E���H�@�w�i�u�z�������ɓ���v�j�����_�����Ă��u�{���@�w�̗̈�͂܂��w��ǖ��ɂ���Ă͂��Ȃ��v�ł͂Ȃ����Əq�ׂĂ���B
�@���āA���́u�@���`���̖{���@�w�v�Ƃ́u�v�������̖{����藬�ʑ��`�������Ƃ���̖��@�̌����ł���B�@���̐����̟Ӊ��Ƃ������Ƃ������ׂ����Ƃł���B�v�Ƃ��A������Ȗ��ɒ�̂����̂��u�O���̌����v�@�i���d���s�@���A�w���O�j�ł���A�u���ꂪ�����̂܂܁A���@�������̐M�s�w�̌䋳���ł���v�Ƃ���B���̂悤�ɁA���Z�����ɂƂ��ď@�w�̊w�́A�s�w�̊w���̂��̂Ƃ��ĎƂ��Ă���A�ȏ�̏��_�͂܂��@���̑�w�̏��i�ɑ��{���I�g���̔�����v��������̂ł��������ł��낤�B
�@���̘_���ł͎��Z�����̌��t�Ƃ��āu�����@�w�v�͏o�Ă��Ȃ����A�u�����@�w�̗��O�Ƃ��̓W�J�v�@�i���_�Q�R���j�Ɏ��M�����B�������A���łɂ��̘_���ŁA�u���X���X�Ƃ������݂̖����@�w���ꝱ���āA�A�M�ɖ��G�ɑ吹�̂��Ƃɂ��ւ邱�Ƃ��B���Q���d���A�]�܂��܂��w�߁A���{���悢��[�����āA�n�߂ċN�ׂ����B�v�Əq�ׂ��Ă���B
�@�u���g�������������v�i���Q�S���A���P�R�N�j�u�����@�w�{���_�̎����Ɩ��\���g���������{�_�A���і��w�I�����v�i���_�Q�T���j�@�u�����@�w�̍j�̓I�W�J�v�@�i���Q�X���A���Q�W�N�j�u����Ȃɂ��Ȃ��ׂ����\����ƑΌ�������̂Ƃ��Ė��w�I�ɍl����\�v�i���R�O���A���R�O�N�j
�@�u���݂̂��߂̋ᖡ�|�����@�w�ɂ�������w�I�̈�\�v�i���R�P���A���R�P�N�j���ɂ����āA�����@�w�̂�����Ƒ̌n�̖�肪�_�q����Ă���B�����āA�̌n�̖��́u�̌n�Ƃ��ӂ��Ɓv�@�i���R�Q���A���R�Q�N�j�A�u�̌n�̓W�J�v�i���R�R���A���R�R�N�j�@�u���Ȕᔻ�̖��_�v�@�m���w��P�P�P���j�@�u�̌n�I�Ό��v�@�i���_�R�S���A���R�U�N�j�ɂ����Ę_�����Ă���B
�@�u�����@�w�̍j�̓I�W�J�v�̊����ŁA�����@�w���K�肵�āA���̂悤�ɂ����B
�@�����A�ł��邾���u����̂܂܁v�A�u�{���̂��́v�A�u�@�c�̂��́v�A�u�@�c�̂��́v�A�u���j�I�Љ�I�ɐ����Ă�����́v�A�u�i���ɐ����čs���ׂ����́v�A�u��ɖ{���I�ȁv�A�u�ł��d�v�ȁv�A�u�ł������ȋ����I�Ȃ��́v�E�E�E������������ړI�����B���o�I�Ɏ��甭�S�A���u�������z�I�M�O�A�l�i����̂Ƃ��A�������ɂ������瓭���ׂ����Ƃ𐫊i�Ƃ�����̂ł���B
�@������A���̎��ア���Ȃ�Љ�ɉ����Ċ��������Ƃ��A����Ƃ��A���グ����̂Ƃ����ӂ��Ƃ͑債�Ė��ł͂Ȃ��B�������ӌŒ肵���̌n��ڂ����Ă͂��Ȃ����A��͖{�����@�c�ɗ���A�@�c���@�c�ɐ����A�Љ�Ɛ��E�ɑS�F���Ɍ��킷�ׂ����߂Ƃ��āA�����ē��炭�ׂ����̂Ƃ��ċK��Â����悤�B
�@���̂悤�Ɏ��Z�����̂��������@�w�Ƃ́A�ߑ������@���l���������ꂽ�����M�̐��E�A����͉�X�̐M�Ɛ����ƁA���@���c�𗥂��鏃���M�̗��O�ł���A�₪�Ă��ׂĂ̐l�ސ��E�ւƊg�債�čs�����O�A���̂��̂���̂��悤�Ƃ�����̂ł���B���̗��O�́u�̌n�v�Ƃ��čl������B
�@����i�̌n�j�͕����Ȋw�ɂ����āA���Ђ͐����Ƃ��͂��悤�ȁA���̖̂{����\�����Ă���B���A���̐����Ƃ����͂����̂́A���̂Â���̌n�I�ɂ���͂�Ă���Ƃ��z�͂�悤�A���Ƃ��Ӗ�����B�E�E�E�킪�@�w�ɉ��Đ����Ƃ����_�Ƃ����͂����̂́A�K���̌n�I�ɂƂ�ւȂ��Ă͂Ȃ�܂��ƐM���邵�A�܂��������ւȂ�����́A��X���g�̏�Ɏ�̉����Ă��邱�Ƃ��ł��܂��B�i�u�̌n�Ƃ������Ɓv�j�@�@�@�@�@���̖{���͌������痝�z�ւ̓��B�ߒ��ŁA�̂����ɑS���f���i���j�A�Ђ��߂�ꂽ�S���J�W���悤�Ƃ���i�s�j�A�S�ɑ��ւ��A�S�����������Ă����i�j�B���ꂪ�{���A���̍��{���i�ł���A�P�Ȃ�m���̌n�̊w�Ƃ́A�{���I�Ӗ��ŏs�ʂ���˂Ȃ�ʂ̂ł���B�i�u�����@�w�̍j�̓I�W�J�v�j
�@���Ƃ��͂����̂́A���Ƃ����l�̗c�҂ɁA�����̖}���ɐL���ꂽ�����̌��t�ł���Ƃ���Ă���B�E�E�E����E���E�t���ɏ����ėI�v�̑�`�ɐ�����Ƃ���A��ϓI���z�̗��ꂩ�玡�����V���̌����E�������w�����S�l�ނ͂ǂ��֍s���ׂ����������ւ�ł��낤�B�i�u�̌n�Ƃ������Ɓv�@�j�u�i���̂悤�ȁj�����A���w�݁A�Ǝ��̓W�J���Ȃ����ނ���̂����A�^���̋��Ƃ��ւ�B�B�������݂̂�����ł��炤�B�v�ƍl���鎺�Z�����́A���w�������̂��̂ɑ傫�ȑO��������A��ʂ̊w�̌������@�Ə@�w�̌����̕��@�Ƃ��s�ʂ��Ď��̂悤�ɉ]���B
�@���w�͈��͈�ʐ������ɂ́A�_���I�V�X�e�������ɁA�̌n�̗Y����ւ��Ă��A���ǂ���͐����̊w�p�I�[�X�`���[���Ȃӂ��̂ŁA�o���ԓI���̖{����ł��邱�ƂɂȂ�Ղ��B�����ꎞ��@�̗V�Y�ɑ��B���w�͂ނ���A�Ȗ�������A���ۉ����ꐶ���������ɒ����ɐ�������˂Ȃ�ʁB�i�u�����@�w�̍j�̓I�W�J�v�j
�@�����͏@�w�����̒��j�����̂悤�ȂƂ���Ɍ����ɗ��Ă�ׂ����ƍl����̂ł����āA�@�w�����̑g�D�I���@�ɂ��Ă͂��܂�ӂ�Ă��Ȃ����u�{�@�w��ɂ����鏔���v�����\�̂悤�ɐ������Ă���B�i�u���݂̂��̋ᖡ�v�j
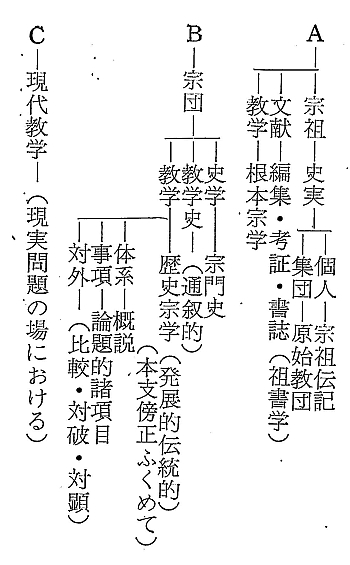
�@���̂悤�ȁu�����@�w�v�́A�@�w����ɑ���ᔻ�E���ȁA���c�ɂ����闝�O�Ǝ��ԂƂ̘�������Ƃ��ďo�����l�@���ꂽ���̂ł��鎖�͒��ӂ��ׂ��ł��낤�i�u���@�@�w�F�w�j�v�@�u�����@�w�̍j�̓I�W�J�v�@�u�̌n�I�Ό��v�j�B
�@�M�҂Ƃ��ẮA���Z�����̏@�w�̍��{�m�ɑŗ��Ă邱�Ƃ��挈�ł���A���S�I�ۑ�ł���Ƃ̐��ɋ���������̂ł��邪�A�Ȃ��A���̏ꍇ�A�����������{�I�ȗ��O�̗�������A�����̂�����u���̎��ԋ�ԓI�����ւ̑����i���̌����I�����I�����j�v�̂��߂Ɍ���̊w��̕��@�Ɛ��ʂɑ��Ăǂ̂悤�ȑԓx�ŗՂނ̂��A����Ɓu���z�ւ̌���i�W�i���̏㏸�I���i�j�v�Ƃ͂ǂ̂悤�ȊW�ɂ��̂��A���ˑR�Ƃ��Ė��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƌ��l������̂ł���B
�@�@�@�@�@�Γc�䋳�������̏@�w�_
�@���Z�������u�����@�w�v���ۑ�Ƃ����̂ɑ��A�Γc�䋳���́u�@�w�̋q�ϐ��v����Ƃ��Ă���B�Γc�䋳���́u�@�w�����v�@�i������@�@���w�������\���I�v�j�@�u�@�w�ɂ�����I����Ǝ�I����v�@�i���w��P�O�R���j�u�@�w�̋q�ϐ��v�i�w�ϐS�{�������������x�|�@��ɑウ�āj���ɏ@�w�ς\����Ă���B�Γc�䋳���́u�@�w�̋q�ϐ��v�Ŏ��̂悤�Ɍ����B
�@��@�̏@�w�́A���c�ɑ��铯�M�E�����E������Ƃ��ē���n���ɂ���Ǝ��o����҂́A���ȗ����̕\���I���E�ł���B���������āA����͓����E���M�̏�Ɍ���ꂽ���Ƃł����āA�َ��I�Ȃ��́A�ِM�̂��̂̊Ԃɂ����Ă͐��������Ȃ��Ƃ������E�������Ă���B�܂�Ƃ��Ă̏@���o�����T�^�ƂȂ��āA�ތ^������Ă����n���̂Ȃ��Ɍ`���������̂ŁA��̓���Ƃ�������̂ł��낤�B
�@�����ŁA���̂悤�ȓ���I�Ȑ��i�����@�w���A���u�w�v�Ƃ��Ă̑̌n�I���E��L�v�����A�u�P�̎v�z�Ƃ��ċq�ϐ��v�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ���A���̋q�ϐ��Ƃ͉����B�܂�A�u�ɂ߂ĐM�I�ł���A�I�̌��I�ł�����̂���ՂƂȂ��Ă���u�@�w�v�I�\���ɁA�q�ϐ������߂�Ƃ���A���́u�q�ρv�Ƃ͂����Ȃ���̂ł��낤�B���Ƃ����̂��A�ۑ�Ƃ��Ē����̂ł���B�@�u�@�c�v���u��l�ԑ��v�Ƃ��ė������邱�Ƃ́A�u�Ȋw�I���@�ɂ��q�ϓI�Ȏ�X�̗���v�A�������؎j�w�I���@��@���S���w�I���@�����蓾�邪�A�u������X�̕��@�ɂ���ĕ�������ɂ��ꂽ�u�@�c�v�Ȃ���̂́A�����ł͍ő��u�@�c�v�ł͂Ȃ����āA�l�Ƃ��Ắu��l�ԑ��v�ɑ��Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ�B�Ȃ��Ȃ�A�u�@�w�I���߂ɂ�����@�c�́A�u��l�ԑ��v�ł���Ɠ����Ɂu�@�c�v�łȂ���Ȃ�Ȃ��v����ł���A�����ɏ@�w�I�u���߁v���u����v������̂́A�u�@���I��̐��v�����A�u���̏o���ɂ����āA���łɎ�̂Ǝ�̂Ƃ��琂ɐ_������Ƃ������Ƃ��A�K�{�����v�Ƃ��Ă̐M���v�������Əq�ׂ�B�����A�u�M�͉��߂݁A���߂͂܂��M�ށv�Ƃ����悤�ȐM�Ɖ��ߊw�Ƃ̊W���@�w�̕��@�ƂȂ���̂ł���A�u�@�c�ɖ₢�A�@�c�ɓ�����v�@�u���́u�₢�v�́A��Ɂu�����v�̌`�ł������Ȏ��g�����킳�Ȃ����̂ł���v�Əq�ׂĂ���B�����āA�u�@�w�ɂ�������߁v�̗��������N�w���T���r�Y���́u���ߊw�v�@�̉𖾂��茜��ɋK�肵�悤�Ƃ���B
�@���u�@�w�v�͒P�Ȃ���߂ɏI����̂ł͂Ȃ������A�u�����ɉ��߂����̕���Ƃ���v���ƁB���u���߁v�@�u�����v�Ɓu�M�v���Ƃ��u���ݔ}��̊W�ɗ��v���ƁB���́u���߁v�́A���R�A�u�����⌾��̏ゾ���ɕ\���������̂łȂ��A�s�ׂƂ��Ă̗����̌`�Ɍ��������߂��v����̂ł��邱�ƁB���u�@�c�ւ̖₢�Ɠ����v�Ƃ������ۂ́u�����v�������u���̍s�דI�\���̐��E�����������̂ł���v���ƁA���������B
�@�Γc�䋳���́A�u�@�w�����v�ɂ����āA�u�@�w�ɉ�����_�����́A�����Č`���_����Ώۘ_���A�܂��͓���_���I�̂��̂ł͂Ȃ��A�M�̘_�ɊO�Ȃ�Ȃ��̂ł���v�Əq�ׂĂ��邪�A����͗אډȊw�̌�����ے肷��̂ł͂Ȃ��A�����̌������u�M�d�Ȉꎑ���v�Ƃ��ĎƂ�Ȃ���@�c�̐M�I�E��̓I���߂Ƃ��̍s����}��Ɨ����ł���ł��낤���B
�@�����āA���̍s���͒P�Ɍ̎����ɂ��������̂łȂ��A���c��O���ɂ������u��I����v���v���������̂ł���i�u�@�w�ɂ������I����v�j�B
�@�@�@�@�@�@�@�ށ@�@���@�@��
�@�ȏ�A���@�@�ɂ����čs�Ȃ�ꂽ���w���́u�@�w�_�v��q�˂Č����B���������\���ɂӂ��Ĕ���ɂȂ��Ă��܂��������m��Ȃ��B�������A�������Đq�˂Č���Ɓu�@�w�_�v�Ƃ����Ă��A���̃A�v���[�`�̎d���͕K��������l�ł͂Ȃ��̂ł���B����͊e�w���̏@�w����ԓx�ɔ�����u�@�w�_�v�̏œ_�ɂ��̂ł��낤�B
�@���A���̖��_�������Ă݂�A
�@�P�A�ߑ�I�w��̕��@�Ƃ̔�r�ɂ�����@�w�̕��@�̖��
�@�Q�A�@�w�ƐM�̌��Ƃ̊֘A
�@�R�A�@�c�̋��w�����Ȃ̂��̂Ƃ���ۂ̎�Â��Ə@�w�̖{���Ƃ̊֘A
�@�S�A���̍ۂ̏@�w�̕��@
�@�T�A�ߑ�I�w��i�אڂ̊w����@�j�Ƃ̊֘A
���X���l������̂ł��낤�B
�@����ɂ��āA�M�҂̏����A�M�҂̏@�w�_���q�ׂ�ׂ��ł��邪�A���̓_�ɂ��Ă͋@������̂Ę_�������Ǝv���B�����A�Q�E�R�̏������q�ׂāq�ނ��сr�Ƃ������B
�@�܂��A���݂ɂ����Ă��A�@�w�����̑g�D�I���@����Ƃ���l������悤�Ɍ�����B�Ȃ�قǁA�@�w�����̑g�D�ɂ��Č������邱�Ƃ͏d�v�ł��낤�B�������A����͏@�w���{���I�ɂ����Ȃ闝�R�����Ȃ���@�ɂ���đ��݂�����̂��Ƃ����ۑ���ɂ��Č�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B
�@����ɂ́A�@�w�ɓ���ȑO�ɁA�u���v�@�i�@�c�ɂ���ĐF�ǂ��ꂽ�@�،o�̐��E�j����̂����悤�ɉ�X�ƌ��т��̂����A�l�����Ȃ���Ȃ�܂��B�]���搶�́u�n���@�w�v�A���Z�����́u�����@�w�v�͔��ɑΏƓI�ȕ\���ł���ɂ�������炸�A���̖���_�������̂Ɨ̉��������B
�@�@�w�͐M�҂ɂ̂ݔ\���̖傪���邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��ƂłȂ��A�\�����������Ƃ��ɓ����ړI�Ɍ����čs������̍s�l�ł���A�o�Ƃ��݉Ƃ��Ƃ��Ɂu���v�ɐ����悤�Ɠw�͂��čs�����Ƃɂ���̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���̂悤�ȏ@�w�̕��@�̒Nj��͋�z�ɉ߂���Ƃ����邩���m��Ȃ��B�������A���̂悤�ȍ��{�I�ȑԓx����@�w�̂���������{�I�ɍl���čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�B
�@�@�i�Ȃ��A���w���́u�@�w�_�v���M�̈Ӑ}���[������ł��Ȃ�������A�I�O����������Ƃł��낤�B�����̌䎶��������̂ł���B�j
1969/3
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@