�@
�@
�@�u�����̊ю�͐�v�Ƃ����_�b�̌`��
���@���@���@�v
�@�͂��߂��@
�P�@�����@���@�̌��������ςɂ݂�_�b�ƈ�E�@
�Q�@�����̗B��҈ӎ��Ƃ��@
�R�@������l���p�������u���`�v�̓��e�@
�S�@��Ύ��Z���Ƃ��Ă̈ӎ��@
�T�@�w�����՞��X���x�������߂��鏔����@
�U�@�w�{���������x�w�ܐl���j�������x�̌����@
�i1�j�����̑�Ύ��嗬�ƒ��ÓV��̊W�@
�i�Q�j�w�{���������x�́u�B����l�v���@
�i�R�j�w�ܐl���j�������x�̊ю�M�I�ȕ\��
�V�@�嗬���̊ю�ɂ݂�B����l�I�Ȍ��Ў�`�̕s���@
�W�@�㐢�E���L�ɂ݂�h�M�S�̌����h�̋����Ɗю�㊯���@
�i1�j�l�@�{���ւ́u�M�S�v���t�푊���Čp���[���L�̌����ρ@
�i�Q�j�ю�㊯���@
�@�X
�@��Ύ��̌����_�b�̌��^�\�\������苗��E�����̓o���@
�i1�j�u��ӑ����v�ɂ����������̎咣
�i�Q�j���@�t���𒆊j�ɒu��������
�i�R�j�u�B���l�v�u�B����l�v�̗p��̕��y�@
�i4�j�u�@��v�̌�̑�Ύ��Z���ւ̓K�p
�i�T�j�O���@�̐�g�@
�i�U�j���������ɂ��O���@�̓`���@
�i�V�j���`���w�̌����@
�i�W�j�ю��l�̖{������
�i�X�j�@�ю�M��
�P�O�@�ߑ�@��̌��������ς̊m���ҁ\�\56���E�����@
�i1�j�Ηv�����̎v�z����w�Ɏ��@�̑����_�@
�i�Q�j���������̋��`�Ɠ������w�̓��ꎋ�@
�@�@���@�_
�@
�@
�@
�@
�@
�͂��߂�
�@�u�{�@�̑m���́A���s�ɂ����Ă��A�܂��L�z�i�W�̏ォ����A�@��̎w��ɐM�����]���Ȃ���Ȃ�܂���v�u������ɑn���w��ł́c�c�{�@�̖����ł���B����l�̌����̑������A�r�������`�����Ă���̂ł���܂��B����́A���炩�ɖ{�@���`�̑m��`�E�����`�ɔw�������掖@�ł���܂��v�u����āA���@���@�́A�@���@�l�n���w���j��ɕt���A�Ȍ���@���@�Ƃ͖��W�̒c�̂ł��邱�Ƃ�ʍ��������܂��v�\�\�B����3�i1991�j�N11��28���A���@���@���n���w��ɒʒm�����w�j��ʍ����x�̈ꕔ�ł���B
�@���@���@�́A�n���w��u�@��̎w��ɐM�����]�v�����u�B����l�̌����̑����v��`�����̂͏d��ȋ��`��w�i��掖@�j�ł���Ƃ��A���̂��Ƃ��傽�闝�R�Ɋw��Ɂu�j��v��ʍ������B��ɂ��A���́w�j��ʍ����x�ɂ́A�@�c�E���@�̈╶�Ɋ�Â��Ċw��̌������w�e�����ӏ�������Ȃ��B���Ȃ킿���@���@�́A�@�c�̋����������́u�@��v�̎w���\�ɗ��ĂĊw����ق����Ƃ����̂ł���B
�@�����͂����ɁA���݂̓��@���@�����O��A�����Ɂu�B����l�̌����v�Ȃ���̂��d�压���A���̌���������Ύ��̊ю�i�@��j���Ή����Ă��邩��m��B���{�����ɂ����āA�c�t�M�Ƃ����̂͂悭���邪�A�ю�M�ƂȂ�Ɨ]�蕷���Ȃ��B���@���@�𖼏���Ύ��嗬�̗��j��U��Ԃ��Ă��A�����̌��Ђ��������Ď��̊ю���Ή�����悤�Ȍ����́A�����E���ځE�������̋��c�����̊ю�ɂ͂Ȃ������B��́A�������猌���̊ю���Ή�����v�l����Ύ��@��ɉ萶���A�蒅�����̂��낤���B�{���̘_������N�����ɂ�����A�^����ɂ��̖����l���Ă݂����B
�@�u�B����l�̌����v�Ƃ́A��l�̎t����l�̒�q�ցA�c��̌������`��邪���Ƃ����@�̉��`���`���l���w���Č����B�����́A���j�I�Ɉ�l�����l�ւ̖@���n�����d�����Ă����̂�����A���̂�������̂��]�X�������͂Ȃ��B����ǂ����݂̓��@���@���W�Ԃ���u�B����l�̌����v�́A��������̓����҂����̎�����Ή��ւ̌_�@���͂��ł���B�u�B����l�̌����ɂ���Ė@�傩��@��֑��{���́h�@�́h��{���́h�@���h���p������Ă����B������A�M�҂͖@��ɐM�����]���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ȂǂƁA���̓��@���@�ł͐M�҂ɐ��������Ă���B���������ю��̎v�z���Ƃ��Ȃ��u�B����l�̌����v�ς������A�{���Ŗ��Ƃ���Ƃ���ł���B
�@�Ƃ���ŁA���@���@�ɂ݂���ю��ΐ��̋N����T������ɂ́A700�N�߂����O�̑�Ύ��嗬�̓���ɂ܂ők��A�����E�ߐ��E�ߑ�E����ւƑ����嗬���̎v�z�������T�ς���Ƃ�����Ƃ����߂���B�����܂ł��Ȃ��A����͑�ςȓ��Ƃł���B�@����̏��j���̒��ŁA�^�̈Ӗ��ŕ����w�I�ɐ^�U���m�肵�Ă�����̂͋ɂ߂ď��Ȃ��B�@����̊ю�ɖ₷��`�L�ނ��R�����A�B�ꑶ����]�ˊ���17���E�����́w�x�m��ƒ������x�i�ȉ��w�ƒ����x�Ɨ����j�́A�㐢�̎j�Ƃ�����ɐh煂ȕ]�����Ă���B��Ύ����w�̌`���ɖ₵�āA�䌣�w�I�ɔ�̑ł������Ȃ��c�_���s�����Ƃ͕s�\�ɋ߂��悤�Ɏv����B
�@�������Ȃ���A��Ύ��嗬�j�ɂ����āu�����̊ю�͐�v�Ƃ����ϔO�����̊Ԃɂ��o�ꂵ�Ė嗬���ɍ���`���������A�Ƃ������Ƃ͏���w�̓w�͂ɂ���Ė��炩�ɂȂ����B��́A���̂�����̎�����A���������ڂ����𖾂ł���A��̊w��I�ȉ����Ƃ��Ēł��邩������Ȃ��B
�@���_���̖ړI�́A���̂悤�ȉ����̌`�������݂邱�Ƃɂ���B��قǏq�ׂ��悤�ɁA��Ύ����̕����̒��ɂ͐^�U�����̂��̂������B���������Ė{�e�œW�J����_�́A�����܂Ŏb��I�����̈���o�Ȃ��B���̗D�ꂽ�����҂��ٍe��ᔻ���A����Ȃ�_�̐i�W���݂��邱�Ƃ����҂��ĕM�����邱�Ƃɂ���B
�@�@�@1�@�����@���@�̌��������ςɂ݂�_�b�ƈ�E
�@�ŏ��ɁA��Ύ��嗬�̏@�c�ł�����@�̌��������ς��m�F���Ă������B���@�́w������厖�������x�i�����ʖ{�j�ŁA���������̖��ɂ��Ď�X�w�삵�Ă���B�{���́A���V��@�̑m�œ��@�̒�q�ƂȂ����Ř@�[���u������厖�����v�ɂ��Ď��₵�����Ƃɑ��A���@���F�߂��ԏ��Ƃ����B
�@�{���̖`���ɂ́u������厖�����Ƃ͏����얳���@�@�،o���Ȃ�A���͎̌̂߉ޑ���̓̒��ɂ��ď�s��F�ɏ��苋���č��̖��@�@�،o�̌��ߋ���������薤�����������ꂴ�錌���Ȃ�v�i�S�W1336�E��{�T�Q�Q�j�Ƃ���A��������������@�͏�s���`�́u�얳���@�@�،o�v�ł���A�Ɛ�����Ă���B�����āA���̓얳���@�@�،o�������������Đ������邱�Ƃ����u������厖�����v�ł���A�Ƃ̎��_���玟�̓�̏C�s�̗v�����������B
-
�v�������̎ߑ��ƊF�������̖@�،o�Ɖ䓙�O���Ƃ̓�S�����ʖ����Ɖ���Ė��@�@�،o�Ə�����鏈����厖�̌����Ƃ͉]���Ȃ�i�S�W�P�R�R�V�E��{�T�Q�Q�j
-
�����ē��@����q�h�ߓ��E�����ލ��̐S�Ȃ������̎v�𐬂��Ĉّ̓��S�ɂ��ē얳���@�@�،o�Ə�����鏈����厖�̌����Ƃ͉]���Ȃ�A�R�������@���O�ʂ��鏈�̏��F���Ȃ�A�Ⴕ�R��L�闬�z�̑��������ׂ��҂��i�S�W�P�R�R�V�E��{�T�Q3�j
-
�����̑�M�͂�v���ē얳���@�@�،o�E�ՏI���O�ƋF�O�����ցA������厖�̌���������O�ɑS�����ނ邱�ƂȂ���A�ϔY�����E���������ςƂ͐��Ȃ�A�M�S�̌����Ȃ���Ζ@�،o�����Ƃ����v�Ȃ�i�S�W�P�R�R�W�E��{�T�Q4�j�����̎ߑ������s��F�ւƌ����������ꂽ�얳���@�@�،o�̖@�̂��A��؏O���������������Đ������ׂ��ł���A����ɂ́u�얳���@�@�،o�v�Ə����邱�Ƃł���B�����A�C�s�҂́A���E�@�E�O���������ʂł��邱�Ƃ�M�����A�u�ّ̓��S�v�Œc�����Ė��@�̍L�闬�z��ڎw���A�����ȁu�M�S�v�������ď���ɗ�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��h�B�ȏオ���@�̌��������ςł���A�ނ͂��̗��ꂩ��Ř@�[�Ɂu���얳���@�@�،o�߉ޑ����s��F���������ƏC�s�����ցv�i�S�W�P�R�R�W�E��{�T�Q�S�j�Ɗ��߂Ă���B
�@���Ȃ킿�A���������̔�@�Ƃ͏�s���`�́u�얳���@�@�،o�v�ȊO�̉����ł��Ȃ��A�������S�\���ŏC�s��������A������l�X�����̐r�[�̖��@���������������̎҂ɂȂ��A�Ɠ��@�͕ۏ����̂ł���B���@�ɂ���Ď����ꂽ���@��m��l�X�ɂƂ��āA�厖�Ȃ��Ƃ͔�`�̑��d�ɂ������ďC�s�̐S�\���ł���B��̓I�ɂ́A�}���s��̐M�O�ƈّ̓��S�̐S�ŏ�s��F���������������@�́����@��M�A���@�̍L�闬�z��ڎw���Ƃ����u�M�S�̌����v�ł���B��Ύ�9���E���L�́w���V���x27���Ɂu�M�Ƃ��Ќ����Ɖ]�Ж@���Ɖ]�ӎ��͓������Ȃ�v�u���c�ߗ��̐M�S����ւ��鎞�͉�ꓙ���F�S���@�@�،o�̐F�S�Ȃ�v�i�x�v�P�P�U�S�j���Ǝw�삵�Ă���A���݂̑n���w������l�Ȍ������Ƃ��Ă���B
�@����ɑ��A�u�얳���@�@�،o�̖@�̂Ƌ��`�͑�Ύ��̗��@�傾�����B����l�����������Ă���A���̎҂͒m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�䂦�ɐM�҂́A��Ύ��̖@��ɐ�ɏ]��˂Ȃ�Ȃ��v�Ƌ����咣����̂������@���@�ł���B���@��́A��s���`�̖@�̂̍����I���݂�@��i�ю�j�̓��ɋ��߁A�ю��Ύ�`�������Ă�܂Ȃ��B�������A���̍l�����͌�q���鍶����苗��E�����̋����ɗR������Ƃ����A��Ύ��̐������w�ɔ�����ْ[�̎v�z�ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B26���E�������w����钾���x�̒��Łu����ߑ��̈�厖�̔�@�Ƃ͌��v�t���̐��́A�@�c�o���̖{���A�O���@�̐���A�{��̖{���̌䎖�Ȃ�v�i�x�v�R�P�X�R�j�Ǝ��������Ƃ��A��Ύ���k���M���ׂ���s�t���̖@�̂Ƃ́u�{��̖{���v���Ȃ킿�u�{����d�̑��{���v�̂��Ƃł���B�����āA���̉��d�{���́u���g�U�́v�Ƃ��Ă̈Ӌ`�����������ʂ̌`�ؖ{�����n���w��ɂ���Đ��E���ɍO�߂��Ă���킯������A��s��F���������������@�̂͌��݁A���S���̐l�X����ɂ���Ƃ���Ȃ̂ł���B
�@�܂����_���ŏڏq���邪�A�M�҂́A��Ύ��嗬�����S�N�ȏ���`�����Ă����Ƃ����O���@�̖@�̂̋��`������̑�Ύ��嗬���ł͍L�����J����A�n���w��ɂ�����u�M�S�̌����v�̏d�������̑O��ɗ��Ɨ������Ă���B
�@�v����ɁA��s���`�̖@�̂Ƌ��`�͍L�����E�Ɍ��J���ꂽ�̂ł���A���Â͂Ƃ���������ɂ����Ă͑�Ύ��ю�̐�L���ƌ����Ȃ��B
�@����Ɍ����A���̓��@���@����������ю��Ύ�`�́q�`���r�́A�㐢�ɑn�삳�ꂽ�_�b�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�Ƃ�킯�h��Ύ��̖@�傾������s�t���̖@�̂����������ł���h�Ƃ��������@���@�̎咣�́A���v�t���̖@�̂��䶗��{���Ƃ��Ė��l�̑O�ɊJ�����悤�Ƃ������@�̈Ӑ}�ɔw�����̂ł���B�����@���@�̌��������ςɂ݂���A���������_�b���E�͉��䂦�ɐ������̂��B���̓����́A��Ύ��̗B����l���������̎v�z�`���j���݂Ă������Ƃɂ��A�����Ɩ��炩�ɂȂ낤�B
�@�@�@�Q�@�����̗B��҈ӎ��Ƃ�
�@���݂̓��@���@�ł́A���@�����g�̓��ł�O�ɂ��ē����ɗ^�����Ƃ����w�g���������x�Ɓw�r�㑊�����x�̓A������u��ӑ����v�̑��݂������āA���@�\�\�����̗B����l����������������̂Ƃ��Ă���B���̓�ӑ����̐^���{�͑������A��Ύ��ɂ́A���m2�i1468�j�N�̏Z�{�����L�̎ʖ{��剓�[�������]�ʂ����{�����ɕۊǂ���Ă���Ƃ����B����̊w�҂́A�Â������ӑ������M���ɋ^�`��悵�Ă���B
�@�M�҂͂����ŁA��ӑ����̐^�U�_���ɂ���������͂Ȃ��B�����A�w�E�������̂́A���@���B����l�̌����ɂ�����������炩�Ȍ`�Ղ͎c���Ă��Ȃ��A�Ƃ����_�ł���B���@�̖{�ӂ́A�u���{���̈�؏O���ɖ@�،o��M�����߂ĕ��ɐ��錌�����p�����߂�Ƃ���v�i�w������厖�������x�A�S�W�P�R�R�V�E��{�T�Q�R�j�Ƃ���ɂ������B�܂�A�����̖��O���ɕ��������`���s�����̂����@�Ȃ̂ł���B
�@���@�́A�����̒�q��݉Ƃ̒h�z�ɏd�v�@�����������Ă���B�܂���Ύ��@�傪�u���@����̍O�@�v�̊j�S�Ƃ���w�@�،o�x���ʕi����̎O���@�`�́A�w��`���`�x�w�{�������x�w�S�Z�ӏ��x�̏��X�ɎU������Ă���B������Ɂw��`���`�x�͓��@���g���Ŗ剺�ꓯ�ɍu�`�������e�̓����L�ƌ����Ă��邵�A�w�{�������x�w�S�Z�ӏ��x����Ύ����ł͕����̖��ɑ��`���ꂽ���̂Ǝ咣���Ă���B����ɓ����́w�@�c��J���L�^�x�ɖ��炩�Ȃ��Ƃ��A���@�͍O��5�i1282�j�N10��8���A�����́u�{��q�v�Ƃ��ĘZ�l�̑m�i�����E�����E�����E�����E���N�E�����j���ߒu���Ă���B�����܂���ƁA�����嗬�̗��ꂩ��u���@�吹�l�́A���@�̌����������l���l�Ɏ�����ꂽ�v�ȂǂƎ咣����͓̂���悤�ɂ��v����B
�@�������Ȃ�����@�������ɑ��A���X�ɓ��@�{���`�̂悤�ȋ��V���n�̖@����������\�����Ȃ��͂Ȃ��B�Z�V�̒��ŁA������l�ɏ@���I�ȓ��@���q���݂���̂͂܂��Ƃɕs�v�c������ł���B���c�^�c�̖ʂɊւ��Ă��A���@�́A�����𒄒�Ƃ��������ŋ��c�����̂��߂ɘZ�V���x���Ƃ����̂�������Ȃ��B���@������������̌�p�҂ƒ�߂��Ƃ����������A��̐����Ƃ��ĂȂ狖�����ł��낤�B
�@����ǂ��������ׂ��́A�����̌������Ɂh�����͓��@���l����B����l�̌��������g�ł���B������S���@�剺�́A�������Ŏ��ɏ]���ׂ����h�Ƃ������ⓚ���p�̑�����`�������������������Ȃ����Ƃł���B�ނ���A�����́h���@�吹�l�̖{��q�Z�l�͊F��������t�̐��`���p�����ׂ��ł��邪�A�����ȊO�̌ܐl�͎c�O�Ȃ��琳�`�ɔw���A���ʓI�Ɏ�����l�����`���O�����Ă���h�Ƃ̒Q����\�����Ă���B
�@�������g�����R�̑O�N�̐������i1288�j�N12���ɏ������w���a��Ԏ��x�i���Îʖ{�E�v�@�����j�̒��ɁA�u���q�����t�G������ʁB������l�{�t�̐��`�𑶂��Ė{���𐋂�����ׂ��m�ɑ����Ċo����ւA�{�ӖY��邱�Ɩ�����v�i��S�P�[�P�V�Q�j�Ƃ��������肪����B��������ǂݎ���̂́A���̌ܘV�m�������u�t�G�v�̎`���\�������ʁA������l�����@�̐��`�̌p���҂ɂȂ����Ƃ����ӎ��ł���B�����́h�B����l�̊ю傽�鎩����������̐��`�ł���Ǝ��Ȃ���ʎ������킯�ł͂Ȃ��A���̓��@�剺�������t�G���s�������ʂƂ��āh�B��ҁh���邱�Ƃ�\�������̂ł���B
�@���̂��Ƃ𗠂Â�����������͏��Ȃ��Ȃ��B�Ⴆ�A�w��u����\�Z�Ӟ��x�i����ʖ{�j�̑����Ɂu�x�m�̗��`�ւ���t�̌�O�ʂɈႹ���邱�Ɓv�Ƃ��邪�A���̎��̑����ɂ́u�ܐl�̗��`��X�ɐ�t�̌�O�ʂɈႷ�鎖�v�Ƃ�����i��S�P�P�X�V�j�B�܂��w�ܐl���j���x�i����M�L�{�A�`�����ʖ{�j�ɂ͂����L����Ă���B
�`�֕����V���t�ɎO��]�̒�q�L��A�͈��N�R�Ƃ��ēƂ�V��B���B�`����t�͎O�痵�̏O�k�������A�`�^�Ȍ�͑��ꖳ�����@���B�����@���l�͖��N�~��ׂ̈ɘZ�l�̏����ށA�R���嫂ǂ��@����ɓ�r�ɕ���嗬����y�Ȃ炸�A�h�K�̎��萳�t�ɋ��ӂ�嫂ǂ��A�`���̐l�����ق���A�\�����̖@���ҍ��l��������A�����ƎႵ���ȂΏ����߂މ��A�o�����߈��������_�̔@���A瑉��̔ߒV�P�����̔@���A�{��̒đJ��D������A�ė��Ⴕ��t�Ɉ�͂Έ�g�̒Z���ނ�����L��A���ӏ������ӂɊ��͂Όܐl�̕T�`�r���J�Ӊ��A��̐����ɔC���v�҂��ċX�������ׂ��]�]�i��S�P�[�R�T�j
�@�u�V���t�ɎO��]�̒�q�L��A�͈��N�R�Ƃ��ēƂ�V��B���v�Ƃ��邲�Ƃ��A�����͌`����̕t���̗L�������@�嗹���̗͂��d�Ă���B�����ēV��[�͈��A�`���[�`�^�Ƃ����B����l�I�Ȍn���������Ȃ�����u�����@���l�͖��N�~��ׂ̈ɘZ�l�̏����ށv�Ƃ��A���ʓI�ɂ͓��@�Ō�̋��c���Łu�`���̐l�����ق���v�Ƃ��������܂ꂽ���Ƃ��q�ׂĂ���B���̓����̌�����A�q�t�����ꂽ��l������ΐ��`�r�Ƃ����ӎ����݂ĂƂ�̂͐r������ł��낤�B�����ł́A���@���V��E�`���ƈقȂ�A�Z�l�̌�p�҂��߂����Ƃ����L����Ă���B�������т��Ă���v�l�́u���ۂɒN���@�c�̐��`���p�����Ă���̂��v�Ƃ��������F���ł����āA�B����l�̖��T���ɂ������ԓx�Ȃǂ͔��o���������Ȃ��B�u�ė��Ⴕ��t�Ɉ�͂Έ�g�̒Z���ނ�����L��A���ӏ������ӂɊ��͂Όܐl�̕T�`�r���J�Ӊ��A��̐����ɔC���v�҂��ċX�������ׂ��v�Ƃ���悤�ɁA�����͌����Ď��Ȃ��Ή������ɌܘV�̖@��ȉ���ᔻ�����̂ł���B
�@�������������̌������A���@����㎖������ꂽ������B���Ă̌����\���Ƃ݂�ނ������낤�B�M�҂����̉\���͔ے肵�Ȃ��B���@�̌�p�҂𐄍l����ɂ������Ă͖{�����x�����݂��Ȃ����������̕������c�̂�������l�����ׂ��ł��邪�A����ǂ��ł���A��p�w�����邱�ƂƎ��Ȑ�Ή��Ƃ͖{���I�ɕʂ̎����̖��ł���B�ނ����p�̐ӔC���䂦�Ɏt���Ɉ��ʂ悤��T�݁A���Ȃ��Ȃ݂ď�ɑ��Ή����A�O�c���d��ю傪���Ă����������͂Ȃ��B
�@�厖�Ȃ��Ƃ́A�����̌������Ɍ��Ў�`�I�Ȏ�����Ή��̈ӎ����S���݂��Ȃ��A�Ƃ�����_�Ȃ̂ł���B�����́A���̒�q�����Ƃ̑Δ�̌��ʂƂ��ėB��҈ӎ��̕\�����s�����ɂ����Ȃ��B���ɓ�ӑ����ɂ�鐳���ӎ��������̐S���ɑ������Ƃ��Ă��A���̌��Ђ�p���Ď��Ȃ̐��������咣���Ȃ������Ƃ����_�ŁA�r�ɂ́A���悻�㐢�ɂ݂���悤�Ȋю��Ή��Ƃ��Ă̗B����l�����Ȃ������ƌ������邾�낤�B
�@�@�@3�@������l���p�������u���`�v�̓��e
�@�ł́A������l���p���������@�́u���`�v�Ƃ͉��������̂��B��Ύ��嗬�ɂ����ẮA��䶗��{���𒆐S�Ƃ����O���@�`�����́u���`�v�Ƃ����B
�@�O���@�Ƃ́u�{��̖{���v�u�{��̉��d�v�u�{��̑�ځv�̂��Ƃ����A�����͂��̈�X�Ɋւ��đ��̌ܘV�m�̌����ƑΔ䂵�A���Ȃ̗����N���ɂ��Ă���B
�@���ɁA�u�{��̖{���v�ɂ��Ă͙�䶗��{����`���Ƃ�B�w�x�m��Ֆ�k���m���x�i���_�ʖ{�j�Ƃ����A�����̈ӂ��č쐬���ꂽ�Ɠ`�����鏑������B���́u�{���̎��v�ɁA���̂��Ƃ��L�q���݂���B
-
�ܐl�ꓯ�ɉ]���A�{���ɉ��Ă͎߉ޔ@���𐒁i�߁j���ׂ��ƂĊ��ɗ�����A���Ē�q�h�ߓ��̒��ɂ��������{�i�́j�䏑�V��݁i��j�Ɖ]�X�B����Ԑ��ɓ��ɂāA���͈�̂����u���A���͕��������e�m�Ƃ��A���Đ��l��M�̖{���ɉ��Ă͔ނ̕����̌�ʂɌ������A�����ɂ̘L�ɔV���́i�āj�u���B
�����]���A���l�䗧�̖@��ɉ��ẮA�S���G���ؑ��̕���F���ȂĖ{���ƈׂ����A�B�䏑�̈ӂɔC���Ė��@�@�،o�̌����ȂĖ{���ƈׂ��ׂ��A���i���j���M�{������i��S�P�[�Q�P�j
�@�����ȊO�̌ܘV�m�́A�{���Ƃ��Ď߉ވ�̕������A���邢�͎߉ޕ����ɕ�����F�╶���F��e�m�Ƃ��Ĉ��u�����B�����ē��@�}���̙�䶗��{�����A�����̌�ʂɌ�������A���ɓ��̗쏊�i�_�j�Ɏ̂Ēu�����肵���Ƃ����̂ł���B����ɂ��A�ܘV�m�͕��E��F�̑���{���ƒ�߁A���@�̕�����䶗����y�������B������ɓ�����l�́A�ؑ���G���̕��E��F��{���Ƃ����A���@���u�䏑�v�ɐ��������Ƃ��A�u���@�@�،o�̌��v�́u���M�{���v���Ȃ킿���@�}���̕�����䶗���{���Ɨ��Ă��̂ł���B
�@�����́A���́u�{���̎��v�̒��Łu���̌�M�̌�{���͐����腕���ɖ������z�����A�������ɖ����O�ʂ�����{����v�u�L�闬�z�̎��{�������q�L�����܂Ő[���h�d�����ׂ��v�u������q���̖{���ɉ��ẮA��X�F�����t����鎖�A���ɖ}�M���ȂĒ��ɐ��M��ꂂ����Łi���j���̋���L��v�u�����̒�q���ɉ��Ă͍݉Əo�Ƃ̒��Ɉ��͐g�����̂Ĉ����r�����͖��ݏ���Ǖ�����āA�ꕪ�M�S�̗L��y�ɁA�z�������ʂ����V�����^����Җ�v�i��S�P�[�Q�P�`�Q�Q�j�Əq�ׂ�ȂǁA���@�}���̙�䶗��{�����ł����h���ׂ����Ƃ��������Ă���B����́A���������@�̎O���@�̒��ł��u�{��̖{���v�𒆐S�Ɉʒu�Â��Ă������Ƃ����O�ɓ��킹����̂ł���B
�@�܂������͑���������@�̌�e�������A��䶗��{���̑O�Ɉ��u���Ă����Ƃ݂���B�������܂��g���ɍݎR���̐������i1288�j�N�A�g�؈䐴���������ɒ�o�����w����x�ɂ́u���ق��i�j�̌��ق��i�@�j����i��j����Ԃ�������ցi��j�܂��点�i�i�j��͂A�ق�i�{�j����i���j�Ȃ�сi���j�Ɍ䂵�₤�i���j�l�̌�i�݁j��i�e�j�̂ɂ��܂�i���j�𐴒����g�ɂ����i���j�ӂ����i�[�j���Ԃ�i��j�ׂ���v�i�x�v�W�[�P�O�j�Ƃ���B�������瓖���̓����剺�ɂ����āA���@�̌�e������䶗��{���ƂƂ��ɐ��q�̑ΏۂƂȂ��Ă����l�q�����������m�邱�Ƃ��ł���B���ہA�����̏����ނ�ǂނƁA���@�̂��Ƃ��u�{�t�v�u���l�v�u�@�ؐ��l�v�u�@�吹�l�v�u��o���@���l�v�u���v���Ƒ��̂��Ă���B�������ɂ́A��������@�c�{���̎v�z���������ƍl�����悤�B
�@����ɓ����́A��䶗��{���̏��ʂɂ������ĕK�����́u�얳���@�@�،o�v�̒����Ɂu���@�䔻�v���ƔF�߂Ă���B����́A���̉��Ɏ����̖����������Ƃ��������嗬�̏��t�Ƃ̑�Ȃ鑊��_�ł���A���@���䶗��{���̓��̂Ƃ݂�ӎ��̌����Ƃ��ĎƂ邱�Ƃ��\�ł���B�����ɁA��̑�Ύ��嗬�ɂ����Č��������u�l�@�̈�v�̖{���`�̗��[���݂�͕̂s���ł͂Ȃ��낤�B
�@���ɁA�����́A��b�R�́u瑖�̉��d�v�ɑ��āu�{��̉��d�v�̖����������咣���Ă���B�w�x�m��Ֆ�k���m���x�ł́A�����ȊO�̌ܘV�m���u���l�̖@��͓V��@�Ȃ�A���Ĕ�b�R�ɉ��ďo�Ǝ������L�ʁv�Ƃ���̂ɔ����āu�ނ̔�b�R�̉��͐���瑖��A���@�����̉���A���@���l�̎���͖@�ؖ{��̉��Ȃ�A�����@�����̐�����v�Ə������A����𗝗R�ɌܘV�m�Ƃ́u�`��v�������Ƃ��邹���Ă���i��S�P�[�P�V�j�B
�@�����āA�����m���́u�{�厛�����ׂ��ݏ��̎��v�ɂ́A�������L����Ă���B
ূɓ����]���A�}�i���j���n���i��j�ʼn�������������͕��@�̒ʗ��B�R��Ώx�͕x�y�R�͐�����{���̖��R��A�ł�������ɉ��Ė{�厛���������ׂ��R�E�t�����L�ʁA���čL�闬�z�̎����荑�卟�̖@���p������̎��́A�K���x�m�R�ɗ��Ă��ׂ��Ȃ�i��S�P�[�Q�Q�j
�@���̌ܘV�m�́A��t�E���@���u�{�厛�v�̍ݏ��ɂ��ĉ�����߂Ȃ������Əq�ׂ����A�����́u�x�m�R�v�ɖ{�厛���������ׂ����Ƃ������咣�����B�{�厛�̌����́A�{����d�̌������܈ӂ���Ƃ݂Ă悢�B�܂�A�����͕x�m���d�����������킯�ł���B���̕x�m���d�����A��̑�Ύ��嗬�ɂ����Č���ɂȂ�M���ł���B
�@�Ō�ɁA�u�{��̑�ځv�ł��邪�A�u�얳���@�@�،o�v�̑�ڂ�������ׂ����Ƃ͑S���@�剺�̋��ʌ����ł���B�������Ȃ��瑼�̌ܘV�ƈقȂ�����̓Ǝ����́A�V��@��瑖�Ƃ����@�@��{��Ƃ���_�ɂ���B���̐M�O����u���@���l�̖@��͓V��@��v�u��t���@���l�V��̗]�������ށv�u��������̌Õ����i���j�œ`����t�̗]�������ݖ@�؏@���O�߂�Ɨ~���]�X�v�i��S�P�[�P�U�j�ƌ�������ܘV�m������͋����ᔻ���A�u���̑���Ɉ˂āA�ܐl�Ɠ����ƌ����Ȃċ`�₵�L�ʁv�i���O�j�Ƃ��Ă���B
�@�������琄����ɁA�����́u�{��̑�ځv�ς́h�V�䂸��h�̌ܘV�m�Ɓu�`��v����قLjقȂ���̂ł������B���Ȃ݂ɁA�w�{�������x�i�`�����ʖ{�E���C�ʖ{�E����ʖ{�j�ɂ́u���̒�Ƃ͋v�������̖����̖��@��]�s�ɂ킽�������B�̐��ρE���s�̈�O�O��̓얳���@�@�،o���Ȃ�v�i�S�W�W�V�V�E��{�Ȃ��j�Ƃ���B�w�{�������x�����@��������֒������ꂽ���ł��邱�Ƃ��w�I�ɏؖ��͂ł��Ȃ��̂ŁA��̎Q�l�Ƃ��ċL���B
�@�ȏ�A���������̌ܘV�m�Ƃ̑Δ��ʂ��Ė��炩�ɂ������@�́u���`�v�̓��e���A�O���@�`�Ƃ����ϓ_���琮���������Ă݂��B����ɂ���āA�����̗B��҈ӎ��̍����ƂȂ�u���`�v�̊ϔO���ނ̖剺�ꓯ�ɂƂ��ĉ��I���������ƁA�����Ă��ꂪ��ɑ�Ύ��嗬�Ǝ��̎O���@�`�ւƐ�������Ă��������Ƃ��m�F�����̂ł���B
�@
�S�@��Ύ��Z���Ƃ��Ă̈ӎ�
�@�����܂Ř_�����悤�ɁA�����͌ܘV�m�̏@�c��w�ɂ���Č��ʓI�ɗB��҈ӎ���\�������B���̂����ŁA�����鋳�`�I�����Ƃ͕ʂɁA�����͐g���R�E�v�����̕ʓ��i�ꎛ�̒��j����ӎ��������Ă����Ƃ��l������B�u�ʓ��v�Ƃ͈ꎛ�̎����̓����҂��Ӗ����A�u�Z���v�Ƃقړ��`�ł���B���ۂɓ��@�Ō�A�����͒n���E�g�؈䎁�̊��}���Đg���ɓ��R���A����2�i1289�j�N�ɗ��R����܂ł̊ԁA�v�����ɏZ���Ă���B
�@�����嗬�̏��ɂ����Ă��A���̑�Ύ��ю傪�����Ă����̂́A�j����͏Z���̈ӎ��ł������B�w���r�u����\�Z�Ӟ��x�ɂ��A�����͖嗬�̌�p�҂��u���̊ю�v�ƕ\�������B�w�L�����x�ł́A���@�́u�ю�E�ю�i����j�v�̈Ӗ��ɂ��āu�V�����ُ̈́B�܂���ɁA�e�@�{�R�⏔�厛�̏Z���̌h�̂Ƃ��Ȃ�v�Ɛ������Ă���B���Ȃ킿�����́A�����̌�p�҂��u���̊ю�v����R�̏Z���Ƃ��đ����Ă����悤�ł���B
�@���̂��Ƃ́A���c���i1332�j�N11���́w�����՞��X���x�i���{�E��Ύ����j�̒��Ɂu��Ύ��͌䓰�Ɖ]���揊�Ɖ]�����ڔV���Ǘ̂��C���������s��v���čL�闬�z��҂ׂ��Ȃ�v�i��S�P�[�X�U�j�Ƃ���_�������m�����B���ڂ̏������w���z��Ԏ��x�i���{�E�ۓc���{�����j�Ɂu��Ύ��Ƀn�l�Ȃ���v�i��S1�[�Q�R�W�j�Ƃ��邪�A�����E���ڂ̎���ɂ́u��Ύ��v�̏Z���E�����łɑ��݂����ƍl�����悤�B
�@���ɁA���ڂ�������ւ̑�Ύ������Ɋւ��Ă͊m����ؕ����Ȃ��A������k�Ƃ̊ԂɖV�n���߂��鑈�����Ă���B�����A�×�2�i1327�j�N11���ɓ��ڂ������ɗ^�������i���{�E��Ύ����j���݂�ƁA���B��ɓ��̓c���E�V�n������ɏ��^����|���L����Ă���i��S�P�[�Q�P�V�j�B����ȂǁA��Ύ��̑����Ƃ͖��W�Ȃ���A�Z���̈ʂ̏��^�Ɠ����ނɑ�����B
�@���āA4���E������5���E���s�Ɍ����������Ƃ������j���Ƃ��āA���@���@�ł͗2�i1339�j�N6��15���ɓ��������ʂ����{���������Ă���B���̖{���̉E�ɂ́A�u���B����싨���ŗ����s�ɔV�����^���A��t����s�͓����̒�q�ꂪ���̈�Ȃ�v�i�x�v�W�[�P�W�X�j�ƔF�߂��Ă���B���@���@�́w�x�m�N�\�x�́A���̖{���̎��^��17���E�����́w�ƒ����x�̋L�q�������āu�����@�@����s�ɕt���v�Ƃ��邪�A���{���̒[�����ɁA���������s�ɖ@��t�������Ƃ������e�͋L����Ă��Ȃ��B�����āA����Ɋւ���w�ƒ����x�̌������A��������m���Ȏj���ɂ���Ă͗��Â����Ȃ��B
�@�����Ŗ��ɂȂ�̂́A�������g�̖嗬�n���ςł���B�����M�Ƃ����w��`�y��x�i���{�E��Ύ����j���A���̂Ƃ���ł��Q�l�ɂȂ�B�����ł́A���@��������ւ̑����ɂ��ĉ����G����Ă��Ȃ��B�������́A�u������l�͑吹��J���V��g���R�ɂčO�@���������A�����i���Ɓj�֓��̂���������Ȃ��ĎO�P�N���Ԑg���R�Ɍ�Z����v�i��S�P�[�Q�U�V�j�Ƃ���݂̂ł���B����́A�������g���R�E�v�����̏Z���E����@��������ꂽ�A�Ƃ��錩���ł���悤�Ɏv����B�܂������Ɠ��ڂ̊W�ɂ��ẮA���ĂƂ������Ƃ����낤�����Ɍ��y����Ă��Ȃ��B
�@�܂�A�w��`�y��x�̖嗬�n���ς̒��ɗB����l�̌����͕W�Ԃ���Ă��炸�A�����Č����ΐg���Z���̒n�ʂ̓����ւ̏��^��F�߂�ӎ���������������x�Ȃ̂ł���B�펯�I�ɂ́A���ɂ�����ւ̋��`���`���䶗��{���̑����������ē��R�����A�w��`�y��x�̍�҂́A���������t�@�̎����ʂɕ\���Ă��Ȃ��B�w��`�y��x���݂�ƁA�ނ���q�������Z���r�̈ӎ��̕����O�ʂɏo�Ă���B
�@�����āA5���E���s����6���E�����ւ̈ڍs���݂Ă݂悤�B���̌��ɂ��Ă��A���@���@�́w�x�m�N�\�x�́A���s��������֎��^���ꂽ�{���Ɓw�ƒ����x�̋L�q�ɂ��A�厡4�i1365�j�N2��15���Ɂu���s�@�@������ɕt���A�{�������^�v�Ɛ��肵�Ă���B�������A�厡4�N2��15�����ʂ̓��s�̖{���̒[���ɂ́u��������J�������ɔV�����^���v�i�x�v�W�|1�X�O�j�ƋL�����݂̂ł���B
�@����ɑ��A6���E��������Ύ��Z���Ƃ��Ă̈ӎ������������Ă����A�Ƃ������Ƃ��j���͑��݂���B����������3�i1392�j�N7���ɏ������Ƃ����i��Ă�����ł���B�����ɂ́u�x�͍���싽��Ύ��ʓ��{������苗������ނ�Ō���v�u�E�����͊J�R���@��l�ȗ������Ɏ���܂Ő��㑊�����ᖳ���Җ�v�i��S1�[�R�O�R�j�ƋL����A�������u��Ύ��ʓ��v�̈ӎ��������Ă������ƁA�ނɑ�Ύ��Z���̈ʂ́u�����v���u����v�����ł����Ƃ��������S�����������Ɠ������������m���B
�@����ɐi��ŁA6���E��������8���E���e�ւ̈ڍs�͂ǂ��������̂��B���i11�i1404�j�N5��1���A����������e�Ɏ��^���ꂽ��䶗��{���ɂ́u��Ύ��Z��������苗����e�ɔV�����^���v�i�x�v�W�[�P�X�R�j�Ƃ̒[�����F�߂��Ă���B��ɂ���āw�x�m�N�\�x�́A���̖{�����^�̐܂ɓ������u���e�ɖ@����t�v�����Ƃ���B���A��͂�E�̖{���[���ɕt�@�̎��������L����Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�@����Ɉ��������A���e�̑�Ύ��Z������ӎ��Ɋւ��ẮA��ꋉ�j�������R�Ƃ��đ�����B���i19�i1412�j�N8���A���e�����ʂ�����䶗��{���ɂ́u��Ύ������e�v�i�x�v�W�[�P�X�S�j�Ƃ���B�u��Ύ����v�Ƃ������t����́A���炩�ɑ�Ύ��́u�Z���v�Ƃ��Ă̓��e�̈ӎ����ǂ݂Ƃ�悤�B
�@�ȏ�A�J�R�̓�������8���E���e�ւƎ����Ύ����̊ю�̎��ȔF����T���Ă݂��B�ނ�̂��̂Ƃ���鏔�����̒��ɂ́u�ю�v�u�Ǘ́v�u�����v�u��Ύ��ʓ��v�u��Ύ����v�Ƃ��������t���ڗ����A6���E�����ȍ~�͖��炩�ɑ�Ύ��Z���Ƃ��Ă̎��o���݂ĂƂ��B�嗬�̏�Âɂ����ẮA�ю�Ԃʼn��炪�̕��@�t�����Ȃ���Ă����Ƃ��Ă��\�ɂ͏o�Ă��Ă��Ȃ��B���̂����A�Z���Ƃ��Ă̊ю�̎��o�Ȃ�Ώ��j���ɎU�������B�����t�@�̊ю�̔r���I���Ђ���O�ɐG����A�Z���Ƃ��Ă̊ю�ς��Ȍ����̑�Ύ���ނƂ̈Ⴂ�͂����ɖ��炩�ł��낤�B
�@�@�@�T�@�w�����՞��X���x��2�����߂��鏔���
�@���ɁA�����@���@���ю��̍����Ƃ��ċ������Â̕����j���������������Ă݂悤�B�ŏ��ɁA�w�����՞��X���x��2�����߂��鏔�����l�@�������B���@���@�́w���@��S���x�ɂ��A����ڂ̓��e�́u�������g�Ɉ��ċ��͂鏊�̍O��2�N�̑��{���͓��ڂɔV�����^���{�厛�Ɍ������ׂ��v�i��S�P�[�X�U�j�ł���B���݂̓��@���@�́A�����L�͂ȕ��Ƃ��āA��Ύ��́u�@��v�ɂ͑��{���́h�@�́h�Ȃ���̂�������������Ă���Ɛ����ɏ����Ă���B
�@�����ō���x�A�����̓��e���w�I�ɍl������K�v��������̂ł��邪�A�x�����́w�����՞��X���x�ɂ��āu���{�ĕ����ɑ��{�R�Ɍ������v�i�x�v�W�[1�V�j�Ə����c���Ă���B�܂�A�w�����՞��X���x�ɂ͐��{�ƈĕ��i�������j�̓�{������A�Ƃ��ɑ�Ύ��ɏ�������Ă���ƌ����̂ł���B
�@
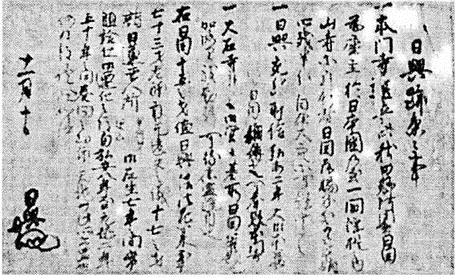 �@��Ύ��̏t�̒������@�v�̍ہA�w�����՞��X���x���ю�̎�ɂ���ĎQ��҂ɔޘI�����B�����k�������s�����w������l�S�W�x�ɂ́A���̒�������̐܂ɎB�e���ꂽ�Ǝv����w�����՞��X���x�̎ʐ^���f�ڂ���Ă���B������݂�ƞ����̂ŏ�����Ă���A�����̎����E�ԉ����݂���B�N�����L�ڂ���Ă��Ȃ��_�����s�R�ł��邪�A�̍قƂ��Ă͐��{�ƍl������B���@���@�O�ǒ��̈����������A���@�̋��w�������������Ɂu���������ɁA�e�����������I�Ȃ����܂����c�c���K�̓����A���ڏ�l�ւ̏����ɂ́c�c�w�������g�Ɉ��ĂĎ��鏊�̍O��2�N�̑��{�\�A���ڂɔV�����^���B�{�厛�Ɍ������ׂ��x�Ƃ������̌䕶�������ł��ˁv�Ɣ������Ă���B
�@��Ύ��̏t�̒������@�v�̍ہA�w�����՞��X���x���ю�̎�ɂ���ĎQ��҂ɔޘI�����B�����k�������s�����w������l�S�W�x�ɂ́A���̒�������̐܂ɎB�e���ꂽ�Ǝv����w�����՞��X���x�̎ʐ^���f�ڂ���Ă���B������݂�ƞ����̂ŏ�����Ă���A�����̎����E�ԉ����݂���B�N�����L�ڂ���Ă��Ȃ��_�����s�R�ł��邪�A�̍قƂ��Ă͐��{�ƍl������B���@���@�O�ǒ��̈����������A���@�̋��w�������������Ɂu���������ɁA�e�����������I�Ȃ����܂����c�c���K�̓����A���ڏ�l�ւ̏����ɂ́c�c�w�������g�Ɉ��ĂĎ��鏊�̍O��2�N�̑��{�\�A���ڂɔV�����^���B�{�厛�Ɍ������ׂ��x�Ƃ������̌䕶�������ł��ˁv�Ɣ������Ă���B
�@�Ȃ�A���̐��{�̑����͂����Ȃ���e�Ȃ̂��낤���B�ʐ^���{�Ƃ��ĉ�ǂ��s�����w������l�S�W�x�̕Ҏ[�҂́A�u�������g�����O����N���{�������������ڎ��o�V�{�厛�v�Ɩ|�����Ă���B�������{�̎��ۂ̋L�q�́A�����ƕ��G�ł���B�吳���ɖx���ԁi��̓����j���Ҏ[�ɑS�ʋ��͂��Ċ��������w���@�@�@�w�S���x��́A��Ύ������̐��{����Ɂw�����՞��X���x�̖|�����s�����B�����ł́A���{�̑����Ɋւ��āu���}���l���͌�l�̈ӂɔV���������Ď��^�̉��ɑ��M���Ȃ��đ��`�V�{�厛�̋㎚��������v�ƒ��L����Ă���B����ɏ]���A�������鐳�{�̑����́u�������g�����O����N���{�������������ڎ��o�V�����V�{�厛�v�ł���A�u���`�V�{�厛�v�̕��������M�Ƃ������ƂɂȂ�B���{����Y���u�i�w�����՞��X���x�́j�����ɂ͎��^�V�̉��Ɂw���`�V�{�厛�x�̋㎚���L��Ɖ]�Ӂv�ƋL���Ă��邪�A���{�̏ꍇ�͐��{�̋L�q�������i�ĕ��j�̂���Ɗ��Ⴂ���Ă���B
�@�������āA�����i���{�j�̋L�q�͏��X�ɔ������Ă���̂ł��邪�A����́w������l�S�e�W�x���ڂ̎ʐ^�̕��͂ɂ��A����Ȃ���������߂���B���S�W�̎ʐ^�́A���Ȃ�s�N���ł���B����ł��Î�����ƁA�u���T�V�v�̏�Ɂu�����V�v�Əd�ˎ�����Ă��邱�Ƃ��킩��B���Ȃ킿�A�^���̑����i���{�j�̋L�q�́u�������g�����O����N���{�������������ڎ��T�V�i���T�V�̏�ɑ����V�j�{�厛�v�ƂȂ�A�u�����V�{�厛�v�����M�Ƃ̌��_�ɒB����B
�@��������A�w�����՞��X���x�����i���{�j�̓����̋L�q���e�́u�������g�����O����N���{�������������ڎ��o�V�v�i�������g�Ɉ��ċ���鏊�̍O����N�̑��{�������������ڂɔV�����^���j�ł��������Ƃ��A�������̂ł���B
�@�Ȃ��A65���E���~�́A�u�{�厛�v�̌�������M�ł͂Ȃ��u������l�����X�Ȃ��ꂽ���Ƃł���v�Ǝ咣���Ă���B�������ɐ��{�̎ʐ^���݂�ƁA�u�����V�{�厛�v�͌���Ƃ͎v������̂́A���M�Ɣ�ׂđ��M�ƌ������قǂ̈Ⴂ���݂���Ȃ��B�䂦�ɓ��~�͂��̋㎚������M�Ɣ��f���A�w������l�S�W�x���u�{�厛�v�̉ӏ��𐳖{�̓��e�Ƃ݂Ȃ��Ė|�����Ă���B
�@����������������������A���{�̐����ȋL�q���e�́u�������g�����O����N���{�������������ڑ����V�{�厛�v�ɕύX����˂Ȃ�Ȃ����A�M�҂Ƃ��Ă͎^�������˂�B���{�𐴏�������ɖ{�l���d�ˏ���������A�Ƃ����̂͗]��ɂ�����������ł���B�d�ˏ������ꂽ���_�ŁA����͂��͂�����ꂽ���{�ł͂Ȃ��A���̈ĕ��ɂȂ��Ă��܂��B�w�����՞��X���x�̐��{�͐����Ȓu��E����Ȃ̂�����A�����ɏd�ˏ���������͕̂s���R�ł���B�䂦�ɁA�u�����V�{�厛�v�̌���͑��M�ł��낤�A�Ƃ���̂��Ó��Ȕ��f�ł���B
�@�Ƃ���A�w�����՞��X���x�̈ĕ��̕��ɂ��u�����V�{�厛�v�Ƃ̋L�q�͂Ȃ��͂��ł���B�펯�I�ɍl����A�}�t�I�ȉӏ��̈ٓ��͂������Ƃ��Ă��A�ĕ��Ƃ���𐴏��������{�ƂŊ�{�I�ȓ��e���H���Ⴄ���Ƃ͂Ȃ��B���������{�ɂ݂���u�����V�{�厛�v�̌���𑼕M�����ɂ��č폜�����̂́A��ɂ͈ĕ��Ɛ��{�Ƃ̊Ԃœ��e�I���������m�ۂ���_�����������̂��낤�B
�@���j�������������Ύ��̓����̊w�m�́A�ȑO����w�����՞��X���x�̐��{�E�ĕ��̗���������̐^�M�ƊӒ肵�Ă���B�����l���ɂ��ƁA�Õ�����ǂ���Ƃ���@���̖^�m���w�����՞��X���x�̈ĕ��Ɛ��{���ɂ킽���Č��������������ʁA�Ƃ��ɓ����M�ł��邱�Ƃ�f�����Ƃ����B�M�҂̌o���I�m�����猾���A���Ȃ��Ƃ��ĕ��̕��͓����̕M�ƍl���Ă悢�B�����łȂ��Ƃ��A�Y������邾�낤�ĕ����킴�킴�U�삷��҂�����Ƃ͎v���Ȃ��B�����A��Ύ������̈ĕ������J���Ȃ����R�́A�����Ɂu�{�厛�v���Ȃ����炾�Ǝv����B�������w�����՞��X���x�̈ĕ�������M�ƒf�肵�A���{�̒��ŋ^�`�̂���ӏ����ĕ��ɂ���ĕ���悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���_�Ƃ��āA�M�҂͓����̌����ɗ��r���A�w�����՞��X���x�����i���{�j�̐��K�̓��e���u�������g�����O����N���{�������������ڎ��o�V�v�Ƒ[�肷����̂ł���B
�@�ł͎��ɁA���{�ɂ�������������̌����ӏ��ɂ��čl�@�������B��܂��Ɍ����āA����ɂ�2��������B��́A���������̌����𑼕M�҂ɂ��Ӑ}�I�폜�̐ՂƂ��A���X�����ɂ́u�O���ܔN�i�܌�������j�䉺���v�i�x�v�W�[�P�W�j�Ƃ̋L�q���������Ƃ���x�����̐��ł���B����́A���������̌���������ɂ��폜�̈ӂƂ݂Ȃ����ł���A���@���@�́w���@��S���x�����̗�����Ƃ�Ǝv����B�������A��҂̐����̗p����͔̂��ɍ���ł���B
�@��ɂ����l�̌������q�ׂ����A�����Ȓu��ł���w�����՞��X���x���{�ɁA��҂̓������폜�̐Ղ��c�����낤���B�u�������g�����O����N���{�������������ڎ��o�V�v������̈ӎu�ɂ�鐳�K�̋L�q�Ƃ���Ȃ�A���������̌��̕������߂����ėl�X�ȉ�������ь����̂����m�̏�ŁA�����͍폜���{�����u����c�������ƂɂȂ�B�������A�킴�킴�㐢�̋^�f�������悤�Ȓu����c���Ƃ͎v���Ȃ��B���������̌����́A��͂�u�����V�{�厛�v�̌�������ꗂ��������Ȃ��悤�Ɍ̈ӂɍ����ꂽ�ՂƂ݂��������ł���B
�@�{�e�ł͂���䂦�A�O�҂̖x�����u�O���ܔN�i�܌�������j�䉺���v�̐���y��Ƃ��ċc�_����߂�B�����́A�ĕ��ɂ���Đ��{�̖��_���������悤�Ƃ����Ƃ݂���B���̌��n���猾���A���������{�̌����������u�O���ܔN�i�܌�������j�䉺���v�Ƃ����̂́A�ĕ��̋L�q���Q�Ƃ������ʂł��낤�B�������A���@���@�́w�x�m�N�\�x�́A�O��5�i1282�j�N2��29����
�u���鎛�䉺���������i�Α��ʁj�v�ƋL���Ă���B��Ύ������̎ʖ{�ɂ��Ƃ��Ă��邪�A���N�\�͓��@���@�̈АM�����������j���ł���B��Ύ��ɑ�����A�@����œ����^�M�Ƃ����w�����՞��X���x�ĕ����������Ȃ��킯���Ȃ��A������ŏI�I�ȍ����Ƃ������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�������u�܌�������v�����Ƃ������R�͉Ǖ��ɂ��Ēm��Ȃ����A���́w�x�m�N�\�x�̋L�q��M�����āu�O���ܔN�i������j�䉺���v�̕���p����B
�@�����A�Ȃ����͎c��B���{�̌����͎l�����Ƃ݂���B���������̌����ӏ��Ɂu�O���ܔN�i������j�䉺���v���������Ƃ���̂́A�����ɖ����̂�����ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B�����ӏ����u�O���ܔN�i�܌�������j�䉺���v�Ƃ��������������������A�u�܌�������v�����ʂɓ��ꂽ�̂��낤�B�������A����ł��u�O���ܔN�䉺���v�ł͎����ƂȂ�A���������̎l�����̌����ӏ��ɓ����ɂ͎�������������B�����ōŋ߂ł́A���������̌������u���䉺���v�Ɛ��@����҂�����Ă���B
�@�M�Ҏ��g�́A���{�̌����ӏ��̌������u�O���ܔN�䉺���v�ɂ��Ă����ɖ��͐����Ȃ��Ǝv���B�����ӏ��̌������l�����Ƃ���̂́A�w���@�@�@�w�S���x����������Ĉȗ��A�m���錟���Ȃ�����������Ă����B����ǂ��A���̌������������̂ł���B�w�����՞��X���x���{�̎ʐ^���݂�ƁA���̒u��̒��ŁA��s���ɓ�s���������܂�Ă���ӏ�������B��O���Ɂu�w���@���l���i�b�B�g���R�j��ݐ����N�V�ԁv�Ƃ���Ƃ���́i�b�B�g���R�j�������ł���B�܂��w������l�S�W�x���ڂ́w�����՞��X���x�̎ʐ^�͕s�N���ł��邪�A�����ӏ�����s���������Ă���悤�ɂ��݂���B
�@�����������Ƃ���A�����ӏ����i�@�@�j�ł���A�����ɗႦ�u�O���ܔN�䉺���v�̎������������Ɛ����ł��Ȃ����Ȃ��B�w���@�@�@�w�S���x��2���̕Ҏ[�ɒ��S�I�Ɋւ�����x�������A�����Ō��������Ɩ|���\�L���ꂽ�����ӏ��ɁA�����āu�O���ܔN�䉺���v�̎�������ꂽ�̂ł���B���ꎩ�́A�����������ӏ����l�����Ƃ͊m�肵�Ă��Ȃ��������Ƃ̏؍��ƌ�����B�����́A�ĕ��̓��e����ސ����āA���̌����ɑ��݂��������́u�O���ܔN�䉺���v�ȊO�ɂ͍l�����Ȃ��A�Ƃ̌��_�ɒB�����̂��낤�B
�@�������āA�w�����՞��X���x�����i���{�j�́u�������g�����O����N���{���i�O���ܔN�䉺���j���ڎ��`�V�v�Ɩ|�������ׂ��ł���A�����ɂ���Ɓu�������g�Ɉ��ċ���鏊�̍O����N�̑��{���O���ܔN�i������j�䉺���A���ڂɔV�����^���v�ɂȂ�B���ꂪ�M�҂̈ӌ��ł���B�i�܌�������j���i������j�ɕς������Ƃ������A�w�x�m�@�w�v�W�x��8���ɏ�������Ă�������̐��i�x�v�W�[�P�W�j�Ƃقړ����ł���B
�@���łȂ���A�u��Ύ��嗬���̎҂��w�O���ܔN�䉺���x�̋L�q���폜���ׂ����R�ȂǂȂ��ł͂Ȃ����v�Ƃ����^��ɂ������Ă������B�u�䉺���v�Ƃ͉����B���̂Ƃ���A����I�Ȍ����͒�o����Ă��Ȃ��B�����̐��l�ł́A�O��4�i1281�j�N�ɓ�������t�������鎛�\��ɑ��ė��N�ɓV�c���玒�������������w���A����͌�ɕ��������Ƃ���Ă���B�����̂��Ƃ��u�䉺���v���M�d�ȏ@��ł���Ƃ���A�u�O���ܔN�䉺���v�̋L�q���Ύ��嗬���̎҂��폜�����Ƃ����̂͂Ȃ�قǕςł���B�䉺���������������߂ɍ�炴��Ȃ������A�Ɛ�������Έꉞ�̗����͒ʂ�B�������Ȃ��琳�{�̑����̕����I�폜�ɂ��ẮA�u�����V�{�厛�v�̌�����ɍ����悤�ɉ��҂��ɂ���čs��ꂽ�\�����l�����悤�B���̌�����̍�҂́A�u�O����N�̑��{���v��{�厛�Ɍ��������ׂ��{���A�܂���d�{���Ƃ����������悤�Ɏv����B�Ȃ̂ɁA���̕��Ɂu�O����N���{���O���ܔN�䉺�����ڎ��T�V�v�ƋL����Ă����Ƃ�����ǂ����낤���B���̌�Ɂu�{�厛�Ɍ������ׂ��v�Ɖ��M���邽�߂ɂ́A�ǂ����Ă��u�O���ܔN�䉺���v���폜���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂܂܂ł́A�u���{���v�݂̂Ȃ炸�u�䉺���v�܂ł��u�{�厛�Ɍ������ׂ��v�Ƃ������ƂɂȂ邩��ł���B������̍�҂́u�O����N�̑��{���v��{�厛�ɕ�f���ׂ��{���Ƃ������̂ł��邩��A��Ύ��@��̎҂Ƃ݂ĊԈႢ�Ȃ��B���̏@��l�ɂƂ��āu�O���ܔN�䉺���v�̋L�q�͂ނ���]�v�ł���A�폜����˂Ȃ�Ȃ������Ƃ����@�ł���̂ł���B
�@���āA�ȏ�̍l�@�Ɋ�Â��A�����@���@�̍l�����̖��_���w�E���Ă��������B����6�i1994�j�N���s�́w�����V�ҁ@���@�吹�l�䏑�x�i���������ďC�j�Ɏ��߂�ꂽ�w�����Տ��X���x�̑����́A�u��A�������g�Ɉ��ċ��͂鏊�̍O����N�̑��{���́A���ڂɔV�𑊓`���B�{�厛�Ɍ������ׂ��v�ƂȂ��Ă���B
�@�w�����՞��X���x�̑����������Ɂu������l������ڏ�l�֑��{���́h�@�́h���������ꂽ�v�Ǝ咣����������������Ƃ��ẮA�u���^�v�����u���`�v�Ƃ����閧�߂������t�̕����悢�̂�������Ȃ��B�u���ڂɔV�𑊓`���v�Ƃ���̂͗v�@�����C�́w�c�t�`�x�����o�ł���A���a27�i1952�j�N���́w���@���@���T�x������������Ƃ�B�Ƃ͂����A��Ύ��嗬�ł�26���E�����i�w������L�x�u���i�W�Q�Q�T�v�w���@��䶗����{���x�y���i�W�V�P�W�z���Q�Ɓj�A48���E���ʁi�w�x�m��Ύ������x�u�x�v�T�[�R�Q�V�v���Q�Ɓj�A59���E�����i�x�v�W�[�P�W���Q�Ɓj�B���A��������u���ڂɔV�����^���v�Ƃ��Ă���B����疼������@�j�E�@�w�҂̋��ʌ�����ނ�����A�����炪������u���ڂɔV�𑊓`���v�ɕύX�����̂́A�����ɂ��ΎR�嗬�̓`������O��f�������ۂ߂Ȃ��B�������A�w�����՞��X���x�����i���{�j�̋L�q�́u���`�v�ł���B������u���`�v�Ƃ���w�����V�Ҍ䏑�x�́A�u���`�v�̏�̌���̏d�ˎ��u�����v���̗p�������ƂɂȂ낤�B
�@������ɂ���A���{�̑����͕����w�I�Ɂu�������g�Ɉ��ċ���鏊�̍O����N�̑��{���O���ܔN�i������j�䉺���A���ڂɔV�����^���v�Ƃ���̂��Ó��ł���A�������獡�̓��@���@��������悤�Ȋю���Ή�������ؑ������������o�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�E�̕��ł́A�u�O����N�̑��{���v���u�O���ܔN�i�܌�������j�̌䉺���v�ƂƂ��ɓ��ڂɎ��^����Ă���B����������ڂւ́u���{���v�̎��^�́A�u�䉺���v�̎��^�Ɠ��l�ɗ�������˂Ȃ�Ȃ��B�܂肻��́A�����܂ŏ@��Ƃ��Ắu���{���v�̏��^�ɑ��Ȃ炸�A�_��I�ȓ��́h�@�́h�Ȃ���̂́u���`�v�Ȃǂł͂Ȃ��̂ł���B�Ȃ��A�u�O����N�̑��{���v�������w���̂��ɂ��āA���Ȃ��Ƃ�17���E�����̍��܂ł͖嗬���ł���������܂��Ă��Ȃ������߂��݂���B������Ύ��̉��d�{���Ƃ��錩�����@���ɒ蒅����̂́A����26���E���������������Ă���̂��Ƃł��낤�B
�@�Ō�ɁA���������炩�̎���ɂ��폜�E���M�����w�����՞��X���x�𐳖{�Ƃ��Ďc������Ȃ������A���邢�͌������鐳�{�Ƃ͕ʂɐ^�̐��{�������������͎c���Ă��Ȃ��A�Ƃ����\���ɂ��Ă��l���Ă����B���Ȃ�����������ł��邪�A���������������S�����藧���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA�w�����V�Ҍ䏑�x�́u��A�������g�Ɉ��ċ��͂鏊�̍O����N�̑��{���́A���ڂɔV�𑊓`���B�{�厛�Ɍ������ׂ��v�Ƃ̋L�q���A���S�ɔے肵���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B���������̏ꍇ�ł��A�������ю��Ή��̕��Ƃ��ėp����͍̂s���߂��ł���B�u�{�厛�Ɍ������v���Ƃ��ł���̂́A�@��Ƃ��Ắu���{���v�ȊO�ɂȂ��B�����ł���ȏ�A�u�O����N�̑��{���́A���ڂɔV�𑊓`���v�Ƃ̕��������āA�ю�Ԃ̑��{���́h�@�́h�̓��ؑ������]�X����̂͊g����߂������Ƃ���Ȃ̂ł���B
�@
�U�@�w�{���������x�w�ܐl���j�������x�̌���
�@��Ύ��嗬�̏��Ɂu�����̊ю�͐�v�Ƃ���v�z���Ȃ��������Ƃ́A���܂ł̗l�X�ȏ��l�@����j���I�ɐ��m�����B�������Ȃ��猻���@���@�̘_�҂����́A������������������悤�Ƃ��Ȃ��B�P�Ȃ�h�O�}�ւ̌Ŏ����唼�ł��邪�A���ɂ͎j���l�̎����Ŕ��_�����݂�҂�����B���̍ہA�悭��肴�������̂��A�O�ʓ�����Ɠ`����w�{���������x�i�����ʖ{���j�▭�@������̍�Ƃ����w�ܐl���j�������x�i�����ʖ{���j�ɑ�����`�I�Ȋю��Ή��Ƃ��ڂ����L�q������A�Ƃ������Ƃł���B
�@�M�҂͌��_�I�ɁA�����̏��ɂ͕����w�I��肪���X����ƍl���Ă���B���R�ɂ��Ă͍�����ڂ����q�ׂ邪�A���̑O�ɏ����̑�Ύ��嗬�ƒ���V��Ƃ̊W��e�X�݂Ă������Ƃɂ��悤�B
�@(1)�����̑�Ύ��嗬�ƒ��ÓV��̊W
�@�����钆��V��́A��������ɐ��܂ꂽ�V��{�o�v�z������Ƃ���B����́A�����̎��ۂ��i���Ȃ�^���̌���Ƃ��Đ�m�肷��v�z�ł���A�u�ϔY�����v�u�O�������v�Ƃ����������̐^���ς������L�߂��Ă������B���������V��{�o�v�z�́A��������܂ł͌��`���邢�͐؎��������ɂ���ē`����ꂽ���A�₪�Ă����̕��������i�݁A���q�����ɂ͎l�d���p�A�O�d���ӂ̖@��Ȃǂ̑̌n�����Ȃ��ꂽ�B�����Ċ��q�������k�E��������ɂ����āA�{�o�v�z�̏W�听�ƂƂ��ɁA���̒��߂�������ɂȂ����ƌ�����B
�@���q�����Ɋ������@���A���ÓV��̎v�z�I�e�����A���̌��`�`���⋳���_����������Ă���B�������ʁA���ϑ����ĊϐS�������Ȃ킿�����@�g������̐_��I�Ȓ����������Ƃ钆��V��ƈقȂ�A�@�،o�̋����Ɍ�����s��F�ւ̕ʕt�����d�������̂����@�ł������B�����ď�s�ʕt�̖@��얳���@�@�،o�Ȃ�Ɩ������A�����剺�Ɋ��߁A���@�̙�䶗��{�����������Ă���B���@�́A�@�،o���痣�ꂽ����V��̊ϐS��`��r���A�ǂ��܂ł����������̖@�̂̌��J��ڎw���A�ŏI�I�ɂ͂�����䶗��{���Ƃ��ċ�������B���@�̌��������ς́A�l�X�Ȗʂʼn������̂ĂȂ��Ƃ���ɓ���ga����B�������A�閧��`�I�Ȍ��`��؎������𒿏d��������V��Ƃ̑���_�ł��낤�B���Ȃ��Ƃ������w�I�ɐM���ł�����@�����ɂ����āA����V��̂��Ƃ��閧��`�̌��������ς͌��o���Ȃ��B
�@���̓��@�ɕ�����̂��A��Ύ��嗬�̏��̊ю���閧�̌������������ȂǂƐ�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�P�ɑ�Ύ��Z���̈ӎ��������͌��ʂƂ��Ă̗B��҂̗��ꂵ���\�����Ȃ������B���������ŁA��Ύ��嗬�̎��ӂł́A�^�U�����ŖT�n�v�z�Ȃ��瑊���̌��Ђ�������������X�ɓo�ꂵ�n�߁A16���I���ɂȂ�Ƒ�Ύ��̊ю厩�炪�u���X�t�@�v�̌��Ђ�ϋɓI�ɋ�������Ɏ����Ă���B
�@�ŏ��ɁA�����̑�Ύ��嗬�ƒ��ÓV��Ƃ̊W���T�ς��Ă������B�����̒�q�Ō�ɏd�{�k���̑���w���ƂȂ�O�ʓ����́A�ꎞ���A��b�R�ŏC�w���Ă���B�w�������J�������x�i���S�ʖ{�j�Ɂu�����c�t����̌Í��ɂ͕x�R�ɓ����ċ������t�̖��P�����N�C�w�̒��Ԃɂ͉b�x�ɓo���ēV��l���̗H�����f�Ёv�i�x�v�Q�[�Q�R�j�ƁA�܂��w�{��S�ꏴ�x�i����ʖ{�j�ɂ��u�����c�t�̐́E�x�R�Ɍw�ŋ��������t�̖��P�ɗa��A����̌�E�b�x�ɏ��ĎO�u�̌��O�ɗ��A�ߗ����[�@�̊w�s���ΏC���v�i�x�v�Q�[�R�U�j���ƋL����Ă���B
�@���ɁA��Ύ����̊ю�̎��ՂׂĂ݂�ƁA5���E���s�A6���E�������A���ꂼ��֓��V��ŏC�w�����\�����l������B�ߔN�̌����ɂ��A�w�̐S�v�`�W�E���������x�Ȃ鏑����Ύ��ɏ�������Ă���Ƃ����B�w�̐S�v�`�W�x�͊֓��V��̊w���ł��鑸�C�̒�q�E�G�C�̒���ł���A�G�C�Ɠ�����̑�Ύ�5���E���s��������E���ʂ����ʖ{����Ύ��ɓ`����ꂽ�B�����č]�ˊ���24���E���i�Ɏ���A���̓��s�ʖ{���炳��ɔ������A���i���g�̌����������Đ����������̂��w�̐S�v�`�W�E���������x�ł���Ƃ݂���B���̏��̖`���ɂ́u�̐S�v�`�W�����V�𑊓`���@���s�V�B���l����i�@���ɉ]���A���s�̌�M���V��q�������Ƃ̊̐S�����B�L���S�������v�A���ɂ́u�E�Z�\�܃����̖@��͓��R��ܑ���s��l���M�ɂĔV���ʂ��B�A����Ƃ̔鑠�V�����̂Ɍ���̐m�����Ɉ������͂��ĔV���v�ӂׂ��v���ƋL����Ă���Ƃ����B�w�̐S�v�`�W�x�͓����̊֓��V��̏��k�тŊw�ꂽ���ƌ����A���̓��e�͒��ÓV��̌��`���w�̋L�q�ł���B���̂��Ƃ���A��Ύ��ܐ��̓��s�͓����̒��ÓV��̌��`���w��M�S�Ɍ��r���Ă����Ɛ��@�����B
�@�܂�6���E�����Ɋւ��ẮA9���E���L�́w�L�t���꒮�����x�Ɂu���Y���S�̍����͕�����g�̌����@��ɂėL�肵���A�x�m��{�̊w���ɐ��苋�ӂāE�L�肵���a��̏Ɖ]�ӑ�̒h�߂̏��ɂāE������l�̌�㊯������l�ɑ���肵��@���ЂĂ܂苋�ЂāE�T���A�������ЂČ�v�i�x�v1�|�Q�P�O�j�Ƃ̋L�q�����邱�Ƃ����ڂ����B���V��@�\���̓��Y�i��Ɍ��{�@�؏@�̊J�c�ƂȂ�j�������̑㊯�ł��鎵���E�����Ƃ̖ⓚ��ʂ��ĕx�m��ɋA�������Ƃ̋L�^�ł��邪�A�������������������֓��V��̐�g�k���ƌ�ʂ��Ă����l�q������������B
�@�����̂��Ƃ��A�����̑�Ύ��嗬�ł́A�֓��V��̒k�����b�R�ŏC�w�����m�炪�ю哙�̗v�E���߂Ă������̂Ƃ݂���B
�@�i�Q�j�w�{���������x�́u�B����l�v��
�@�������Ȃ����Ύ��̗��ɗ�����s������ɂ́A���ÓV��̑��`�d���A�����d���̎v�z����̉e�������o���Ȃ��B�Ƃ�킯�����̌����ɂ́A��Ύ��Z���Ƃ��Ă̎��o���ۗ����Ă���B
�@����ɑ��A�b�R�V�w���o�ďd�{�̊w���E�߂��O�ʓ����Ɋւ��ẮA���ÓV��̑��`�d���̎v������e�������\�����������Ă����K�v������B�Ƃ����̂��A�w�{�������x�̒��ߏ��ł���A�����̍�Ƃ����w�{���������x�̖����Ɂu���̌����͍��c���l�E�O���ܔN�\���\����̌�L���E�B����l�̈�l�͓�����l�ɂČ����v�i�x�v�Q�[�W�S�j�Ƃ̈ꕶ�����邩��ł���B����ɂ́A��Ύ����w�j�ɂ����ď��߂ē��@�[�����́u�B����l�v������������������ł���Ƃ����B
�@�ނ��A�u�B����l�̈�l�͓�����l�ɂČ����v�Ƃ̕��݂̂������āA�w�{���������x�Ɋю��Ή��̎v�z������Ă���Ƃ܂ł͌����Ȃ��B����ǂ��A�����̕������i����������́j�Ɂu�B����l�v�Ƃ����p��͊F���ł���B�B����l���������������ۂ��ɂ�����炸�A�������u�B����l�v��\�Ɍf���Ď�������ЂÂ��邱�Ƃ͂Ȃ������B������v���A�w�{���������x�̖������u�B����l�v�̌��Ђ�ϋɓI�Ɏ]�Q���Ă���̂́A������`�I�Ȋю��ΐ��̖G��ł���ƌ����邩������Ȃ��B
�@�������A�×����w�{���������x���U��Ƃ���_�҂͑����B�Ⴆ�A�����Ɂu���@��@�v�i�x�v�Q�[�W�O�j�u���@�@�v�i�x�v�Q�[�W�Q�j�Ƃ������\��������̂͊�قȊ����������B�����̑��̒���ł���w�������J�������x�w���ח������x�w�O�^���j���x�ł́u�@�؏@�v�Ƃ������t���p�����Ă���B�w�������J�������x�Ɂu�@�؏@�ƌĂԂ̑��E���S�y�ɂ��āE���邱�Ƌ��t�ɋA���v�i�x�v�Q�[�Q�Q�j�ƋL����Ă��邲�Ƃ��ł���B�u���@�@�v�Ƃ������̂́A�V��5�i1536�j�N�̓V���@�̗��œ��@���c���u�@�؏@�v�̖��̎g�p���֎~����Ă���p����悤�ɂȂ����ƌ�����B��������l����A�u���@�@�v�̗p�ꂪ�p�o����w�{���������x��14���I�ɐ����������̍�Ƃ݂�͓̂���B�Ƃ͂����A�x�m�嗬�W�̎j���ł́w�����k�x��w�L�t���꒮�������Ձ@��x�̒��Ɂu���@�@�v�̕������݂���i�x�v�Q�[�P�R�Q�A�P�[�P�X�S�j�B�䂦�ɒf��I�Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��B
�@�܂��i�\���i1558�j�N11���A13���E���@���A�v�@�����C�ɑ���ʗp���ۂ̏�����쐬����ɂ�����A�w�{���������x�̈ꕔ����������ؗp���Ă���B������Ɂu�{�������@�吹�l���v�������̎���p�g�Ǝ���ߐ\���ׂ��Ȃ�A�Ƃ����̕���瑖�\���̋���Ȃ��瑋@�̏n�E��@�v��������ӂȂ�A���팠�Ȃ�Έʖ퍂������Ȃ荟�̕��̏�������@�͏I�ɓ��o��]���Ė��o�ɓ���Ȃ�B���č��c�̉��������@�͌���藝���Ȃ�A�����ʒn�̖��@�𗝑��̖}�l�ɗ^���ӂ͓��o��]���ė����ɓ���Ȃ�B�ݐ����ɐ������N�̌���������b���������l��o���̎����ɐ�������{�L�̖��@��O�������֕��s��̐g�Ɋ�̗��Ԃ��������������ł��҂Ȃ�v�i��S�P�[�S�T�O�j�Ƃ����L�q�����邪�A���͂���Ƃقړ������e���w�{���������x�̒��ɂ݂���i�x�v�Q�[�W�R�j�B�v�@�����C�ɑ��������@�̏���́A���R�Ȃ����Ύ����Ɏc��Ȃ��B���������āw�{���������x�̍�҂����@�̏���̓��e���݂ĎQ�l�ɂ����\���͒Ⴍ�A�t�ɓ��@�̕����w�{���������x�̈ꕔ�������̐��̂��Ƃ��p�������̂ƍl������B
�@���������_�܂��A�w�{���������x�̐������ꉞ�A16���I�����Ɛ��肷�邱�Ƃ��ł��悤�B�w�{���������x�̎ʖ{���݂Ă��A�ߐ��̂��̂������B
�@���ɁA�w�{���������x�̓��e�ɂ��Č�������B���@���@�̑勴�����ɂ��A�x�����́w�{���������x�̓��e�ɂ��āu���̎���Ƃ��ēV��F�̂�����̂�����B�䂦�Ɉ�ʓ��@�@�ł́A�����͌�l�����t�ɂ������āA�V��F�̂�����̂��������Ƃ݂Ă���B���������@�吹�l�̂��́A���̂��̂��A���ÓV��̐����g�p���Ă���B�䂦�ɏ��t������������Ƃ����ċU��ɂ���͕̂ςł���v�Əq�ׂ��Ƃ����B�Ɠ����ɁA�u�����ɂ͑F�v���Ƃ����ʑ肪����B�������܂��A�Ђǂ����̂ł���v�Ƃ��]�����Ƃ����B�勴�̋L�^���ǂ��܂Ő��m�Ȃ̂��s���͎c�邪�A������̗p����A�����́w�{���������x�������Ƃ��Ȃ�����A���́u�����v�ɂ��Ă͋^�O��悵�Ă���B�����̌����u�����v���ǂ����w���A�ǂ̂悤�Ɂu�Ђǂ��v�̂��A�勴�̋L�^����͂悭�킩��Ȃ��B���������́u�B����l�v�]�X�̕��́A�܂��ɓ������̖����A�������u�F�v���v�Ə����ꂽ��ɓo�ꂷ��B���@�[�����́u�B����l�v�����������铯�����̖����̉ӏ��ɂ��āA���������炩�̈Ӗ��ʼn��^�I�������\���͏\���ɍl������B
�@�܂��������́u���̌����͍��c���l�E�O���ܔN�\���\����̌�L���E�B����l�̈�l�͓�����l�ɂČ����v�Ƃ������ɂ�����u�O���ܔN�\���\����̌�L���v�Ƃ́w�{�������x���w���Ă���B�w�{�������x�̖����ɂ́u���̌������ɖ{���̑厖�͓��@��������`�@�̏������������h���B����l�̌����Ȃ�v�i�S�W�W�V�V�E��{�Ȃ��j�Ƃ���̂ŁA�����ɂ݂���u�B����l�̌����Ȃ�v�́u��l�v�������̂��Ƃł���A�Ɓw�{���������x�̍�҂͎咣�����̂�������Ȃ��B���@���@�́u�@�`���r�ψ���v���A���́w�{�������x�̖��������ƂɁw�{���������x�́u�B����l�v�̕��ӂǂ������Ǝ咣����B�������x�����́A�w�{�������x�̖�����������Ɣ��肵�Ă���̂ŁA�w�{���������x�́w�{�������x�̌������������Ɍ�̎���ɏ����ꂽ���ƂɂȂ�B��������ƁA�w�{���������x�̕��́u�B����l�v���@���Â̓����̋L�q�Ƃ݂�̂͑����ɋꂵ���B
�@�Ȃ�A�u���̌����͍��c���l�E�O���ܔN�\���\����̌�L���E�B����l�̈�l�͓�����l�ɂČ����v�Ƃ̕����h�w�{�������x��������B����l�ő������ꂽ�h�Ƃ����Ӗ��ɉ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤���B�E���̎����Ɂu�{�n�r�[�̉��`�E���@���v�̍����Ȃ�A��ɐM�S�[���ҁE��V�ɌP�`����Ӂv�i�x�v�Q�[�W�S�j���Ƃ��邱�Ƃ���A���̍�҂́A�������B����l�ő������ꂽ�w�{�������x�̉��`�𒍎߂������Łw�{���������x�����̂�������Ȃ��B����ǂ�����́A���@���@�ɂƂ��ēs���̈������߂ɈႢ�Ȃ��B��Ύ���17���E������56���E�����́A�w�S�Z�ӏ��x�w�{�������x�̗�����B����l�̑������Ƃ͍l���Ȃ������B�����̑����́u�@��y�t�̑����v�i�w�٘f�ϐS���x�j�Ƃ���̂��A�ߑ�ȍ~�̑�Ύ��@��̒k���ł���B�Ƃ���ƁA�w�{���������x�����ɂ݂���u�B����l�v���͖@�告���̎����ł̗B����l�ł���A���@���@�̕ʕt�̗B����l���������������Â��镶�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@�ʂ̊p�x����A������_�����q�ׂĂ������B�w�{���������x�������Ƃ���A����͏d�{�n�̑m�̒��q�ł���B���̓_�͈ӊO�ɏd�v�ł���B�w�������J�������x�ł́u������l�́E������@���l�̕t���E�{�及�`�̓��t�Ȃ�v�i�x�v�Q�[�Q�Q�j�Ƃ��u�����a���́E��������l�̒�q�E���ڑ����̑哿�Ȃ�v�i���O�j�Əq�ׂ��A�u�ꗬ���`�̌����v�i�x�v�Q�[�Q�S�j�Ƃ��āq�߉ޔ@����s��F�|��g���@�[�����[�����[�����[�����E�喭�r�Ƃ������悪���Ă��Ă���B��������l����ɁA�w�{���������x�������Ƃ����ꍇ�A���́u�B����l�̈�l�͓�����l�v�Ƃ̋L�q�́A������������A�����ւƎ��悵�Ă����d�{�̊w��E�̗����O���ɗ������ׂ��ł���A�����[���ځ[�����[���s�Ƒ�����Ύ��̑����n���̎n�������镶�Ƃ��ׂ��ł͂Ȃ��B
�@
�i�R�j�w�ܐl���j�������x�̊ю�M�I�ȕ\��
�@�w�ܐl���j�������x�́A���@�̓��ł����100�N��A�N��2�i1380�j�N�ɖ��@�����Ⴊ�������Ɠ`������B�������ɂ́u��������������ʂЎ���ɏ���ʂЂē�������̖@��̏��ɋA��W�鏈�̖@�،o�Ȃ�Ζ@���ɂč݂���v�i�x�v�S�[�X�j�Ƃ����ю�i�@��j�M�I�ȕ\�����݂���B�����ɂ́A���炩�ɑ�����`�I�Ȋю��ΐ�������Ă���B�����������āA�@����ɂ��ю�M���������Ƃ݂Ȃ��ׂ��Ȃ̂��낤���B
�@�w�ܐl���j�������x�͓���̐^�M�������A�x�����̈ӌ��ł͓`�ʖ{�ɒʓǂ���قǂ̍�����肪��������i�x�v�S�[�Q�U�j�A���e�I�ɂ��U�������Z���Ƃ���Ă���B���ѐ����́u�@���Θ_�̌`���Ƃ��̔ᔻ�v�̒��ŁA�{��p�C�̐��܂��u�w�ܐl���j�������x�ɂ͖��炩�ɕ���2�i1470�j�N�ȍ~�łȂ���Ώ����Ȃ��L�q������A���@��������ɑ傫�ȋ^�₪�����������Ă���v�Əq�ׂĂ���B�܂��r�c�ߓ��́A���������̑O���E�����́w�S�\�ӏ��x���Ɠ������Ƃ̓��e�I�ȑ����Ȃǂɒ��ڂ��A���̐��������w�S�\�ӏ��x�����w�ܐl���j�������x�ƍl���Ă���B
�@�����镶���w�I�ȏ���肪�����邱�Ƃ܂��A�w�ܐl���j�������x�́u��������������ʂЎ���ɏ���ʂЂē�������̖@��̏��ɋA��W�鏈�̖@�،o�Ȃ�Ζ@���ɂč݂���v���X�̕����ɂ��ĉ��߂Č������Ă݂悤�B
�@���ɁA�����ŏq�ׂ���u�@��v�u�@���v�̌ꂪ���ƂȂ�B�x�����ɂ��A����͓�������̖��q�ł���A��Ύ��̎l���E������ܐ��E���s�̎w�������Ƃ����B��������q�̂��Ƃ��A�����E���s�֘A�̏��j���̂����ɑ�����`�I�Ȋю��ΐ����݂ĂƂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂��w�ܐl���j�������x�������ꂽ�Ƃ����N��2�i1380�j�N�����A��Ύ��@��𗦂��Ă����̂�6���E�����ł������B��Ɏ������Ƃ���A���̓����ɂ���Ύ��Z���Ƃ��Ă̈ӎ������݂�ꂸ�A������B����l�́u�@��v�Ƃ��Č��ЂÂ����L�^�ȂǑ��݂��Ȃ��B���̂悤�Ȓ��ŁA���@���̓��Ⴞ�������������X�́u�@��v�ւ̖@�،o�t����͐�����Ƃ����̂́A�����ɂ��s���R�ł���B�������A���̖@�،o�t���̕��ɐ旧���āu���@���l�V��t���O���ܔN�㌎�\����A���\���\�O���̌���ł̎��̌䔻�`������v�i�x�v�S�[�W�j�Ƃ���A�����嗬�ł͏��߂ē�ӑ����̑��݂𖾂����Ă�����B
�@�嗬�̊J�c�ł���������u�@��v�ƌ����Ƃ��A����͏�ɏ@�c�̓��@�̂��Ƃ��w���Ă����B�䂦�ɏ��̑�Ύ��Z�E�������A���g���u�@��v�Ə̂�����A�Ă�����͂��Ȃ������B�Ƃ��낪�A���������9�����L�̔ӔN�ɏZ�{���n�̍�����������Ύ��ɋA�����A���߂đ�Ύ��̗��ю���w���āu�@��v�Ə̂��n�߂��B�����́A��ӑ����̓��e�����߂ċL�q���A���̈Ӌ`�����������w�m�Ƃ��Ă��m����B�����������Ƃ���l����ƁA�����Ō�̖���̑�Ύ��Z�E�����u�@��v�Ə̂��A�Ȃ�����ӑ����������o���Ă���w�ܐl���j�������x��嗬��Â̐����Ƃ݂�͓̂���B���������̉e�����ɐ����������̂Ƃ݂Ȃ��̂��A���e�ʂ��猾���Ă���Ԕ[���ł���B
�@����ł��A�����āw�ܐl���j�������x�̒��҂����@������ł������Ɖ��肵���ꍇ�A����͒��ÓV��̎v�����牽�炩�̉e�����Ă����ƍl����ׂ����낤�B���ÓV��̓��`�@��I�ȓ`���`�Ԃ́A���@�̎�����܂߁A�����̓��{�����E�������v���ł������B���R�A����͏����̓����嗬�ɂ��y��ł����ƌ�����B���@��������w�m�ƌ���ꂽ�ȏ�A���ÓV��̖@��₻�̓`���`�ԂɊւ��ď\���Ȓm���������Ă����͂��ł���B�ނ��A�������猌�������A���`�d���̎v�z��ێ悵�A�����嗬�Ƃ��Ă̖@�،o�̌��������̌n����z�肵���\�����S���l�����Ȃ��͂Ȃ��B
�@�������A���Ƃ��������Ƃ��Ă��u��������������ʂЎ���ɏ���ʂЂē�������̖@��̏��ɋA��W�鏈�̖@�،o�Ȃ�v�]�X�Ƃ����w�ܐl���j�������x�̕��Ɋւ��ẮA�����܂ő�Ύ����ɂ�������̖T�n�v�z�Ƃ��ė������Ă����K�v������B�J��Ԃ��悤�����A������̑�Ύ��ю�̕����ނɁA�����鑊����`�݂͂��Ȃ��B
�@�ȏ��v����ɁA����M�Ɠ`������w�ܐl���j�������x�͋U���ł���^���������A���̊ю�M�I�ȕ\���͖T�n�v�z�ł�����B���Ƃ�����́A��Ύ����̏Z���ł͂Ȃ��B����ē������́A�����̑�Ύ��嗬�Ɂu�����̊ю�͐�v�Ƃ����M�������������Ƃ𗠂Â���j���ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��̂ł���B
�@�@�@�V�@�嗬���̊ю�ɂ݂�B����l�I�Ȍ��Ў�`�̕s��
�@�E�̍l�@�ɂ��A�w�{���������x�w�ܐl���j�������x�̗����������@���@�̑�����`�I�Ȋю��ΐ��̍����Â��Ƃ��ėp����̂́A�ɂ߂ē�����Ƃ����m�ɂȂ����ƐM����B�����ő��̊p�x������A�嗬���̑�Ύ��ю�ɂ͗B����l�I�Ȍ��Ў�`�ɂ�鎩����Ή��̎v�z���Ȃ������A�Ƃ����_���m�F���Ă��������B
�@���m�̂��Ƃ��A�嗬�̊J�c�ł�������́A��t�̓��@���Z�V�m���߂���ɂȂ炢�A���ځE���E���G�E���T�E����E����̘Z�l����p�̍���Ƃ��Ē�߂��B�܂��d�{�Ɉڂ��Ă���́A�V���ɓ���E�����E���r�E�����E���|�i�����j�@�E�����̘Z�����A������u�V�Z�l�v�̒�q�Ɏw�������B
�@�����͎����̎���A���c�^�c�̖ʂł͈��̉Ǔ�����]��ł����Ǝv����B�������Ȃ�������́A�w�����՞��X���x�̒��œ��ڂ̂��Ƃ��u���q�v�ƕ\�����Ă���̂ŁA�ŏ��̘Z���̖{��q�̒��ł����ɓ��ڂ𒆐S�҂ɒ�߂Ă������Ƃ��m����B���łɏq�ׂ����A���Ȃ��Ƃ��w�����՞��X���x�̈ĕ��͓����M�Ƃ݂���B�����ɁA���ڂ������ē����̐����Ƃ���L�q�����R�Ƃ���킯������A�����Ɉ�l�̒�����߂�Ӑ}�����������Ƃ͋^�����Ȃ��B�����̒���I�o�͓��@�̍l���������炵�����̂Ǝv���A���@���܂���l�̒�����߂����Ƃ��z���ɓ�Ȃ��B���R�A�����钄��I�o�̐��ɏ]���A�嗬���̑�Ύ��ю����l�̒�����߂ėߖ@�v�Z���������ł��낤�B
�@����ǂ��A���̂悤�ȏ��̒���I�o�̂�������A�㐢�ɐ�������ю��Ή��Ƃ��Ắu�B����l���������v�v�z�Ɠ��ꎋ���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@���z�̑�Ύ��嗬�ɂ����Ă��A���̊ю傩���l�̒���ւƏd�v�@�`�����`���ꂽ�Ƒz�������B����ǂ��A����ɂ���Đ_���`�I�A�`����`�I�Ɍ�p�ю傪��Ό��Ђ��l������悤�ȕ����͂Ȃ������ƌ�������B�M���ł���j���Ɋ�Â�������A��������ڂ͗B����l�I�Ȍ��Ђ��֎�������A����ɂ���Ď������Ή�������͂��Ă��Ȃ��B�ނ�������Ȃǂ́A�@�c���������u�˖@�s�ːl�i�@�Ɉ˂��Đl�Ɉ˂炴��j�v�̌P���ɑ���A���嗬�̊ю�̌��Ђ��Ӑ}�I�ɑ��Ή����Ă���B�ނ́w��u����\�Z�Ӟ��x�ɂ́u���̊ю��嫂����@�ɑ��Ⴕ�Ė��`���\���ΔV��p���ׂ��炴�鎖�v�i��S�P�|�X�W�j�u��t�̔@���\�����V�����m�ׂ���A�A�����̊ю͏K�w�̐m�ɉ��Ă݂͐���U��媱�ƗL���嫂��O�ނɍ��u�������v�i��S�|�X�X�j�Ƃ�����ڂ�������قǂł���B
�@�܂������E���ڂ̖Ō�A��Ύ����p�����l���E�������A�B����l�I�Ȍ��Ў�`�������đ��n�̋���h��ᔻ������͂��Ă��Ȃ��B��̓I�ɂ݂Ă݂悤�B���ڂ̏}������2�N���o�߂�������2�i1335�j�N�A��Ύ��l���E�����͓����֏���𑗂����B���̒��œ����́A�u������l�̌�Ղɐl�l�ʖʂɖ@��𗧂ĈႢ��B���͓V�ڂ̕��֕i�s���u�ɓ����A���͊��q����瑖哾���̎|�ɓ����ė��Đ\����B�B������l���`�𗧂�ԋ��G�[������v�i��S�P�[�Q�W�V�j�ƋL���A�����̖嗬�������`�ʁA�C�s�ʂō����̉Q���ɂ��������Ƃ�����ɓ`���Ă���B�����͂����Łu�B������l���`�𗧂�v�Ƃ̎��o�����l���Ă��邪�A���̎��o�͓����Ɠ��l�́q���ʂƂ��Ă̗B��҈ӎ��̕\���r�ł��邱�Ƃ������㖾�炩�ł���B�����������A�����[���ځ[�����Ƃ����@���n�����ł��d�����A������`�I�Ȋю��̎v�z��L���Ă����Ȃ�A�^����Ɏ����̌��������̐����������ʂɋL���Ȃ��킯���Ȃ��B
�@����Ɍ����A���̓����̏���̌�A�����嗬�ɑ����鉽�l���̍��m���{�����ʂ��s���Ă��邪�A������������ᔻ�����������c���Ă��Ȃ��B�㐢�̑�Ύ��嗬�ɂ����Đ��������r���I�ȑ�����`�Ɋ�Â��ƁA�B����l�̋������������ɖ{�������ʂ���s�ׂ͑�Ȃ�掖@�s�ׂƂ����B��掖@�͎��@�E���@���킸��������ӂ���[�[���ꂪ�@�c�E���@�̌����ł������B�ɂ�������炸�A�������A�����Ɠ�������ɑ����鏔�m�̖{�����ʂ��掖@�Ƃ��ę�߂��Ƃ����j����̎����͂Ȃ��B�������畂���яオ���Ă���̂́A17���E�����̍�����ڗ����n�߂�q�ю��l�̖{�����ʁr�Ƃ����v�z���嗬���ɂ͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł���B
�@������A�����[�������������Ă݂悤�B�����̓��₩��9�N��̗5�i1342�j�N�ɏ����ꂽ�O�ʓ����́w�����x�̒��ɁA���̂��Ƃ��L�q���݂���B
���吹�x�R���̈�Ղ�撿����ɁE�M�ˌ݂��ɕΎ��������E���������ً`�𑶂��A����m��ʈ�͐��ɂ��ė]�͔�Ȃ邱�Ƃ��A�����ΊF���~�ƈĂ̈��Ђ��A�\�����@�Ҏz�l������̌o���������_�̔@���A��������u�E�גq�z�Ȃƕ��L毂ɑ��@�Ɍ�����c�c���ƈꖡ�̎t�h�̒��ɑ厖��������ƁE�o���̎��͖{�������������Ċe���`�����ցA�ΐ���j�p�����߂ċX�����O�c�𐬂��ׂ��A�R�炸��Ό�y��掄�Ȃ��\�l�@���ɒf��ɋy��i�x�v2�|28�`29�j
�@�E�������ɖƂ����Ȃ�B�[�[�@�J���c�̖Ō�A����ł́A�m�K�̋M�G�ɂ�炸�݂��ɕΎ��������A�ً`�𗧂Ă�悤�ɂȂ����B���`�͈�ł��葼�͌��ł���Ƃ����̂ɁA���炭�F�A�~��ƈĂɎ������Ă���̂��낤�B�u�\�����@�Ҏz�l������v�̌o�����܂��ɕ��_����ł���B�u��������u�גq�z�ȁv�Ƃ̌o���͑��@�Ɍ���Ȃ��E�E�E����A���嗬�̑m���̊Ԃŏd��ȏo���������������ɂ́A�{���̑O�ŘA�����A�ΐ��ȐS���̂ĂĊF�ŋc�_���Ȃ��ׂ��ł���B�����Ȃ��A��y�͂܂��܂���������������悤�ɂȂ�A�l���@�����ɒf�₷��ɋy�Ԃ��낤�\�\�B
�@���������O�ʓ����̒Q�����݂Ă��A�����̓����嗬�ɗB����l�I�Ȍ��Ў�`���������Ǝ咣���邱�Ƃɂ͖���������B�����͏d�{�k���̑���w���܂Ŗ��߂����m�ł���B���̓������A�B����l�̌��Ђɂ������ԓx�Ȃǔ��o���݂����A�����F�ŋc�_�������ċ���̐��`�𗧂ėߖ@�v�Z�������ׂ����Ƒi���Ă���̂͂ǂ������킯���B�[���ł��铚���͈�����Ȃ��B����́A�����̓����嗬���ɗB����l�̌����𐳎ׂ̐�ΓI��Ƃ���v�l�͂Ȃ������A�Ƃ��鐄��ł���B�nj��̌���A���z�̑�Ύ��嗬�ɂ����Ċю傪������`�I�Ɏ��Ȑ�Ή����͂��铮���͐₦�ĂȂ������B�{�e�̑O������߂�����ɂ�����A���̓_�͉��߂ċ������Ă��������Ǝv���B
�@�@�@�W�@9���E���L�ɂ݂�h�M�S�̌����h�̋����Ɗю�㊯��
�@����̖��쎛�����ɂ��ƁA9���E���L�͉��i9�i1402�j�N4��16���ɐ��܂ꂽ�B�����̑�Ύ��́A��70�N�ɂ��y�ԓ����嗬�Ƃ̌W���ɂ���Ĕ敾�̋ɂ݂ɂ������B���̂悤�Ȓ��A���L�͑�Ύ�8���̓��e���t�Ƃ��ďo�Ƃ��A�C�w�ɗ�B���i26�i1419�j�N�A�t�̓��e�������������A���̔N�ɎႭ���đ�Ύ��̖@�����p�������̂Ɛ��肳���B
�@���L�̎��Ղ��݂�ƁA�����k�т̌c�w���g�k���́u���O���t�v�ƌ𗬂��Ă����l�q�����������A��Ύ����̏��t�̗�ɘR�ꂸ�A���ÓV��̎v�z�ɐ��ʂ����l���������ƍl������B���炭���L���A�֓��V��̒k�тɂ����Č��`�@�哙��M�S�Ɋw�̂��낤�B
�@�������Ȃ���A���L�͒���V��̖@��ɌX�|���Ă����킯�ł͂Ȃ��A�ނ��낻��ɔᔻ�I�ȗ�����Ƃ��Ă����B���̂��Ƃ́A�A�z�[�̕����Ɂu�q�d�ˊo�����@�Ȃ�ΓV��@���Ɏᘰ�̒q�҂��营�ꖔ���@�ɔ��Ȃ�A���ĐM�S����ɂ��ċؖڂ��Ⴆ�����@�C�s������C�s�L�闬�z�Ƃ͉]�ӂȂ�v�i�x�v�Q�[�P�S�U�j�Ƃ��邲�Ƃ��A�V��I�ȁu�q�d�ˊo�v��ނ��đ�Ύ��嗬�̐M�S�d���̗�����g����Ƃ���ɖ��炩�ł���B���L�͒��ÓV��̌��`�@���m�邱�Ƃɂ��A�������đ䓖�̑���m�Ɏ��o���A��Ύ��Ǝ��̉��핧�@�̗�����m�����悤�Ƃ��Ă����B
�@�ʓr�̓��@�剺�����@�̖{�ӂƂ���v���{�ʂ̕��Ɩ@�͍ݐ��E�v�ׂ̈ł���B���@�̓V�䂷��{�ʂ̖@���ύs���̈ʂɈ��������A���S�̈����̊ϖ@���C�s�����B�����▖�@�́A���@�̒q�҂ɋy�ʎO�ŋ����̖}�v�ł���A�䓙�}�v���{�ʂ̖��@�̗��v�邱�ƂȂǂł��Ȃ��i���숢苗��̕����A�x�v�Q�[�P�T�Q�j�B�����l�������L�́A���@�̋���̏O���͖������S�̈ʂŗ����{�@�̎�q���閭�@��M�ׂ��A�Ɨ͐������i���O�A�x�v�Q�[�P�T�R�j�B
�@�Ƃ���A���������Ɋւ��Ă��A���L���V�䗬�́u���������v�̍l������ϋɓI�ɍ̗p�����Ƃ͍l���ɂ����B�ȉ��A�{�߂ł́A���L�̐^�̌����ς�ю�ς�_���Ă������Ƃɂ���B
�i1�j�l�@�{���ւ́u�M�S�v���t�푊���Čp���|���L�̌�����
�@�ŏ��Ɏw�E���Ă����ƁA���L�k�Ƃ���鏔�����̒��ő�Ύ��́u�B����l���������v��_�����ӏ��͈���Ȃ��B���L������ɋ��������͎̂t�푊��ʂ����u�M�S�v�̌����ł���A����͓��@�̌����ςƓ��`�ł���B
�@���L�ɂ��A�t�푊�Ƃ͖}�v�̗���Ŏ��̈�O�O��𐬏A���邽�߂ɕK�v�Ƃ����C�s�ł���B���@�ɂ����ẮA�F���O�ŋ����̍r�}�v�ł���B�}�v���ɉʂ̌���ɂ́A���@�@�،o�̐M�S�ɂ�邵���Ȃ��B�����ŁA���@�̖}�v���M�S�C�s�ɗ�ނ����ł́u�t�푊�v�Ƃ�����������s���ƂȂ��Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�t�푊�̉��V�ɂ���ĐM�S�����@�����Ă����Ƃ���ɁA�t�i���E�j��i��E�j�����̎��̈�O�O��A���g�����̎p�������邩��ł���\�\�B���ꂪ���L�̎t��_�̍��q�ł��낤�B
�@�����Œ��ڂ��ׂ��́A���L�ɂ�����t�푊���u�t�틤�ɎO�ŋ����̖}�v�v�ł��邱�Ƃ�O��Ƃ���_�ł���B�A�z�[�̕����ɂ́A���L���u���@�����͈��S�݂̂ɂ��đP�S�����E�t�틤�ɎO�ŋ����̖}�v�̎t�푊���āE���]�O�������@�@�،o�����鏈�g�����Ƃ���������Ƃ��]�͂��Ȃ�v�u��ܕS�̍����Ɏt�틤�ɎO�ŋ����̋��Җ��҂̏�ɂ��ĈʁE�����̏��S�ɋ����Ďt�푊���Ė��]�O�Ȃ��얳���@�@�،o�Ǝ��閼���͉���Ȃ�A���̉���Ɉ˂��ďI�ɒE����Ȃ�v�i�x�v�Q�[�P�S�V�j�Ȃǂƒk�������Ƃ��L����Ă���B���L�̏ꍇ�A�t�푊�ƌ����Ă��A�t��̊Ԃɖ{���I�ȋ��U�̍��ق�F�߂���̂ł͂Ȃ��B�t�ł���A��q�ł���A�Ƃ��Ɂu���Җ��ҁv�̖������̈ʂł���Ƃ��A���̈Ӗ��Ŏt�핽���̈ӎ��ɗ��̂ł���B���L�́A�u��t���v�ɂ��āu���Ƃ̖{���v�Ƌ����@����u���f�f�̓��t�v�i�w���V���x�A�x�v�P�[�U�T�j�ƈӋ`�Â��Ă���A���̖{���_�I�Ȏt�핽���̈ӎ��͂܂��ƂɓO�ꂵ�Ă���B
�@���������ē��L���u�t�푊�v��u�{���t��̋ؖځv����������̂́A�����t�ƂȂ��Ύ��̊ю�▖���Z�E�̑��݂�_�������邽�߂ł͂Ȃ��B���L�̎t��_�̐^�ӂ́A�t�푊�̉��V�������Ď��s�̐M�S�A���̈�O�O��̐M�S�C�s�Ƃ���Ƃ���ɂ���B���L�́u�M�S�Ɖ]���Έ�l���Ă͎���A�t�푊���Ď��s�̐M�S�����v�i�x�v�Q�[�P�U�T�j�ƌ���Ă���B�u�t�푊���鏈������̑̂ɂĎ��s�̖��@�@�،o�Ȃ�v�i�w���V���x�A�x�v�P�[�U�S�j�u����Ɖ]�ӂ͎t�푊�̋`�Ȃ�v�i���B�̕����A�x�v�Q�[�P�T�R�j�Ƃ̓��L�̏��������A���@�̖}�v�͎t�푊���Ă����^�ɖ��@�ւ̐M�S�����Ɓi����j���ł���A�Ƃ��鎖�s�̐M�S�̗������������̂��낤�B
�@�Ƃ������A�u�t�틤�ɎO�ŋ����̖}�v�v�Ƃ����F������o��������L�̎t��_�ɁA���Ў�`�I�Ȏt��̏㉺�W�����o���͓̂���B�w���V���x�ɂ́u���̍s�̂��Ȃ��l�ɂ͎t�͂���Ƃ���V��v���ׂ��v�i�x�v�P�[�V�O�j�Ƃ����ꕶ������B�u���̍s�̂��Ȃ��l�v�Ƃ́A���s�����ɐ��i����M�S�����l���w���Ǝv����B���L�̍l���́A�����܂Łh�M�S���{�̎t�푊�h�ł������B
�@�����l����ƁA�u�����v�Ɋւ���w���V���x���\�����̎��̎w����M�S���{�̐��_�Ɋт���Ă��邱�Ƃ��悭�킩��B
�M�Ɖ]�Ќ����Ɖ]�Ж@���Ɖ]�ӎ��͓������Ȃ�A�M���������Α��ؖڈ�ӂׂ��炴��Ȃ�B��͂���Ό����@���͈�ӂׂ��炸�A�v�Ƃ͐��Ԃɂ͐e�̐S����ւ��A�o���ɂ͎t���̐S������ւ��邪�����@���̒������Ȃ�A���c�����̐M�S����ւ��鎞�͉�ꓙ���F�S���@�@�،o�̐F�S�Ȃ�A���̐M�S����ӎ��͉�ꓙ���F�S�}�v�Ȃ�A�}�v�Ȃ邪�̂ɑ��g�����̌����Ȃ�ׂ��炸�i�x�v�P�[�U�S�j
�@�@�c�E���@�ȗ��́u�M�S�v�������@���̒��g�ł���A�Ɠ��L�͒f����B�����@�����X�����_�鉻������A�t�����Љ�������A���邢�͔閧��`�I�ɉB�������肷��ԓx�́A���L�ɂ͑S���݂��Ȃ��B
�@�Ƃ���ŁA���L�̌����u�M�S�v�Ƃ͈�̂ǂ̂悤�ȐM�S�Ȃ̂��낤���B����́A�J�R�̓����ȗ��A��Ύ��嗬���M���Ă����l�@�{���[�l�{��������@�A�@�{��������@�}���̙�䶗��{���\�\�ɑ��閳��̐M�S�̂��Ƃł���B�w���V���x�́u���Ƃ̖{���̎��A���@���l�Ɍ�������v�i�x�v�P�|�U�T�j�u�@�؏@�͉��Ȃ閼�M�Ȃ�Ƃ��ω��������̏�������F��{���ƈׂ����炸�A���\�E���}�̓��@���l�̗V���ꂽ�鏊�̖{����p�ӂׂ��Ȃ�A���ꑦ�@�،o�Ȃ�v�i�x�v�P�[�V�O�j�Ɩ嗬�̖{���ς����Ă���B���L�͖嗬�m���̐M�s�̑ΏۂƂ��āA�͂�����Ɛl�@�̖{�����߂Ă���B
�@�䂦�Ɂu�o���ɂ͎t���̐S������ւ��邪�����@���̒������Ȃ�A���c�ߗ��̐M�S����ւ��鎞�͉䓙���F�S���@�@�،o�̐F�S�Ȃ�v�i�x�v�P�[�U�S�j�Ƃ�����̓��L�̎w��́A���@�ȗ��̐l�@�{���ɑ���M�S���t�푊���Ď��H�����g��������A�Ƃ̈ӂł���B�܂��A���̐l�@�{���͏�s���`�̖@�̂ɑ��Ȃ�Ȃ��B�l�@�{���ɑ���M�S�́A��s��F�̌����@����M���邱�Ƃł���B�����炱���u�M�S�v�́u�����v�u�@���v�Ɠ��`�Ȃ̂ł���B
�@�����ŁA����̐l�@�{���ɑ���M�S���k�ɋ�����ю�́A�嗬�̋��`���߂̍ō����Ў҂ł��낤�B�����A���̏ꍇ�̋��`���߂̍ō����Ў҂͐�Ό��Ў҂ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���L�́u���`�v��u�@�́v�����u�M�S�v��\�ɗ��Ă������ς�����Ă��邩��ł���B�����ɂ́u���@�̖}�v���A����̒q�d�ˊo�ŋ��`�����S�ɗ��������������肷�邱�ƂȂǂł��Ȃ��B�ю�Ƃ����ǂ������ł���A�����M�S�ɂ���Ă̂ݐ����ł���v�Ƃ���A���L�̓O�ꂵ�����@�}�v��`�������Ă����悤�Ɏv����B
�@���ʂ́u���v�Ƃ͈Ⴂ�A���s�́u�M�S�v�ɂ͉��P��������B���L���u�M���������v�u��͂���v�u�M�S����ւ��鎞�́v�u���̐M�S����ӎ��́v�Ȃǂƌ��A�M�S�̉T���ɒ��ӂ𑣂��Ă���B���������P�I�ȐM�S�̖����ő厖�Ƃ�����L�̌����ς���A�ю��̎v�z���A������͍̂���ł���B�u�����Ō����M�S�͊ю�̐M�S�ł͂Ȃ��v�ƍl����ނ������낤���A���L�́u���̎��j�����]�͂��A���L�q���q���]�͂��A�M�S����Ȃ鎞�͑��g�����Ȃ�E�E�E�A���j�����q�ɂ��ď�ʂƂȂ��ׂ��炸�v�i�x�v�P�[�P�S�U�j�Ƃ��āA�ю�i�����E�L�q�̏�ʁj���܂߂��M�S�̎p���i�M�S����j����ɂ��Ă���B
�@���łɁA�����炪�V���L�t���B����l���������̐�ΐ�������Ă����h�Ǝ咣����ۂɁA�悭�����o���Ă���w���V���x�̑�l�����������Ă������B
�葱�̎t���̏��͎O���̏������c������X��l�̂��ʂ���ꂽ��̂Ɏt���̏���\���\������߂ĐM�����ׂ��A���䂪��q�������̔@�����ɐM�����ׂ��A���̎��͉�������@�@�،o�̐F�S�ɂ��đS���ꕧ�Ȃ�E����g�����Ɖ]�ӂȂ�i�x�v�P�[�U�P�j
�u�葱�̎t���v�Ƃ́A����̎�ɂ���ĕ��@���q�Ɏ�����t���������B�����ł́A��q������Ύ��̊ю�▖���Z�E���w���āu�葱�̎t���v�ƌĂԁB���ƂȂ�̂́u�O���̏������c������X��l�̂��ʂ���ꂽ��v�Ƃ������ł���B�����Ɂu���ʂ���ꂽ��v�Ƃ��邪�A��̉��������ʂ���r�̂��B66���E���B�́A�u���ʂ���Ƃ́A�ցA��A�\���̐����̂Ƃ��A�O���E�����ƁA�����邱�Ƃł���v�Ɛ������Ă���B����ɏ]���A�u�O���̏������c������X��l�̂��ʂ���ꂽ��v�Ƃ����\���́A��̉������A�O���̏����E���c�i���@�j�@�E��X��l�i���ю�j�Ǝp�`��ς��ĒE�炷��悤�Ɏ�̓I�ɘA�����Ă����l���������ƂɂȂ�B
�@�ł́A�O���̏���������@�ցA���@������ю�ցA�Ǝ��X�ɒE�炵�Ă�����̂Ƃ͉����B���B�͂���ɂ��āu�O��������吹�l���炢�A���̖@���l�̂��S���ʂ����āA�t���̏��ɗ��Ă���v�Əq�ׁA���́u���S�v���p�`��ς��ĒE�炷�邪���Ƃ��A�����Ă����̂��Ƃ���B���̓��B�̕\���͔��ɞB���ł���A�l�X�ȉ��߂��ł���B�Ⴆ�A����������́A�q���ʂ���r
��̂��u�吹�l�̌䖽�v�ł���Ǝ咣���A�E�Ɉ��p�����w���V���x��4���ɂ��āu�����l�ɂ͑吹�l�̌䖽�����ʂ����A���ݑ吹�l�̌䖽�͎����ɏh���Ă���̂ł��邩��A�����ɐM���Ƃ�悤�ɂƌ�w�삳��Ă���v�Ɖ��߂��Ă���B�ނ�́A�u�吹�l�̌䖽�v���{���̐��������ю�ɏ��ڂ��Ă������݂́u�@��v�ɏh���Ă���Ɛ����B�܂��ɗB����l�ɂ��ю��Ή��̎v�z�ł���B
�@�������A���̓�����́q���@�̖����h�����@��r�Ƃ����l�����́A���L�̑��̌����Ɩ������Ă���B���E�̕����ɂ��A���L�́u��s��F�̌��g���@��m�͋�E�̒��ソ��{�ʂ̕��E�ƌ���A���Ӎs��F�̍Ēa�����͖{�����̋�E�ƌ���L�ʁB�R��Ζ{�ʖ����@�͌o���������ʂւΖ{�����̓����͎�������q���ʂӎ��t�푊���Ďz�o�̉��V�M�S�̏���\���ʂӖ�v�]�X�i��S�P�[�S�O�X�j�ƒk�����Ƃ����B���L�͂����ŁA���@���u��E�̒��ソ��{�ʂ̕��E�v�A�������u�{�����̋�E�v�ɔz���Ă���B���V��̎w��ł���Ɠ����ɁA��Ƃ̖{���{�ʘ_�ł�����̂��낤�B�܂�A���L�́A�\�E�̈��ʂƂ����ʂ�����@�[�����̎t�푊�̉��V��_���A�t�̓��@�����핧�@�ɂ�����{�ʖ��A��q�̓���������ɑ���{�����Ɨ��ĕ������̂ł���B
�@���̓��L���A�{�ʂ̕��E����u�吹�l�̌䖽�v�̗��ю�ւ̓]�ڂ�����킯���Ȃ��B�܂��A�t�푊�̐M�S�����A�����łɂ͎t�����q�ւƖ{���̐������]�ڂ���̂��A�ƌ����̂Ȃ�A���l�ȐM�S���т���O��M�ނɂ��{���̐������ڂ�h��Ȃ��Ɨ����ɍ���Ȃ��B���L�̎t��_������ю�̓��ؑ������o���̂́A�y�䖳���Șb�ł���B�����Ő������邪�A���L�ɂ�����ю呦���@�̋`���A�ю����@�̑㊯�Ƃ��闧�ꂩ��́A�t�푊�̉��V�̈�ǖʂɌ��肳��Ă���B
�@�w���V���x��l���Ő����ꂽ�����ʂ���r��̂́A�{�����@�̐����Ȃǂł͂Ȃ��B�����͍���x�A���L�̎t��_���т��M�S���{�̐��_��z�N����K�v������B���L���������t�푊�́A�t�����q�ւƌ��Ў�`�I�ɐ��Ȃ���̂������n���悤�ȊW�ł͂Ȃ��B���łɏq�ׂ��Ƃ���A���L�͖{���_�I�Ɂu�t�틤�ɎO�ŋ����̖}�v�v�Ƃ����F�������������Ă����B�������瓱�����t�푊�̉��V�Ƃ́A���Ƃ����E�̑��ɗ��t�Ƃ����ǂ��}�v�Ƃ��Ė��@��M���A���̎t�̐M���q�����̂܂p�������֓`���Ă����A�Ƃ������̂ł��낤�B���ꂱ�����A��Ƃ̖{���{�ʂɂӂ��킵���t��̂�����ƌ����Ă悢�B�䂦�ɓ��L�́A�O�o�́w���V���x��27���Łu���c�����̐M�S����ւ��鎞�͉䓙���F�S���@�@�،o�̐F�S�Ȃ�A���̐M�S����ӎ��͉�ꓙ���F�S�}�v�Ȃ�A�}�v�Ȃ邪�̂ɑ��g�����̌����Ȃ�ׂ��炸�v�i�x�v�P�P�U�S�j�ƒk���A�u���c�����̐M�S�v���u�䓙�v���p�����ׂ����Ƃ��������Ă���̂ł���B
�@�v����ɁA�u�葱�̎t���̏��͎O���̏������c������X��l�̂��ʂ���ꂽ��̂Ɏt���̏���\���\������߂ĐM�����ׂ��v�i�x�v1�|�U�P�j�Ƃ́w���V���x��4���̕����́A�h�u�O���̏������c������X��l�v�́u�M�S�v���O���̎p�`��ς��u�葱�̎t���̏��v�ɗ��Ă���͂�������A���@�ȗ��̐������M�S���������t�����悭����߂đI�сA���̐��t�̐M�S�Ɋw��ł����Ȃ����h�Ƃ����w��Ȃ̂ł���B�w��`���`�x�Ɂu�O���̏����̐������M�̈ꎚ���N��Ȃ�v�i�S�W�V�Q�T��{�E�Q�U�Q�V�j�Ƃ��邲�Ƃ��A�����嗬�ł͎O���̏������u�M�S�v�ɓO���Đ��������Ƃ݂Ȃ��B���L���u���c�����̐M�S�v���ł��d�����Ă���A���@�ȗ��̉���̐l�@�{���ւ́u�M�S�v�����ю�̎t�푊�ɂ���Čp������Ă���l���u�O���̏������c������X��l�̂��ʂ���ꂽ��v���ƕ\�������̂ł���B
�@���ǁA9���E���L�́A�@�c�̓��@�Ɠ������h�M�S�̌����h�̏d�v����i�����ю�Ƃ��ĕ]�������ׂ��ł���B���L�̌����u�M�S�v�́A����̐l�@�{���ɑ���u�M�S�v�ł���B���������L�́A�M�S�d���̗��ꂩ��A���`�̑��`��{���@�̂̏ؓ��Ƃ������ю�̌��Ђɂ�����鑤�ʂ���i�ɑނ��Ă���B�ނ͂����A�ю����ނ��M�S���ő厖�Ƃ���A�Ɨ͐������̂ł���B
�@��Ύ��嗬�ɂ�����ю��ΐ��̐����j�I�𖾁A�Ƃ����{�e�̖ړI�ɖ߂�l���Ă݂�ƁA9���E���L���ю��Ύ�`�҂Ƃ݂Ȃ��͕̂s�K�ł���B���L�́A���ю�ɂ�鉺��̐l�@�{���ւ̐M�S�̓`�����̂������A�M�S�͉T�I�ł��邩��A���ꂪ�q���ݐi�s�`�̊ю�r�̐�Ή��Ɍ��т����Ƃ͂Ȃ��B�T�I�ȐM�S���t�푊�̌����̊j�S�Ƃ��邱�Ǝ��́A�ю�ɂ����T�̌���F�߂Ȃ��Ƃ������L�̍l�����̌����ł��낤�B���L�Ɋւ��長���ނ̒��ɂ́A���L���g���M��̌���Ƃ����̌�������ʂ��o�Ă���B���ؑ����_�I�Ȋю��Ύ�`�͓��L�̍l�����ł͂Ȃ��B
�@���L�ɂ����ẮA���ю�͌��ʓI�ɐ������M�S���т������炱�������̎t�Ƌ���A���݂̊ю�͐������M�S���������萒�h�̑ΏۂƂȂ�B�ނ̎t�푊�ΐ��́A��s�̌����@����M��ю�ւ̐��h��������̂ł���A����Ίю吒�h��`�̗���ɗ��B���̓_�A����ю傪�t�Ƃ��ĐM�S��������Ƃ����̂́A�����܂Ŗ�ނɐM�S�̖͔͂������Ƃ������ƂłȂ���Ȃ�Ȃ��B�����ɂ����āA�����̊ю�͌����Ė@�`���u���ׂ��ł͂Ȃ��v���A�����Ɂu��蓾��v���݂Ƃ�������̂ł���
�i�Q�j�ю�㊯��
�@���ɁA�ߐ��ȍ~�̏@��Ŗڗ����Ă���ю呦���@�̐M���A���L�̉��V�_�ɂ݂��邩�ۂ����l���Ă݂����B
�@�q�{�ʖ��̓��@�[�{�����̓����r�̎p�Ɏt�푊�̉��V�̋��ɂ��݂���L�ɂ����āA�ю呦���@�̉��V�͍ŏI�I�ɂ͔ے肳��邵���Ȃ��B�������A���L�̎t�푊�Ίςɂ͎O�킪����B���ɓ��@�i�t�j�Ɗю�ȉ��̂��ׂĂ̖�k�i��q�j�Ƃ̎t�푊�A���ɖ{���Z��=�ю�i�t�j�Ƃ���ɏ]����k�i��q�j�Ƃ̎t�푊�A��O�ɖ����Z���i�t�j�Ƃ���ɏ]����k�i��q�j�Ƃ̎t�푊�ł���B���̂����A���Ԗڂ̎t�푊�̉��V�ɂ����Ă͊ю呦���@�̉��V���̗p�����B
�@��̗�����X�����Ă݂悤�B
��q�h�߂̋��{���ΐ�Ñ��̏��̏Z���̌�ڂɂ����ďZ���̋`�Ɉ˂��ĕ��\���グ�����Q�炷�ׂ��Ȃ�A��t��t�͉ߋ����Ďc�鏊�͓��Z���v��Ȃ�̂Ȃ�A�Z���̌����܂ӏ����������҂̌����܂ӏ��Ȃ�i�x�v�P�[�U�R�j
�@�w���V���x��24���̕��ł���B�x�����̒����Ɋ�Â��ƁA�{���͖{�R�i��Ύ��j�̖�m����q�h�߂̋��{����莟�����ꍇ�A�܂��{���̏Z���i�ю�j�̎w�������ׂ����Ƃ������Ă���B�����āA���̗��R�́A��Ύ��̌��ю�i���Z���j���u���J�O�i���@�E�����E���ڂ̂��Ɓ��M�Ғ��j�̑�\�ɂ��āE���Z�́i�{�����j���鏊�͕����l�̌����ӏ��Ȃ�v�i�x�v1���P�S�U�j���炾�Ƃ����B
�@�{���ɂ݂���u�Z���̌����܂ӏ����������҂̌����܂ӏ��v�Ƃ̓��L�̎w��́A�ю呦���@�̋`�ɒʂ���Ƃ��낪����B�����A����͉��V�̈�ǖʂɂ�����w��ɂ������A�ю�M�I�ȈӖ��������Ɋ܂܂�Ă���̂ł͂Ȃ��B���ю傪��莟���̖�m����͂���ꂽ��q�h�߂̎{��������Ɂu���\���グ�����Q�炷�v�悤�Ɏw������A�Ƃ���Ă���̂́A���ю�����ƒ�q�h�߂̊Ԃɗ��掟�����ɑ��Ȃ�Ȃ����Ƃ������Ă���B���������ē����̉���̂��Ƃ��A�{���ɂ����錻�ю�́u���J�O�̑�\�v�u�{�掟�v�i�x�v1�[1�S�U�j�Ƃ��ĈӋ`�Â����A���̂����Ɋю呦���̋`�����Ă���̂ł���B��������A���ю�͓��@�ɑ����ĉ��V�ʂœ��@�̐U�����Ȃ��킯�ł���A�����ɓ��L�̐^�ӂ��������Ƃ݂�ׂ��ł���B
�M�Җ�k��藈���̎����Γ��Z���n�߂��ׂ��A����������x�Ԍ����v�莙�̎n�߂���Ȃ�A���͎̌̂O���̏������c�J�R�����Z���̏��ɂ��ʂ����鏊�Ȃ邪�̂ɁA���ɕ��@�̎u�����c�J�R���ڏ�l�̎��ӎp�Ȃ�i�x�v�P�[162�j
�@���x�́w���V���x��14���ł���B���̏�ڂɂ��Ắu����������x�Ԍ����v�莙�̎n�߂���Ȃ�v���ǂ��������ׂ���������A���������������߂̉\���������Ă���B�������A�u�O���̏������c�J�R�����Z���̏��ɂ��ʂ����鏊�Ȃ邪�̂ɁA���ɕ��@�̎u�����c�J�R���ڏ�l�̎��ӎp�Ȃ�v�Ƃ̓��L�̎w��ɑ�������̈ӌ��͊m�肵�Ă���A�u�{�R�̏Z���̓��E�i���������ɏy���j�͎O���������c�J�R�O�c�̗B��̑�\�҂Ȃ�E���c����Ɍ��Z���h�d�����ӂ��̂ɋ��{�̈�̎��Z�����n����͖ܘ_�̎��ɂāE���@�J�O�c��������ӎp�Ȃ�v�i�x�v�P�[�P�S�T�j�Ƃ������̂ł���B
�@��ɍl�@�����悤�ɁA���L�́w���V���x�ɂ����Ă����ʂ���r��̂ƂȂ�͉̂��핧�@�ւ́u�M�S�v�ł���B���̑O��ɗ��ĂA�O�������E���@�E�����E���ڂ̉��핧�@�ւ́u�M�S�v�������ʂ���r�Ƃ���̌���Ύ��ю�́u�O���������c�J�R�O�c�̗B��̑�\�ҁv�Ƃ��ĐM�Җ�k����̕��@�̎u�����ׂ����A�Ƃ����̂��{���̎�|�ł��낤�B�����ɂ��A���@�̑���Ɍ��ю傪���V�̏�œ��@�̐U�����Ȃ��A�Ƃ������L�̎v�z���Ŏ悳���B
�@���̂悤�ɁA���L�́w���V���x�ł́A���ю傪�O�������E���@�E�����E���ڂɑ����Ď�X�̉��V������s���ׂ����Ƃ����X�Ő���������Ă���B���L�́A�ю�㊯���Ɋ�Â��A�t�푊�̉��V�̈�ǖʂɂ����Ċю呦���@�̋`���U�������̂ł���B
�@���������w���V���x�ɂ́A���ю���q���̑㊯�r�Ƃ݂Ȃ��ׂ����Ƃm�ɒ�߂���ڂ�������B�w���V���x��61��������ł���A�u���Z�̑m�������̑m��������M�͎u�͓�������ׂ��̂ɁA�����̎��߂��镧�̌�㊯��\���Ȃ��牓�ߕΐ��L��ׂ��炸�v�i�x�v�P�[�U�X�j�Ƃ���B�����ɂ����u���̌�㊯�v�̂��Ƃ��A�����́u���̌�㊯�Ƃ͕ʂ��Ė{���̏�l�E�y���Ă͖�m�����]�ӁA�ʂ��Ė��h���̑m�������̑㊯�̋`�Ȃ�Ƃ��ւǂ��E�����̑F�ɂ��炸�v�i�x�v1�|118�j�Ɛ������Ă���B�������ɁA�u���Z�̑m�v�Ɓu�����̑m�v��ΐ��Ȃ����߂������Č���ׂ�����Ƃ́A�F����Ƃ���u�{���̏�l�v����Ύ��̊ю�ɑ��Ȃ�Ȃ��B��Ύ��̌��ю���u���̌�㊯�v�A���Ȃ킿�{���E���@�̑㗝�l�Ƃ���v�z�����L�ɂ��������Ƃ͖��炩�ɂ݂ĂƂ��B
�@������ю�㊯���܂��������ŁA���L�ɂ�����ю呦���@�̉��V�𑨂������Ƃ��A���ꂪ���ؑ����_�I�ȁq�ю偁���@�r���Ӗ����Ȃ����Ƃ͈�w���ĂɂȂ낤�B�����́A���L�́w���V���x�Ɋю呦���@�̋`��������Ă��邩��Ƃ����āA�������̎����Ř_���Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@
�@
�X�@��Ύ��̌����_�b�̌��^�\�\������苗��E�����̓o��
�@�����̓����嗬�ɂ����āA���ÓV��̎v�z�Ƃ̐ڐG���݂��邱�Ƃ͂��łɏq�ׂ��B�������Ȃ���A���̎����̑�Ύ��ю�͒N��l�Ƃ��Ē���V�䗬�̑�����`���������Ă��Ȃ��B9���E���L�Ȃǂ́A�V��Ƃ̓��`�@��̌��������ɑ��āh�M�S�̌����h�Ƃ������@�{���̌����ς𗧂āA�@�c�E���@�́u�M�S�v���p���������ю����@�ɂȂ��炦�ċ��c�����鉻�V���m�����Ă���B
�@�Ƃ��낪�A���L�̔ӔN���Ɉ�l�̑���̊w�m����Ύ��ɋA�����A���̂܂ɂ����ÓV�䗬�̑�����`���Ύ����w�̒��Ɏ������B���̊w�m�̖��͍�����苗��E�����Ƃ����B���X�����́A�����剺�̒��ł��V�䋳�w�̉e�����������Ƃ����ʖ��v��苗��E�����̖嗬�ɑ����Ă����B���s�̏Z�{���n�Ŗ{�R�i�Ƃ��ꂽ�o�_�̔n�ؑ�V�i���{���j�̏Z���߁A�{���@�����Ɩ����L�͑m�������Ƃ����B
�@���̓����̖��Œ����ꂽ���Ɂw�S�\�ӏ��x������B�����͓�������Ύ��ɋA������ȑO�̍�ƌ����A���e�͏K�w�҂̂��߂ɓ����̓����嗬�̖@����܂Ƃ߂����̂Ƃ݂���B���̒��œ����́A�S�\�ӏ��̂����̑唼���O�d���Ӗ@��ɂ��Ă̑䓖�̑���̂��߂ɔ�₵�Ă���B��������A�����������ɒ��ÓV��̌��`�@����d��ȃe�[�}�Ƃ��Ă������A�����������m�邱�Ƃ��ł��悤�B
�@�����Ƃ��A�w�S�\�ӏ��x�̎��̈�͓V��ƂƓ��@�剺�Ƃ̕��@�I�ȑ�����������ƂȂ̂ŁA���ÓV��̌��`�@��ɑ��Ă������̑ԓx�͔ᔻ�I�ł���B�Ⴆ�A�w�S�\�ӏ��x�̑�X���ɂ́u�y���ēV��ꗬ�̌��`���`�������₩���{��O�ʂ̘@�t�̌䏑��j����ɂ��v�i�x�v�Q�[�P�V�X�j�u�V��ꗬ�̌��`��M���Č䏑����ʂ��͖����L��ׂ����Ȃ�v�i�x�v�Q�[�P�W�O�j���Ƃ���B�����͂����ŁA�V��Ƃ̖{瑈�v�̌��`�@��������ē��@�́u�䏑�v�����߂���҂����邱�Ƃ�Q���A������������Ă���B�����́A�V��Ƃ̌��`�@��̓��e�Ɋւ��Ĕᔻ�I�ȗ�����Ƃ�B
�@�������ʁA���������������A����V�䂪�Ƃ���������`�Ƃ�����������̂ɂ��Ă͍m��I�ȑԓx�������Ă���B�w�S�\�ӏ��x�̑�10���ɂ����āA�����́u���嗬�ɑ吹�l�ȗ��͓������ȂāE�@��Ƃ���c�c�y�ʂ̒��ɕʂ��Ė@��v�����̓��t�ƂȂ�Ɛ\���`������A�B��^��̎����`�ɂ���v���Əq�ׁA���@����߂��Z�V�m�̒��ł��u�B��^��v�́u�@��v�͓�����l�ł��邱�Ƃ��������Ă���i�x�v�Q�[�P�W�Q�j�B�܂����̑�11���ł́A������u��ӑ����v�̑S�������p���Ă���i���O�j�B���Ȃ킿�V��Ƃ̌��`�����̂��Ƃ��A���嗬�ł����@���������l�ւ̌����������������Ƃ��A����䂦�ɓ����́u�@��v�Ƒ��̂����ׂ����Ƒi���Ă���B
�@�����ē����́A�w�S�\�ӏ��x�̑�148���ŁA
��Ƃɂ͋��t�̑c���E�����̑����Ƃē�̖@��L�邱�Ə�̔@���A���@�̋��t�������ɓ`����Ȃ�A�߉ނ̋������������ɂĕʕt��������s��F�Ȃ�A��������������͋����Ȃ�A���t�͎߉ނ��O�\�n�O�̕�F���g�F���F�ɂĐ���ʂӂȂ���t�Ȃ�A�������̖�������s�Ɏ�����s�Ēa�̓��@�����Ɏ����A����Γ������Ȃĉ���̒m���Ɛ\���Ȃ�i�x�v�Q�[�Q�S�T�j
�Ƃ��q�ׂĂ���B
�@�V��@�ł́A�w���d�~�ρx�̏��̋L�q����Ɂu���������v�Ɓu���t�����v�̓���𗧂Ă�B���������Ƃ́A�w�t�@�������`�x�Ɋ�Â��A�߉ނ���ޗt�A����ւƎ��悵�Ďt�q��u�Ɏ���܂ł�23�c�̎t�������̌n���𖾂炩�ɂ������̂ł���B�܂����t�����Ƃ́A���t�ł���V��q��k���Ēq��̎t�����x�d�v�A�d�v�̎t����k�Čd���������A����Ɍd�����Ō㑊���Ƃ��ċ��������̏\�O�c�E�����ɂȂ��邱�Ƃ��������̂ł���B�܂�A�����E���t�̗�������������āA�V��Ƃ��߉ނ̕��@�̐������p���@�ł��邱�Ƃ������킯�ł���B���̗������́w���C���`���x��w�����������x�̒��Ř_������ȂǁA���ÓV��ɂ����Ă��d�����ꂽ�B�������A�w���C���`���x�ł́A��ݗ�R�̋�����V��q�{�ւ̒����ɂ���č��t�̒m�����������Ă���B
�@��̓����́w�S�\�ӏ��x�̕��ɖ߂�ƁA�����́u���t�v�ł͂Ȃ��u���t�v�̑c����_���Ă���B����͂Ƃ������Ƃ��āA���ڂ����͓̂����̋����������ł���B�����́A���@�̖@�؏@��
�y�[�W�����i58-59�j
���������������B
�i�P�j�u��ӑ����v�ɂ����������̎咣
�@��ӑ����Ɋւ��ẮA�ΎR�A���ȑO�̓����̍�ƌ�����w�S�\�ӏ��x�ɂ����āA���łɂ��̑S�������p����Ă���i�x�v�Q�[�P�W�Q�j�B���R�A�A����̓�������ӑ����̌��Ђ��g���Ă������B�����́A�w�s�쏴�x�̒��Łu���@���l�\�N�̖@����Γ�����t���̒i�͂₪�ď\���\����p�ߔN�̌�����Ȃ莄�@�t�����̎�����������m�炴��Ȃ�v�i�x�v�Q�[�Q�V�R�j�Əq�ׂĂ���B�܂��w���ڊˏW���x�i�x�v�Q�[�R�P�S�j�Ɓw�Z�l���`�j�������L�x�i�x�v�S�[�S�S�j�ł͓�ӑ����̑S�������p�E�Љ�A�u���l�Ȃ��T��]���ɗL��ΑF��������A�R��ɗ]���ɂ͂Ȃ���v�i�x�v�S�[�S�S�j���ƋL���Ȃ���A���������@�̐�������䂦����ӑ����̑��݂ɋ��߂Ă���B
�@��Ύ��嗬�j�ɂ����ē�ӑ����̑��݂ɍŏ��ɐG�ꂽ�����́A�N��2�i1380�j�N�A���@������̍�Ƃ����w�ܐl���j�������x�ł���B�������A���łɏq�ׂ��悤�Ɂw�ܐl���j�������x������Ɗm�肷�邱�Ƃ͕����w�I�ɂł��Ȃ��B�������������́A��ӑ����ɂ��āu���@���l�V��t���O���ܔN�㌎�\����A���\���\�O���̌���ł̎��̌䔻�`������v�i�x�v�S�[�W�j�Ǝ����I�ɋL���ɂƂǂ܂��Ă���B
�@���������āA���@��������ւ̓�ӑ������X�I�Ɏ��グ�A���̑S�������p���Ȃ��猠�ЂÂ��������́A��Ύ��嗬�ł͒���2�i1488
�j�N�̍��������w���ڊˏW���x�i�x�v�Q-�R�P�S�j�������Ě���Ƃ���B��ӑ����̌��Ђ�O�ʂɗ��Ăē����������咣���铮���́A�������A������O�̐Ζ嗬�ɂ͂Ȃ������B��ӑ����̓��e���Q�l�ɂ���ƁA�������g���R�v�����̕ʓ����������Ԃ�6�N�]�̌v�Z�ɂȂ�B�������ŌÂ̎O�t�`�Ƃ����w��`�y��x�́A�u������l�͑吹��J���̌�g���R�ɂčO�@���������A�����֓��̂���������Ȃ��ĎO���N���Ԑg���R�Ɍ�Z����v�i��S�P�[�Q�U�V�j�Ƃ��Ă���B�����ɂ����u�O���N�v���A�����������ɐ\��𑗂����O��8�i1285�j�N����3�N�Ԃ̐g���ݏZ�Ɖ�����������邪�A�����ɒ����ȉ��߂Ƃ͌����Ȃ��B���������w��`�y��x�̍�҂͓�ӑ����ɉ�����y���Ă��Ȃ��̂�����A���̑��݂�m��Ȃ������\���̕��������̂ł���B����Ɏ��オ������9���E���L�̌������݂Ă��A��ӑ����̌��Ђ���X�ɏ������`�Ղ݂͂��Ȃ��B
�@��ӑ����ɂ����������̌����́A��Ύ��嗬�ɂ����Ă͕�����Ȃ����������Ɏn�܂��Ă���B�����ȍ~�̑�Ύ��̗��ю�́A�����̏����������ʂ����葊�`�����肵�āA���̎v�z���瑽��ȉe�������B���̂䂦���A�u��ӑ��������邩����@�̐�������p�҂͓�����l�ł���v�Ƃ������������`�I�Ȏv�l���A����ɑ�Ύ��@��̐V���ȓ`���Ƃ��Ē蒅���Ă����̂ł���B
�@
�i�Q�j���@�t���𒆊j�ɒu��������
�@���ɁA�����́A���@�̕��@����Ύ��̗��Z���ɂ���ĘA�Ȃƕt������Ă��邱�Ƃ���X�ɋ������A��Ύ��嗬���ɍL�߂��B9���E���L�́A���@�ȗ��́u�M�S�v����Ύ��̗��Z���Ɍp������Ă���Ɛ��������A���̕��@�t���ɂ��Ă͗��ʂɉB���������������B���L�ȑO�̑�Ύ��̗��ю���A�M�p�ł���j���̒��ł́A����̕��@�t�����g���邪���Ƃ��������c���Ă��Ȃ��B���ɂ́w��`�y��x�̂悤�Ɏߑ������s���@�ւ̖{��t�����q�ׂ����������邪�i��S�P�[�Q�V�P�j�A��Ύ��̊ю�Ԃ̕��@�t���ɂ͌��y���Ă��Ȃ��B���@�̏O���͂��ׂĖ}�v�ł���A�ю�Ƃė�O�ł͂Ȃ��\�\���������l�����ɗ��ĂA�ΎR�̗��ю�ɂ����M�����̕��@�t����W�Ԃ��邱�Ƃ͓���Ȃ낤�B
�@�Ƃ��낪���������̏������ł́A��Ύ����ɂ�镧�@�t���̌n�����֎����錾�������鏊�Ɍ��o�����B�w�s�쏴�x�ɂ́A�u�ߑ����ȗ��̗B���l�̌�t���������ꂸ�C�s�L�鐹�l��M��鏊�̐M�S���A���Ύt�h���Ɏ��̍s�������ׂ��A���Ă������ƂȂ�v�i�x�v�Q�[�Q�U�Q�j�u���̖�Ƃɂ͓��@���l���ȗ��̕��@������@�̖@���^�ЂȂ��Ȃ�v�i�x�v�Q�[�Q�V�S�j�u���̌�{���͜z�������c���l���ȗ��t�@�̊ю�̂��������܂ӎ��^�̌�{�����O�ɋ���ӂɔC���ď�������v�i�x�v�Q�[�Q�W�R�j�Ƃ������L�q���݂���B��������A��Ύ��������ߑ��[���@�ȗ��̕��@��t�����Ă������������̖�Ƃł���|��邵�����ł���B
�@�܂��w���ڊˏW���x�ł��u���@���l����ŗL��Ƃ��⏈���ށA���̎������̎����ɕ��@�������ē���̖@��̏��ɖ{���̗̑L��ׂ��Ȃ�v�i�x�v�Q�[�R�O�X�j�Əq�ׂ��A���@�̖Ō�́u���̎������̎����ɕ��@�����v���đ�Ύ��́u����̖@��v�̏��ɖ{���̑̂�����A�Ƃ̌�����������Ă���B
�@���L�̌��������͐M�S�p�����j�Ƃ��邪�A�����ɂƂ��Ă̌����͑��ɕ��@�t�����w�����t�ł������B�u���c���l���ȗ��t�@�̊ю�v�i�w�s�쏴�x�A�x�v�Q�[�Q�W�R�j�u�������ꂴ��t���X��l�v�i�w�Z�l���`�j�������L�x�A�x�v�S�[�Q�X�j�u�t�@�������炴��͕��@�ɂĂ͗L��ׂ��炴���v�i�w�l�M�ܕi�������x�A�x�v�S�|�T�Q�j�Ƃ����������̌����̐��X���݂Ă��A�ނ����@�t���i�t�@�j�������Č����Ə̂��Ă������Ƃ����炩�ł���B
�@���X�����̏o���ł�������嗬�ł́A���̌��n�̎����茌���t�@�d�����悤�ł���B�����́A�N�i3�i1344�j�N�A����ɖ{���E��e�̏���i���{�E�v�@�����j��^���Ă��邪�A�����Ɂu�E�t��Ƃ��Ď��^���鏊���̔@���v�i�x�v�W�[�P�O�P�j�Ƃ̈ꕶ��Y���Ă���B�܂�����̋L�^�ɂ��A�����́u�t���l�v�̖{�����ʂ���Ɏw�������Ƃ�������B�����́A���听���̓�������ю�̕t�@���d������Ă������Ƃ���������j���Ƃ����A����o�g�̓������t�@�n�����莋�������R�������Ă���B
�@���@�́A���`�@��̎�����֎����铖���̒��ÓV��̌��������ɑ��A�u�M�S�̌����v�̏d�v�����q�����ɐ����������B�������A�܂��嗬���̑�Ύ��Z���������A�@�c�́u�M�S�v�̒����Ȍp���ɍł��ӂ𒍂��ł���B9���E���L�̑�ɂ́u�M�Ɖ]�Ќ����Ɖ]�Ж@���Ɖ]�ӎ��͓������Ȃ�v�u���c�ߗ��̐M�S����ւ��鎞�͉�ꓙ���F�S���@�@�،o�̐F�S�Ȃ�v�i�x�v�P�[�U�S�j�Ƃ����h�M�S�̌����h�ς��A���߂Đ��������Ɏ������B����́A���炪�t���̓����҂ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�ނ����s�t���̖��@���������M��A�Ƃ�������̕\���ł��������ƌ����悤�B�������������́A���̑�Ύ��嗬���ɁA�ю傪��̓I�ɕ��@�����t�����Ă����Ƃ��������ς��L�߂悤�Ƃ��A��q�̂悤�ȗl�X�Ȑ��������c�����B����ɂ���đ�Ύ��{���́h�M�S�̌����h�ς͕ώ����A�₪�ē������̌����t�@�ςɎ���đ�����̂ł���B
�@�܂��A��������w�������Ƃ����12���E�����́A��i6�i1528�j�N�ɒu����F�߁A���̒��Łu��Ύ��y�O�h�߁v�ɑ��A�u�lj��a�v�i���13���E���@�j�����l�����łɂ́u�����̐��ԕ��@���Ɍ�n���v����悤�ɁA�Ə����c�����i�w�t���x�m���{�E��Ύ����n�A��S�P�[�S�S�R�j�B���̎j���́A�ӔN�̓������������̌����t�@�ς������Ă������Ƃ�m��ɏ[���ł���B�܂��������瑊������13���E���@���A�v�@�����C�ɑ��A�u�t���������v�ɂ���āu�O�ӂ̔�@�v����Ύ��ɂ���|���q�ׂĂ���̂Łi�w�v�@�����C���x�A��S�P�[�S�T�P�j�A��͂蕧�@�t���𒆊j�ɒu�������ς�L���Ă����ƍl������B
�@���ɁA��Ύ����v�@���ƒʗp���n�߂鎞��ɓ���ƁA14���E���傪���������ɂ�镧�@�t����O�ʂɑł��o���n�߂�B����͗v�@�����痈�������Ɂw�䑊������x�i���{�E��Ύ����j��n�������A���̒��Łu�������ړ������X�t�@�̈�Ղ̎��A���@���̋��������̈ꎚ���c�����t�����d���v�i��S�P�[�S�U�R�j���Ə����c���ȂǁA�ӎ��I�ɋ������X���������̗�����������Ă���B�v�@���m�ɑ��鏉�߂Ă̑����䂦�Ɏ�X�̔w�i����l�����邪�A���̎��_�ő�Ύ��嗬�͌����Ɂu�����t�@�v�̊Ŕ��f����悤�ɂȂ����ƌ����Ă悢�B
�@�����č]�ˎ���̏����ɂ�17���E�������o�����A���Ɍ����t�@�j�ςɊ�Â���Ύ��̗��ю�`�i�w�x�m��ƒ������x�j��҂ނ܂łɂȂ�B���������q�����w�ƒ����x3���́A2�ӑ����������ē����������������Ƃ���n�܂�A�u�A�����ڂ͍��c�̎��ҁA���t�̒��q�Ȃ�Ζ{���̑厖�A���Ɏ��ӌ��������`�����Ӂv�i�x�v�T�[�P�V�R�j�u�㗌�̍��ɂ͖@������ɕt���v�i�x�v�T�[�Q�P�U�j�u���ڗ��t�ɏ]���Č������h�����铙����s�ɓ`�����v�i�x�v�T�[�Q�T�O�j�u����������ɑ��`����Ȃ�v�i�x�v�T�[�Q�T�P�j���X�ƁA��Ύ��̕��@�����̎���������D������Ȃ����L���Ă���B���́w�ƒ����x�ȊO�A��Ύ��嗬�͌n���������@�j�̋L�^�������Ȃ��B����ē����́w�ƒ����x�͑�Ύ��̗��ю�`�̊�b�j���ƂȂ�A���̌����t�@�j�ς���X�܂ň����p����Ă������B
�@���������o�܂ɂ��A�����������������q���@�t���𒆊j�ɒu�������ρr�͓��L�ȑO�̑�Ύ��嗬�ɂ������q�M�S�p�����j�S�Ƃ��錌���ρr�����S�ɗ��킵�Ă��܂����B����̓��@���@���ւ�Ƃ���700�N�́u�����t�@�v�̓`���́A���͍��������̌��������Ƃ���̂ł���B
�@
�i�R�j�u�B���l�v�u�B����l�v�̗p��̕��y
�@��Ύ��̌��������́u�B���l�v�u�B����l�v�łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��\�\�����͏�����̒��ŁA���̈�_���J��Ԃ��������B�w�i�ɂ́A�V��@�̑����_�ւ̑R�S��A�������g������̑��`���𑊏��������ƂȂǂ��������Ǝv����B����������15���I�A����V��b�S���̌��`�@��͗��������}���Ă����B�����̌b�S���Ƒ�Ύ��嗬�Ƃ̎v�z�I���ɂ��āA�Ⴆ�w���C���`���x�́u������l�̊O�ɍX�Ɍ��O�Ȃ������[��̌��`�Ȃ�v�Ƃ������ނ̕�������Ύ��ł́u�B����l�v���ɂȂ����A�ȂǂƐ��f����҂�����B���̓_�͂����ƏڍׂɌ��������K�v�����邪�A���ɂ��������������������Ƃ���A�����͏d�v�Ȗ�����S�����ƍl�����悤�B���Ȃ݂ɁA�����́w�s�쏴�x��w�l�M�ܕi�������x�̒��Ōb�S���̋`�ɐG��Ă���B
�@�ł́A���������Ă��u�B���l�v�u�B����l�v�̐��Ƃ͂����Ȃ���̂��B���ɁA�ނ́w�@�،o�x栚g�i�Ɂu�B���l�@�\�~��v�Ƃ��邱�Ƃɒ��ڂ���B�w���ڊˏW���x�ł́A����栚g�i�̕���`���ɋL�ڂ��i�x�v�Q�[�R�O4�A��16�u�B���l�̎��v�̒��Ŏߑ����B���l�̋~�ώ҂ł��邱�Ƃ�������u�吹�l�������@�̗B���l�Ȃ�v�i�x�v�Q�[�R�S�Q�j�ƌ��_���Ă���B�������āu�ݐ��Ō㋤�ɓ��t�͗B���l�Ȃ�v�i�w�s�쏴�x�A�x�v�Q�[�Q�T�O�j�u�B���l�̓��t�ɂčݐ��Ō㐳�����̍O�o�Ȃ�l�̌��Ɍ����ĘZ�l���ɈȂĖ@��ɂĂ͗L��ׂ��炴��Ȃ�v�i���O�A�x�v�Q�[�Q�V�R�j�Ƃ������u�B���l�v�̑����ς��������̂ł���B
�@���ɁA�w�@�،o�x�̋����̋V���ɂ�����ߑ������s�ւ̕ʕt�����u�B���l�v�ł���A�Ƃ����_�ɂ������͒��ڂ����B�w�s�쏴�x�Ɂu�ߑ��̗B���l�̌䓱�t�Ƃ��Ė��ʕt���͗B���l�Ȃ�A�O���s�ނɗB���l�B���l�Ǝ���A�����ď��֕���ڂ��ȂāE�@�E�ꔫ�̎�q����̉���̖@�ԂƐ\���Ȃ�v�i�x�v�Q�[�Q�T�V�j�Ƃ����L�q������B�ߑ�����s�ւ̕ʕt�����u�B���l�v�Ȃ̂�����A��s�̍Ēa������@�̋��c���u�B���l�B���l�Ǝ���A�����āv���@�𑊏����Ă����ׂ����A�Ɠ����͍l�����悤�ł���B���̂��Ƃ́A�����Ɂu�ߑ����ȗ��̗B���l�̌�t���������ꂸ�C�s�L�鐹�l��M��鏊�̐M�S���A���Ύt�h���Ɏ��̍s�������ׂ��A���Ă������ƂȂ�v�i�x�v�Q�[�Q�U�Q�j�u���t�͐s�����ۂɌ�o���L����B���l�Ȃ�ׂ��v�i�x�v�Q�[�Q�V�P�j�Əq�ׂ��Ă��邱�Ƃ������m����悤�B
�@��O�ɁA�����͋��c�̓����Ƃ����ϓ_����A�����������u�B����l�v�ł���ׂ����Ƃ������i�����B�w�s�쏴�x�ł́u���l��嗬�ɂ͕t�@�̖@��͓�l�L��ׂ��炴��Ȃ�v�i�x�v�Q�[�Q�W�U�j�ƒf���A�w�l�M�ܕi�������x�ɂ́u�v�ꑊ���Ƃ͗B����l�Ɖ]�Ӗ��l�ɋ��ւĂ͕��@���y�_���čאl�e�l���ɔƉ߂̌̂ɑ��̕��@������v�i�x�v�S�[�S�X�j�Ɛ����A�w�Z�l���`�j�������L�x�ɂȂ�Ɓu���o�Ƃɓ�l�̕⏈�L��Α��ƕK���S���Đ��ɓ������ɓ�喳���v�i�x�v�S�[�S�S�j�Ƌ����@���Ă���B�v����ɁA���c���ɓ�l�̕t�@�̖@�傪����Ε]�_���N���ĕ��@���ق�ԁA�����瑊���͕K���B����l�łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����̂������̎咣�ł������B�����͑���̏o�g�ł���B�u�x�m��Ղ͕t���l���ʂ����ׂ��̗R�A������l�̌���]�X�A���͖̂@�����܂��Ȃč����𗧂邪�ז�v�Ƃ��������̋������A�ނ́u�B����l�v�v�z�ɉe����^�����\�������낤�B
�@��l�ɁA�������ΎR�A���O�Ɏt�̓��s���瑊�������w�{�������x�w�S�Z�ӏ��x�w�Y���������x���̑��`���̏��X�Ɂu�B����l�v�̕t�킽��ׂ��Ƃ̎咣���݂���B���炭�͂��̂����肪�A�����́u�B����l�v���̍ő�̘_���ł͂Ȃ��낤���B�����́w���ڊˏW���x�ɂ́w�Y���������x�̑S�������p����Ă��邪�i�x�v�Q�[�W�P�T�`�R�P�U�j�A���̖����́u���̑����͓��@���X��l�����E�B����l��`�Ȃ�_���_���Ɖ]�ЏI���ė��ߕL��ʁv�i�x�v�Q�|�R�P�U�j�ł���B�܂������̏����쒆�Ɉ��p����Ă��Ȃ����̂́A�w�{�������x�̌�����ɂ́u���̌������ɖ{���̑厖�͓��@��������`�@�̏������������h���B����l�̌����Ȃ�A���\�֑��\�֔邷���邷���`�Ӊ��B�@�ؖ{��@���������L��ʁv�i�x�v�P�P�W�j�ƁA����Ɂw�S�Z�ӏ��x�̌�����ɂ��u�������v�t���͈�l�Ȃ�A���@���J���������Ȃđy�ю�ƈׂē��@�����`�����ȂĖѓ������V����c�������t�������ߕL��ʁA���߉����ɖ��퓙�٘_�����s�����ۂɎ���܂ŗ\�������̔@�����������t�@�̏�l���Ȃđy�ю�Ƌ����҂Ȃ�v�i�x�v�P�|�Q�O�j�u�E���̌��v�{瑏���͗B����l�̌����Ȃ�v�i�x�v�P�[�Q�S�j�Ƃ���B������������������s�̓����[����n���̖嗬�ɂ����č��ꂽ���̂��Ƃ���A�������o���Ƃ��A�Ȃ����w�{�������x�w�S�Z�ӏ��x�𑊓`���ꂽ�������u�B����l�v�Ƃ����p����d������̂����R�ł���B
�@�������ē����́A��Ύ��嗬���Łu�B���l�v�u�B����l�v�Ƃ����p��y�����Ă������B��ɐG�ꂽ���A�����̑�Ύ��嗬�ł���l�̒���̑I�o�͍s��ꂽ�Ƃ݂���B�������Ȃ���A���̒���I�o���u�B���l�v�u�B����l�v�Ƃ����p��Ő_�鉻���A�ю��̎v�z�ɂȂ��Ă����悤�ȓ����͂Ȃ������B����ɑ��A�����́u�r��ɉ����ĉ��B�V�c�������ڂɗ]�l�����ėB����l�̌䑊�����t�����̑c������Ȃ�v�i�w���ڊˏW���x�A�x�v�Q�[�R�P�R�j�u�O�ӂ̔�@���B����l��v�i�w�l�M�ܕi�������x�A�x�v�S�[�T�Q�j�ȂǂƏq�ׂȂ���A�u�B����l�v�Ƃ����p����Ύ����̊ԂŒ蒅�����A���ʓI�Ɋю��Ύ�`�̌`���𑣂��Ă������̂ł���B
�i�S�j�u�@��v�̌�̑�Ύ��Z���ւ̓K�p
�@�u�@��v�̌�́w��ɘ_�x�ɂ݂��A�^���̎�A���̂��Ƃ��Ӗ�����B�܂��w��{�ۖ��`�x�ł͖@�i�����j�ɒB�����l��@������l�A�w���όo�x�ł͈�̕����y���x�z����l�̂��Ƃ��u�@��v�ƌ����B�܂�Ƃ���A�@�����݂ɐ����u���v���u�@��v�Ə̂���B
�@�����̖嗬�ł́A�u�@��v�Ƃ������t���@�c�E���@�̑��̂Ƃ��ėp���邱�Ƃ��������B�O��2�i1279�j�N�́w��\��x�́A�����剺�̓��G�E���ٓ��̖��Ŗ��{�ɒ�o���ꂽ�i��ł��邪�A���̒��œ��@�̂��Ƃ��u�@�吹�l�v�Ə̂���Ƃ��낪��ӏ�����i�S�W�W�T�O�E��{�P�U�V�W�j�B���̉ӏ��́A���͓��@���g�̕M�ɂȂ�B���炭�͓��@�ݐ��̍��A�����̎��ӂɓ��@���u�@��v�Ƒ��̂���剺�������̂��낤�B���@�Ō�ɂȂ�ƁA�������g�A��������̒��œ��@���u�@�吹�l�v�ƌĂ�ł���i�w��ߋ���Ԏ��x�m���{�E���R�{�厛���n�A��S�P�|�P�X�V�j�B�܂������̒���q�̓�ʓ������A�w�{��S�ꏴ�x��w���ח������x�œ��@�̂��Ƃ��u�@�吹�l�v�Ə̂��Ă���B
�@�Ƃ͂����A�����̓����嗬�ɂ����ē��@���u�@��v�ƌĂԗ�͔��ɋH�ł������B�����̏����ނ���@����ɁA���@�ɑ��Ắu���l�v�u���v�u�@�ؐ��l�v�u�قƂ����₤�ɂ�i�����l�j�v�Ƃ��������̂�p���邱�Ƃ̕������������悤�ł���B
�@�v����ɁA�����嗬�ɂ����Ė@��̌�͂Ȃ��݂������A���܁A�@�c�̓��@�������ĂԂ��Ƃ��������Ƃ������x�ł���B���R�A�����̓��@���@�̂��Ƃ��A�嗬�̊ю�ɖ@��̑��̂����Čh�ӂ�\���銵��͂Ȃ������B�w���r�u����\�Z�Ӟ��x�ɂ��Ɠ����͖嗬�̒����u�ю�v�i��S�P�|�X�W�A�X�X�j�ƌĂсA�w�����՞��X���x�ł͖{�厛�����̎��̓��ڂ̗�����u����v�i��S�P�|�X6�j�ƒ�߂Ă���B
�@�����Ȍ�̏��̐ΎR�ю���݂Ă��A�ю��@��Ə̂�����͌�������Ȃ��B����ǂ��납�A���ڈȍ~�̊ю�ɂȂ�ƁA�@�c�E���@��@��ƌĂ���F���ł���B�ނ�́A�����ς���@�Ɂu���l�v�̑��̂����A�ю�Ƃ̍��ʉ����͂������B���ڂ́w������l���Վ��x�i���{�E��Ύ����A��S1�|�Q�P�R�j�̒��ŁA���@���u���l�v�A�������u��l�v�ƌĂѕ����Ă���B�l���E�����̍�Ƃ����w��`�y��x�������Ăѕ������s���A���ڂ����u��l�v�Ƃ���B�ܐ��E���s�����l�ł���A�w�\��x�i���w�ʖ{�A��S�P�[�Q�X�V�j�ł́A���@���u���l�v�A�����E���ځE�������u��l�v�ƌĂ�ŋ�ʂ���B�����A�Z���E�����̑i��Ăɂ́u���@��l�v�Ƃ̕\�����݂���B���A�����ɓ������g���u��Ύ��ʓ��v�i��S�P�[�R�O�R�j�Ǝ��̂��Ă���_���ڂ������B9���E���L�ɂ��ẮA���@�݂̂��u���c�v�u���l�v�Ɠ��̂��A�����ɂ́u�J�R�v�A��Ύ����ɑ��Ắu��l�v�u��X��l�v�u�{���̏�l�v�u�{���Z���v�Ƃ������Ăѕ������Ă���B
�@���̂悤�ɁA3�c�E���ڂ���9���E���L�܂ł̑�Ύ����͖@��̌��p�����A���������@�Ɠ����ȍ~�̊ю�Ƃ���ʂ���ӎ������������Ă����悤�ł���B
�@�����A�����ցu�@��v�̌���d�����A���܂�����Ύ��̗��ɂ�����g���K�p���悤�Ƃ���l�������ꂽ�B���������ł���B�����嗬�����`���Ƃ��Ē��d�����w�{�������x�̒��Ɂu�^�͉���̖@��Ȃ�v�i�x�v�P�[�T�j�Ƃ̕��������邪�A�����͏Z�{���n�̍��m������������u�@��v�̌���D��ŗp���Ă����B�w�S�\�ӏ��x���݂�ƁA���@�̂��Ƃ��u�@�吹�l�v�i�x�v�Q�[�S�T�j�Ƒ��̂������ŁA�u���嗬�ɑ吹�l�ȗ��͓������ȂāE�@��Ƃ���v�u���̊Ԕނ��ю�@��Ɖ]�ӎ�����v�u�y�ʂ̒��ɕʂ��Ė@��v�����̓��t�ƂȂ�Ɛ\���`������v�u�����@���l�A���N�~��ׂ̈ɘZ�l�̏����ށA�����@�喳������s�R�V�����A����ɂ��@��̏���ʂւ�䔻�L�邼��q�ʂׂ��v�Ə����A������l�����@����u�@��v�̈ʂ�����ꂽ���Ƃ�͐����Ă���i�x�v�Q�[�P�W�Q�j�B
�@���@��������ցu�@��v�̈ʂ����^���ꂽ�Ƃ���A���̓����i�����j�̐��́A�ނ���Ύ��ɋA������Ɏ���A����Ȃ�W�J�𐋂���B���Ȃ킿�����́A�u�@��v�̒n�ʂ����������Ύ��̗��Z�E�֘A�ȂƎp����Ă���A�Ƃ��咣����悤�ɂȂ����B��Ύ��������u�@��v�Ƃ݂Ȃ��A�����̌����̐��X���Љ�Ă������B
�@�w�s�쏴�x
�@�@�@���F�͓���̋���@�����O�͖{��̖{���͖����ƍ��̐M���A���鎞�A�߉ޔ@���̈��s�ʓ��̖��s���P�E���g�����̌����@�傪�@��̌���Ɏ��܂鎞�E�M�S���A����ƐM�����Ȃ�i�x�v�Q�[�Q�T�R�j
�@�A�@����͔@���Ɖ]�͂Ζ@�Ԃ̐M�҂͖@��ɒl�Е�鐥��Ȃ�i�x�v�Q�[�Q�U�P�j
�@�w���ڊˏW���x
�@�B�@���@���l����ŗL��Ƃ��⏈���ށA���̎������̎����ɕ��@�������ē���̖@��̏��ɖ{���̗̑L��ׂ��Ȃ�A���̖@��ɒl�Е��͐��l�̐�����ďo�������܂Ӂi�x�v�Q�[�R�O�X�j
�@�C�@���o�҂͖�����̖@��ɒl�Е�鎞�E�{���ɒl�ӂȂ�i�x�v�Q�[�R�Q�X�j
�@�ŏ��́w�s�쏴�x�̇@�́A�O��̕�������͓��@���w���āu����v�u�@���v�u�@��v�Ƃ���悤�ɂ��ǂ߂邪�A��̇A�B�C�Ƃ̐��������l����ƁA��͂���ю���܈ӂ����@��_�ł���\���������B�����́A���@�݂̂Ȃ炸��Ύ��̗��ю�����u�@��v�Ƒ��̂����B�������������́q�@�偁���@�y�ё�Ύ����r�ς́A��q����ނ̊ю�M�Ɩ��ڂȊւ�荇�������B�{���͕��̑��̂ł���u�@��v�̌ꂪ��Ύ����ɓK�p����邱�Ƃɂ��A��Ύ��̗��ю�͐����̎t����ɂƂǂ܂炸�A�u�{���̑́v�̏����҂Ƃ��Ė�k�̐M�̑ΏۂƂ��Ȃ�̂ł���B
�@��Ύ��̊ю���u�@��v�Ə̂��ĐM�Ώۂɂ���A�������������̐��́A�������ɑ�Ύ��@��ł����������Ƃ݂��A�ߐ��܂œ����̖@��_�ɏ]���@��l�͂��Ȃ������B����ɂ́A�����̋��w��ێ悵����������ю�M��r�������A26���E�����̋��w�I�e���͂��傫�������ƍl������B
�@�����������ȍ~�̏@��ł́A�����ȊO����̉e���ɂ���Ċю���u�@��v�Ə̂��铮�����������B����21�@�i1888�j�N12�����́w���句����G���x�ɁA����v�����̖������C���u��@��̖��`�v�Ƒ肷��ꕶ���Ă���B���̒��œ��C�́A���@�@��v�h�Ŋǒ��̖��̂�p�~���āu��@��v�Ə̂���|���_�c���ꂽ���Ƃ��Љ�A�u���@����ɂđ�@��ƂȂ�吹�l�ƂȂ蕧�����ƂȂ�Ƃ����莟�悽��ׂ���嫂��c�c�{�������ɕ��͒E�v�̋���^�͉���̖@��ƌ����@���k���ɂ͖@��͏@�c��l�Ɍ���R��������@����̒��ɉ��Ă��獟��������@�����{�h�ɉ��Ă���@�@��Ɖ]���������ꂠ��ׂ��A������̎������ւ��ɉ��Ă���v�Əq�ׂĂ���B��������m����̂́A����20�N��̏����̒i�K�ł͑�Ύ��̊ю�͂��납����h�̊ǒ��ɂ��u�@��v�̖��������邱�Ƃ��Ȃ������A�Ƃ������j�I�����ł���B
�@�Ƃ��낪�A����23�i1900�j�N9���A����h����̑�Ύ��̕����Ɨ����F����A�������u���@�@�x�y�h�v�ƌ��̂��鎞�z�ɂȂ�ƁA���̏ɕω����K���B���@�@�x�m�h�Ƃ��ēƗ���ɒ�߂�ꂽ�u�@�����@�v�i����33�N9��18���F�j���݂�ƁA���̑�6���Ɂu��㒄�X�������Č���56�k�@��Ɏ���v�Ƃ̕������D�荞�܂�Ă���B���̎��_�ŁA�@��l�͐����ɑ�Ύ��ю�̂��Ƃ��u�@��v�ƌĂюn�߂Ă���B
�@�Ȍ�A���̌ď̖@�͋}���ɏ@���ɒ蒅�����B�Ⴆ�A�@�������36�i1903�j�N7���ɔ��s�����G���w�@�̓��x�̊����ɁA�u�Z�����v�̈�������ɂƂ��Ȃ��u�\��L���v���f�ڂ���Ă���B�����ɂ́u���{�R26�k�@�������l���q�@���{�R56�k�@�������l�����v�Ƃ̋L�ڂ��݂���B�܂����N10�����s�́w�@�̓��x�ɂ́u�{�@�L���v�̗�������A�u�䒎����̊T���v���L����Ă��邪�A�����ł��u�@���l�v�Ƃ����\�������x���g���Ă���B���������̑�Ύ��嗬�́A���@�@�̓������ɉe������A���̊Ԃɂ�����̊ю���u�@���l�v�Ə̂���悤�ɂȂ����B
�@�������āA�ߑ�ȍ~�̏@��ł͑�Ύ��̊ю���u�@��v�ƌĂԂ��Ƃ����ቻ�����B���̉ߒ����̂́A���������́q�@�偁���@�y�ё�Ύ����r�ςƂ͖��W�ɐi�s�����̂�������Ȃ��B����ǂ��ߔN�A67�������̂��鈢���������n���w����u�j��v����Ƃ�����������N�����A�����@���@�͓����̖@��_��p���Ȃ���h��Ύ�������@�Ɠ��i�́u�@��v�Ƃ݂邱�Ƃ͏@��̓`���ł���h�ȂǂƏ����n�߂��B������́A���������ɓs���̂悢�ю�M����j�I�ɐ��������邽�߁A���˂ɓ����̖@��_�������o���Ă����B
�@�����ɂ����āA�����̖@��_���q�@��×��̓`���r�Ƃ���咣����Ύ����Ŕ��������킯�ł���B���A��Ύ��嗬�ɂ�����u�@��v�̈Ӗ������߂Ė₢�������ׂ������}���Ă���B���q�̂��Ƃ��A�����́q�ю偁�@��r���͑�Ύ��{���̓`���Ȃǂł͂Ȃ��B����́A���̊O���v�z�ɂ������A���ߐ��̏@��ł͔r�����ꂽ�B�Ƃ͌������̂́A���ł��@��×��̓`���ɉ�������v�z�Ƃ��āA�����́q�ю�\�@��r���͍��Ȃ��B�R����͂����������Ă���̂ł���B
�i�T�j�O���@�̐�g
�@���@�́w�@�؎�v���x�̒��Ŗ{��̖{���E���d�E��ڂ������A�w���x�ɂ��̋�̓I�ȓ��e
�𖾂����Ă���B�܂��A�w�`��[�䏑�x��w�O���@�h�����x�i�w�O���@���x�j�ł́u�O���@�v
�Ƃ����p����݂邱�Ƃ��ł���B
�@������ɁA��Ύ��̗��ю�̏������ׂĂ����ƁA9���E���L�̍��܂ł͒N��l�Ƃ��ĎO���@���Ӗ�����p����g���Ă��Ȃ����ƂɋC�Â������B�O�q�̂��Ƃ��A�����́A��̑�Ύ����w�Ō����Ƃ���̎O���@�`����@�́u���`�v�Ƃ݂Ă����߂����邪�A�O���@���T�O�����Ė嗬�̍��{���`�ƒ�߂��킯�ł͂Ȃ������B�����ȍ~�̑�Ύ��ю�����l�ł���B�����A��Ύ����ȊO�̘_�t�ɖڂ�������ƁA�O�ʓ����́w�{���������x�i�x�v�Q�[�V�Q�j�▭�@������́w�����k�x�i�x�v�Q�[�P�R�T�j�Ɂw�O���@���x����̈��p���݂���B���A�w�{���������x�͌��̏��Ƃ���������e�I�ɗ����ł��邵�A�w�����k�x�������N�オ�s���ł���B���ɗ�������������̐^��Ƃ���ɂ��Ă��A�嗬���̑�Ύ��ю�̎咣�ɂ͂Ȃ��T�n�v�z�̏q��ł���A���������������p���Ă���w�O���@���x�̕��u��ڂƂ͓�̈ӗL��v�i�S�W�P�O�Q�Q�E��{�P�W�U�S�j�́A�O���@�̈Ӌ`�ړI�Ɍ��g������̂ł͂Ȃ��B
�@�����������Ƃ���A��Ύ��嗬�ł͓��L�̑�܂ŁA�O���@���f���Ă�����@�|�̍��{�Ɉʒu�Â��铮���͂Ȃ������Ɛ��@�����B�ł́A�O���@���Ύ��̍��{���`�Ƃ��Ď��o�I�ɋK�肵���ŏ��̐l���͒N�Ȃ̂��B������́A����܂����������ł���B
�@�����͐ΎR�A���̌�A�u�{��O�ӂ̔�@��y��Ƃ��ď��䏑���Ƃ̐M�̖@��𐬗����ׂ��Ȃ�v�i�w�s�쏴�x�A�x�v�Q�[�Q�T�O�j�u���̎O�ӂ̔�@�͓��@�̓ƕ��Ȃ�v�i���O�A�x�v�Q�[�Q�T�V�j�u���̎O�ӂ̔�@�]���ɑ��m�����v�i�w���ڊˏW���x�A�x�v�Q�[�R�P�R�j�u�{��O�ӂ̔�@�͎��ʕi�̕���ɔ邵���ߋ��ւ�v�i���O�j���Əq�ׁA���傪�m��Ȃ����ʕi����́u�O�ӂ̔�@�v���u���@�v�̖@��́u�y��v�Ƃ��ׂ����Ƃ�Ɍې������B
�@�������u�{���ӂ̔�@�v����@�����̍����ƍl�������R�Ƃ��ẮA�܂��w�O���@���x��ǂ�ł������Ƃ��傫���Ǝv����B�ނ́w���ڊˏW���x�i�x�v�Q�[�R�P�Q�A�R�S�X�A�R�T�O�j�ŎO�x�A�w�l�M�ܕi�������x�i�x�v�S�P�R�V�A�T�R�A�U�T�j�ł��O�x�ɂ킽��w�O���@���x����������Ă���B�����ł́A�O���@�����@�̋��`�̐��v�ł���A���̖{��̉��d�𖢗��Ɍ������ׂ����Ƃ������i�����Ă���B
�@�܂��A���ďZ�{���n�̑m�����������ɁA���ÓV��́u���`�O�ӂ̑厖�v����@�̎O���@�ƌ��т��锭�z���������Ƃ����_���������Ȃ��B���`�O�ӂ̑厖�Ƃ́A���ÓV��ɂ�����u�L�`�l�ӂ̑厖�v�i��S�O�ρE�S���`�f�~�ϑ�|�E�@�ؐ[�`�j�̒��̑�l�́u�@�ؐ[�`�v���J�����u�~���O�g�v�u�����y�`�v�u�@�؈��ʁv�̓�̑厖�̂��Ƃł���B�����́w���ڊˏW���x�̒��ŁA���ÓV��̎O�ӂ̑厖�Ɠ��Ƃ̎O���@�Ƃ̍��قɂ��Ę_���A�u�E��Ƃɂ͉~���O�g�E�����y�E�@�؈��ʂ��O�ӑ厖�Ƃ��A���Ƃɂ͖{�勳��ߑ��E�{����d�E�얳���@�@�،o�̍L�闬�z����ׂ����̎O�ӂ̔�@�Ɛ\���Ȃ�v�i�x�v�Q�[�R�Q�O�j�Əq�ׂĂ���B���̂悤�ȁA���ÓV��̋��`�ƑΏƂ���`�ł̎O���@�̐�g�̎d���́A���i�h�̓������ɂ��݂��邪�A�����������ΎR�A���̑O�ɗl�X�ȏ��ŏC�w���d�˂邤���ɐg�ɕt�����̂ł��낤�B
�@�����̂��Ƃ��A�����͑�Ύ��ɉ��߂���O����O���@����@���w�̍����Ƃ݂闧����ł߁A�A����͂����x�m�嗬���ł��咣���Ă������̂ł���B
�@�Ȃ�A�������O���@���u���@�̓ƕ��v����Ύ��Ǝ��̔�@�Ƃ����䂦��͂ǂ��ɂ������̂��B���̖��Ɋւ��ẮA���@������ڂ֎O���@���u�B����l�v�ő������ꂽ�A�Ƃ���`��������������M���Ă������Ƃ�m��K�v�����낤�B�u�����@��v�ƌĂ��b������B�\�\���@�͒r��ł̓��łɍۂ��A���ڂ��Ă�ŎO���@��B����l�������A����ɂ��̔�@������̗ՏI���ɂ��̎����ł����₭�悤�ɖ������B������đA���N�́A���ڂ̎������������������\�\�B���ꂪ�����̐��������@��`���̑�ł���A�ނ͂��̘b���w�s�쏴�x�i�x�v�Q�[�Q�T�V�j�w���ڊˏW���x�i�x�v�Q�[�W�P�R�j�w�l�M�ܕi�������x�i�x�v�S�[�T�Q�j�̒��ŏЉ�Ă���B�������������߂������@��̓��e�Ƃ͑����̈Ⴂ�����邪�A���������b�ɂ��ẮA�ߑ�@��̖x�������u���ڏ�l�n�̏��R�����ڏ�l�d���邠�܂�̓`���ł���v�ƌ�����Ƃ����B�u���ڏ�l�n�̏��R�v�Ƃ͕ۓc���{�������w�����A�������ǂ����玨���@��̐������̂��͕s���Ƃ��邵���Ȃ��B�Ƃ������j���ォ�猾���A��Ύ��嗬���Ŏ����@��̓`�����ڂ����q�ׂ��ŏ��̐l�������������ł���B������ɁA���������ƎO���@���d�������Ȃ���������@��̐��ɂ͐S�䂩��A�u��ӂ̔�@���B����l�琥����N�̎����@��Ƃē��ڏ�l�̎��������ʂӂȂ�v�i�w�l�M�ܕi�������x�A�x�v�S�[�T�Q�j�Ƃ������咣�����������������̂��낤�B
�@�������O���@���Ύ��Ǝ��̔�`�Ƃ݂Ȃ������R���A�ʂ̊p�x������l���Ă݂悤�B�Z�{���n�̑m���������A���X�̋���̑��`���𑊏����������́A�����ɕx�m���d�̋`��������Ă��邱�Ƃ�m��A��Ύ����L�ɋA�˂�����A�x�m��k�ɂ����O���@�����R�Ɠ`�����Ă���A�Ƃ̊m�M�Ɏ������̂ł͂Ȃ��낤���B�w�S�Z�ӏ��x�ɂ́u����O�ʉ��d�����̖{瑁@�O�ӂ̔�@�����̏��n�͕x�m�R�{�厛�{���Ȃ�v�i�S�W�W�U�V�E��{�Ȃ��j�ƁA�܂���ӑ����̂����́w�g���������x�Ɂu���卟�̖@�𗧂Ă���Εx�m�R�ɖ{�厛�̉��d�����������ׂ��Ȃ�v�i�S�W�P�U�O�O�E��{�Q�P�W�S�j�ƁA����Ɂw�Y���������x�ɂ��u���@�͕x�m�R���R�̖����Ȃ�A�x�m�͌S���Ȃ�������Α���@�؎R�Ɖ]���Ȃ�v�i�S�W�W�V�X�E��{�Ȃ��j�Ƃ���A���ꂼ��O���@���́u�{��̉��d�v�̌����n�Ƃ��ĕx�m�R���w���Ȃ�����������Ă���B�Ƃ��Ɂw�S�Z�ӏ��x�́u����O�ʉ��d�����̖{瑁@�O�ӂ̔�@�����̏��n�͕x�m�R�{�厛�{���Ȃ�v�Ƃ̕��Ɋւ��ẮA�ΎR�A����̓������w���ڊˏW���x�i�x�v�Q�[�R�Q�R�j��w�Z�l���`�j�������L�x�i�x�v�S�[�S�R�j�ɍĎO���p���Ă���A�������������瑊���ȉe���������Ƃ����������m���B����䂦���A�����́w���ڊˏW���x�̒��Łu��R��y�Ɏ������ŏ��̒n�͓�腕�����̎R�E�x�B�x�m�S�̑���@�؎R�E��t���R�̖����L��R�̘[�E�V�����ɘZ���V�����L��ׂ��v�i�x�v�Q�[�R�T�O�j�Əq�ׂ�ȂǁA��Ύ��̖�ɓ����Ă���͔M�S�ȕx�m���d�̏����҂ƂȂ����̂ł���B
�@���āA�ȏ�̂悤�ȓ����ɂ��O���@�̐�g�́A��̑�Ύ��ю�̋��w�v�z�ɖ����ł��Ȃ��e����^�����ƌ�������B13���E���@�́A�ʗp�����������Ă����v�@���̓��C�ɑ��u�t���������A�O�ӂ̔�@�����c�Ďl���O���̍��𑊑҂҂Ȃ�v�w�v�@�����C���x�A��S�|�P�S�T�P�j�Ɠ����A����s�m�̎O���@���f���闧���\�����Ă���B�܂�14���E����͓��������𑽂����ʂ��A�����𗝋��V���T���瑊�`����Ă���B
�@�]�ˊ��ɓ���ƁA17���E�������̗v�@���o�g�̊ю傪�������������u���̈ٗ��`�̕��������ƂȂ�A��㋳�w�̕�����ڎw����Ύ��o�g�̊ю�炪���������̏����������ʂ��Ă����B�Ⴆ�A26���E�����́w�s�쏴�x��w���ڊˏW���x���甲�����Ă���B���̂悤�Ȓ��Łu���O���@�͉��҂���A�{��̖{���Ƃ͓������d�̔{���ɔ�A���̉��d�̖{���̍����n�͍L�z�̎��炴�閘�͍��̒n���d�ɔ�v�i22���E���r�w���x���@�x�A��S�R�[103�j�u���l�͎O����{���ƈׂ��v�i25���E���G�w���@�̓����x�A��S�R�[�S�O�S�j�Ƃ������咣������ɂȂ����悤�ɂȂ�A17���I���ɂ͎O���@���Ύ����w�̍����Ƃ��闧�ꂪ���������̂ł���B
�@��Ύ��Ɠ��̎O���@�ς́A���`�M���Ƃ��Ă͓�������ڂ̍����炠�����B�������Ȃ���O���@�̖@��������ē��@���w�̊j�S�Ƃ�����́A�퍑���オ�n�܂鍠�A���傩��ΎR�ɗ������������������n�߂����̂������B���ꂩ���200�N���o�āA���̓����̐��͑�Ύ��嗬���Ŋ��S�Ɏ嗬�����A�Ȍ�A�����܂ő����Ă���B
�@
�i�U�j���������ɂ��O���@�̓`��
�@���������͂܂��A�x�m��k�ɎO���@�̏d�v����F�������������łȂ��A���ꂪ���t�E�����̑����ɂ���đ�Ύ��́u�@��v�ɓ`�����Ă���Ƃ��������B
�@��ɂ��q�ׂ����A�����i�����j�́w�S�\�ӏ��x�̒��œV��̑����_�ɐG��Ȃ���A�����嗬�ɂ��u���t�v�u�����v�̑�������A�Ǝ咣���Ă����B��Ύ��A���̌�A���̓����̍l���́h���@������ڂ��t�E�����̑���������A����ɂ���ĎO���@���閧���ɓ`����ꂽ�h�Ƃ̌����ݏo���Ɏ����Ă���B�w���ڊˏW���x�Ɂu���̓�ӂ̔�@�]���ɑ��m�����������Ȃ�A�r��ɉ����ĉ��B�V�c�������ڂɗ]�l�������ėB����l�̌䑊�����t�����̑c������Ȃ�v�i�x�v�Q�[�R�P�R�j�Ƃ���̂������ł���B��̎����@��̓`����p���Ȃ���A���@���ՏI�̐܂ɓ��ڂ������Ă�ŎO���@�𑊏��������Ƃ��u�B����l�̌䑊�����t�����̑c���v�ɂ�����A�Ɠ����͎咣���Ă���B���Ȃ݂ɁA�w�S�\�ӏ��x�ł͓��@�[�����Ƃ��������n��������Ă���B
�@�����ɂ́A�V��Ƃ̋����E���t�̗�����������Ɏ�����悤�Ƃ���p���������݂���B�ނ́w�l�M�ܕi�������x�̒��ŁA��Ƃ́u�����c���v�u���t�c���v�u���w�ϊw�̌��������v���ɂ��Ē��X�Ɖ�����i�x�v�S�[�S�X�`�T�Q�j�A���̌�Ɂu���Ƃɂ͎��̐������ȂĐ��ӂƂ����v�u���Ƃ̕t���A�����t���A�������B��Ď��^����ʕt����A���O�l�̕t�@�̎�������ׂ��炴���{��t���Ȃ�Ζ�A�l��F�̏��͏�s��F���l�A�B�Ǝ������͑����\�M�̎��A��t���I���C�s�L��Ďn�S�M�S�̏��͖��@���l�O���@�̖�����t����v�i�x�v�S�[�T�Q�j���Əq�ׂāA���@�剺�̕t���������L����Ǝ��̈Ӌ`�������Ă���B
�@�v����ɁA�����́A�����̎߉ށ[��s�����@�[�����E���ڂƂȂ���O���@�̋��t�E�����̑����Ƃ����������Ƃ��Ă����悤�Ɏv����B���������v�z�́A�����I�ɂ́w�O���@���x���ł��L�͂ȍ����Ƃ����̂ł͂Ȃ��낤���B�Ƃ����̂��A�����ɂ́u���̎O���@�͓��]�N�̓����E�n�O��E�̏��Ƃ��ē��@�҂��ɋ����o�������������������Ȃ�A�����@�����s�͗�h�R���h���ɊH���v��̑���Ȃ��F���ւ�ʎ��ʕi�̎��̎O�厖�Ȃ�v�i�S�W�P�O�Q�R���{�P�W�U�T�j�Ƃ����ӏ�������A��������͓����̂��Ƃ����𗧂Ă邱�Ƃ��\������ł���B�����A�����́w���ڊˏW���x�̒��ʼnE�̕��̂قڑS�������p���Ă���i�x�v�Q�[�R�S�X�j�B���������́w�O���@���x�̕���m��A�Ȃ����d�����Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@�����āA�q���t�E�����̑����ɂ��O���@�̓`���r�Ƃ������������̌��������ς́A��Ύ��̗��ю�ɂ���Č㐢�Ɉ����p����Ă����B�������A�˂���O�̑�Ύ��@��ł́A�����鑊���ς�������ю��w�m�Ȃ�1�l�����Ȃ������B������ɁA�����Ȍ�ɂȂ�ƁA13���̓��@���u�t���������A�O�ӂ̔�@�����c����Ďl���O���̍��𑊑҂҂Ȃ�v�i�w�v�@�����C���x�A��S�P�[�S�T�P�j�Əq�ׁA��Ύ��嗬�Ǝ��́u�t���������v�ɂ��u�O�ӂ̔�@�v�̓`�����֎����n�߂�B
�@�܂���Ύ����v�@���ƌ𗬂��Ă��������ɂ́A���������t�����̊ϔO���\�ɏo�Ȃ��Ȃ�A���������̈Ӌ`��������������Ă������B������`�Ɋ�Â��@��j�ς��m������17���E�����ɂ��w�ƒ����x�́u�����`�v��ǂނƁA�u��㗌�̍��ɂ͖@������ɕt���������`����E�̑����A���ۖ����̑������Ȃ�A�y���ĔV�����͂Γ��p�O�p�����̒q���Ȃ�A�ʂ��ĔV��_���Ώ\��ӏ��̖@�傠��r�[�̌����Ȃ葴�̊�ɔ�Γ`�ւ��v�]�X�i�x�v�T�[�Q�P�U�j�Ƃ̋L�q���ڂɓ���B�����͂����ŁA�u�����̒q���v�����ڂ�������ɑ������ꂽ�Əq�ׂĂ��邪�A���t�����̖��ɂ͐G��Ă��Ȃ��B������݂邩����A�����͋��t�E�����̑����ł͂Ȃ��A���������݂̂������đ�Ύ��̌��������ƍl���Ă����悤�Ɏv����B
�@����ɗv�@���o�g�̊ю�̎��オ�I���A��Ύ��o�g��24���E���i���ю�ɏA��17���I�̖��ȍ~�ɂȂ�ƁA���m�ɋ��������݂̂��Ύ��̌��������Ƃ��錾���������B���i����Ύ��ю傾�������\12�i1699�j�N�A�o�^���@�i���26���E�����j�́u�ڎt����X���ɉ��āA���l������̑����Ɛ\���Ĉ��̐������Ɏʂ����@���O���@��t���Ȃ���đ�Ύ��ɂ̂ݎ~�܂��v�i�w���ʕi�k�`�x�A�x�v�P�O�[�P�R�P�j�Ɛ��@���Ă���B
�@���Ȃ݂ɁA�����́A��Ύ���26���Ƃ��ēo�����鐔�N�O�ɒ������w������L�x�̒��ł��u�����y�ј@�E���E�ړ��]�]�B����m�鏊�ɔ�Ȃ�v�i���i�W�Q�V�P�j�Əq�ׂĂ���B����́A���������ɗR������ΎR�̋����������Ɍ��y�������̂ł��낤�B
�@�����A�����̂悤�ȋ����������͂��łɏ@���Œ�������Ă����ɈႢ�Ȃ��B25���E���G���A�w�ϐS�{�����L�x�Ɂu���̋����������ܑ啔�O���̖{���̖��ӂɉ߂����v�i��S�R�[�R�U�X�j�ƋL���Ă���B
�@18���I�ȍ~�̑�Ύ��嗬�ɂ����āA�q���t�E�����̑����ɂ��O���@�̓`���r�Ƃ��������̑�Ύ������ς́A���t�����̊ϔO���������������Ƃ������A�قڂ��̂܂p���ꂽ�B�����ċߌ���̑�Ύ��@��ł́A���͂₻�ꂪ�����̏펯�ƂȂ�̂ł���B
�@
�i�V�j���`���w�̌���
�@������`�҂̡�����́A��Ύ��嗬�ɂ����đ��`���w�̊w�������グ���l���ł�����B���������̒��ł́A�����͋L����Ȃ����̂́A��ӑ������͂��߁w�{�������x�w�S�Z�ӏ��x�w�Y���������x�w��`���`�x���̋���̑��`�������X�ň��p����Ă���B���悤�ȑ��`���́A9���E���L�̒k���L�^���������ނ���L�ȑO�̑�Ύ��W�̏������Ɉ��p����Ă��Ȃ��B�����Ƃ��w�{�������x�Ɋւ��ẮA�]���A�ŌÂ̎ʖ{�Ƃ���6���E�����̂��̂�����Ƃ���Ă����B�������A���̎ʖ{�͓����̏���.�ԉ��⏑�ʔN�L�������A�����Ă��̕M�Ղ��{���ɓ����̂��̂��ǂ�����l�̗]�n������B�x�������u�ΎR�ɉ��Ă��Â�����̐�t���X�͍��̗�����]���ɂȂ���Ȃ������炵���v�ƌ���Ă���悤�ɁA�ߐ��ȍ~�A��Ύ����w�̊�ՂƂȂ����w�{�������x�w�S�Z�ӏ��x�̗������������A���ł͂��قǏd������Ȃ������Ƃ݂���B
�@���������p�������`���̑唼�́A�Z�{���n�̊w�m���������A�t�̓��s���瑊�����ꂽ���̂ł���B��Ύ��嗬�ɍs���Ă�����A�����͂����̑��`���̋L�q�������ɂ��Ĉ��p���A��g�ɓw�߂��B���̌��ʁA26���E�����̑�Ɏ����A��Ύ��ł͑��`���w�̉Ԃ��炭�B�������w�ɂ��Ă͗l�X�Ȋp�x����̈Ӌ`�Â����\�ł��邪�A��ӑ����A���������A�Y�������A��`���`���X�̋���̑��`���������������@�╶��V�䋳�w��p���Ȃ���̌n�������A�Ƃ����_�ł͑��`���w�ƌĂԂ̂��ł��ӂ��킵���B��������Ύ��̑��`���w���`�����邤���ŁA���������̋��w�͖����ł��Ȃ��e����^�����ƌ�������B�����͓����̑��݂�m��Ȃ��������A���̏����������w��ł���B���̂��Ƃ��A�����ɑ��`���d���̗�����Ƃ点���̌_�@�ɂȂ������̂Ɛ��@�����B
�@�u���������Ɠ������w�v���e�[�}�ɁA�ڍׂȌ������s�����Ƃ͖{�e�̔C���ł͂Ȃ��B���A�����ł́A�������w�ɂ����č��������̒��q���Q�l�ɂ����Ǝv����ӏ�����̓I�ɂ������w�E���Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B
�@���ɁA�����́w�O�d��`���x�̒��Łu��E���̈�O���v�𖾂����ɂ�����A�u�����[��̑��`�v�Ƃ��āw�{�������x����u���ʕi�E����̑厖�Ɖ]����@�@���A�����ĉ]���B���̐��@�Ȃ�邷���邷����㉞���̂������Ђ���������͗��̏�̖@���Ȃ�Έꕔ���ɗ��̈�O�O��瑂̏�̖{����ʂ��Ɠ��ӂ����ނ鎖��E�v�̕��̏�Ɛ\���Ȃ�A���̒�Ƃ͋v�������̖����̖��@��]�s�ɂ킽�������B�̐��ρE���s�̈�O�O��̓얳���@�@�،o���Ȃ�v�i�S�W�W�V�V�E��{�Ȃ��j�Ƃ̕��������Ă���i�x�v�R�[�T�O�j�B�����ɂ����ẮA�u�����̈�O�O��v�������i�ł��u��㉞���̂������Ђ���������͗��̏�̖@���Ȃ�Έꕔ���ɗ��̈�O�O��v�Ƃ����ӏ����d�˂Ĉ��p�����i�x�v�R�[�T�R�j�B���������p�����A���́w�{�������x�̕��́A���͍����������w�Z�l���`�j�������L�x���łƂɋ����������̂ł������B���Ȃ킿�����́A�����L�Łu���͐M�ɂ���܂��v�Əq�ׂA�������u���ʕi�̕���̑厖�Ɖ]�Ӕ�@�@���A���ĉ]���B���̐��@�Ȃ�邷�ׂ��邷�ׂ���㉞���́��v�i�x�v�S�[�R�U�j�Ɨ������Ă���B�܂��w���ڊˏW���x�ł́A�u�{��O�ӂ̔�@�͎��ʕi�̕���ɔ邵���ߋ��ւ�v�Ǝ咣������A��́w�{�������x�̕��̈ꕔ�u����Ƃ͋v�������̖����̖��@��]�s�ɘj���������B�̐��ώ��s�̈�O���̓얳���@�@�،o���Ȃ�v�������Ă���i�x�v�Q�|�R�P�R�j�B
�@���ɁA�w����钾���x�̐l�{����_���鏊�ŁA�����́A����p�g�Ɠ��@�Ƃ́u�s�ʑS���v�𖾂������߂Ɂw�S�Z�ӏ��x�̕����O�����Ă���B���̂����́u�����@���C�s�͋v�������̐U���ɊH���v����킴��Ȃ�v�i�S�W�W�U�R�E��{�Ȃ��j�Ƃ������́A�����������w���ڊˏW���x�̒��ň��p���Ă���i�x�v�Q�[�R�P�S�j�B�܂������͓����ӏ��ŁA�u�{�����̋���v�����@�ł��邱�Ƃ����邽�߂Ɂw�S�Z�ӏ��x�́u�䓙�����̎��ʕi�Ƃ͒E�v���ʂ̕���̖{�����̎��Ȃ�A���̋���͖^�Ȃ�v�i�S�W�W�U�R�E��{�Ȃ��j�Ƃ̕��������邪�i�x�v�R�[�W�O�j�A���̕����������w���ڊˏW���x�Ŏ��グ�Ă���i�x�v�Q�[�R�P�S�j�B
�@��O�ɁA�w����钾���x�̕x�m���d�_�ɂ����āA�����͏@�c�W�̑��`���Ƃ��āw�O���@���x�w���@����O�@���x�w�S�Z�ӏ��x�������Ă���B�����͂�������A���������̎�ɂ���đ�Ύ��嗬���ŏd�v�����m����悤�ɂȂ����������ł���B�Ƃ�킯�A�����œ��������p���Ă���w�S�Z�ӏ��x�́u�������������̙�䶗����ȂĖ{���̐��{���ƈׂ����Ȃ�v�i�S�W�W�U�X�E��{�Ȃ��j�Ƃ̌�����ɂ��Ắi�x�v�R�[�X�U�j�A�������w�Z�l���`�j�������L�x�i�x�v�S�[�S�R�j�̒��œ����ւ̕��@�t�����咣����ۂɋ����Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă��������B
�@��l�ɁA�w����钾���x�́u�{��̑�ڕҁv�́A�w�{�������x�́u���̒�Ƃ͋v�������̖����̖��@��]�s�ɂ킽�������B�̐��ρE���s�̈�O�O��̓얳���@�@�،o���Ȃ�v�i�S�W�W�V�V�E��{�Ȃ��j�Ƃ̕��Œ��߂������Ă���B�����́w�����s�����x�́u����сv�ł������̈ӂ��ŏ��Ɏ����A�u����Ƃ̍Ő[��@�c�����̈�厖�Ȃ�v�i�x�v�R�[�Q�P�Q�j�Ɛ����Ă���B��ɏq�ׂ��悤�ɁA���́w�{�������x�̕��́A���������́w���ڊˏW���x�i�x�v�Q�[�R�P�R�j�̒��Ŏ��グ���Ă���B�w���ڊˏW���x�̓��e����ҕs���́u��@�����v�Ƃ��������́A���̉{���⏑�ʂ�ʂ��A��������̂ق��d������Ɏ������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@��܂ɁA�����́w�����s�����x�̕��֕i���u�_�ɂ����āA���������́w���ڊˏW���x�̐����u��@�����ɉ]���v�Ƃ��Ď��グ�A�����̐����������镶�Ƃ��Ă���B
��ӌ�@�����ɉ]���݁X���X��瑖���̂Ă�Ə��Č͗\���ǂޏ���瑂ɔƂ͍��̎��ʕi�͐��l��瑖�Ȃ蕶��瑖�`�ݖ{�哙�]�]�B�Ⴕ�����ɋ��萳�Ɏ��ʕi���Ȃė\���ǂޏ���瑖�Ɩ����������֕i�Ɖ]����A���ӁA���̕��̗R���͋��M�V���ϐS�{�����̖����������̕��͂ɏA��瑖���u�܂����]�]�A�̂ɏ@�c�̈ӂ͒��Ɏ��ʕi���w���ė\���u�ޏ���瑂Ɩ���ɔ��Ȃ�A�̂ɒm�ʌ�@�����̈ӊ��Ɏ��ʕi���Ƃ�瑖�Ȃ���Ȃĕ��֕i�Ɏ��ʕi�Ɖ]�ӂȂ�A�Ⴙ�ΎY���L�̒���栚g�i�Ɏ��ʕi�Ɖ]�ӂ��@���A�ޕ��ɉ]���A���ʕi�ɉ]�������O�E�]�]�A���⎟���̕��ɉ]������瑖�`�ݖ{��]�]�����ӂȂ�i�x�v�R�[�P�W�T�j
�@�����ɂ���u�݁X���X��瑖���̂Ă�Ə��Č͗\���ǂޏ���瑂ɔƂ͍��̎��ʕi�͐��l��瑖�Ȃ蕶��瑖�`�ݖ{�哙�]�]�v�Ƃ́u��@�����v�̕��́A�w���ڊˏW���x�́u���ɉ]���A�݁X���X��瑖喳�����Ə����Č�͗\���ǂޏ���瑂ɂ͔V��ߎ���瑂�j���Č�Ȃ�]�]�A���̎��ʕi�͐��l��瑖�Ȃ�E����瑖�`�ݖ{��E瑖喳�v�{��L�v�]�]�v�i�x�v�Q�[�R�T�R�j�Ƃ��������̐�������������������̂ɑ��Ȃ�Ȃ��B�����́A�����̍�ł���w���ڊˏW���x����u���̎��ʕi�͐��l��瑖�Ȃ�E����瑖�`�ݖ{��v�Ƃ����ӏ����o���A�����ɂ�����u���̎��ʕi�v���h���ʕi���Ƃ̕��֕i�h�Ɖ��߂��邱�ƂŁA���֕i�����s�Ƃ��ē��u���闧��̐�������T���悤�Ƃ����̂ł���B�u����瑖�`�ݖ{��v�́A�w�S�Z�ӏ��x�̌�����ƍl������ӏ��ɂ݂���i�S�W�W�U�P�E��{�Ȃ��j�B
�@�����̂��Ƃ��A26���E�����́A�@�̘_�̗v�ł���O���@�`�̊e�_�̈�X�⋻��̏C�s�_�̈�呈�_�ƂȂ���֕i���u�_�ɂ����āA�������������������ꂽ���������̒��q�𑊓��ɎQ�l�ɂ��_�𗧂ĂĂ���B�����ɁA�h�������w�͋���Ǝ��̑��`�������{�����Ƃ��đg�D����Ă���h�ƕ]�����䂦�������B
�@�ނ��A�u�l�@�̈�v�̖@�哙�A�����������Ȃ����������Ǝ��̏d�v�@�������������B�������A��������������Ă��A�������̌n���������`���w�̌����̈������̑��`���𑽗p�������������̘_���ł��邱�Ƃ͑����Ȃ��B
�i�W�j�ю��l�̖{������
�@���������́A��Ύ��嗬�ɂ�����{�����ʂ�t�@�̊ю�݂̂̓����ƍl�����B�w���V���x�Ɂu�����ɉ��Ē�q�h�߂����l�͎���Ώ����ׂ��A�A�����`�͗L��ׂ��炸�{���Z���̏���Ɍ���ׂ��v�u�֒����͖����ɉ��Ē�q�h�߂����l�͔V�������ׂ����`���Έׂ��ׂ��炸�]�]�A�A���{���̏Z���͑��g�����̐M�S���̓����ɂ͔��`�𐬂���鎖������A��Ȃ�`�Ȃ�v�i�x�v�|�P�V�P�j�Ƃ��邲�Ƃ��A9���E���L�́A���m�̔��`����������֎~����Ƃ���������t���������ŁA�����Z�E�̎��R�Ȗ{�����ʂ�F�߂��B
�@�Ƃ��낪�A���L�̔ӔN�ɂ��̖剺�ƂȂ��������́A�q�����t���̎��R�Ȗ{�����ʁr��e�F�������L�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�h�{�����ʂ͑�Ύ��̊ю��l�Ɍ���h�Ƌ����咣�����̂ł���B�����͑�Ύ��ɋA������O�A���炭���s�E�Z�{���n�̑m�������B���̏Z�{�����J�������́w���t���^�x�̒��Łu�x�m��Ղ͕t���l�V�����ʂ����ׂ��R�A������l����v�ƋL���Ă���B���X�A���s�̑���ɂ́u�t���l���ʁv�̎v�z���������B���̎v�z��������p�������̂ƍl������B
�@�����́A�w�s�쏴�x�ɂ����āu���̌�{���͜z�������c���l���ȗ��t�@�̊ю�̂��������܂ӎ��^�̌�{�����O�ɋ���ӂɔC���ď�������v�i�x�v�Q�[�Q�W3�j�u�{�����ʂ̎��@��{�����ʂ̎��́E���l��嗬�ɂ͕t�@�̖@��͓�l�L��ׂ��炴��Ȃ�c�c�{�����ʕt�@�̓��t�͈�l�Ɍ�����ׂ��Ȃ�v�i�x�v�Q�|�Q�W�U�j���Əq�ׁA�{�����ʂ͕t�@�̑�Ύ��ю傾���ɋ�����Ă���A�Ɨ͂����߂đi�����B�����̑�����`�I�ȁq�ю��l�̖{�����ʁr�Ƃ����咣�́A�q�����t���̎��R�Ȗ{�����ʁr�����������L�́w���V���x�̏�ڂƐ^��������Η�����B
�@�����͑��傩��̉����m�ł���B�{�����猾���A��Ύ��嗬�͓��L�w���V���x�������q�����t���̎��R�Ȗ{�����ʁr�ς��p�����ׂ������ƌ����悤�B�����A12���E�����Ȍ�̑�Ύ��ю�́A�����̑�����`���瑽��ȉe�������B���̂��߁A�ߐ��̐Ζ�ł́q�ю��l�̖{�����ʁr�Ƃ��������̎v�z�̕����嗬������B
�@����������Ă݂����B17���E�����́A�w���Ɛr�[�V�����V���x�i�ʖ{�E��Ύ����j�Łu�{�����`�B����l�̑����̑�X��l�̊O���ʔV�����v�i��S�Q�[�R�P�S�j�ƋL���Ă���B�܂�A�h���Ƃ́u�B����l�̑����v�����ю��l�����{�������ʂł��Ȃ����܂�ɂȂ��Ă���h�Ƒi�����̂ł���B���̓����̌�������A17���I�̑�Ύ��@��ł́q�ю��l�̖{�����ʁr�Ƃ�������
�R���̎v�z���`�������Ă������Ƃ�c���ł���B
�@�܂��ߌ���̑�Ύ��@��ɂȂ�ƁA���悢��������̖{�����ʊς��×���т̓`���ł��邩�̂��Ƃ��݂Ȃ���Ă����B56���E�����́u�������X����������Ό����Ė{���̏��ʂ��Ȃ����Ɣ\�͂��v�Ƃ����咣�A�x�����i���59���E�����j�́u��䶗����ʂ̑匠�͗B����l���������̖@��ɍ݂�v�i�x�v�P�[�P�P�Q�j�Ƃ̌����݂Ă��킩��Ƃ���A��������吳�ɂ����Ă̑�Ύ��@��ł́q�ю��l�̖{�����ʁr�Ƃ��������R���̎v�z�����S�ɒ蒅�����B����ɂƂ��Ȃ��A���L�w���V���x����߂��q�����t���̎��R�Ȗ{�����ʁr�̋��́A�ނ������Ȏ���ɂ������O�I�[�u�Ƃ��ė�������A�����I�ɂ͎��������Ă��܂��B
�@�f���Ă������A�M�҂́q�����t���̎��R�Ȗ{�����ʁr��F�߂���L�̋K����`�I�Ȍ����Ɓq�ю��l�̖{�����ʁr��͐���������̑�����`�I�Ȏ咣�Ƃ̗������ɍڂ��A������ԈႢ�ň�����������A�ȂǂƘ_�f�������͂Ȃ��B�����A�����w�E�������̂́A��Ύ��嗬�ɂ�����{�����ʂ̉��V�K�����ϓI�ł���A�ߐ��ȍ~�͓����R���́q�ю��l�̖{�����ʁr�̎v�z���嗬�ɂȂ��č������}���Ă���A�Ƃ������ƂȂ̂ł���B
�@�Ȃ��A������́w���t���^�x�̋L�q���������Ƃ���ƁA�ŏ��Ɂq�ю��l�̖{�����ʁr�����������͍̂��������ł͂Ȃ��A��Ύ��J�R�̓����Ƃ������ƂɂȂ�B�����������̖Ō�A���L�̑�܂ł̑�Ύ���ނ��u�t���l���ʁv�̈�ɂ���������Ƃ����L�^�́A�ǂ���T���Ă���������Ȃ��B��Ύ��嗬�ɂ����Ċю��l�̖{�����ʂƂ����l�������ڗ����n�߂�̂́A���ۂɂ͍������������Ă���ł���B�܂��w���t���^�x�̂悤�ɓ`�����L�ڂ���̂ł͂Ȃ��A�ю��l�̖{�����ʂ�嗬�̝|�Ƃ��Ē��ɏ�������Ύ��W�̎j���́A�����́w�s�쏴�x�������ď����Ƃ���B�����l����ƁA����̏@��ɂ܂ň����p����Ă���q�ю��l�̖{�����ʁr�Ƃ����v�z�́A��͂荶�������ɗR������ƍl���Ă����ׂ����낤�B
�i�X�j�ю�M��
�@������������Ύ��嗬�̋��w�ɗ^�����ő�̉e���́A���ƌ����Ă��u�ю�i�@��j�M�v�����������Ƃł��낤�B�����̊ю�M�́A�ޓƓ��̖{���ςɊ�Â��Ă���B�w�s�쏴�x�̒��Ɂu���̌�{���͉�����\����▖�@�̓��t�̍�p��{���ƌ����Ȃ�v�i�x�v�Q�[�Q�W�S�j�Ƃ�������������B��������킩��悤�ɁA�����́u���@�̓��t�v������@�ɖ{���̎��̂����߁A��䶗��{���͂��́u��p�v�ł���Ƃ����B
�@���̓����̖{���ς͂���ɁA���@�ȗ��̕��@�t���̌n���ɘA�Ȃ��Ύ��̗��ю�����{���̎��̂Ƌ��l�����ݏo���Ă����B�����́A���������L���Ă���B
���F�͓���̋���@�����O�͖{��̖{���͖����ƍ��̐M���A���鎞�A�߉ޔ@���̈��s�ʓ��̖��s���P�E���g�����̌����@�傪�@��̌���Ɏ��܂鎞�E�M�S���A����ƐM�����Ȃ�A�ߑ������\���ł̖��ɑււĖ���̏O���𗘉v����ׂ��A���ʕi�̌��߂Ȃ�E���c���l����s���g���Ƃ�����C�s����A�M�S���A�̎���Ό㐶�P���Ȃ�Ό��������Ȃ�A腕����̌�{�����^���͗p�Ȃ�i�w�s�쏴�x�A�x�v�Q�[�Q�T�R�j
���@���l����ŗL��Ƃ��⏈���ށA���̎������̎����ɕ��@�������ē���̖@��̏��ɖ{���̗̑L��ׂ��Ȃ�A���̖@��ɒl�Е��͐��l�̐�����ďo�������܂ӌ̂ɁA���g�̐��l�ɒl���������Ďt�푊�̑�ڂ��ɏ��֕��M�S�ّ��Ȃ��q�֗��A���g���V���A��������̉䓙�����\��D�̕��ɒl�Е��ׂ��A����̐��l�̐M�S����̏��������g�̌�{���Ȃ�i�w���ڊˏW���x�A�x�v�Q�[�R�O�X�j
�@�����Ƃ��A���@�ȗ��̕��@��t�����ꂽ����̑�Ύ��ю�̐M�̏��Ɂu�{��̖{���v�u�{���̑́v������|������Ă���B�����āA�w�s�쏴�x�̕��Ɂu腕����̌�{�����^���͗p�Ȃ�v�Ƃ��邲�Ƃ��A���@���}�������A���邢�͗��ю傪���ʂ����A��䶗��{���́u�p�v�ƈʒu�Â�����B�v����ɁA�����̖{���ς́q���@�E���ю�̐M�̏����{���̑́A��䶗��{�����{���̗p�r�ł���B
�@�������ю�̐M�S�����������̂́A�����Ɏt�E���L�̉e�����Ă̂��Ƃł��낤�B�w���ڊˏW���x�Ɂu�ߗ������֎Q��M�̓������ĐM�S�ɐg�̖ї����āv�i�x�v�Q�[�R�O�T�j�Ƃ��邪�A�����͑�Ύ��ɗ��ĐM�S���{�̓��L���w�Əo��A�ȑO�̎���̍l������ҏȂ����悤�ł���B��Ύ��ю�̓��ʂɈ����̐M�S�Ɖʕ��̌��̗������݂�Ƃ����A����Ӗ��Ŗ������������̋����́A�ތ��X�̑�����`�ɓ��L�̐M�S��`������������߂ł͂Ȃ��낤���Ɛ��@�����B
�@�Ƃ���ŁA�M�̑���������ؑ����ցA�Ƃ����ϓ_�ɗ��ĂA���ю�̒�q�h�߂̐M�̏������l�Ɂu�{���̑́v�Ƃ��������ɂȂ낤�B�����������̋��w�ł́A�������E�ɂ�����u�{���̑́v�̍����I���݂��䶗��{���ɂł͂Ȃ�����ю�̓��ɋ��߂�B����䂦�A��q�h�߂��u�{���̑́v���ؓ�����ɂ́u����̖@��v�ɑ����A�˂̐M�i�ю�M�j���s���Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B
�@���������������ю咆�S�̓��ؑ����_�𗧂Ă��̂́A����ɂ͔N���̊ю��12���E��������邽�߂������Ƃ�������B���̐^�U�͂��Ă����Ƃ��Ă��A�ю咆�S�̓��ؑ����_�͓������t���������L�̐��ɂ݂͂��Ȃ��B�w�����E��x�ɁA
��A��l�ɉ]���A���̌o�V�l�M�S����ɂ��ė]���]�O�Ȃ��얳���@�@�،o�Ə�������ւΑ��̓��ʂɑ��g������s��F��Ɛ\���ؕ��V�L��A�_�͕i�ɉ]���A������s���Ɖ]�]�A�����ꓙ�̐ꐥ��i��S�P�[�S�Q�Q�j
��A���]���A���c���@���l�̌䏴�ɂ́A���@�͓��{���̈�؏O���̐e�Ȃ�ƗV���Č�����͐l�̏�ɂČ�B�A���̎t���݉ƂɂĂ�����A�o�ƂɂĂ�����A��E�����ɂĂ�����M�S����ɂ��č����@�@�Ԃ�\���i�ނ�l�T����t�e��A�\���\���S���ւ��i��S�P�[�S�Q�U�j
�@�Ƃ��邲�Ƃ��A�u�M�S����v�̐l�͍݉ƁE�o�Ƃ̕ʂȂ��N�ł��u��s��F�v�ł���u��t�e�v�O������̕��ł���A�Ƃ����̂����L�̍l���ł������B���L�́A�M�S�̏�Ŏt��̋ؖڂ��d���������A�ю咆�S�̓��ؑ����_�Ȃǂ͗��ĂĂ��Ȃ��B
�@���Ƃ������̂悤�Ȗ{���̗p���́A��ɑ�Ύ����w���m������26���E�����������l�@�̈�`�ɔ������v�z�ł���B����͑�Ύ��̐������w�ɂ͎�������Ă��Ȃ��B�������Ȃ��瑼���ł́A�ߐ��@��ɂ����ē������̓��ؑ����_�ɗ��r����ю�M���Ύ��̓`�����`�Ƃ݂Ȃ��X�����o�Ă������Ƃ��ے肵���Ȃ������ł���B
�@�����̌�A��Ύ��嗬���ōŏ��Ɋю�M���������̂́A�v�@���o�g�̖@�َ������ł������B17���L�����̘b�ɂȂ邪�A19���E���w�����G�Ȏ�����o�đ�Ύ��ɓ��R�����܁A�����̎R���m�������w�ю���y������A�Ƃ�����肪�������B�����ŁA�嗬�̗L�͑m�����������͑�Ύ��̒h���ɂ��Ăď����F�߁A���Ƃ����w��i�삵�悤�Ƃ����B48���E���ʂ́w���ƒ����x�ɂ��A�����͂��̏���Ɂu�ʂ��āA��Ύ����͋����̑����Ɛ\������āA���m��������N�l�͊w�s�w�ɂ�炸���g�̎߉ޓ��@�ƐM����M�̈�r���ȂĖ���̏O���ɕ����A�����ނ鎖�ɂČ����v�u����ʂ̑P�����Ȃ��A�������ȂĊю�ƒ�߂���A�̂��ȂĈ�R�F�ю�̍���܂��鎖�����M�̈ꎚ�̏C�s�ɂČ�v�u�߉ޓ��@��X��l�Ƒ����̖@���������ւΏ�㖖�㑴�m�g�̊�͑ւ�Ƃ��@���̑ւ鎖�������V�Ȃ���A�����̔@���M���鎞�͖��㖘�����@�����̔@���ɂď�Ɏ��h�����A���O��̌�Ќ����ɉ��ԕ���L�ߗ��z�͋^�ЂȂ����Ɍ�A���|�𑊒m����͔@���l�̑m�ю�ƂȂ�Ƃ������`�����͐��g�߉ޓ��@����ׂ����ƊJ�R�̌�{�ӈ��̗̊v�ɂČ����v�ƋL�����Ƃ����i�x�v�T�[�Q�V�P�j�B
�@��Ύ��̋������������ю�́A�w��̗L�����ʂ̑P�������ɂ�����炸�u���g�̎߉ޓ��@�v�ł���B�����M���ׂ��A�Ƃ����̂��J�R��������̖{�ӂł���A��Ύ��嗬�̐M�̗̊v�Ȃ̂ł���\�\�B�����͂��������āA�����̑�Ύ��m���̕s�����������������Ƃ����B�����̊ю�M�́A�ю�̐M�S�̏��Ɂu�{���̑́v��F�߂鍶�������̂���ɔ�ׂ�ƁA�Ƃ����L�������킹�ʌ��Ў�`���@�ɂ��B����ǂ����@�����Ƃ��Ắu�����v�������Ɋю呦���@�̋`��������_�ł́A���҂̊ю�M�͑S���ł���ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B
�@���ɁA18���I�����̑�Ύ��@��ł́A31���E�������O��_�ɑ������ю�M��W�J���Ă���B�����́A���7�i1757�j�N�́w�L�t���꒮�������Ձx�Łu���@�o�Ƃ̓��̑����@�m�O��Ȃ�v�u�m������{����Ύ��畧�E�̋��{�ƂȂ�`�Ȃ�ׂ��v�i�x�v�P�|�P�X�Q�j�Ɛ����Ă���B�����������u�m��v�Ƃ͑�Ύ��̗��ю�ł���A�������ю偁�m��̓��Ƃ���Ƃ���ɔނ̖{�ӂ��������ƍl������B�ƌ����̂��A���4�i1754�j�N10���A�����͋���̐M�ނɑ��u������l�����̑�X���������Ȃ�@���ɏ��鑥�����@�O�p�Ɉ˂�Α��m��Ȃ�@�̂ɖ��@����̑哱�t���@���l�̑����ɑi���j��A���O�p�𑶂��i�āj�m��ƈׂ�̂݁v���Ǝw�삵�Ă��邩��ł���B�@�q��Ύ��ю偁�m���̓��͕���r�Ƃ��������̎v�z�́A���@�̓��̌�肪���������ɂ���ė��ю�ɓ`������A�Ƃ����l������O��ɂ��Ă����\��������B�{���A�����̌��͌l�̓��X�̏C�s��ʂ��Ă̂ݓ�����B�Ȃ̂ɁA�@�c�̌�肪���ю�̊ԂŐ_��I�ɓ`�B����Ă����Ƃ���̂́A���ʘ_�I�ɖ��������l�����ł���A���������ΏC�s�s�v�_�ɂȂ肩�˂Ȃ��B��̂�������A�������_���`�I�ȁq���̏��^�r�̎v�z����Ύ��嗬���ɉ萶�����̂��B�j���ォ�猾���A��͂肻�̋N���́A���@�t���ɂ���ē���ю傪�u�{���̑́v���������Ă���A�Ƃ������������̋����ɋ��߂�ȊO�ɂȂ��낤�B
�@�Ƃ�����A��Ύ����̈�l�ł���������A�E�̂��Ƃ��ю���ؕ��̎v�z�����R�Ə������̂ł���B��300�N�O�ɍ�������������������ю�M�́A���̍��A���ɑ�Ύ��@��̒����ɓ��荞�ƌ����Ă悢�B�����A18���I����19���I�ɂ����Ă̑�Ύ��嗬�ł́A�������̊ю�M������ю傪���X�Ɠo�ꂷ��B
�@���a2�i1765�j�N�A33���E�����͓����̗���̉��A�O�\�ܐ��E�����ւ̌����������s�����B���̎��̋L�^�������ɓ`����Ă���B����ɂ��ƁA�����́u���@�������̓��c�ɔ�B�����ʂӏ��̗B�Ȉ�厖�̔�@��B����{�������c�吹�l�J�R��l��O�ɂ���35��������l�Ɉꎚ��Ԃ��s�c�����ߕt���ނĒ�������ׂ��v�Əq�ׂāu��厖�̔�@�v������ɕt�����A�����ē��@���͂��߂Ƃ������t�́u��Ӟ��̞��X�v���c�炸�n������A�u���̔�@�����ɔ[�ߋʂӏ�͓��@�������ڔT��������l���̋��S�̈�̂ɂČ�@�A�������ɂ͓������@�̌��Z��t�e�O�������ɂ��đ�Ύ���嗬�̑�ڂ͊F�M���̓��ؔ�@�̓얳���@�@�،o�ƌ�ӓ���ցv�ƌ�����Ƃ����B�����ɖ��炩�Ȃ��Ƃ��A�����́A�u��厖�̔�@�v�������ɔ[�߂����ׂĂ̗��ю����@������ƈ�̂̑��݂Ƃ݂Ȃ��A�Ȃ��������������ē���ƂȂ����������u��t�e�O�������v�̑哱�t�̕��Ƃ��ĈӋ`�Â��Ă���B���@�̓��̌��Ƃ��Ắu��厖�̔�@�v���������ꂽ���ʁA�V�ю�̓����́u��t�e�O�������v�̕��ɂȂ����\�\�����́A�����錾�����킯�ł���B
�@����A������_���`�I�Ȍ��������̋V����ʂ��A�嗬�S�̂��������ׂ����̈ʂɍՂ�グ��ꂽ�����̑����A�������̓��ؑ����_�Ɋ�Â��ю�M�̏����҂ɂȂ����悤�ł���B�����́A�������瑊���������N�A����̑�Ύ��M�ނɑ��鋳���̒��ŁA���ڂ��u���p�{���̐���v�A�������g���u���������̎�v�ƈʒu�Â��Ă���B
�@����ɓ����Ȍ�̊ю�ł́A42���E�������ю�M���������Ƃ݂���B������37���E��琫�猌�����������̂́A����11
�i1799�j�N11���ł������B���炭����ȑO�̂��ƂƎv�����琫���Q�����Đ��@���s�����A����ފ݉�ɂ����āA�����͓�琫琫���u���@�����̓��@�吹�l�̌�S�́v�ȂǂƏ̗g���A�݂邩��Ɋю�M�I�Ȕ������J��Ԃ��Ă���B
���ƐM�h�̏�Ő\������琫��l�t�̌��g�͌���͈ꕝ�̌�{����B�e�p�����ɓ��@�吹�l�̌�S�̖�
������琫琫��l�t���A�吹�l���J�R������l�t����X��厖��@�𑊓`���A���c�̋����ɋ}�x�䏊���V���̓�琫琫��l�t�̋��̊Ԃ͑吹�l�����̏��A��̏�͑吹�l����@�̏��A�A�͑吹�l��a���̏��A�����͑吹�l�䐳�o�̌�Ȃ�ׂ��B������s�v��琫��l�t�̌���@�̓���Ȃ�A���̗�R���̎���y�ɂ��āA�V����h�R�ɂ����ׂ��炸�A�@���Ȃ�̂ɐl�M���l�M���̂ɏ��������āA��ȂȂ����O���@�̌�{���̌�ݗl��
�@�����ɂ݂���u�吹�l���J�R������l�t����X��厖��@�𑊓`���A���c�̋����ɋ}�x�䏊���V���̂ɁA��琫琫��l�t�̋��̊Ԃ͑吹�l�����̏��v�]�X�Ƃ��������̔����́A��ɏЉ��33���E�����̊ю�M�̌����ƑS�������ł���B�������������玝���グ��ꂽ��琫琫���g�A���̐܂̔ފ݉�ɎQ�����Ă���B�܂�����́A��琫琫�̎��ɓ��邱�Ƃ��d�X���m�̏�ʼnE�̂��Ƃ������Ȃ����킯�ł���B���ꂩ�炵�炭�̌�A�����͓�琫琫���猌�����������ƍl������B18���I�㔼�̑�Ύ��@��ł́A���̂悤�ȗނ̊ю�M���x�z�I�ȗ͂������Ă����̂��낤�B
�@�Ȃ��A�����́A���@�a����̐��@�i�N�����s�ځj�ɂ����āu�e�ӂƂ��m�炸�ʂ炸�얳���@�@�،o�Ə�����镃�ꏊ���̓��g�Ȃ�ǂ��A���̌�{���̔@���A�@���t�̐l�@�̈�̌�{���Ɛ��āA�����\�@�E�𗘉v���A�Ԃ��Ԃ����^�������v���ƒk���Ă���B����́A�{���ؓ����M��}��Ƃ��Ė嗬�̑m���ɂ��J����Ă��邱�Ƃ��������̂ł���B���̓����̍l�����́A��k�ɂ����ؑ�����F�߂鍶�������̎v�z�Ǝ��Ă���B���邢�́A���������������l���@�I�Ȗ{���ؓ��̎v�z����e�������̂�������Ȃ��B
�@�Ō�ɂ�����A�ߐ��@��ɂ�����ю�M�̗�������Ă������B�������ɂ́A�w���E�߂��v���@�������ю�M�I�Ȍ������c���Ă���B�O�����i1844�j�N�A�����͌������D�̗�������ޑm���������ׂ��w�ٗ��`�Ӕj���x�����B�����ɂ́A
�O��̐��������R�̊ђ��Ɉ��������߂���@�{�����ӂ̑��`�ɉ]�����@�䔻�Ƒ�X�����ׂ����@���@�t�̉]����X�̐��l�������@�Ɛ\���S��]�X�Ⴕ����Γ��@������͓��ɑ吹�l�����l�����ɓ����҂Ȃ苵����|�Ŏ��E���ׂ��]�X�@�ʐl��@�̏d�ߐ������Ȃ�͗L��ׂ��炸����ׂ�����ׂ��i�����Q�R�[�T�U�R�j�B
�@�Ƃ̎咣���݂���B�����͂����Łu�O��̐����v����ΎR�ю�̌��Ђɑi���A��Ύ���ᔻ������D���������ӂ߂Ă���B�Ɠ����ɁA�w��{�����ӑ����x�̒lj���ڂ����p���Đ_���`�I�Ȋю呦���@�̋`��U�肩�����Ă�����B
�@�ȏ�A��X�̎�����݂Ă������A���������̊ю�M�͍]�ˎ���̑�Ύ��@��ɏd��ȉe�����y�ڂ����ƌ����Ă悢�B�Ƃ���18���I���t����́A��Ύ��̗��ю傪����ю�M��������悤�ɂȂ����B��Ύ��嗬�ɂ�����ю���ؖ{���E�ю���ؕ��̎v�z�I�N���́A�ю�Ԃ́u�{���̑́v�̎��������������̏������ȊO�ɂ͍l�����Ȃ��B�߂��̑�Ύ��@��ɑ䓪���Ă���ю�M�́A�����̋��w�W�J��[���Ƃ���悤�Ɏv����B
�@�������A���炭�͓��L�̉e������ю�̐M�S������]�Q���������Ɣ�ׂ�ƁA�ߐ��ȍ~�̊ю�M�҂͎��Ƃ��ĐM�𗣂ꂽ���Ў�`�Ɋׂ邱�Ƃ��������B���݂̑�Ύ��@��Ɏ����ẮA�ɓx�Ɍ��Ў�`�I�Ȋю�M�Ɏx�z����Ă���B�����Ƃ��Ă��A���̓_�ɂ͓��ʂȒ��ӂ�˂Ȃ�Ȃ��B
�P�O�@�ߑ�@��̌��������ς̊m���ҁ\�\�Z���E����
�@�����܂ŁA��Ύ��嗬�ɂ�����u�B����l���������v�̎v�z�̌`���ߒ���_���Ă����B�u�B����l���������v�̎v�z���������݁A�Ȃ����u�����̊ю�͐�v�Ƃ����_�b�I�v�l���Ύ����ɐZ���������̂́A���s�ɒ��S��u�������嗬���痈�����������ł���B
�@�u�B����l���������v�́A��Ύ��@��ɂƂ��Ĉ��̊O���v�z�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A��Ύ��̗��ю���@���I�ɈӖ��Â���A���̊O���v�z�́A����ɑ�Ύ����w�̊�ՂƂȂ��Ă����A�����̍��ɂ͊��S�ɏ@��×��̓`�����`�Ƃ݂Ȃ����Ɏ������B
�@���āA�ߑ���}����ƁA�������{�̏@������ɂ��A��Ύ��嗬�́u���@�@����h�v�i��Ɂu�{��@�v�Ɖ��́j�ւ̕ғ���]�V�Ȃ������B�����̑�Ύ��́A�e�{�R�̈قȂ鋳�`�M�����G�����鋻��h����A�ꍏ�����������Ɨ����ʂ������Ɠw�͂��Ă����B�����ɂ����đ�Ύ��̋��`�̐��������������邽�߂ɁA��w�u�B����l���������v�̎v�z����������Ă����B���̓����̒��S�ɂ����̂́A56���̑�Γ����ł������B
�@����25�i1892�j�N5���A��Ύ��Ɠ�������h�ɑ�����v�@���̑O�Z�E�E釔�����́w���@�ϐS�_�x���A��Ύ������̋��w���������ᔻ�����B����ɑ��A���̑�Ύ��ю�̑�Γ����͋���h�ǒ��̍�{����i�����̗v�@���Z�E�j�ɍĎO�R�c���������͉��������A������26�i1893�j�N�A����h�ǒ�������v�����̖������C�ɂȂ��Ă���A�悤�₭�w���@�ϐS�_�x�̔��s�Еz���֎~����[�u���Ƃ�ꂽ�B�����������ŁA�����͓���́w���@�ϐS�_�x�ɑ��锽�_���������i�߁A����27�i1894�j�N6���Ɂw�٘f�ϐS���x�������B
�@���́w�٘f�ϐS���x�́A����̘_�ւ̔�������ړI�Ƃ��Ȃ�����A��Ύ��́u�B����l���������v�������邲�Ƃɐ�g������e�ɂȂ��Ă���B�����̓����́A�P�ɓ������w�̐��`��i���邾���łȂ��A��Ύ��݂̂�����h�ɂ�����B��̐�����Ƃ��邱�Ƃ�����K�v�ɂ������Ă����B
�@�w�٘f�ϐS���x�ɂ݂�������̑����_�̓����́A���̓�_�ɏW��悤�B
�@�i�P�j�Ηv�����̎v�z����w�Ɏ��@�̑����_
�@�q���������ɂ��O���@�̓`���r�Ƃ�����Ύ��嗬�̌��������ς́A15���I�㔼�ɍ������������̌��^����A26���E����������18���I�O��Ɍł܂����ƍl������B�ߑ�̓������A���̌��������ς��p�����A�u���̎O���@�͏@�c����J�R�����֒������`�݂���@�Ȃ�v���Əq�ׂĂ���B
�@�������Ȃ�������ɂ����ẮA��Ύ��鑠�́u�{����d�̑��{���v�̗B����l������������������Ƃ��낪�����I�ł���B�����́A�w�٘f�ϐS���x�̑�6�́u���Ƒ�����_���v�Łu�@�̕ʕt���ʂЂ���t��^�̗B����l���������t�@�̑哱�t�Ɖ]�ӂׂ��v�Əq�ׁA���̖@�̂ɂ��Ắu�ʕt�̖@�̂Ƃ͌�R�ɔ鑠����{����d�̑��{�����Ȃ�v�Ɛ������Ă���B�@�̂����Ύ��̉��d�{���̑����������āu�^�̗B����l���������t�@�v�Ƃ��ׂ����A�Ƃ����̂������̎咣�ł���A�ނ͂��̈Ӗ��ɂ����錌���������u�@�̑����v�Ə̂��Ă���B
�@�@�̑����Ƃ������t�͓����̑n��ł��邪�A���̌����͋ߐ��@��́q���������ɂ��O���@�̓`���r�ςƐ[���֘A���������Ă���B���d�{���́A���̖��̂��猾���Ă��O���@�̒��́u�{��̖{���v�ɂ�����B�����āA26���E�������w����钾���x�Łu�O���@�̐���A�{��{���v�i�x�v�R�[�X�R�j�Əq�ׂĂ���悤�ɁA��Ύ����w�ł͎O���@�̑̂��u�{��̖{���v�Ƃ���B���������āq���������ɂ��O���@�̓`���r��@�̂̎������猾���A�u�{��̖{���v������d�{���̑����ƂȂ�킯�ł���B
�@�����Ƃ��A��Ύ��嗬�ɂ�����O���@�̋��������́A�����܂ŋ��`�ʂ̑������Ӗ����Ă���B����́A�����������u�����@��v�̌̎���ʂ��ĎO���@�́u���t�����̑c���v����������ƁA17���E�����́w�ƒ����x���u�`����E�̑����A���ۖ����̑������v���u�����̒q���v�Ƃ������ƁA25���E���G���w�ϐS�{�����L�x�Łu���̋����������ܑ啔�O���̖{���̖��ӂɉ߂����v�i��S�R�[�R�U�X�j�Ɩ����������Ɠ��X����@�m�����B
�@�����œ����́A�w�٘f�ϐS���x�Łu���@�̑�������ɕt�����B����l�������X�����Ȃ���̂���v�Əq�ׂ�Ȃǂ��āA�h��Ύ��ɂ͋��`�ʂ̋��������ƂƂ��ɖ@�̖ʂ̑���������h�Ǝ咣�����̂ł���B���������ƁA�@�̖ʂ̗B����l����������v�z�͋ߑ�ȑO�̑�Ύ��@��ɂ��������B14���E����̍�Ɂw�����՞��X�������x������B
�x�m�l�P���̒��ɎO�P���͈����Ȃđ����������B���͑y�t���̕��Ȃ�B��Ύ��͌�{�����ȂĈ��Ɛ������A�����ʕt���B����l�̈ӂȂ�B�吹���{����d��{���A���t�]�萳���̌�{���@�̌�t���A�Ⴙ�Ώ�s�F埵埵�����v�t���̑哱�t�ƒ�ލ��̔@���ӓ�����ȂČ�{���̏��̗v�Ȃ�B�v���]�荡����R�̐_�͌��v��s���`�̌�t���A���@���@�E�����E���ڌ����t���A�S�̐F���ւ炸���ԂȂ�B���ʎl�ʂ͑y�t�����A�����ꎆ�O�P���̕t�����͕��؎��ʕi�̋V�Ȃ�A��{���͋v���ȗ���������������鏊�̕t����i��S�P�[�S�T�X�j
�@�u�����ꎆ�O�P���̕t�����v�Ƃ́w�����՞��X���x�ł���B����ɂ��A�w�����՞��X���x�͏�s��F�̌��v�t���̖@�̂����������ł���A�@�̂̕��ƂȂ���ʕi�̂��Ƃ����̂ł���B�������đ�Ύ��ł́A��s�t���̖@�̂��̂��́\�\�u�{����d��{���v�i���d�{���j�Ɓu�����̌�{���v�i�����{���j�\�\�������Đ^�̈��Ƃ���̂��Ƃ����B����䂦�A���̎����ł͑�Ύ��ю�Ԃ̙�䶗��{���̏��n��@�̕t���Ə̂��Ă���B
�@����́A���������̕����𑊓`�����ȂǁA�����̋��w�v�z����傫�ȉe�������Ƃ݂���B��䶗��{���̑����������đ�Ύ��̗B����l���������̐��v�ƂȂ��A�E�̂��Ƃ�����̌������A��Ύ��J�n�ȗ��̙�䶗��{���M�ɓ����R���̑�����`������������ʂƍl�����悤�B�����̑�����`�́A�ю�̕t�@�d����v�R�i�����嗬�j�̏@�����琶�܂�Ă���B���̈Ӗ��ł́A����̖@�̕t���_�͐ΎR�Ɨv�R�̎v�z�I�����ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�����āA���̐Ηv�����̓���̖@�̕t���_���Ύ��́u�B����l���������v�̍����Ɉʒu�Â���ׂ��A���߂āu�@�̑����v�̈Ӌ`�����g�����̂��ߑ�̓����������Ƃ������ƂɂȂ�B����̖@�̕t���_�͉��d�{���Ə����{���̓�̂�@�̂Ƃ��邪�A�����̖@�̑����_�̕��͉��d�{���݂̂�@�̂Ƃ���B���������Ⴂ�͂�����̂́A��䶗��{���̑����������đ�Ύ��ŗL�̕ʕt�B����l�����Ƃ���_�ł͗��҂͈�v���Ă���B
�@���̂悤�ɁA�����̖@�̑����_�́A�Ηv�����̋��w�v�z�i����̖@�̕t���_�j����w�Ɏ��ƌ�����̂ł���B
�i�Q�j���������̋��`�Ɠ������w�̓��ꎋ
�@�����́w�٘f�ϐS���x�ɂ����đ�Ύ��̌��������Ɂu�@�̑����v�u���������v�u�@�告���v�̎O�킪����Ɛ������A���ꂼ��ɖ��m�Ȓ�`��^���Ă��Ȃ��B�Ƃ��ɁA�@�̑����Ƌ��������̈Ⴂ�͕s���Ăł���A�����u���@�̑�������ɕt�����B����l�������X�����Ȃ���̂���v�Ɛ����݂̂ł���B
�@�������A��قǘ_�����A��Ύ��嗬�ɂ�����@�̑����y�ы��������̊T�O�`���j���Q�Ƃ���Ȃ�A�ꉞ�A�@�̑����͖@�̕t���Ƃ��Ă̖{�������A���������͎O���@�`�̑��`�Ƃ����悤�ɋ�ʂł���B�������A�w�٘f�ϐS���x�ɂ́u�@�̑����̌����v�Ƃ����\��������̂ŁA�@�̑����͋�����������������T�O���Ǝv����B���Ȃ킿�@�̑����i�@�̕t���j�Ƃ́A�O���@�`�̑��`���Ƃ��Ȃ����d�{���̑����Ƃ����Ӗ��ɉ������B
�@�����@���@�̂��Ƃ��A�����̖@�̑����_�ɗ��r���Ċю�̓��ؑ�����������̂́A�����������j�I����w�٘f�ϐS���x�̋L�q�������ԓx�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�ނ�́u�B���̗��`�v�Ȃ�l���������o���A�����̖@�̑����_���ю�̓��ؑ����𗠖ʂɉB���Ă���ȂǂƋ��ق��邪�A���F�͗����I�ȋc�_����̓����ł���B�����́w�٘f�ϐS���x�̒��Ŗ@�̑������������ɂ�����A�ߐ��ȍ~�̏@��Ŋю�M�𐳓������邽�߂ɗp����ꂽ������������������A�����w�����՞��X���x�����݂̂����p���Ă���B�@����́u�������g�Ɉ��ċ��͂鏊�̍O����N�̑��{���͓��ڂɔV�����^���@�{�厛�Ɍ������ׂ��v�i��S�P-�X�U�j�ł���A�����́u�{�厛�Ɍ������ׂ��v�̉ӏ��𗪂��Ĉ��p���A��Ύ����̖@�̑����̕��Ƃ��Ă���B���͓������������u�{�厛�Ɍ������ׂ��v�̕��������A�ނ̖@�̑����̊ϔO�𗝉����錮�ƂȂ�B�����́u�{�厛�Ɍ������ׂ��v�Ɩ����āu�O����N�̑��{���v����ڂɎ��^�����\�\���ꂪ�����̗����ł������B�����܂ł��Ȃ��A���̌���{�厛�Ɂu�������v���ƂȂǂł��Ȃ��B�u�������v���Ƃ��ł���̂́A�����ɏ@��Ƃ��đ��݂���u�O����N�̑��{���v�����ł���B
�@���ǁA�����̌����@�̑����̊j�S�͏@��Ƃ��Ẳ��d�{���̑����ł���A�����ɋ��`���`�Ƃ��Ă̋����������t������̂ł���B�Ƃ���A���������Ɋւ��Ă����@��̂悤�ɐ_���`�I�ȉ��߂��s�����Ƃ͋�����Ȃ��Ȃ�B�@�̑����̖{������ؑ����Ƃ݂�ꍇ�A���������ɂ�鋳�`���`�́A�{���̌��̎����ړI�Ƃ����_��I�Ȍ��`�ɂ���Ă��܂��B����ǂ��A�����̌����@�̑��������d�{���̑������j�S�Ƃ��邱�Ƃ�m��A�t���I�ȋ��`���`�Ƃ��Ă̋��������̐_�鐫���K�R�I�ɕ��@�����B
�@�Ȃ�A�����ɂ�������������̋��`�Ƃ͈�̉����B����́A�����̖�k���g�߂ɖڂɂ��A����I�Ɍ��r���Ă���26���E�����̋��w�̈���o�Ȃ��B���_���ŏڏq���邪�A�����͍��������̓o��ȗ��A��Ύ��ɂ����ėB����l�̋��������Ƃ݂Ȃ���Ă����O���@�`�𗝘_�I�ɊJ�������ю�ł���B�������w�ł͓��@�{���_��l�@�̈�`���Ύ��̎O���@�`�̐��v�Ƃ݂Ȃ����A�����͓�������Ύ��̋��������Ƃ��Ď����������`�ł��������B
�@�Ⴆ�A�w�٘f�ϐS���x�̒��Ɏ��̂悤�ȋL�q������B
���̋����̌��������@�c�̖@�����ʂ��{���̋Ɉӂ�`����̂Ȃ�V��^�̗B����l�Ɖ]�ӁA���`�@���ɉ����邪�@����������̉��߂��������`��X�̉�ʂ����֑������咣���@�c��}�v�����v���{������s�̐�瑂Ƃ�毂Ɏz�̔@������������A毂Ɏz�̔@������������̂ɗ\�͒f�������R�͕s���`�Ȃ薳�����Ȃ�ƋX�����ҏȂ��ׂ�
�@���̋L�q�́A�����ɂ��u�����̌����v��_��I�Ɋ���������\���Ŏn�܂��Ă���B�������A����ɑ����ē����́A�v�@���ɂ݂��鑢���`�A�@�c�̖}�v���A�v���{������s�̐�瑂Ƃ��錩������Ă����A�������Ɂu��Ɏz�̔@������������A毂Ɏz�̔@������������̂ɗ\�͒f�������R�͕s���`�ȃ��������Ȃ�v�ƒf���Ă���B�u�z�̔@�������v�Ƃ́u�����̌����v���w�����A���̂�����͏n���ɒl����B
�@�v�R�̓k�͋����������Ȃ����瑢���`�������A�v���̖{������@�c��}�v���s�̐�瑂Ƃ݂Ȃ��̂��\�\�B���ꂪ�����̎咣�ł���B���̎咣�𗠕Ԃ��A�h�������������҂́A�F�������̑������s�킸�A���@���v���̖{���Ƃ݂Ȃ��h�Ƃ����l���ɂȂ낤���B�܂�A�����̍l������������̋��`�͓��@�{���_�ɐ[���������A�������w�̎O���@�`�Ɠ��e�I�ɏd�Ȃ荇�����̂Ɛ���ł���̂ł���B
�@���̂��Ƃ̖T�Ƃ��āA����Ɂw�٘f�ϐS���x����������Ă������B
�ד}���瓙�͉�@�c�̖{�����邱�Ƃ�m�炴�邪�̂Ɏ��ʕi�̕���m�炴��ׂ��A�p�ē����s���`��q�Ȃ錻�Ɖ]�ӂׂ��Ȃ���ɏ@�c�͋v�������̎���p��g�ɂč݂������Ƃ͊J�ڏ��y������̕��ӂ̔@���|���^�ӂׂ��ɂ��炴��Ȃ�A�̂ɌႪ��ɉ��Ă͍�������̕ӂыv�������̎���p��g���@�L����t�e�̎O���{�����̋���얳�@�c�吹�l�Ƒ�������邱�ƂȂ�A������ƕ��̋Ɉӂɂ��ĕs���`�̓\�Ēm��ׂ��@��ɂ��炸���ד}�X�ނ͉������i�̎���p�g���Ȃċv�������̎���p�g�Ɩ����邪�̂ɑ���ӐF�������̑����d���j�ĕs���`�̌��ؐ��ɖ��ĂȂ�
�@������̕�������A���������@�{���_�������đ�Ύ��̑��`���`�̋ɈӁA���Ȃ킿���������̔�`�ƍl���Ă������Ƃ��ǂݎ��悤�B
�@�܂������́A�l�@�̈�`����Ύ��̋��������̉��`�Ƃ݂Ȃ��Ă���B�����ɂ��A�u�l���@�@���l�̋`�v�́u���ɉ��ċ��\��ׂ���̖@��v�ł͂Ȃ��A���@�����őO�Ɂu�t�@�̒�q������l�Ɉ�t�����Ӌ����̙��فv�Ȃ̂��Ƃ����B�����́A�������{�i�I�ɐ鎦�����l�@�̈�`���u���̒��̓��ɂ��đ����̏�ɂ��炴��Ηe�Ղɉ����邱�Ɣ\�͂���v�@��Ƃ��Ĉʒu�Â���B
�@���̂悤�ɁA�����́w�٘f�ϐS���x�ł́A�������Z������䏑���i���Ř_�����O���@�`�̐��v�\�\���@�{���_�Ɛl�@�̈�`�\�\���܂��ɑ�Ύ��̓ƈ�A�B����l�̋��������̉��`�Ƃ��Ď�����Ă���̂ł���B�����́A�u�������������B����l�̔�Ȃ͏O���ɓ`�d���邪�@�����̂ɂ��炸�A���͔V��B���^���̔�@�ɂ��ēƂ莞�̊ю�̏������鏊�Ȃ�v�u���ߍL�z�̎��Ƃ��ւǂ��ʕt���������Ȃ���̂͑��ɔތ������ނ���̂ɔv�Ƃ����������̕����ɖڂ�D���A�@�h��Ύ��̋��������̋��`�͖����J�̔�`�ł���h�ƈ����ɍl���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�u�����̌��������@�c�̖@�����ʂ��{���̋Ɉӂ�`����̂Ȃ�v�Ƃ��������̋L�q�ɂ��Ă��A�h���@�{���_��l�@�̈�`���́u�{���̋ɈӁv�܂��Ă����u�@�c�̖@���v���ʂ��������{�����ʂ��\�ɂȂ�h�Ƃ̈ӂɉ����ׂ��Ȃ̂ł���B
�@���_���Ř_���邪�A�������u�������������B����l�̔�ȁv�Ƃ�����@�{���_��l�@�̈�`�͓����ɂ���ė��_�I�ɊJ������A���݂ł͑�Ύ��嗬�̑S�m�����m�蓾��Ƃ���ƂȂ��Ă���B�Ȃ�قǓ����́A�B����l�̖@����L�������ӂ̏�ڂ����邱�Ƃ߂����Ă���B�������A���ɂ����������ӂ̏�ڂ��B����l�Ŕ���J�̂܂܂��Ƃ��Ă��A���̋��`��̊j�S�͓����ɂ���ė��_�I�ɊJ������Ă���B�������g�A�w�٘f�ϐS���x�̒��ŁA���������̋��`�̊j�S���������w�ɑ��Ȃ�Ȃ����Ƃ��킸���Ɍ���Ă���B����20�N��ɓ������咣�������������̋��`�̔���J���́A���Ȃ��Ƃ������̎���ɂ͂��Ă͂܂�Ȃ��B
�@�ȏ�̂��Ƃ��A�������������������̋��`�Ɠ������w�Ƃ͐[���֘A������̂����A����G��Ă����������Ƃ�����B����́A�������w�{�������x�w�S�Z�ӏ��x�̑��`���u�@��y�t�̑����v�Ƃ��A�B����l�����Ƃ݂Ȃ��Ȃ����Ƃł���B�w�{�������x�w�S�Z�ӏ��x�̗����������́A���ɓ����嗬�ő��d����Ă������ł���B���̂��߂��A����̗v�@���ɑ����Ύ��̗D�z�����咣�����������́A�������������B����l�̑��`���łȂ����Ƃ��J��Ԃ��w�E�����B�����A�B����l�łȂ��Ƃ͂����A��Ύ��̌��������ɂ����ė����������̓��e�͋ɂ߂ďd�v�ł���B�����������͍��������̐�g�ɂ���đ�Ύ��嗬�ł��d�������悤�ɂȂ�A��̓������w�̍\�z�ɏd�v�Ȗ������ʂ������B�B����l�̋������X�����ƌ����Ă����F�͓������w�̘g�ɂ����܂�킯������A�������w���x���Ă���w�{�������x�w�S�Z�ӏ��x�͑�Ύ��̋��������̕����I�����ł�����B
�@��Ύ��̗B����l���������̋V���̍ۂɗp������u�������v�̒��ɂ́w�{�������x�w�S�Z�ӏ��x�������Ă���A�Ƃ̌����`��������B���̐^�ۂ͂Ƃ������A��Ύ��̋��������̋��`�ƌ����Ă��A�w�{�������x�w�S�Z�ӏ��x�̓��e�Ƃ������ꂽ�O�㖢���̔���Ȃǂł͂Ȃ��B�ނ��낻��́A�����������̓��e��ΎR�̋��`�M���Ɂ\�\���d�{�����S��`�A���@�{���_�A�l�@�̈�`�\�\�ɂ���čč\���������̂ɂ����Ȃ��̂ł���B���̈Ӗ�������A��Ύ��́u�B����l���������v�͐Ηv�����̎Y���Ƃ݂�ׂ��ł��낤�B
�@�ߑ�̑�Ύ��ю�ł���56���E�����̑����_�Ɋւ��āA���̓�����2�_�A�E�����Ă݂��B��Ύ��@�傪���@�@����h�̒��ɑg�ݓ����ꂽ����ɐΎR���𗦂��A�v�R�̘_�q�Ƃ��Ό����������́A�����嗬���ɂ����đ�Ύ��@��̋��`�I�ȓƎ��F���o�����Ƃɕ��S���Ă����B���̒��ŁA��Ύ��̗B����l�����������u�@�̑����v�u���������v�u�@�告���v�ɕ��ނ��鎎�݂��Ȃ���A�����͋ߑ�@��̌��������ς̊m���҂ƂȂ����̂ł������B����̓��@���@�̌��������ς́A��{�I�ɂ��̓����̑����_�P���Ă���B
�@�M�҂̍l�@�Ɋ�Â��A�w�٘f�ϐS���x�̋c�_�́A�Ηv�����̑�����`�i�������j�ɂ���ėv�R�̑�����`�i���瑤�j���U������A�Ƃ�������킵���\�}���Ƃ��Ă���B�����͂��Ƃ��A��̑�Ύ���k�������A���̂��тȍ\�}�ɂ͖����o�I�ł���B����̑�Ύ��@��́A�������m�������Ηv�����̑�����`���A���������J�R�ȗ��̈�т����`���ł��邩�̂��Ƃ����o���Ă���̂ł���B
���@�_
�@�����̒��n�����������Ύ����́A�얳���@�@�،o�̑�ڐM�A�l�i�@�c�̓��@�j�@�E�@�i������䶗��j�̖{���ւ̐M�A�x�m�ɖ{��̉��d����������Ƃ���M����L���Ă����B�v����ɁA�ΎR�ŗL�̎O���@�ւ̐M�ł���B�܂���Ύ��̏��ю傪�{�����ʂɍۂ��āu�얳���@�@�،o�@���@�v�Ƃ������̏�������n�炵�Ă���l���݂�A�l�{���i���@�j�Ɩ@�{���i������䶗��j�ꎋ����l�@�̈�ς��A���炭���c�����̓������炠�����̂��낤�B�������A���������ΎR�̋��`�M�����A���叔�R�̌��������������𐧂���܂ł̗͂��������Ȃ������B9���E���L�̑�܂ł̑�Ύ��嗬�ł́A���`�M���̓`���͂����Ă��A���`���w�ƌĂт��邾���̋��`�̌n����������Ă��Ȃ������B
�@�����ɋ��s�̓����嗬�����l�̊w�m�����đ�Ύ����L�ɓ��債�A������苗��E�����Ɩ�����Ď��X�Ɩ@�`�����n�߂��B�����̓����嗬�́A�֓��̋���������w�ʂł̐������x��Ă����ƌ�����B���̍��A���łɑ�Ύ��▭�{���ł́A���L����v�ɂ���Ė{�����v�z���������Ă����B�������Ȃ��瑸��ɂ́A�w�{�������x�w�S�Z�ӏ��x�w�Y���������x�w��`���`�x���̋���̑��`�����d������`�����������B�����ɁA����̏o�̓�������Ύ����̖{�����v�z�Əo��A����ŏd��ꂽ���`���Ƒ�Ύ��̋��`�M���Ƃ̌��������݂�_�@���������ƍl������B
�@�����́A���s�̓��@���c�ō��g���ꂽ�q�ߑ��[��s�[���@�r�̗�R����������ՂɁA�����嗬�Ƃ��Ă̋��������̌n������A����ɂ�����Ύ����L�̎O��M�ƌ��т����B���̌��ʁh��R�t���ȗ��A���@�A�����A��Ύ��̗��ю�ɂ���ĎO���@���B����l�Ō�����������Ă����h�Ƃ����V���ȋ��`�M�����������A��������镶���Ƃ��đ���R���̑��`���ނ��c�����s�ɗp����ꂽ�B
�@����̐������������锼�ʁA����̖@���̐��`��葖�����悤�ȋ��w�̌n�����L���Ă��Ȃ����������̑�Ύ��嗬���A���̂悤�ȓ����̋��w�W�J�Ɉ������܂�Ă������͖̂�������ʂ��Ƃł������B����̌���������`�ނ�Ɉ��p���鍶�������̑��`���w�ɂ���đ�Ύ����w���`�����ꂽ���Ƃ́A�ƂɎw�E����Ă���B�����A����ɂ���đ�Ύ��嗬�ɂ͊ю��̎v�z�����Â��n�߁A�ΎR�×��̐M����̈�E�������炵���˂Ȃ��ю�M���萶�����B�Ȃ��A�����̑�Ύ��嗬�������̑�����`���R�Ȃ����ꂽ�w�i�Ƃ��āA���̊ю��w�m�炪���ÓV��̌��`�@��Ɋ���e����ł������ƁA���L���u�M�S�v�̗���ɓO�������ю�̌������������n�߂Ă������ƂȂǂ��l�����ׂ��ł���B
�@���_�I�ɁA�u�����̊ю�͐�v�Ƃ������@���@�̐_�b�́A������`�҂̍����������q��ҁr�Ƃ��A��Ύ��嗬�̋��`�M���Ɠ����嗬�i��̗v�@���嗬�j�̕t�@�d���E���`���d���̓`���Ƃ�w�i�Ɍ`�����ꂽ���̂ƍl����B�ߐ��ȍ~�̑�Ύ��嗬�̌����v�z���Ηv�����̎Y���ł��邱�Ƃ́A56���E�����̌��������ςɍł��悭����Ă��悤�B�v�@���̊w�m�ƑΌ��������w�٘f�ϐS���x�̒��ŁA�����͑�Ύ��̌����������u�@�̑����v�u���������v�u�@�告���v�ɍו��������B�������g�͋C�Â��Ă��Ȃ����A�ו����̗��R�́A��Ύ��̌����v�z�����͐Ηv����������ł���B�������ΎR�̌��������̗D�ʐ����咣����ɂ́A�ΎR�̋��`�M���ɗv�R���d�����鑊�`����v�R�o�g�̓����̑�����`�����т������́i�@�̑����E���������j�ƁA�v�R���d�����鑊�`�����̂��̂̑����i�@�告���j�Ƃ����ʉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B
�@���Ȃ݂ɁA�������L�߂��u�{���̑́v�������Ɋ�Â��ю�M�́A�ߐ��ȍ~�̑�Ύ��@��j�ɒf���I�Ɏp�������Ă���B�����A��Ύ��ŗL�̎O��M�𗝘_�����J������26���E�����́A���̎O���@�`����ю�M�����S�ɏ��O�����B���̂��߁A��Ύ��̐������`�ɓ����R���̊ю�M���Z�����邱�Ƃ͖h���ꂽ�B����ǂ��ْ[�I�Ƃ͂����A�ю�M�͑�Ύ��@��̓`���v�z�Ƃ��Ă̒n�ʂ�z���Ă���B���̓_����݂Ƃ��āA�ю�M�I�ȋ�����������ю�⍂�m�͂���܂łɉ��l�������B�ŋ߂ł́A67�������̂��鈢�������������ł������B��Ύ��̊ю�M����q�`���r�̉��ʂ�����Ƃ́A�܂��n�܂�������ł���B��Ύ��̊ю�M�̋N�����q�ϓI�ɉ𖾂��邱�Ƃ́A����̕x�m�嗬�����҂ɉۂ���ꂽ�d�v�Ȏd���ł���ɈႢ�Ȃ��B
�@�@�@���@�@�@�@��
�@���_���̍l�@���I����O�ɁA��Ύ��嗬�j�ɂ݂���ю�ς����Ă������B��Â��݂Ɍ����ƁA��Ύ��嗬�ɂ����Ă͇@�ю咆�S��`�A�ю吒�h��`�B�ю��Ύ�`�Ƃł������ׂ��O�l�̊ю�ς�������̂ł͂Ȃ����낤���B�������A����͗ތ^�I�ɏq�ׂ����̂ł���A���ԂƂ��ẮA����炪���݂��Ă���P�[�X�����Ȃ��Ȃ��Ǝv����B
�@�ŏ��́u�ю咆�S��`�v�́A���c�g�D���w�����钆�S�҂Ƃ��Ă̊ю�ς��������闧��ł���B�ю�͋��c�̒��ł��邪�A��ΓI�Ȍ����͎����Ă��Ȃ��B���c�Ƃ��Ă̕��j�⋳�`���߂́A�ю傪�ŏI�I�Ɍ��肷����̂́A��R��O�̔[�����ׂ��ł���ƍl�����Ă���B�܂�A�ю�̌��Ђ͕��@�̐�ΓI���Ђɏ]�����Ă���A�ю�̈ӌ������炩�ɏ@�`�ɔw���ꍇ�͑�O���狑�ۂ����B���������ю�ς́A�J�R�����́w��u����\�Z�Ӟ��x�̒��ɖ��Ăɂ����������Ƃ��ł���B�u���̊ю��嫂����@�ɑ��Ⴕ�Ė��`���\���ΔV��p���ׂ��炴�鎖�v�i��S�P�[�X�W�j�u�O�`�����嫂����@�ɑ���L��Ίю�V��F���ׂ����v�i��S1�|�X�X�j�B�܂��������@��̉��ł̊ю咆�S��`�ł���B�u�˖@�s�ːl�i�@�Ɉ˂��Đl�Ɉ˂炴��j�v���ю咆�S��`�̉������ƂȂ�B
�@��Ԗڂ́u�ю吒�h��`�v�ł́A�ю�́u�M�S�̌����v��������������A�u�ю呦���@�v�̉��V����������B���̗���ł́A�ю�̑������̌��́u�M�S�v�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ŁA�����Ă͖剺�̑m�����M�S����Łu�����@�v�Ƃ����B�܂��A�����Ă͂Ȃ�Ȃ��͂������ю�̐M�S�����炩�ɋ������Ƃ݂Ȃ����A���h�̑Ώۂł͂Ȃ��Ȃ�]�n���c����Ă���B���̏ꍇ�́A��ɂ������w���r�u���x�́u���̊ю��嫂����@�ɑ��Ⴕ�Ė��`���\���ΔV��p���ׂ��炴�鎖�v���@�\���Ă���ƌ�����B���̊ю吒�h��`�̗�́A9���E���L�̎t�푊�ΐ���ю�㊯���ł���B
�@�Ō�́u�ю��Ύ�`�v�ɂ��ẮA���͂�����̗v���Ȃ��B�ю�́A�B����l�������邱�Ƃɂ��A���V�ʂ݂̂Ȃ炸���ؖʂł��u�����@�v�Ƃ����B���ؖʂŖ{���ƈ�̉�����킯������A�ю�̏@���I���Ђ͐��ł���A�嗬�̑S�m���͊ю�̓��ɑ��Đ�Ε��]��v�������B�����ł́A�w���r�u���x�́u���̊ю��嫂����@�ɑ��Ⴕ�Čȋ`���\���ΔV��p���ׂ��炴�鎖�v�Ƃ�����ڂ��ю��Ύ�`�I�ɉ��߂���A�u���@�ɑ��Ⴕ�Ă��邩�ǂ��������肷��̂͊ю厩�g�ł���v�ȂǂƎ咣�����B�������A�����������߂������A�{��ڂ͎����I�ɋ@�\���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����炩�ł���A���̓����̈���̂����Ӗ��ƂȂ낤�B
�@�{�e�ł݂Ă����悤�ɁA�ΎR�̊ю��Ύ�`�̋N���͍��������̋��w�v�z�ł���B�����A�����ɂ��ẮA�ю�́u�M�S����v�̏���{���Ƃ��A��k���ю���t�Ƃ��ĐM�S�ɗ�ނ��ƂŖ{���ؓ��������A�Ɛ��������肪��̊ю吒�h���`�ɒʂ��Ă���B���̂悤�Ɋю吒�h��`�I�Ȗʂ��c�����A�ю�̐M�S�����O��Ƃ���u�����t���̊ю��Ύ�`�v�́A�~�s�I�ɂ��Ă͂߂��31���E�����A33���E�����A3���E�����A43���E�������ɂ��݂���悤�Ɏv���B
�@�����A�^�Ɂu�������̊ю��Ύ�`�v���Ƃ�_�҂Ƃ��ẮA�ߐ��̖@�َ������⌻��̈��������̖��������Ă����ׂ����낤�B�ނ�͊ю�̐M�S�s�̂��d�����邱�ƂȂ��A�Ђ����猠�Ў�`�I�Ɂu�ю呦���@�v�u�ю呦�{���v�̋`��������B�u�˖@�s�ːl�v�Ƃ͐����́u�ːl�s�˖@�v�ł���A�����܂ŗ���Ί��S�ɏ@�J���c�̋����Ɉ�w���Ă���ƌ��������Ȃ��B
�@��Ύ��ю�̓����I�n�ʂɊւ��ẮA�����̂��Ƃ��l�X�ȍl�������������B���j�I�ɂ́A�Ζ���̊ю咆�S��`����ю吒�h��`�����܂�A����Ɋю吒�h��`��w�i�Ƃ��āu�����t���v�������́u�������v�̊ю��Ύ�`�����ꂽ�悤�ɂ݂���B�������A����͉E�̏��Ԓʂ�ɗ��ю�̗��ꂪ�ϑJ���Ă����Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B
�@�d�v�Ȃ̂́A��Ύ��̊ю�ς��߂���_�c�ɂ����āA�����̗��ꂪ������������Ă���Ƃ��������ł���B�Ⴆ�A�����@���@�́u�������̊ю��Ύ�`�v��ᔻ���錾�ɑ��A���@�����u�ю咆�S��`�v�u�ю吒�h��`�v�u�����t���̊ю��T���`�v��������j����p���Ĕ�������A�Ƃ��������Ƃ��悭����B
�@�Ȃ��A�����ɂȂ邪�A��Ύ��ю�̗��j�I������߂����X�̍�����h���ɂ́A�ю吒�h��`�̎��_���L���ł���悤�Ɏv����B�Ⴆ�A���ؖʂ̎O���̂�_����ہA�����ɗ��ю���܂߂�ׂ����ۂ����悭���ƂȂ�B�ю��Ύ�`�҂́u���ׂĂ̊ю�̓�������E�@��ƈ�̂ł���v�ƌ������邯��ǂ��A�s�@�̊ю�������Ƃ������j�I�����ɂ͔�����B����ɑ��A�u�M�s�@�@�̊ю�ɂ͓��ؖʂ̎O���̂�F�߂�v�Ƃ����ю吒�h��`�̎��_���Ƃ�A���j�I�����Ƃ��Ă̑�Ύ��ю�̈Ӌ`���悭�����ł��邾�낤�B�ю�Ɍ��炸�A�������M�S���т����������l�̓����A�{���E�{�@�ƈ�̂Ȃ͓̂�����O�̂��Ƃł���B���ɁA�s�@�̎҂͊ю�Ƃ����ǂ��m��Ƃ͌ĂׂȂ��B���������]����̋�ʂ��\�ɂȂ�̂́A�����Ƃ��Ċю�̎���ł���B���܂��M���H�̓r��ɂ��錻�݂̊ю�Ɋւ��āA���ؖʂ̎O���̂������̂͑��v��掂��Ƃ�Ȃ��B�܂��Ă�A�N�̓��ɂ����炩�Ȍ֖@�s�ׂ�Ƃ��Ă��錻�݂̊ю�̓����O���̂Ƃ݂Ȃ��̂́A�ю吒�h��`�̕����ȊO�̉����ł��Ȃ��낤�B���̂Ƃ���A�������̊ю��Ύ�`�͊ю�𐒌h���Ȃ��B�����́A���̊ю�M�̃p���h�b�N�X�ɋC�Â��K�v������B
�@�M�҂������Ŏ������ю�ς̎O�ތ^�i�ׂ��������Ύl�ތ^�j�͈ꉞ�̉����ł���B�����A����Ɍ����K�i�ȕ��ނ��Ȃ����ƂƂ��ɁA��Ύ��̊ю�ς̗��j�I�ϑJ���𖾂���邱�Ƃ��肢�A�ٕ��𝦕M�������B
�@
�@
�@
���ǂ�
�@
�@
�@
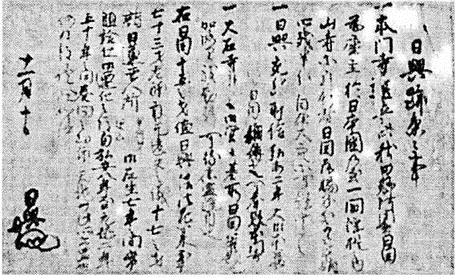 �@��Ύ��̏t�̒������@�v�̍ہA�w�����՞��X���x���ю�̎�ɂ���ĎQ��҂ɔޘI�����B�����k�������s�����w������l�S�W�x�ɂ́A���̒�������̐܂ɎB�e���ꂽ�Ǝv����w�����՞��X���x�̎ʐ^���f�ڂ���Ă���B������݂�ƞ����̂ŏ�����Ă���A�����̎����E�ԉ����݂���B�N�����L�ڂ���Ă��Ȃ��_�����s�R�ł��邪�A�̍قƂ��Ă͐��{�ƍl������B���@���@�O�ǒ��̈����������A���@�̋��w�������������Ɂu���������ɁA�e�����������I�Ȃ����܂����c�c���K�̓����A���ڏ�l�ւ̏����ɂ́c�c�w�������g�Ɉ��ĂĎ��鏊�̍O��2�N�̑��{�\�A���ڂɔV�����^���B�{�厛�Ɍ������ׂ��x�Ƃ������̌䕶�������ł��ˁv�Ɣ������Ă���B
�@��Ύ��̏t�̒������@�v�̍ہA�w�����՞��X���x���ю�̎�ɂ���ĎQ��҂ɔޘI�����B�����k�������s�����w������l�S�W�x�ɂ́A���̒�������̐܂ɎB�e���ꂽ�Ǝv����w�����՞��X���x�̎ʐ^���f�ڂ���Ă���B������݂�ƞ����̂ŏ�����Ă���A�����̎����E�ԉ����݂���B�N�����L�ڂ���Ă��Ȃ��_�����s�R�ł��邪�A�̍قƂ��Ă͐��{�ƍl������B���@���@�O�ǒ��̈����������A���@�̋��w�������������Ɂu���������ɁA�e�����������I�Ȃ����܂����c�c���K�̓����A���ڏ�l�ւ̏����ɂ́c�c�w�������g�Ɉ��ĂĎ��鏊�̍O��2�N�̑��{�\�A���ڂɔV�����^���B�{�厛�Ɍ������ׂ��x�Ƃ������̌䕶�������ł��ˁv�Ɣ������Ă���B