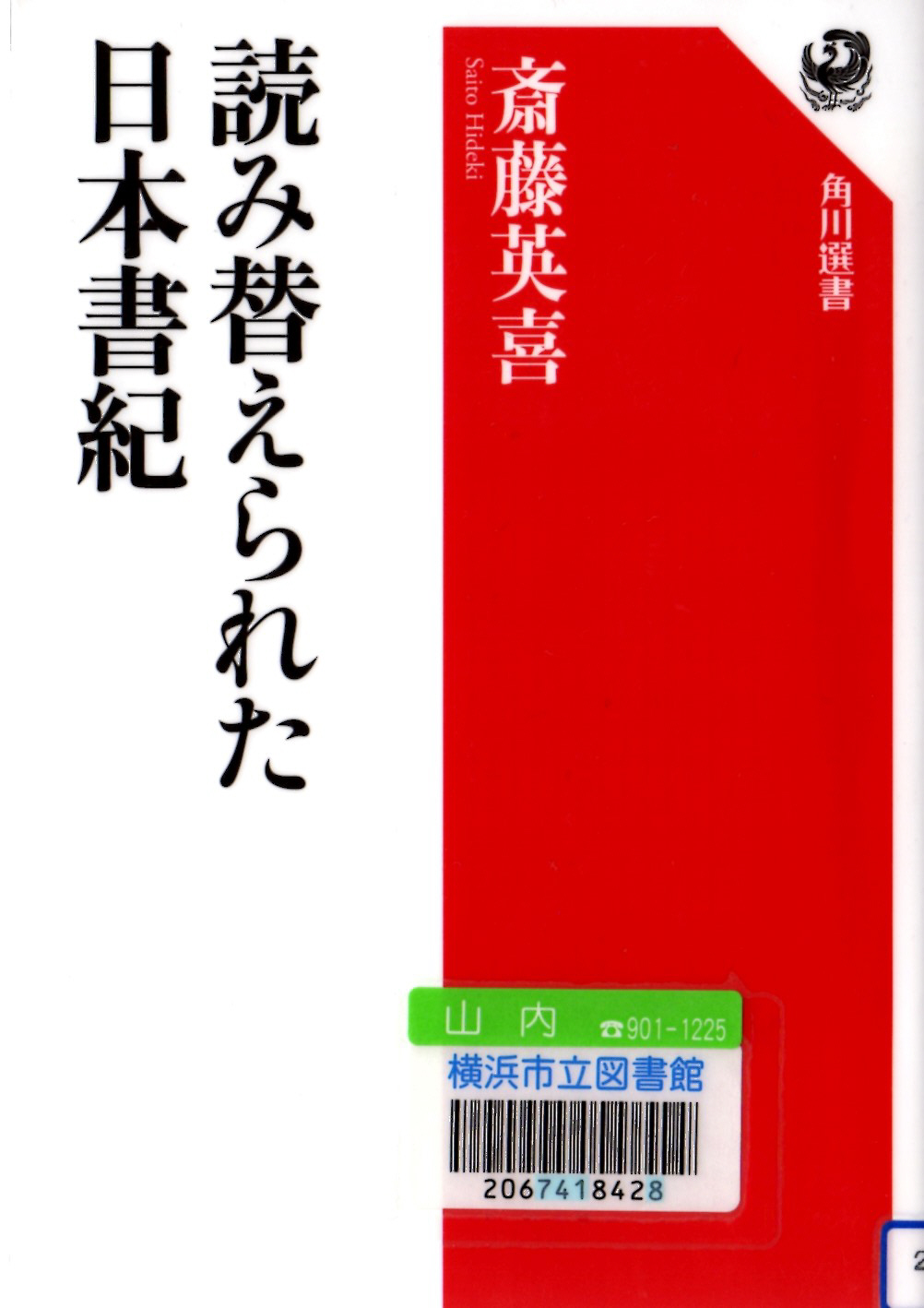
プロローグ 『日本書紀』 13000年紀にむけて
『日本書紀』成立1300年
遠い遥かな天地の始まりから、神々の誕生、彼らが活躍する神話物語、そして初代の神武天皇から7世紀後半までの持統天皇の事蹟と歴史を記す書物――『日本書紀』。
古代国家の正史とされた、この書物は、舎人親王をリーダーとする編纂プロジェクトチームによって、奈良時代初期の養老4年(720)5月に完成し、時の帝元正天皇に献上された。そして本年、令和2年(2020)は、『日本書紀』が成立して、1300年を迎えた年である。
ところで、古代日本には『日本書紀』と並び称される、もうひとつの史書がある。そう、『古事記』だ。『日本書紀』よりも8年前、和銅5年(712)に太安万侶が撰録し、元明天皇に献上された『古事記』は、平成24年(2012)に、成立1300年を迎えた。
「古事記1300年」の年は、『古事記』に関する図書が多数刊行され、博物館などでの企画展示、多数のイベントなどが繰り広げられて、多くの人たちが『古事記』に関心を寄せ、「古事記ブーム」が起きたほどだ。それに比べて「日本書紀1300年」の今年は、残念ながら、世間一般の関心は薄いようだ。『古事記』のときのような盛り上がりには欠けるように見える。『古事記』に比べ 『日本書紀』には人気がない……。
その理由はいろいろ考えられる。なによりも『古事記』は、中国文化の影響を受けていない、古層の日本を伝えていると認識されたことが大きい。そのことを喧伝したのは、汪戸時代の国学者・本居宣長だ。彼が、35年の歳月をかけて執筆した『古事記』の注釈書『古事記伝』によって、正史の『日本書紀』よりも「古事記」のほうが「皇国の古人の真心」を伝えていることが明らかにされた。たとえば父帝に疎まれながら、果敢に戦った悲劇の皇子・ヤマトタケルの物語は、『古事記』にのみ伝えられたと説くことで、『古事記』の魅力を世間に広めたのである。
ここから『古事記』は、「日本人の心」の原点とされ、成立1300年紀のときは、失われた日本への自信を取り戻そうとする動きや、さらに平成23年(2011)3月11日の東日本大震災によって傷ついた日本の復興、再生と結びつけられたのだ。
このように現代にあっては、『古事記』のほうがポピュラーな轡物として人びとに受容され、読まれている。たしかに文学的にも『古事記』のほうが面白い。因幡の白兎を助けるオホクニヌシの神話や悲劇の皇子ヤマトタケルなど、物語的にも魅力があるだろう。
けれども、日本の歴史全体を見渡したとき、じつは『古事記』よりも『日本書紀』のほうが圧倒的に長い時代にわたって読まれ、受容されてきたのである。
たとえば『古事記』の一番古い写本は南北朝期にまで遡れないが、『日本書紀』のほうは、断片的ながら平安時代初期の写本が現存している。また版本(刊本)となって世間に出回るのも、『古事記』は江戸時代中期の寛永21年(1644)だが、『日本書紀』のほうは関ヶ原合戦の前年、慶長4年(1599)には刊行されている。
さらに注釈、研究についても、『日本書紀』は平安時代初期から朝廷主宰で講義が行われ、早くも注釈、研究が始まっていた。ちなみにその場で『古事記』は、『日本書紀』を読むうえでの参考書のひとつ、として扱われていた。したがって、今のように『古事記』がメジャーな本になったのは、18世紀の本居宣長のおかげ、といってもいいぐらいだ。もちろん、そうはいっても、宣長以前に『古事記』が読まれていなかったわけではない。
このように見ていくと、現代における人気度は圧倒的に『古事記』が高いが、歴史的には、『日本書紀』のほうが、長く読み継がれてきたことは、間違いないのである。それにもかかわらず、『日本書紀』の受容、注釈、研究の歴史は、一般に知られていないことも、たしかであろう。
はたして、奈良時代初頭に成立した『日本書紀』は、1300年にわたり、誰がどのように読んできたのだろうか。1300年にわたる「日本書紀」受容と研究の歴史とは――。
本書は、その知られざる1300年の歴史に迫っていくものである。
「中世日本紀」とはなにか
『日本書紀』の1300年の受容史のなかで、ひとつのブラックボックスになっていたのが、鎌倉時代から南北朝、室町、戦国時代へと至る「中世」の時代である。天皇・朝廷にたいして幕府というあらたな権力が創出され、朝廷と幕府は対抗しつつも、互いに補い合うような関係のなかで列島社会を支配し、しかしやがて各地にあらたな勢力が跋扈、割拠していく戦乱の時代。また神々への信仰よりも、仏教が人びとの救済を担い、寺院が大きな権力を有した時代――。そうした中世にあって、『日本書紀』は、誰が、どのように読んできたのだろうか。
たとえば戦後の歴史学を牽引し、教科書裁判を闘ってきた家永三郎(1913〜2002)は、中世には数多くの『日本書紀』の注釈書が作られたが、それらは「古紀の学問的研究のために今日読むに値するものは一つもない」と全面的に否定している【永・1967】。なぜか。中世に作られた夥しい数の『日本書紀』の注釈書は、当時の神道家たちが、自己の神道説を喧伝するために『日本書紀』を曲解し、空理空論を展開したにすぎないと、家永はいう。中世の神道家たちが作った注釈書類を否定するのは、戦後歴史学が、戦前の国家神道や皇国史観の復活に対抗し、歴史の真実を追求しようとしてきたことと通じる発想ともいえようか。その根柢にあるのは、科学的、近代的な文献王義、文献史学の論理である。
けれどもそうした認識は、ひとつの論文の出現によってひっくり返った。1972年に発表された、中世文学研究者の伊藤正義の「中世日本紀の輪郭」(『文学』1972・10)という論文だ。この一篇の論考が発火点になって、阿部泰郎、伊藤聡、小川豊生、原克昭、山本ひろ子といった、中世文学、思想史の研究者たちによって、中世の『日本書紀』注釈への評価は180度逆転したのだ。そこからは、次のようなあらたな視点が開かれた。
中世びとたちの『日本書紀』を読む態度は、われわれ近代人とは違う。彼らにとって注釈することは、『日本書紀』の原典を理解するための補助的な作業ではなかった。当時の最新の信仰、学問、知識である仏教や儒学(宋学)、道教、陰陽道などを使って注釈することで、原典の『日本書紀』とは異なる、彼らが生きている中世にふさわしい「日本紀」を再創造することにあった。そしてその「日本紀」は、中世の人びとにとっての、あらたな神話として広がっていく。これを「中世日本紀」、または「中世神話」と呼ぶ(なお、現在では『日本書紀』の名称が一般的だが、古代、中世では『日本紀』と呼ばれた)。
変貌する神々の世界
それにしても、「中世神話」という用語には、多くの読者は戸惑うかもしれない。一般に「神話」といえば、古代のものと相場は決まっているからだ。また古代以降に「神話」が作られた場合は、それは古代神話の亜流、二次創作、偽作といった否定的な扱いを受けてきた。とりわけ近代における国家神道と結びつく神話は、天皇制を妄信させるものとして否定・批判されるものであった。民衆支配のイデオロギーとしての神話という認識である。
しかし、1970年代以降に展開した「中世神話」「中世日本紀」の研究は、そうした神話そのものの概念をも変えていったのだ。
では「中世神話」とは、どんな神話なのか。詳しくは本書のなかで見ていくが、ざっと概要を紹介しておこう。たとえば『記』『紀』のなかで、イザナキ・イザナミの最初の子どもでありながら、足が立たなかったために流し捨てられたヒルコという神がいる。古代神話のなかでは、流されたヒルコのその後は、まったく出てこない。しかし中世にあっては、流されたヒルコは、龍宮城の龍神に育てられ、また西宮に流れついて恵比須として再生・復活してくる。
あるいはスサノヲといえば、荒ぶる神でありながら、出雲のヤマタノヲロチを退治する、魅力的な英雄神だ。しかし、中世にあっては、高天原から追放されたスサノヲは、出雲の国を固め作っていく神であり、出雲大社の祭神として祀られていた(『記』『紀』によれば出雲大社の祭神はオホクニヌシ〔オホナムヂ〕である)。あるいはスサノヲの本当の姿は、地獄の閻魔王であるという言説も生まれる。またスサノヲは、京都の三大祭りとして有名な祇園祭の祭神として、祇園社(現在の八坂神社)にも祀られていくことになる。
一方、天皇家の皇祖神であり、伊勢神宮に鎮座する太陽の女神アマテラスは、中世にあっては、仏教の敵、第六天魔王と対決し、魔王を欺いて、日本に仏教を広めていく神とされた。また密教の最高尊格の大日如来と合体し、さらに衆生の苦を代わりに受ける、蛇体の神として、秘かに伝えられていく……。
さて、いかがだろうか。『古事記』『日本書紀』の古代神話に慣れている読者の目からは、まったくトンデモ本のような、奇妙奇天烈な神話世界と思われることだろう。荒唐無稽な二次創作とみなされるかもしれない。しかし、奇妙な二次創作のような中世神話の世界の多くは、中世の人びとが、『日本書紀』を研究、注釈するなかから生み出したものなのだ。中世びとたちは、こうした中世神話のことを「日本紀」と認識したのだ。
そして中世にあって『日本書紀』を読み替え、中世独自な神話を創造していったのは、神祇官の伝統的な祭祀一族の卜部氏であり、また皇祖神アマテラスを祀る伊勢神宮の神官たち、あるいは藤原摂関家の貴族知識人たちであった。さらには真言や天台の仏教僧侶たちもまた、担い手になったのである。
時代の転換期のなかで
中世の『日本書紀』注釈が展開し、発展していくのは、蒙古襲来や南北朝の動乱、あるいは応仁・文明の乱が起こり、時代が激勤し、転換していくときであった。日本があらたな「国際社会」との関係のなかに巻き込まれ、あるいは「天皇」という権威そのものが分裂し、また中世の朝廷・幕府の権力が相対化されて、地方の地域社会の独自性が強められ、列島社会全体が、それまでとは異なる様相を呈していく時代。そうした歴史変動のダイナミズムと『日本書紀』注釈とは、密接なかかわりを持っていたのではないだろうか。
そもそも8世紀に成立した『日本書紀』もまた、7世紀後半の壬申の乱に勝利した天武天皇による、国家秩序の形成と不可分にあった。そこで形成されていく「律令国家」というあらたな現実と、それを支配していく「天皇」という存在の由来、起源を語ることが日的であった。神話とは、つねに、今目のまえにある現実が、なぜ始まったのか、その起源を解き明かす想像力をもたらすのである。
ここからは、次のように考えられよう。中世日本紀、中世神話とは、古代国家とは異なる、あらたな中世の国家、天皇のあり方の由来、起源を解き明かすことが目的であった。それが神話であるとき、「日本紀」というネーミングが必要とされたのである。そして新しい現実を意味づける神話は、また同時に、時代の現実を超え出て、それを変えていく想像力や知をもたらしてくれるだろう。
こうした視点にたったとき、1300年にわたる『日本書紀』の受容・注釈、研究の歴史とは、その時代にふさわしい、「神話」を創造していく過程であったという展望が開かれてくるのである。したがって、本書では「中世」を起点にして、古代へ、さらに近世、近現代にあって、『日本書紀』がどのように受容され、読まれていったのか、そしてどのような神話が渇望されたのかを考察しながら、1300年の歴史を見通すことをめざしたい。
本書の構成と目的
さて、本論に入るに先立って、本書のおおまかな流れを紹介しておこう。まずは焦点となる中世における『日本書紀』注釈の世界から出発し(第1章)、さらに戦乱の時代に読まれた『日本書紀』(第2章)、平安時代に遡って朝廷主宰の『日本書紀』講義である「日本紀講」とその周辺の世界(第3章)、一方、中世からの飛躍、断絶を會む近世社会に繰り広げられた『日本書紀』注釈の世界に転じ(第4章)、そして明治維新によって作り出された「近代日本」にとっての『日本書紀』の解釈、研究のあり方を、「国家神道」や「国体」観念の形成とともに、西洋学問との影響、競合という緊張関係のなかで形成される歴史学、国文学、民俗学、神話学、神道学という諸学のなかから探っていく。さらに敗戦を契機とした戦後学問が、どのように『日本書紀』を読んできたのかを探り(第5章)、その最新の『記』『紀』研究を踏まえ今っえで、八世紀において、なぜ『日本書紀』は作り出されたのか、『古事記』とのかかわりとともに、その成立の現場へと分け入っていく(第6章)。
以上のような本書から何が見えてくるのだろうか。それは『日本書紀』という書名にある「日本」そのものの認識が、古代以来、一貰してはいなかったこと、それが時代のなかでいかに変容していくものであるかが、『日本書紀』の受容、注釈、研究の現場から浮かび上がってくるのである。現在、われわれが「日本国民」として所属している「日本」なるものの自己認識が、じつは1300年にわたる歴史の激動のなかで、つねに更新し、変貌してきた、ひとつの結果としてあることが見えてくるはずだ。
さて、それではさっそく第1章へと進行ことにしよう。まず立ち会うのは、モンゴル軍が襲来した、未曾有の時代のただ中である。
あとがき
それにしても「日本書紀」は運が悪い。ただでさえ「成立1300年」の話題は、世間的にはバッとしなかったのに、数少ない高演の企画や講座などのイベントも、新型コロナウイルスの猛威によって、ほぽ吹き飛ばされてしまった。まったく間が悪い『日本書紀』だ。
そんななかで、山下久夫さんと共編で『日本書紀1300年史を問う』(思文閣出版)を刊行できたのは幸いであった。ただこの本は、あくまでも専門研究者向けの論文集なので、やはり、もっと広い読者を対象とした、『日本書紀』 1300年の通史本が必要だろう、ということで、本書の執筆となったのである。4月以降の大学の授業は、すべてオンライン、リモート授業となってしまい、まったく初めての経験で大いに戸惑いながら、また外出自粛という、なんだか引き託りのような生活が続くなかで、ひたすら執筆に専念するしかなかっだ。そんななかでの「成果」が本書、ということになる。
けれどもあらためて考えてみると、『日本書紀』が編纂されて1300年目という年は、21世紀の世界が初めて経験したコロナ禍の年でもあった、というように記憶されることになるだろう。本書が、この時代を生きた人びとの「記憶」作りの手助けになれば、これに越したことはない。
さて、本書は、『日本書紀』が編纂された8世紀初頭から、21世紀の現在まで、この書物が、誰に、どのように読まれてきたのか、ということを通史として記述したものだ。だが、本の構成としては、中世から始まり、平安期の古代へ、そして近世、近代、現代へと展開し、最後に、『日本書紀』が成立した8世紀に至る、という変則的な語り方になっている。
なぜ、中世から始まるのか――。すでに本書を読んでいただけた方にはわかってもらえると思う。『日本書紀』がどう読まれてきたか、というのは、けっして受け身的な受容、享受の行為ではなく、『日本書紀』を「読む」ことは、「読み替える」ことであり、その読み替えを通して、時代固有な「神話」を生み出すことであっだ。そのことをもっともラディカルに実践してきたのが中世という時代であっだ。だから『日本書紀』 1300年の歴史を見ていく本書は、「中世日本紀」「中世神話」と名付けられた、もっともスポットライトを当てるべき時代の現場からスタートしたわけだ。
そして『日本書紀』を読み替えて、新しい神話を創造する行為が、けっして中世だけに限られたことではなく、じつは近世、近代、現代にまで貫通する、知の実践行為であっだこと、そしてその視点から、「日本書紀」成立の8世紀をも読み替えていくことになった。
本書が記述する「通史」とは、そんな歴史の読み替えでもあったということになるだろう。
さらに、『日本書紀』の1300年の歴史を通して、あらためて思い知るのは、それぞれの時代を生きる人びとの神話への渇望ではないだろうか。その神話への思いは、エピグラフに引用した、ドイツ・ロマン派のフリードリヒ・シュレーゲルのいう「精神の最も奥深い深み」からのもの、あるいは第6章で引用した政治思想史家の橋川文三が述べた「歴史の危機的転換期」を生きる人びとの「内奥」を捉えて離さないもの、ということになろう。『日本書紀』 1300年史を記述してきた本書は、まさしく、今われわれが体験している「歴史の危機的転換期」における、あらたな「神話」の探究でもあった、ともいえようか。