

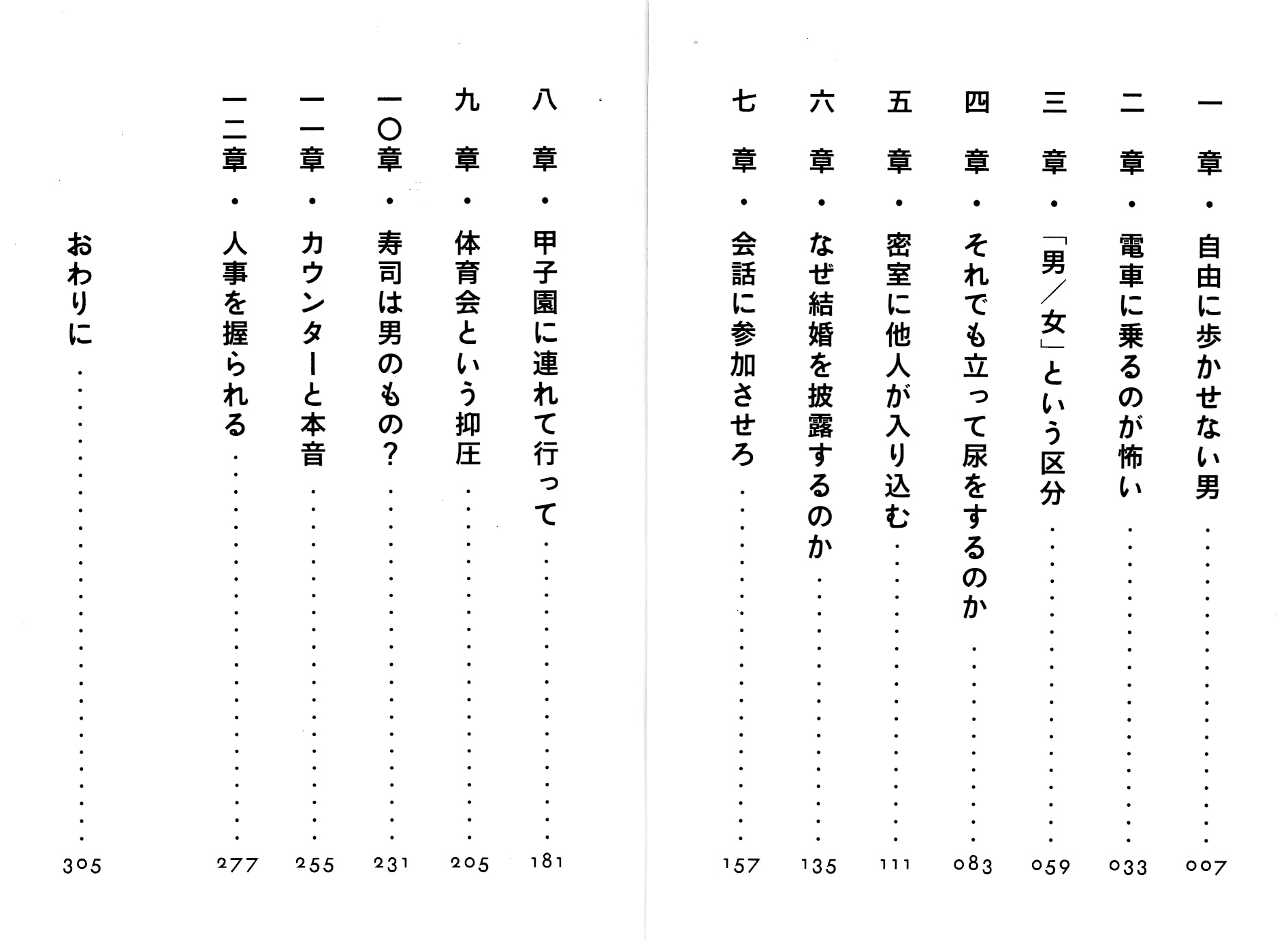
おわりに
ジェンダーについての問題が取り抄汰されると、問題を起こした主体への疑問や苦言を、 「でも、自分にだってそういう一面があるし・・・」などと言いながら、引き下げてしまう光景を見かける。どうしてそうなっちゃうかな、と思う。そういう一面を確かに感じながら、自分なりに受け止めながら、その上で疑問や苦言を投げることは許されないのだろうか。この本を書きながら、何度もそう感じた。
痴漢を問題視すると、「あたかも男がみんな痴漢みたいな扱いをするな」と怒る人がいる。そんなこと誰も言ってない。あなたを指差しながら問題視しているわけではない。
[男性]が批判されると、こうして、すぐさま、個人の領域に踏み込まれた、と嫌悪する人がいる。なぜ自分が「男性」を代表しているのだろう。もしくは、「男性」という枠組みはどこかで一蓮托生だと思っているのだろうか。
個人として考える。個人の経験を振り返る。社会の問題として捉える。この社会の将来のために問いかける。これらはすべて連動している。同時に、すべて異なるものである。
日々、切り替えながら考え、そして重ね合わせながら考えてきたはず。それなのに、本書で取り上げた「マチズモ」の場面では、なぜか、ものすごく適当に一緒くたにされてきた。男性個人として考える。男性個人の経験を振り返る。社会の問題としてジェンダーを捉える。この社会の将来のためにジェンダー平等を問いかける。個人で考えて、考えを重ね合わせていく。これができない。「なんか最近、ちょっと言うだけですげー叩かれるじやん]。こんな感じで、身勝手に、ひとつの塊にしてしまう。結果、社会に残る理不尽を見つけ、ひとつずつ問題点を指摘し、その改善の道を探っている人たちの取り組みを軽視してしまう。
社会の構造上の問題点を指摘されただけで、男性の自分が悪いと言われたと苛立ってしまうのは、社会は男性が動かすものだと思っているからなのだろうか。別にあなたのことを言っているわけではないのに、なぜかあなたが怒り始めたという場面を、よく見かける。その一方で、この話題は自分に関係ないからどうでもいいや、と声に出さない人も多くいるのだろう。私という個人は社会ではないが、社会は個人の集積である。ジェンダーにまつわる問題を前にすると、自分も含め、社会を生きる男性という個人の多くがバグつてしまうのはなぜなのか、との疑問があった。国家権力を根気強く追及する物書きでも、日常で起きたちょっとしたエピソードを柔らかく丁寧に書く物書きでも、その手の問題になると、「なんか最近、ちょっと言うだけですげー叩かれるじやん」で終わらせようとする。いつものしつこさや慎重さが吹っ飛ぶのだ。
個人として、当事者として、第3者として、社会の問題を考えるとは、どういうことなのか。ジェンダーについての問題で、とりわけ男性が問いに答えようとしてこなかった。この本が回答だ、とは思わないが、回答しようとするプロセスを複数盛り込んでみた、とは言える。様々な場に出かけ、多くの人に話を聞き、マチズモの在り処を探し当て、こびりついた問題点を削り取る作業を繰り返すと、社会の問題と自分の問題が浮き上がってきた。それらは、混ぜる前のドレッシングのように分離していたり、あるいは混ぜた後のドレッシングのように境目がなくなったりする。どちらが重要、こっちのほうが問題、ではない。どちらも重要で、どちらも問題である。混ざる前の「個人」と混ざった後の[社会」、その両方を考えないと、すぐに「なんか最近、ちょっと言うだけですげー叩かれるじやん」が顔を出す。あれが出ると、世の中の構造はそのままになる。
政治家の女性蔑視発言が問題視されると、①発言の全体を読めばそんなことはない、②仲間内で言っただけ、③男性蔑視はスルーするくせに、④発言は確かに問題だけどこれで彼のキャリアを潰してもいいのか、といった擁護が並ぶ。この4種類が必ず並ぶのだ。共通項はなんだろう。「この社会はやっぱり男が勣かすべきだ」という前提の保持ではないか。それくらいのことで・・・なんて言う。それくらいがどれくらいかを決めるのは、その蔑視を受けた側であるべきだが、投げつけた側に乗っかり、とにかく矮小化する。小さく見せる。
マチズモと聞けば、力ずくで突破するイメージが頭に湧くだろう。駅構内で女性だけを選んでぶつかる男性など、あからさまなものもあった。しかし、この社会に残存するマチズモは決して強い力が露出しているとは限らず、もっと、せせこましい、できればこのままバレずにいてくれれば、自分たちは心地よくいられるのに、という類いのものも多かった。
「問題だとは思うけど、自分たちの心地よさを保ちたくって」という内心が、「問題だとは思うけど。別の問題もあるよね」という回避につながる。男性である書き手の自分が、主に男性の問題であるマチズモを考察する、という型にとらわれすぎた部分もあったかもしれない。しかし、その型に体を押し込めることによって、壁の固さや、意外なところに空いている通気孔や、そこにいる人の鼻息を感じられた。この本に解決策が並んでいるわけではない。全体像を提示できたわけでもない。でも、削るならここからだな、という問題をいくつも突き出せたのではないかと思っている。自分には関係ない、ではない。もう関係しているのだ。それを知らせたかった。
読んでいただいた方にはおわかりの通り、本書は、編集者Kさんの怒りがなければ、始まりもしなかったし、終わりもしなかった。打ち合わせをする度に、「砂鉄さん、こないだの○○の○○、あれ、本当に○○だと思うんですけど」と、正確には文字に起こさないほうがいい言葉を駆使しながらぶつけてくれたからこそ、この本ができた。Kさんの怒りと私の怒りを混ぜ合わせ、今、そこに残っているマチズモを捉えていく作業は、古い価値観を壊し、新しい価値観を構築しようと試みる作業になった。視界が広くなった感覚を何度も得た。皆さんにもその感覚がお裾分けできていれば嬉しい。ということで、最後に、編集者Kさんこと岸優希さんに感謝します。ありがとうございました。
2021年5月
武田砂鉄