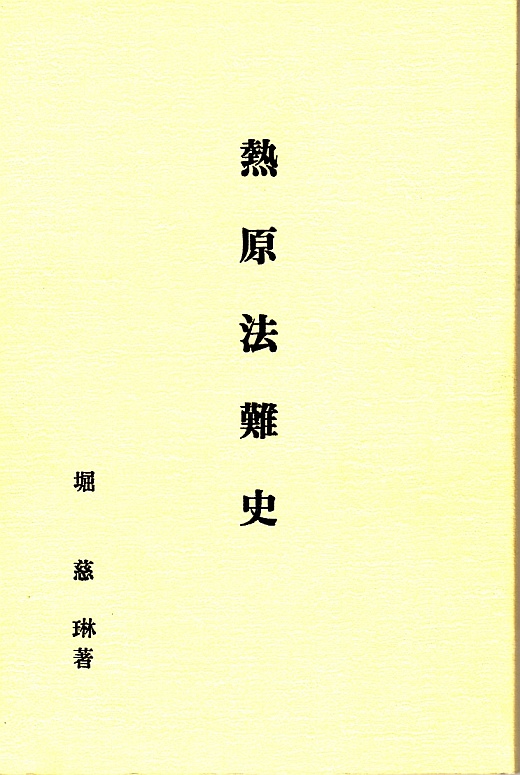�@
�@
�@
�@
���@�s�@�́@�Ӂ@��
���ꂩ����@���@���w�p�������s���邱�ƂɂȂ�܂����B���e�́A�@�|�Ə@�`�ƍs�̂Ǝߋ`�ƌP�b�ƂŁA����������҂��o�����l���ł��B�M�́A�����͎�������܂����A�������͑��t�ɍ��������Ŗ{���𑑌��q�����r�邱�Ƃɂ��܂��B���̊�ẮA�L��A�����̏@��Ɋ��s���̏�����₤�āA���@�吹�l�̌䐳�`���Ȃ�ׂ��āq�Ђ�r���O�߂�Ƃ̔O��ł���܂��B���������ēǂ݁A�l�ɂ��ǂ܂��邱�ƂƁA�悭�ǂ�ŐM�s�̗ƂƂ��Ă������邱�ƂƁA�P���ɍS�͂炸�����Ȃ��ᔻ�����Ă������邱�Ƃ�]�݂܂��B������A���̗͂Ƃ��ė�݂Ƃ��Ă��̑��𐬏A�������Ǝv���܂��B
�吳11�N7���@��
��R���[��l
�@
�M���@��j�̂͂�����
�@���@���@���w�p���̑�2�҂Ƃ��āw�M���@��j�x�s���܂��B����́A�j�k�ƔN���Ǝj������ƌÓ`�W�^�̏W���ł����A���̎j������́A���āw���@�x����Ɉ�N�]�ɘj��Čf�������̂��A����ɒ��J�ɏC������������̂ŁA���Ȃ荜���܂�Ă���܂����A�{�j�̊�ڂ��A��͂肱�̎j������ɂ���āA�j�k���N�����Ó`�̔ᔻ���F���ꂩ��o�Â�̂ł���B
�@�������A�e����ɂ����ꂼ��̓����������Ă���B���Ȃ킿�A
�@��C�ɑS�ǁq���ׂār�����悤�Ƃ���ɂ͎j�k���A
�@��ڂ��Ď��ցq���Ƃ���r��N���ɒm�낤�Ƃ���ɂ͔N�����A
�@�T�`�q����܂�r��r���Đ��`�q���������r���ς����m���q�������r�ɒm�낤�Ƃ���ɂ͎j��������A
�@�Ó`�̐^�U�q���r�̒��x�q�قǁr��m�낤�Ƃ���ɂ͏W�^�̏㗓�q���傤���r�̔ᔻ���A
�䗗���������B�������āA�j�k�ƔN���Ɖ���Ƃ��A�Í������̓`���Ƒ傢�ɐ�q����r���فq���Ɓr�ɂ��Ă�Ƃ��ɂ́A���ə��ځq�������r���ďn�ǂ��Ă��������B
�@�܂��A���p�̕����́A�����̂̂�ĉ����ɂ�����A���q���ׁr�Č��Ղ����܂����B
�@�Ō�Ɍ�肢����̂́A���̏��q�ق�r���䗗��������l�́A���̂��ߐ_�̂��ߕ��̂��ߌN�̂��ߐl�̂��߂Ƃ��āA���@���l�̋�����āA�S��𗽁q���́r����������l���G��l���ُ�l�̕����A�Áq���r���ċ����̂��Ƃ��Ȃ�M�̌��������q���{�ɝ��q�����r���Łq�r���đ����q������r�̊́q�����r��D����_�l�Y���̑s���A�[��������Ă��������B
�@
�@�@�@�吳11�N10���@��
�x�@���@�@�ԁ@���邷
�@
�@
�@
�ځ@�@�@��
�P�A�M���O���̔��[�@�t�@�������y�юl�\��@�̎�
�Q�A�G�E�فE�T�O�t�̝��o
�R�A�_�l�Y���̓��M
�S�A�s�q�E�퓡���̌���Ƒ�i�E�O�ʖ[�̔�����萔�x�̔��Q
�T�A��̑化�܂ɐM�k�̌��{���20�l���q�ɏ����グ���
�U�A���G�E���ق̑i��y�ъ��q�̒f��
�V�A�@��̗]��
�W�A�M���@��j�W�N��
�P�A�M���O���̑�̂ɂ��Ă̌䏑�y�щ��
�Q�A���n�[�E�O�ʖ[�ɂ��Ă̌䏑���
�R�A��i�[�ɂ��Ă̌䏑���
�S�A�@��^���ɂ��Ă̕������
�T�A���G�E���ى����ɂ��Ă̌䏑���
�U�A�@���̎��ǂ��ɂ��Ă̕������
�@
�@
�@
���̖@��̂��Ƃ�������V�������̂���R���邪�A���ɂ͐��������t��ˋk�q���������������r�ɗ���Ă�̂�����B�����͐��j��`����ɑ�Ȃ�ז��ɂȂ�B�ǂ��ޗ��̂Ȃ��É��q�ނ����r�Ȃ��ނ����ʂ��A���̎j������̉��ɕ��ׂ��悤�ɁA�[���Ȏj�����e�Ձq���₷�r�������鍡���ł�����A�Ȃ�ׂ��j����`���������̂ł���B�j�k�q���̂ȂȂ��r�ɂ���A�N���ɂ���A�����̐���͂�ނ����ʂ��A��z�t��ɂׂ͊点�����Ȃ��B���̍l���ŏ��������̎j�k�ł�����A���ė����悤�ȉR���q�����r���Ȃ��̂ŁA���邢�͍s�͂��ʕ�����ʂւ������ł��낤���A���j�Ƃ��Ă͂��̏�ɂ͏����ʁB����ʏ��͑�����Ȃ���z���ɔC���邱�ƂƂ��������B�������A�|�p�I�Ƃ��ŁA�֑�ϑz��痂����������⏬���ɂł����̂��A�����Đ��j�����]����q����Ԃ��傤�r�̈����M�ې��q�������r�̈ꏕ�ƂȂ邱�Ƃ������Ƃ������ƂȂ�A������̂Ă��ʈꗝ�ł��낤����A�������ɂ����Ĉꖋ�q�܂��r�̉@�{�q����ق�r�ꊪ�̕B�j�q���傤���r�����݂Ă݂悤�Ǝv��ʂł��Ȃ��B
��1�@�M���@��j�k
�@
�@�����q���イ����r���N�A�@�c���@�吹�l�l�����ƊЋł̐S�����ׂ��x�͂̍��x�m�S��q�����肩���܁r�̏��A��{�������̈�،o���ɓ���ꂽ�B����14�̔��ˌ��q�ق����r�Ƃ��Ă̓�����l���A���ԂɌ��q�ɂȂ�ꂽ�B���ꂩ��10�]�N�̌�ɁA�@�؈�苗�������l���A�b��q�����r���Ƃ��Ă̏����q�킩���Ƃ��r�ɁA������l�̌��q�Ɋ�{�łȂ�ꂽ�B��ɊԂ��Ȃ����ʁq�ɂ����r��l�������q���ԁr���Ƃ��Ē�q�Ɏ����ꂽ���t����͑���q�ɓ���B
�@���̍��A����q�������r���̌��G�����q���イ�ɂ�����r�����x����ꂽ���A����͂���ۂnj�ɁA���t�ɂ��ĉ��@����ꂽ�B���̛ߑO�A�����E���ʂ̌��q�́A�ނ����@�@�ł����Ď������Ǝl�\��@�Ƃɂ���ꂽ�B���̊O�Ɏ������ł́A�L�O�q�Ԃ���r�[�E�}�O�q��������r�[�������������̍����Ƃ̉��̂ŋ��t�ɂ���ĉ��߂���ꂽ���A���̊O�ɂ����X�̋A�ˎ҂��ł����̂͂ނ��̂��ƂŁA�傢�Ɏ������̉@��B�̊���������āA���ɊO���}�Ƃ��Ė@�؏O�����X�q���낻��r���Q���������B
�@����͕��i11�N�ɏ@�c�l�����n�����͖ƂɂȂ��āA���R���Ă�����Ă���̂��Ƃł���B���Ȃ킿�A�g���Ɗ�{�Ƃ͈���̍s���q�݂��̂�r�̏��ł���A�܂��x�m�̏��̓���Ƃ͐�ォ��̌�M�҂ŁA��̍����Ƃɂ͋��t�̏f��䂪���Â��Ă�����B�͍��q���킢�r�̗R��Ƃ͊O�ʁq�͂͂����r�̂��Ƃł��邩��A���̊Ԃ��������Ă���ꂽ�B
�@�x�m�̉������q�����������傤�r�̔M���̑�́A�������Ƃ͖ڂƕ@�Ƃ̋ߏ��ŁA�܂������V��@�̂��Ƃł��邩��A���̑�O���ɂȂɂ��̂���ɉ�����邱�Ƃ����������A���̑�O�̕M���q������r�ł��鉺��[���G���n�߂Ƃ��āA�z��q�������r�[���فE����q���傤�فr�[���T�E�O�́q�݂���r�[���~�q�炢����r�́A����A�˂ċ��t�̌��q�ł����āA�\�W�]�̐���̔O���܂��A�����݉Ƃւ̗U�����������̂ł���B�łĂ��q�Ёr�т������̂��ƁA�Ȃ�ĉ@�哙���m�炸�ɂ��悤�A����q����߂��r�̑m�����ِ��~���Ă��悤���B�т��̖@�_���������A�ƂĂ��y�ʂ̂ŁA���̏�͑����𗊂�ɐ����q�܂�ǂ���r�̖�l�ǂ��̗͂���Ă���X�̖@�̑m����ؔ��q�����ς��r�����B
�@�����̂��Ƃ��A�g���ɕ����āA�@�c�l����͍݁q���r�肠�킹���o�Áq�������傤�r�[�i���n�̐l�B��̑�̓��Â��B�j�ƍ��n�q���ǁr�[�q�Z�V�̓����r�Ƃ����킵�āA���t�̍O�������q�����r����ꂽ�B���Ȃ킿�A�@��̎叫�ɂ͓�����l�A�����ɂ͓��G�E���فE���T�E���~�E���R�Ƃ��Ă͓����E���Â̂Q���ŁA�܂��َt�̒�q�̘a��q�����݁r�����@���傢�ɓ����ꂽ���Ƃł��낤�B�����̐M�m�ɂ́A���(���)�A���(���R)�A�R��(�͍�)�A����(����)�A�Ή�(�d�{)���̐l�X�Ă���B
�@����́A���i�P�P�N�̏H��茚�����N�Ɏ���P�N�L���̊Ԃ̂ł����ƂŁA����ΐv���q����炢�r�����������ɉɂȂ��قǂ̍ő�ً}�����ŁA����̋����q���ǂ낫�r�͂����Ƃ��̂��Ƃł���B
�@�@�t�L�i������j�@�������̂���
�@������l�̌�{���ł����{�������́A�x�m�͂̓��݂ō��̊⏼������{�̓��ɂ��邪�A���݂̋����́A���̓������l�����ɁX�k�����Ă���B����͉i�\�P�Q�N�̂P�Q���ɁA���c�M���̂��߂ɏđł������đS�R�œy�q�������r�ƕς����B���ꂪ���������q�ɂ�����r�̎��ŁA���ꂩ��b���p���ƂȂ����̂��A�c���N�Ԃɐg���̔��q�Ђ̂���r�V�̓��P�q�ɂ������r�����������̂ł��邩��A�x�m�n����g���̖��h�ɓ]�����̂ł���B
�@�܂��A���̉��N�ɂ͓V��@����h�̐^�����Ƃ����Ă���̂��A�q�ؑ�t����،o����t���Ƃ����Ă���̂��A�l�\��@���̌ܕS�V���̂Ƃ����Ă���̂��A�傢�ɉȘb�ł��邪�A���ۂ͓�����l�̌䐳�M�ɂȂ镶�i�T�N�́w�\��q���������傤�r�x�i���ł͓����ɂ��ėY��̎j���ł���B�j�ɂ��ׂ��ł��邩��A�����������ƁA�n���͋v���q���イ����r�N���A���H�@�c�̌��Œq���l�̊J�R�ł����āA�b�R���́q�悩��r�̗��������ł���B�Q���͑T��@���q�ق����傤�r�ŁA�����哰�̖��T�̒�q�ł���B���̓��̊ԂɍG��Ȃ鎛���̍\�����ł����B�E�叫���������ĕ��ƒ����̋F��������B�k���������s�������Ďq���ɏ����F�����B�R���́A�����m�s���Łq�ǂ����傤�r�ŁA���̐l�̔ӔN�q�����r�ɂ�◐�s�ɂȂ����B4���̎����E�q���ނ����r�͖������L���ĂȂ����A���́w�\��x�̑Ύ�q�����ār(�����̓`�L�Ɍ��_�Ƃ����Ă��邪�A�w�l�\��@�\��x�̒��l�\��@�̎����̓�ʗ��t���_�ł��邱�Ƃ́A�����̏�̎����ł��邯��ǂ��A���̌��_�̊�{����l�\��@�������������ۂ��͔��R�ʁB)���̑�Ɉ�R�����̋ɓx�ɒB�����̂ŁA�\��ӏ��̔�_�q����r�������āA���Ƒm�q���������r��犙�q���{�Ɍ������E���Ձq���������r�̑i��q�˂����r�������B���ꂪ�A���́w�\��x�ŁA������l�̌䐳�M���S���c���Ă���B
�@���̕��i�T�N�́A���t23�̑s���q������r�ŁA���邢�͎t���d�h�̊v���h�̎叫�q�������傤�r�ł����������m��ʁB���ꂩ���ɉ@��Ǝ��ƂƂ̌o�܁q�������r�́A�����m��j�������݂��ʂ��A�\����̔�_�Ƃ����̂́A�����q���Ă��́r�̈ێ���������čr�p�ɔC���Ă��邱�Ƃ��A���q�⊗���̗V�N�q����낤�r�������Ɍ}���Ă����n�ɏ悹�Ă̑���}���Ɏ��Ƃ̑m�����g�����邱�Ƃ́A�@��̖V�ɗV�N��u���܂��͗{�q�悤����r�����ނ邱�Ƃ́A����̓��F�Ŏ����q��������r�����邱�Ƃ̋�����߂邱�Ƃ́A���m�̖[�n�������グ�č݉Ƃɒ��݁q�����r����̂������ӖV������A���l�q���Ȃ�r��ӂߎE�����̂��S�l�A���̊O���܂��܂̊���̂��Ƃǂ��A�ƂĂ����Ɓq�����イ�r�̐��`�Ȑ���ȑm���ł͈�����َ����Ă����ʂ��Ƃ���ł���B
�@���A���̕��ɏo�Â�A�����́A�{���A�s�����A���������A���A��،o���D���O�A���A�H���q�����ǂ��r�A�����A�[���q�Ȃ�����r�ł��邪�A����͍r�ꂽ�܂܂ɏC���̎���|���ʏ�ڂ̒��ł��邩��A���̊O�ɖ����Ȍ��������������낤�B���Ƃɉ@��̖[�A���Ƃ̖[�ɂ͂ނ��ׂ��ł���B
�@���ɁA���Ƒm�̖�����яZ�[�́A���]�q�����イ�r�[�A�]��q���ʂ��r�[�A�a��q�����݁r�[�A���q�����Ɂr�[�A��i�[�i���肵����i�[�ƌ���l����B�@����B�j�@���n�[�A�}�O�[�i�����}�O�[���B�j�ǒ��q��傤����r�[�A�s�P�[�A�薞�q���傤�܂�r�[�A�~���q���傤�r�[�A��������B����́A��������@����s�҂���ꂽ�[�݂̂ł��邩��A���̊O�ɉ@��Â��́A�܂����������ʖ[���K������ׂ��ł���B
�@���ɁA�Ύd�q���r�̉��l�q���Ȃ�r�Ƃ��ẮA�����Y���v�A����A���Y��A���l�Y�A��Y��Y�A�ʓ��ܘY�A��ܘY��������B�����q�����r�Ƃ��Ă͋S�߁q���ɂÂ�r������B�����͐ӂߎE���ꂽ��A���g�̂��߂ɔp�l�q������r�ɂȂ����҂݂̂ł��邩��A���̊O�ɖ����̏����q�����r������A���l���������낤�B
�@������ǂ��A�l�\��̉@�Ƃ��ܕS�̖V�Ƃ������吔�́A���܂�ɖ��ӔC�ȑ�@���q�����ڂ�r�ł���������������Ƃ݂˂Ȃ�ʁB
�@���t�E���t���̏Z�[�̖��͔̂��R�q�͂�����r���ʂ��A���邢�͔��˖[�E�b��[�E����[�Ȃǂ������̂ł͂Ȃ��낤���B�V���N���ɋ��t�̋��ՂƂ��ď�݉@���������Ƃ������A��i�N���Ɏ��t�̋��ՂƂ��Đ^��@���������Ƃ����̂��A���i�E�O���̌Ö���`�����̂ł͂Ȃ��낤�B
�@�܂��A�@�c�̌䏑�y�ы��t�̕M���q�ӂł��́r�ׂĂ݂�ƁA�d�����ēG�����m�́A�������̔�����苗����Ǝl�\��@�̏��c��[�q�ςȖ��ł���B�`�ʂ̌��ł��낤�B�r�Ǝl�\��@�̕ʓ����_�ł���B�A���l�M�����̂́A�������̖L�O�[�E���[�E�~��[�E�}�O�[�͋��t�̒�q���ł��邱�Ƃ͖��邪�A�������`�L�����R�q�͂�����r���ʁB�l�\��@�̎����[�͈ʎt�ŁA���̊O�͋��t�E���t�E���t�͐\���܂ł��Ȃ��������O�ł������B���̒��̒}�O�[�͉�̍����Ƃ̐l�ŁA�V��̏o�ƂŁA���̏��q�ނ��߁r���L�O�[�ɉł��Ă���B����ŁA�䏑�̖L�O���͓����̂��Ƃł͂Ȃ����ƂɂȂ�B
�l�\��@�̂���
�@�l�\��@�Ƃ����̂́A�����q�����r���̓��ŁA���͕x�m�쒬�������q�Ȃ��̂����r�ŁA���Ȃ킿�╣�q����Ԃ��r��ԏ�̖k�̍���ł���B�����ɂ͌����ʂ��A�������Ɠ��@�܂��͉͂����q�ւ��r�Ă�������������ʁB��{�ł́A�l�\��@�͉͓��̋����ɂ��������̂Ƃ��āA�������̐������ɂ��̐Ղ�����Ƃ������Ă���B�܂��A�l�\��@�́A�����������@�@�ɂȂ����̂Ō��_���̔��Γk�����ނ������Ƃ������Ă�̂�����͑S���o�`�q����܂�r�ł��낤�B
�@�������A�l�\��@�Ƃ���������ƂāA�K�����ӂ̎l�\��@�ł��ꂾ���̕ʖV���������킯�ł͂Ȃ��낤�B��@�̖��̂ł����āA���邢�͐��ӂ̏��[���t�����Ă����̂ł��낤�B���t�������������o�Ă����Ɋ��ꂽ�B����͎����[�����̎����ɂ����̂ŁA����ɖ@�؏O���B���Ėڂ̏��ᎂ������Ȃ����ŁA�ʓ��̌��_�������q���r���ĒǏo�����̂ŁA����ċ��t��M���Ƃ��āA����ɍR�c���ׂ��O�����N�Q���́w�l�\��@�\��x���ł����̂ł��낤�B����Ȃ��炳��Ɉ�l����ɁA���t���͒������l�\��@�̋��m�q�������r�ɓ]����ꂽ���̂Ƃ��v���邪�A�m�R����؍��q���傤����r�͓����ʁB
�@���̎l�\��@�̚��͍��̓��o���Ƃ������Ă邪�A���̍��䒆�ɍ��ɖV���J�ˁq�ڂ�����Ɓr�A�l�\��Ȃǂ̏����q�������r���c���Ă邩��قڐ��m��������B�ʎt���r�c�Ɉڂ��Č�́A���݂͎̂l�\��@�Ɏc���Ă���ꂽ�Ƃ����Ă邪�A�r�c�̖{�o���ł����Ă邱�ƂƂ͈Ⴄ�悤�����A�����̑F���Ɏc���Ă����B
�@�������A�������ƂƂ��ɕ��c���ɏđł������Č�͂邩�ɓ��o�����ł����B���̋K�͂̏��Ȃ�́A�r�c���ʎt�̖{���ցq�ق����r�ƒ�܂��Ă��邩�疳�p�����Ă̏�ł��낤�B
�@�����̑�ɂ͉@��͂��������A�e������������邱�Ƃł��ʎ���ł������B�����Ŗk���Ƃ̏����q��������r�ŁA���̕ӓy�ɕY�����Ă��������ߓ����s�q�Ƃ��������S�̒s���q������́r�����q�ɉ^�����āA�ꎞ�̗a���ƂȂ�@���Ƃ��Đ�玛�����戵���Ă������A�w�₪����킯�łȂ��C�s���ς�Ă�̂ł��l���������킯�ł��Ȃ��B�����Ƃ��}�ɔ�q���r�ĈВ���U�炵�Ă����B�ߏ��̈��҂ǂ������Â��ĕ����q�Ԃ��́r�𗐂�Ɉ��ݐH�����Ă����̂ŁA�����̑�O���̔��R�������N�����B���̂���Ɏ��Ƃ̏d�������l�l��������l�̒�q�ƂȂ��ē��@���l�̖@��M���n�߂�����A�c��̎��ƈꓯ�����łɈꓝ�ɂȂ��Ƃ��Ă�B
�@���̎���̓V��@���́A�啪�M�s�ɓ��h���Ă��Ă��̋�O���Ŗ��ߍ����Ă邩�A���邢�́A�قƂ�ǖ��M���s�̎҂���ł������������A���M�ł�����������Ȃ����Ƃ��]�����ʉ@��オ�A�@�ؐM�̑�G�������ɉ�킵�Ă͂Ȃ�Ƃ��d�l�̂Ȃ����ƂɂȂ�A��������ɉ@���Ƃ������ڂ���̉��ɉ������݉B�����R�̋����Ɋׂ���˂Ȃ�ʂ̂ŁA��l�q���Â߁r��㊯�B�ɗ���ł܂��l�l�̎��Ƃɔ��Q�I�̓����o�����B
�@����͓����ł͖@�،o��ǂ薭�@�̑�ڂ��������肵�Ă͂Ȃ�ʁA�O��ɂ�舢��Ɍo����u������ɂ��̖̏��O�����Ȃ��ׂ��ł��邩��A�������̐�����Q�点��A���������܂ł̖@�ؓ��u�̍߂͋������킵�]�O�ʂ莛���ɍ��u���ł��낤�A�������̋N�������������o���ʂɂ����Ă͎����������̎���ގU����ƁA�@��̖V�ɗ^�}�q�Ȃ��܁r�̑m����w��q���肦�r�ɏ]���āA�l�l�ɋ��k�ɋy�̂ŁA���G�E���ق͌��𑵂��āA����͉@���̋��Ƃ��S���ʁA�����͓V��@�ʼnb�R�̖����ł���A���̍��{��t�̌䐸�_�q�݂�����r�ɏ]���Ė@�ؓ��u������̂��Ȃ�Ĉ����A���@���l�̌��`�Ɉڂ�Ǝv������Ɓq�Ђ��r�݂��o��ł��낤�B�`����t�̌��Ɋ҂�Ǝv���Č�g���ƂĂ��ᓙ�ƂƂ��ɖ@�ؓ��u���n�߂���A��ɔO���͓��R�ł͊���O����n�܂������Ƃ��ɋߑ�ł͂�����ʂ��A���X����|�����Čᓙ�̐��`�ɏ]���߂���A���ꂪ�������Ď߉ޕ��̌�{�ӂł�����ƁA���@���Ă̍R�قɖ��w�̉@���ꌾ�̓������ł����A���₱���͘_��łȂ���Ζ@�_���v�ł���ᓙ�@��E�̉��m�ɏ]��ʂƂȂ瑁�X���̎��𗧑ނ�����A���������܂Œq����r�����Ă�����Ȃ�h���ڂ�������ł��낤�ƁA�\�Ђ����U���l�q�ł��邩��A�M�S�����̎O�͖[���~�����Ɍ��A�ؕ���l��Ĉ��g��������B
�@����q���傤�Ӂr�[���T�́A���悤�ȕ��@���n�̈��k�Ɍ����p�ł���ƁA�����V�Ɂq�ڂ�����r�𖾂��n���ĉ͍��ֈ����グ���B���G�E���ق́A��ނȂ��V�ɂ𗣂ꂽ���A�s���ׂ������Ȃ��B���ƂɁA���݂̖V�͎t�����̑��`�ŏC���Ȃɂ���{�@�̖��ɂȂ��Ă���ʁA���܂����c�q���ł�r�����l����X�̂�����̂ŁA����炪�閧�q�Ȃ�����r�ɉA�Ձq�����܂��r���ƂɂȂ����̂��@��オ���X�m��Ȃ�������̏�̖\�Ђ͐U�邦�ʂ̂ŁA�ꎞ�ڂ��ڂ��̑̂ł������́A���t�ɂƂ�Ă͕s�K���K���Ɂq���Ƃ܁r����ɔC���Ď��R�ɋߗ��q����r�ɉ������Ė��ɕz���̎���g����ꂽ�B����͌�����N���̂ł����Ƃł���B
�@
�@�����R�N����S�N�ɂ����ẮA����͖��_�̂��ƂŁA��{�������̉@�储��ю��Ƃ̖ʁX�A�����l�\��@�̎����E�Ƒ�O�����@�̑m�������q�ɂ��ށr�ނ��Ƃ͕���̋w�G�q�������r�������Ȃ�ʓ�����ɗ��Ȃ�䂫�A���@���l�̖@��M����҂��ΊO���Ă������āA������W�Q���������B
�@��ł͂S�l�̖@�ؓ}��ǂ��o�����B�ᓙ�ł����@�}�����̂܂܂ɒu���ׂ��łȂ��ƁA���ɓ����E�����E��������{����ǂ��o���Ċ����ɍs���ꂽ���A�܂����ʂƂƂ��ɒǂ��o���Ă��܂����B
�@����ŔM���ł���{�ł������ł��@�ؓ}�͈ꎞ��ł̎p�ł���掓k�ǂ��͈��S�̖��������������A����͕\�ʂ����̂��ƂŁA��{�ɂ͂��܂����[��L�O�[���c���Ă���B�����͖����͂̏��Ȋw�O�łȂ����l�����Ăΐe���������m�ł��邩��A�\�͂ɂ͑i�����ʁB�������A���w�̑��m��Ɩ��f���Ă��钆�ɁA�������Ĕ閧�̉^�����ł����B����ɔM���ł́A�G�t�E�َt�����ɉ���Ă���������̔M���̕z���ɑ����̌��ʂ�����ꂽ�B
�@��͖�ɔO���̋����ɜq�������r�炸�ڊo�߂��ҁA�܂��͍s�q���ꖡ�̗��s�����q�ق���r�ɕ�����ʂĂĂ鐳�`�̎҂ǂ��́A���R�ɗ��t�ɐS�ꂩ�瓯��銉����B���̈�ӂŋ����̐M�k���M���s�뎛�q�������r�ӂ����ς��ɂł����B���̒��̏d���҂��A���̑�@��̗��Ď҂ł���M�����̕S������_�q����r�l�Y�Ɩ�q��r�ܘY�Ɩ�Z�Y�ƂĂ���B���̎O�l�Z��͍݉Ƃ̐g�Ȃ���A�����̕����̚n�q�����ȁr�݂�����A���������ė��`�ɋ��_�ŁA�m���q���ނ炢
�r���p���������̑��v�q�܂��炨�r�ł������̂ŁA���ꂪ��ɑ��ɂ�����Đ��|�q�������r�����Ђɋ����ʖ@�؍���������̂ł���B�����͌����S�N�̂Q�����ɍO���Ɖ�������ꂽ��̂ł����Ƃł���B
�@�q�{�R�̌Ó`�ɂ́A�M���_�l�Y�@�c���l�Y�@�L��푾�Y�ƂȂ��Ă���B����ɂ͗��h�ȍ������������낤���A���ĂɎ������Ƃʂ͎̂c�O�ł���B�r
�@
�@�_�l�Y�E��ܘY�̌Z�ɖ퓡�������Ƃ����̂��������B���|�@�q�̋Ȏ҂ŁA���ł̌����ł���B�퓙�����@�@�ɂȂ����̂��A����c�̕��@��j��́A�����̐M�𗐂��́A����ɕ��̓G���̂ƁA�^�悩���ĉƌZ�̌��Ђŋ��M�Ɉ����߂����Ƃ�������ǂ��A�_�l�Y�͂��ł��@�̐���������O���O���̎�����ׁA�����͌����O���̗��v����ׂ����łȂ��A�������̐M�͌Ȃ��Q����������̂ł��邱�Ƃ��A���X�Ɛ�����������̂ŁA�����ɂ͂͂ނ��������̂܂܂ɂȂ邯��ǂ��A�Ȃɂ��̋@���߂��Ă͑ޓ]�����߂悤�Ƃ����B
�@��̉@���s�q���A���łɓ��G�E���ٓ��̎�����ƐE�����̂ł����S�̑̂ł��������^���̐M�͊K����̖ʂ��炭����̂łȂ��B���Ƃ�����ׂȂ��Q�l�V��ł��A���S�̔M���͐��������ɑM�߂��A���X�̍O���ɂ��M���̓k�͗O���o�Â�B
�@�_�l�Y���n�߂Ƃ��ċ��M�҂��A�M���͐\���ɋy���ߋ��ߍ݂܂ł��g����B����炪�A���@�̏ォ��O�����ԁE�^���S�������сA���͉@���̕��햳�Ζ��M���s���U������̂ŁA�O���ꖡ�̍݉Ƃ܂ŐS�������ɍs�q��a��悤�ɂȂ����̂ŁA���͂�I���ɂ͉߂�����ʁB��X�Ɋ̒_��ڂ��āA�n�̔��ȐS�̂Ȃ��s���q������́r�����ł��邩��A���Ə��Ǝ����悾�Ƌ��������A���̗��ɋ����鎞�͎����̉��l�����W�߂��G�������A�K��߂莭��߂�āA�@��̖V�ň��ݐH��������B
�@�͂Ă͕��O�̕����r�ɓŖ�����āA��������ɌQ�ꂢ���������āA�����ɔ���ɏo���Ď��̗����q����r����͂܂������̂��ƁA���������Ȃ������O�ɔ���������@�،o���U�X�ɉ��q�ق��r���ďa���ɒ��炷��B����͖��M�̘a��[�@�C�̎d�Ƃł���B
�@�܂��A���q�����Ƃ��s�������ׂ����ق��Ǘ��������M�q�ӂ�����r���A�s�q�����グ�Ď��V�̕����ɂ���B�܂��A�������̖����ɂ��邽�߂ɂ́A�O�Ȏ҂̕����[�È�����X����̉ߗ���������āA�������ĕ\�ʂɂ͊w�������R��\�����Ăċ��m�ɗp���B�퓡�������̈����������ŎE���Ė����ɓ���āA�@�ؐM�҂̋s�ҁq�����߁r����\������B
�@���̍��̉������q���������̂��傤�r�́A�����͖k����Ƃ̎��̒n�ł���������A�s���Y���̖����Ƃ��Đ�����`�@���ɒu���Ă������B���̐����̉��i�q�����₭�ɂ�r�͎����̂��ƂŁA���ɂ͒����̕ʓ���܂Ă��������B�����ő��̐����Ɩ@���Ƃ����鐭����ƁA���������Ă̌����Ől�̋�����퓡���Ƒ厛�̉@���Ƃ��[��������āA�����錠�\�𗐗p���āA�������i�ɑi���āA�M�̖h�����������̂ŁA���܂������̂ł͂Ȃ��B���������Ȏ҂͕K���ޓ]���邱�Ɛ����ł���B
�@�������A���G�E���ق��_�l�Y�E��ܘY�����A���X���X�ɑ�������䅋�ɘJ�q���r��Ȃ�����A�g����g���Ă̐M�ł��邩��A���̒ʂ��ۂ͂Ɠ����ăr�N�Ƃ����Ȃ������̂ŁA�ɂ͌ȓ�����߂������ꂸ���q���{�̌䋳�����U�삵�āA�@��M����҂͏d�Ȃɏ�����R��G����炵�����A���̈Њd�������ł������B
�@�M���ߋ��̐M�k�̒c���͖��_�̂��ƁA��E�Ζ{�E�͍��E���R�E���̘A���ٖ͋��Ȃ��̂ŁA���̏�b�x�����[���̑S�M�k�E�S�m�����؎��̎��͉������悤�Ƃ������Ƃł��邩��A�M���̐M�͂܂��܂��D���ɂȂ����ł���B
�@���̏�́A���̌��������̓������������ɂ�����ɂ�Ȃ�ʂƍs�q���Ӂq������r�Â����B���̏p���Ɋׂ����̂��M�҂ł́A��̑��c�e���q�����܂��r�E���莟�Y���q���̎m���ł���B�m���ł́A���X��E����ӂɏo�������i�[�ƎO�ʖ[�Ƃ̊w���ł���B��i�E�O�ʂ͂�������̊w�m�ł���A�����ł͎t���̓��@���l�������w�����炢�Ɍȍ��q���ʂځr��āA�����E���G�����ቺ�Ɍ��Ă�������ǂ��A���Ď��n�ɍs���Ă݂�Ɗ�{�ɍs���Ă��M���ɗ��Ă���ɉ����Ă��A�v�������������ĂʁA���t�قǂɑ��h���ʂ̂ŁA��y�̓������ɓ��������邱�Ƃ͂����ɂ��c�O���Ƃ������S�ɂ�����ŐM���キ�Ȃ�B���̊Ԍ������q�˂�r���āA�s�q�Ɩ퓡���Ƃ��Ì��������Ď��������B
�@�]�V�Ȃ��t�G���ׂ����Ԃ��s���A�m�炸�m�炸�[��������āA���ɂ͖@�̑m������b���O�����̐M�F���u���c�Q����̎�`����������悤�ɂȂ����B�e���⎞�j�������Z�Y�ɂȂɂ��⍦�������ĕs�a�ł������B���̊Ԍ��ɂ�����Ŗ����Ɉ������ꂽ�B
�@����炪�A�����Ė@�̐M�k�̏W���`���āA�����ň������ŎU�X�ɑŝ��q���傤���Ⴍ�r�ɂ��������̂ň��̏C����������A�ᘰ�̉���l���ł������A��i�[���͔����̖@���U�ʁq�Ă��߂�r�ɗ��āA���̑����̒��ɗ��n�����B���ɂ���i�[�́A���̒ɂ݂������ŊԂ��Ȃ��㎀�������B�O�ʖ[��������N�Ɏ��B
�@�����̌����ɊႪ�o�߂��A���̂��т͎�������Đ�����𔗐����q���ǂ����Ɓr���ĂS���q�O��2�N�r�̐�Ԑ_�Ђ̍�̍��G���ɐM�҂̎l�Y�E���ɂ������B�W���ɂ͂܂���l�Y�����炵���B��������s�q�Ɩ퓡���̕ʓ���̍H�ł��邩��A�Ɛl���\�ʁq�����Ăނ��r�ɋ�����悤���Ȃ��B�����̖\�t�́A�@�̐M�҂�\���h�����ׂ��Њd�q���ǂ��r�̎�i�ɂ����ʂ��A����Ɉ����ނׂ��́A�����̔Ɛl���s���Ȃ肵�ɏ悶�ċ㌎�̑化�܂̍��i��̒��ɂ́A�������ē��G�������̂Q�l��n�����E�Q�������̂悤�ɂʂ�����B
�@�������A�@��̍āX�̔��Q�ɂ��@�̑m�����@�̂��߂ɋ����Ċ��E���Ă����̂ŁA���ɋ㌎�̑呛���ƂȂ����B�ߏ�́A�O�����N�̂R����蓯�Q�N�̂W���܂ł̂ł����Ƃł���B
�@
�@��@�O�ʂ̂��߂ɂ́A�����E�J�Z�q�ɂ�ɂ���낢�r�����ĎO�ނ̋��G�ɓ����Ă����M���M�k�̊��E�܂��A�O���Q�N�X���Q�P���̈�̏�Ŗ\���B����́A�G�t�ɂ͎���̏����̓c�����������炵���B�����M�҂̕S���𗊂�Ŋ������������B�P�l�Q�l�ł��Ԃɍ����ׂ����A���̎����̂ʼn��l�����l���o�Ď�`���������B
�@���Ă����̂��Ƃ��M�k�̏W�܂肠�ꂩ���Ƒ҂��݂�����s�q�́A�`�߈ꉺ���Ď����̕S�����퓡���̈ꖡ��萭����̉��i���܂ł��₩�ɋ��Â����āA�ڂɗ]�鑽���������ėp�ӂ̓����|���ř��q�ǂ��r�Ƌ��q���߁r���ĐM�҂̕S����������B�M�k���ł́A����܂ł͋��t�̌P���ƏG�E�ٗ��t�̍��@����������āA���q�Ȃ��r������A������A���������͓����邪���ɂȂ��Ă������A�ĎO�̗��\�Ɋ��E�܂̏�����āA��l�Ƃ��ē�����������������G�t�����Ȃ�Ǝ~�߂Ă��������ďG�t��ގU�����߂āA�_�l�Y���w�������Ď��������̖_�⊙�ʼn���������B������E������̕S���ł���A�r�͂�����Ε�����ł���B������_�l�Y�́A�g�͔_�v�ł���Ǖ����̐S���a�q���Ɓr����ʎ҂Ȃ�A�����̋�����R�ł���B���ɂ͖\�k�̕����D������āA������Ɏt�q���v�̗E��U�邤���B�����٘̕_�̐ܕ����A���������͕��͂ɑւ��ē������B���̂ꑞ�����s�q�z�E�퓡���̎��ɑ����A�N���̖��O�𐰂��͍����ł���B�l�Y�̓G���A��l�Y�̉��G�o�傹��A�@�ؐܕ��̗����̖����Ă݂�ƁA���������炸�������Ďv���܂܂ɑ����̈��k��Y�܂������A�c�O�Ȃ��瑽���ɖ����A����20�l�̐M�k�͗͂��Ďc�炸�����֔���ꂽ�B
�@��ł͖d��݂������Ƃł��邩��A�����퓡�����i�l�ƂȂ��āA���̌��܂̈���������S�R�q��������r�@�̕��ɂȂ�����Ċ��q�ւƑi�����B�v�́A���G���n��ő����̕S�����w�����A��������|����т��đ�̉@��̌�V�֗��������B�܂��A�I���Y�ɍ��D�𗧂Ă��߂āA����̈������ē��G�̏Z���ɉ^�Ԃ悤�ɂ����B�����̗��\��h�����߂ɑ化�܂ƂȂ�A���ꂱ��̎蕉�����l���ł��܂����B�������̗��\�l�������グ�āA�䎮�ڒʂ�Ɍ�ْf��������悤�Ə����グ���B
�@�����Ƃ�����ɂ͐�����̎w���Ă��邩��A�킯���Ȃ������ɂ��̂Q�O�l�͑厖�̍ߐl�Ƃ��āA��݂ɔY�ނ��p�̂Ȃ����q�Ɉ������Ă�ꂽ�B���ꂪ��@��̒[���q���Ƃ����r�ŁA�Ԃ����Ԃ����c�O�̎���ł���B
�@
�@���̑�����O�ɂ������G�E���ق̐S�ɂ͈���Ȃ炸�A�����~�܂蕠�q�͂�킽�r���f�q�����r������ł������B���Ɏg����y���ċ��t�̋��ɂ��̗R��m�点���B���t���傢�ɋ�����āA���˂Ă��������Ƃ��炩���ߌP���������Ă������A�c�O�Ȃ��ƂɂȂ�������ǂ��A����܂Őh�������̂͊����ׂ����Ƃł���Ɗ��Q�̐����������A���������ƂɊ��đP��̕]�c���Â炳�ꂽ�B������g���ւ��}�g�����B���E���R�E�͍��E����̉��~�ɂ��g�����y�����B
�@������Ɏ葱�����Ė퓡���̑i��̎ʂ���������B����ɍR�i����̐\��̈ĕ������t�������āA�G�t���M����߂��B���ꂪ���݂̐\��Ăł���B�v�́A�M�������化�܂Ɏ����X�ɑi��q���傤�r���Ė����Ȃ锽���ł���B����ɍs�q�����@���@�̗��s�𐔂������āA���̖ƐE����̊v�������ꂽ�̂ł���B
�@���̈Ă�g���Ɏ������ď@�c�̌�w�}�������B�@�c�͒����ɕM���������āA�����10��12���̌���Y���ĂQ�t�̋��֕Ԃ��ꂽ�̂ŁA���ɐ������āA���t�͗��t���]�����Ĕn�����āA�������q�ɏ��ꂽ�B���̐����́A�قƂ�ǒ��錓�s�ł��������A���q�ɒ����ꂽ���́A���łɈꉝ������q����ׁr������œ��S�ɋy���ł������̂ŁA�Ƃ������\����Ζ⒐���ɏグ��ꂽ���A���̌�͍āX�Q�肹���Ă��A�Ȃ�̏��o�����撲�ׂ��Ȃ��B
�@����10��15��������q����ׁr�̗L�l�́A�����ɂ����\�̌���ł������B�⒐�̓��l�q������r�͖��_�A�����q��ї��j�ŁA20�l���L��Ɉ����o���Ċ̐S�̌��܂̒��ׂ͑��}�ɕЂÂ��A�͂ẮA�͑����@�̐M���~�߂ĔO����\���A������Ήȍ߁q�݂Ƃ��r���͂��ċA�����g�����ނ�ł��낤�B�����M�����߂��A�h�x�q�����Ɓr�d�߂ɍs�Ȃ��ׂ����A����̑厖�����߂Đ\���グ��ƁA�ł������ɐ\�������B���̊�F�A���̐��A�Ȃ�Ƃ����낵���̋ɂ݂ŁA�����Ȃ鍄�̎҂��r���ɜЁq�����r�ꕚ���āA�����̎��q���Ƃr����ɏ��ׂ����Ȃ��̂ɁA�_�l�Y�͎���Ƃ��ĐF�����ς�����������₩�ɁA�@�̐M���̂��X�̖@��ɂ��y��Ƃ����̂ŁA���j�傢�Ɍ��{���āA�y�S���̕��ۂƂ��ēV���̊Ǘ̂Ɍ��t��Ԃ����s�G���A������{�S�ł͂���܂��A�V���g�{���߁q�r���Č��킷�隔��q�˂��Ɓr�ł��낤�B�������邩�A����寖ڂ������Ē�������ƂāA�P�Q�̏���ɋ}�X�\�������̂āA�|��肠�����я������́A寖ڂ̓L����͂��āA���̂�_�l�Y���ɜ߂��鈫���������ǂ����̐_��̉��ɑގU������ƁA�E�i�����Ďˏo����̐��ɁA���M�̎҂Ȃ���������A�_�l�Y���͖̓L�̓���ɂ��������ď������������A���Ɉꓯ����グ�ē얳���@�@�،o�얳���@�@�،o�Ə����o�����̂ŁA�����̍��q��т͂��߈ꓯ�猩���킹�āA�������ċS�فq������r�������A����͂Ȃ���L�̂��Ƃ��A���̓V���̖@������ꂸ寖ڂ̒����ɋ������A�������u���Ȃ��ʑ��v�̐��_���_�̕�����y�ʂ��ƁA���̏�����⏃���v�A����S�ɂɈ����ċ���������Ƃ����Ė@��͕���ꂽ�B
�@���̂��Ƃ𑁔n�����ď@�c�̌䋖�ɍ�����ꂽ�B���̌�Ԏ����A10��17���̌��Ő_�l�Y���̍��M�����Q�����܂��A�܂����t�E�G�t�E�َt�l���ƌ�ܔ��̖����q�Ȃ��ār�����Ă������ꂽ�̂ł���B
�@���t�͊��q�ɑ؍݂��āA�@�Z�̓�����x�E��c�E�l�̐M�m�̗͂��W�߂Ė⒐���ւ̍R�i�ɓw�߂�ꂽ���A����ɂ��̌����݂��ʂ̂ŁA����11���ɂ͏G�E�ٗ��t��x�m�ɋA���āA����ɑ�̈��k���̓Ŏ�ɂ����点�Ă͑��Ȃ�ʂƁA�@�c���̌�w���ʼn����Ɍ��킵�Đ^�Ԃ̓����̍O���̕⏕���ƂȂ��ꂽ�B
�@���t���܂��A�⒐���ꌏ�A�M���M�k�̉A�Ȃ���̕ی���Ί��q�̑m���Ɍ䗊�݂��āA�x�m�Ɉ��グ�A�Q�O�l�̉Ƒ��������ĈԂ߂āA����E�����ɖ������ς˂āA�ꎞ���]�̐V�r�Ƃɍs���ꂽ�̂��~�ނʎ���ł���B
�@�x�́E���͂ɂ����ď@��ɑ������c�q���������r�Ȃ肵�O���Q�N�������āA���R�N�̂S���W���ɕ����q��ї��j�́A��ɘS�ɂ�20�l��@��Ɉ����o���A�L���������킹���A���ɖ����Đ_�l�Y�E��ܘY�E��Z�Y�͒��{�Ƃ����āA���ɑŎ�ɂ����B�R�l�͌��Ċo��̂��ƂƂĂ��̏L�����q�����ׁr��@�،o�̂��߂ə��˂��Ȃ�A�����̉ʕ�͑���ł���B���ꂱ���ɉ������Ձq���r������́A����x����ƐS�F����Ƃ��Č����悭���ׂ̂��B���̗]�̂P�V�l�͒Ǖ��Ɛ\���n���������A�߂̌y�����x�ԐF�͔��o���Ȃ��āA��������3�l�ɐ旧���ꂽ�̂������ɂ��c�O�C�ł������B
�@���N������q����ׁr�̏�Ƃ����A���̎d�u���̏�Ƃ����A���Ƃ��M�Ƃ͂����Ȃ��牺�˂̐g�ɕ��m���p�������C����ƁA���V�Ƌ��|�Ƃ��i���Ɍ����̐S���[���A�������̂ł���B
�@�����̏��Y�́A�\�ʂ͑化�܂Ɏ�q�������r�̐n���E�Q���o�����������l�ł���Ƃ̂��Ƃł������낤����ǂ��A�^���͐����h���ɂ����ʁB������A�]�O�ĎO�̐n���E�Q���\�͂Ȃ�Ƃ���B�����̌����ȋ��f�����Ȃ��ŁA��T�ɖ@�̐M�𔗊Q���鈫���_�́A�������ė��j�͂��ߑ�ꖡ�̈��k�ɓV���̜߂��鈫�S�����g�̌o���̎����ł��낤�B
�@���̉�̒f�߁q�����r�Ŋ��q�̑m���͂Ȃ�Ƃ��d�l���Ȃ��A��������ɖ��O�̌��ɗ܂����̂Ă���B�Ƃ������M���̑�@��͂���ŏI������������A���V�̏Ɗӂ͂��̂܂܂ɂ͂��܂ʁB�����@�������ނ�ɉ���đ�͊Ԃ��Ȃ����F�ƈ��m�͏��U�����B�����j�́A���t��d��ČȂ���܂�寖ڂ�20�l���ꂵ�߂��я��������n�C�q���イ�肭�r����ꂽ�B��10�N�̊ԁA�g�͊Ǘ̂̉��ʂɂ���Ȃ���A���������厞���������قǂ̌��͂�M���ē��{�����Ɉ��ꂽ���̌��Ў҂��A���t�̈������Ĉ���̓��ɐg���Ƃ������͂�Ƃ����̂́A�@�G�Ƃ͂����Ȃ��疳�c�̎���ł���B
�@�s�q�����ɂM�k��20�l�̊O�ɂ�����B�����킢��9��21���̓��Ƃ�Ċe���ɐ������Ă�҂��A�ǂ����Ă��k���o���Ċ��q�ɓ˂��o�����Ƃ��Ă���B�ޓ��̉L�̖ڑ�̖ڂ́A�����ӂ킵�����̂Ă������B����ƂɉB��Ă���M���̐V���n�̐_��q�����ʂ��r�́A�i�炭�����疜�̋�J�������B�����E����E�R�䓙�̏��m�����ʂ��Ă��̖@��ɐg�������ɂ܂��肵������Y�����̈�g�ɂ́A�s�q���̍��݂��[�����������Ă��邪�A����ɂ��ꋽ�̒n���ł���Ύ�̂��悤���Ȃ��B�܂��ď��̏�����ł��邩��A��������������ǂ����悤���Ȃ��̂ŁA���Ɋ��q�ɂ��邱�ƂȂ����ƒ��i����B���̍��݂��A�����q��̎�Ō����ɔ��Q�������ꂽ�B�s���̒�������(���イ���イ�Ԃ��r�͕����ł͂Ȃ������B
�@���̓�V�́A���t��������̑��������Ɏ�邲�Ƃ��@�c�̌䎨�ɓ���̂ŁA�እ�̎��Y���Y�͂܂��Ȃ��@�̍s�҂ɂ݂�ꂽ�B�w����䏑�x���͂��߂Ƃ��āA�āX�̌�Ԃ߂̌䏑�����������B�M�m�̖��_�ł���B��̊ӂł���B
�@�������A�@��̗]���͍ی��Ȃ����̂ł͂Ȃ������B�s�q���̈��m���́A�N�N�����ɋ����q�ނ炳���r�̔�������������ł��邩��A�l�𔗊Q������܂��Ȃ�����ɂ�Ȃ�ʂ悤�ɂȂ����̂ŁA�O��5�N���ɂ͔��Q�͑S�����U���Ĉ��̖��Ɖ����������̂ł���B
�@����ǂ�������l�ɂ����ẮA���̑�@��̂��Ƃ���ɔO���ɉ������Ă���B���{�̌��Ђ����ꂸ�g���q���̂��r�����сq���̂��r�Ɍy�đ�@����C��C�q���Ă��������r�ɏd��20�l�̌��łȐM�A�Ƃ�킯�_�l�Y3�l�̑s��Ȃ�Ō�A�䂪�����q�̒��ɂ悭��������̐M�S�̌��C�Ȏ҂��ł����B
�@�M���̋�s�̕S�����A��ē��{��̍��̎҂ƂȂ����́A�����A�ρq�肻����������r�̖}�v���ꑫ��тɋ��푦���o�q�����傤�����݂傤�����r�̕��ɂƂȂ����̂ł���B��{���̏]���ނ���̒�q�������A���̗]�c�Ŏ����܂ł����l�Ƒ厜����̎t���̌�[���瑸�h����ꂽ�̂́A����̖ʖڂł���ƁA��ɉ��O�����Ă������B
�@�g���䗣�R�̌�ɑ�Ύ��J�n�̗��X�N�A���Ȃ킿�����T�N�S���W���́A�_�l�Y���a�߂�12�N���ɓ���̂ŁA��V�̖k�ӂɕ��q���r�𗧂ĂĎO�l��ǒ��q�����傤�r�L�O����ꂽ�B���̖�����N�̉i�m���N�ɂ́A�����j���q���@�̔��������n�C����ꂽ�B
�@�i�m�U�N�Ɂw��q�����x���L���āA�ʂ��Đ_�l�Y�R�l�̉��ɂ͖@��̎�����L���Ȃ��ꂽ�B���ꂩ�瓿���Q�N�S���W���ɂ́A�킴�ƂR�l�̂��߂ɑ��䶗��������Ė@�̏ܔ��𖾂炩�Ɍ㐢�Ɏ����ꂽ�B����A�_�l�Y���̔M�����Ɍ��������̂łȂ��B���@���N�̖��X�m�X���閭�@�̏ܔ��ł���˂Ȃ�ʁB
�@
�@
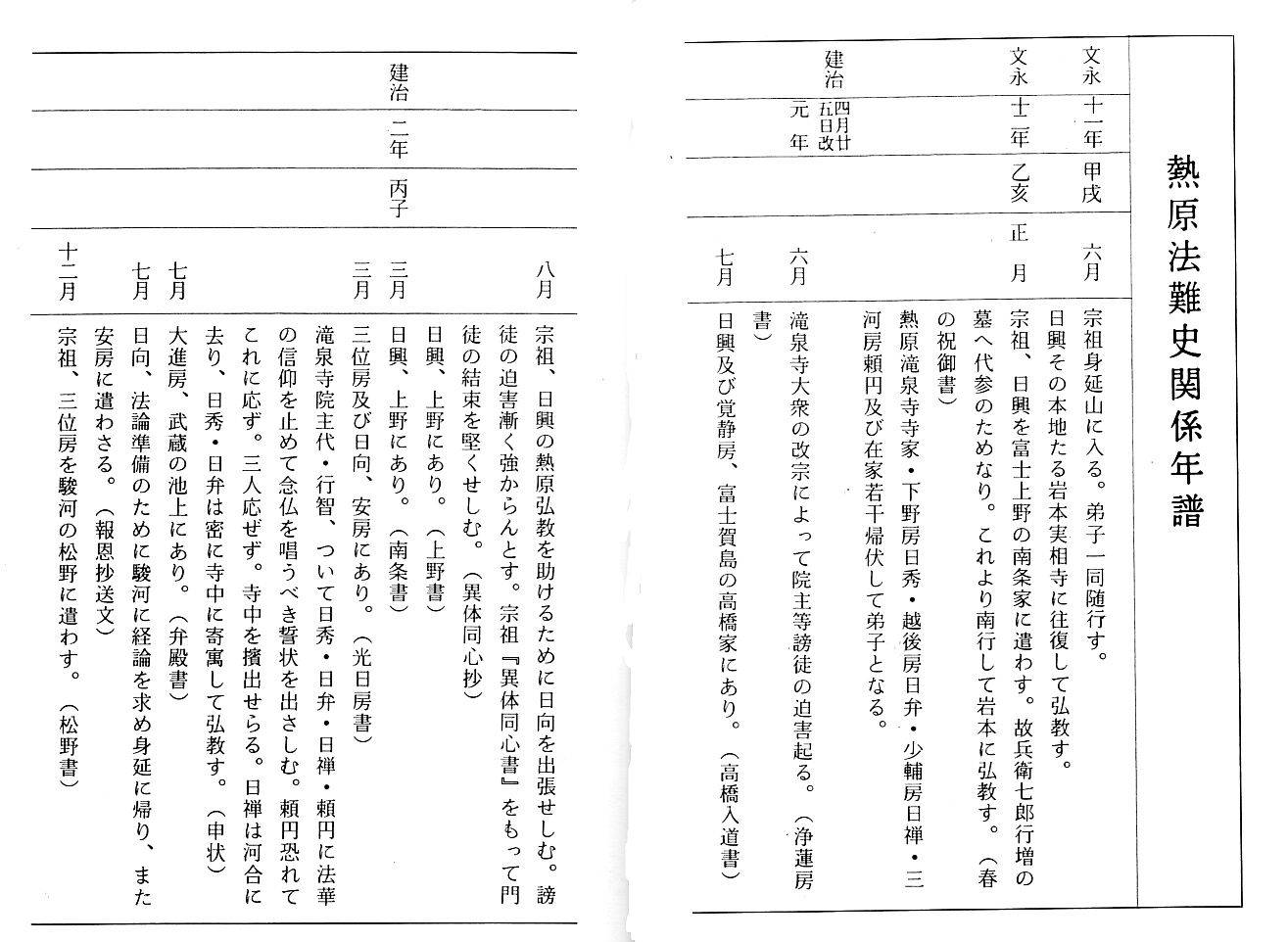
�@
�@
�@
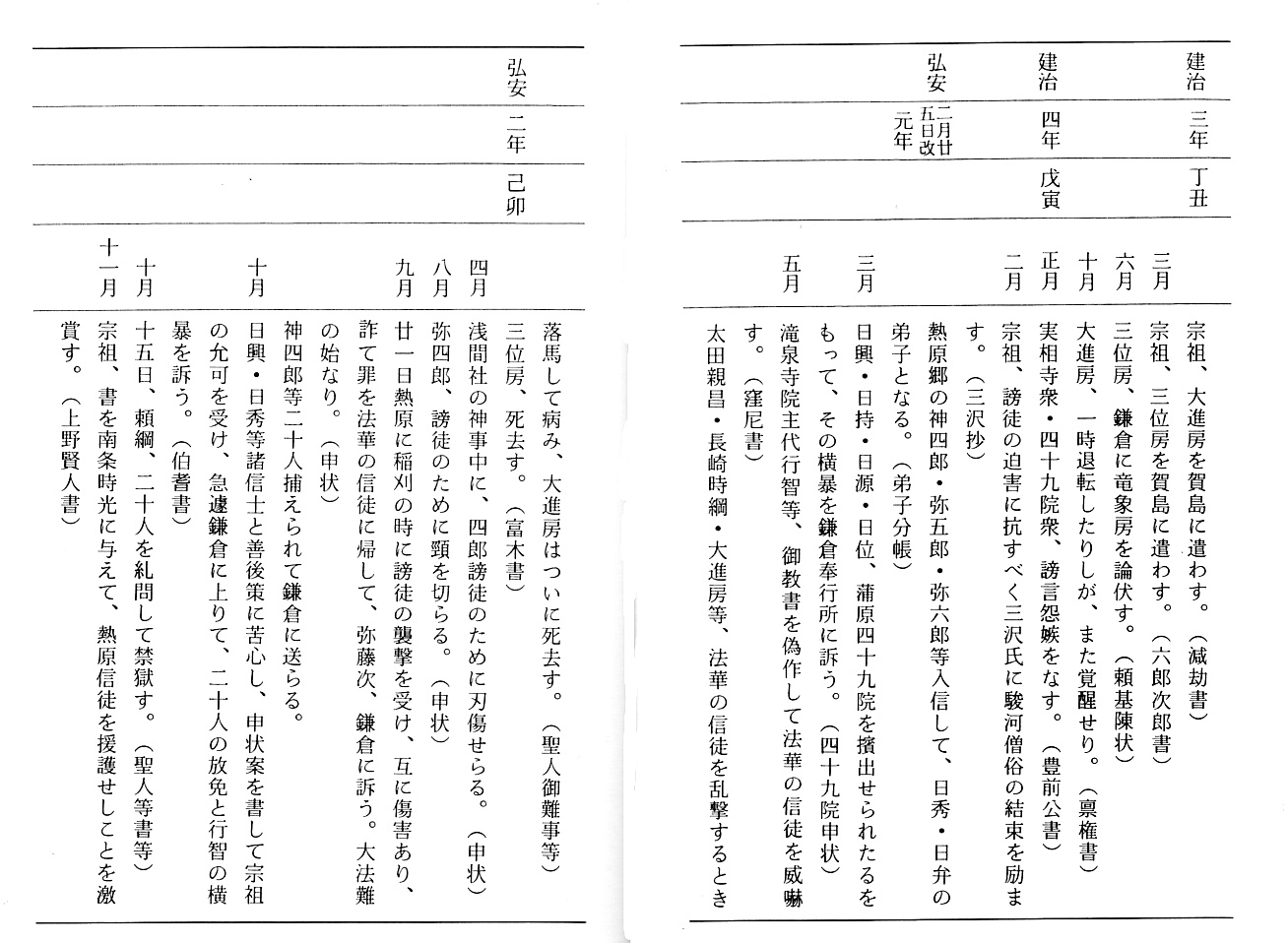
�@
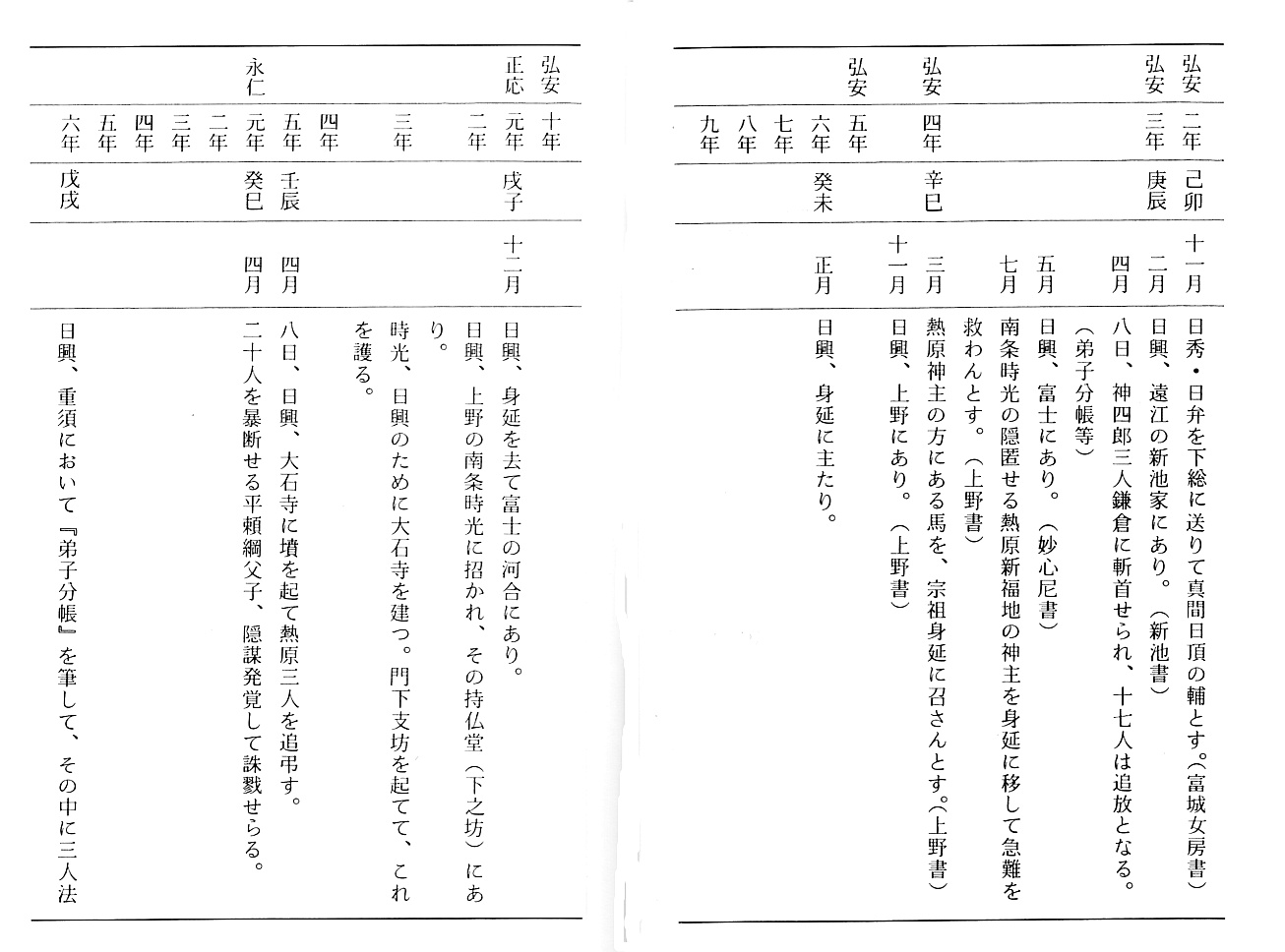
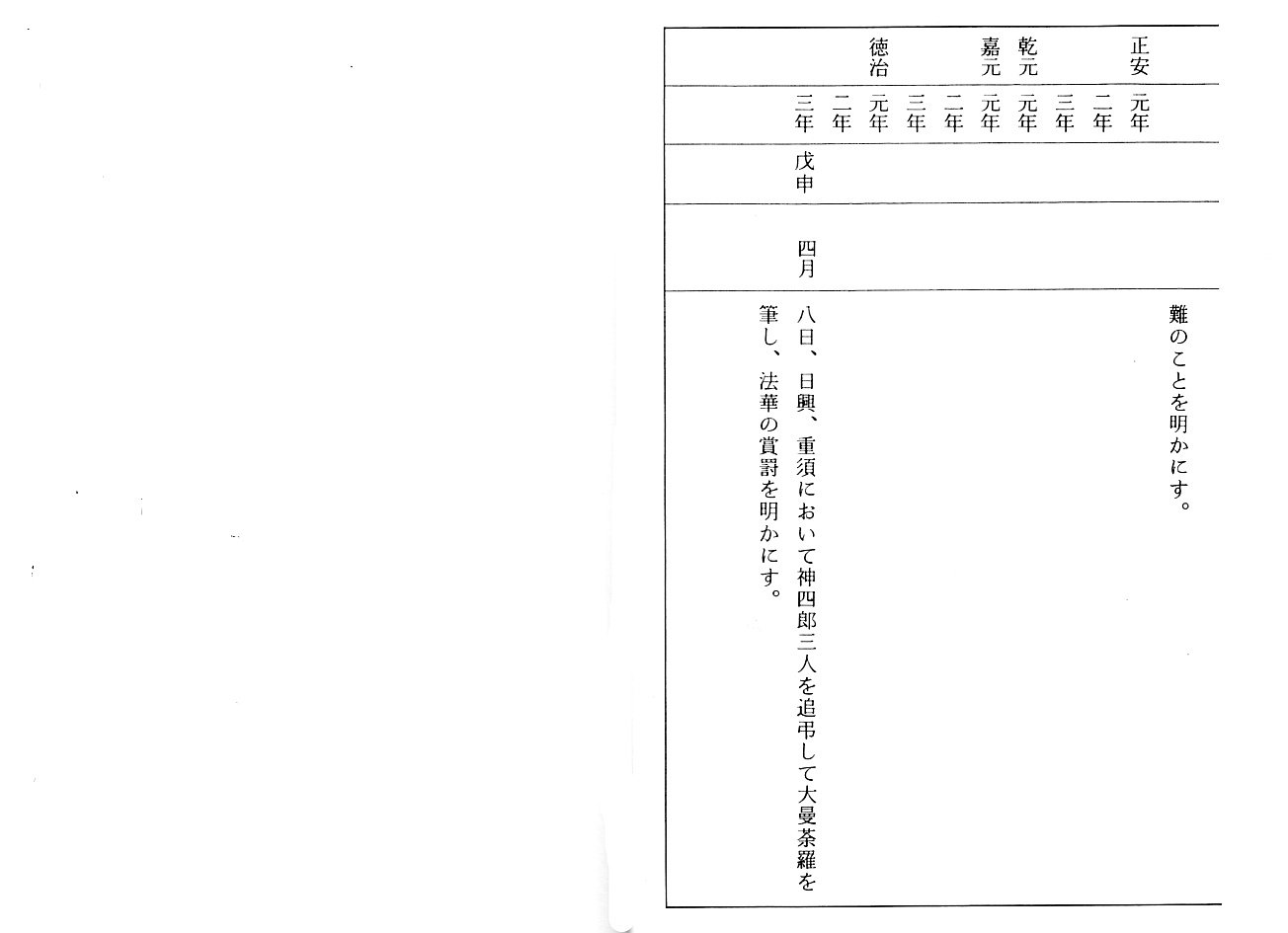
�@
�@
�@
�@
�@�M���@��̂��Ƃ́A�@�c��ݐ����A��q�h�߂̍ő�@��ł���������łȂ��B�j�����܂�����L�x�Ƃ����ׂ����Ⴊ�A�×��̓`���ɂƂ�Ɩ��ׂƊm���Ƃ�`���ĂȂ��B
�@���ł���A�Â��͓��t�́w�O�t�`�x�Ɉꌾ�A�����́w�s��q�ނ����r���x�Ɉꌾ�A���t�́w�N���x�Ɓw�ƒ����x�Ƃɂ͈ς�����ǁA�`�����d�Ďj�����ڂ݂��邩�̊��݂�����B
�@����ł͌Â��͖w��ǂȂ��A������̂́w�ƒ����x�̈ڋL�q�����r�ł���B�ߌÂɎ���āA�e��̎j�`�̒��ɑQ����s��s�Ɏ~�܂�A�w�N���y�فq�˂�Ԃ������r�x�̂��Ƃ�����ς������L���ĂȂ��B�ד����m�́w�^���`�x�ɑ�̂��Ƃ�������ɁA�@��̂��Ƃ͈ꌾ�������Ă���ʁB
�@�v����ɁA�䏑�ɂ͎U�����邪�A����𖾂�ނ�̊Ⴊ�Ȃ������B���̊�͂Ȃ�ł���w��\��x�ł���B���́u�\��v���A������J�����̂͑Q���ߍ��̂��Ƃł������B����Ȃ���A�w�\��x�ɂ͐_�l�Y���̖����֍��̂��Ƃ��a�߂̂��Ƃ��ڂ��Ă���ʁB����́A���̖@��I���܂ł̓������̕����ł���������ŁA�^���̏I�ǂ̎j��ƂȂ�ׂ����̂͌�J�R�́w��q�����x���̋L���ł���B���ꂪ���Ȃ킿�M���@��j�ɂ̌��Ƃ������ׂ����̂��Ⴊ�A��������܂����J�����Ă���ʁB
�@���̉���̔��͑吳9�N��2���ɋN�������̂ŁA10�N��3���Ɂu���@�@�w�S���v�́m����W�n�����s�����āA���̒��Ɏn�߂Č��J�����B
�@�����̂��Ƃ��ޗ�����邱�Ƃ�����ł���������A���m�̋L�����Ȃ��̂������Ȃ�ʎ���ł���B�܂����̏�A�����̍ޗ����ꎛ��R��㕂܂��Ă���Ȃ�A���̈ꎛ��R�����ɂ͖��Ăł������킯���Ⴊ�A�d�{���̒��R���̂ƍ����u���ď@��ʂɂ��Ĕ鑠���A���q�݂���r�ɑ��l�Ɏ����ʎ���ł������̂Œv�����Ȃ��킯�ł���B
�@�������A���̓�ւ��M�S������Γ˔j�����ʂ��Ƃ��Ȃ������낤���A�Ȃɂ��낱�̖@��W�̑m���������ɕx�m���t�n�̐l�ŁA�x�m�n�͎c�O�ɂ���`�@�ւ��R���ł��������߂ɁA�@��j���g����Ȃ������̂ł�����A�����܂����실���Ȃ������̂ł��낤�B����Ȃ���w�ƌ��L�x�̂��Ƃ�����������A�����Âł����������̂�����̂͑S�����t�̌䍜�܂�̎��̂ł��낤�B
�@�܂����̖@��̑�Ƃ����Ƃ���ɂ́A��剺�̕��啐�m�͈�l�����Â��炸�A�a�ߋ֍��Ǖ�20�l�́A�݂Ȏ����y���S���ŁA���ƂɋߌÂɂ܂ő��h���ʎЉ�̉����ɊÂ��҂ł��邩��A���R�ɋL�q�̌��h���肵���̂Ƃ��v����B
�@�܂��ܕ��@�x�A���̌䖳����ނ��̎���ɁA�M�̏�Ƃ͂����Ȃ���A���{�̖�l�̖����ɕ����Ȃ����������͏����ɂ��������ł��낤�B�����A�͂����Ă������������ł������Ȃ�A�y������`�ɓ���Ă͂Ȃ��C�W�q�Ă������r���������@�̐M�O�Â��ēS�̂��Ƃ��A���X�q���������r�Ƃ��ĉ�����O����̍��y���������A�_���S���̍����Ȃ����啐�m�̋C�������|����̂��肳�܁A�����đ傢�ɓ`������ׂ��炸�ł���B
�@�ߍ��A�e�R��ɂ̌��J�ɂ��j�����������Ƃ��납��A�ڂڂ��̂��Ƃ��L�`�搶������悤�ɂȂ�A���Ƃɓc�����m�̈�h�傢�ɐ�`�ɗ́q�Ɓr�߂���͂͂Ȃ͂��������Ƃł���A�܂����̌�`�L�̒��ɂ��A�F�c���̂��Ƃ����ɕx�m�̌Ó`�����ꂽ�͉x�������Ƃł���A���̑��̒��q���Q���ɖ��m��������悤�ɂȂ�������Ƃ��A��ނɂ������ɂ�������̂�����A�܂�����ʂ̂�����B�߂��Ă͕B�j�q�͂����r���k�ɗ����������āA����猻���̐��j����ʁq��ԁr�邱�Ə����Ȃ��B�{�@���M�̐l�ɂ��ď@�j�̑��w�ɐƂ��납��A���q�݂���r�ɑ��̕����ɕT�q����r�܂��Ƃ̋C�̓ł����A�����ɐ������j�����ׂĂ��̂܂܂̉�������݂���A���Ȃ������p�̘V�k�e�ł͂Ȃ��낤�Ǝv���B
�@�������A���̎j���Ƃ��ẮA
�@��1�ɁA�@����̕��������˂Ȃ�ʁB�����
1�A�@�c�吹�l�����̎��ɏ����ꂽ����
2�ɁA�������S�̍ٔ��p�̐\��
�@��2�ɁA�@��W�҂̒NjL�̕������܂��K�v�ł���B����́A
1�ɁA�J�R��l�́w��q�����x�̒��̋L��
2�ɁA����l�̒ǒ���䶗��̒[��
�������˂Ȃ�ʁB�܂���炱���ɋ���˂Ȃ�ʁB
�@�����̎j���ƂȂ�ׂ����́A�@�c�E�J�R�̕����̊e���ɎU�݂��邪�䂦�ɁA���ɗ��ڂ��Č��o���ɕւȂ炵�߂悤�B�܂��������w���炩�ɂ��邽�߂ɁA���̕����̉��ɋL�ڂ̐l���n�����������f���邱�Ƃɂ��邪�A���̉���̖ڎ��͍��̒ʂ�ł���B
�@
�@
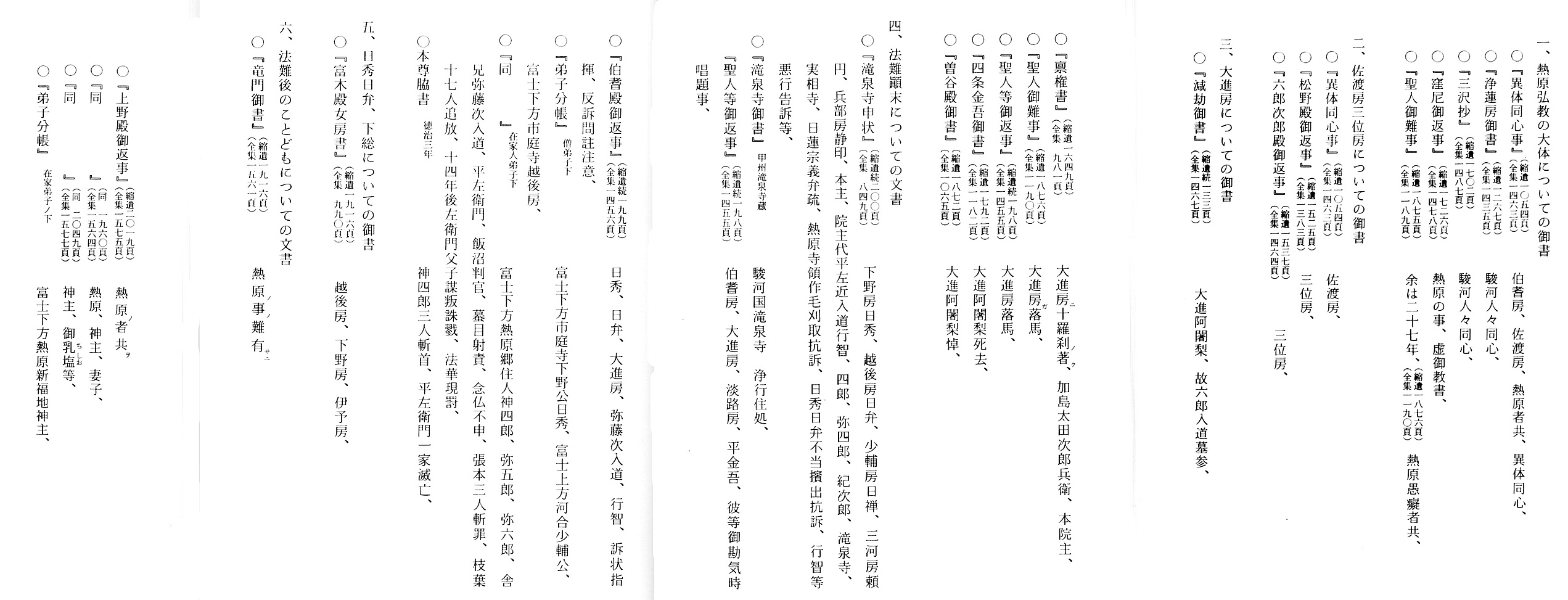
�@
�@
�@
����ɂĎ�v�̍ޗ��͋����s����������ł��邯��ǁA�Ȃ��R�ꂽ����̂���Βlj����悤�B���͂͂��̖ژ^�ɂ��Ē��ɂ��̌䏑�����n�ǂȂ���ΊԈႢ�͂Ȃ��͂��ł��邯��ƁA���M���w�̐m�q�ЂƁr�̂��߂ɂ���Ɉς��������������̂ł���B
�@�Ȃ����̘Z�ӂ̍��ڂ̒��ɁA�����E�O�ʁE��i�̎O�l�͕ʍ��ɂȂ��Ă��āA�����E���G�E���ق̊̐S�̓����҂̕ʍ���݂��Ȃ��̂́A���̎O�t�̌䎖�Ղ͎n�I�ɂ킽���Ă���B���̓�t���Ȃ���ΔM���̖@�w�͒���ʂ̂ł���B���ƂɁA���t�͂��̐Վn���܂łȂ��ꂽ�m�ł��邩��A�ʂ��Ă��̎����S������J�R��l�̊O�`�Ƃ�����ׂ����̂ł���̂ŁA���Ƃ���ɕʍ���݂��ʂ̂ł���B
�@���t���ʌ����i�[�́A�ꎞ�̔������`���ɂ����ʂ̂��A�������đ�̏Z�E�܂��͑n���҂̂ƂƂ��咣������������邩��A�킴�Ƃ��̊W�j���𖾂炩�ɂ��āA���̌�����炵�߂悤�Ƃ̔����q�т��イ�r�ɊO�Ȃ�ʂ̂ł���B
�@
�@
�@
��Q�@�M���@��j�����
�w�ّ̓��S���x�i�S�W�@1463�Łj�@�@�@�@����������Ȃ̏����B���˖[�̕X���A�ځq���Ɂr��ѕ��Ɏ��B���˖[���n�[�̎��A�M���̎ҋ��̌�u���A�ّ̓��S�Ȃ�Ζ����𐬂��A���ِ̈S�Ȃ�Ώ����������Ȃ��Ɛ\�����́A�O�T�O��]���ɒ�܂��Č�B
�@
�w�@���@�x�i�S�W�@1463�Łj�@�@
���̏�A�M�ӂ͑��N�ΐς�ĕ���@�،o�Ɍ�������q����r�����A���x�͔@���ɂ�����Č�S�����������������R�A�l�X���\����B���ޓ����\����B��X�ɏ���ē��V�ɂ���_�ɂ��\�グ�ČB�䕶�͋}����Ԏ��\���ׂ���Ђ�Ƃ��A�ҁq�������r�Ȃ�X��͂ō��܂Đ\����͂��A�و�苗����X�]�葁�X�ɂď������ւ���B
�@���˖[�͔��@���t�ŁA���n�[�͖������t�ł��邱�Ɛ\���܂ł��Ȃ����A���̌䏑�ɂ͈������Ȃ��B�䐳�M�ɂ͂������̂��A�ʓ`�̎����Ƃ������̂ƌ����B
�@�w�����ژ^�x�Ȃǂɂ͑�c�a�ւ̎���Ƃ��Ă��邪�A���邢�͎l������a�ł��낤�B�䕶�́u�M�ӂ͑��N�ΐς�ĕ���@�،o�Ɍ����v�Ƃ���ɂ��A�u�و�苗��q�����r���X�v�Ƃ���ɂ���������B
�@�܂��W���U���Ƃ݂̂����ĔN�����Ȃ��B���ژ^�����͕��i�P�P�N�ɕғ����Ă��邪�A����͏����Z�q���r���Ⴂ�ł��낤�B�v���@�́w���ٖژ^�q�����������낭�r�x�ɂ́A������Ƃ��čO���Q�N�������Ă���B�M���_�l�Y���̓��M�̔N�́A�O�����N�Ȃ邱�Ƃ����t���L�������ꂽ�̂ŁA���̍O���Q�N���͌䕶�́u�M���̎ҋ��̌�u���v�Ƃ���ɓK������悤�����A�O���ɓ���Ė������t���M���ɕz���������Ƃ͉��ɂ������Ă���ʁB
�@�w�������x�q�S�W�R�R�O�Łr�ɁA�u���̌�[�͏x�͂̍����킵�ē����������Č�ցv�Ƃ���ɂ��A�@�_�̂���ׂ������q�������r�Ƃ��Ċe��q�����e�n���Ɍo�_���W�߂ɍs���ꂽ���̈�l�̖������t���A���̖T�q������r��]�O���]������ꂵ���@���t
�̔M���z���̎�`������������ꂽ���̂ŁA���ꂪ����2����7���A���Ȃ킿�A�w���x���������Đ����Ɍ��킳���O�ɂ́A�g���ɋA���Ă����̂ł��邱�Ƃ����̌䕶�̈ӂł��낤�Ǝv���B��������A���̌䏑�͌������N�ɒu���ׂ��ł͂Ȃ��낤���B
�@�_�l�Y��Ƃ͍O�����N�̉��@�Ƃ��āA��̓��G�E���ٓ��͐g�͓V��^���̎��ɂ���Ȃ���A���t�ɋA�����Ė@��M�������߂ɂ�������Z�V��ǂ��o���ꂽ�̂�����2�N�ł��邩��A�A���̔N�͂��̛ߑO�ł��邱�Ɩ��ĂŁA�܂����̕t�߂̔M���̓y�����A����ɐ������ĐM���Ă������Ƃ��@�����ʂ��Ƃ͂Ȃ��B
�@���̌䏑�Ɂu�M���̎ҋ��v�ƗV���̂́A���Ȃ킿���̖����̐M�k�ł��낤�Ǝv���B���̌䏑�Ɉّ̓��S�̌x����V���̂́A���̔M����~�̑m���Ɍ��������ƂłȂ��B�����Ƃ����̎�̂́A���t��叫�Ƃ��Č��t���V���ɏG�t�َt�������ŁA���̑��̖����̏����m�܂��͐M�k�������ƂȂ��Ă̈�c�ł͂��邪�A�Ђ��Ă͕x�m��~�ɂ��y�ڂ��A�܂����Ɉ����̂��Ƃ��A�x�͈ꍑ�ّ̈̓��S�����サ�A�ʂĂ͂��̏��̉��̂��Ƃ����q�ӂ܂ł̐M�k�̓��S���ّ͈̓��S��]�܂��̂ŁA�܂��e�n�̑m�����A�x�m�̍O���ɑ���̊��҂����Ȃ��A�S�ɂ��d�˂����̂Ƃ݂��B
�@
�@�w��@�[��́x�i�S�W1435�Łj�@
�ԕԁA�x�͂̐l�X�F���S�Ɛ\�������Ќ�ցB
�@�w�O�x�@�i�S�W1478�Łj�@�@
�ԕԁA�x�͂̐l�X�F������S�Ɛ\�������Ќ�ցB
�@���̗��䏑�̕Ԃ����́A��͖����ɂ���A��͎ɂ��邪�A����͓���ł���A�܂��w��@�[�x�̂͋��t�̌�ʂ�������A�w�O�x�͌䐳�M�����݂���B
�@����͎����ĊȒZ���Ⴊ�A�M���@��ɂ��Ă��̉��\�̔��Q�ɒ�R���ׂ��A�x�͂̐M�k�̈�v�c������������ꂽ�̂ł���B
�@��@�[�Ƃ����̂́A�]�J�����̒�ő�i�[�̌Z�ɓ���A�����@���Ƃč݉Ƃ̑m�ŁA�����̔э��ƒ����Ƃ̊Ԃɂ����{�̕ʓ����߂��l���Ɓw�����ژ^�x���ɏ����Ă���B
�@�܂��A���]�̕l���S�̖������Ƃ��������A��@���Ȃ킿�����@�����߂̊J��ł���A�����Ƃ��A�ȂƂ��Ă��̎��̒h���ł���ƁA�����ł͂����Ă��邪�A�������Ȃ����킩���B
�@�����@���Ə�@�[�Ƃ͕ʐl�ł����āA���邢�͂��̐l�͋��t�̑����Ȃ�M�҂Ȃ鍂���Ƃ�����̐l�ŁA�x�m�S�ɁA���ƂɔM���Ɗi�ʗ���ĂȂ����ɏZ�݉Ƃ̑m�ł��낤�ƌv��v����͂����ɂ�B
�@�O��a�Ƃ����̂́A�x�m����̎O��ŁA���̑厭�E�q�����������ځr�̎O�q�������r�́A���̚������Ƃ�����̈ړ]�n���Ƃ������Ƃł���B�������x�͂Ƃ����Ă��A�x�m�S���̐M�ҕ��́A��������n����ڋ߂��Ă�̂ŁA���̔��Q�ɑ��ẮA�Ȃɂ��Ɨ͂������Ă����̂ł���B
�@�܂��w��@�[���x�̋I�N�́A�������N�ɒu���Ă��邩��A�w�ّ̓��S���x���������N�ƒ�ނ�]���Ƃ��Ȃ�B�w�O�x�͍O�����N�ɒu���Ă��邩��A�w�ّ̓��S���x���O�����N�ɒ�ނ�̏��Ƃ��Ȃ�B����ǂ��A�������ɔN�����Ȃ��䕶���ɂ����N�ɒu���ׂ����̂ƒ�ނ�̋L�����Ȃ�����A�m���̂��Ƃ͌���̌�����҂Ƃ���B
�@�w�E���O��Ԏ��x�i�S�W1478�Łj�@
���Ă͔M���̎��A���x���ȂĎv���߂��B�O�q�����r�������q���炲�Ɓr�Ȃ�B
�@��̉@���s�q�y�і퓡�������q��l�Y�̌Z�r�����A�x�m���������̖�l���ƌ���āA�āX���q���{�̌䋳�����U�����ĔM���̐M�k���Њd�q���ǁr�������Ƃ�������̂ł���B�ޓ��͌����Q�N�ɓ��G�E���ٓ�������Ǐo��������ǁA�@�ؐM�̋C���q���������r�𐄂���i�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��ŁA���q���ׂ��ׁr�ɐM�k����������̂ŁA�~�ނ����{�̖��ߏ����U�����āA�@��M����ȁA���G�E���ق�݁q���r���ȁA���@�̖剺�ƂȂ�ȂƁA���������̂��A���̎����q�Ƃ��r�ɋU��ł��邱�Ƃ��I�������B����͍O�����N�T���ł���̂ŁA���̛ߑO�̌������N���ɔޓ����p�����̂��U���ƒm���A�u�O�������Ȃ�v�ƗV����A����ɍ��n�䗬�ߒ��ɂ��A����̎דk�����R�x�܂ŋ��䋳�������ď@�c�𔗊Q�������Ƃ��ɋ�����ꂽ�̂ł���B
�@���̌E��Ƃ����̂́A������ɂ͎��t�q�Z�V�r�̕�ŁA������Ƃ����Ƃ��邪�A���q�����ԁr�邢�����킵���B���t�̕�Ȃ珼��ɕ悪����ׂ��ŁA���ɏ���̖@�@���Ɏ��t�䗼�e�̌ܗ֓�����āA�u���@�@���V�E�O���O�M�C�N�Z�������A�ꖭ�@����E�O���\����N�O������v�Ƃ���R���Ⴉ��A�܂����̕��𐳂Ƃ��ׂ��ł��낤�B
�@������A���R�̌E�q���̑�v�ہr�ɂ��鎝����q������M�q���������r�̕�́A���̓����̒n�����Ȃ킿���R�a�Ƃ���ꂽ����Ƃ̕v�l�ł����āA���Ȃ킿���̌䏑�̌E���O�ɓ���ׂ��Ǝv���B
�@�w���l���x�@�i�P�P�W�X�Łj�@
���錚���ܔN�q���M�N�r�l����\�����ɁA���[�������S�̓������̋��A���͌S�Ȃ�B�V�Ƒ�_�̌�~�E�叫�Ƃ̗��Ďn�ߋ��������{���̌�~�A���͓��{���Ȃ�B���̌S�̓��������Ɛ\�����̏����V�̎������̓�ʂɂ��āA�߂̎��ɍ��̖@��\���n�߂č��ɓ�\���N�A�O����N�q���ΐS�K�r�Ȃ�A���͎l�\�]�N�A�V���t�͎O�\�]�N�A�`����t�͓�\�]�N�ɏo���̖{���𐋂������B���̒��̑��\���v�Ȃ��A���ɐ\�����@���B�]�͓�\���N�Ȃ�B���̊Ԃ̑��͊e�e���m���߂���B
�@���̌䏑�͐��M���������āA�܂������O���Q�N�P�O��1���̂ŁA���Ȃ킿�M���@��̐^�Œ��̌䏑�ł���B����͂X���Q�P���̈���猖�܂��n�܂��ĕ\�����ƂȂ�A��@������N�����̂ł���ɁA����ɂ͌�l���w���l���x�Ƒ肶���邲�Ƃ��A�@�c�䎩�g�̈ɓ��⏬�����⍲�n�̑��������A�܂��ߑ��̋㉡�̑������V��E�`���̂��Ƃ��������Ă��邯��ƁA�悭�悭�q������ΔM���@����S�ƂȂ��Ă���B
�@�܂������́u�l�X�䒆�v�Ƃ��āA���Ɂu�O�Y���q��a�̋��ɗ��߂��ׂ��v�Ƃ��邲�Ƃ��A�ʂ��Ċ֓��̊e�M�҂ɉꂽ���̂��A��w��̂悤�Ɏl��a���a����Ȃ��ŁA�x�ؓa���a�������܂܂ɒ��R�Ɍ�������̂ł��낤�B
�@����͗v����ɔM���ꋽ�̖@��łȂ��B�x�m��т̖@��ł���B���ȏx�͈�~�̂ł���B���Ȃ��ȏ@�c��ꐶ�̌�@��ł���B�@��m���ꓯ�̑�@��ł��邱�Ƃ��A���̌䏑�̊e���ɂ�����Ă�B
�@����Ɉ�����䕶�̒��Ɂu���ɓ�\���N�v�@�u�]�͓�\���N�Ȃ�v�Ƃ���āA����ɂ͈����ʂ������Ɂu����ɓ��@��\���N���ԁv�@�u����\���N���ԁv�ƂQ�V�N���l�ȏ��ɂ���B�Q�V�N�̐����͗L�ӂ����ӂ�������ɂ��Ă��A�����@���̎n�߂�荡�O���Q�N�Ɏ���Q�V�N�Ԃ̑召�̖@��h��䅓�̔N�����w���ꂽ���̂ł��邪�A��Q�Ԗڂ́u�]�͓�\���N�Ȃ�v�Ƃ����Ƃ���͕��̌��J�̔N�����w�������̂łȂ��B����́A����́u���͎l�\�]�N�A�V���t�͎O�\�]�N�A�`����t�͓�\�]�N�ɏo���̖{���𐋂������v�Ƃ����ɑ����Ă̌䕶�ł��邩��A�����́A�@�|�d�����Q�V�N�ڂɖ@����I�����Ďn�߂ďo���̖{���������̂ł���Ƃ�����ӂƔq�����˂Ȃ�ʁB�@��{���ł͂Ȃ��āA�@��I���ɂ悹�ĉ����{�������̎������j�������̂ł͂���܂����B
�@����A�����������@�c�̖{�������Ƃ����j�����������낤���ƍl���Ă݂�ƁA��t�����Ē��ɂ��̕��������ĉ��d�{�������̈˕��Ƃ��ꂽ�悤�����A���ڂ̕��ւ͂Ȃ��悤�ł���B�@��I������{�������Ɖ^�тāA�����ɉ��d�{�����Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ�˂Ȃ�܂����Ǝv���B
�@���Ȃ킿�A��l�Y���d���肢�o���Ă����������L�闬�z�̎��ɉ��d���Ɉ��u�����ׂ���{�����A���̌��̂P�Q���ɐ������āA�ʂ��Ĕ��@���t�ɖ��t����ꂽ�̂��A�@�c��o���̖{�������A���Ȃ킿���̎��̌���ӂł������낤�ƁA���Ĉ�q�@�����̂ł���B
�@�������Ė�l�Y���d�Ƃ͂����Ȃ�o���̐l�Ȃ��Ƃ����ɁA��t�͂����g�؈���̖�l�Y�ɋ[����ꂽ���A�w��q�����x�ɂ͔g�؈�펟�Y�����q���ʂɂ͎����l�ƌ��r�͂���ƁA��l�Y�͌����ʁB�܂����~�����̒��e�ɂ́A�암�Ɗ��点�Ă���B�암�Z�Y���Y�A���Z�Y�O�Y�A����Z�Y������ŁA�����g�؈���̗L�͎ҋߐe�҂Ȃ炱���̓암�������ׂ����Ⴊ�A�����Ƃ��g�؈�ɖ�l�Y�Ȃ��Ƃ͒f�����ʂ��A�����́A���̖�l�Y���d�𖼑��唴�̒����A�ނ��떳�����ʂ̓y���S���̒��ɋ��߂����B
�@�@�c�吹�l�́u���[������ЊC�̐Β����˖����q�Ȃ�v�Ƃ��u���@�����ɂ͕n�����˂̎҂Ɛ���{�ɗ����Ƃ��o�ł���v�Ƃ�����ꂽ��쌩�ɑ��邱�Ƃɂ��Ă݂����B�����ŁA���̑�@��̑嗧�ҁE�_�l�Y�ɖڂ����B��l�Y���d�Ƃ����̂͐_�l�Y�̋����ł͂Ȃ��낤���B�����{�Ǝ��̉��N�ɖ��Y�Ƃ��������@�c���_�l�Y�Ɖ��߂Ă����������Ə����Ă���̂́A�S�R�q�܂�r���o�`�q���ł�r�ł��Ȃ��낤�B
�@��l�Y�̖�����R����B�O���Q�N�W���ɎE���ꂽ����l�Y�ŁA�s�뎛�ɂ���l�Y�l���q�l���̔N�͕s���ł���r����������B����Ŗ@��O�̊肢�o�ɁA���̖�l�Y�Ƌ�ʂ��邽�߂ɍ��d�̖�����������ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B�O���Q�N�P�O���P�T���̌䊨�C�ߌ�ɂ��A�܂��͂R�N�̎a�ߌ�ɋ��t���ǑP���{���c�܂ꂽ�܂ɁA�_�l�Y�Əܔ��̉������Ȃ��ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���Ǝv����B
�@�������A���̕ӂ͑��ɔM�S�Ȍ����҂����邩��A�����ꂻ�̔��\��҂��ƂƂ���B
�@
�w�@���@�x�@�i�S�W1190�Łj
���Ƃ��ĕ������铙���{��č��̈����U�X�ƂȂ������o�����A����ǂ��ŊϔO����B�����̐l�X�}���ւ���������B�܂������l�܂��ޏ��Ɍ��ւ�l�X���䂪�g�Ɉ������Ă�B�����܂ō��̈��ɍ��̒V���Ȃ��B�ޓ��͌��Ɏz�̔@���B�E����Ζ��n���։����ׂ��B�䓙���ɂ͍��̑��ɒl���Ƃ��㐶�͕��ɐ���Ȃ�B�݂������̔@���A�����͒ɂ���Ƃ���̖�Ȃ�Βɂ��炸�B
�@�ނ̔M���̋�s�̎҂ǂ�������܂��Ċd�����Ȃ���B�ޓ��ɂ͗B��~�Ǝv�А��B�P�����͕s�v�c�A�������͈��Ǝv�ցB��邵�Ǝv�͂Ή�S����������B�����Ƃ���Δ����n����������B���낵�Ƃ���Α�ɋ�������A�L�ɋ�����l�𑼐l�Ǝv�����Ȃ���B
�@��̔g���͑�C�ɖ�q�Ђ�r����B�M���̈ꋽ�̎������S�@��ɋ����ʂ��Ƃ͂Ȃ��B���˂ĉ����̓��@���ꂩ���Ƒ҂��Ă��镽���q���H�c���ȂƂ̖�l�����A���@�����Ɍ����Ă����Ȃ锗�Q�̑���q�����Ȃ��r��U���������ʁB���@�̎҂́A�Öh���̂��߂ɋ�B�Ɍ�����B���݂͖h��ɋꂵ�݁A�ŕ�������Βn���̋ꂵ�݂ł���B������ɁA�䂪���ɂ́A���܂����Γ��ȂƂɌ���ꂽ�҂��Ȃ��B���Ƃ����̂��т̑�@��ɋ����Ƃ��A�������݈�Z���̋ꂵ�݁A�����͉i�X�����̉��y�q���̂��݁r�ɋ�������Ɨ�܂���Ă���B���Ȃ킿�A��剺�ꓯ�ւ̌����ł���B
�@�㍀�q�̂��r�̌䕶�ɂ́A�܂������u�M���̋�s�̎ҋ��v�Ǝw���āA����𑼂̈���范�シ��悤�ɉ��삷��悤�ɐ��߂��Ă�B���q�ɕ߂�ꂽ�Q�O�l�̒��ɁA�_�l�Y�R�l�͒��{�Ƃ�����ʂ�A�݂��ƂȖ@�؍��A���m���y�ʍ��_�ł������낤���A�]��17�l�܂����Ɏc�肵�V��w���͂����͂䂭�܂��B���݂̐M��̂��߂ɐi�ނɖ����Ă�A���Ȃ킿��s�̎҂���߂����������ł��낤���A�����ɓ��ɋ�s�̎ҋ��Ǝw���ꂽ�͎̂��q���Ƃ��Ƃ��r���y���D�����ł���āA���B�̕��m���������ʂƂ�����w���ꂽ���̂ł���B
�@���炭���t�w��q�����x�ɂ��ɁA�m�����Ƃɂ��炴��҂��W�߂č݉Ɛl��q���ƕW���Ă���B�݉ƂƂ́A�����ɔ_�Ƃ̂��Ƃł���B���̐l���́A���G�E���ٗ��t�̒�q���ɂĖ{���̎�l���Ȃ�����߂ɒu���āA�ʂ��Ė@��̎���������Y���Ă���B���Ȃ킿�x�m�����M�����Z�l�_�l�Y�A����ܘY�A����Z�Y�̎O�l�B���ɋ��t�̒�q���ɂāA��싽�Z�l���l�Y�A����O�Y�d���A�������Y�A��싽�V�ܘY�A����Y��v��ƍŖ���̌ܐl�B���ɏG�t�̒�q���ɂāA�M���Z�Y�g��q�g��ւ̏@�c�̖�䶗��́A���t�̓Y�������t���ɂċ��s�E���o���ɁA�������Ă���B�O���O�N���̓��t�ł���B�r�A���V���n�_��A���O�Y��Y�̎O�l�B���ɕَt�̒�q���ɂāA�]���펟�Y�A�s�뎛���Y���v�����A�����Y�A�������Y�A����l�Y�����A���c�����Y�̘Z�l�������Ă���B
�@����������t��肵�đ吹�l�̌�{�������^����ꂽ�̂ł���B���̊O�ɏ@�c�̖{���q��̉h�ʍ݉Ƃ̎҂������������낤���A���̕����ɂ��ΔM�����ɂ��A�s�뎛�ɂ����ƌ�Ɛl�̎m���͈�l���Ȃ������̂ł���B
�@�䂦�ɏ@�c�́A���̊���ɏ����āu�M���̎ҋ��v�Ƃ��u�M���̋�s�̎ҋ��v�Ƃ��A�����Čh���p�����ʁB���̐��ԓI�h����ʔ_�v�y�����A�@��ɏ����Đ�Ö��]�L�̓S�ΐS�q�Ă�������r�����킵���̂́A�ЂƂ��ɏ펖�q�������Ɓr�łȂ��B����F�̔ޓ����g�S�ɓ���ς�点���������̂ł��낤�B������������߁q�r����Ǝv����寖ځq�Ђ��߁r�̖���U�X�ɕ����Ē��������߂������q�嗊�j�e�q�̑̂��炭�͏Ύ~�疜�̎���ł���B
�@
�w�ّ̓��S���x�i�S�W1463�Łj�@�@�����[�E���n�[�̎��A�����̎ҋ��A�i�O�ɏڂ����o�����j
�@
�w����a��Ԏ��x�i�S�W1383�Łj�@
���̎O�ʖ[�͉���̎҂Ȃ�Ƃ��������@�،o�̖@���\���҂Ȃ�Ε��̔@���h���āA�@�����q�˂���ׂ��B�˖@�s�ːl�A������v���ׂ��B
�w�Z�Y���Y�a��Ԏ��x�i�S�W1464�Łj�@
�����A�O�ʖ[�������ׂ���B
�w�l������a��Ԏ��x�i�S�W1182�Łj�@�O�ʖ[�����A�����l�Y�����A���̎��͈������_���_�Ɛ\�����ЂČ�B
�w���l���x�i�S�W1191�Łj�@�@���ׁ͍X�Ə����͎z���N�N���������ɐ\���Č�ւƂ��A���z�̓�E����[�E�\�o�[�E�O�ʖ[�Ȃ�Ƃ̂悤�Ɍ�A���a�E���o�����E
�~�[���^�������ҋ��́A�h��鎽�ɐ��������A���肽��悤�ɌB�O�ʖ[�����͑�s�v�c�̎��Ƃ����Ƃ��A�a���̎v���ɒq�b����҂����܂��������Ƌ�s�̐l�v���Ȃ�Ǝv���ĕ���\���Ō��A�����ƂȂ�đ��ɂ�����ČA���X�U�X�Ƃ��ɐ\�������Ώ�����ӂ����Ȃ�B�]��ɕs�v�c���ɐ\�����肵�Ȃ�B���z���\���Βs�l�q��������r�ǂ��͎��S�̎�������Ɛ\���ׂ��B���̂��߂ɐ\���B�����̎��͔ޓ��̐l�X�������͕|��������ނƊo���B
�@���n�[���Ȃ킿�������t���A�M���z���̎�`�������ꂽ���Ƃ́A�����̉��ɂ��������ʂ�ŁA����͌������N����ŁA���ꂩ���ɂ͂���ɂ��̗l�q�������ʂ̂ł�����A�������Č��t������N���A�܂��͏Z�E�ł���Ɩϐ���痂��イ����҂��ł����B���̔j�܂͑�l���̏��̑�̉��ł�������A�����ɂ͏����ʁB
�@�w�N���q�˂�ԁr�x�y�сu�ƒ����q�����イ���傤�r�v�ɂ́A�a������@���@�c�̌䖽�ł���`���������Ə����Ă��邪�A�䏑���̎j���Ƃ��ׂ����̂ɂ͕Ў��q�������Ɓr�������ʁB�܂��w��q�����x�ɂ��A�a����͋��t�̑���q�ł��邩��A���̎g�p�͎t���̐��ӂł���ׂ����A�@�c����킴�Ɣh������ꂽ�Ƃ������Ƃ͗�̓`���̌��ŁA���̉��{�E�����������̕z���n�̐ՂƂ����̂́A����ɑ�Ȃ���ŁA�Ȃ��̎j���������ʂ���łȂ��A�����������ċ�����̂ł���B
�@�O�ʖ[�Ƃ����̂́A�����o�g�̓��s�̂��ƂŁA���q�Ƃ��Ă͘V�y�ł���A�b�R�����̊w��̌����ς܂�Ă��邪�A�c�O�ɂ��M�s�s���ł��������߂ɁA���Ɏt�G��掖@�̈����ɂ����Ď��ɕ������������B���̐l�́A�@��O�̌䏑�ɂ͎j���������Ⴊ�A���p�ł��邩�炱���ɂ͈����ʁB
�@���̏���a�ւ̂͌����Q�N�P�Q���X���̌��ł���B�Z�Y���Y�ւ̂͌����Q�N�R���P�X���̌��ł���B�����q���͂�r�S�̏���Ƃ����A�x�m�S�̉����Ƃ����A�g�����͈�����̏����Ⴉ��āX���������āA���̊Ԏ����������ɂ��M���z���ɂ���o�����Ȃ��̂́A���R���肤�ׂ����Ƃł��邪�A�ǂ�������t�����叫�ŁA�܂�����ɂ������ɂ������[������A�������̎O�ʖ[���莝���s�����ŊԂ��Ȃ������グ�āA����Ɋ��q�ɏo�āA���̔N�̂U���X���ɌK�J�q���킪��r�̗��ۖ[��_�j���Ďl������̑厖�����o���q�ł��r���ꂽ���̂Ƃ݂��A���̌�͂ǂ��ƍ������������ɔM���̂��Ƃ��������ċ��t�̎ז��ɂȂ邭�炢�ŁA��ɂ͔��̎ד��ɓ��ݖ���ꂽ�炵���B�w���l���x���̌䕶���Âɂ��̂��Ƃ������Ă���B
�@�����Ȃ�s������������A�����Ȗ��S�Ȏ��ɕ������ꂽ���́A�䕶�Ɉς����Ȃ��B�`�����c���ĂȂ�����Ƃ��A�����䎜�߂̌x��(���܂��߁r�͂������炵���B�܂��u���̂��߂ɐ\���v�Ƃ��u�ޓ��̐l�X�������͕|��������ނƊo����v�Ƃ���ꂽ����݂�A���@�̌����Ǝ������Ɍ���ׂ����炩�ȕώ��ł������낤�Ǝv���B�܂��u���_���_�Ɛ\�����ЂČ�v�Ƃ̌䕶������A��x���̓��������Ƃł��낤�B�܂��Ƃɐɂ����l�ł������B�M�s�w�̎��悪�����ł����ĂS�T�N�����������A�U�V�̑�Q�ʂɕK������ׂ��m���̂ɁA�s�M���s����Ȃ�Ђł��邱�Ƃ́A���̎O�ʖ[���i�[��ʂ��āA�@�c�������ɐ��ߒu���ꂽ�̂ł���B
�@
�@
�@
�w�����䏑�x�i�S�W1467�Łj���̑�i��苗����̘Z�Y�l���̌�������B�́A���̖@����Č�l�X�ɂ́A�֓��̓��Ȃ�Ή����āA���̕�Ɏ����ǂ���Ƒ����Č�B�R��ǂ������̗L�l�͓��@�ޏ��q�������r�։����Ȃ�A���̓��Ɉꍑ�ɕ��ցA�����q�܂ł�������͂A�S��������l�Ȃ�Ƃ���������̐l�X�ڂ�����ʂׂ��B���܂ŖK����͂˂ΐ��삢���ɗ�����������Ǝv�ւΗL��l������Ȃ�B���̒��悸��q�������Č��Ɏ�����ǂ܂��i�����Ȃ�B���̗R��S����ցB
�@�M���z���R�̑匳���͖��_�@�c�ł��邪�A�@��n�̑叫�͓�����l�ŁA���G�E���ق̗��t�͍��E�̕����ł���B���̑��̓����߉��̐l�X�́A�ꎞ�̗V���ł�������A�����ł�������ł���B
�@���̒��ŁA���߂͂����ł��Ȃ��������A��ɂ͑S����������掖@�R�ɍ~��A���̒܉�q�������r�ƂȂ��ĎU�X�ɖ@���R���ꂵ�߂��t�q�g���̑��m������B���ꂪ�A���̑�i��苗��ł���B���̑�i��苗��܂���i�[�ƁA�O���ŏo�����O�ʈ�苗��܂��O�ʖ[�ƍO���Q�N�T���P�V���̕x�ؓa�ւ̏�ɁA�u���s�[�����̎��A�s�ւɂČ�v�Ƃ�����s�Ƃ̎O�́A���l�ł��邩�ʐl�ł��邩�B�������䏑�̏�ōs�������R�q�͂�����r���ʂ���A���炩�ɓ���l�Ȃ�ׂ��M���@������������t�m�Ƃ����Ă���l������B�܂��A������ʂ̎j���ł́A��i��苗��͑]�J�����@�@�̒�ŁA�O�ʈ�苗����s�͕x�ؓ�����E�̒�ł���Ƃ��Ă��邪�A�m���Ȏj���ɂ��܂��͐M���ׂ��`�����炫���̂ł͂Ȃ��낤����ǁA�܂�����ɂ��l�������悤�ł���B����͌���̌����ɏ���B
�@���́w�����䏑�x�ɂ��Ă��A�O���Ɍf�����w�Z�Y���Y��Ԏ��x�ɂ��Ă��A��i�[���O�ʖ[���O�サ�ĕx�m�̍����Ƃɔh������ꂽ�悤�ł���B�䏑�ɂ́A�����̐l�����t�̕����Ƃ������ׂ��Ƃ��ʓ����Ƃ��ĂƂ������ĂȂ��B���_�A���̎���̂��ƂƂĊi�ʂ̎��߂͂Ȃ������낤�B
�@���̂Q�m�͂Ȃɂ��̏����ʼn����ɍs�����ƂɂȂ����B�\�ʁA�����̍����Z�Y�����̕�Q�Ɍ�t���̌䖼��Ƃ������Ƃł������B���̓s���ŋ��t�E�G�t�E�َt���̍O���������Ă悢���炢�̋��͂������낤�Ǝv���B������N�y�Ƃ����A�w���Ƃ����A���t��肸���Ɛ�y�ł��邩��A�x�m��т̑m���͎��Ȃ̟����ɏW�܂���̂Ǝv������A��N�̋��t�Ȃ�ǂ����������̈ꖡ�̑m���̑��叫�ł���A����̈ꖡ�̑m���̎t���ƂȂ��Ă����A�܂��M�ґ��ɂ͏��a�E���R�a�E�R��a���n�߂Ƃ��Ė@�������d��҂���ŁA���Ƃ���Ȃ����킳�ꂽ�����̍����Ƃł͎�l�Z�Y���q�͋��t�̒�q�ł���A���̉����͋��t�̏f��ł����Ă݂�A�ƂĂ�������̂��悤���Ȃ��B����l�́A���̕ӂɎ��i���Ă������ċt�G�ƂȂ���������߂̂��߂ɔM���@����䂫�N�������̂ł���悤�ɂ����Ă��邪�A�������煂łȂ������낤���A�S�́A���̐l�X���w��������N�y�������������ɐM�s�Ɍ��ׂ��������̂ŁA���ɖ@�G���̌��ʂɗ����������̂ł��낤�B���Ă܂��w�����䏑�x�̓��ʂɂ͉����Ƃ������Ƃ������Ȃ�����ǂ��A�w����������Ԏ��x�q�S�W1461�Łr�Q�l�@�����āA�����l�����̂ł���B
�@�܂��A�O���Ɉ�����Z�Y���Y�̕��́A�A���̎��Y���q�͉����̑��c���Y���q�Ȃ�ׂ��A�Z�Y���Y�͍����Z�Y���q�̒�ł��낤�B����ژ^�ɁA�g�؈�Z�Y���Y�Ƃ��Ă��邪�A�����͎��ʁB�w��Ԏ��x�̍��������͘Z�Y���q�̕��ŁA���́w�����䏑�x�̘Z�Y�������Ȃ킿���ł��낤�B��N�͂��܂��Z�q���r��������A�������N�����N���̓��ŁA���̌䏑�������Q�C�R�N�̂��̂ł��낤�B�ł��낤����ŁA�r���s�������Ⴊ�A�����Z�Y���q�͖@���E����A�i�m3�����N3��15���A���̉������鋻�t�̏f�ꖭ���͉��c2�ȓєN5��13���𖽓��Əd�{�ɓ`���Ă���B�܂��A�f�ꂽ�邱�ƁA�y�јZ�Y���q�͓������̒�q���邱�Ƃ́A�w��q�����x�ɏڂ炩�ɏ����Ă���B
�@
�w�g�����x�@�i�S�W981�Łj�@�@�@�@�����̍����̎����߂Č̂���ďo������B�����̑�c���Y���q�E��i�[�A���{�@��������ɂƂ�\�����A�悭�悭��������ցB�����͌o���Ɏe�ׂ��邱�ƂȂ�B�@�،o�̍s�҂��Α�Z�V�̖����̕K�����ׂ��ɂČ�
�w�@���@�x�@�j�i�S�W982�Łj�@�@�@�@�@
��i�[�����A��X�������킵�Č�l�ɁA���X�Ə����グ�\��������ցB��i�[�ɂ͏\�����̜߂������ЂĈ��Ԃ��������ӂƊo���B�������̎g�҂Ȃ�Ƃ��߂��Č邪�A����Č�Ɗo���B���S�l���S�͂�������ɂĂ͌�͂��B
�@���̌䏑�͕x�ؓa�ւ̂ł���B��i�[�̂��Ƃ���ӏ��ɏo�Ă��邪�A�ꏊ�Ƃ��Ƃ��炪���ĂłȂ��B�n�̕��͂��̌䏑�̋N��Ƃ���̗����̂ƕx�ؓa�Ƃ̑Θ_�ɊW����炵���B�����Ɂu�{�@��v�Ƃ���͒N�l�ł��邩�B�w��̐\��x�̖��ɂ��u�R��Α����s�P���s�̉@���s�q�����Ղ����A�����{�卟�̏d�Ȃ�E�ꂪ�������v�Ƃ���B��̖{�@�傪���l�ł��������A�^�ԂƔM���Ƃ́A��������V��@�؏@�̂��Ƃł���A�y�n�͂�������Ă��Ă��Ȃɂ��̘A������������������ʁB�����̑�c���Y���q�̑�c�́A�����̑��c�ŁA��i�[�̐e���Ă�������������ʂ��A���́w���l���x�̗Ɠ��l�����Ƃ��邪�ւ�����̂ł���B
�@��̕��̌䕶���Ȃ����Ă��ʁB�܂��u�����̎g�҂Ȃ�Ƃ��߂��Č邪����Č�v�Ƃ���̂́A��i�[�͈�x�����������A�����͉��S�������Ƃ����Ӗ��ɂ݂��B�u��i�[�ɂ͏\�����̜߂������ЂĈ��Ԃ��������v�Ƃ���̂��A�@�؎��̏\�����̐_�͂ĉ��S�������Ƃ����ӂɂ݂��B�����͉����̎����A�����͔M���ł̂��Ƃł��낤����ǂ��A���f�̎j���ʂ͎̂c�O�̎���ł���B
�@
�@
�w���l���x�@(�S�W1190��)�@�@
���c�e���E���莟�Y���q�ю��j�E��i�[�����n���͖@�،o�̔��̌����邩�B���͑����E�ʔ��E�����E�����l��B���{���̑�u�a�Ƒ�Q���Ɠ��m���Ƒ������U�߂���͑����Ȃ�B�u�a�͖����Ȃ�B���c���͌����Ȃ�B�e�X�t�q���̐S�����o���Ă����ɐl�Ђ��Ƃ��|�Â邱�ƂȂ���B
�w���l����Ԏ��x�@(�S�W1455��)�@�@
���̎���ӂ�Ȃ���̕��ɂ͉ȂȂ��ƊF�l�\���ׂ��B���A��i�[�����n����ׂ��A����ΐl�X���Ƃɕ|�Âׂ��B
�@���̓�̌䏑�ɑ�i�[�̗��n�̂��Ƃ������Ă���B���̗��n�͂X���A�@��̌��܂̎��ɔn��ɂ���đ��掖@�҂��w�����āA���G�E���ق̐M�k���U�X�ɉ��ł��鎞�̂悤�ɂ����Ă���̂����邪�A���͂�������]���O�̂��Ƃł��낤�B�O���Q�N�ł͎�N������ʂ���A�O�����N�̋㌎�ȑO�̂��Ƃł��낤�B
�w�\��x�ɂ́A�O���Q�N�̂S���ƂW���ƂX���Ƃ̂R�̎E�������ڂ��ĂȂ�����ǂ��A���̊O�̎��ɑ�i�[�E�e���E���Y���q�����n��Ŗ@�؏O��ǂ������鎞�A�Ƃ��ɗ��n���ĕa�݂������Ƃ��������B���ꂪ�a���ŁA��i�[�͊Ԃ��Ȃ��㎀�����B����͖@�؏O�𔗊Q����掖@�̕ʔ��Ȃ�Ƃ̗��R���w��\��x������Đ\�����Ă�����Ȃ�A���q�⒐���̖�l�B�ɂ���ʂ̐l�ɂ����ɓB��łł��낤�ƁA�@�c���{���ɂ��Ċ��q�֏o�{���鋻�t��G�t�E�َt���������ス��ꂽ���̂ł���B
�@
�w�l������a��Ԏ��x(�S�W1182��)
���A��i���t���̎����̎��A������˔k�q���r�����ł�����ɉ߂��ׂ��ƊF�l���U���Ȃ�B���ɂĂ�������B�O�ʖ[���������l�Y�����A���̎��͕��_���_�Ɛ\�����ЂČ�B
�w�]�J�a��Ԏ��x(�S�W1065��)�@�@�@
�̑�i���ŗ��̎��A�V��������ւǂ��A���ꖔ�@�،o�̗��z�o�����ׂ������ɂĂ����Ǝv�����ׂ��B
�@���̗����ɑ�i�[�̎����̂��Ƃ������Ă��邪�A�l��a�͍̂O�����N�X���P�T���̎���ł���B��i�[�̎����ɋ߂����ł��낤�B�]�J�a�̂́A���̖�����N�̍O���Q�N�W���P�V���ł���B
�@����Ɏl��a�ւ́A��i�ɑ��Ă��O�ʂɑ��Ă��A�@�c�̂�������ׂ��挩�̈�킴�邱�Ƃ�������Ă��邪�A�]�J�a�ւ́A���������̐e���Ȃ�ɂ����̈ӌ������킳��A�@�،o�̍O�܂�ׂ���������ƒ��߂�ƈԂ��߂��Ă���̂́A�s�M�s�`�Ȃ�Z����������M�҂ւ̌䓯��Ă���Ɣq���ׂ��ł��낤�B
�@�l��a�ւ̂ɂ��A��i�ƎO�ʂƂ͕ʐl�̂��Ƃ��v����B�����ɂ͈��p���ʂ��A�w���l���x�ɂ��@���������A�܂��w�ٓa������x�q�S�W1224�Łr�@�́u�ٓa�E��i��苗���[�E�O�ʓa�v�Ɨ���̂́A���_�ʐl�̕��ł��낤�B����͈��ɋL���Ēu�����A�O���f�����肵�䏑�������ɍāX�n�ǂ��A���R�ɑ��Ă̂��Ƃ����������邱�Ƃ���Ǝv���B
�@
�@
�w��\��x�@(�S�W1849��)
�x�͂̍��x�m�S������̑�O�A�z��[���فE����[���G���ނ�ŕٌ����B�����@���A���̍��ߓ����s�q�A�����̎��Ȃ��ǁq�͂��r���Ձq�������r����߂ɕs���̗��i�q��r��v���͈���Ȃ����ƁB
�i��ɓ��킭�A���G�E���ق͓��@�[�̒�q�ƍ����B�@�،o���O�̗]�o�A���邢�͐^���̍s�l�́A�F�����č����㐢�����ׂ��炴��̗R�A�����\���]�]��ӁB
�@�w��\��x�Ƃ����̂́A�s�q�E�퓡����������掓k�̎v�q��邾���݁r���Ȃ肽���āA���ɍO���Q�N�X���Q�P���ɁA�G�t�����M���̐M�҂̔_���𗊂݂āA���������̂ɕ�������ė��\�ŝ��q���傤���Ⴍ�r��������łȂ��B����Ɏ�����ύ��q�ւr���āA���G�E���ٓ����������Â����Ĉ��͊�����Ă��܂��A�|����ттĉ@�啪�̖V���ɂ܂ŗ��������ƁA���q�̖⒐���ɑi�����B
�@�ޓ��͒������{�̖⒐���̖�l���ɂ��A�n���́A���Ȃ킿�x�m�����̐�����ɂ��A�������邩��A���̑i��͗e�ՂɌ���グ�ɂȂ��āA�������\�̒��{���߂̉������M���ɏo�����āA���Đ����ɍS�������Ă�_�l�Y��20�l�̐M�k�����菬��ɔ���グ�Ċ��q�Ɉ������Ă��B
�@���ƂɎc�����Ȏq�����̏D�V�q���イ����r�ڂ����Ă��ʂ��A�����ɂ���A���͂̑m���ƂĂ������ɂ͂͂ނ����ʁB�������A������l�̋��ւ����̓�������̕��ւ��}�g���y�����B���t�Ƃ��ďG�t�E�َt�ɓ���E�������̐l�X���z�����킹�đP���𗧂Ă���B
�@�����q������Ԃ�r�̏d�������҂ŁA�O��20�l�ɑ����ď��߂�ꂻ���Ȏ҂̉B���q�����܂��r�́A�K�������̋����������Ƃł�����Γ��a������B�u���Ő����ɍ���҂̎蓖�Ă���������������A���ꂩ�犙�q���{�ɂ͕s���̌䉺�m�̒V������ĂQ�O�l�̏��l�q�߂����Ɓr�����߁q�������ǁr���Ă��炢�A�@��㓙�̕s�s�Ղ₱��܂ł̓��G�E���فE���T�ɑ���s�@�̏��������������ɁA�@���̖ƐE�����ɂ�Ȃ�ʁB�x�X�q���������r���Ă��20�l�̎҂��A�����Ȃ�ߏd�̏������ʂƂ�����ʁB
�@�����ő����ł����������̂��A���́w�\��x�ŁA�����g���R�Ɏ����čs���ď@�c�̌�ڂɂ�����B�����Ƃ��吹�l�̌䋖�ɂ́A���߂��狐�ׁq�������r�̒��i���Q���Ă�̂ŁA���Ɍ�ӂ�ɂ߂Ă�����B���̏��u���ɂ����Ƃ��Ƃ����āA�u�\��v�̈ĕ��ɂ́A���ꂱ��ƏC���̕M������ꂽ�B�������⒐���ɏo��Ȃ�A�����������悤�Ɏ��v�炦��ƌ��ɂ��`���ɂ��ׁX�ƌ�ӗV�ꂽ�̂ł���B
�@�������c�O�Ȃ���A���̖ڈ������t�ّ̕`���o�łʑO��20�l�͓��S�ɋy�̂ŁA���������́w�\��x�̍R�ق������̌��ɂȂ�Ȃ��������A�����̔��Ȃ͂������낤����ǁA��́A�����j���̓�������Ă����B�������̂��̂��ٔ�����l���łȂ��B��r�ɖ@�̐M�k�𔗊Q���āA���̍L�z��h矁q�ڂ����r����悢�̂ł���B
�@����Ƃ��A���{�̂����̎v�͐������Ȃ��A�قƂ�Ǘ�������ǁq�悤�����r�����̂ނ����Ƃł������B�����݂̂Ȃ炸�A�����q�傻�̎҂��@���������d���̈����Ɉ�ƑS�ł������B
�@���́w��\��x�̈ĕ��́A�َt�������Ɏ����čs���ĕ�̖������ɓ`����Ă������A��ɒ��R�̖@�،o���̏Y���ƂȂ����B����q�ӂr�t�̋L�ɂ��A�㔼�͏G�t�̕M�Ȃ�ׂ��@�c�̌�Y�킪���邪�A�O���͑��M�ł���Ƃ̂��ƁB���̌㔼�ɓǂݓ���Ƃ���\���ӏ����邪�A����t���́w�k����╶�x�̌�ɂł����{�ɂ��A�Ȃ��������������ɂ��̓�ǂ����̂܂P�����Ă���B���̍G�˔��w�̐m�ɂ͗e�Ղɓǂ߂���̂Ƃ݂��̂͗L����Ƃ��Ⴊ�A�����ɂ͐疜�x�l�������Ă��ǂނ��Ƃ��ł��ʁB
�@������ɁA���̌Â��ʖ{���É��̊������ƎR���̑�Ƃɂ���B����ɂ��A��ǂ̉ӏ��������Ɠǂ߂�B�w�ҒB�ɂ͑����܂ʂ��A���v�����ĉ��ɂ��̎ʖ{�ɂ���ėp���̒��������A�܂��P�_�����ނ邱�Ƃɂ����B�������A�m���̏��͂���ɐ��{���n�q������̂��Ƃ���B
�@�ߏ�A�w��̐\��x�ɂ��đ�̂��q�ׂ�����A�������炷���ɖ{���̎j���ƂȂ�ׂ��_�ɂ��ĉ�����悤�B
�@�x�m�����Ƃ����̂́A�x�m�S�̑�{���y�т��̖k����������q���݂����̂��傤�r�Ƃ��A������암�����悻�������q���������̂��傤�r�Ƃ��Ă���B���q����ɂ͖��_�A��������܂ł����̖��̂��s�Ȃ�ꂽ�B�������A�ډ��̉��X����������ʼn��X�������������Ƃ������m�ȕ��͂Ȃ��Ȃ��������ʁB
�@���́w�\��x�ɂ́A�M�����Ƃ��������q���ȁr������������Ă���́A�ĕ��̈ꎞ�̑a����������ʂ��A�������̎�����{�̎������ƌ�����ׂĂ̑厛�ł���������ł����낤�B
�@���邢�͂��̎��������Ď������̖������̂��Ƃ������҂����邪�A��Ȃ����ł���B�܂��M�����͉������̓��̂悤�Ɏv������A���������̊O����O���_���̗]�g���M���@��������N������Ƃ̌�T�q����܂�r�̓`����肵�Ă��A���m�ɔM���@��Ƃ������̂��A���邢�͗����̖@��𑍍��������肩������ʂ��A�킴�Ɖ����@��ƌĂёւ�铙�̋������Ȃ����ނ������邪�A�����͉߂����߂���悩�낤�Ǝv���B
�@�V�����̌Õ����ɁA�����Ɖ����Ƃ������̂�����B���邢�͉����͉����̊O�ł�������������ʁB���t�䐳�M�́w�������\��x�ɂ͖��炩�Ɂu�������������v�Ƃ���A���ۓ�N�̌�{���[���ɂ́u�x�͍��������v�Ƃ���āA�Ƃ��ɉ������Ƃ͏����ĂȂ��̂��Q�l���ׂ�����B
�@�܂��A���́w�\��x�̖��ɁA�u�����������ɗ�@�����v�Ƃ������傪����B����͂��̉��ł��邪�A���ꂪ�{���W�̂Ȃ����̂Ƃ�����ׂ��ł���B
�@�����Ƃ����̂́A���́w�\��x�ɂ��Α��@�ł���B���Ȃ킿�������Ɠ��@�ł��邯��ǂ��A�������̉��얖�Ȃ邱�Ƃ����炩�Ȃ�ɑ��āA���̎��͓����Ƃ������q�����Ƃ��r�Ƃ��킩��ʁB���_�A�J�R���̂킩��悤���Ȃ��B�w�O����^�q�������낭�r�x�̐��a�V�c�̒�όܔN�ɕx�m�S�@�Ǝ��������Ē�z���q���傤�������r�ƂȂ��Ƃ������Ƃ�����B��z���Ƃ����̂́A�������Ɏ������̊����ŁA�Z�m20���q�ɂ�r�Ƃ�30���Ƃ��̕}���Ă��A���{��艺�n���̂ŁA�܂��S���̑厛�ł���B���̖@�Ǝ��̖����ǂ��Ȃ������킩��ʂ̂ŁA�����������ł��낤�Ƃ����Ă�����̂������B�������M���@���̑�̉��v��m�肽���ĎU�X��J�������A���ɐ��m�̎�������邱�Ƃ��ł��ʁB
�@��̌ゾ�Ƃ����Ă���É��s�̊������ɂ��镶���Ɂu�����L�v�Ƃ���������B�c���N�Ԃ̂��̂ŁA�܂������ł͑�̂��Ƃ��������ŌÂ̂��̂ł��낤���A�S�������t��q�������r�̉����Ő����̐M�p�ɂ�����ʁB�������ł��A�S�R����ɂ���Ă�悤�ɂ������ʁB�����Ƃ��A�ϐ�q�ł���߁r�̎��̉��N�Ƃ������̂́A���Əꍇ�œ��ς��Ă邪�A����͂܂��ł��r�������B��N�A���@�@�łł����w���@��ρx�̒��̊������̉��N�Ƃ�����A�u�J��A�M���@��ɖ������M���r�l�Y���d�B�J�R�A�����@������l�B�n���O����N�v�Ƃ���B���ō�������Ҏ҂���������A������ϐ�q�ł���߁r�ł��낤�B���邢�͐r�l�Y���̖��������������̏����C����Ó`���ꖕ�����̂�������ʁB
�@�������A�������ɂ���`�����k�߂Ă������̒ʂ�ł���B�u�x�m�S��z���̖@�Ǝ��́A�āX�Ђɋ������B���m�������̔��f�����āA�@�̎��͐�����A�Ƃ̎��͉Ώ��炷�ł��邩��A�ǂ����Ă��Ă��˂Ȃ�ʂ킯�����邩��A���ꂩ��͋ɒ[�ɐ��Z��ɂȂ��ĉ̉��͏������Ȃ��悤�Ƃđ�Ɖ��̂����B�ォ��͑�ŁA������͐�A���ꂶ��̗J���͂Ȃ����A��ˁq�����ǁr��̑��ł��邩��āX����ɋ������B���̎��̓��G�E���ٓ��̌ܐl�̊w�����A���@��l�ɖ@�_��ŕ����������q�ƂȂ��āA������苗��������Z�E�ɏ��҂����B
�@���̒�q�����E���d�Ƒ��`���āA���O���N�ɐk�Ђ̂��߂ɔj�Ē���ɋA���A���悻�S�]�N���o�āA�n���̊�z�Y�������R���q�����܂��r�̋��n�Ɋ����R��Ƃ��������������̂��A�����\���N�ɐÉ��{���Ɉڂ��Ċ������Ɖ��߂��B
�@����ƍN�����{���ɓ���ɋy��ŁA���̈��������̕��̐M�ɂ���Ċ�����������ɂȂ������A�Ԃ��Ȃ������̕����a�̎R�Ɉڂ�ɂ��ē��s�ɂ����������ł����B�܂��b�B���B���ɂ��ł����v�Ƃ����悤�ɏ����Ă��邪�A���`�̏��߂͌㐢�̋U�ρq�������r�ŁA���ɑ���ʁB�ܐl�̊w���ȂǂƂ�ł��Ȃ����Ƃ��B���������̑�ʓ��Ƃ͐^�ԂȋU��B���������ɑ��Ⴗ��B�܂����V�ܖV�̊J�R�ɂ��Ă��m��q������r�̂��̂ł���B���������ɑ����ɘA��������Ƃ��邱�Ƃ��A�܂��X�������̂ł���B
�@�����������ɂ��߂ɂ⊴�����ɓ������M���̌ܐl���Ȃ킿���G�E���فE���T�E���~�E�@�C�Ɏ��^�����{�����A�ߌÁA���R���ӂ��甭�������Ƃ����`���Ă���B����͐���ł���^�U�����̂��̂ŁA�����]�ɉ����ʁB
�@�v����ɁA���̐É��̊������ȑO�̎j���͉_�����ޒ��Ȕ��R������̂ł���B�c�O�łȂ�ʁB�ύׂ��������Ă���������������A�痢�������Ƃ������Ĕq������B
�@��̚��͂ǂ̕ӂł��������Ƃ����ƁA�鉪����˂ɂāA���̓��R���w�q�x�m�g���S���r�̈꒚���萼���A���n�S���H�̐���ɏ�������������B�����ɍ��䗅�q����҂�r�̏��Ёq�₵��r�������āA���̌X���鍶���ʂɁA��̌̚��Ə��鏬�肪����B�O���@���q����ق������r��22�����q�ɂ�����r�̍Č��ł��邩��Â����ł��Ȃ����A���傪�C�ɓ���ʁB�Â��蕶����������Q�l�ɂ��Ȃ낤���c�O�ł���B���̔肪�m�ɂȂ�킯�ł͂Ȃ����A�匩��������A���̏����𒆐S�Ƃ��Đ��͑�ː�܂ŁA���͋v������q�����킠�͂�r�̕����܂ŁA���̊Ԃ̂�����̕ӂɂ��{�@�y�јZ���̖V�ɂ����������̂ł��낤�B
�@�������̖V�����E�ӛߏ㖾�ĂȂ�ɔ�Ԃ�A��⏭�Ȃ��悤�����A�e�Î����N�̕S�V�Ƃ��ܕS�V�Ƃ��l�\��@�Ƃ����̂���̂́A�܂�Ō֑�ϑz�ł��ĂɂȂ�ʁB�c�ɂł́A���ۂɎ����ɏE��������Α債�����̂��Ƃ����Ă悢�B
�@����u���E�Z���W�v�ƌĂ�ł�ނ�������B��˕ӂł́u���E�Z�m�W�v�Ƃ����Ă���B��������́u�����E�Z���W�v�Ə����Ă���B���������u�����E�Z���W�v�̕��ł���B
�@��̂��̌�̉��v�ɂ��ċ����Ď����̉����������A���̒ʂ�ł���B
�@�ܘ_�A�M���ׂ��Õ����ËL�^���̏o�łāA�����ے肹�ɂ�Ȃ�ʎ��́A�u�Ԃɂ��̉���������q�ق��Ă��r���邱�Ƃ������ʁB�܂��A�����E�O�����̑�͑厛�ł������낤���A�]�����^�̕��ŗ��h�ȉ@����u���ʂ��炢�ŁA�����̑m�����V��Ƃ��Ă̐����͊y�łȂ��B���Ƃ̎d�����_�Ƃ≽���Ŕ��q�����r���ɕ�炵�����̂Ǝv����B��߂ē��F���j�������Ă����낤�B����Ɍ����r�ꎛ���B����ɖV��̂����Ȏ҂͖@�؏@�ɂȂ�B�\�ʁq�����Ăނ��r���̗͂���Ēǂ��o���Ă��A�����q������r��2�l�͂܂������Ɏc���Ă���B����ɉ@��オ���������ʎ������B�@���̍s�q�Ƃ������l�����Ⴊ�A������z�q�ւ�r���Ă��鑭�m�Ƃ��Ƃ�����A�܂�łȂ��ĂȂ��B�m���̌��Ђ��Ȃ���A�V��@�̐M�Ȃ��q�Ƃ��r�ɒn�ɗ����Ă�̂ŁA�r�����r�炵����ɂȂ����̂ł��낤�B
�@�@���ɂ́A���G�E���ق��O�̖@�ؑm�������Ɋ��ʂ̂ŁA���^����������Ǝv������A�c�v��l�q�ł�Ղ₶��r�ɂ��ǐS������B�ꎞ�̏@���M�ʼn@����퓡���ɐ��q�����r�ďグ���Ė@�؏@�����߂̎�`���͂������̂́A�M���قɂ���O�ɂ͉��̈ӎ�⍦���Ȃ��B���ɂ͐e�����F�̊W�����낤�B����炪����̎҂�����a��ꂽ�������ɋy�B�c��Ȏq�͋����̗܂ċ�J�����Ă���B�������̖��������ł���B�����c�ɂ̏~�p�Ȑl�B���C�ɏ�q���r�����ɂ��������B�@�؏@�𔗊Q��������̎v���͕��ɏ]���āA�@����퓡���ւ̓��̉�����������ɂȂ�B���̖V�ɂ̉����ւ̎�`���ɂ��C�����ʁB�@�����̑��m�ǂ��́A�ڂ̏��ᎂ���ꂽ�̂ŁA�H���L���ĉ䂪�܂O���ɓ��𑗂��Ă���B���@�̌o�c���Ȃɂ����������̂łȂ��B�����œ��F�͍r��ɍr��Ď��R���ł��B���̓��ɂ͕�������A������A��������B���܂�ł��j��̎�`�������Ă����B�@�Ǝ��ł���ł��ǂ����Ȃ��킯���B
�@���ُ�l�́A�������̕ӂɗ��Ȃ�������������ʂ��A���G��l�́A��̂����T�Ɏ������ĂčO���̍����Ƃ�����B�������N�n���̍��̋v��̎s��R��掛������ł���B
�@������l�́A��{�������o�����Ă��A�_���̎l�\��@�q���̊⟺��ԏ�̌��̉��̏�ŁA���o���ӂ���r���o����Ă��A���̓���A���R�̑���A�͍��̗R��A�����̍������������Ƃ��ĕs�f�ɖ@⥂���B�@��̔������������Ė@�̉̎��ɂ���B���������l�\��@���A���ɋ��t�̎��ƂȂ�B�s�q��퓡�����A�����Ɏ������肵�Ă��ǂ����ʁB�����̗��݂̓�����B�����q�ւ������r���Ă��Ȃ���A�������đ����̑����ɔ��b�q�͂��r����ꂻ���ŁA��������掓k�̒��{����X���X�Ƃ��āA���ɒn�����ɂ��ׂ藎�����B����O�Ђɋ����āA�Ƃ��ɐՌ`�Ȃ��Ȃ�����ł���B
�@�����ނ̌b��q��������r�Ȃ�����Ȃ�s�w�����q���傤�����ɂ����傤�r�������A�͂邩��ɍċ����āA������Ƃ����v�����̉��N������Ă������̂��A����Ɏ���ɗ��v�Ȃ���ʂɂ̂ݏ����U��ꂽ�̂��A���Ẩ��N�ł͂Ȃ��낤���Ǝv���͂����ɁB
�@��O�Ƃ����̂́A������̗��h�ȑm���ł���B�w�\��x�ɂ��ƁA����[���G�E�z��[���فE����[���T�E�O�͖[���~�̎l�l�����Ƃł���B���Ȃ킿�����̏Z�E�ŁA���̊O�ɖ@�؎O�����̋��m�ɘa��[�@�C�Ƃ���������A�܂��ʂɋ��m�̕����[�È�Ƃ����̂�����B����ɉ@���̍s�q�ƍ��v�q���߁r�Ď��l�ŁA�����@�傪�����Ƃ���Δ��l�ł���B�������������������낤���A�l�������������炩�łȂ��B
�@��������������̉��N���ɂ́A�S�l�̑�O������ܐl�̊w���������B���̌ܐl���g���ɉ����đ吹�l�Ɩⓚ���ċA�������ƁA�Ƃ�ł��Ȃ����������������A���R���p���Ă�l��������������B
�@�@��ł����y�̐l�ɁA���̍l�����Ȃ��ܐl�̊w���Ȃ�ǂƏ����ꂽ�l������B�����悤�ȑg�D�q���݂��ār�ɂ����Ƃ���ŁA10�l��20�l���炸�̎��Ɍܐl�̊w���������Ă��܂���̂łȂ��B��b�R�S���̎��A����̊w���q�������傤�r��O���钆�ɁA�w���炵���҂͈꓃�Ɉ�l���炢�A���v�ē�l���l�l�ł��������Ƃ��l���邪�悢�B
�@�z��[���فE����[���G���Ƃ����̂́A������Z�E�Ƃ��ċ��t�̒�q�ƂȂ�A������Ǐo����Ă��������������A���n�������A�Ō�܂ő�@�̂��߂ɕ�����������̗��҂ł���B���G�E���ق̖��ɂ��Ă��́w�\��x�͍쐬����ꂽ�B�O�Ɏv���m�����Ȃ�����A���Ȃ킿���̓��̎��́A�����̈ӂ�����A�����ɍ݉Ɛl�̑y��ɂȂ�ӂ�����B�Ȃ��A���̓`�L�Ȃǂ́A���̏��̉��́w��q�����x�̉���Ɉς�������B
�@�����@��㕽���ߓ����s�q�Ƃ����̂́A��ɂ͑����̉@�傪�������낤�ɁA�a�C�Ƃ����Ƃ��̎���ŁA���̎��ɂ͂��Ȃ��������A�܂��͂��Ă��\�ʂɏo�Ď���������Ȃ������ŁA���_���̖�������ʁB�����ŁA���̍��߂Ƃ���������k���Ƃ̏����q�����イ�r�̎҂ŁA���̓y�n�ɂ������̂��l�����čs�q�Ɩ����A���̎��̉@�����߂Ă����B�ܘ_�A�s�w�̌��J����ׂ��łȂ��B�ޒ��q���傭�r�ɋ߂Ă��Ă����ʓ����B�s�w�̌��ς������Ƃ̏Z�E���ɂ͐S���猠�Ђ̂���ׂ��łȂ��B����ɕ��햳�̒s�ҁq������́r�Ƃ��Ă��邩��A���̕ӂ�����ꑛ���N��ׂ��ł���B�����[���q�����Ɓr���Ă��炦�Ă������G�E���ٓ��́A�܂��Ƃɏ��ɓI�Ȑ��m�̎�i�����ꂽ�̂ł������낤�Ǝv���B
�@���X�̎����Ƃ����̂́A���́w�\��x�̒��ɂ�����G�E���فE���T���ɑ���s�������A�����q�Ԃ��r�̗��p�A�S�����l��n���E�Q�A���b���ނ̎���p�ՐH�q�����Ⴍ�����r���̗��\�̉ȁq�Ƃ��r�ł���B�s�q���A���̌Ȃ��߉Ȃ�h��B�����߂ɁA��X�ɖ������w���q�Ԃ����r���i�������̂ŁA20�l�������߂��đ�@��N�����̂ł���B���̖����̑i���́A���́w�\��x���ɒ��o�q���傤����r���ĕٔ��q�ׂ�ς��r�������Ă���B
�@�i��ɓ��킭���Ƃ����́A������A���Ȃ킿�s�q���̑i��ł���B�����艺�́A��X�ɑi��̗v���q���傤�r���ĕِˁq�ׂ��r��������̂ł���B
�@���߂Ɂu���G�E���ق͓��@�[�̒�q�ƍ����A�@�،o���O�̗]�o���邢�͐^���̍s�l�͊F�����č����㐢�����ׂ��炴��̗R�����\���]�]�v�Ƃ����B����̑i��̕���͒�߂Ē��������̂��A�v�_�ɏk�߂��̂ł��낤�B����ɂ��Ăّ̕`�̕������钷���A���S�]���B
�@���Ɂu����Ɍo���Ȃė�̋߂ƂȂ��ׂ��R�̎��v�̑i��̕���ɂ��ČܕS�]���ِ̕ˁq�ׂ��r������B�@�`��̂��Ƃ͑����ɂ͂킩��ɂ�������A���R�ɒ����Ȃ�킯�ł���B�@�ؑΐ^���A�@�ؑΔO���̖@��ɂ��Ċ̗v�̕����������Ȃ����A���̉���ɂ́A�Ȃ�ׂ��j�����d��������@�`��̂��Ƃ́A�����ɂ͎~�ނ���������B
�@�������A�@��̌����͑S�������ɂ��邩��A��ʂ̏n�ǂ������ߐ\���Ă����B���p���Ⴉ�������Ȃ����킯�ł͂��炳��Ȃ��̂ł���B���Ƃɂ��̐߂̖��́u�����G���A�ނ̏��o�q����Ɍo�Ȃ�r�̓��u��e���@�،o����u���A�@�E�Ɋ��i���āA�얳���@�@�،o�Ə������A���Ɏꒉ�ɂ��炸��B�����̎q��s�R�𑊑ق������m���������ꐥ����������ׂ����v���Ƃ���B����Ό��̍Ñ��A�����@�k�̖ʖڂ����@�Ƃ��Č������ʼn߂��Ă͂Ȃ�ʁB
�w���x(�S�W852��)�i��ɉ]�킭�A������\��������q���܂��r�̐l�����Â��|����т��@�啪�̌�V���ɑł�����A����[�͔n�ɏ��A�M���̕S���I���Y�j�q�����낤���Ƃ��r�𑊋�A�_�D�q�Ăr�𗧂č�т������ē��G���Z�[�҂Ɏ����L�ʁB�]�]���ӁB
�@���̍s�q���i��̈Ӗ��́A�O���Q�N�X���Q�P���ɉ���[���G�́A�|�����������吨�̕S������n��Ɏw�����ĉ@��̖V�ɗ��������B�I���Y�Ƃ����S���́A���G�̏��������D�𗧂ĂĔM���̕S�������W�߁A����̈�܂Ŋ������āA���G����h����V���ɉ^��ł��܂����Ƒi�����̂ł���B���Ȃ킿���\�T�Ёq�낤�����r�����̑i������B
�@����ł��w���q�Ԃ����r�ƒm��ʊ��q�̖����ł́A�ߐl�ǂ������߂炴������ʂ킯�ł��邪�A�܂����������̕ʓ��܂��͑����̏��i�����킵�ĉ����ׂ�������悩�낤�ɁA�n�́A���{�̖�l���̑����݂̂������Ă�@�؏@�ł��邩��A�e�Ղɏ��߂����̂Ă��낤�B�I���Y�̉��ɒj�Ƃ����������Ă���̂́A�����̕S�����l�̖��ɂ���@��̊��p��ł���B���̎l�Y�j�E��l�Y�j�Ƃ���̂����R�ł���B
�@�܂����̖��́u�P�]�]�v�́A��╶�ɂ́u���V�v�ƂȂ��Ă���B���V�ł͈Ӗ����ʂ��ʂ̂ŁA�������̓����̎ʖ{�Œ����������B���̐�ɂȂ�10���ӏ�����������������A��ӏ��������˂Γǂ߂ʏ�������B
�w���x(�S�W852��)���̏�Ռ`���Ȃ����a�Ȃ�A���G���͌Ȃ����s�҂���A�s���g�̏�͒N�l�����G���̓_�D�����p�����ނׂ���A������尫��q�������Ⴍ�r�Ȃ�y���̑����G���Ɍق��z������B����������|����т����s�����Ƃ������͉̂]��B�s�q�]�킭�A�ߗׂ̐l�X�����ċ|����D�����A���̐g���������ƁA�q�ׂ͐\�������A�����q���傤���傭�r�̎���X�������@�ɑ���ׂ�
�@����͑O�̗��\�����̑i���ɂ��Ăٔ̕��q�ׂ�ς��r�ł���B���̈ӂ́A�s�q���̌������͑S�������Ռ`���Ȃ���育�Ƃł���ƁA��q�͂��߁r�ɗv�̂��q�ׂĂ����āA���ꂩ�牺�͂��̗��R�ł���B
�@���G���͂Ȃ��̌��Ђ��Ȃ����Q�̏o�Ƃł���B�Z�Ƃ���m���Ɏ����ʈ���̐g�̏�ł���B���̌�H�V��̏��������D�̕����N�l���M�p���Ď�`���ɗ��悤���B�_�カ�S�������A�Ȃ�ŗW��q�ނ炨���r���l�����ɂ܂�Ă���G���Ɍق��悤��B���̏�A�|����ттė��\�T�Ђ����́A�܂��͋|����D������ĕS�������g�ɂ����Ƃ����B��́A���̋|���͂ǂ��ɂ������̂��A�ǂ������҂ǂ����A�ǂ������ӂ��ɗ��\���������A��X�Ɉς����q�ׂ�\���グ��̂��B�����炦���ƁA���育�Ƃ��r�����������ł��邩��A���l�̖��炩�Ȍ�ڋ��Ō�@�����肤�ƍR�c������̂ł���B
�@��́A���̈�藐�\�̂��Ƃ͐j���_��̐\�����łł��邩��A���ׂɂ͑i���邱�Ƃ��A������ł��ł��Ȃ������̂ł��낤�B
�@�܂����̕��̒��Ɂu�ތىz�q�����Ƃ������r�v�ƌ�╶�ɂ��邪�A�ǂ߂ʂ̂ŁA��ɂ���Ĕނ��ƒ������āu�z�����v�ƌP�q��r��ł������B�܂��u�s�q�]�v�̑O��ɒE��������悤�ł���B��̎ʖ{�ɂ������ʂŁA�݁q�͂���r�葽�����ƂȂ���u�҉]�v�̉��Ɂu���v�̎��������ēǂ�ł������B�u���g�v�Ɓu�s�\�v�Ƃ̊Ԃɂ��ꎚ�l�ꂽ�����̂ł��邪�A�]�苰�����ŁA���̂܂܂ɐh�����Ă����B
�@
�w���x�@(�S�W�@852��)���G���ق͓�����X�̑m���Ƃ��čs�@�̌O�C��ςݓV���n�v�̌�F����v�����ɁA�s�q�͂����܂��ɓ�����n�̉@���ɕ₵�A���ƎO�͖[���~���тɏ���q���傤�فr�[���T���G���ٓ��ɁA�s�q�����āA�@�،o�ɉ��Ă͕s�M�p�̖@�Ȃ葬�₩�ɖ@�̓��u���~���A����Ɉ���Ɍo��ǂݔO����\���ׂ��̗R���N�����ɏ����A��������g���ׂ��̎|�����m�����ނ�̊ԁA���~�͉��m�ɐ����ċN���������Ĉ��g�����ނƂ����ǂ��A���T�͋N������������ɂ���ŏ��E�Z�[��D�����̎��A���T�͑������U�����ߕL��ʁB���G���ق͖����̐g����ɂ�菊���𑊜߁q���́r�ݎ����Ɋ�h�����ނ�̊ԁA���̎l�ӔN�̒��A���G���̏��E�Z�[��D����茵�d�̌�F����ł��~�ނ�̗]��A���s�Ȃ������ŖO�����炴�邽�߂ɁA�@�،o�̍s�҂̐Ղ����d�Ă��\���Ď�X�̕s����\������̏��A���ɍݐ��̒��B�ɂ��炸��B
�@���ꂩ�牺�́A����̑i��̍R�قł͂Ȃ��B�O���ɂ��łɑi��̕��|��ٔj���Ă��܂����̂ŁA����ɐi��ōs�q���̕s�@�\�s�����q�ڂ����Ⴍ�ق���r���w�E���āA��̗������v������Ƃ���̂ł��邪�A���f���鏊�́w�\��x�̕��ӂ́A���̒ʂ�ł���B
�@���G�E���ٓ��͑�ɔ����̎҂ł͂Ȃ��B�t�������̂܂��t��������ƂȂ����̎����ɏZ�E���āA�����ɍs�w�̌O�C��ς�ł���B�܂����Ƃ̂��߂ɂ͓V���n�v���A���R�Ƃ̂��߂ɂ͕��^���v�̌�F�������ƈ�����x�܂��߂Ĉ�_�̑Ӗ����Ȃ��B
�@������ɍs�q�́A�g�ɂȂ��̍s�w���ς܂ʑ��l�ł���Ȃ���A�����܂��ɓ����ۂ߂Ė@�̂ƂȂ�A���ꑽ�������̑���̉@��̑㗝���߂Ȃ���A�Ȃ�̉�����߂��Ȃ����N�s�w�̎��Ƃ̘V�m�����X�B�ɁA���Ȃ킿���~�E���T�E���G���قɜ݁q�͂��r����Ȃ����߂������Č����ɂ́A�@�،o�͐M�p����ɑ���ʁA���O���̓ǂ�ł�@�،o�͍������葊�~�߂�A����͈���Ɍo��ǂݔO����\���A���̂��Ƃɂ����Ă����Ƒ����A���̖��߂Ɉ�w�v���ʐ��������A���������炱��܂Ă̍߂͎͂��āA���̂܂����ɍ����u���ł��낤�B�����A���̎|�ɏ]�킸�A���@�[�̋����ɂ�肠���܂Ŗ@�،o��ǂނƂ����Ȃ�A���̂܂܂ɂ͂��܂��ʂ��ƌ��d�ɒB�����B
�@�����ŁA���~�͉��a�ɂ��Ӎߐ\���ċN�����������Ď����ɒu���Ă�������B���T�E���G�E���ق͌����ċN�����������ʁB�V��̏@�k�Ƃ��ĉb�R�̖����Ƃ��āA���@��l�̂ƂƂ��@�ؓ��u���Ȃ����Ƃ��A�Ȃ�č��{��t�̌�ӂɔw�������B���̋��B�̖�ɔO�������������Ďt�G��掖@�ł���Ƌt���������B
�@�����ōs�q�͍Ō�̎�i�Ƃ��ĎO�l�̎��Ƃ�ǂ��o�����B���T�͎d�����Ȃ�������ގU�������A���G�E���ق͑��ɗ���ӂ̂Ȃ��g�ł��邩��A�����̈ꕔ�ɏh������Ă��邪�A���͂�l�ӔN�ɂȂ�B���̎l�ӔN�̊ԁA�ᓙ�̏Z�E�n��D������Ď��Ƃ̑������V���̌�F��������ɍ��~�߂Ă�̂́A�@���Ƃ��Ă̗��\���r�������̂ł��邪�A�܂�����ɂ������炸�ᓙ�@�̍s�҂̐Ղ��i�v�ɍ��̂Ă悤�Ƃ��āA���ҋ����k�������čI���ݖd��Ė����̑i�����Ȃ��A���q�����݁r���\�q�����ށr���ēV�������̌�ٔ��ɂ܂Ŕ݁q�����r�����悤�Ƃ����̂ł���B
�@�@�ؔ�掂̏d�߁A���@�j�p�̑�t�́A�ߑ���ݐ��̒�k�B���q�����������r�̏��s�ƕς�鏊�͂Ȃ��B���Ԓn���������J���đ҂��Ă���B�Ȃ�Ƌ��낵�����Ƃł͂Ȃ����B�ƁA�����ƉE�l�̈Ӗ�����B
�@���̉��ɂ͑啪������P�_�̌�����������B���Ȃ킿���̒ʂ�B
�@�u�s�@�̌O��ςނ̏�V���n�v�̌�F����v�����̍s�҂ɕ₵���A������n�̉@���v�ƌ�╶�ɂ���B�Ȃ�Ǔǂݒ����Ă��A�Ȃ�̂��Ƃ����킩�肩�˂�B����ɕ����̈Ⴂ�́u���v�Ɓu�ҁv�ŁA����́u�C�v�Ɓu�q�v�Ƃ̌��ł���B�����ł͎��Ă邩��ł��낤�B�܂��P�_��ւ��č��̒ʂ�ɂ����B
�@�u�s�@�̌O�C��ςݓV���n�v�̌�F����v�����ɍs�q�͓�ɓ�����n�̉@���ɕ₵�v�B����ł���Ɠǂ߂�B
�@�u�Ƃ莛���v�Ƃ���u�Ɓv���u�P�v�ƒ��������B�Ƃł͂Ȃ�̂��Ƃ��킩��ʁB
�@�u���E�̏Z�[��D�����ł��~�ߌ��d�Ɍ�F���̗]��v�B������ǂ������Ă��ǂ߂ʂŁA���̒ʂ�P�_��ւ����B
�u���E�Z�[��D����茵�d�̌�F����ł��~�ނ�̗]��v�ƓǂށB
�w���x�@(�S�W�@853��)�}���s�q�̏��s�́A�@�؎O���̋��m�a��[�@�C�������Ė@�،o���`���ɍ��A�����`�A���ɂ̏C�����Ȃ��B���قɌ䏑�����������č\���u�����̏㕘���q�ӂ�����r�ꖜ��琡�̓����琡�����p�����ށB
�����̐�����Ɋ��߂ċ���l����_���̍Œ��ɁA�@�ؐM�S�̍s�l����l�Y�j��n�������߁A���锪����l�Y�j�̌z��炵�߁A���G���ɓ^�q���сr�q�͂ˁr�邱�Ƃ��[���č��̒��ɏ�������B
���q���˂̓��l�����[�È���ߗ������A��ʂ̐m�Ə̂��ē����̋��m�ɕ₹���ށB
���͎����̕S�������Â����G�q���Â�r��E�K�E�E�T���̎������āA�ʓ��̖V�ɉ��Ă����H���A���͓ŕ��O�̒r�ɓ�����̋��ނ��E���A�����ɏo���Ă����B�����̐l���ڂ�����������͂Ȃ��B���@�j�ł̊��A�߂��݂Ă��]�肠��B���̔@���̕s�P���s�A���X���ςނ̊ԁA���G���D�V�̗]��A����ď㕷�q���傤�Ԃ�r����������Ɨ~���B
�@���̉��̒����͍��̒ʂ�ł���B
�@�u���䏑�v�Ɓu�����v�̘A�ڂ��ނ������B�����̎ʖ{�ɂ͌����̈�Ɂ����u���ł���B�����͂���Ɂu�v�̈ꎚ�߂œǂ�ł݂��B
�܂������́u�V��v�́u��v�̎��̈Ӗ������炩�łȂ��B�����ɂ��Ȃɂ��̌�肪���낤�B�u�����v�ł͂Ȃ�̂��Ƃ����킩��ʂ���A���{�q�ق��ق�r�ɂ���Łu�����v�ƒ��������B�܂��u���ꖜ��琡��v�Ɠǂ܂��ł���̂́A�����A���������̈ӂɌ�������̂ł���
���ŁA�u�����q�ӂ�����r�ꖜ���́v�ƌP�ݑւ����B
�@�u�l�Y�[�j�v�́u�[�v�̈ꎚ��������B�݉Ƃ̎҂ł��邩��A�[�̎��͕s�s���ł���B���Ƃɉ��ɒj�̎������ł��邩��A�Ȃ�����ł���B
�@�u���v���u�[�v�ɉ��߂��B�u���G����������ʂ鎖�����̒��ɏ�������v�ł́A�Ȃ�̂��Ƃ����킩��ʁB�u��������ʂ�v�Ȃ�Ă��|�������������ɂł��ł�����̂łȂ��B
�@�u����������͎Z�q�ȁr���v�́u�Z�v���Ȃ��ƌP�q��r�ޗ��m��ʂ��A�ǂ���猴�{�ɖ��炩�Ɂu�i�V�v�̉����܂ł��ł���悤�ŁA���̂܂܂ɋ^���ł����B
�@�}���s�q�̏��s���Ƃ����̂́A���̉��ɂ܂��@���̗��s���W�߂����̂ŁA���̖`���̌�ł���B
�@�@�؎O���̋��m���Ƃ����̂́A�V��@�̂��Ƃł���A�����ɖ@�؎O�����������āA�@�C�Ƃ�������炱�̎O�����ɕ�d���ł����B
�@�@�،o���`���ɑ����Ƃ����̂́A�@�،o�̊��q�Ȃ�ܖ{�Ȃ���U�X�q���r�ɂ��āA�Ђ����Ċ������L�������S�q�r�����킹�ŏa����������̂ł���B�o���̕s�p�q����ށr�̂����q���炩�݁r�ɒ��邳���ւ��ׂ��ɁA����͂Ȃ閳���O���\�̋ɂ�ł��낤���B
�@�����`�Ƃ����͕s���ł���B�������Ȃɂ�����ł͂��ʂ��B
�@�������Ƃ́A�Ɖ����ؒ[�q�����ρr�̂��Ƃł���B������ڋЎO�����퐡�Ƃ��Ă���B���ꂪ�ꖜ��琡����ŁA���Ɍ�p�̂��߂ɁA���ق���̋���ւ�ŕۊǂ��Ă����̂��A�@��オ����Ɏ��o���āA���V�̕������ɂ����B������҂��ɔw�C�̑�߂ƂȂ���̂ł���B
�@�����̐����㓙�Ƃ����̂́A�����͋��s�E���q�̌����Ƃ̑������̂��e�n���ɎU�݂��鏊�ɁA������u���ŌY����̂��Ƃ����q�����ǁr�点���B��Ȃ鎛�@�ɂ��܂��������������B�������͖k���ƈ��̎��̒n�ł���B�����́A�`�@�q�ł�ۂ��r���̖{���q���Ƃނ�r�ɂ������낤�Ǝv���B�����ɂ͐ꖱ�̕ʓ������Ȃ��ŁA�㊯�������Ƃ݂��B�����ꉺ�i�̂��ƂŁA�������킩��ʂ��A���_�A�s�q�E�퓡�����̈ꖡ�̎҂ł������炵���B
�@�l���̌�_�����Ƃ́A��{��Ԑ_�Ђ̍P��̑�Ղł���B���ł��×�ɏ����Đ_�`�q�݂����r�̓n��q�Ƃ���r������B���L�n�q��Ԃ��߁r������B�`�@���̎O���s��̐�Ԃ́A�Ȃ��Ȃ��̌ÎЂŁA��{��Ԃ��Ă������ɉ��a�ɂȂ������Ƃ�����ƕ������A���邢�͂��̌�_���Ƃ����̂��A���̎O���s��ōs�Ȃ�ꂽ��������ʁB
�@�O���Q�N�T���S���́u�E�̓��O��Ԏ��v�ɁA�@�@�@�@�@(�S�W1481��)
�@�u���̏�A�{�̑��c�ɂČ�Ȃ�v
�Ƃ���A��5��11���́u���R�a��Ԏ��v�ɁA�@�@�@�@�@�@�@(�S�W1478��)
�u�����͊��_�Ɛ\���A��{���q�����݂����r�Ɛ\���A�Ӗ��q���������r�̉ɂȂ��v
�Ƃ���̂ł��A����1���O��4���ł��邩��A�`�@�ōs�Ȃ�ꂽ��������ʁB
�@�M�������{�ւ�2�������邪�A�O���s��܂ł͔����ɉ߂��ʂŁA�M���̐l�B�̌S�W�ɂ��֗�������B���̌�_���̎G�B�̒��Ɍ��܂Ɏ��悹�Ă��A�l�Y��������ꂽ�B�N�������Ƃ��킩��ʁB
�@����8����l�Y�j�̓���炵�ނƂ����̂́A�ꏊ�⓮�@���킩���ĂȂ��B�N������������ʁB�����ꂱ�̓�l�́A�M�����s�뎛���̕S���ł����āA���G�E���ق̒�q�ł������Ƃ��납��A�s�q��퓡�������̂��߂ɑ��ʂɂ�����ꂽ�̂ł���B�u��q�����v�ɂ͍ڂ��Ă��ʁB���̖�l�Y�́A���d�{���̖�l�Y�ł͂���܂��B�M�d�Ȑl�����Ă����������m���ē��X�ɂ�点���̂ŁA�\�ʂɂ͉��l���������킩�����悤�ł킩��ʁB�_�l�Y���̂悤�ɏ}��̑s������`���������ʂ̂́A�傢�ɋC�̓ł̎���ł���B������}��҂Ƃ��āA�_�l�Y���ƂƂ��ɕ_�H�ǒ��q�т傤���傭�����傤�r�����ׂ��ł��邱�Ƃ�^���ɐi�����ɂ�Ȃ�ʁB
�@���G���Ɍz�ʂ鎖���[�������Ƃ����̂́A�s�q���͈�r�ɔM���̖@�؏O�݂āA�����Ȃ��i������Ă��Њd���悤�Ƃ����B����ǂ��A�Ȃ�ׂ������������l�ɂȂ肽���Ȃ��B�ꖡ�̈��k�ɈÎE��\�����Ă����Ȃ���A�؋��s�\���Ȃ̂𗊂݂ɂ��āA�������Ă��̍߂��G�t���ɓh�蒅���悤�Ƃ��āA�i��̕���ɍI�q�����r�B�Ȃ鈫���q�����́r�ł��낤���B
�@���q���˂̓��l�����[�Ƃ����̂́A���q���˂̗r�m�̏�ɁA�Ȃɂ����������邩���̔���������āA������͂����B�z���m������ߗ�������Ă��̍߂��͂邷�̂��痐�\���Ⴊ�A�������Ă����L���̍ނƂ��ċ��m�ɔ��F�����Ȃǂ͌��ꓹ�f�̎���ł���B
�@���͎����̕S�����Â������Ƃ����̂́A�������E���Ȋ��q����ł���c�Ɏ��ł���B�m�����Δz�����āA�����̕S���j������W�߂ĎR��̗�������B���̊l�����钹�b�̓�����ɁA�s�q�̖V�ŁA��������̋����Ŋ��y���ɂ߂��ł��낤�B
�@���͓ŕ���������Ƃ����̂́A���O�̒r�͕����r�ł���B��������̂��߂ɖ����킴�Ƃ��̒r�ɐ���������ɗ���B�E���֒f�ł��邩�狛�ނ̊y�V�n�ł���B�O�ڂ̌����ڂ�������킯�ł���B����ɐΊD�Ȃ�ǂ̓ŕ������āA�S����ߋ����đ����ɔ���o���āA����̗��Ƃ�����B���낫�����ꂽ���Ƃł���B
�@�����̂��Ƃ��w�������̐\��x�ɂ������B���i5�N���̊�{�������̗����͔M���Ɠ���ŁA���̉@�傪��ɗ����ė��s�̌�����������B�J�R��l����{���̂Ă��Ȃ������̂́A��͂��ꂪ�v���̌�ӔC�������Ă���ꂾ����ł���B�����́A�����̂��R���̈��m�ɋ��ʂ̂��ƂƂ݂��B
�@�����̐l���Ƃ����̂́A���m�̂��鏊�K�����l�����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�����ɂɐM�͍s�q���Ɠ�������ɔO���ł��A�ޓ��̕������q�ق���ނ���r����Ԏ҂͂��̈ꖡ�ƂȂ�āA������̗��v������҂̊O�ɂ͂Ȃ��B���̏����̈��������̊O�̑����̕S���ǂ��́A�������̗��\�ɍ����q���܂��r�Ă��������̂ł���B�G�t���́A��̕��@�����̍s�q�̂��߂ɔj�ł̎��������ƁA�ߒQ�̗]��ɂ��́w�\��x������āA���̌䕷���ɒB����Ƃċ��ׁq�������r�ɒقɋy���̂ł���B�����̏Z�E���D����ꂽ����ƂāA�������ɂ�����̂łȂ��B�ޓ��̏����͕s���ł���B�Ԉ���Ă�B�ǂ��܂ł��������͑�̏Z�m�ł���B��̕��@�̋��p�q�����͂��r�͎������̙Ԍ��q��������r�ɂ�������̂ł���Ƃ̔M�����o�ł���A���̒قł���B
�w���x�@(�S�W853��)�s�q���X�̎��Ȃ��ǁq�ӂ��r�����߂Ɏ�X�̔�v����炵�A�ߗׂ̔y�q�Ƃ�����r�𑊌�炢�Ձq�������r���ĐՌ`���Ȃ��s����\���t���A���G���S�����߂�Ƌ[�q���r����̏��A���ꓹ�f�̎���Ȃ�B���ɂ����ɂ��A���q�����Łr�����߂̌䍹���Ȃ�����B���F�A���@�̌����A�����̐^�U����q����ł��r�����q����r�߂Č�q�˂���B���q���r�͐����q���傤�����r�̋����ɔC���A���͎����̖����ɏy���A�֒ǁq���r���������A���̑P�_�ς������i��q�悤���r�̏��V��q���݁r���܂܂�B
�@���̉��ɂĂ��A�܂����̒ʂ��������B
�u���q�Ă��r�v�́u�Ձv�̌��ł���B�u稂Ɂv�ł͈Ӗ����킩��ʁB�u�Ձq�������r��āv�łȂ��Ă͂Ȃ�ʁB�����ɂ������Ă������̂��Ă������Ă��A�Ƃ����ӂł���B
�@�u���ɂ���ɂ��v�ł́A�Ȃ�̂��Ƃ��킪��ʁB������ɉ���������ł��낤�B����́u���ɂ����ɂ��v�̌��ł���B���ɉ�����邪�A�����̎ʖ{�Œ��������̂ł���B
�@�u�������߂āv�ł͂킩��ʁB�u��v�́u���v�̎��̌��ł��낤�B���Ȃ킿�u���߂āv�łȂ��Ă͂Ȃ�ʁB����͎����̒����ł���B�v����ɛߏ�̎l���͑����ł͔��Ɏ������ŁA�����ʂ����肷����̂ł���B
�@���X�̎��ȁA��X�̔�v�A�ߗׂ̔y�𑊌�炢���Ƃ����̂́A�O�ɂ��łɈς�������������Ȃ����Ƃɂ���B
�@���ɂ����ɂ����Ƃ����̂́A���Ƃ����́A�l�ڂ̂Ȃ����q���r�炫���ł��邱�ƂŁA���̌䍹���͐_���̌��ڂł���B���Ƃ����́A�l�̌�������\�ʌ��̂��ƂŁA���̍����͐��{�̌��ڂł���B�`�Ɍ���ʐM�⓹���ɂ��āA�������Ƃ������͕̂��_�����߂Ė�����������B��ɔO���Ɏ������Ė@�،o�̔@���̋�����掂�҂ɂ́A��Ȃ閳�Ԓn���̍߂��݂��Ă���B�܂��͏��X�̌��݂̍߉Еs�K���m��ʊԂɏP���ė���B�n���q�ɂ傤�r�E�Q�s�@���������q�ق���r���\�́A����ꂽ���Ԃ̍߈��ł��邩��A���ꂼ��̐��{�̌��l�ْ̍f�q�����r�Ō���������B
�@�����ɂ���A�����ɂ���A�s�q���͖Ƃ�ʂƂ���ł���B��s���l�������M�q���r��߂ē����̍߉ȁq�݂Ƃ��r��E��Ă��A�����̈����͑傫�Ȍ����J���đ҂Ă���̂ł���B
�@���F���@�̌����Ȃ����u��������߂Č�q�˂���v�Ƃ����̂́A���߂̖@�`�ّ̕`�̖����ɂ���u���ꓙ�̎q��s�R�𑊑فq�̂��r�����m����������A�������������ׂ����B���@�̗D��̋�����v�����Ƃ́A�����A���y�E���{�̐��Ȃ�B
���A�����ɓ����ĂȂO���̋��K�ɔw����v�Ƃ���̂ɑ�������̂ł���B
�@�ʂ��Ղł͂����ʁA���ꂷ�Ȃ킿�ݐ������̒�̂悤�ȉ���܂ł����߂����Č�q�˂Ȃ��邪�悢�B����łȂ��䍇�_���Q�炸�A������̍��m�B���ĂъāA�����ɒ������Č䗗�Ȃ��邪�悢�Ɠ˂�����ł���B
�@���͐����̋����ɔC���Ƃ����̂́A�w�@�،o�@�����ʕi�x�ɂ���u�@�������V��v�Ƃ������������āA�ʂ��ĕ��̖@�،o�̌䕶�͐����̋����ł��邩��A���o���@���ْf���錠�\�������Ă���Ƃ����̂ł���B
�@���͎��𖾕��ɏy�����Ƃ́A�w��i���ځx���̓����̖@���̖����̏�ŁA��@���s�̋֒f���Ȃ��ꂽ���Ɗ肤�̂ł���B
�@���̑P�_�ς��������Ƃ́A���@���@�̗��ʂ̖����ň��s掖@���֒f����ꂽ���ƂȂ�A�V�ϒn��܂ł����ł��āA���V�P�_�͖@�x�̍���܂�ŁA���y���K���Ɍ��肭������ł��낤�Ƃ���ꂽ�B
�w���x�@(�S�W852��)�R��Α����s�P���s�̉@���E�s�q�����Ղ����A�������A�{�卟�̏d����E�����B�����������ɗ�@����B��炴��̓����ɔC���āA�ڏG�E���ٓ����g�̌䐬�s��ւ�ē��ɂ��C�����߁A�V���n�v��F?�̒��𒊂ł�Ɨ~���B���ď���ӂ��Ĕ���㌏�̔@���B
�O����N�\���@�@�@������G���ٓ����
�@�R��Α������Ƃ����́A�㌏�̂��ƂƂƊF�@���̍߂ł���s�q��ƐE����Α勥�̖{�͒f�ł��āA�����̉����͂����Ƃł��邯��ǂ��A�{��^�����̐ӂ�Ƃ�邱�Ƃ͂ł��܂��B���̖����̖{�@��́A���Ƃ����̉��u�̒n�ɂ���Ƃ��A�܂��{�@�ɕa�炵����Ƃ��Ă��A�����̂��Ƃ͑S�������̒m�������ƂłȂ��A�F�@���̏��肾�Ƃ��܂��Ă͂����܂��Ƃ����̂ł���B���̕��ɂ���Ă݂�ƁA�@��ʓ��͜ҁq�������r�ɂ��������̂Ƃ݂��B
�@�����������ɗ�@�������Ƃ����̂́A���Ċ�{���������O����O���_���R����h�ɕ��ꂽ����A�������@��͊O���_�̎�l�Ƃ��ŁA���t�E���t�E���t���̓��@���l�̌��q�ƂȂ��l�X���A�R�����ǂ��o�������Ƃ������̂ł��낤�B
�@����ɂ͒P�ɕ��@�_�̏ォ��V�`���������҂�ǂ��o���������ŁA���@�ْ̍f(�����r�ɂ�����҂łȂ��B���@�̏�ł͎�������ɍ߂͂Ȃ��B��@���̐��@�d�X�̍߈�����҂Ƃ́A��ɂȂ�ʂƂ�����̂ł��낤�B
�@���̕��ɂ��Ă��A�������̖@��Ƒ�̖@��Ƃ́A��قnj`�Ԃ��قɂ������łȂ��B掓k���̘A���������[�����̂ł͂Ȃ��낤���Ƃ݂�������Ƃ��邱�Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B
�@�������A���t�̏ォ��͗��n�Ɏ叫�ł��邩��W���傠��ł��낤���A�M���̏G�t�E�َt����{�����ɊW������A�܂��Ύ�̍s�q��퓡������{�ɊW�����Ƃ͉��ɂ��݂��ʁB�܂��āA�������@��}���M�������ɊW�������Ƃ������ʂ̂ł���B
�@�������A���̓y�n���ꗢ�Ƌ��q���r��ʖ��ʁq�������傤�r�̊Ԃɂ���A����������t�̎x�z�ł��邱�Ƃ����������������錴�����Ȃ������̂ł��낤�B
�@���g�̌䐬�s��ւ����Ƃ����̂́A�Ύ�q�����ār�̍s�q��ƐE���āA���G�E���ق͎����ɕ��E���g����䐬�s�������̂ł���B�������́A�L���̉@����}���āA�j���̓����ɏC���������A����𐴏�ɑ����Ɍ��E���A�V���n�v�������J�̌�F�����݂������̂ł���ƁA�M���O���q�˂����イ�����r�����߂Ắw�\��x�ł���B
�@�������A���́w�\��x�́A20�l�͖ƁA���G�E���ق̕��E�A��̉��v���̓��ʂ̖����Ȃ����ɂ܂��ƂɎc�O�疜�ł���������ǂ��A���̒��ɉ��삷��吸�_�͖��Õs�łɂ��āA�����̏@�k�ɂ���Đ����ɔ�������ꂽ���Ƃł���B
�w�b�B�����E������x�f�с@�@�@�@�x�͂̍���Ɛ\�́A��Â͏�s�̏Z���Ȃ�B
���A���ʓ��Ȃ点�B
�@����2�s27���̒f�т́A��̏Y��q���イ�ق��r�ŁA���̑O��̕�����ш����E�N�����͎ʖ���c���ĂȂ��B�M�@�͏@�c�̂悤�ł��邪�A�p�������Ƃ��\�����ʂ���A�ޕ��q������r�ł͌䐳�M�Ƃ��A���Ƃɖ��������ւ̎���Ƃ��Ă���B���̕s���̕�����U�M�q���Ђr�̓����{���q�O�ɏo�������r�������Ă��̑�̏Z�����肵���Ƃ̏؋��ɂ���̂͂��܂�ɔ���̎���ł���B
�@�{���̏��߂ɂ��������ʂ�A�@��ߌ�̑�͍��̂Ƃ���ł͖��ĂłȂ��Ƃ������B���ł���B�����������ɓ`���A���������b�ɓ`���Č��O���N7���ɑ�n�k�Ŕj��150�N���₵���Ƃ����̂́A�͂邩�㐢�̋U�`�ł���B�̓����́w�����q�ɂ������r�L�x�̓��T�q�ɂ��Ă�r�̉����ŁA���b�q�ɂ����r�͓����̒�q���Ƃ����́A�U����d�˂��̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�܂��A��S���R�q�����ǂ���܁r�ɂ�����q�ɂ�����r�̔���匩���ŏꏊ���悢���痧�����܂łŁA���̒n����̉��V�̏����͖��炩�ɂ����ׂ��łȂ��B
�@���̕������A�䐳�M�łȂ��ƒf������ɂ�������ʂ��A�䐳�M�ł����ē����ւ̎���ł���Ƃ����͑呁�v�ł���B
�@�܂������������̂悤�ɁA�@���ɂ���炪�{�@�ɓ]�����Ȃ�A���G��l���ʓ��ƂȂ��ׂ��ł���B�G�t�E�َt�������q���r������A���t���@��ɋ��ׂ��ł���B�܂��A�G�t���t�͂��鋻�t�̌�ē̉��Ɏ�E�����邱�Ƃ́A�����̕x�m�̎���̏�ł�����ׂ����Ƃ��Ǝv����B�����͉����̋c�_�݂̂ł��邪�A�����ʓ��̕t����]���C�������Ă���
�@�܂��A���̌䕶�ɁA�u��Ɛ\���͏�Â͏�s�̏Z���Ȃ�v�Ƃ�����A�w�O�o�i�x�́u�O����s�v�Ɖ��߂�����肪�A���ɎO����s��F���Ղ鏊�ȂƔޓ��̏����ɍl�����Ȃ������U�炷�́A�ޓ����ʊ����q�ׂ��傤�r�D�݂ŁA�ǂ����ł������ߑ̂̂킩��ʌÐ_���������q���傤�r���Č���K�q����������r���W�߂��i�̈��K�ł��邪�A�����̂��Ƃ��A��ׂ̂��Ƃ��A���ʎR�̂��Ƃ��Ȃɂ��ˏ��q���ǂ���r�̂Ȃ����̂���������Ȃ珟�肶�Ⴊ�A����ɂ��@�c�̌䏑�������Đ^���炵����`����Ȃ�A�䕶�̉��߂����ł��ꉝ�͐����ɂ��ׂ��ł���B
�@������A�u��Áv�Ƃ������������Ƃ݂�B�u�Z���v�Ƃ������������Ƃ݂�B�v���ܕS�o�_���̖��n�̎�����ÂƂ������̂��A�ǂ��ɂ��邩�B�Ղ��������������Ƃ�N���Z���Ƃ��������̂����邩�B�@�،o�̎l���F�̊����Ȃ�A���@�o���Ȃ���@�c�ߑO�ɏ������l���ǂ��ɂ��邩�B���̏�s��F���O�ɂ��āA��3�̏�s��ʂɍՂ�Ƃ������Ƃ�������̂��B��T�ɂ��邪�悢�B
�@�܂��A�Z���Ƃ������Ƃ�^�ʖڂɍl���A��s�Ƃ������Ƃ��O����s�Ƃ�����ǂ��Ȃ�B���{�̕x�m�S�́A�ܕS�o�_�����n����̕��s�ł��邱�ƂɂȂ�B�����A�x�m���ɂ̕x�m�_�s�_�q�ӂ�����Ƃ��r�Ǝ��ʂ��āA�^�@�w�҂̍D�ދc�_���������邱�ƂɂȂ�B�l���F�̒��̑�3��s���M���̏Z�l���Ƃ���A��1�̏�s��F�͏��̏Z�l���B��Ύ��͂�����Ă���B���@�͋��֍ہq�������r�Ɋтʂ��s���̔Ƃ�������@�x�̗~�߂����ʐl���Ă���Ă��낤�B��{�́A��4���Ӎs��F�̏Z���ł��邩�B�����A�r�����Ȃ������͂悻���B
�@�������A�����Ă��̌䕶���䐳�M�Ƃ��ĉ��߂���Ȃ�A��̎n�߂̓ޗǒ�������������ɁA��s�Ə̂���L���ȍ������Z��Ă����Ƃ݂��Ó��ƂȂ��ׂ��Ă͂���܂����B
�@�Ƃ����A�Ðl�̂��߂ɂ����������̂܂܊ۓۂ݂ɂ��āA�V���������̒q��������̂܂Ă��l�@�������A�ᔻ����������̂͋�������̊O�͂Ȃ��B
�w���˓a��Ԏ��x(�S�W1456��)�@�@��̍��̎�q�����ނ��r���Ȃď����ギ�ׂ����B�A���M���̕S���������g�����߂A���G���͕ʂɖ⒍�L��ׂ��炴�邩�B��i�[�E�퓡���������̘T�Ђ̎��Ɏ���Ă͌��q�݂Ȃ��Ɓr�ƍs�q�̊��q�����r�߂Ɉ˂�E�Q�n�����鏊�Ȃ�B�Ⴕ���N�����ɋy�Ԃׂ����V��\���A���������ׂ��炸�B���̌̂͐l�ɎE�Q�n���������ɏd�˂ċN�����������Ď������҂́A�Í����]�L�̍����Ȃ�B���̏�s�q�̏��s�������ނ�@����ΐg��e��鏈�Ȃ��A�V���߂ɍs���ɕ��q����r�Ԃ���̖�����ׂ����B���������B���̎|�𑶂��Ė⒍�̎��A���X�q��Â�r�ƔV��\���A��߂ď㕷�ɋy�Ԃׂ����B���A�s�q�ؐl�𗧂Đ\���A�ޓ��̐l�X�s�q�Ɠ��ӂ��ĕS�����̓c�����\������̗R�V��\���B�Ⴕ���A�ؕ����o���Ζd���q�ڂ�����r�̗R�V��\���B���X�ؐl�̋N������p��ׂ��炸�B�A���A���̎E�Q�n���̂݁B�Ⴕ���̋`�ɔw���Γ��@����Ƃɂ��炸�A���@����Ƃɂ��炸�B���X�ތ��B
�O����N�\���\����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�䔻
���˓a�@�@���G���ٓ��A������
�@���̌䏑�ɂ��ẮA���X��L�̉���𗪂��āA��ӂ����ɂ��Ă����B���߂Ɂu��̍��̎���Ȃāv���Ƃ����̂́A�����̕�����萄���w��\��x�ł��邪�A���́w�\��x�̂Ȃ�O�ɑ嗪�q�����Ɓr�����ڈ��̈ĕ���^����ꂽ��������ʁB
�@�M���̕S�����̑���̎҂Ɩ@�؏@���̎҂Ƃ̌��܂̍ٔ��������ɂł����Ȃ�A�����ɂ����ɗ��������g������̂ŁA���G���̑m���ɂ͂Ȃ��̍���������ׂ��łȂ��B��i�[��퓡�����������A�M���̔_���������W�߂Ė@�̐M�҂��E�Q�n�������̂́A�@���s�q�̐����q�����ār�ł���B���s�s�ɎE�Q����ꂽ��ɎӍߓI�̋N�����܂ŏ����Ƃ����Ȃ�A��؏����Ă͂Ȃ�ʁB���̂悤�ȊԈ�����n���������ƁA�É���������ׂ����̂���Ȃ��B����ǂ��납�A�s�q���������\�ȗl�l�ȏ��s�������グ���Ȃ�A�s�q�͖ʖڂȂ��ŁA���ɓ���˂Ȃ�܂��B�@���ɓ��Ă͂ߏ����Ȃ��قǂ̑�߂ł���B�K�������Ƃ��̈ӌ��q����������r�Ŗ⒍���ł����`�q�������r�ɓ˒��邪�悢�B��������Ύ��R�Ɍ��̌䎨�ɓ���ł��낤�B�ޓ����ؐl���o�����炩�������ɁA�ؕ����o�����炩�������ɁA�����ďؐl�ɑ���ɂȂ�ȁB�N������p���ȁB�������A���݂̌��܂ɂ��đ��݁q���������r�̑��Q�����͂݉B���������̌�ٔ��ɏ]����B�ߏ�̒��ӂՁq�Ȃ�����r�ɂ���悤�Ȃ�A�\����q�łȂ����B�ƁA���̎����Ŋ��q�ɏo��ꂽ���t�E�G�t�E�َt�����܂��ꂽ�̂ł���B
�@
�@�w���l���ҕԎ��x(�S�W1455��)
�����\�ܓ��э��̌䕶�����\�����э��ɓ������B�ޓ��䊨�C��ւ�̎��A�얳���@�@�،o�얳���@�@�،o�Ə������B�ɑ����ɔB
��߂ĕ��̋���̐g�ɏ\�����̓���Ղ��@�،o�̍s�҂����݂��B�Ⴙ�ΐ�R���q�˔��q���сr�����̔@���B���q�́r�����A���S���̐g�ɓ���҂��B�߉ޑ���\���̏������铙�̌܌ܕS�̖@�،o�̍s�҂���삷�ׂ��̌䐾�͐��Ȃ�B�w��_�x�ɉ]�킭�A�\���ł�ς��Ė�ƂȂ��ƁB�V��]�킭�A�ł�ς��Ė�ƂȂ��Ɖ]�]�B���̎����q�ނȂ��r���炸��ΐ{�k�q�����r�ɏܔ��L��B���˖[���[�����̎|�𑶂��Ė⒍�𐋂��ׂ��B���̋���ɐ\���ׂ��悤�́A���i�̌䊨�C�̎����l�̋���Y�ꋋ�����B���̉��q�킴�킢�r�����L�炸�B�d�˂ŏ\�����̔���������邩�ƁA�Ō�ɐ\������B���X�ތ��B
�@�O����N�\���\���������@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�䔻
�@���l����Ԏ�
���̎���q�́r�Ԃ�Ȃ�A���̕��ɂ͙�q�Ƃ��r�Ȃ��ƊF�l�\���ׂ��B���A��i�[�����n����ׂ��B����ΐl�X��q���Ɓr�ɕ|�Âׂ��A�V�̌�v���Ȃ�B�e�X���|�Â邱�ƂȂ���B���q��r����čs���Β�߂Ďq�ׂł��ʂƊo���Ȃ�B���x�̎g�ɂ͒W�H�[�����ׂ��B
�@���̌䏑�ƑO�̂Ƃ́A���t�̌�e�ʂ��d�{�{�厛�Ɍ������Ă���B�܂����̌䕶�̑O��ɋ��t�̕t�L������B����͌䕕���Ɂu�����˖[���@�v�Ƃ���B�u���v�̎��ɂ��Ĉِ��̊������Ȃ��ꂽ���Ƃł��邪�A���̗v�łȂ�����ȗ�����B
�@�����\�ܓ����Ƃ����̂́A�\�ܓ��̗[����葁�n�����Č�剺�����q�𗧂��āA�\�����̗[���ɑ吹�l�̌䋖�ɓ��������̂ł���B
�@�ޓ��䊨�C�����Ƃ����̂́A�\���\�ܓ��ɕ����q��ї��j�̖����~�ɎU�X�̐u�₪�������B�v�q�܂�r�͖@����߂ĔO���\���Ƃ̂��Ƃł���ɁA�_�l�Y���͂������Đ�����グ�Č��ڂ��������̂ŁA���ɂ͎a�߂ɂ������ׂ��S�ɓ��ꂽ�B�䊨�C�Ƃ́A���̎��̌䏈���̂��Ƃł���̂ɁA���̌䊨�C��M�������̎��ɌJ��グ�A�܂��͎a�ߎˎE�̎��̂悤�ɖ\��������̂�����B����͕L�킱�̕��y��
�@�w��q�����x�q�����Ɉ��p���r�ǂ�������̌��ł���B
�@�ɑ����ɔ����Ƃ����̂́A��͕����q���P���ҁq����r�Ɍ����ċ�����̂ŁA���Ȃ킿�@�؎��̏\�����������j�̐g�ɓ���Ղ��āA�_�l�Y���ɂ͂����ċ��`�̓S�ΐS�̐M�����ۂ�����q���r�߂����߂ɁA�O����\���Ζ��ߕ��Ƃɂ��ĉƂɋA���Ă�邼�A�\�����Ζ��͂Ȃ����ƈЊd�����B����͐�R���q�̋����S�̋�������߂����S�̂��Ƃ��A�˔����q���r�̎{�S�̑召�����߂���̂��Ƃ����̂ł���Ƃ̗��������ꂽ�B
�@�܂���́A���j�������҂Ɍ����ċ����āA��ʂ�̐u��ő��炸�ɁA寖ځq�Ђ��߁r�Ȃǂ��U�X�Ɏ˂����Ė��@�Ȗ⒍�Ԃ�́A���S�̜߂��ċ����鋶���̔����ł͂���܂����Ƃ���ꂽ�B
�@�߉ޑ���\�����Ƃ����̂́A���@�̖@�،o�̍s�҂��Ε��E��F�E���V��ߓ�����삷�ׂ��ł���B�@�̖��̗͓͂ł�ς��Ė�Ƃ���̕s�v�c�������Ă�B���̓�̗͗p�q�͂��炫�r�͂킯���Ȃ��@�̋������\�s�̐����Ɉ���������悤�Ȃ��Ƃ͂���܂��Ƃ̌�ӂł���B�͂����čٔ��ɂ͕��������A�������������q��͊Ԃ��Ȃ����n�����A���̎�l���̖k���Ƃ��Ռ`���Ȃ��S�сA���R�Ƃ������Ɍ��Ђ��������B�܂��čs�q���͎��ƂƂ��ɏ����Ă��������B�������_�l�Y�̕��͉i�v�ɂ��̑s�����@�̍��Ƌ����̂ŁA�ܔ����炩�Ȃ���̂ł���B
�@����͎���̐���s���ł��邪�A�����Ȃ�ׂ�������S���ɐ[���l���āA�@��ɗ����ĕ٘_���ׂ��A���t���Ɍ����܂߂���̂ł���B
�@���̋���ɐ\���ׂ��悤�����Ƃ����̂́A����q���r�́A���q��сq��������̂��傤�r�Ƃ������̂̎x�ߖ��ł����ĉ��сq�Ă����r���̗ނł���B
�@�u���i�̌䊨�C�̎��̐��l�̋v�Ƃ́A�w��X�U�����x�q�S�W911�Łr�́@
�u�S����N�O�N���N�����ɍ��̌��哯�m�����n�܂�ׂ��B���̌�͑����N�N��ƂĎl������ɂ͐������U�߂�ꂳ�������ׂ��B���̎��������ׂ��ƕ����q��тɐ\���������ǂ��v
�Ƃ��邱�Ƃ��A����ł���B���i�̑吹�l�̋����A����Y�ꂽ���B���E���t�E�����N�N�̍Г���܂��L��ʂł͂Ȃ����B���̏�ɗ��j���g�ɂ͖@�؎��̏\�������@����ł��낤���ƁA�����̍Ō�̖@���ł����Ɛ\���n����A�Ƌ����킳�ꂽ�̂ł���B
�w���l����Ԏ��x�Ƃ����̂́A���t���l�Ƃ���ꂽ�̂ŁA�J�R��l�̊�������ꂽ�ꕶ�ł���B
�@���̎���Ԃ�Ȃ�����Ƃ����̂́A���̒Ǐ��́A�O�Ɉ�����w���˓a��Ԏ��x�ɂ��ׂ����̂ł���悤�Ɏv���B�u���̎���Ԃ�v���́A�w�\��x�ɂ��Ēق���@��㓙�̍߉Ȃ̏��X�ł���˂Ȃ�ʁB����ɂ���ē����̖��߂������ĉ@��㑤�̗L�߁A���Ƃɔ����̑�i�[�����ɂ��ė��n��������������ł��낤�B���ꂪ���炩�Ɉ�ʂɒm��ꂽ��@�������낵���v���ł��낤�B�����̂��Ƃ��O�̌䏑�̒Ǐ��Ƃ��邪�悢�悤�ł���B���{�����˂Ίm���Ȃ��Ƃ͌����ʂ��A�ʖ{�Ō��Ă������͍����q���������r�����`�ł��邩��A�Ȃ����炱�̎v����[������B
�@�e�X�ɂ͕|�Â鎖�Ȃ����Ƃ����̂́A���̔��̈ӂŁA�\�����̉��삪�\���ɂ��邩��ł���B
�@������čs�������Ƃ����̂́A��s���l�������ꂸ�A�Ȃɂ��Ƃɂ��Ă����M���������āA���̕����狭���I�Ɏd�|�q�����r���邪�A��l�B�ɔ��Ȍڗ��q�����r��^���Ŏ����������ɍٔ��q���r�������ƂȂ�̂ł���B
�@��╶�ɂ́u�������Ă䂩�v�Ƃ���B�ʖ{�ɂ́u�����Ă䂪�v�Ƃ���B�u�����v�ł͓���Ӗ����Ȃ��ʂ���A�ʖ{�ɂ��āu����v�ƒ����Ă݂��B
�܂��A���߂́u��Ȃ��Ɓv�́A��╶�ɂ��ʖ{���u�Ƃ��Ȃ�Ɓv�ƂȂ��Ă��邪�A����ł͈Ӗ����Ƃ�ʁB�ܑ̂Ȃ����Ƃł��A���炭�����Ă����B
�@���x�̎g�ɂ͒W�H�[���ׂׂ��Ƃ����́A���̎��Ɋ��q���}�g�𗧂�Ȃ�A�W�H�[���悢���Ƃ����̂ł���B����͋��t�̒�q���ł͂Ȃ����A��{�o�̐l�ŁA�����Ƃ����āA�w��Ԓ��x�̓̉��ɋ��t�̒�q�̔g�؈�z�O���ƂƂ��ɂ���W�H���ł��낤�B
�w��q�����x(�m��q�̉�)
�x�m�����s�뎛�q�����ł�r��������G�́A�����̒�q�Ȃ�B����ė^�\�����A���̔@���B�x�͂̍��x�m����͍�����q���킢���傤�فr�����T�́A�������̒�q�Ȃ�B����ė^�\�����A���̔@���B
�w�@���@�x
�x�m�����s�뎛�z��q�������r�[�́A�����̒�q�Ȃ�B����ė^���\�����A���̔@���B�A���A�O���N���A���@�ɔw������ʁB
�@�����Ɂw��q�����q�ł��Ԃ傤�r�x�Ƃ����̂́A�d�{�{�厛�Ɍ������������l�̌䐳�M�ŁA�ς����͓���ɁA
�@�u���@��q���ɗ^�\����M��{���ژ^�̎��B�i�m�Z�N����q���̂����ʁr�v
�Ƃ���ʂ�A�@�c�吹��M�̌�{�����A���t���A�䎩���̌��q���Ɍ���^�ɂȂ������̋L�^�ł���B
�@�����Ƃ��A��ݐ����i�m�Z�N�܂ł̂��Ƃ��L�����āA��꒼���̒�q�������]���̒�q���܂ł����L���Ă���B�܂��A�M�̕ϑJ��ώ��E�}���̂��Ƃ܂ł��L���Ă���B���ɏ@��Ƃ��Ē��d�̎j���ł���B
�@�J�R��l�̌䖟䶗����^�ɂ��ċތ����d�q����Ă����傤�r�������ꂽ���Ƃ́A�w��k���m���x�̋L���ł��킩�邪�A���̋L�^��q�����Ĉ�w���肪�����A���̘V�m���ɂ͕C�ށq�������r�Ȃ��肵���ƂƎv���B
�@����ɂ͏��߂ɏo�Ƃ̑m��q�E���̓�����q�������āA���ɑ���q�����A���ɏ��l��q�����A���ɍ݉ƒ�q���������Ă��邪�A�y�v��66�����˂Ă���B
�@����́A�J�R��l�̑m���̌��q�̑����ł͂Ȃ��A�\����ɂ��߂��Ȃ��낤�B
�����A�@�c��{�������肢�������ꂽ�[�M�̐l�B����ł���B������J�R��l�̌䔼���ɑ���ʋ͂��̎���̂��Ƃł���B
�@�����Ƃ����̂́A���łɑO�Ɍ������x�m�S�̓��암�ł���B
�@�s�뎛�Ƃ����̂́A�M���ӂ̒n���ł��낤�B���邢�͑�̒n���M���̎s��Ƃ����B���Ȃ킿�A�����̌����̖k���Ȃ�v����R���q�����킢���܂��r�ӂɂ��肵���A����s��̎��Ƃ��������̂��A�@���ɑ���Ԃ�āA���̕ӂ̏��Ɏs�뎛�ƒn�����c�����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�w��q�����x�ɂ��A�s�뎛�ƔM���Ƃ�ʁX�̒n�ɂ��Ă���B���t�́w�O�t�`�x�ɂ��u���G�E���ق͎s���o�q�Ђ��r�����v�Ƃ���B�v��̈�掛�́w���u�x�ɂ��u�������N�A�@�c���@��m�@���q�ق�����r�m���G�n�����A�v��R�s��q�����킳�Ђr���ƍ����v�Ƃ���āA�s�뎛�̖���p���Ă���B
�@�s��q�����r�Ƃ����n���̋N��́A��Õ��X��������̎s��̐ՂɂāA�x�m�S�ɂ��e���Ɂu�����v�̖����c���Ă���B�����t�߂̎O���s��E�����̖{�s�ꓙ�ł��邪�A�v����R���ӂɂ��̖��͎c���ĂȂ��悤�ł���B
�@��������G�Ƃ����̂́A��m���̎���ł��낤���A����̓`�ɂ́A�����َt������̂悤�ɂ��Ă���B�ܐl�̊w�����Ȃ�Ė��������l�B�̂��Ƃ��Ⴊ��A�M�p�͂ł��ʁB�َt���A�����シ���ɉ����ɍs���āA��͓��R�Ɏt�̋��t�Ƃ͑a���ɂȂ��āA�������đ���Ƃ̌�ʂ��[�������̂ŁA����ɂ͏G�t���َt�̖����m���Ă�ӂ�����A�������ʂɗ��h�Ȏ��ւ��c���Ă�ӂ���ł�����
�@����q�������r���Ƃ����ē��G�̖������炩�ɂȂ����Ղɂ́A�َt�̓���Ə̂��鉺������E�ƊԈႦ���邱�Ƃ�����B���G�Ƃ����Ă�������ƂȂ����Ղɂ͖Ό��q���͂�r�̒O�g�����G�ƊԈႤ���Ƃ�����B���n����ɁA�����̓���E�𖼂̓���ō��G����j�`����������悤�ł���B
�@�G�t�̉�����̌𖼁q���傤�݂傤�r�́A�����ɖ[���ɂ��p���Ă���͒ʓr�̂��Ƃł���B�V��@����̖{���͂킩��ʁB������͈ꎞ�����ɉ���ꂵ���A�Ԃ��Ȃ����t�̋��ɂ�����āA�g�����R�̌䋟�����āA���̖{�R�̗����V�����Ă�ꂽ�B�ӔN�ɂ͏���ɊՋ�����ꂽ�Ƃ����{�R�̌Ó`�ł��邪�A���̖{��@�̖{�R�v�����̒n������ł���Ƃ�����������B�������N�Ɏs�뎛���N�����Ƃ����́A��掛�̓`�ł���B�V���N�ԁA��z�@���v�q����悤����ɂ��悤�r�����q�����Ɓr�̊J��ŁA�G�t�͊����J�R�̂悤�ɂ������Ă��邪�A�S���G�t���s�뎛�𗧂ĂČ������N8��10���̑J����ɔp�₵�����̂��A����ŕ����������̂ł��낤�B
�@�܂��A�G�t�̐����E�����͏������L�������̂��Ȃ��B����2�N�A����o�q�Ђ��r�̎��ɁA���łɑ����͖ŖS���Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@����͍����T���Ƃ����̂́A����q���݂����r�Ƃ͑�{�Ȗk�̒n�ŁA�͍��͌����̖{��@�̖{�R���R�{�厛�̓���Ŗ������̂��鏊�A���t�̊O�ʁE�R��Ƃ̏Z���ł���B�Ő삪�x�m��ɍ�����Ƃ���t�߂ł���B
�@���t�́A�����쑺�ŁA�b�B���S�ݏ��̒n���ƌ����Ă��邯��ǂ��A�������̂��̂ɂ�B�͍��̐l�ŁA�R��Ƃ̈ꑰ�ł���Ƃ������Ƃ������ł��낤�B
�@����2�N�ɑ���o�̎��������Ɏ����o�łāA�͍��̑��Ƃɂ���ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B�{�R�̓�V�V�����Ă�ꂽ���A���̌�Z�͑��q�����Ӂr��苗����P���Ȃ킿���t�̉��ŁA�R��Ƃ̓���̌Z�ł���B��Ύ��̕t�߂ɓ����������Ă�ꂽ�̂́A�͍��̘@���q���t�̊O�c���r�̕��J�q���r�������߂ł���Ƃ����Ă���B����2�N3��12���̌�J���ł���B
�@�z��[�Ƃ����̂́A�َt�̂��Ƃł���B���قƖ��L���ĂȂ��Ƃ��A��ݐ��ɊO�ɉz��[�Ƃ����l���Ȃ��B�܂��s�뎛�ɂ͖��_�̂��Ƃł���B�u�O���N���A���@�ɔw�����ʁv�Ƃ��邪��َt�̊O�ɂ͂Ȃ��B��ɓ��ݗ��܂��čŌ�܂ŕ������ďG�t�Ƌ��ɖ@��ɋ���ꂽ�E���ł���B
�@�����ɉ����Ă�����̖��������N�āA�㑍�ɍO�����Ęh���q�킵�̂��r�̘h�R���q���ス�r�����Ă�ꂽ�B�u�O�����A���@�ɔw���v�Ƃ���ꂽ�̂́A���̊ԂɊ֓����̖@�`�ɗ^�����ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�܂��A���@�E�V�ڂƒʗp����ꂽ�͎����ł���A�u�����̍��̏Z�A��o�q�����݁r�[�͉z��[�̒�q�Ȃ�B����ē����V��^���\���B�z��[�t�߂̎��A�����ɔw�����ʁv�ƁA�w��q�����x�ɂ���B���̐�o�Ƃ����́A�a��q�����݁r�̒ʗp�ł����āA�a������@��l�ł͂Ȃ��낤���B��������A�@�t���M���z���ɊW�̂���Ó`���́A���������ǂ��날�邱�ƂƂȂ�B
�@�O��6�N�����́w��Ԓ��x�ɂ́A�z����̖����a����̖������邩��A�吹�l��a�C�̐܂Ɉꎞ���l���ł������̂Ƃ݂�ׂ��ŁA���̕�֔�18�V�m�̒��ɁA�u�z�O���g�؈� �z������� ��������G �@�؈�苗����� �a������@ ���������� ���@��苗����� �����ړ� ����[���@��9�l�̒�q�E����q������A�W�H�������̖@��������B���Ȃ킿�ߔ����̖��������������鋻�t�̐��͂�����������B
�@�َt�̑����͎���ł͕s���ł��邪�A����ł͔M���r�l�Y���d�̒��j�ŁA�x�ؓa�̖�������͂��̎o�ŁA��������E�͂��̒�A�����E�����E����O�͂��̉��E�ÁA�V�ڂ��܂����ł���悤�ɂ����Ă���B�ʂ��Ă�����A�r�l�Y���d�͂�قǂ̘V�N�Ƃ݂��B���̌Z�̖퓡���͐����Ēm��ׂ�����B���Ƃɐ��͌����ŔM�������ł���ɂ����ẮA�w��q�����x�̔M�����̏Z�l�݉ƕS���Ƃ���ꂽ�̂ɂ��A�@�c�́u�M���̎ҋ��v�A�܂��́u�M���̋�ᓂ̎ҋ��v�Ƃ���ꂽ�̂ɑ�ςɑ��Ⴗ��̂ł���B
�@�َt�͏@�`�ɂ��āA�t�̋��t�ɂ͈��ꂽ���A�ܕ��O���̐��_�q������r�͘V��܂ł��ς��ʂƂ݂��A�������N��6��26���ɉ��B�̈ɋ�q�����r�S�̍�����73�̘V�̂Őܕ��̐w��ꂽ���ɁA掖@�҂̂��߂ɎE�Q����ꂽ�Ƃ������ƂŁA���ɐɂ����l�ł������B
�w�@���@�x�݉Ɛl�@��q���x�m�����M�����̏Z�l�A�_�l�Y�Z
�x�m���������̏Z�l�A��ܘY��
�x�m�����M�����̏Z�l�A��Z�Y
���̎O�l�͉z��[�E����[�̒�q��\�l�̓��Ȃ�B�O�����N�M���n�ߕ�鏈�ɁA�ɌZ�q���Ⴏ���r�퓡�������̑i�ւɈ˂��Ċ��q�ɏ����グ���A�I�Ɍz����L��ʁB���̍��q��l���̍����Ȃ�B�q���я������\��寖ځq�Ђ��߁r���ȂĎU�X�Ɏ˂āA�O���\���ׂ��̎|�ĎO�V��ӂނ�Ƃ����ǂ��A��\�l�X�ɈȂĔV��\������̊ԁA���{�O�l�������ցq���܂��r�߂Ďa�߂����ނ鏊�Ȃ�B�}�t�\���l�ɋ֍������ނƂ����ǂ��A�I�ɕ����L��ʁB���̌�A�\�l�N���o�ĕ��̓����E�������q�A�d���q�����r���n�q���イ�r�����L��ʁB���q����
�������ɂ��炸�B�@�̌�����ւ��B
�@���̍݉Ɛl��q���̉��ɁA�_�l�Y���n�߂Ƃ��ĕS���A�������Ή��l�����q�Ȃ�r�ׂĂ���B�_�l�Y���m���Ƃ���̓`�҂́A�K���Q�Ƃ��Ă��̌����|�����ׂ��ł���B
�@�_�l�Y�Z��ܘY���̌䕶�́A�������ًc���ׂ��Ƃ��낪�Ȃ����A��3�l�ڂ́A���{�ɂ͔M���ƘY�Ƃ̒����قǂ��������Ă���B�d�{���D�̊����̎ʖ{�ɂ́A������u���Z�l�펟�v�̌��Ŗ��߂Ă���B������ɁA���̖펟�Y�͐_�l�Y�̌Z��Ȃ�⑼�l�Ȃ��Ƃ����ɁA��̌䕶�ɂ��A���̎O�l�͌Z��̂悤�ł���B
�@������A���Y�Ȃ�Ύl�Y�̌Z�Ȃ�ׂ��ɁA���{�ɂ��ʖ{�ɂ��_�l�Y�̉��ɌZ�Ə��������A��ܘY�̉��ɒ�Ɠ���Ă����ɏ�����ƁA�펟�Y�̉��ɂ͌Z�Ƃ���Ƃ����������Ȃ��B�����Ƃ��Z�ɖ퓡��������A�펟�Y������ׂ��ł͂Ȃ��낤�B���l�Ȃ�Βm�炸�A�Z��Ƃ����Ȃ�A��ܘY�̎��ɗ�˂Ă��邩��A��Z�Y���펵�Y�ł���ׂ����A�D�t����ʂ����̂ł͂Ȃ��낤���B���̐���������āA�킴�Ɩ�Z�Y�ƕW���Ă������B����́A�ЂƂ��ɔ���q�͂����r�̎����q���������r��҂����߂ł���B
�@�_�l�Y���@��̓��ł��邱�Ƃ͉��ِ̈����Ȃ����A�r�l�Y�Ə����Ă���̂�����B�w���c���I�q�Ԃ����Ƃ����r�x�ɂ́A�u���Z�T��́A���فE���E���t�̕��B�M�����B�r�l�Y���d�Ȃ�v�Ƃ���B�܂��A�O��4�N�ɉ�̏���������邱�Ƃ��L���Ė@��ɋ�����m�Ȃ邱�Ƃ͋L���ĂȂ��B
�@�w�N�����فq�˂�Ԃ������r�x�ɂ́A�u�M���r�l�Y���d�͏x�B�x�m�S��̐l�Ȃ�B�����^�Ɏd���B�ٌ��E�E���̕��Ȃ�B�v�ȏ��q���r�ĉ����m�q�������r�ɎB�S�̏@���ɗ�����҂�����@�q���������r�Ƃ���B�v�͖@�������A�Ȃ͖���Ƒ�m����𖽂Â��B�O�����ɕv�͖@�̂��߂ɍ��ɉ���B��m����^���Ă�����ԂށB��Ɏa�ɏ������v�Ƃ���B����ł͖@��̐_�l�Y�Ƃ݂����A��̐l�Ƃ������Ƃ��A�����Ƃ̉Ɛl�Ƃ������Ƃ��A�x�m�M�҂̎n�߂Ƃ������Ƃ��S����`�ł���B�܂��A����E�����̖@���́A�����Ƃ̂Ǝ��Ⴆ�����̂ł���B
�@�������A2���Ƃ��ɐr�l�Y���d�Ƃ������Ƃ͈�v���邪�A�����̏o�ǂ���͂�����ɂ����B���邢�͔M���{�Ǝ��̓`�Ȃ����v���ʁB�{�Ǝ��̖���N�́w���L�x�ɂ́A�u�M���_�l�Y���d�A�@���E�@����Z�T��A�����̋��m�Ȃ�B���̖��͔M�����Y�B�@�c�̋������ċA���̌�A�_�l�Y�Ɩ����v�Ƃ���̂�����̂��Ƃ��v���B�������A200�N��̋L�^�Ȃ�A�M��u�����B�@����Z�T��̖@�����^�킵���̂ł���B�܂��ĉߋ����ɂ͌���2�N���q4��8���Ƃ���A�����̋��m�Ƃ�����A�܂��܂��^�킵�����Ƃł���B����^������������A����̋L�́w���I�x��w���فx���ɂ��Č㐢�ɂ����炦�����̂�������ʁB�Ƃɂ����A�{�����ꌩ���˂Ό��肪�ł��ʁB����ɖ푾�Y���_�l�Y�Ɖ��������Ƃ͂Ȃ�̂��Ƃ��B�푾�Y�Ȃ�퓡���̌Z�ł��낤�ɁA�ǂ��������̂ł��낤�B
�@�v����ɁA�����̏��`���݂Ȃ������Ȃ镶���ɂ�炸���āA�͂邩�̌㐢���o�`�q���ł�r�Ƃ��ׂ����̂ŁA�S���J�R��l�̌�L�ɂ��āA�}�X�������s�ׂ����̂ł���B
�@�܂��A���̎O�l�̎a�ߎ҂��A�w�N���x�܂����w�ƒ����x�ɂ́A�M���_�l�Y�E�c���l�Y�E�L����Y�Ƃ��Ă���̂́A���́w��q�����x�ɑ��Ⴗ�邪�A������ɂ��ǂ����u���ꂵ��A���t�̊e���ɂ͖��炩�Ɏ����ĂȂ�����ǂ��A�����̍��������������̂ł��낤�B
�@������ɖ{�Ǝ��̋L�ɂ́A�u�s�ɐg���̍s�ҎO�l����B�����A�M���_�l�Y�E�c�����Y�E�L����Y�A�E�O�l�@�̂��߂Ɋ��q�ɂ����Ď��߂ɍs�Ȃ�ꂯ��v�Ƃ���B����́A�����̓����q�ɂ����傤�r�̖���N�̋L�ŁA���t�́w�N���x�Ƃ͑O��s���Ȃ�ǂ��w�ƒ����x���炵���B�w�ƒ����q�����イ���傤�r�x�̉��q���r�͕s���ŁA���q���イ�r�͖���O�N�A��q���傤�r�͊����q����Ԃ�r��N�ł���A�����ꂪ�݂��ɂ��ǂ���ƂȂ������킪��ʁB
�@���邢�́A���L�݂��ɊW�Ȃ����āA���Ƃ���̓`������v���Ă����̂�������ʁB�c�����Y�Ƃ������A�c���l�Y�Ƃ��A���Ǝl�Ƃ�����Ă�Ƃ���͂����炵�����݂��邪�A�v�͌Ó`���̒��ɂ͖��q�ɂ���r�ɐM�����ʂ��̂�����B�������J�R�̌��q�ŁA�����̒ǑP�ɂ͗�Ȃ���ꂽ��Ǝv���������l�́w�O�t�`�x�ɂ́A�S����24�l�A�a���2�l�Ƃ���B�x�m��̂��Ƃ��悭�m��ׂ������́w�s��q�ނ����r���x�ɂ͑S��23�l�A�������l1�l�A�a���2�l�Ƃ���B�킸����5�A60�N�̌�̓`�ɂ���A20��24�A3��2�ƌ��Ă���B20�N��̓����̋L�ɂ������Č��̐������Ȃ����قƂ��邭�炢�ł���B
�@�Ƃ������A���̑哖���ҊJ�R��l�̌䎩�M�̋L�ɂ͑S�R���Ȃ����̂ƐM���Ă������̎j���Ƃ��A����ɑ��Ⴗ��̓`���͓�����ɒu���͂�ނ����ʓ��R�̂��Ƃł���ƐM����B
�@���O�l�͔T�����l�̓��Ȃ��Ƃ����̂́A�_�l�Y���O�l�̊O���l�Ȃ��͕������`�����Ȃ��B�w��q�����x�ɂ́A����[�̒�q�Ƃ��ĔM���̘Z�Y�g��A�������V���n�q����ӂ��r�̐_��q�����ʂ��r�A�O�Y��Y�B�܂��z��[�̒�q�Ƃ��č]���q���݁r�̖펟�Y�A�s�뎛�̑�Y���v�����A���������̎q�푾�Y�A�������햔���Y�A��������l�Y�����A�������c�����Y��9�l�������Ă���B
�@���̒��ŐV���n�̐_��͌䏑�q�@���̎��ǂ��Ƃ��Ă��Ƃɏo���r�ɂ�����ʂ�A�������ɖ@��ɋ����ׂ��l�ł���B�s�뎛�̖��Y�Ɠc���̖��Y�Ƃ́A�w�{�Ǝ��L�x���̍L����Y�E�c�����Y�Ɠ��ق�����B���������l�̕ւ��Ȃ��B�������Ȃ���A�����̒��ɂ͑S���łȂ��Ƃ��������̒l��҂�����ł��낤�B
�@���s�̖��o���ɑ�����O��3�N2���̗D�k�Ǔ����̌�{���ɂ́A���t���M���Z�Y�g��ɗ^���\���̓Y��������B����͖@���Ԃ��Ȃ����^����ꂽ���Ƃ��Ă݂�A���̐l��17�l�̓��ł͂���܂����B��������A17�l���܂�ł킩��ʂƂ������ʁB
�@�O�����N�M���n�ߕ�鏈���Ƃ����̂́A���G�E���ٓ������t�̉������̂͌����̏��N�ł������ɁA���̐܂͂��܂��݉Ƃ̐M�҂ɐ_�l�Y���̂��Ƃ����̎҂͂Ȃ������Ƃ݂��B
�@�ɌZ�퓡�������̑i���Ɉ˂��Ċ��q�ɏ����グ���A�I�Ɍz����L����Ƃ����̂́A�퓡���̖��͂��łɑO�Ɉ�����O��2�N10���̌䏑�Ɍ����̂ŁA�s�q�@���ƌ�����݉Ƃ̓G�}�̎�́q������r�ł���B�ނꂪ�M���̗^�}�̕S�������g�t���ĐM�k�̕S���Ɍ��܂𐁂������A�U�X�ɐn�����Łq�ɂ傤�������r�̖\�t���Ȃ������ɁA���������̖�l�ǂ��ɘd�G�q�킢��r���Ĕ��q���ׂ��ׁr�Ɏ������\�ρq���ւ�r���Ċ��q���{�ɑi���o���̂ł���B
�@������20�l�̐M�k�������Ɋ��q�ɑ����A�����q�嗊�j�̖����ō���ɂ������閖�ɘS�ɓ���āA������N��3�l���a�߂ɏ������̂ł���B���́u�I�v�ɂƂ��������y�X�Ɋʼn߂��Ă͂Ȃ�ʁB
�@���̍��q������̍����Ȃ��Ƃ����̂́A���̎����̍ٔ����Ȃ��ׂ���C�́A���q��ї��j�����ʉ~�q������r�ł���B
�@�q���я������\�O��寖ڂ��ȂĎU�X�Ɏ˂ĔO����\���ׂ��̎|�ĎO�V��ӂނƂ����ǂ��Ƃ����̂́A�����͗��j�̎��j�A��Ɉ��[��ƂȂ�A���Ƌ��ɔ��t�q�͂Ⴍ�r���n�q���イ�r�ɕ������l�ł���B
�@寖ڂ̖�́A�V�q�₶��r��ɂđ���A������ə��q���r��āA�ˏo�������ɂӂ�ĉ��̂���悤�ɂ��Ă���B�������q���傤�Ԃ��r���ЉЁq�킴�킢�r�����q�́r�炤�p�Ɍ×��p���̂ŁA����͐_�l�Y���������ɖ@��M���ė��j�̖҈Ђɋ����ʂ̂��A�ʂ��ēV���Ȃǂ��߂��ė͂�Y���ł��낤�A�����Ė��S���̋ƍ�q���킴�r�łȂ��B���ꔻ���A寖ڂ������Ē������Ĉ������ĔO�����������߂�ƁA�����q�傪�������̂ł���B�����ĎˎE���߂ł͂Ȃ��B�܂�寖ڂ��V�͒��E�q�Ȃ����ځr�̊ۖł��邩��A�l�������Ă��K���E�����ׂ����̂łȂ��B�����_�l�Y�������O�T�Ǝ˓��q���Ƃ��r�����̑N�����قƂ������́A7�{�ڂ̐��Ŗ��c��_�l�Y�̑��͐₦���̂ƌ����Ă�ґ����́A�����犄�o���������Y��q���傤�����r�ł��낤���B���Ƃ��A�@��̑s��ߎS�����邽�̂̑P�ӂ̐�`�ł��A�@�O�̋��ρq�������r�͐T���ނׂ����Ƃł͂Ȃ��낤���B
�@���l�X�ɈȂĔV��\������̊ԁA���{�O�l�������ւ߂Ďa�߂����ނ鏊�Ȃ�B�}�t�\���l�͋֍������ނƂ����ǂ��A�I�ɕ����L����Ƃ����̂́A寖ڂ̒����ɋ�����Ȃ����A��l���O���������鉰�a�҂��Ȃ������̂ŁA��\�l�͋֍��ƒ�܂�A�v�����S�ɂ̋ꂵ�݂����߂��B�����Ė^���q���邹�r�̂��Ƃ����j�̑�������q���イ����r�̒�q�r�ɎˎE���ꂽ�̂ł��a��ꂽ���̂ł��Ȃ��B
�@�O�Ɉ�����w���l����Ԏ��x�ɁA�u�ޓ��䊨�C��ւނ�̎��A�얳���@�@�،o�Ə������v�Ƃ���̂́A����寖ڂ̒�ł����Ď��߂̎��ł͂Ȃ��B�u���{�O�l�������ւ߂Ďa�߂����ނ鏊�Ȃ�v�̏��ւ̕����ƁA�u�}�t�\���l�͋֍������ނƂ����ǂ��I�ɕ����L��ʁv�̋֍��ƏI�ƕ��Ƃ̕����ɒ��ӂ��ׂ��ł����āA�O�l�̏��ցq���܂��߁r�Ə\���l�̋֍��q�����r�Ƃ͓����ł���˂Ȃ�ʁB�܂��A�O�́u�I�Ɍz����L��ʁv�ƁA���́u�I�ɕ����L��ʁv�Ƃ������ł���˂Ȃ�ʁB���Ȃ킿���j��寖ڂ̖@������20�l�������ɓ��S�����߂��B�܂�������N20�l���ɏ��������B���{3�l�͎a�߁A�}�t17�l�͒Ǖ��ł���͕��̒ʂ�ł���B�肭�́A�ǎ҂͂��̌䕶��ǂ�ŁA�\�̉���̂ƂƂ������ɐM����ꂽ���B�ǂ������ցq�ӂ��r�̐��ɘf�킳��邱�ƂȂ��悤�ɂƋF��̂ł���B
�@���̌�\�l�N���o�ĕ��̓����E�������q�A�d�����n�����L��ʁB���q����B���ɂ��炸�B�@�̌�����ւ���Ƃ����̂́A�����͗��j�̂��ƂŁA�������ĉʉ~�Ə̂��A�����ɂ͐������Ĉ��[��ƂȂ����B�w�k�����L�x�ɂ��ɁA�i�m���N4�������厞�̎��ɁA���j�v�����v�E�ɂ��肵���Ђ��ւ��āA���R�y�ю�����S�ڂ��A���̎q���[��q�я������r�����R�Ƃ����Ă������B����ƁA���j�̒��q�E�@�j�q�ނ˂ȁr����ɕ��̈���D��ꂵ������ŁA���̂��Ƃ������ɖ��������̂ŁA�������߁q�����ǂ�r����n�C�q���イ�肭�r�����A���~��荏��q��������r�Ȏq�͒Ǖ��ƂȂ��āA���ꂪ�@�̌����ł���ƁA�J�R��l������ꂽ�B
�@���t�́w�O�t�`�x�ɂ́A�u��X�ɝ��߂Ƃ�ĕ����q�傪��ɉg����������A�T�����̒�ɂ͕��̍��q��������q�����v�Ƃ���B���ʂ̉邱���U�ʁq�Ă��߂�r�ł���B
�@����ׂ����Ƃ��B
�@���̖��̕����A����ʖ{�ɂ́u�@�̌����Ȃ�v�Ƃ���B���D�̎ʖ{�ɂ́u�@�̌�����ւ��v�Ƃ���B�������A�䐳�{�ɂ́A���̉����炪�Ɍ��������āA�Ȃ�������߉��E�����肠�肵�悤�ł���B�ǂ���������ł����������ǂ��ł��ʂ��A�D�{�q�䂤�ق�r�ߑO�ɖ��Łq�܂߂r�������̂Ƃ݂��B�c�O�̎��悶�Ⴊ�A�D�{�ɂ��̊O�͂Ȃ��B����������̏ォ��́A����{�́u�����Ȃ�v�̕����傢�ɗ͂�����B���̉i�m���N��肳���̂ڂ���14�N�ڂ́A�O��3�N�ɓ���B����͎a�߂��O��3�N�ɂ������ł���B
�w���t��M��䶗��e���x�����O��\�K�����������x�͂̍��x�m�����M�����̏Z�l�_�l�Y�@�؏O�ƍ����A���̍��q��т̂��߂Ɍz�����O�l�̓��Ȃ�B���̍��q������@�؏O�̓^���̌�A�\�l�N���o�Ėd�����邾��̊ԁA�n�����L��ʁB���̎q���Ռ`�Ȃ��ŖS���L��ʁB
�@����3�N�͍O��2�N���29�N�ڂł��邩��A���Ԃ̔N�����̂��߂ɏ��ʂ��ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�������̂��Ƃ̗]��ɔߜƂŁA�܂��s��ł������̂��A�����ɒlj����Ĉꕝ�̌�{���������āA�d�{�ɂĈ��q�������r�̖@⥁q�ق�����r��ĕ��q�������r��E�q�����r�߂�ꂽ���̂ł���B����͖��_�A�䎩�g�����̖@��̑��叫�ł���������̌䎜�O���o�����̂ł���B
�@�������āA���̒[���q�͂������r�̕���́A�قƂ�ǑO�́w��q�����x�Ɠ���ł��邩��A�ς킵������������ʂ��Ƃɂ��邪�A���̌�{���̓��t�̉K�������ɋ����������Ă݂�ƁA����4��8���͐_�l�Y�����z���ꂽ�ˌ������ł͂Ȃ��낤���B���Ƃ��N�����ʂɂ��Ă��A�����q���傤�Ƃ��r�̌������тĒǑP���{�����ꂽ�Ƃ���̂������̐��l���Ǝv��˂Ȃ�ʁB
�@�܂��A�{�Ǝ��̉ߋ����ɂ́A����2���q�q�ւ��ˁr�N4��8���Ƃ���B�ߋ����̂��Ƃł���Γ��t�̌�T�͂���ׂ��łȂ��B���Ɍ����債�ȊԈႢ�͂Ȃ��낤�B�N��͌Â�������Ɠ]�ʂ̍ۂɊԈႢ�Ȃ���ۂ��ʂŁA�܂�����4��8�������͎��ׂ��ł��邤�Ǝv���B���ꂩ�痊�j���q�p�C�q���イ�肭�r�̓��͕s���ł��邪�A���͂�������4���ł���ŁA���邢��8���ł������ł͂Ȃ��낤���B
�@�����́u���̎q���Ռ`�Ȃ��ŖS���L��ʁv�Ƃ���̂��A�w��q�����x���ς����B���̉i�m���N�̏����̎��͗��j�ƈ��[�炪���̉��~�œ�����āA�i�l�����Z�̏@�j�q�ނ��ȁr�ɂ͌�J�����Ȃ��A������i����s�F�̎҂Ƃ��č��n�ɗ����ꂽ���A�Ԃ��Ȃ������҂��ē������q�Ȃ������傤�r�ƂȂ��ꂽ���A�߂��ď㑍�q�������r���ɗ����ꂽ�B��������̓��荠�ɂ͎��ł������̂ŁA�����Ɂu�Ռ`�Ȃ��v�Ə����ꂽ�̂ł��낤�B
�w�x�ؓa���[���O�䏑�x(�S�W990��)���Ă͉z��[�E����[�Ɛ\���m���ɗ\�a�ɂ��ČB�b���s�ւɓ��点���ւƕx�ؓa�ɂ͐\��������
�@���̌��͍O��2�N11��25���ł���B�@��̌�A2�ӌ����o�Ă���B���̊ԁA���m�͔M���ɂ͂��������A�n�߂͂��̕t�߂ɂ���ċ��t�̖����đP���ɖz���������̂Ƃ݂�邪�A�Ȃɂ��뎖���̓����҂ł��邩��A�G�}�̖ڂ̓͂����ɂ͏Z�ݓ�A���t�ɂ��Ċ��q�ɍR�i�q�������r�ɏo��ꂽ���A�{������i������20�l�����S�ƂȂ��̂ŁA�G�E�ٓ�t�ɂ͂����݁q�킸��r������q�����r��܂��B����Ȃ���A�]���̉��̂ŕx�m�̋��t�̎�ɂ��Ă������Ȃ�A��̈��k���Ɍ��q�ˁr�����ł��낤�Ƃ̌䎜�O����A�傢�ɕ��ʂ������ĉ����̉����Ɍ��킳�ꂽ�̂ł���B
�@�ɗ\�[�����q�ɂ����傤�r�́A�x�ؓa�Ɍ㌩�����Đ^�ԁq�܂܁r�ɂ���̂��Ⴊ�A�܂�20�O�̎�N�ł��邪��A�����Ԃ�N����2�l�̊w��������ꂽ�̂ł��낤�B�����̐���E�����������A���邢�͂��̐܂͕x�ؓa�A���Ă��������̂Ƃ݂����B���l��2�l�̂��Ƃ���E�q���傤�ɂ�r�����ɂ�낵������ł���Ƃ̌��ł���B
�@���[���O���A��������ł���Ȃ�A����̓`�L�ł͉z��[���قƂ͎o��ł���ɁA���̏�ɂ͏��������̈ӂ������ʁB�u�z��[�E����[�Ɛ\���m���v�Ƃē��O�ɂ͖ʎ����Ȃ����̂Ƃ��Ă���B
�w���a��Ԏ��x(�S�W1560��)���y�q���낱���r�ɗ���Ɛ\���ꂠ��B
�w���x(�S�W1561��)
�肭�Ή䂪��q�������������B���N���X�N�q�������ƂƂ��r�̉u�a�Ɏ��ɂ��l�X�̐��ɂ����炸�A�������Â̍U�ɖƂ���ׂ��Ƃ��݂����A�Ƃɂ������͈��Ȃ�B���̎��̒V���͓����̂��Ƃ��B�������Ή��ɂ��@�،o�̌̂ɖ����̂Ă�B�I���C�ɂ��炦�o���n�ɖ��ނƎv���B
�w���x(�S�W1561��)�@�@�\�ꌎ�Z���@���@�ԉ��@�@��쌫�l�a��Ԏ�
����͔M���̎��̗L��ɐ\����Ԏ��Ȃ�B
�@���ꂩ��@���̌䏑���f����B����w����䏑�x�́A�O��2�N�ŁA������Ԃ��Ȃ��ł���B���y�̗���̑�ɓo�邤�Ƃ��鋛�͑������A�o�肤����̂͌�̈ꕔ�ł���B����������ĕ����C�s���Ȃ��҂͑������A�S�����ɂȂ肤����͓̂��@����q�h�߂̈ꕔ�ł���B�M�a�́A�M���̑厖���ɐg����ɂ܂����������Ȏq�����ڂ݂����āA�Ȃɂ��Ɛs�͂���ꂽ�B���̖@�،o�ւ̌����䂦�ɓo����̗_��ɂ��Â��邱�Ƃ��ł��悤���B�܂��ƂɗL����Ƃł��邼�ƁA��܂��ꂽ���ł���B����́A�������܂��S���͉��������ĂȂ��A���̌�����a�̐s�͂����ׂ����Ƃ��������邪��ł���B
�w���a��Ԏ��x(�S�W1564��)
����Z���\�ܓ��̌��Q�x�ѓ����Č�B���Ă͐_��q�����ʂ��r�������A���܂����������������ČA�L��o����B���������X�͖@�،o�����܂����ɂĂ͌�ւǂ��A��ɂ͑��̎��ɊĎ���q���Ƃ��Ár�����܂�邩�̌̂ɁA�M���̎҂Ɏ��Ă��������������ǁq���r�����ɂ�����ʂ�B����Ƃď�Ɏ����ǂ��čǂ������Ɍ�p����킸�Ε��o���ʐl�ɂȂ点�����ׂ��B���������Ĉ�����ʂׂ��悤�ɂČ��A���炭�_�哙������ւƋ��ׂ��B�Ȏq�q�߂��r�Ȃ�ǂ͂���ɌƂ��A�����q�˂͌�킶�B���̐Â܂�܂ł���ɂ��������Č���낵����Ȃ�Ɗo����B
�@�q�S�W1564�Łr�@���炭�̋ꂱ����Ƃ����ɂ͊y������ׂ��A������l�̑��q�̔@���B�����ł��ʂɑ��q�r�������Ǝv������ցB���X�ތ��B�O���O�N��������@�@���@�ԉ��@�@���a��Ԏ�
�l�ɒm�点�����āA�Ђ����ɋ��ׂ��B
�@����Z���\�ܓ��̌��Q���Ƃ����̂́A������Y���Y���o�R���ď@�c�ɂ��ڒʂ�Ȃ��ꂽ���x���̂ł���B
�@�_�傪���܂����Ƃ����̂́A�_��́A�䏑�Ɂu�R�E�k�V�v���ł́u�J�m�k�V�v�ƌ����Ă���B�_�Ɏd����҂ł���B�P�ɐ_��Ƃ̂ĂԂƂ��́A�����Đg���̔ڂ����҂ł���B����͉��Ɉ����w��q�����x�̔M���̐V���n�_�Ђ̐_��ł��邻�̊O�A���l�������ƂɉB�����Ă���B������M�҂̂����Ȃ�҂ŁA�K���ɕߔ���Ƃꂽ����ǂ��A��N�����������܂ł�������̑F�c�͂��т����̂ŁA����Ƃł��[���B�܂��Ă���B�����̎����̋�J���ܒV����ꂽ�̂ł���B
�@�����������͓��Ƃ����̂́A�k�����@�͓��X�ɂ͏@�c�̖@�،o�������q���r���邯��ǁA�\�ʂ͑��̂��Ƃɂ������ď@�c����ђ�q�h�߂ނ���A���͓��a���M���̎c�}���B�܂��������̌��^����A���̂��Ƃɑ�Ď�X�ɓ��a�������߂Ȃ���̂ƕ���ł���B
�@����Ƃď�Ɏ��������Ƃ����̂́A���R�Ƃ�k���Ƃ���M���̂��Ƃɑ�Ė����Ȗ��߂�������̂��A����͂��܂�䖳�̂���ƌ����Č䔽�R�Ȃ���悤�ł͂����ʁB��̌�ӂ̓����q�������ԂƁr�������q�݂����r�Ă��Ă��A�ȂɂƂƂ��_���q���Ȃ��r�Ɍ䕞�]�Ȃ��邪�悢�B���̂��ڂ��ʕs�o�̖v���Ŋ��q�킩�炸��r�ɂȂ�ʂ悤�ɂ���Ƃ̌䒍�ӂł���B
�@���������Ĉ���������Ƃ����̂́A��l�̑F�c�����т����ē���B�܂�����ʂ悤�ɂȂ����Ȃ�A�g���֓������Ȃ����B�����܂ŒT���̎���͂��܂��B����͓��X�ɐ\������ꂽ���B���ɘR��Ă͂Ȃ�ɂ��Ȃ�ʂƒǏ��ɂ����ӂ����ł���B
�@�Ȏq�Ȃ�����Ƃ́A�䌾�́u���R�v�͂��Ȃ킿�Ȏq�ł���B��l�ɂ͏�̌��߂����낤���A���q���ɂ͍߉߂͂Ȃ��낤����A�����̑S����������܂Ō�ʓ|�ł����{���Ȃ���悤�ɂƋ�����B�O��2�N��10����20�l�����S���A�O��3�N��4����3�l�̎a��A17�l�̒Ǖ��łЂƂ܂������̂悤�ɂ݂�邪�A���ۂ͂��̌�܂ł�����c�q�����r�����т��������Ƃ݂��B����́A���R�Ƃ⎷���Ƃ̖��߂���Ȃ��B�����q��̌v�炢�ł��낤�A�ہA���j�̍s�ׂ���Ȃ��B�@���s�q�≺�������̉��i�ǂ���퓡���������̎d���ł��낤�B�����̕\�����ɂȂ�ʎ��ł��䋳�����U�����ĈЊd���邭�炢�̂��Ƃ́A�Ȃ�Ƃ��v��ʈ����ł���B�܂��čٔ��͑叟���̂��Ƃł���B�Ȃɂ����Ă����x���Ȃ��Ǝv���Ă���B���Ɉ��q�ɂ��r�ނׂ���s�ł���B
�@�ޓ����l�Ԃ̌��͒ʂ��Ă��낤�ɁA������O�l�܂ŎE�����Ă����āA�܂����s����������ʂƂ����̂͑S�����S�����g�q�������ɂゲ����r�̂��߂ł��낤�B
�@���炭�̋����Ƃ����̂́A�M�������̂��̂̌�䅋�q�����r�͉i�����Ƃ���Ȃ��A�����炭�ł���B���������ׂɌ�M�S������悤�ɂȂ낤�B��l�̑��q�́A�����ɋ�J���Ȃ���Ă��A�����ꍑ���̈ʂɑ��q�r����ׂ��ł���B���a�́A�{�Ձq�����r�Ő����̑f���q�������r�𐋂����Đg���S�����ׂȂ�ׂ��ł���Ǝv��ꂽ���Ƃ̌����ł���B
�@�l�ɂ��点���������Ƃ����̂́A�_�哙��g���ɑ��邱�Ƃ̘b�͂Ȃ�ׂ��閧�ɐ\�������ׂ��ƁA���Ȃ킿�O�ɂ��q�ׂ��ʂ�ł���B
�@���̌䌾�Ə�́w����䏑�x�Ƃ́A�@�c�̌䐳�M���{�R�Ɍ�������B�w���发�x�͊��ǂł��邪�A���̏��͒����̒f�тł���B
�@�܂��A�����̓́A���t�̌�ʂ����{�R�Ɍ�������B
�w���a��Ԏ��x(�S�W1575��)
�M�ӂ͂��łɖ@�،o�̍s�҂Ɏ��������ւ鎖�A���̐l�Ɏ��A�݂̌��Ɏ����邪�@���B�M���̎ҋ��̂����ɂ܂����ւ鎖�́A�����q���傤�ւ��r�̏���q�܂����ǁr�A�V��q�Ăr�̒哖�q�����Ƃ��r�̂悤�ɂ��̍��̎ҋ��͎v�ЂČB����ЂƂ��ɖ@�،o�ɖ����̂�̂Ȃ�B�S����N�ɔw���l�Ƃ͓V�䗗���炶�B���̏�킸���̏����ɑ����̌������߂ɂ��Ă��āA�䂪�g�͏��ׂ��n�Ȃ��B�Ȏq�͈���������ׂ��߂Ȃ��B
�@����͍O��3�N12��27���̌��ł���B�S������̉ӏ����Ȃ���Β����𗪂���B�M���̐M�ҒB�̂��߂ɂ��Ƃ��Ƃ܂ł��A�_�哙���B�܂���ɂ��g�������Ȃ������Ė@�،o�ւ̌�����������a�̂��肳�܁A���ɑ��Ƃ��̌���ł���B���{�̖������͑������Č����ӂ́A���Ȃ킿�c�d�q�łr���ŕv���q�Ԃ₭�r���̕��ہq�Ԃ��r���ߕ��ł���̂ŁA�n���̐g���Ƃ��Đ����ɕn��������̂ɁA�@�c�ɂ��������̌�u�͏������ӂ�Ȃ����Ƃ���ܒV�Ȃ���Ă���B
�w���a��Ԏ��x(�S�W1575��)����U�����L��ʁB���A�_��̋��Ɍ������q���������r��D�q�Ђ��r���тɌ��t����l��B�T���A�Ȃ����Ȃ����@�،o�����ގ��͐₦�Ƃ�������͂˂A�������������Ȃ鎖����͂�߂ǂ��A���܂Ŋ��ւ������ւ鎖�B�܂��Ƃ����炸��B
�@����͍O��4�N3��18���̎���ł���B���̎��܂ł����a�ɑ��锗�Q�̎�͂�܂Ȃ��������̂Ƃ݂��B�����בR�q�����r�Ɗ����ʂ��Ă����邱�Ƃ́A�Ȃ��Ȃ��ɗe�ՂȂ�ʂ��ƂŁA�^���̂��ƂƂ͎v���ʂ��炢�ł���Ǝ]�V�������Ă���B
�@���A�_��̋��Ɍ����Ƃ����̂́A���̎��͐_��͐g���ɍs���Ă������A����Ƃɑ�����炸�~�܂��Ă������A�܂��͔M���Ɉ��g���Ă��������ĂłȂ����A�����_��̗����Ɍ�����q���������r�Ƃ����n��D�ƌ��t���̕ʓ�����l�������̂��A�n����������@�c�́A�����g���Ɍ��킹�Ƌ�����̂ł��낤�B
�w��q�����x�@(�݉Ƃł��̉�)�x�m�����M���V���n�̐_��́A����[�̒�q�Ȃ�B����ē����V��^���\���B
�@�J�R��l���A���q���ɏ@�c�̌�{�������^����ꂽ���̈�l�ł���B�����̐M�҂ɑ���Ȃ��B���邢�͐_�l�Y�Z��Ɏ������̎҂ŁA����ƂɉB�܂�ꂽ�_��Ɠ��l�ł��낤�B��}�����܂ł����q�˂���r���̂��A�s�v�c�ƍГ��Ƃ�āA���́w���x�o���q����������r�̉i�m6�N�܂ł͑����ł������B
�@�V���n�Ƃ����̂́A���n�Ƃ����q�Ƃ��s��Ƃ����i�Ƃ������āA��������x�m�̋[���q���Ă��r�ł���B����ɐV�̎������Ă��邩��A��{�̕x�m��Ԑ_�Ђ̐V�������Ђł���B�ꏊ�͂�������s�����Ⴊ�A���̔M�����̒��ɂ͂���炵�����q���Ɓr���Ȃ��B���q����̔M�����̋�悪���Ă��ʂ��A���̔M�����L���������Ƃ͊m���ł���B�O��4���̌�_���̉��Ɍ������O���s��̐�Ԑ_�Ђ��A���邢�͂��̐V���n�_�ЂŁA�������̕ӂ܂ł��M�����ł͂Ȃ������낤���B
�@��{�̐_��������ɂ��s���ׂ��x�m�_�Ђɂ́A�m�l�q���ނ炢�r�̑����̋{�i�������ł��낤����A���̐_��͂��̉����̒n���q�����r�̎҂ł������낤���A�����͂Ȃɂɂ��ڂ��ĂȂ��B�^���q���邵��r�ɁA�䏑�́u�R�E�k�V�v�̂��Ƃ�_��Ɛ����ɓǂ͂悩�������A�֑������ŁA��{��Ԃ̐_���E����^�ƖϏ̂����͉̂�������Ƃł���B
�@��������A�Ȃ�����ނׂ��́A�u�R�E�k�W�v���u�_�l�Y�m�v�̒��̎l�Y���Ȃ������̂��Ƌȉ����߂����Ȃ���Ȃ�ʐl�̑��݂��邱�Ƃ�s�v�c�Ɏv���B
�@�������A�����̌��́A���łɌ�{�l���������R�ɋC�����Ē�������ꂽ��������ʁB�܂��������]����̂ł���B
�@
�@
�@
�@
�@
�M���@��Îj�`�W�^�ɂ���
�@�M���̑�Ƃ��̑�@��Ƃ��L�����ËL�^��j�`�Ȃǂ́A�����ď��Ȃ�����ǁA�����̏��Ȃ��Â����̂��E�^�q���イ�낭�r���āA���̌�T�q����܂�r�͌��Ȃ���ɁA�Ðl�̈ӌ��������������Ƃɂ���B
�@���̌Â����̂̒��ɁA���Ȃ���������Ȃ�����A�Ȃ�ׂ����Ăɂ��ċL�������̂�����B�������ނƂ��Ă����B����͏@�c�E�J�R���̒��ڎj�������Ȃ��ł��A���̎��Ƃ��̖@��Ƃ̊W�̐[���@�k�̓`�����Ȃ���̂ŁA������l�i�{�R�P�W���j�́w�@�c�N���x��w�ƒ����x�����S���Ȃ��Ă���B����́A�x�m���R�̌Ó`�����ʐΓ��ˁq���傭�����ǂ����r���Đ��t��㕂߂�ꂽ���̂ł���B���̂��Ƃ��j�����N�W�q���イ���イ�r����������̊�Ō���A�����������T������悤�ɂ݂��āA�傢�ɂ��̑���ʊ����͂��邪�A��̂͌����ē����ʂ��̂ł���B
�@���̌�̎j���́A�������̐��t�̉e�����Ă���B���ɂ��w�ƌ��L�x�̂��Ƃ��́A�L�҂͕x�m�n�łȂ��Ĉ�v�n�̂��̂炵�����A���̖@��ɂ��Ă͑S�����t�̐����L�ۂ݂ɂ��āA����܂ł����̂܂ܗp���Ă���B����́A����ɂ͂Ȃ��̍ޗ����Ȃ��S���������R�ł��邩��ł����낤���A�Z�V�̒��ɁA�Ƃ�킯���t�����̂��Ƃ���d�{���̂��Ƃ܂ł����̂܂����ł���̂́A����̌Ï��Ƃ��Ă����炵�����̂ŁA���ɂ��̕M�҂̐M�̏~���q�����ڂ��r���������v�������̂ł���B
�@�I��ɁA�ł����M�Ƃ��ׂ��́A��t��迁q�ɂ��ł�r��l�i�{�R52���j�́w���^�G�q�����ւ�r�x�̈ꕶ�ł���B����͕x�m���d�ɂ��Ă̂��ƂŁA�M���@���łȂ����玖���𖾔��ɂ͏�����ĂȂ����A�ł��������j���������Ă̊m���ł����āA���Ƃ������ł������Ԃ�M�d���ׂ��̕����ł���B���ƂɁA���t���̂���ӂꂽ�`���ɂ���Ȃ������A������͔��ɂ��肪������������B������w�Z�q���������r�Ȃ�v���@�����q������ɂ��Ƃ��r�t�̋�S���ďW�S�q���イ���イ�r����ꂽ�w��q�����x���̔镶�������ɗ������̂ł���B
�@�������A���̖@��̎n�I�ɂ��ẮA迎t�͂����悤�Ȃ��ӌ��ł������������m�q�������r����̍ޗ����Ȃ����A�w���t���`�x�ɂ́A���Ƃ����M�̐m�q�ЂƁr���������Ƃ��Ă��A�S�R�q�܂������r�����t�̓`���q���j���P�����Ă���̂́A�w���^�G�x�̕����猩��Ƒ傢�Ɉق��ނׂ��ł��邪�A����͖��q�݂���r�ɐ�t�̌������c�q�Ђ��r���ʐT�d�̑ԓx���炫�����̂ŁA�^���q�܂��Ɓr�̖��Ӂq������r�͐������j���d����ꂽ���̂�����^���ʂ̂ł���B
�@���ꂩ��A��Ɠ����E���ٓ��̂��Ƃ���L���āA�@��̂��Ƃɂ͏������G��ʂ��̂�����B�������ނƂ��Ă����B����́A�@�c�E�J�R�̒��ڂ̎j�������悤�Ƃ����ʂ̂͑���̂��ƂŎ~�ޓ��ʂ��Ƃł��邪�A���ɂ͂킴�ƕx�m�̓`����ˁq����r�����A�܂��͒m��ʊ炵�ČȂ���ɗ�����Ƃ����Ղ������Ɍ����̂�����B���������Č�T�q����܂�r���܂��܂���w�r�������̂ŁA�w�{�����c���I�q�قԂ����Ƃ����j�x�̂��Ƃ������Ȃ킿����ł���A�܂����̏����傢�ɋЂ𗘁q���r�����Ă���B����Β��S���Ȃ��Ă���̂ł���B�������́w���N�x�Ɓw���I�x�Ƃ͂����ꂪ�����ł��邩�͕s���ł��邯��ǂ��A���ɔ�����T�q����܂�j�̎�����q�܁r���Ă��āA�w���q�Ԃ����r�̍ߐr���y���炸�ł���B
�@���̊O�ɂ́A�����̗_�ꍂ���[�֓��u�q���������ɂ������r�̂��Ƃ�����M���̑厖��m�炸���āA�c���̃A�c�n����z���q��͂�r�ɉ����������̕�����|���q�ق��ӂ������Ƃ����j������B�����̐^�@�[�J��q����ɂ�ڂ����܂����j���̖ϐ��q�������r���A�ׁi�����ǂ��r�̏����R�点���̂��A�Ȃɂ������������Ă̂��Ƃł͂Ȃ��낤���Ƃ��v����B
�@�ߏ��ނ̎j�`�̗v�����f���āA���̏㗓�q�����r�ɊԁX�]���q�܂܂Ђ傤���イ�j�������邱�Ƃ肷��B
�@���̊O�̋ߑ�̒����A���Ƃɓc�������h�̏����ꂽ���́A�܂��͂���ɉe�������e��̖@��j�ǂ��́A�ߏ�̌Ó`�Ɣ�ׂ�ΓV�n�_�D�̔�r�ɂȂ�ʒ��̌��\�̂��̂ł��邪�A�~�������ޗ��̋�����ʌ���������A�܂��ޗ��̈��������Ⴄ�Ă���̂�����āA�܂��[���̐M�p�͒v����ʂŁA���̒��̔�]�͉���̒��ɏ��X���Ă��������A�����ɏW�^���Ȃ��̂͂ȂɂԂ�������тł͂��邵�A���܂����̏����e�Ղɓ����邩��ł���B
�@
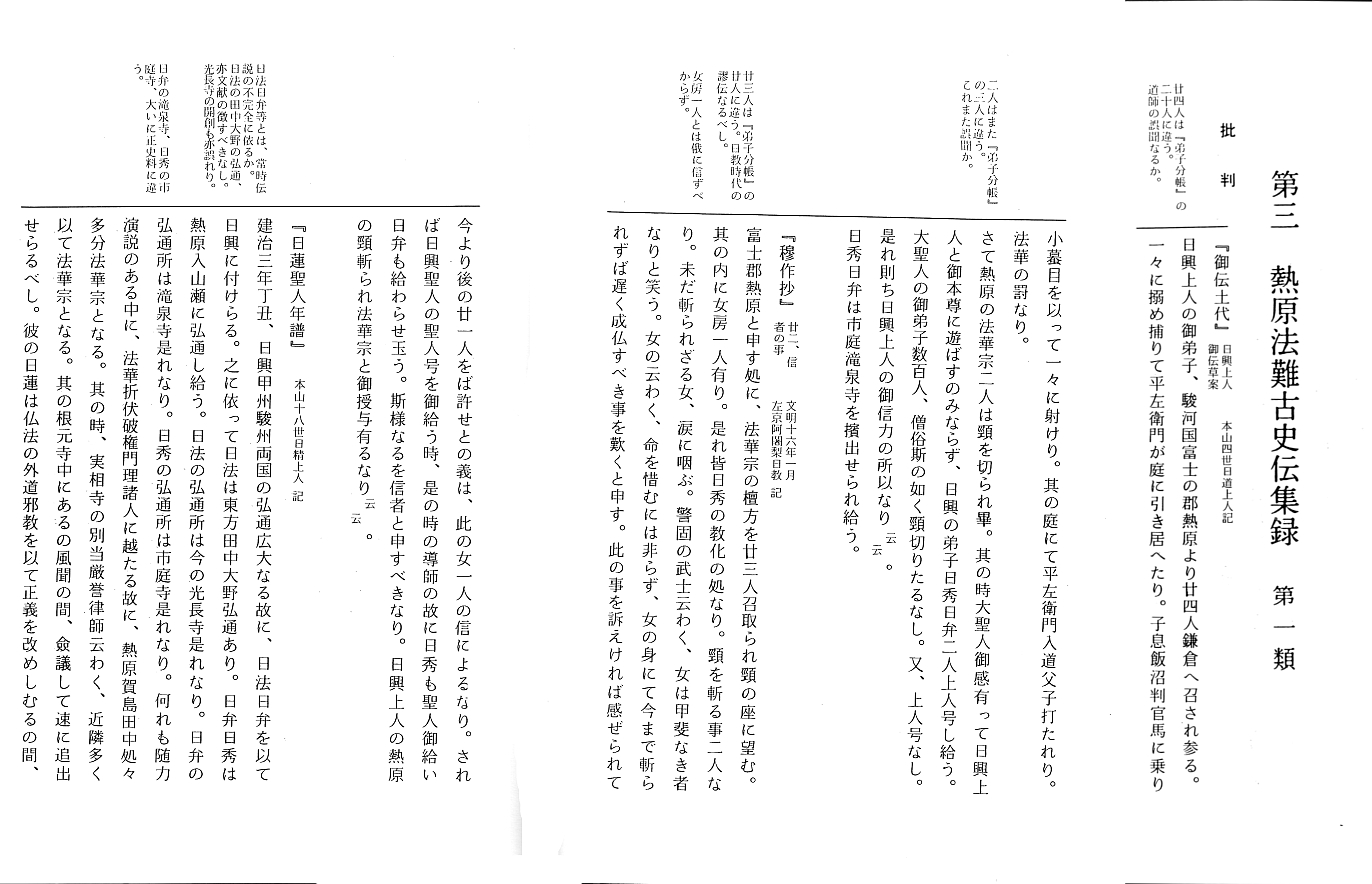
1
�@
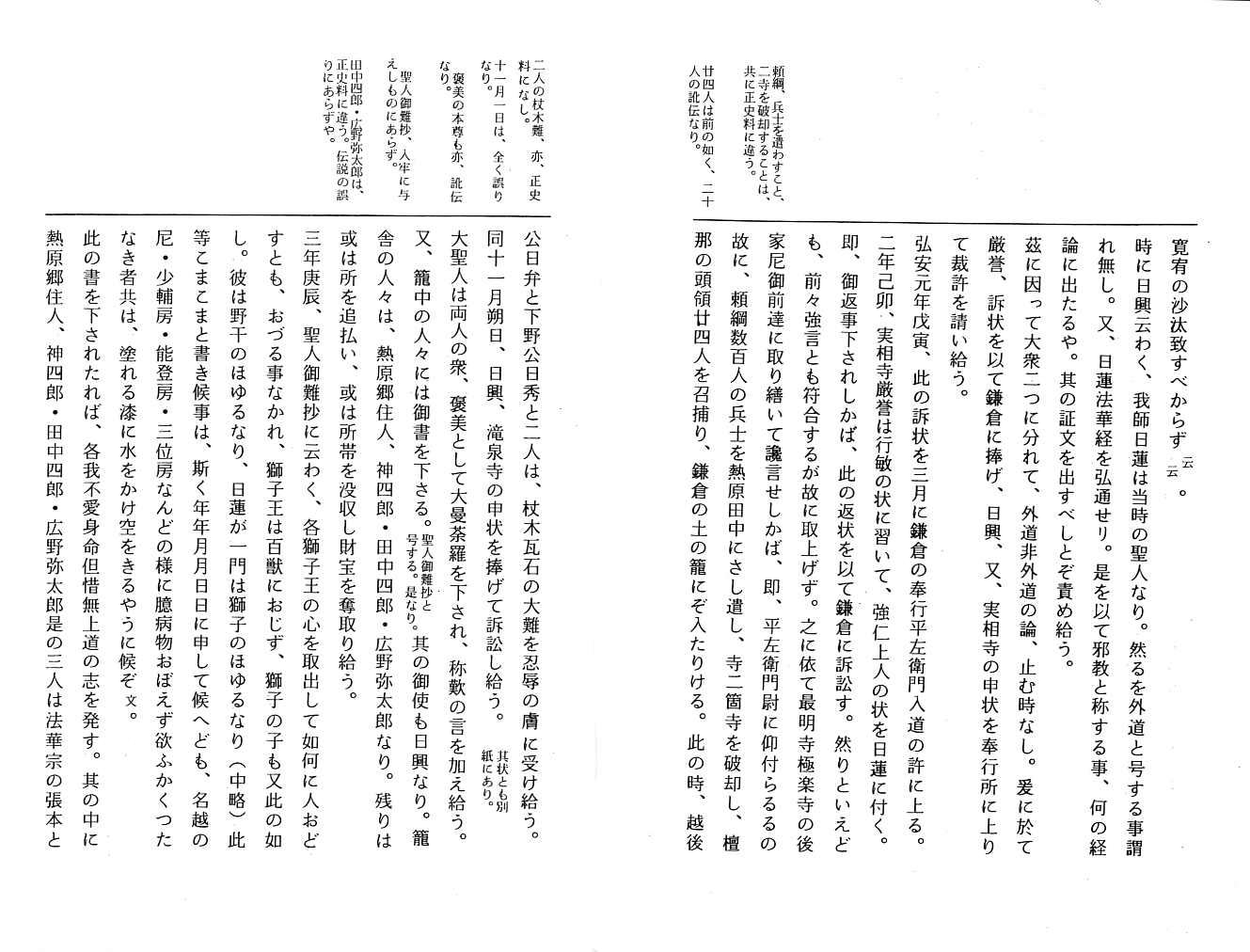
2
�@
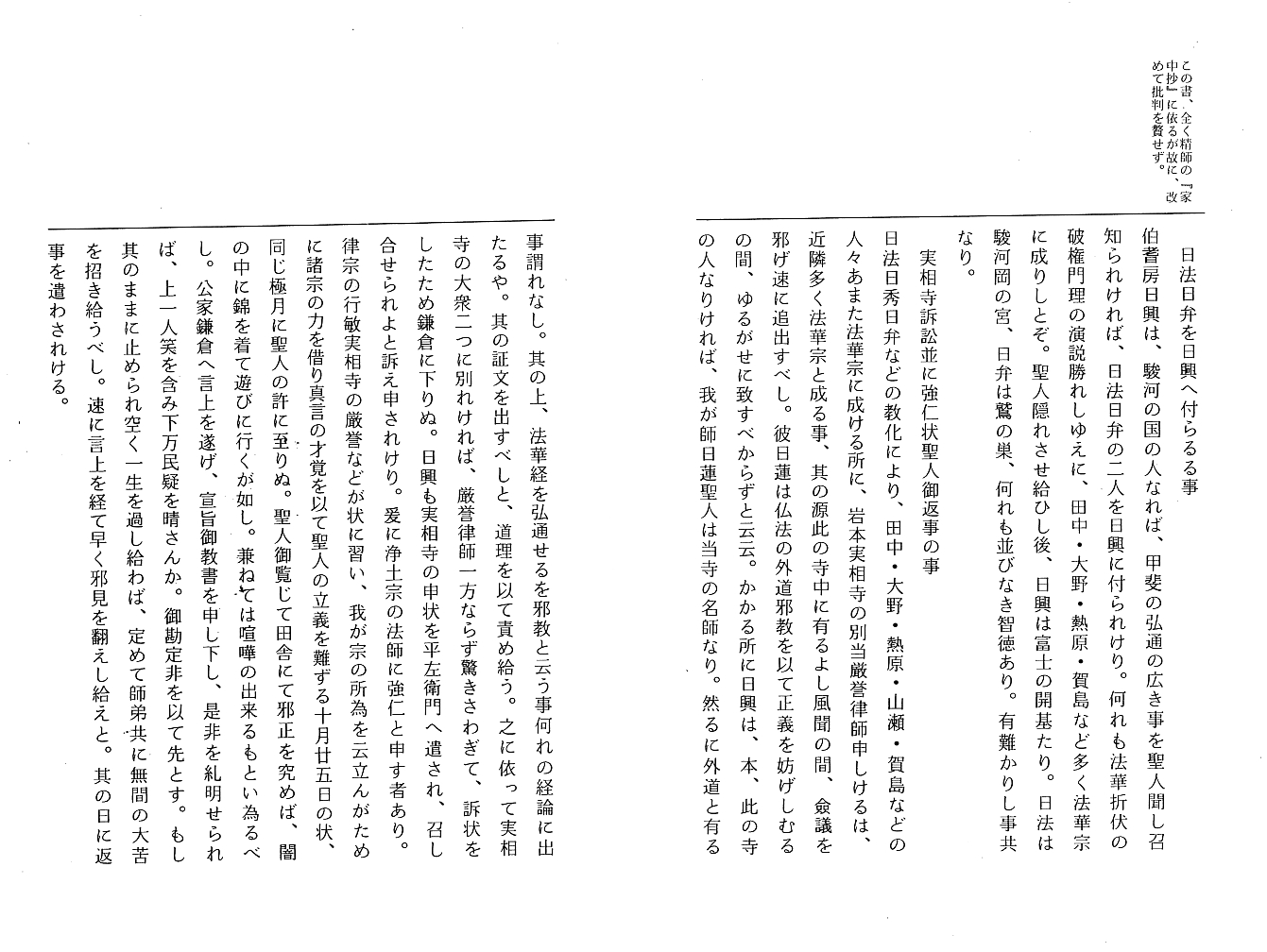
3
�@
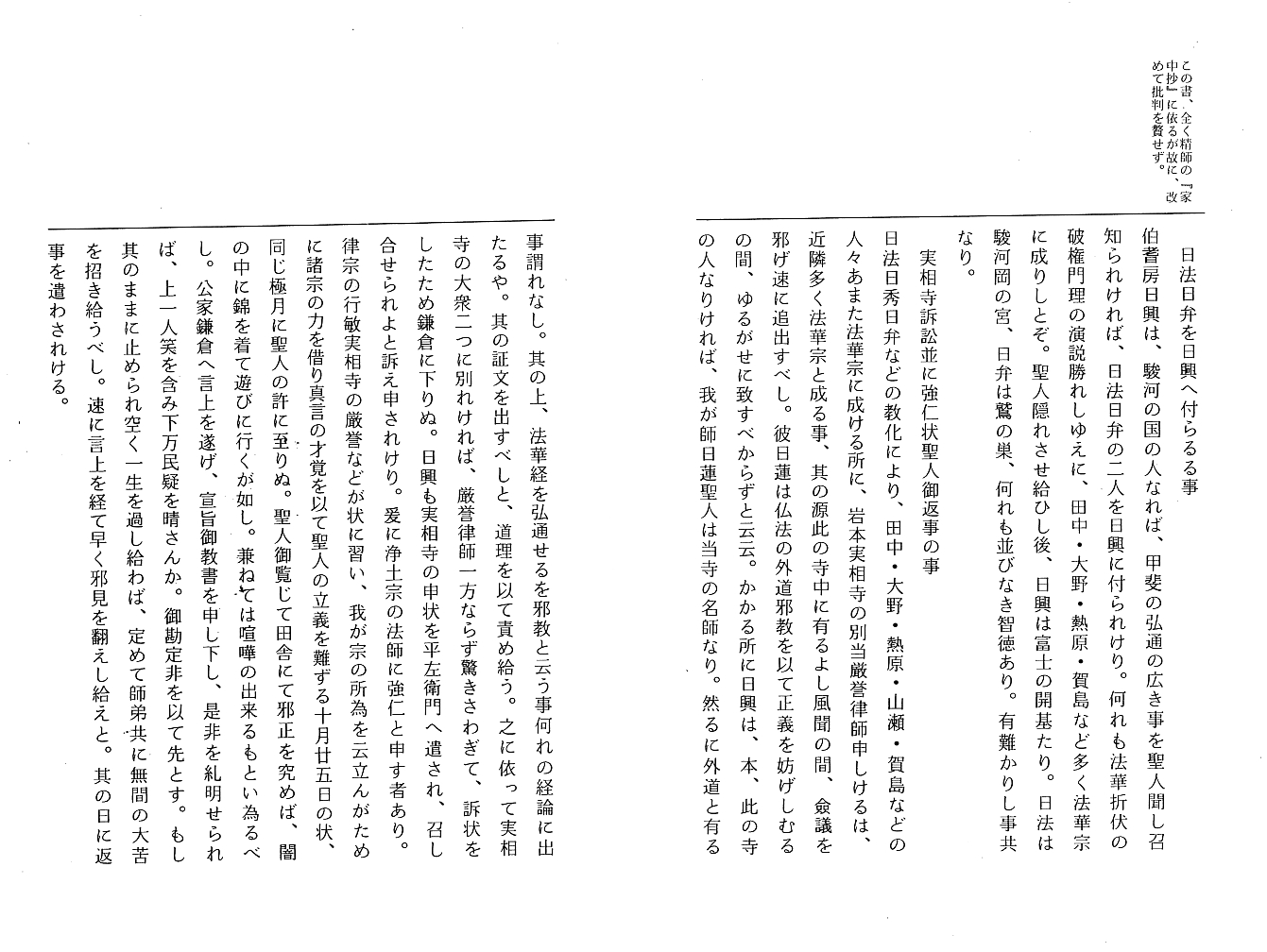
4
�@
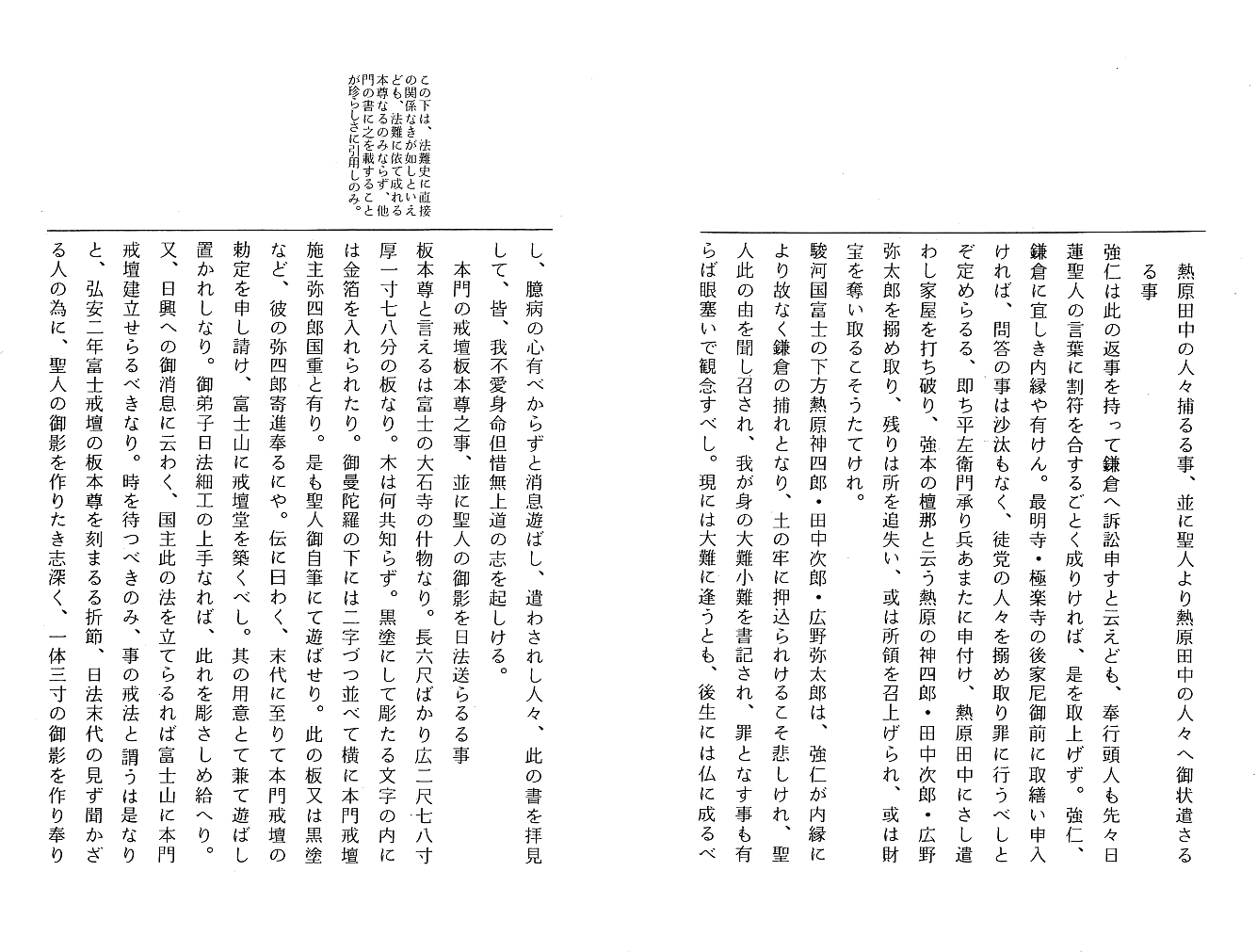
5
�@
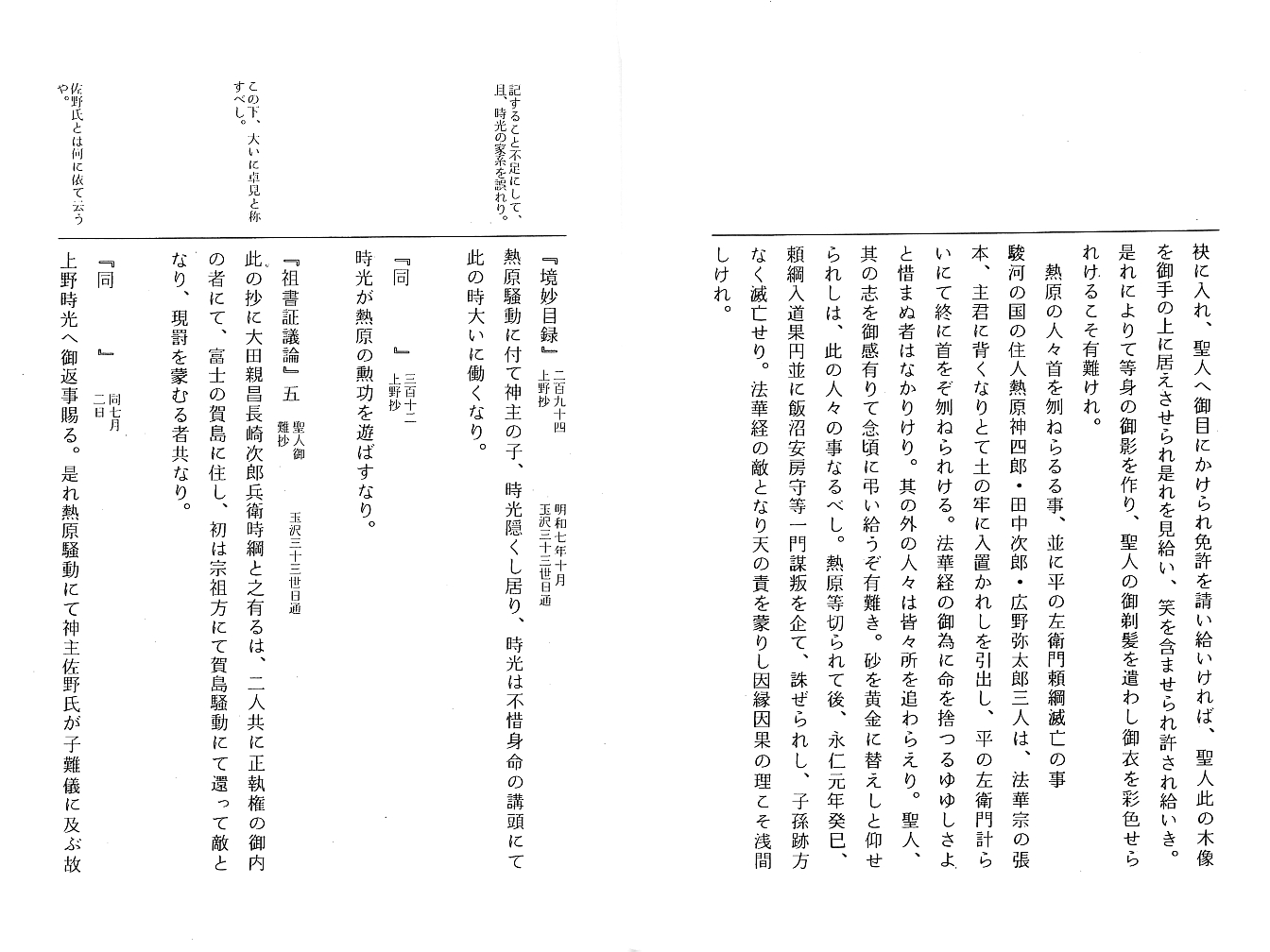
6
�@
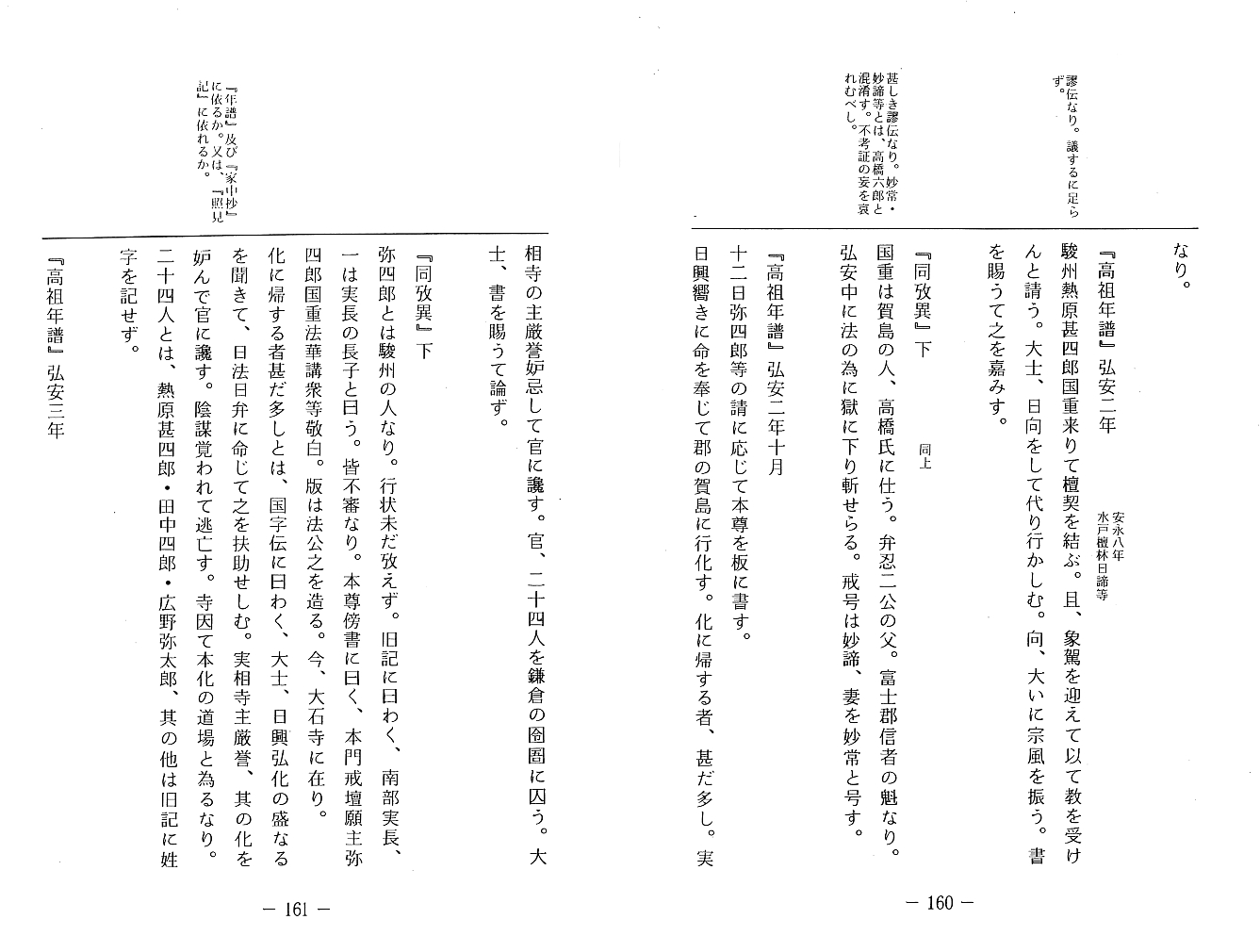
7
�@
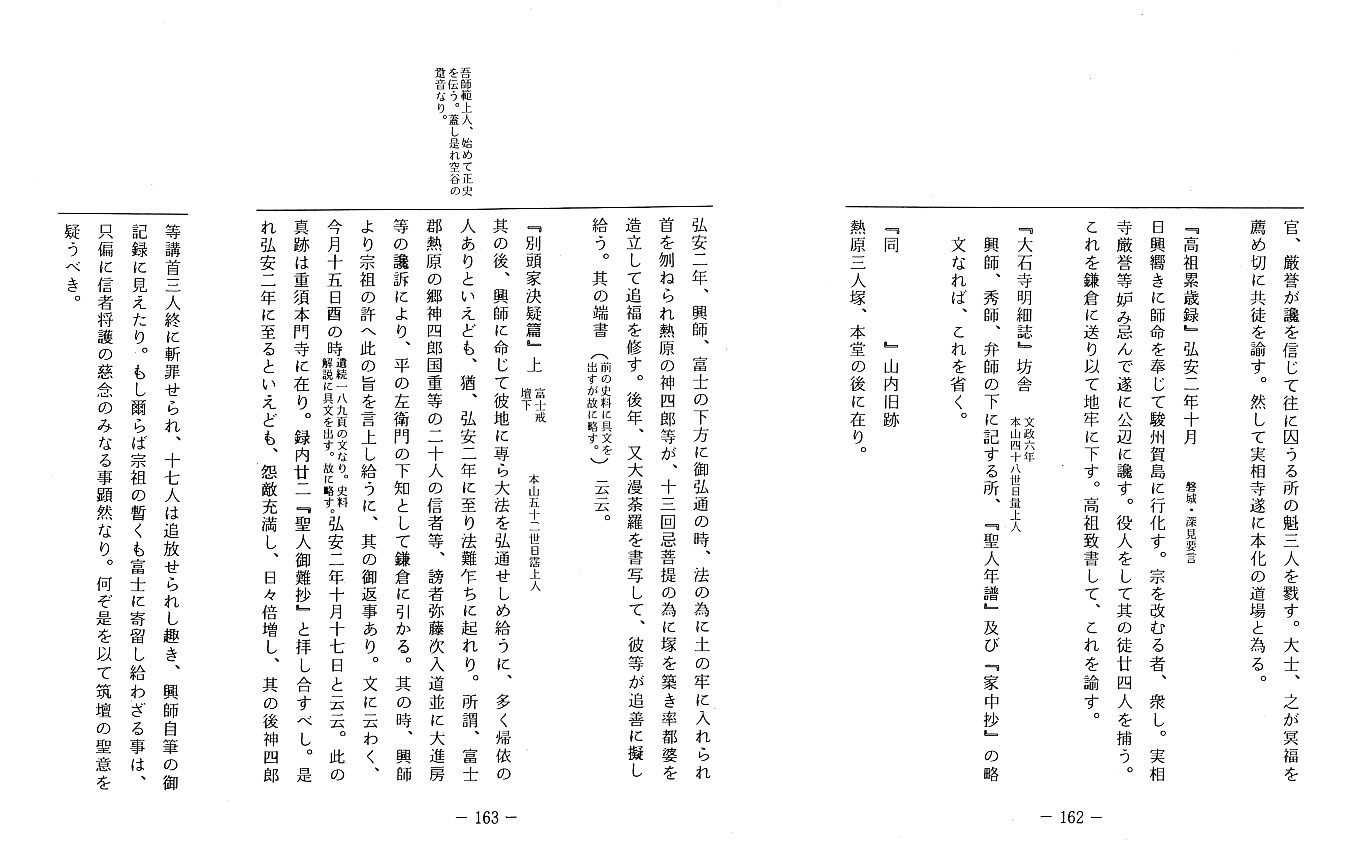
8
�@
�@
�@
�@
�@
�@
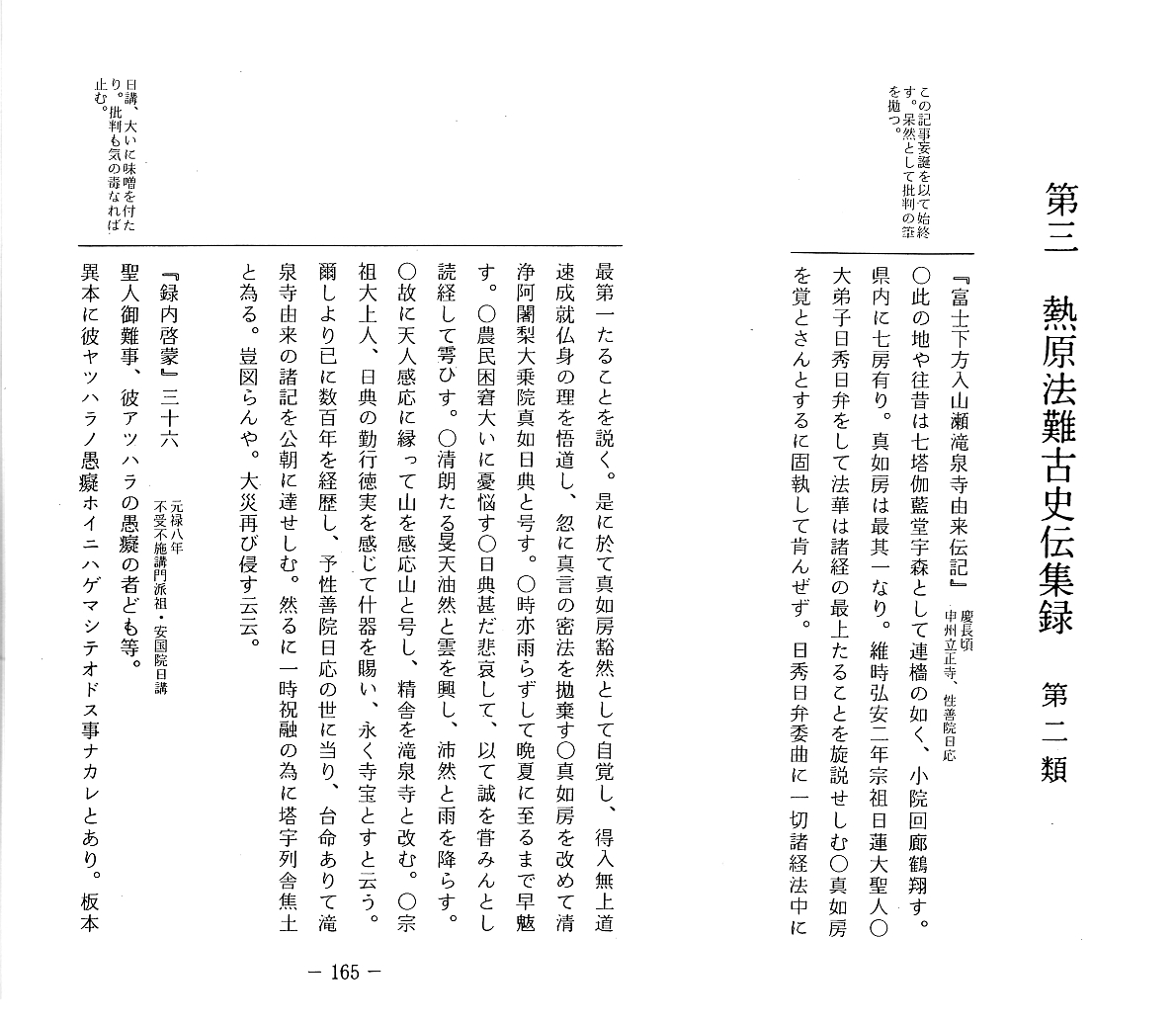
1
�@
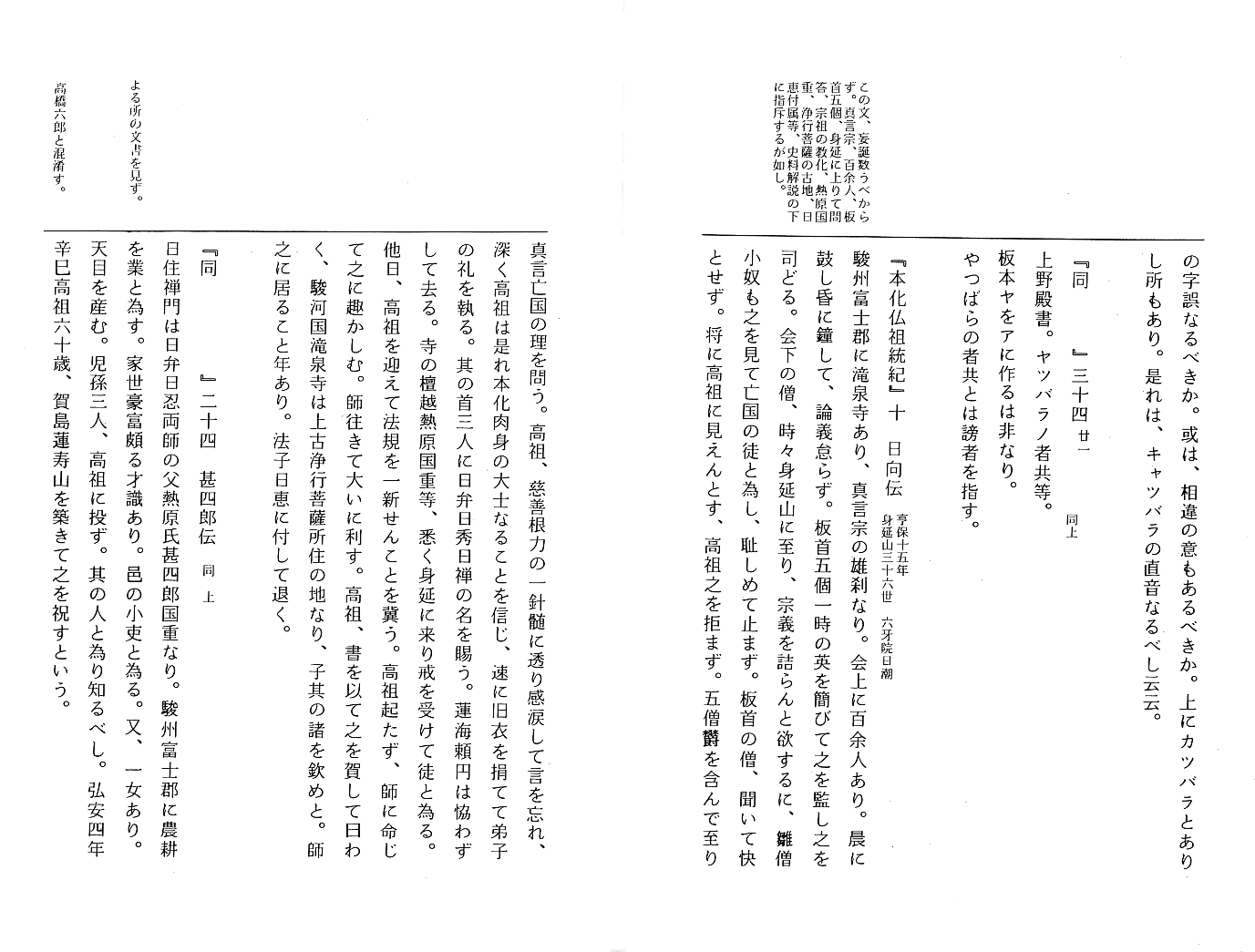
2
�@
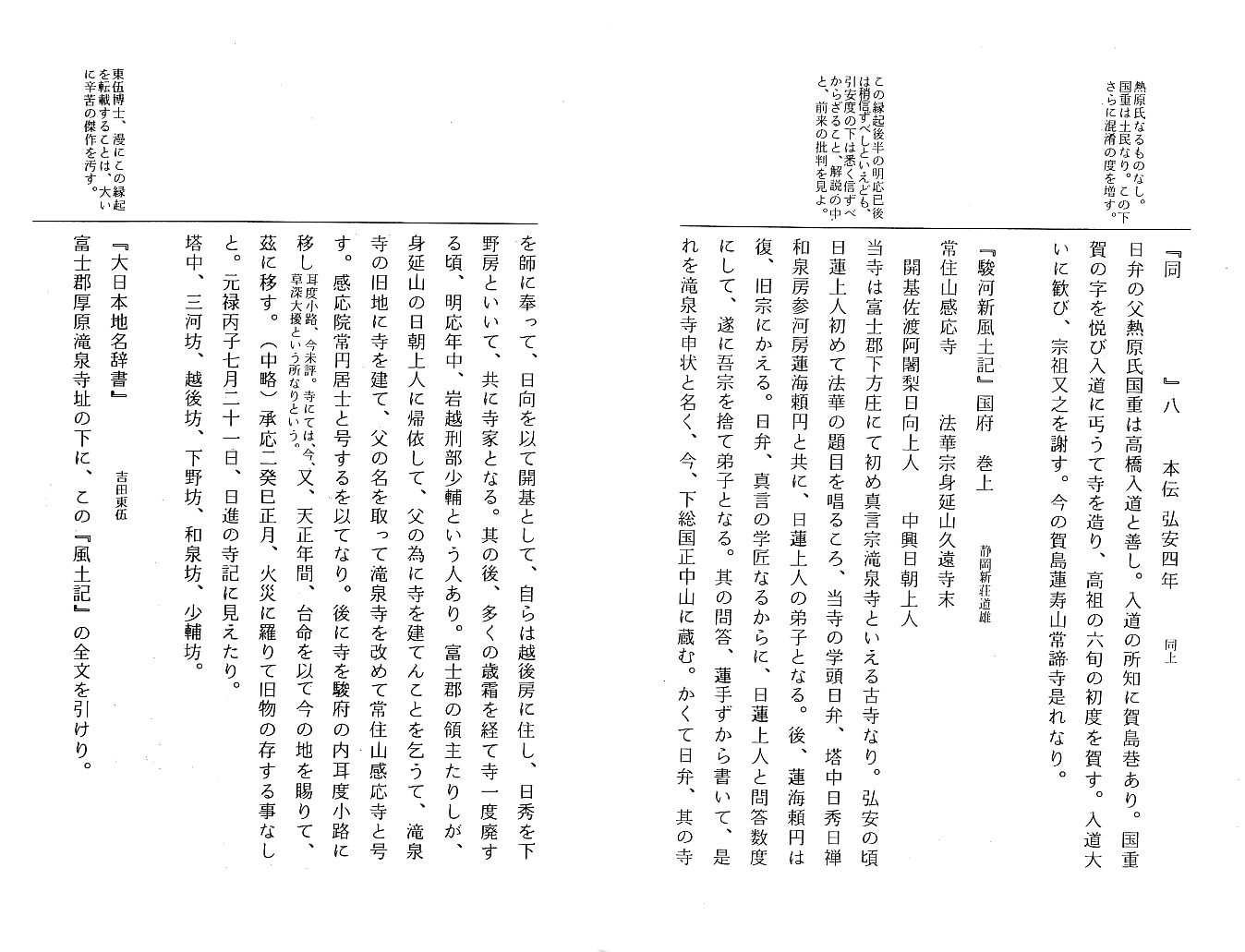
3
�@

4
�@
�@
�@
�@