

「孤独に負けるな」 学生との対話(上)
東京工業大学で開いた「池上彰先生に『いい質問』をする会」での模様を3回に分けて取り上げます。東工大生の疑問や不安に、私が答えるというものです。例年は大教室を会場にしてきましたが、新型コロナウイルスの感染対策のため、初めてオンラインによる開催となりました。
■新たな気づきを生む「いい質問」を
これは私が所属するリベラルアーツ研究教育院による名物イベントです。学生が日ごろの問題意識を言葉にする訓練の場でもあります。私が考える大学での「いい質問」とは他の学生や教授陣が新たな気づきを得るような問いかけです。若者たちから寄せられた約400の声の一部を紹介します。
質問 「新型コロナにおびえすぎる人だけでなく軽視しすぎる人もいます。ウイルスへの対応についてどうバランスを取ればよいでしょう」
池上 「ウイルスに対する捉え方が異なるのはやむを得ないでしょう。感染者の多くは、無症状だったり、軽症だったりする特徴があるといわれます。海外に比べて重症化する感染者が少ないという事情もあるでしょう。東工大生なら感染者を重症化させない仕組みや、社会全体でどう取り組めばよいのかといったテーマを考えてほしいです」
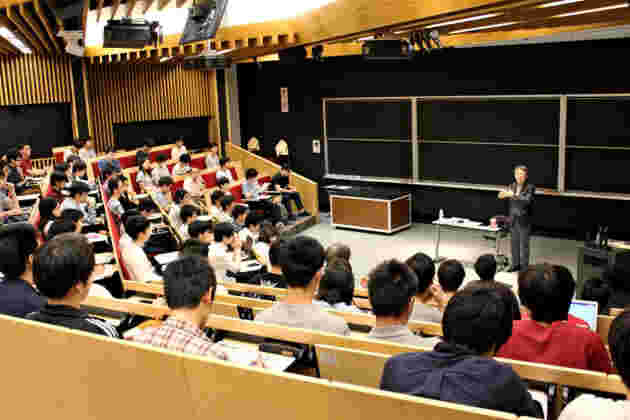
池上教授は学生との対話を重ねてきた(2018年6月、東工大大岡山キャンパス)=同大提供
質問 「政府が経済対策として打ち出した『Go To キャンペーン』のような判断は正しいのでしょうか」
池上 「これは第1次補正予算で打ち出されました。経済を立て直すアイデアとしては大切なことだけれど、その段階では大変な状態にあった医療の現場にお金をつぎ込むことを優先すべきだったのではないでしょうか。新型コロナを抑え込む前の実施は、個人的には早いと考えています」
質問 「ウイルスの感染リスクを心配して、公共交通機関の利用を怖がる人もいます。自動車を買う若者が増えるのではないでしょうか」
池上 「若者らしい視点です。実際に自動車通勤する人が増えたり、ペーパードライバーが教習所に通い直したり、自動車利用は増えているといえるでしょう。ただ、こうした景気情勢で自動車を新たに購入するかどうかといえば厳しい環境ではないかと思います。健康を考えて自転車利用が増えているようです」
■「悩んでいるのは君だけじゃない」
質問 「在宅での講義の視聴が続いているうえ、研究室にも行くことができません。大学での学びや生活に不安があります」
池上 「キャンパスに通えず、友人にも会いにくい状況が続いています。学生諸君は孤独にさいなまれているのではないかと思います。気持ちが落ち込むこともあるでしょう」
「でも、こうした状況に追い込まれて苦しんだり、悩んだりしているのはあなただけじゃないということを伝えたいです。私自身の体験を振り返れば、青春のある時期に孤独に耐えることは人間として成長する上で必要な体験だと思います」
質問 「今春、上京しました。対面での意見交換や価値観を共有する機会がほとんどなく、インプットの学びだけでは先に広げるのが難しいのではないかと感じます」
池上 「大学の先生方もいまの状況をどうすればよいのか悩んでいます。東工大生は首都圏出身者が多く、ほかの地域から学生が加わるのはよい刺激になるでしょう。たとえば授業でも使っているビデオ会議システムを用いて、学生同士で意見交換してみてはどうでしょうか。アウトプットの機会を創造して、交流を広げてみるのも大事です」
「思いを伝える言葉とは」 学生との対話(中)
今回も東京工業大学で開いた学生参加イベント「池上彰先生に『いい質問』をする会」の模様を取り上げます。学生の疑問や不安は、新型コロナウイルス問題が収束した後の学びや就職にも及びました。「ニューノーマル(新常態)」への問題意識がうかがえます。
■仕組みやルールを見直す契機に
質問 「新型コロナのワクチンが完成すれば、生活は元に戻るのでしょうか」
池上 「新型コロナ後の世界は、それ以前と全く同じ状態には戻らないのではないかと思います。たとえば働き方です。感染防止対策のため、時差通勤や在宅勤務が奨励されました。当たり前だった仕組みやルールを見直すきっかけになるのではないでしょうか」
質問 「首都圏では公務員の志願者が増え、安定感のある公務員への関心が高まったという報道がありました。不況になると公務員人気が高まるようですが、安定した人生とは価値の高いものでしょうか」
池上 「私の教え子にも国家公務員や地方公務員になった卒業生がいます。でも、最初から公務員になることを目標にしていたわけではなかった。人生をかけて取り組みたいことを考え抜いた結果、その仕事が公務員だったのです。まずは自身がどんな働き方、生き方をしたいのかということを考えるべきではないでしょうか」

新型コロナの感染問題は大学生の学びや生き方にも課題をつきつけている(7月、東京・新宿を歩くマスク姿の人たち)
質問 「今後、どのような業種や事業に注目していけばよいでしょう」
池上 「働きたい仕事を考えるだけではない大事な視点があります。たとえば新型コロナ問題に直面し、採用活動をリモートに切り替えた企業は環境の変化にも適応できるでしょう。どれくらいのスピードで取り組んでいるのか見極めてみることです。まさに経営判断です。変化し始めた企業にも注目してはいかがでしょうか」
質問 「オンライン授業の普及によって、教育現場はどのように変わっていくでしょうか」
■授業の話をしっかり聞いてほしい
池上 「オンラインで話をするのが上手な先生、苦手な先生がいるでしょう。でも、上手な先生が授業を受け持てばよいという問題ではないと思います。学生に真摯に対応できるかどうかという姿勢が大事なのです。オンライン授業が苦手な先生であっても、授業の話をじっくり聞いてほしいと思います」
質問 「リモートによる教育でも、肌で感じながら学ぶ価値を提供することは可能でしょうか」
池上 「教室での対面授業とすべて同じようにできるとは思いません。ただ、私がリモートで授業をしているときも、学生が鋭い疑問を投げかけたりすることもあります。それに答えることで双方向が実現したともいえます。それはリモート授業の可能性といえるかもしれません」
質問 「授業をオンラインにすればよいという風潮が広がっています。対面でしかできないことがあると思います」
池上 「リモート授業は講師がいる場所や時間に縛られないというメリットがあります。新型コロナ問題が収束しても、リモート授業は必要ないということにはならないでしょう。どちらがよいかではなく、バランスの問題だと考えています」
質問 「大切な人には感謝や思いを正直に伝えたいと思います。池上先生は人とのかかわりで何か変化はありましたか」
池上 「ステイホームが始まったころでしょうか。自分の来し方を振り返り、どう生きるべきかを考えたとき、ご無沙汰している人に会いたいと思ったことがあります。電子メールで済ませる時代ですが、ときには手紙を直筆で書いてみてはどうでしょう。思いを伝えるとはそういうことではないでしょうか」
「多様性が強い社会育む」 学生との対話(下)
東京工業大学で開いた学生参加イベント「池上彰先生に『いい質問』をする会」の模様を伝える最終回です。学生の質問には、新型コロナウイルス問題による混乱のなかで大切な視点を提起するものがありました。コロナ後の世界にどのように備えればよいでしょう。
■若者の柔軟性や鋭い感性が強み
質問 「今後、仕事や日常生活が変わっていくといわれます。時代を生き抜くために、学生が身につけた方がよい能力や考え方はありますか」
池上 「新しい時代を生き抜く上で足りない能力の問題は、学生に限らず、大人にもいえることです。むしろ、新しい環境や変化に柔軟に対応できるのは若者たちではないでしょうか。柔軟性や鋭い感性を持っていることが強みなのです」
質問 「ニュースには新型コロナに関する情報があふれ、正確な情報をつかんだり、正しく理解したりすることが難しく感じています」
池上 「今回、多くの東工大生から君と同じような不安を抱いているという質問を受け取りました。むしろ、そういう姿勢を持ち続けながら勉強していくことが大事ではないかと思います。私は専門家の声を伝える役割を担っていると考えています。私自身の理解に間違いがないか気をつけています。そうした懸念を持つことは大事なことだと考えています」
質問 「読書を通じて学んだことをアウトプットするためによい方法はありませんか」
池上 「読書ノートをつけていたことがありましたが、結構大変でした。読書後に題名、1〜2行の感想を手帳に書き込んでおいてはどうでしょうか。後から関心や問題意識を振り返ることができます。仲間とオンラインで読書会を開いて、感想を言い合うこともできますね」
■ブームに流されず冷静な視点を
質問 「新型コロナ問題が収束した後、私たちはどのように地球環境問題に向き合っていけばよいでしょうか」
池上 「環境破壊が異常気象の原因ではないかという指摘があります。海外ではバッタが大量発生し、農作物を食べてしまい、深刻な被害が出ていると報じられました」
「日本ではプラスチック製の廃棄物を減らそうと、プラ製レジ袋が有料化されました。行動を起こそうという機運は大事ですが、ムードに流されないようにしてほしいです。理工系の専門分野を学ぶ若者として、根本的な解決には何が必要かという冷静な視点を忘れずにいてください」
上田紀行(教授、東工大リベラルアーツ研究教育院長) 「学生が問いを発する力が格段に高まっていると感じます。池上先生は新入生への講演で『常に世の中は想定外の出来事が起こる』と話されました。そんなとき、自ら選択肢を増やして乗り切っていける人が本当に強い人なのだとわかってきました。先の見通せない時代だからこそ、私たちは変化への対応力が問われているのです」
池上 「今回も学生との対話を通じ、若者たちの問題意識を知ることができました。他人の考えを知ることで問題意識が生まれます。様々な考えを持つ人がいて多様性が育まれるのです。多様性を重んじる社会こそ、本当に強い社会だといえるでしょう。議論で解決策や新しい道を見つけ出すことができます。議論し合うことはその第一歩になると考えています」