�@
�@
��9�́@�\�W�]���h�`���Q�[���h
�@
�@
�@��������i��\���i��P�V�́j�Ɂu�\�W�]�̌����v��������Ă���B����́A���y�������炷��������̂��̐��E�ɖ������A���ׂĂ̏O�����������̈ʂɗ������邱�Ƃɂ���ē�������ƁA���̖@��̈�̎���i��j�ł�����1�l���珇�Ԃɓ`���Ă����āA50�Ԗڂ̐l�������Ċ�Ԃ��Ƃɂ������Ƃł́A�ǂ��炪�傫�������r�����ʂɏo�Ă���B
�@���̔�r�̌��_�͎��̒ʂ�ł���B
�@�u�k��҂ł���l���̒��f�Ȃ��A���ɂ���āk���p���ꂽ�l����50�Ԗڂ̐l���A���̖@�傩���̎���i��j�ł��A��̋�ł������āA��ԂƂ���Ȃ���\�\�܂��ɂ��́m��҂̏ꍇ�́n�ق����A���́k�O�҂̏ꍇ�l���������Ɓk���e���l�x��ł���̂ł���v�i�A�ؖ�w�@�،o�x�����A299�Łj
�@�������Y�͂�������̂悤�Ɋ����B
�@�u�����̔@����50�̐l�̓W�]���āA�@�،o���Đ��삹������A���A���ʖ��ӈ��m�_�Ȃ�B���ɋ���A�ŏ���ɉ����āA�����Đ��삹��҂���v�i���A298�Łj
�@����́A������������������A���́w�@�،o�x�����p�����Ƃ����シ�邽�߂̌��t�Ƃ����悤�B���̔��ʁA�w�@�،o�x�\�\����͕����ƌ����Ă�������������Ȃ����A���̎v�z�̓��������̌��t����ǂݎ���̂ł͂Ȃ����B
�@50�l���̐l�Ɍ��p���Ƃ������Ƃ́A�܂����h�`���Q�[���h�ł���A�r���ɂ͌����Ԉ�����`���������Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��B�M�҂��A2011�N�Ɂw�����A�{���̋����\�\�C���h�A�����A���{�̗����ƌ���x�i�����V���j�Ƃ����{���o�������A�����V���ҏW���̓��g���������u�s��ȓ`���Q�[���̉ʂĂɁv�u2500�N�A5000�L���A�u�b�_�̋����͂ǂ̂悤�ɓ`������̂��v�Ƃ������R�s�[��{�̑тɂ��Ă��ꂽ�B����́A2500�N��5000�L���Ƃ���������u�Ă��C���h���璆���A���{�ւƓ`�d���钆�łǂ̂悤�ɗ����ƌ�����o�ĕϗe�����̂������ǂ������̂��B���ꂩ�炷��ƁA�u�\�W�]�v���@�h�`���Q�[���h�ɕς��Ȃ��B����Ȃ̂ɁA�ǂ�����50�l���̐l�Ɂw�@�،o�x�������Ɍ��p���ŁA50�Ԗڂ̐l�ɂ��������傫���ƌ����̂ł��낤���B
�@
������錴���̂��낢��
�@10�l�قǂ̓`���Q�[���ł��K���ƌ����Ă����قǁA�Ō�ɂ͎��Ă������ʂ��̂ɕς��ʂĂ邱�Ƃ������B�ǂ����ē`���̂��тɌ����������̂��A�l���Ă݂悤�B���������̐l�ɓ`�����J��Ԃ��Ȃ��Ă��A1��1�̊Ԃł�����͂����̂ł���B�����̂��̂̌����A�b�̎~�ߕ��A�l�����ɂ��̌���������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���̈�́A��l�ρA���邢�͎v�����݂ł��̂��Ƃ����邱�Ƃɂ����̂��B�Ⴆ�A���͉��F���ƕ������ƁA�������́A�������Ƃ���7�F�Ɠ�����B�Ƃ��낪�A�X�E�F�[�f���ł�6�F�A�h�C�c�ł�5�F�A�A�t���J�̂��镔���ł�3�F���Ɠ�����B�������̂����Ă��A���̂悤�ȍ���������B����́A�������Ȃ��̖��ł͂Ȃ��B�����I�ɖ��ӎ��̂����Ɍ`�����ꂽ��l�ςœ������Ă���Ƃ����_�́A��������ς��Ȃ��̂��B�Ȋw�I�ɂ͌��̔g���̈Ⴂ�ŋ��ܗ����قȂ�A���X�ɐF���ω����Ă���̂Ŏ��ۂ�7�F�ǂ���ł͂Ȃ��B���o�͂Ȃ����A�����̈���Ă��������ɂ���Ă��̂̌����A�l�������K�肳��Ă��邱�Ƃ������D��ł��낤�B
�@������S�̂Ɗ��Ⴂ���邱�Ƃɂ���Č���������邱�Ƃ�����B�u�Z�x�W�o�v�́u�Q�ӏۂ��v��栂��̎����Ƃ���ł���B����́A���܂�Ȃ���ɖڂ̕s���R�Ȑl�������A�ۂ�G���āA���̊��z���q�����Ƃ����b�ł���i�w�吳�V���呠�o�x��3�A50�ʼn��j�B
�@����G�����l�́u�ۂ͓��̂悤�Ȃ��̂��v�Ɠ������B�K����G�����l�́uⴂ̂悤���v�Ɠ����A���ꂼ��A�K���̍����Ƃ�G�����l�͏�A����G�����l�͑��ہA�e����G�����l�͕ǁA�w��G�����l�͍������A����G�����l�͒c��A����G�����l�͑傫�Ȃ����܂�A���G�����l�͊p�A�@��G�����l�͑����j�̂悤�Ȃ��̂��Ɠ������B�����āA��ꂱ�����������ƌ��������ɂȂ����B����́A�����Ɏ����āA��������ׂĂƎv�����ސl�̎p�������Ă���B
�@����Ɨގ��̘b���A�����̓V���t�q�{�̒��킵���w�����~�ρx�i��g���ɁA�㊪�A150�Łj�ɂ���B��̕s���R�Ȑl�ɓ��̔����F���������b���B���o�ɑi����킯�ɂ������A栚g�I�ɐ������邵���Ȃ��B�����ŁA�u�F�������ƊL�E���E��E�ߓ��̂��Ƃ��v�Ɠ������B�ڂ̕s���R�Ȑl�����́A���ꂼ��̎~�ߕ������āA�_�����N�������Ƃ����B
�@����Ɋ֘A���āw�����~�ρx�̕ʂ̉ӏ��ɁA���̈�߂�������B
�@�u���������Ĕނ��^���A��Ƃ��ď����Ƃ��B�i�����j��̂��Ƃ��ƕ����ė�₩�Ȃ�ƈ����A�T���A�߂̂��Ƃ��ƕ����ē����ƈ����v�i���A35�Łj
�@�u�����F�͗₽�����̂��v�u����Ⴄ�B�������̂��v�u�H�тɕ����Ă�����̂��v�Ƃ������ӌ������킳�ꂽ�̂ł��낤�B��́u�����v��`���悤�Ƃ������A��́u�₽���v�Ŏ���A�߂́u�����v���`��炸�A�߂́u�������Ɓv�u�H�тɕ����Ă��邱�Ɓv�Ŏ��ꂽ�B栚g��p���āA�Ӑ}�������Ƃƕʂ̑��ʂŎ����Ƃ����D��ł���B
�@����������ɁA�l�̐S�݂̍���A�����ɂ���Č��������S���قȂ邱�Ƃ��������悤�B�B���n�̕��T�ɂ́A�u�ꐅ�l���v�Ƃ���栚g��������Ă���B�����͂̐������Ă��A�V�l�͗ڗ��A�l�Ԃ͐��A��S�͔^���A���͏Z���ƁA���ꂼ��قȂ�������������Ƃ������̂��B
�@�Ԃ��F�ዾ�������Ă���A�Ԃ��F�͔��Ɠ����F�Ɍ����A��F�̗ΐF�͍����F�Ɍ�����B
�@�A�t���J�ɌC��ɍs�������[���b�p�l�̘b������B����l�́A�A�����āu�������ł͌C�͔���܂���B�݂�ȗ����ł��邩��A�C��K�v�Ƃ��Ă��܂���v�ƕ����B�ʂ̐l�́A�u�������́A�����ɌC������܂��B������܂��C�𗚂��Ă��܂���v�ƕ����B�������Ƃ����Ă��A�O�����̐l�ƁA�������̐l�Ƃł͎������S���t�ł���B
�@�w�@�،o�x�ɂ́A�U���_�[�F�o�[�V���isamdha-bhasya)�ƂƂ������t�������Ώo�Ă���B�U���_�[�isamdha�Ӑ}�j�ƃo�[�V���ibhasya�A��邱�Ɓj�̕�����ł���B�u�Ӑ}�������Č��ꂽ���Ɓv�Ƃ����Ӗ������A�M�҂́u�[���Ӗ������߂Č��ꂽ���Ɓv�i�A�{��w�@�،o�x�㊪�A77�łق��j�ƈӖĂ������B�ߑ��̐��@�ɍ��߂�ꂽ�u�Ӑ}�v�u�[���Ӗ��v�����ݎ�ꂸ�ɁA�\�ʓI�ȂƂ���Ŏ~�߂āA������悾�Ǝv������ł��܂����l�����̂��Ƃ��w�@�،o�x�O�����ɕ`����Ă���B�ނ�͂��̂��Ƃ��ߑ��ɗ@����A���Ȕ��Ȃ��āA�������F�ł��������Ƃ�z���N�����B�������Ė����ɂ����鐬���̗\���i���L�j���Ȃ���Ă���B�������ăV���[���v�g�����͂��߂Ƃ�����̍앧���������ꂽ�B
�@�u���Ă�����́v����u���Ĕ�Ȃ���́v�ցA�����Ă��ɂ́u���Ă������ʂ��́v�ւƕϑJ�𐋂���Ƃ������Ƃ�����B�Ⴆ�A�}�E�X�̓l�Y�~�̂��Ƃ����A���̌`���Ă��邱�Ƃ���A�R���s���[�^�[�̉�ʏ�ŕ������I��������A���߂��w�������肷��|�C���e�B���O�E�f�o�C�X�Ƀ}�E�X�Ƃ������O���t����ꂽ�B�ЂƐ̑O�Ȃ�Ƃ̒��Ńl�Y�~�����邱�Ƃ����܂ɂ��������A���̎q�ǂ������́A�g�̉��Ńl�Y�~�����邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ��A�}�E�X�Ƃ����A�R���s���[�^�[�̗p��̂��Ƃ����v�������Ȃ����ォ������Ȃ��B�������āA�{���̈Ӗ�����������B�Ӗ��̒��S��������ӕ��ւƂ���Ă��܂��̂��B���̂悤�ɁA������u�ĂĐ�����Ӗ��̂�����w�E�ł��悤�B
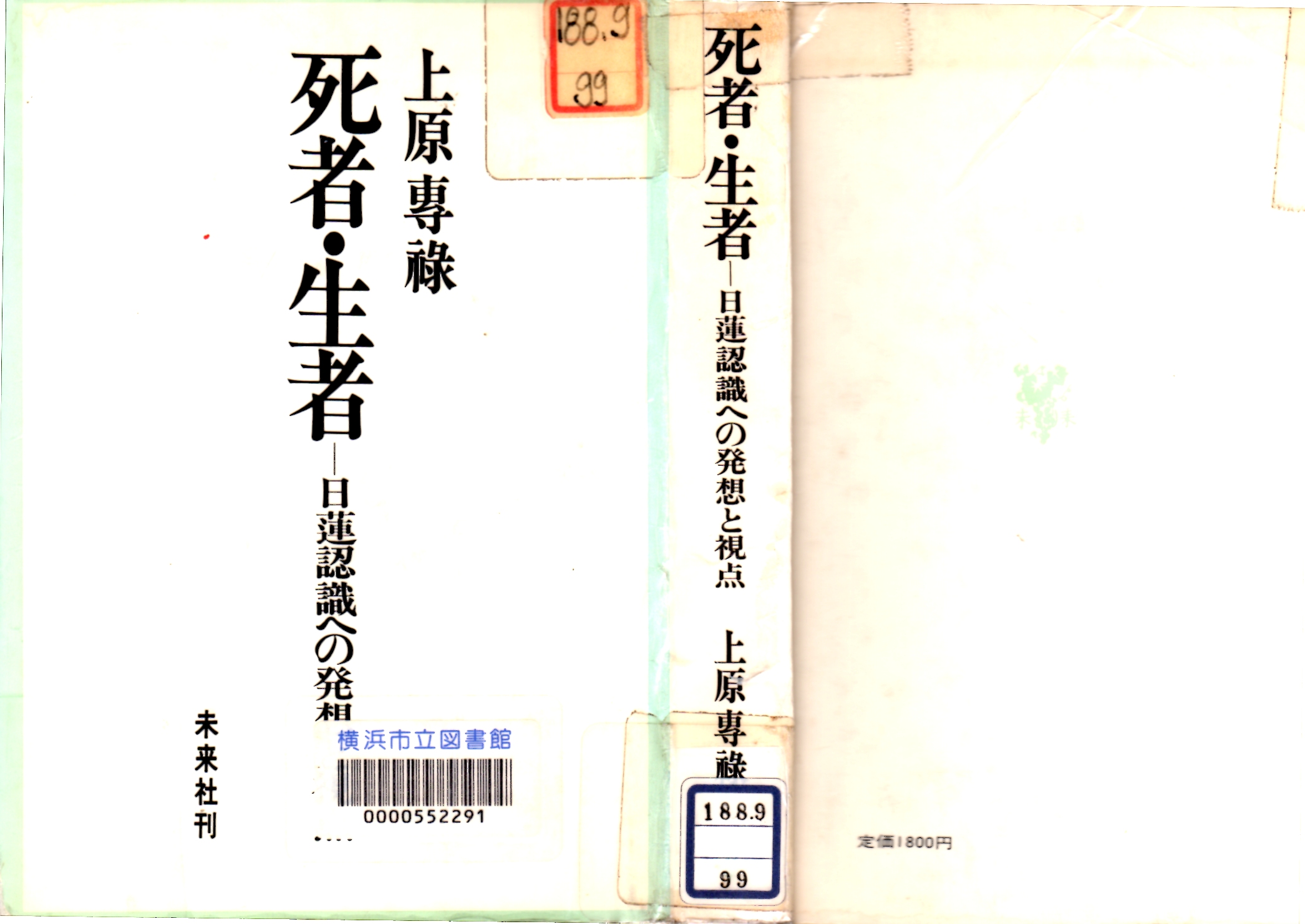
�@
�@���l�ɁA�{���̈Ӗ��`�ɂ���A'�Ƃ����������Ȃ��ꂽ�Ƃ��悤�B�`��A'�Ƃ́u���Ă�����́v�ł͂���B����A'�������l���AA'�̒��Ƃ͂����`�Ƃ͏d�Ȃ�̂Ȃ����ӕ��Ɏ����āA����������A"�Ƃ��Đ��������Ƃ��悤�BA'��A"�͕����I�ɏd�Ȃ��Ă��邯��ǂ��A�`�Ƃ͏d�Ȃ��Ă��Ȃ��B���̎��_��A"�́A�`�Ɓu���Ĕ�Ȃ���́v�ƂȂ�B����ɁA���̐����A�f�Ƃ͏d�Ȃ�̂Ȃ�A"�̎��ӕ����Ƃ炦��A"�f�Ɛ��������Ƃ��悤�B�����Ȃ�ƁA���͂�`��A"�f�Ƃ́u���Ă������ʂ��́v�ƂȂ��Ă��܂��B���t�̈Ӗ����A�u���Ă�����́v����u���Ĕ�Ȃ���́v�A�����āu���Ă������ʂ��́v�ւƎ��X�ɂ���Ă����B����ɂ����������̂́A���̂���𐳓������邽�߂ɁA������������ĈӋ`�Â����悤�Ƃ���l������̂ŁA�܂��܂��{���̈Ӌ`�������ɂ����Ȃ��Ă��܂��B���̉�����͌��_�Ɋ҂邱�Ƃł���B
�@�u���Ă�����́v����u���Ĕ�Ȃ���́v�����āu���Ă������ʂ��́v�ւƂ����ω��́A�����̕����j�ςƂ������ׂ��u���@�v�isaddharma�A�����������v�A�u���@�v�isaddharma-pratirupaka�A�����������Ɏ��Ă�����́j�A�u���@�v�isaddharma-vipralopa �����������̐�Łj�Ƃ����l�����ɂ����Ă͂܂�ł��낤�B���ꂼ��A��N�A���邢�͌ܕS�N�̒������o�Ă���Ă����ƍl����ꂽ�B
�@���{�ł́A���t�̎��Ӗ��̈�̒f�ʂ���������āA���̌��t��p����Ƃ������Ƃ������N���Ă���B�O����̎�荞�݂ł���͂悭������B�h�C�c��̃A���o�C�g�����̈��ł���B�u���͑�w�Ō����̃A���o�C�g�����Ă��܂��v�Ƃ������͂́A���Ƃ��Ƃ̃h�C�c�ł͂��̌������{�E�ł��邱�Ƃ��Ӗ����邪�A���{�ł͓��E�݂����Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂��Ă���B���t�̈Ӗ��̂��ꂪ�r�������B
�@���{��́u�́v�Ƃ����i�����̂����炷���������B�u�X�v�[���͐H��ł���v�Ƃ������͂����āA�X�v�[�����H��̂��Ƃ��Ǝv������ŁA�u�H������������v�ƌ����Ă��A�X�v�[���͎��Ȃ��ł��낤�B���̕��͂͐��m�Ɍ����A�u�X�v�[���͐H��̈��ł���v�Ƃ������Ƃ��B�H��Ƃ����W���̒��̈�Ƃ��ăX�v�[��������B�u�X�v�[���͍��ł���v�Ƃ������͂ƍ\���͑S�����������A�X�v�[���ƍ��͉p��Ɠ��{��̌Ăі��̈Ⴂ�����ŁA�������̂������Ă���B��̏W���Ɋ܂܂�邱�Ƃ��������͂ƁA�C�R�[���ł��邱�Ƃ��������͂��S�������\���ł��邱�Ƃ������������邱�Ƃ�����B
�@�_���̋t�]�Ƃ������Ƃ�����B�M�҂��A���w���̎q�ǂ��Ƃ��̐e�����Ɂu���͗�x�œ���A100�x�ŕ�������v�Ƃ����b�����Ă����B����ƁA�u�w�[���A�҂������x�ƕS�x�Ȃ́A���R�Ă悭�ł��Ă�ˁv�Ɗ�������e�������B����͋t�ŁA�W����C���Ő������鉷�x���x�A�������鉷�x��S�x�ƌ��߂������ł��肢��������悤�ȂƂ���ł͂Ȃ��B
�@��i�ƖړI�̗����Ⴆ�ɂ�銨�Ⴂ��A�ړI������������A����ւ�����肵�āA��i���Ƃ�������邱�Ƃ�����B�Ⴆ�A�ʌo�����鏑�ʍs�ł���B�w�@�،o�x���̂��A��̏C�s�̈�Ƃ��ď��ʍs�̌������g���Ă���B���̗��R��M�҂́A����Z�p�̂Ȃ�����ł��������Ƃɋ��߂Ă���B�o�T���L�����z���邽�߂ɂ́A�菑���ŏ����ʂ��A�ʖ{�̐��̐�ΐ��𑝂₷���Ƃ����߂�ꂽ�B����ɂ���āA�o�T�������蕷������ł���l�����������邵�A�~����l��������B���̌��ʂ������炵���̂́A���ʍs��������l�����ł���B������A���ʍs�Ɍ���������[�[�Ƃ������_���ŁA���コ�ꂽ�̂ł��낤�B
�@�Ƃ��낪�A�����̈���Z�p�̔��B�͖ڊo�܂������̂�����B���̈Ӗ��ł́A�����đ傫���������ʍs�̕K�v���͏������Ȃ����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�Ƃ��낪�A���̏��ʍs���̂Ɏ�p�I�Ȃ����v�̂悤�Ȃ��̂��������ꂽ�肵�āA���コ��Ă���B���̌o�T�ɏ�����Ă���v�z��T��������A����̐������Ƃ��Ė₤���Ƃ����A���ʂ��邱�Ǝ��̂��ړI�ɂȂ��Ă��܂�����������B����́A�K���̗��K�A���_�W���Ȃǂ̈Ӌ`�͔F�߂���Ƃ��Ă��A�o�T����p�I�Ȃ��̂ɂ��邱�Ƃ́A�o�T�𐳓��ɕ]�������Ă���Ƃ͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�@���邢�́A���m��������������邾�낤�B����l�̍u�����ɂ������m�l���A���Ă��āA�u�f�J���g�N�w�ɂ��Ă̍u���������v�Ƌ����Ă��ꂽ�B�Ƃ��낪�A����A�����ɂȂ������̍u���̃f�J���g�Ɋւ��镔���́A���̂��Ƃɂ́u�f�J���g���W�v�i�����Ƃ�������Ȃ钼�����W�j�̂悤�Ɋ������Ƃ����b�ŁA�f�J���g�N�w�ł����ł��Ȃ������B
�@�܂��A�`���Q�[���Ō���ވ���Ƃ��āA���ӓI���߂������邱�Ƃ��ł��悤�B����͐���ؗL�����A��\�I��q��������݉ƂƏ������폜���Ēj���o�Ǝ҂́u�\���q�v�Ɍ��肵�Ă��܂������T�̉�₁i��1��65�ŎQ�Ɓj��A�v�ɑ��Č����Ă����Ȃւ̕�d���A��d����l���Ȃ����Ɍ��肵�Ă��܂��������ł̊���̂����i��7��256�ŎQ�Ɓj�ȂǂɌ�����B
�@�w�@�،o�x�͏������ʂ̌o�T���Ɣᔻ����l���A���̗��R�Ƃ��āw�@�،o�x�ɏ������u�b�_��A�]�����Ȃ�5�̂��̂ɂȂ�Ȃ��i��j�Ɛ�����Ă��邱�Ƃ������Ă����B�������A����́w�@�،o�x�̎咣�ł͂Ȃ��A���敧���̏����ςɎ���ꂽ�V���[���v�g���i�ɗ����j�̌��t�Ƃ��ċ������Ă��āA�w�@�،o�x�͂����_�j���Ă���̂ł���B����́A�O��̖�����ǂ݊ԈႦ�����Ⴂ�ł���B
�@�Ƃ�����̏����̒��Ō��ꂽ���Ƃ��A���̏����������Ƃ�����A���������肵�Č��p����邱�Ƃ�����B�Ⴆ�A�u�����A�`�ł��邱�Ƃ������Ȃ�A����͂a���Ǝ��͎v���v�Ƃ������t���āA�u���̐l���A�w����͂a���x�ƌ����Ă���v�ƌ����G�炷�l������悤���B
�@�܂��A�u���ӂɂ��c�ȁv�������邱�Ƃ��ł��悤�B�ȑO�A�M�҂�����Ƃ���ōu���������A�`���A���̂悤�ɘb�����B
�u�F����A�^��Ɏv��ꂽ���Ƃ͉������Ȃ��Ŏ��₵�Ă��������B�^��͎c���Ă͂����܂���B�������[�����邱�Ƃ���ł��B������ƌ����āA���̏�œ������Ȃ����Ƃ����邩������܂���B���̎��́A������x����@�����܂�����A����܂łɒ��ׂĂ���������悤�ɂ��܂��B����ɂ���āA�����C�Â��Ȃ��������Ƃ��w�Ԃ��Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�܂��B�����牓�����Ȃ��Ŏ��₵�Ă��������v
�@�Ƃ��낪�A������A�m�l���u�A����A���t�����ɋC�������ق��������ł���B�w�A����͘����ł��ˁx�ƌ����Ă���l�����܂��B�w���͉��ł��m���Ă���B���ł������Ă݂��邩��A���ł����₵�Ă�x�ƌ�������ł����āH�v�ƌ����Ă����B�����ǂ������A���̂悤�ɂȂ�̂������ł��Ȃ����A����͈��ӂɂ��c�ȂŁA�������Ęb�͘c�߂���悤���B
�@�����ł́A�g�E���E�ӂōs�Ȃ��u�\���v�̂���4�����ɂ����̂Ƃ��āA�@�ό�i�R�����j�A�A�Y��i�Y�킲�Ƃ������Č얀�����j�A�B�����i�����������j�A�C����i����g���j�\�\�������ċւ��Ă���B�w�X�b�^�j�n�[�^�x�ɂ����Ďߑ��͎��̂悤�Ɍ���Ă���B
�u�l�����܂ꂽ�Ƃ��ɂ́A���Ɍ��̒��ɂ͕��������Ă���B���҂͈��������āA���̕��ɂ���Ď�����芄���̂ł���B�ʂ�ׂ��l��_�߁A�܂��_���ׂ��l��ʂ�ҁA�\�\����͌��ɂ���ĉЂ������ˁA���̉Ђ̂䂦�ɕ��y���邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�i��������w�u�b�_�̂��Ƃx146�Łj
�@����́A�T�[���v�b�N�i�ɗ����j�ƃ��b�K���[�i�i�����A�j�̃f�}�������ӂ炵���R�[�J�[�����Ƃ����C�s�m�ɂ��ďq�ׂ����̂ł���B�f�}�̓��e�́A��l���q�����Ɠ��A�œ��𖾂������Ƃ������ƂŁA�u��l�ɂ͎הO������v�Ƃ������̂��B��l�͖\���J�̖�A�J��������ē��A�̒��œ��𖾂����A�����A�o�čs�����B�Ƃ��낪�A���̓��A�̉��ɂ͖q��������ɉJ�h������Ă����悤�ŁA��l���o�čs������ɁA���A����o�Ă����B�����ڌ������R�[�J�[�����́A�u��l�ɂ͂悱���܂ȗ~�]������܂��v�Ɛ��������i���A366�Łj�B
�@�����납���l�ɑ��ēG�ӂ�����Ă����R�[�J�[�����́A�ߑ����牽�x���k2�l���l�M���Ȃ����v�Ɨ@���ꂽ�ɂ�������炸�A�������邱�Ƃ���߂悤�Ƃ��Ȃ������B���̃R�[�J�[�����́A�S�g�Ɏ�ꕨ�������A���̕a��̂��߂Ɏ������A�u�g�@�n���ɐ��܂ꂽ�v�i���A144�Łj�ƕ��T�ɋL����Ă���B
�@�������������ɑ���ɂ́A�V���@�ĕP�̌��܂蕶��u������č�������ȁv�Ɋw�Ԃׂ��ŁA�ǂ��܂ł������ŁA�ǂ��܂ł��������̂��m�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�u���邪�܂܂Ɍ���v���Ƃ̓��
�@�ȏ�̗�����Ă��Ă�������Ƃ���A�l�͂���̂܂܂ɂ��̂��Ƃ�����̂�����Ȃ悤�ł���B����́A���́i3�Łj�ɋ������k�m�v���̋��ɂ��Ă̘b�������ł������B�Ƃ��낪�A���ʕi��\�Z�i��P�T�́j
�@�u�@���͎O�E���A���ɂ��邪�܂܂Ɍ���idrstam yatha-bhutam�j�v
�@�u�@���@���m���O�E�V���v�i�@���́A�@���ɎO�E�̑���m�������A�ؖ�w�@�،o�x�����A228�A229�Łj
�@�u�@���m���v�Ƃ́A�u���邪�܂܂ɁA���̂��Ƃ�m������v�Ƃ������Ƃ��B����́A���Ɍ��n���T�ɂ����Ă����ΐ�����Ă����B�������A�����͂���܂Ō��Ă����Ƃ���A����̂܂܂ɕ��������Ă��Ȃ����Ƃ������B��l�ςŌ�����A������S�̂Ǝv������A���Ђ������Č���Ă��邱�Ƃɂ���āA�������������Ƃ܂Ŕے肵�Ă��܂����Ƃ�����B
�@�]�ˎ���Ɋ����̈�t�������땪���i��U�j�����w�ɍs�����B��������J�����ƁA�f�@���̕ǂɓ\���ē����납�猩����Ă����ܑ��Z��̐}�ƈʒu������Ă����B����ɋC�Â����ނ�́A���h���邪�A�ŏI�I�ɂǂ����_�����������Ƃ����ƁA�u�����D��������Ă���j�͍ߐl�ł���B�������Ƃ������̂ŁA�S�����ł͂Ȃ��ܑ��Z�D�̈ʒu�܂ŋ����Ă��܂����̂��v�ƁB����ȂǁA�����̊�Œ��ڌ��Ă��邠��̂܂܂̎�����F�߂悤�Ƃ��Ȃ��ŁA���Ђ��銿���̋����͐���Ƃ��Ă���ɌŎ����Ă��܂����Ƃ�����ł���B���ɏ��Ȃ��h���R�̐��h�̋��P�ł��낤�B����l�ɒ��ډ���āA���̒����܂œǂ�Ŋ������Ă����Ȃ���A���ꂩ�Ƀf�}�𐁂����܂�đԓx��^�ς�����̂��������Ƃ��B����قǂ܂łɁA�u���邪�܂܂Ɍ���v�Ƃ������Ƃ͍���ł���B
�@�������R�����z���Ă��āA�ق��ƈꑧ�����Ƃ��A���̕Ћ��ɂЂ�����ƉԂ��炢�Ă����B���̉��Ő��^�Ȏp�ɋ����ƂƂ��ɐS�������ꂽ�B�߂Â��Ă݂�Ɠ��̉Ԃł������B�����m�Ԃ́A���̎��̎v�������̋�ɉr�B
�@�@�R�H���ĉ����䂩�����݂ꑐ
�@����́A���s�����Â���������R�z���̐܂̂��Ƃ��r���̂��B���[�ɂЂ�����ƉԂ��炩���铟�ɁA���C�łЂ��ނ��Ȑ����͂������A����̐������Əd�ˍ��킹�A�u�����䂩���v�Ɖr�Q�̎v�������߂ĉr�̂ł��낤�B
�@�Ƃ��낪�A�����ł���A���ꂢ���ȂƎv���ċ߂Â��āA�u�����A�����v�ŏI����Ă��܂������ł���B���̈ꌾ�����ɂ����u�ԂɁA���̂��Ƃ�������������ɂȂ��Ă��܂��A���g�������������A���������֒u���āA�����������������Ă��铟�̒m����A����ςɈ��Z���Ă��܂��B����̂܂܂Ɍ��邱�Ƃ�������Ă��܂��̂��B
�@�����́A����قǂɂ��̂��ƂɎ������A�Œ�I�ɂƂ炦�邱�ƂɊׂ肪���ł���B�����ł́A���̂��ƂɎ������邱�Ƃ�ے肷�邽�߂ɁA��������̂ɂ͕s�ς̎��̂͂Ȃ��Ƃ��āu��v�isunya)���������ꂽ�B�Ƃ��낪�A���́u��v���̂����̂Ƃ��ČŒ�I�ɂƂ炦�A�u��Ƃ������́v�Ɏ�������l���o�Ă����B�����ł���ɁA�u����v�i���������j�ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�u����v���܂�������̂Ƃ݂Ȃ��ꂽ��A�u�w����x������v�ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����قǁA��������Ȃ������Ȃ��̂ł���B
�@�ߑ��̏C�s�́A�T����s�Ƃ����������̏펯�Ƃ���Ă����C�s���@�ɂ̂��Ƃ��Ďn�܂����B������A����܂ł������������Ƃ��Ȃ��قǓO�ꂵ�����̂ł������B�������A����ɂ���Ė������邱�Ƃ͂Ȃ������B�����̋��߂邱�ƂƂ͈Ⴄ�Ƃ����A���̈�a�����傫���Ȃ�A�ŏI�I�ɂ�����������ĎR������A��Őg�𐴂߁A������������ĐH�ׂđ̗͂����A�����̉��Ŋo�����B��s��������A�H�ו���������ĐH�ׂ����Ƃɑ��āA�ꏏ�ɏC�s���Ă����ܐl��������A�u�S�[�^�}�͑������v�Ɣ��ꂽ�B����ł��A�����T�O���l�ςɎ����邱�ƂȂ��A�ߑ��͎����̔[������܂܂ɏC�s�����B�����āA�o����B
�@���̊o��̓��e�́A�u�\������v�i�\��x���N�j���Ƃ��A�u�����v���Ƃ��A�u�l���v�u�������v���Ƃ��A���낢��Ǝ�荹������Ă���B�o�T�ɂ���ĈقȂ��Ă���̂��B�����ɋ��ʍ��̂悤�Ȃ��̂́A���o���������B�M�҂́A���̈Ⴂ�́u�ꐅ�l���v���l�A�ߑ��̋���������q�����̎~�ߕ��̈Ⴂ�ɂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�����āA�����ɍő�������o���Ƃ���A�ߑ��́u���邪�܂܂ɂ��̂��Ƃ�����v�Ƃ����u���̂̌����v���o�����̂ł͂Ȃ����B����́A�S���ʁX�̌��ۂ̂悤�Ɍ����郊���S�̗������ƁA�V�̂̉^�s�̂����ɋ��ʂ��Ă�����̂Ƃ��ăj���[�g�������L���͂����o�����悤�Ȃ��̂ł��낤�B
�@�u�\������v�Ȃǂ́A�u���邪�܂܂Ɂv�������ʂĂ͂Ȃ����B���Ȃ킿�u�@���m���v�Ƃ����፷���ŁA�l�̔Y�݂�ꂵ�݂̐�����������u�\������v�ƂȂ�A���̊�őP�ƈ��Ȃǂ̓I�Η�������A���ɒ[�ɕ�Ȃ��u�����v�Ƃ����݂���ƂȂ�A�C�s�݂̍��������A�u�������v�ƂȂ�A��̐����Ə��ł̈��ʂ݂̍��������A�u�l�����v�ƂȂ��������ŁA�����Ɉ�т��Ă���̂́A�u���邪�܂܂ɂ��̂��Ƃ�����v�����ł���B�u���邪�܂܁v�Ƃ������Ƃ́A���̂��ƂɎ����Ȃ��Ƃ������ƂŁA������~�]�ȂǂɎ����Ȃ��Ƃ������Ƃł����낤�B��Ɍ���������炷���̂Ƃ��Č�����������ς�A���Ђ��鋳���A���ӁA�����ςɎ����邱�Ƃ��A�����S�̌����ł���B
�@�����������O������Ō���A�ߑ����O�ꂵ��������`������A���M�E�h�O�}����ے肵�Ă������Ɓi�����V���w�����A�{���̋����x���͎Q�Ɓj�́A���R�̋A���ł������B
�@�x�i���X�x�O�̎��̉��i���쉑�j�Ő����㏉�̐��@�i���]�@�ցj���I���A�E�����F�[���[�i�D�O�p���j�ɕ����߂����ߑ��́A�o���������̉̍s�҂Ƃ��ĕ]���ł������J�b�T�o�i�ޗt�j�O�Z������������B�ߑ��́u�悭�����ꂽ���t�ƁA�@�Ɨ��������v���āA��q�ƂȂ����J�b�T�n�O�Z��̖���K���[�E�J�b�T�o�i�ޖ�ޗt�j�́u���邪�܂܂̐^���ɑ����������v(�w�e�[���E�K�[�^�[�x39�Łj�Ƃ����z��R�炵���B����́A�u���邪�܂܂ɂ��̂��Ƃ�����v��Ō����Ă��������Ƃ����Ӗ��ł��낤�B
�@���̂悤�ɁA�u�\������v���A�u�����v�u�l�����v�u�������v���A�u�@���m���v�Ƃ������̂̌����Ō��������ʂł���A���{�ɂ́u�@���m���v������B�ʓI�Ȓm�ł���u�\������v�u�����v�u�l�����v�u�������v�����A��荪�{�́u�@���m���v�̂ق�����蕁�ՓI�ł���B�O�҂͒f�ГI�Ȓm�ɂȂ�₷���A�Ӗ����Œ艻���₷�����A��҂͐W�ՓI�ʼn��p�������B
�@
�ʓI�Ȓm�ƐW�ՓI�ȍl����
�@�ߑ��̋������Ē�q�ƂȂ������̂����́A�����Ɂu�҂̊p�̂悤�ɂ����Ƃ���߁v�ƌ����āA�`���̗��ɏo�Ă���B���]�@�ւŌܐl�̒�q�������o��ƁA�����Ɏߑ��͕ʍs��������Ă���B���̂ق��̒�q�������A�ߑ����狳�������̂͂���Ȃɒ����Ԃ̂��Ƃł͂Ȃ��B�f�ГI�Ȓm���ł���A����ȂɒZ���ԂɏK���ł��Ȃ��ł��낤�B�܂��A�ʂ̏�ɑΉ��ł��Ă��قȂ��ɂ͑Ή��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��N����B���{�̕��ՓI�ȁu���̂̌����v��g�ɒ��������牞�p���������̂ł��낤�B
�@���c�@�l�u���{���w��v��2011�N�ɑ�w����Z��l��Ώۂɍs�Ȃ������w�̓e�X�g�ŁA�_���I�v�l�͂��R�����w������������Ɣ��\�����B���̖₢�̒��ɁA��Ƌ����𑫂��Z����Ɗ�ɂȂ闝�R��₤���̂��������B
�@���Ƃ������R���Ƃ���ƁA���ׂĂ̋�����2���ŕ\�킳��A���2��-1�ŕ\�킳���B���҂𑫂�
�@2��+�i2��-1�j��2�i��+���j-1
�@�����ŁA���\�����m�ƒu��������ƁA2N-1�ƂȂ�A2��-1�Ɠ����`�Ȃ̂ŁA��ɂȂ邱�Ƃ��ؖ������B����ɂ���āA���ׂĂ̊�Ƌ����̏ꍇ�̑����Z�ɂ��Ă̏ؖ����Ȃ��ꂽ���ƂɂȂ�B
�o��҂́A�����������������߂��̂ł��낤�B
�@�Ƃ��낪�A�����̒��Ɂu�����̒m���Ă����Ƌ����𑫂��Ă݂����ɂȂ�������v�Ƃ��������̂��������Ƃ����B�Ⴆ�A�P�ƂS�łT�A3�ƂU�łX�Ƃ�������Ɏ����Ă݂��̂ł��낤�B�������A����́A�P�ƂS�A�R�ƂU�̏ꍇ�ɂ��܂��܊�ɂȂ����̂�������Ȃ��B�����Ƌ���Ȑ��ł́A��ɂȂ�Ȃ���������Ȃ��B���̕��@�ł́A���ׂĂ̐��ɂ��Ė����Ɍ������Ȃ���Ό��_���o���Ȃ��B
�@�����ɌʓI�Ȓm���ƁA���ՓI�ȍl�����̈Ⴂ�����Ď��悤�B�w��Ƃ������Ƃ́A�ʓI�Ȓm���𑝂₷���Ƃ����A���̂̌����A�l������g�ɒ����邱�Ƃ̂ق����d�v�ł���B�N�B�Y�ԑg�̓����̂悤�Ȓm������������o���Ă��A�����̒m���̒f�Ђ𑝂₷�݂̂ŁA����ɂ���Ēm�̑n���I���W�͓����Ȃ��B�ʓI�Ȓm�����w�Ԃ��Ƃ�ʂ��āA���̂̌����A�l������m��A������Ȃ����Ƃɏo���킵�Ă��A�ǂ̂悤�ɒ��ׂ�Γ�����������̂��Ƃ������_��g�ɒ�����Ή��p�������B
�@�ߑ����A�ʂ̋����Ɏ����邱�Ƃ����߂Ă���B�W�ՓI�Ȏ��_���d�����Ă������Ƃ̕\���ł���B
����́u���̏Q���v���ߑ����g�������Ă������Ƃ�����m�邱�Ƃ��ł���B����́A�w�}�b�W�}�E�j�J�[���x�i�h�E134�`135�j�ɂ��Ǝ��̂悤�Șb�ł���B
�@�X��������Ă���l���A���������̗���ɏo������B������݂̊͊댯�ŋ��낵���Ƃ���ŁA�������݂͈����ȂƂ���ł���B����ǂ��A������ɂ͓n���M���Ȃ��A�����˂����Ă��Ȃ��B���̐l�́A��}�Ȃǂ��W�߂Ĕ���g�ݗ��āA����ɂ���Ė����Ɍ������݂֓n�邱�Ƃ��ł����B�����ōl�����B�u���̔��́A���̂��߂ɑ傢�ɖ��ɗ������B���́A���ꂩ�������̔��ɍڂ��A���邢�͌��ɒS���ŕ����Ă������Ƃɂ��悤�v�ƁB
�@���̂悤�Ɍ���Ďߑ��́A�u����́A���ɑ��ēK�Ȃ��Ƃł��邩�H�v�Ɩ₢�������B�����́A�������u�m�[�v�ł���B�w�����ʎ�o�x�ɂ́A���̌��t��������B
�@�u�䂪���@�̚g���̔@���ƒm��҂́A�@����Ȃ��܂��Ɏׂ̂��B�����ɋ�����@����v�i�������E�I���`�w�ʎ�S�o�E�����ʎ�o�x56�Łj
�@�ߑ��̋����́A�u���a�^��v�i�a�ɉ����Ė��^���j�ƌ����āA�O���̔\�͂�u���ꂽ��ɉ����Đ����ꂽ�B����̏�ɂ����Đ����ꂽ���̂�����A�قȂ��ł͂��̂܂ܓ��Ă͂܂�Ȃ��Ƃ������Ƃ��N����B�]���āA�ʂ̋������Ή����邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ����r�߂��̂��u����栂��v�ł���B������A�ʂ̋�����f�ГI�ɊW�߂Ċo��������A�ꌩ�A�o���n���Ɍ�������̂Ɋт���Ă��镁�ՓI�Ȏ��_��g�ɒ����邱�Ƃ��厖�ł���B
�@�f�ГI�m���ł́A���Əꍇ�Ə���킫�܂��邱�Ƃ��ł����A�ߑ��̋�����������`�I�ɐ�Ή����āA�����������邱�Ƃ����낤�B����킫�܂��鉞�p�͂́A���̂̌����A�q�d��g�ɒ����邱�Ƃɂ���Ĕ��������B�m���̒f�Ђ̊W�߂ł͉��p�������Ȃ��B�u���̂̌����v�������Ջ@���ςɂ��̂��Ƃ̖{�����������đΉ��ł���B���ꂪ�u�@���m���v�ł��낤�B
�@���n���T�́w�X�b�^�j�o�[�^�x��202��ɁA���̌��t������B
�@�u���̐��ɂ������q�d������C�s�҂́A�ڊo�߂��l�k�ł���u�b�_�l�̌��t���āA���́k���t�l�����S�ɗ������A���邪�܂܂Ɍ���iyathabhatam passati�j�̂ł���v�i�w�X�b�^�j�o�[�^�x35�Łj
�@����́A�ߑ��̌��t���āA��q�������u���邪�܂܂Ɍ���v���Ƃ��Ȃ��Ă������Ƃ������Ă���A���̂悤�Ȓ�q�����̂��Ƃ��u�q�d������C�s�ҁv�Ƃ��Ă��邱�Ƃ�����������B�ߑ����A���邪�܂܂Ɍ���q�d���d�����Ă������Ƃ��A����������ǂݎ��悤�B
�@
�u�^�̎��ȁv�̒T���Ɓu�����g��m��v
�@�������u�@���m���v�������̂ŁA�d���������̂̈�́A���Ȃł������B�u�^�̎��ȁv�̒T�����d�����Ă������Ƃ��G�s�\�[�h���w�}�n�[�D���@�b�K�x�i�h�E14�j�ɋL����Ă���B����́A�ߑ����A�x�i���X�x�O�̎��̉��i���쉑�j�ŏ��]�@�ւ��I���āA���炪�o����J�����Ƃ���ł���E�����F�[���[�w�Ɩ߂�r���̂��Ƃ������B�ߑ��́A�X�����炻��ėтɓ����Ď��̍����Ƃɍ����Ă���ꂽ�B���̗т�30�l�̗F�l�������v�l�����ŗV�тɗ��Ă����B���̂����̈�l�����́A�Ɛg�������̂ŗV����A��Ă��Ă����B�Ƃ��낪�A���̗V�����݂�Ȃ̎������������ē��������Ă��܂����B���̏���T�����߂ėт����܂���Ă��āA�ߑ��������Đq�˂��B�u1�l�̏��������܂���ł������v�ƁB�����ŁA�ߑ��́A�������B
�@�u�N������B���݂�͂ǂ��l���܂����H�@���݂������w����T�����߂�̂ƁA���ȁiatta�j��T�����߂�̂ƁA���݂����ɂƂ��Ăǂ��炪������Ă��܂����H�v�i��������j
�@�N�����́A�u���Ȃ����߂邱�Ƃł��v�Ɠ����A�ߑ��̐��@���ďo�Ƃ�\���o���Ƃ����B�����ł́A�u�^�̎��ȁv�̒T���Ƃ������Ƃ��d������Ă���B����́A���͂ł��G�ꂽ�u���A�ˁv�u�@�A�ˁv�Ƃ��d�Ȃ��Ă���B���]�@�֒���̋����ƁA���Ŋԍۂ̋������A����|�ł���B�Ƃ������Ƃ́A�ߑ�����т��Đ��������������Ƃ́A���邪�܂܂Ɍ��邱�Ƃɂ��u�^�̎��ȁv�̒T���ł������ƌ����Ă������ł��낤�B���́A���̈�_�ɂ����u�\�W�]�v���h�`���Q�[���h�Ɍ�����Ȃ��\�\�Ƃ��������A���������Ȃ��J�M������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�����ŕM�҂́A�u�\�N���e�X�̓V�r���G�C�ŁA���������т�Ă��邩�炱���l�����тꂳ���邱�Ƃ��ł���B����Ɠ����悤�ɁA�������������Ă��邩��A�l�����������邱�Ƃ��ł���B�������������ĂȂ��Đl�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ������ƂŁA���́u�\�W�]�v�ɂ��āA��l�ЂƂ肪�w�@�،o�x�̈����Ċ�������A���̃����[�̌��ʂƂ��Č\�ԓ����������Č������傫�\�\�Ɛ������悤�Ƃ��Ă����B����܂ŁA�\�N���e�X�̌�����V�r���G�C�̘b�͈ȏ�̂悤�Ȏ�|�Ō���Ă����悤�Ɏv���B
�@�Ƃ��낪�A���߂ē���ߕv��w���\���x�i��g���ɁA42�`44�Łj���J���đO��W��ǂ�ł݂�ƁA���̉��߂́A�ǂ������҂̃v���g�����Ӑ}�������ƂƈႤ�悤���B�Θ_�҂̃��\���́A�\�N���e�X���\�ǂ���u�݂����獢��ɍs���Â܂��ẮA�ق��̐l�X���s���Â܂点���ɂ͂��Ȃ��l�v�ł���A�\�N���e�X�̊炩�������̑����A�C�ɂ��镽�ׂ������V�r���G�C�������肾�Ɲ�������B�V�r���G�C���A�߂Â��ĐG�����̂�N�ł����тꂳ���邩�炾�B
�@����ɑ��ă\�N���e�X�́A�u�����A���̃V�r���G�C���A�������g�����т�Ă��邩�炱���A���l�����тꂳ����Ƃ����̂Ȃ�A�����ɂ��ڂ��̓V�r���G�C�Ɏ��Ă��邾�낤�v�Ɠ�����B�����Ō����u���т��v�Ƃ́A�u�S����������Ă����Ƃ肷��v�Ƃ��m��������n�Ƃ����]�p���ꂽ�Ӗ��ł͂Ȃ��A���Ƃ��Ƃ́u�g�̂̊��o�������A���R�������Ȃ��Ȃ�v�Ƃ����Ӗ��ł���B�q�E�}�b�W���[�����A�����r�G�@��w�N�w�҂����̓������x�ł́A�u�������g�����т�Ă���v�̕������u�������g�����������ɏ�Ԃɂ����āv147�Łj�Ɩ�Ă���B���̖�u��������v�Ƃ����Ӗ��͏o�Ă��Ȃ��B
�@�\�N���e�X�́A������V�r���G�C�Ə̂��邻�̗��R���A�u�Ȃ��Ȃ�m�����n�����������Ă���̂́A�܂��N�����ڂ����g�ł���A���̂��߂ɂЂ��ẮA���l��������ɍs���Â܂点�錋�ʂƂȂ�̂��v�Əq�ׂĂ���B�����ɂ́A�����Ƃ����Ӗ��͊܂܂�Ă��Ȃ��B
�@���������m�ł��邽�߂ɁA�u��ꂱ���͒m���Ă���v�Ǝv������ł���l�ɑf�p�ȋ^��𓊂�������B����ɂ���āA�u��ꂱ���͒m���Ă���v�Ǝv������ł���l�����͍��f�Ɋׂ�Ƃ����̂ł��낤�B�\�N���e�X�́u���m�̒m�v�̗���ɗ����đΘb�����Ă���̂��B�����l����ƁA�w�_���}�E�p�_�x�̒��Ŏߑ�����������̑�63����v���o���B
�@�u���������҂��݂�������ł���ƍl����A���Ȃ킿���҂ł���B���҂ł���Ȃ���A�������݂����猫�҂��Ǝv���҂����A�w���ҁx���ƌ�����v��������w�u�b�_�̐^���̂��ƂΊ����̂��Ƃx19�Łj
�@�\�N���e�X�ɂ���Ă�肱�߂�ꂽ�\�t�B�X�g�i�E�ƓI�٘_�Ɓj�����́A�������ւ�A�m���蕨�ɂ��A�c�_�̂��߂̋c�_�ɒ^���Ă����B�\�N���e�X�́A�ނ�ɑ��Ēɗ�Ȕ�������߂āA�u����͖��m�ł���v�ƌ���Ă����B���ꂪ�A������V�r���G�C�Ƃ��Ă������Ƃł���B����́A�\�t�B�X�g�����̌����u�m�v���炷��u���m�v�Ƃ������Ƃł������Ǝv���B
�@�u���v�͊w�Ԃ��Ƃ��ł���̂��Ƃ����A���\���Ƃ̑Θb�ł��A�\�N���e�X�́u���͕s���Ȃ���̂ł���k�����l�������łɊw��ł��܂��Ă��Ȃ��悤�Ȃ��̂́A���ЂƂƂ��Ă����v�B������u���ɂ��Ă��k�����l�ȑO�ɂ��m���Ă����Ƃ���̂��̂ł���ȏ�A���������̂��̂�z���N�����Ƃ��ł���̂́A�����s�v�c�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��v�Ƃ��āA�u�T������Ƃ��w�ԂƂ��������Ƃ́A���͑S�̂Ƃ��āA�z�N���邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��v�ƌ���Ă���B�u�����g��m��v�ɂ́A���������w�i���������̂��낤�B�ߑ����E�b�r���[�Ƃ��������Ɂu���Ȃ����g��m��Ȃ����v�ƌ�肩���Ă����i�w�f�[���[�E�K�[�^�[�x128�Łj�B
�@�\�N���e�X�̌����u�z���N���v�u�z�N����v�́A�����́u�^�̎��߂ɖڊo�߂�v�ɓ�����ł��낤�B�܂��A�\�N���e�X�̌����u���v�́A�u�@�v�Ɗ��ꂽ�u�_���}�v�idharma�j�ƒʂ�����̂ł���i�w�����A�{���̋����x47�ŎQ�Ɓj�B����́A�w�Ԃׂ����̂ł͂Ȃ��A�z�N����ׂ����̂��Ƃ����̂��A�_���}�i���j�����o�߂�i��budh�j�ׂ����̂Ƃ���Ă����̂Ƌ��ʂ��Ă���B����́A�ق��ł��Ȃ����Ȃɋ����Ă�����̂ł��邩�炾�B
�@
���Ȃ𗣂�āu�@�v�͂Ȃ�
�@�ߑ����g�A���̃_���}�i�@�j�Ǝ��g�Ƃ̊W���Ȍ��Ɏ��̂悤�ɕ\�����Ă����B
�@�u���@�b�J����A���ɖ@��������͎̂�������B����������͖̂@������B���@�b�J����A���ɖ@�����Ȃ��玄������̂ł����āA�������Ȃ���@������̂ł���v�i�w�T�����b�^�E�j�J�[���V�x120�Łj
�@�u�b�_������Ƃ������Ƃ́A���ʂȑ��݂Ƃ��Ẵu�b�_�ł͂Ȃ��A���̃u�b�_���u�b�_���炵�߂Ă���u�@�v�����邱�Ƃł���A���́u�@�v���ϔO�I�E���ۓI�Ȃ��̂Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��A�u�b�_�̐l�i��A�������Ƃ��ċ�̉�����đ��݂��Ă���Ƃ����̂ł���B
�@�������A���́u�@�v�̓u�b�_�݂̂ɊJ����Ă���̂ł͂Ȃ��A����l�ɂ������ɊJ����Ă���B�]���āA���́u�@�v�ɖڊo�߁A�u�@�v������ɑ̌�����A����ł��u�b�_�A���Ȃ킿�ڊo�߂��l�i�o�ҁj�ł���Ƃ������ƂȂ̂��B����́A�l�i�I���ʂ��Ƃ炦���u�l�v�ƁA���ՓI�^���Ƃ��Ắu�@�v�Ƃ̐��Ă��藣���Ȃ��W�����������̂��B�����u�l�v�Ɓu�@�v�ł́A��ۓI�ȁu�l�v�̂ق��ɖڂ��D���₷���B��̓I�Ȃ��ꂩ����ʎ����āA�����ډ����Ă��܂��A���ȂɁu�@�v��̌����邱�Ƃ������������ł���B���̓_�ɑ��āA�w���όo�x�i�w�吳�V���呠�o�x��12�A642�ŏ�j�A���邢�́w�ۖ��o�x�i�A�ؖ�A576�Łj�́A���̂悤�ɉ��߂Ă���B
�@�u�˖@�s�ːl�v�i�@�Ɉ˂��Đl�Ɉ˂炴��j
�u�l�v����������ƁA��̓I�ł���Ƃ����悤�B�Ƃ��낪�A�������̐l�������ʂŁA�����͑ʖڂȑ��݂��Ƃ��鍷�ʂ������A���̐l�ɗ�������A���������肷��Ƃ����W�ɂȂ�₷���B����A�u�@�v����������ƁA���ՓI�ł���A�����ł����č��ʂ��Ȃ��Ȃ�B����ǂ��A���z�_�A���ۘ_�Ɋׂ�₷���B����ɑ��āA��́w�T�����b�^�E�j�J�[���x�̌��t�́A�ߑ��Ƃ����u�l�v�ɋ�̉����ꂽ�u�@�v�ł���A����͒��ۘ_�ł͂Ȃ��ߑ��Ƃ����u�l�v�̐������Ƃ��ċ�̉����ꂽ���̂ł���B���́u�@�v�͒N�l�ɂ��J����Ă�����̂ł���A���ꂼ��́u�l�v������ɋ������ׂ����̂ł���B������A�u���A�ˁv�u�@�A�ˁv�Ƃ��āA�u�l�v�Ƃ��Ă̎��ȂƁA�u�@�v�����ǂ���Ƃ���ׂ����Ƃ���������Ă����̂ł���B
�@�u�@�v�ƁA�u�l�v�Ƃ��Ắu���ȁv�́A�藣������̂ł͂Ȃ��B�u�@�v�����߂�Ƃ����Ă��A�u���ȁv�Ƃ������ꂽ�Ƃ���ŋ��߂Ă��A����������̂͂Ȃ��ł��낤�B�ȏ�̂��Ƃ������Ȃ���A�w�،��o�x��F����i��Z�̎��̈�߂����ɕ����B
�@�u�Q���Εn���̐l�A����ɑ��̕�𐔂�����A���甼�K�̕��Ȃ����@���B�������܂������̔@���v�i�w�吳�V���呠�o�x��9�A429�ŏ�j
�@���ȂƂ������ꂽ�Ƃ���ł́u�����v�A���Ȃ킿�u���m��v�u�����v�ł��邱�Ƃ́A�\�t�B�X�g�̌ւ邱�ƂƓ����ł���A�u���ȁv�Ƃ͊W�Ȃ��B������A�����琔���グ�Ă����Ȃ�L���ɂ�����̂ł͂Ȃ��Ƃ����̂��B����́A�\�N���e�X�ɂƂ��Ċ��D�̔���̑ΏۂƂȂ���̂ł��낤�B���@�͂��̈�߂܂��āA34�Œ��킵���Ƃ����w�ꐶ�������x�Ɏ��̂悤�ɋL���Ă���B
�@�u�Ⴕ�ȐS�̊O�ɖ@����Ǝv�͂A�S�����@�ɂ��炸�A�e�@�Ȃ�m�����n�s�Ĉ�㔪���̐����E�O���\���̏�����F���䂪�S�̊O�ɗL��Ƃ́B��߂�ߎv�ӂׂ��炸�A�R��Ε������K�ӂƂ��ւǂ��S�����ς�����ΑS�������𗣂�鎖�Ȃ��Ȃ�A�Ⴕ�S�O�ɓ������߂Ė��s���P���C�����栂��Εn���̐l����ɗׂ̍����v�ւ���ǂ����K�̓������Ȃ����@���A�R��ΓV��̎߂̒��ɂ͎Ⴕ�S���ς�����Ώd�ߖł����ƂĎႵ�S���ς�����Ζ��ʂ̋�s�ƂȂ�Ɣ�����v�i������́A����22�ŎQ�Ɓj
�@�{���̕����́A���ȂƂ������ꂽ�ʐ��E�̂��Ƃ���������̂ł͂Ȃ��A�ق��Ȃ�ʎ��Ȃ̂��Ƃ�����Ă���̂ł���B�ʐ��E�̘b���Ƃ��ꂼ��̏���Ȏ~�ߕ����Ȃ���邱�Ƃ͔������Ȃ��B���Ă̐��m�̋��ȏ��ɏЉ��Ă����t�W���}�A�P�C�V���A�X�V�A�j���W���A�T�����C�Ȃǂɑ�\�������{�l�̎p�A�����Ԃ��`�����G�����āA�����ꂽ�̂Ɠ������Ƃ��B�s�������Ƃ̂Ȃ��j�b�|���ɂ��Ă̘b���������őz�����ĕ`�������̂�����A�u���Ĕ�Ȃ���́v�Ɓu���Ă������ʂ��́v�̃I���p���[�h�ɂȂ炴��Ȃ��B����ɑ��āA�{���̕����͐l�ԑ��݂ɂ��Č�������̂ł���A���Ȃ𗣂�邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@�ߑ����������@�́A�ʐ��E�̖��m�̂��Ƃł͂Ȃ��B�������g�̂��Ƃł���B������A���ȂɈ�ЂƂ˂����킹��悤�Ɋm�F�ł�����̂ł���B����������I�Ɉ���Ă���B���Ȃɂ��Č��ꂽ�@�́A�ۈËL�����肷����̂Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��B�ڊo�߂���̂ł���A�\�N���e�X�̌����悤��"�z�N�h������̂Ȃ̂��B����ɂ�������炸�A�ۈËL������̂Ƃ��āA���ȂƂ������ꂽ�Ƃ���Ō��p���ł����A����A�v�����݁A���ӓI�ȉ��߂����荞��"�`���Q�[���h�ɂ�����̊g��Đ��Y�ƂȂ낤�B
�@�u�����̗����͓���v�u������ɂ����v�Ƃ����������������B�m���ɓ��������ɂ���������l������������������Ȃ��B���M�r�����A�K���ł������悤�ɖ{��ǂ݂������Ă����w������ɁA�O�{���́w�Ǐ��Ɛl���x�i�p�앶�Ɂj��ǂ�ł��āA���̉ӏ��ɏo����Ė��Ɋ����������Ƃ��v���o���B
�u�w�ނÂ������x�Ƃ������ƂƁw�킩��Ȃ��x�Ƃ������ƂƂ͓����łȂ��B���Ƃ��A�������w�͂ނÂ������B�������킩��Ȃ����̂ł͂Ȃ��B������Ō�������킩��͂��̂��̂ł���B�i�����j�킩��Ȃ����̂�������Ă��邽�߂ɁA�N�w�͂ނÂ������Ƃ����]���������Ă��邱�Ƃ��Ȃ��ł��Ȃ��悤�ł���B�N�w���w�ނÂ������x�Ƃ������Ƃ͒v�������Ȃ��Ƃ��Ă��A�w�킩��Ȃ��x���̂��������Ƃ����͍̂��������Ƃ��B�킩��Ȃ��̂́A���͂�������������l�ɂ��悭�킩���Ă��Ȃ����炾�Ƃ�����ł��낤�v�i85�Łj
�u�ЂƂɌĂт�����Ƃ������Ƃ��낪�̑�ȓN�w�ɂ͊܂܂�Ă���悤�ł���B�����������̂̌��R���N�w���ނÂ������v�킹�Ă���̂ł͂Ȃ����B�ƌ�I�ȓN�w�͂ނÂ������v�i92�Łj
�@�O�{�����g�A�u����͂܂������g�ɂ����������錾�t�ł���v�i���j�ƌ���ł��邪�A�M�Ҏ��g�A�����鎞�́A���̈�߂������Ɍ����������Ȃ������Ă�������ł���B
�@�����搶���A�u������Ȃ����Ƃ��w�p�I���Ǝv���Ă���l�����邪�A�����ł͂���܂���B������₷�����Ƃ��w�p�I�Ȃ̂ł��v�u���{�ɂ́A������Ȃ����Ƃ��L�����Ƃ��Ƃ����ςȎv�z������܂��v�Ə�X����Ă���ꂽ�B
�@�ߑ��́A�N�l�ɂ��킩�錾�t�Ō�肩���A��l�ЂƂ�����Ȃɖڊo�߂����A�������ɖڊo�߂������B
�����́u�ł�������₷�����́v�ł���͂����Ǝv���B�Ȃ����ƌ����A�ق��ł��Ȃ��������g�̂��Ƃł��邩�炾�B�\�N���e�X�̌����悤�ɑz���N���������̂��B�����A������ז�������̂�����B����́A���Ђ������Č��ꂽ���t�Ɏ��ꎩ���ɂȂ�����A��X���܂��܂̎����S�Ɏ����邱�Ƃł���B�����̐g�̉��ɂ͂��̂悤�ȑ����������ɂ���B������̎ߑ����u���̊o�������Ƃ͐��ԂƋt�s���Ă���v�ƌ������̂͂��̂��Ƃł��낤�B���Ў�`�Ɏ���ꂸ�A�@���m�����Ď����S�𖾂炩�Ɍ������A����ςȂǂ̎���ꂩ�痣���Ƃ���Ɏ��R���݂Ȏ��Ȃ��P���o���̂��B
�@
�u�^�̎��ȁv�ւ̖ڊo�߂��u�\�W�]�v�̃J�M
�@�o�T�Ƃ��Ă܂Ƃ߂�ꂽ�^���̋����́A�����̂��߂ɐ����ꂽ�̂ł͂Ȃ��B�l�ԑ��݂ƁA���E�͂����Ȃ���̂��𖾂炩�ɂ������̂ł���A�l�������ɐ����Ă���������������̂��B
�@����Ȃ̂ɁA������l�ԗ��ꂵ�����́A�ʐ��E�̘b�ɂ��Ă��܂��ƁA�����͓�����̂ƂȂ�ł��낤�B�w�@�،o�x���A�ǂގ҂ɕ�F�ł��邱�Ƃ����o�����A��F�Ƃ��Ă̐U�镑�����Ăт����Ă���B�ʐl�̘b��A�ʐ��E�̘b�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�u�n�I���g�v�̂��ƂƂ��ēǂނׂ��ł���B�u���ҋ��q��栂��v�ɂ��Ă��A�u�ߗ����栂��v�ɂ��Ă��A�����n�������̂��Ǝv�����݁A���Ȕډ����Ď���ɖ���̕�������Ă��邱�Ƃ�m��Ȃ��q�ǂ��ɁA��̏��L�����o�����镨��ł���B��l�ЂƂ肪�^�̎��Ȃɖڊo�߂邱�Ƃ��e�[�}�ɂȂ��Ă���B
�@���֕i�Ŗ������ꂽ�ߑ��̏o���̖{���́A����o�������̒m�������ׂĂ̏O���ɊJ���A�����A��点�A���点��\�\������u�J�E���E��E�l�v�ƌ�������̂ł������i�A�ؖ�w�@�،o�x�㊪�A94�A96�Łj�B����́A�@���ɂƂ��Ắu��̎d���v�u��Ȃ����ׂ����Ɓv�u�傫�Ȏd���v�u�傫�ȂȂ����ׂ����Ɓv�i���A95�Łj�Ƃ��ĂȂ��ꂽ�̂ł���B���Ȃ킿�A�w�@�،o�x�́u�B��厖�̈������Ȃł̌̂Ɂv�i���A94�Łj�����ꂽ�߂ł���A�ߑ��́A�u��̏O�����āA�䂪�@�����������ĈقȂ邱�Ɩ����炵�߂�v�i���A110�Łj�Ɨ~���Ă����B����́A�ߑ��̗��ꂩ��̌��t�����A�����̗��ꂩ�猾���A��l�ЂƂ肪���߂ɕ��m�����J�����Ƃ��ڎw���ׂ����ƂȂ̂��B���@�̒���ɂ́A���̂悤�ɂ��������ϓ_�̌��t�������B
�@�u�����l��̖@���͉�g��l�̓��L�����Ȃ�v�i�w���a��{���@���l�╶�x1692�ŁA�w���@�吹�l�䏑�S�W�x563��
�@�u��l����{�Ƃ��Ĉ�؏O�������Ȃ邱�Ɛ��̔@���v�i�w���a��{���@���l�╶�x1693�ŁA�w���@�吹�l�䏑�S�W�x564�Łj
�@����ɁA���ʕi��510��������Ȃ�C���̎���u���v�Ŏn�܂�A�u�g�v�Ƃ��������ŏI��邱�Ƃ��Ƃ炦�āA�u�n�I���g�Ȃ�v�ƌ����Ă����̂��A�ȏ�̂��ƂƓ���|�ł���i�����V���w�����A�{���̋����x142�ŎQ�Ɓj�B������̌��t�ɂ����Ȃւ̎��_����т��Ă���B
�@�ȏ�̂悤�Ɍ��Ă��āA�u�\�W�]�v���́h�`�����|���h�ɂ����Ăǂ����Ċ����������Đ������`���ł���̂��Ƃ����₢�ւ̓����́A��l�ЂƂ肪���Ȃɖڊo�߂邱�Ƃ�����o�T�ł��邩�炾�Ƃ������Ƃ��ł��悤�B���̏�ŁA�����́A�����t����A��������������̂ł͂Ȃ��A�[�����d��������̂��Ƃ������Ƃ������ł��Ȃ����Ƃ��B
�@�ߑ�������̏��߂Ă̐��@�ɂ��čl���Ă݂悤�B5�l�̒�q�����Ƃ̊Ԃɉ��x������Ⴂ���J��Ԃ��ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B����ł����Ƃ��������Ă��炨���ƁA�ߑ��͊p�x��ς��A��X�̕\������ւ�p���Đ��������ݑ������B�����āA�u����Ȃ��Ƃ�������Ȃ��̂��v�Ƃ͌���Ȃ������B���̌��ʁA���@�ikondana�j�����߂Ċo�����B���̎��A�ߑ��͊�т̂��܂�A�u���@���o�������I�v�iannato kondano)�Ƌ��B�u�������o�������Ƃ́A���̒��Ƌt�s���Ă���B����ɂ���������Ȃ����낤�v�ƍl���A�u�����������ɓ��ł��悤���v�Ǝv�������Ƃ��������B���ꂾ���ɁA�o�������@�����ߑ��̊�т̂ق����傫�������ɈႢ�Ȃ��B
�@�������o�������Ƃ��A��������l�ł��ꗝ������l������ꂽ�B�ߑ��̊o�肪�B�h�Љ�h���ꂽ�̂��B���̎��̋��ѐ���������A���j���[�E�R���_���j���iannato kondana�A�o�������@�j�ƂȂ��āu���ዡ�@�v�Ɖ��ʂ���A���̐l�̖��O�̂悤�ɒ蒅���Ă���B���Ƃ��������Ă��炢�����Ƃ����v������I�݂Ȃ�栚g�����܂�A�I���Ȍ���\���ƂȂ��Ĉӎv�a�ʂ��\�Ƃ��錴���͂ƂȂ����̂ł��낤�B�����ɁA�@�h���t�̌��E���h�ƂƂ��Ɂh���t�Ő������Ƃ̕K�R���h��������B���ꂪ�h�s��ȓ`���Q�[���h�̎n�܂�ł������B���̎ߑ��̑Θb�̎p�����p������Ă���A���̌�̃C���h�A�����A���{�ɂ��������̑����͖h�����ł��낤�B���̌�́A�h���t�Ő������Ƃ̕K�R���h���̂āA�h���t�̌��E���h�݂̂��������ꂽ�肵�āA�u���Ƃ��������Ă��炢�����v�Ƃ����ߑ��̎v���͌������Ă��܂����悤���B
�@�������A�ߑ��Ō�A�������c�͕ێ牻�ƌ��Ў�`�������߁A�u�Ղ̈Ђ���ρv�̌̎��̂悤�ɁA�ߑ��̐_�i���ƕ��s���ďo�Ǝ҂����̌��ЂÂ����s�Ȃ�ꂽ�B�u�ߑ��v�Ɓu�@�v�́A�l�X���牓���������ꂽ���̂��J��グ���Ă��܂��A�ߑ��̑Θb�̎p���Ƃ͑S���قȂ���̂ƂȂ����B�w�@�،o�x�Łu�\�W�]�̌����v����������Ă���̂́A���_����̃Y���������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ȃ܂��Ă̂��Ƃ��Ǝv���ĂȂ�Ȃ��B
�@�\�W�]�́h�`���Q�[���h���A����̊g��Đ��Y�ł͂Ȃ��A��l���玟�̈�l�ւƐ������`����Ă������߂ɂ́A��l�ЂƂ�́u�^�̎��ȁv�ւ̖ڊo�߂Ƃ������_��������Ȃ����Ƃ��������Ȃ��B���̂��߂ɂ́A�����A���邢�́w�@�،o�x�����Ȃ݂̍���A�������Ƃ̊ւ��̒��łƂ炦���Ƃ��������Ȃ��B����͕������v�z�Ƃ��ĂƂ炦�A���ȂƂ̎v�z�I�Ό��̒��ŕ������Ƃ炦��Ƃ������Ƃ��B���͂ł����p�����u��S�𖭂ƒm��ʂ�A���]���ė]�S�������@�ƒm�鏈�o�Ƃ͉]�ӂȂ�v�Ƃ�����߂̂悤�ɁA�ڊo�߂��鎩�ȁi��S�j���瑼�ҁi�]�S�j�ւƌ���\���i���o�j�ɂ���Ċg�����Ă����݂�����d�v�ł���B
�@�V���t�q���킵���w�����~�ρx�̏����i��g���ɁA23�Łj�̒��ŁA�͈���t�́A�u�ȐS���ɍs�����Ƃ���̖@�������������v�i���ȐS�����s�@��j�ƋL���Ă���B�q�u�ȐS���v�ɖ@����s�����Ƃ������Ƃ́A�����������̓I�ɎƂ߁A�v�z�I�Ό����s�Ȃ��Ă����Ƃ������Ƃł��낤�B
�@�u���[�e�B���[�N�V���ipratimoksa)�Ƃ������t������B�u�g����؍��v�Ɖ��ʂ���A�u�ʉ�E�v�Ɗ��ꂽ�B���ӂ́u���ꂼ��́iprati�j��E(moksa)�Ƃ������Ƃł���A�u���ꂼ��̔ϔY�ɂ��ĉ�E�邱�Ɓv�ł���B���ꂪ�]���ĉ����̏Ƃ����Ӗ��ŗp�����u�ʉ�E���v�Ɗ��ꂽ�B���ӂɖ߂�ƁA���ꂼ��̕�����Y�݂�A���ꂼ��̒��ʂ��鍢��ƑΌ����ď��z���邱�Ƃɂ���ē������E�Ƃ������Ƃł��낤�B����̒u���ꂽ�Ƃ���𗣂�ĉ�E�͂Ȃ��B���ՓI�^���ւ̓�����́A���ꂼ��̒��ʂ��Ă��邱�ƈȊO�ɂ͂Ȃ��Ƃ����悤�B
�@���ꂼ�ꂪ�A���Ȃ̒��ʂ��Ă��邱�ƂƎv�z�I�Ό��A�i�����Ȃ��B���̌��ʁA���ꂼ��́u��S�𖭂ƒm��ʂ�v�Ƃ������Ƃ�������ł��낤�B����ɂ���āA�����́A�W�Ր��������Č���ɈӋ`���l�����A�h��ł��낤�B
�@
���Ђ���
�@�o���������̐��T�́A�傫���@�V�����e�C�i�V�[���T�j�A�A�X�����e�C�i�`�����T�j�\�\��2��ނɕ�������B�O�҂͐l�Ԃ���������̂ł͂Ȃ��A�V��������������̂Ƃ���A��҂͐l�Ԃɂ���č���`������Ă�����̂��Ƃ����B�������A�V������������ƌ����Ă��A����͐_�b�I�Șb�ŁA���F�͐l�Ԃ���������̂Ɍ��ЂÂ��Ă��邾���ł��낤�B����́A�����搶�̎��̌��t������@���邱�Ƃ��ł���B
�u���T���Ύ�����v�ҌX���͐̂��獪���������B�k�����l���T�̌��Ђ�ӖړI�ɏ��F���邱�Ƃ��C���h�l�̓`���I�v�ҕ��@�̗L�͂Ȑ��i���Â��肠���Ă���v�i�w�C���h�l�̎v�ҕ��@�x263�Łj
�@����ɑ��āA�����̏ꍇ�́A������o�T���u�@���䕷�v�i�����̔@����ꕷ�����j�Ŏn�܂��Ă���B�����Č����A�A�̓`�����T�ɑ�������B�_������I�ɓV������������Ȃǂƌ������Ƃ͂Ȃ������B�������A���n�����ł́A���̐��T�Ƃ��Ă̌o�T�ɖӖړI�ɏ]���Ƃ������Ƃ͋�������Ȃ������B���ɏЉ���u���̏Q���v����́A����̐����������ł����Ή����A�ӏ]���邱�Ƃ��ߑ����g�����m�ɔے肵�Ă������Ƃ�m�邱�Ƃ��ł���B
�@�����ł́A���E���E���̎O���d�����Ă����B���Ƃ́A�������^���ł��邩�ǂ������o������؋��Â��邱�Ƃ����A���̕����A���A���Ȃ킿�����◝���ɂ��Ȃ��Ă��邩�Ƃ������_�I�_�����ꂽ�B���Ƃ́A�����Ɍ���ꂽ���ʂɂ���Č����邱�Ƃł���B����3��������Ă͂��߂āA�������^���ł���Əؖ�����邱�ƂɂȂ�B
�@�u���肪���������v�Ƃ���Ă��邱�ƂŖӖړI�ɐM����̂ł͂Ȃ��A�����ɂ��Ȃ��Ă��邩�Ƃ������Ƃ����ꂽ�B���M�E�h�O�}����O��I�ɔr�������̂��{���̕����ł������i�w�����A�{���̋����x30�ňȉ��Q�Ɓj�B����́A�K���[�E�J�b�T�p�́u���邪�܂܂̐^���ɑ����������v�Ƃ������t�̂Ƃ���ł���B
�@�̂���̌��Ђ��鐹�T������Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�̂��l�̋���������Ƃ����̂ł��Ȃ��A�������g�̐������ɂƂ��ĈӖ�������̂��A�u�����牽�Ȃ̂��v�Ƃ����₢�ɔ[���������ƁA���ꂪ���Ր��������Č���ɈӖ��������ƂɂȂ�ł��낤�B���̎��ȂƂ̑Ό��Ƃ�����Ƃ��A�������v�z�Ƃ��Č���ɑh�点�邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƌ��l����B
�@�S�|�^�}�̎v�z�́k�����l�l�Ԃ̐^���𖾂炩�ɂ���Ƃ������Ƃ��A�߂����Ă����v�i���������w�@���ɂ�����v���Ǝ��H�x12�Łj�ɂ�������炸�A�C���h�̎ߑ�����u2500�N�A5000�L���v�̎�����o�āu�s��ȓ`���Q�[���̉ʂĂɁv�A���M��A������A��p�I�M�ɕϗe�������̂�����A�킪���̕����̌���͋ʐ����̏�Ԃɂ���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�@����܂ŁA����̐l�ԂƂ��Ă̐������ɏƂ炵�āA�������Ӌ`����������̂��ǂ����Ƃ����������قƂ�Ǎs�Ȃ��Ă��Ȃ������B���̌��̕K�v����i���Ă���ꂽ�̂��A�����搶�ł������B�����搶���S���Ȃ���10�N�ڂ�2009�N�Ɂw�@���ɂ�����v���Ǝ��H�x���A�T���K�Ƃ����o�ŎЂ���o�ł��ꂽ�B���a24�i1949�j�N2���A�s���킸��3�N����ɁA����36�̓��叕�����ł����������搶���A�����V���Ђ���o���ꂽ���삾�B����60�N�Ԃ�̍Ċ��ł���B
�@�����搶�́A���̒��Ŏ���̐푈�ɂ��Ă̎v�������̂悤�ɒԂ��Ă���B
�@�u�ߋ�10���N�̊ԂɌo���������{�����̉^���́A���܂���v���������ƁA�܂�ň����ɂƂ����Ė��ɂ��Ȃ���Ă����悤�Ȃ��̂ł������B����߂��e���A��߂��{���A���Ȃ锚���A�������Ή��\�\���܂Ȃ������̎��ɂȂ܂Ȃ܂����c��A��������Ǝ��o�ɂ�݂�����v�i168�Łj
�@���̐푈�̂Ȃ܂Ȃ܂����L���̂Ȃ��A�[���Ȕ��Ȃ܂��ĐV���Ȏw�W�����߂Ă��̖{�͎��M���ꂽ�B���̑i���́A36�̎�X�����͋����ɖ����Ă���B
�@�u���{�l�ɂ��܂�ɂ������ɋ��]���ꑮ����X���������ł������v33�Łj
�u�����͎v�z�̌n�Ƃ��Ă͗�������Ă��Ȃ��B���݂̓��{�ɂ����ẮA��Ƃ��ċV��I��p�I�Ȍ`�Ԃɂ���āA��Ƃ��Ċ���I�Ȗʂɂ����āA��ʖ��O�ƌ��т��Ă���̂ł����āA���ݎv�z�I�w�����͋ɂ߂ĖR�����Ƃ���˂Ȃ�ʁv�i25�Łj
�@�u�����̊����@���́A���炩�̌Œ肵�����`�𗧂āA����N�ɂ킽��`���I���Ђ��}�ɒ��Đl�Ԃ̎��R�Ȏv���ɑ��Ĉ����I�ԓx���Ƃ��ė����v�i34�Łj
�@����������ɑ��āA�����搶�́u���ȂƂ̑Ό��v�i32�v�j��ʂ��ĕ����𑨂��Ȃ����K�v����i���Ă���ꂽ�B���N�i2012�N�́A�����搶�̐��a�S�N�ɓ�����B�킪���̌�����������A63�N�O�ɒ����搶���w�E����Ă������Ƃ́A�c�O�Ȃ��獡�Ȃ��ς���Ă��Ȃ��ƌ��킴��Ȃ��B���߂āA�u���ȂƂ̑Ό��v�ɂ���ĕ������v�z�Ƃ��ĂƂ炦�邱�Ƃ̕K�v����Ɋ�����B
�@
�@
�@
�@